4 / 4
4
しおりを挟む
その日、空はどこまでも青く澄みわたっていて、まるでわたしの心までも映しているみたいだった。
アルフレッド様との距離が少し縮まったあの日から、わたしの世界はほんの少しずつ、でも確実に変わりはじめていた。
仕事は忙しいけれど、それすらも充実して感じるようになって……。
そんなある日の午後。
わたしが文書整理をしていると、部屋の扉がノックされました。
「リディア様。お客様がお見えです」
「……お客様、ですか?」
めずらしいことに、城の使用人さんがわざわざ私室まで来るほどの急ぎの用件。
誰だろうと思いながら応接室へ向かうと――
そこにいたのは、思いもしない人でした。
「……っ!? アマーリエ様……?」
わたしの――元婚約者、ルーク様の母親。
伯爵夫人、アマーリエ・バルティア。
お美しい方ではあるけれど、その目にはいつも誰かを見下すような冷たい光があって、わたしはいつも苦手意識を持っていた。
でも今、目の前にいる彼女は……まるで別人みたいに、疲れ切った顔で、目元は赤く腫れていた。
「リディア……いいえ、リディア様……どうか……助けて……」
「……助ける……? わたしが……ですか?」
理解が追いつかず、ただ反射的に問い返したわたしに、彼女はすがるように両手を差し出してきた。
「ルークが……あの子が、捕まったのよ! あんな、くだらない横領に……うちの家名まで巻き添えにされるなんて……!」
「……横領?」
「そうよ! あの子、領地の税金を私用に使っていたって……! でも違うのよ、きっと誰かが、あの子に濡れ衣を着せたのよ! あの子にそんな知恵があるわけないでしょう!? リディア様、あなたならわかるわよね!?」
必死な様子でまくし立てる彼女の姿は、まるで、かつての高慢な伯爵夫人とは思えなかった。
でも……わたしの心には、冷たいものがじんわりと広がっていった。
「……申し訳ありません。ですが、わたしには何もできません」
「そんなっ……! だってあなた、アルフレッド様に気に入られているんでしょう!? あなたが頼めば、きっと助けてくださるはず……!」
「どうしてわたしが、ルーク様のために、アルフレッド様にお願いしなければならないのですか?」
静かに、でもはっきりとそう言うと、彼女は凍りついたように黙った。
「わたしを下げて、見下して、婚約を破棄してきたのは……ルーク様、そしてあなたです。今さら都合のいいときだけ頼るなんて、虫がよすぎます」
「リディア……あなた……っ」
アマーリエ様の声は、かすれたように震えていた。
でもわたしは、もう、迷わない。
「どうかお引き取りください。今のわたしには……守るべき人がいます。アルフレッド様や、今のこの場所、そして……自分自身です」
そのときだった。
「……立派になられたのですね、リディア様」
廊下の奥から、落ち着いた声が聞こえてきた。
「アルフレッド様……!」
アルフレッド様は静かに、けれど力強い足取りでこちらへと歩いてきて、わたしの隣に立ってくれた。
「この件は、すでに王家でも調査が始まっております。ルーク・クローディア侯爵の件は、法に則り、厳正に処理されます。いかなる情状酌量もありません」
「っ、そんな……!」
アマーリエ様の声が、くずれるように小さくなった。
そしてそのまま、ふらふらと立ち上がり、崩れた足取りで応接室を後にしていった。
***
あのときのわたしの鼓動は、今でも忘れられない。
本当の意味で心が晴れたのは。
わたしが、アルフレッド様の隣で、ちゃんと「自分の意志」で誰かに「NO」と言えたから。
過去を断ち切って、今を選べたから。
「よく、言えましたね」
アルフレッド様が、優しく微笑んでくれた。
「はい……わたし、もう……過去にしがみつくの、やめます」
アルフレッド様の手が、そっとわたしの肩に触れる。
あたたかくて、やわらかくて――涙が出そうになった。
「ありがとう、ございます……わたし、あなたに出会えてよかった……」
この気持ちは、もう誤魔化せない。
きっと――これは、恋なんだ。
あの日の夜のことは、たぶん……一生忘れられないと思う。
わたしの中で何かが、ゆっくりと、でも確かに変わっていったから。
アマーリエ様が帰ったあと、気が張っていたせいか、わたしはどっと疲れが押し寄せて、応接室のソファにぺたりと座り込んでしまった。
「……疲れた、かもしれません」
そうつぶやいたときだった。
ふわり、とあたたかいものが肩にかけられて。
「少し、休みましょうか」
静かな声。
アルフレッド様だった。
「わたしの部屋でお茶でも飲みませんか? ……もちろん、無理には言いません」
「……アルフレッド様のお部屋……?」
わたしは、思わず顔を赤くしてしまった。
だって、だってそれって、ちょっと……意味深すぎて。
「わ、わたし……その……」
口ごもるわたしに、アルフレッド様はくすっと笑った。
「心配しなくても、危ないことはしませんよ。まだ、早いですから」
……え。
「まだ」って、なに……? 「早い」って、えっ……!?
顔が熱くなるのが自分でもわかった。
でも、アルフレッド様の優しい声とまなざしに、どこか安心して――
「……はい。ご一緒させてください」
わたしは、静かにうなずいた。
***
アルフレッド様のお部屋は、思っていたよりもずっと落ち着いた雰囲気だった。
重厚な家具や、壁の古地図。大きな本棚には歴史書や魔法の書物がぎっしりと並んでいて、まさに“知性”と“威厳”の詰まった空間。
でも、驚いたのは――
「このお花……生花ですか?」
「はい。リディア様のように、優しく咲くものが好きで」
「えっ……」
あまりにさりげなく、あまりに自然に、そんなことを言うものだから。
わたしはどう反応していいかわからなくなって、ただ、俯いてしまった。
「……そんなふうに言われたの、初めてです」
「そうですか? では、これからは何度でも言います」
「っ、アルフレッド様……!」
――ずるい。そんなの、反則です。
優しくて、誠実で、わたしの気持ちをこんなに丁寧に扱ってくれる人なんて、いままで、誰一人いなかった。
「リディア様が、今日きっぱりと自分の意志で拒絶されたのを見て……とても、誇らしく思いました」
「誇らしい……わたしが?」
「ええ。あなたは、もう過去に縛られていない。自分の未来を、自分で選べる人です」
わたしの胸の奥が、ぎゅっと締めつけられたみたいだった。
でも、それは苦しさじゃなくて――あたたかい、何か。
「……アルフレッド様。わたし……自分に、自信なんて、なかったんです。誰かに必要とされることも……夢みたいで……」
そのとき、アルフレッド様がそっとわたしの手に、触れた。
強くも、弱くもない。とてもやさしい、ぬくもり。
「あなたは……もう、必要とされています。わたしが……心から、あなたを求めています」
「……っ……」
胸の奥から、こみあげてくる想いを、もう抑えきれなかった。
涙が、ぽろりと、頬を伝って落ちる。
「アルフレッド様……ありがとう、ございます……」
わたしの手を包む彼のぬくもりが、すべてをあたためてくれた。
この人の隣でなら、わたしは、もう迷わなくていい。
もう泣かなくていい。
そう、心から思えた夜だった。
朝の光が窓からやさしく差し込んでいるのに、わたしの胸の中は、ざわざわと波立っていた。
その日は、城中にひそやかな噂が駆け巡っていた。あの、かつての婚約者――エドワルド侯爵が、公の場で大きな恥をかかされたというのだ。
わたしは、使用人から小声で聞いた話を反芻しながら、自分の部屋の窓辺に座っていた。
「ルーク子爵は、王の前で完全に暴かれたそうです。横領の証拠も、隠蔽しようとしたことも、ぜんぶ……」
ため息が出た。
かつては、あんなに自信たっぷりで、わたしを見下していたあの男が。今や、すべてを失って崩れ落ちているなんて。
胸の奥に、じわじわと湧き上がる感情があった。
それは、ただの復讐心じゃなくて。
わたしはもっと……強くなったんだって、感じたかった。
***
午後になって、アルフレッド様が城に戻られたとき、わたしは声を震わせて言った。
「アルフレッド様……あの、ルーク子爵は、もう……完全に破滅したんでしょうか?」
彼は優しくわたしの手を握り、真剣な眼差しで答えてくれた。
「はい。もう取り返しのつかないところまできています。領地も没収され、爵位も剥奪されるでしょう」
「……それでも、かわいそう……なんて思ったりしますか?」
恥ずかしくて、でも素直な気持ちを隠せずに訊いた。
「最初はわたしもそう思いました。でも……リディア様、あなたがこれまで耐えたこと、傷ついたことを思い出してください」
アルフレッド様の言葉に、胸が締めつけられる。
「ルーク子爵は自分の都合だけで、あなたを傷つけました。そして今、自分の罪から逃げることもできずにいます」
そう、わたしはもう、泣いてばかりの弱い子じゃない。
「……わたしは、もう、負けません」
そう心の中で強く誓った。
***
夜。アルフレッド様と並んで庭を歩きながら、わたしはぽつりと言った。
「アルフレッド様。どうして……わたしを守ってくれるんですか?」
「リディア様の強さに惹かれたからです。あなたは誰よりも優しく、誰よりも真っ直ぐです。僕は、そのすべてを守りたい」
わたしの胸はあたたかくなって、涙が自然にこぼれた。
「ありがとう……アルフレッド様。わたし、本当に幸せです」
「リディア様、これからも一緒に歩きましょう。どんな困難も、僕が支えます」
その約束に、わたしは強くうなずいた。
そして、心の中に新しい光が灯った。
朝日がゆっくりと昇りはじめたころ、わたしは窓のそばに立っていた。
外の空気はまだひんやりしていて、草木の匂いがふわりと鼻をくすぐる。
「今日も、いい一日になりそうだな」
わたしは小さく笑った。
***
ここまで来るのに、たくさん泣いて、傷ついて、怖かった。
でも、もう大丈夫。
だって、アルフレッド様がそばにいてくれるから。
あの人のやさしい声を思い出すと、胸がぽかぽかあたたかくなる。
「リディア様」
庭に咲く花のそばで、アルフレッド様が笑いかけてくれた。
「おはようございます、アルフレッド様」
わたしは礼儀正しく答えるけど、心はドキドキしていた。
「今日は、あなたに伝えたいことがあるんです」
「な、なんでしょう?」
アルフレッド様の真剣なまなざしに、胸が高鳴った。
「リディア様、これからもずっと、一緒に歩んでほしい。結婚してください」
その言葉に、わたしは思わず目を見開いた。
「……えっ」
しばらく声が出なかった。
「わたしと……結婚してくれるんですか?」
「はい。あなたと未来を築きたい。どんなことも、二人で乗り越えられると思うから」
アルフレッド様の誠実な声に、涙がこぼれた。
「わたしも……アルフレッド様と一緒に歩みたい。ずっと、ずっと」
そう言って、わたしは彼の手を強く握った。
***
あのときのルーク子爵のことは、もう過去のこと。
彼がどんなに嫌なことを言っても、わたしの心はもう揺らがない。
それに、いまのわたしには、大切な人がいるから。
「アルフレッド様、ありがとう。わたし、あなたのことを心から信じてる」
「リディア様、これからも一緒に笑って、泣いて、幸せを分かち合おう」
そう誓った瞬間、わたしの胸の中に、新しい光が満ちていった。
***
これからどんなことがあっても、わたしは負けない。
過去に縛られず、自分の力で未来を選ぶ――そんな強さを手に入れたから。
そして何より、わたしは幸せになる権利がある。
「ありがとう、わたしの人生」
そう心の中でつぶやきながら、わたしは新しい一歩を踏み出した。
アルフレッド様との距離が少し縮まったあの日から、わたしの世界はほんの少しずつ、でも確実に変わりはじめていた。
仕事は忙しいけれど、それすらも充実して感じるようになって……。
そんなある日の午後。
わたしが文書整理をしていると、部屋の扉がノックされました。
「リディア様。お客様がお見えです」
「……お客様、ですか?」
めずらしいことに、城の使用人さんがわざわざ私室まで来るほどの急ぎの用件。
誰だろうと思いながら応接室へ向かうと――
そこにいたのは、思いもしない人でした。
「……っ!? アマーリエ様……?」
わたしの――元婚約者、ルーク様の母親。
伯爵夫人、アマーリエ・バルティア。
お美しい方ではあるけれど、その目にはいつも誰かを見下すような冷たい光があって、わたしはいつも苦手意識を持っていた。
でも今、目の前にいる彼女は……まるで別人みたいに、疲れ切った顔で、目元は赤く腫れていた。
「リディア……いいえ、リディア様……どうか……助けて……」
「……助ける……? わたしが……ですか?」
理解が追いつかず、ただ反射的に問い返したわたしに、彼女はすがるように両手を差し出してきた。
「ルークが……あの子が、捕まったのよ! あんな、くだらない横領に……うちの家名まで巻き添えにされるなんて……!」
「……横領?」
「そうよ! あの子、領地の税金を私用に使っていたって……! でも違うのよ、きっと誰かが、あの子に濡れ衣を着せたのよ! あの子にそんな知恵があるわけないでしょう!? リディア様、あなたならわかるわよね!?」
必死な様子でまくし立てる彼女の姿は、まるで、かつての高慢な伯爵夫人とは思えなかった。
でも……わたしの心には、冷たいものがじんわりと広がっていった。
「……申し訳ありません。ですが、わたしには何もできません」
「そんなっ……! だってあなた、アルフレッド様に気に入られているんでしょう!? あなたが頼めば、きっと助けてくださるはず……!」
「どうしてわたしが、ルーク様のために、アルフレッド様にお願いしなければならないのですか?」
静かに、でもはっきりとそう言うと、彼女は凍りついたように黙った。
「わたしを下げて、見下して、婚約を破棄してきたのは……ルーク様、そしてあなたです。今さら都合のいいときだけ頼るなんて、虫がよすぎます」
「リディア……あなた……っ」
アマーリエ様の声は、かすれたように震えていた。
でもわたしは、もう、迷わない。
「どうかお引き取りください。今のわたしには……守るべき人がいます。アルフレッド様や、今のこの場所、そして……自分自身です」
そのときだった。
「……立派になられたのですね、リディア様」
廊下の奥から、落ち着いた声が聞こえてきた。
「アルフレッド様……!」
アルフレッド様は静かに、けれど力強い足取りでこちらへと歩いてきて、わたしの隣に立ってくれた。
「この件は、すでに王家でも調査が始まっております。ルーク・クローディア侯爵の件は、法に則り、厳正に処理されます。いかなる情状酌量もありません」
「っ、そんな……!」
アマーリエ様の声が、くずれるように小さくなった。
そしてそのまま、ふらふらと立ち上がり、崩れた足取りで応接室を後にしていった。
***
あのときのわたしの鼓動は、今でも忘れられない。
本当の意味で心が晴れたのは。
わたしが、アルフレッド様の隣で、ちゃんと「自分の意志」で誰かに「NO」と言えたから。
過去を断ち切って、今を選べたから。
「よく、言えましたね」
アルフレッド様が、優しく微笑んでくれた。
「はい……わたし、もう……過去にしがみつくの、やめます」
アルフレッド様の手が、そっとわたしの肩に触れる。
あたたかくて、やわらかくて――涙が出そうになった。
「ありがとう、ございます……わたし、あなたに出会えてよかった……」
この気持ちは、もう誤魔化せない。
きっと――これは、恋なんだ。
あの日の夜のことは、たぶん……一生忘れられないと思う。
わたしの中で何かが、ゆっくりと、でも確かに変わっていったから。
アマーリエ様が帰ったあと、気が張っていたせいか、わたしはどっと疲れが押し寄せて、応接室のソファにぺたりと座り込んでしまった。
「……疲れた、かもしれません」
そうつぶやいたときだった。
ふわり、とあたたかいものが肩にかけられて。
「少し、休みましょうか」
静かな声。
アルフレッド様だった。
「わたしの部屋でお茶でも飲みませんか? ……もちろん、無理には言いません」
「……アルフレッド様のお部屋……?」
わたしは、思わず顔を赤くしてしまった。
だって、だってそれって、ちょっと……意味深すぎて。
「わ、わたし……その……」
口ごもるわたしに、アルフレッド様はくすっと笑った。
「心配しなくても、危ないことはしませんよ。まだ、早いですから」
……え。
「まだ」って、なに……? 「早い」って、えっ……!?
顔が熱くなるのが自分でもわかった。
でも、アルフレッド様の優しい声とまなざしに、どこか安心して――
「……はい。ご一緒させてください」
わたしは、静かにうなずいた。
***
アルフレッド様のお部屋は、思っていたよりもずっと落ち着いた雰囲気だった。
重厚な家具や、壁の古地図。大きな本棚には歴史書や魔法の書物がぎっしりと並んでいて、まさに“知性”と“威厳”の詰まった空間。
でも、驚いたのは――
「このお花……生花ですか?」
「はい。リディア様のように、優しく咲くものが好きで」
「えっ……」
あまりにさりげなく、あまりに自然に、そんなことを言うものだから。
わたしはどう反応していいかわからなくなって、ただ、俯いてしまった。
「……そんなふうに言われたの、初めてです」
「そうですか? では、これからは何度でも言います」
「っ、アルフレッド様……!」
――ずるい。そんなの、反則です。
優しくて、誠実で、わたしの気持ちをこんなに丁寧に扱ってくれる人なんて、いままで、誰一人いなかった。
「リディア様が、今日きっぱりと自分の意志で拒絶されたのを見て……とても、誇らしく思いました」
「誇らしい……わたしが?」
「ええ。あなたは、もう過去に縛られていない。自分の未来を、自分で選べる人です」
わたしの胸の奥が、ぎゅっと締めつけられたみたいだった。
でも、それは苦しさじゃなくて――あたたかい、何か。
「……アルフレッド様。わたし……自分に、自信なんて、なかったんです。誰かに必要とされることも……夢みたいで……」
そのとき、アルフレッド様がそっとわたしの手に、触れた。
強くも、弱くもない。とてもやさしい、ぬくもり。
「あなたは……もう、必要とされています。わたしが……心から、あなたを求めています」
「……っ……」
胸の奥から、こみあげてくる想いを、もう抑えきれなかった。
涙が、ぽろりと、頬を伝って落ちる。
「アルフレッド様……ありがとう、ございます……」
わたしの手を包む彼のぬくもりが、すべてをあたためてくれた。
この人の隣でなら、わたしは、もう迷わなくていい。
もう泣かなくていい。
そう、心から思えた夜だった。
朝の光が窓からやさしく差し込んでいるのに、わたしの胸の中は、ざわざわと波立っていた。
その日は、城中にひそやかな噂が駆け巡っていた。あの、かつての婚約者――エドワルド侯爵が、公の場で大きな恥をかかされたというのだ。
わたしは、使用人から小声で聞いた話を反芻しながら、自分の部屋の窓辺に座っていた。
「ルーク子爵は、王の前で完全に暴かれたそうです。横領の証拠も、隠蔽しようとしたことも、ぜんぶ……」
ため息が出た。
かつては、あんなに自信たっぷりで、わたしを見下していたあの男が。今や、すべてを失って崩れ落ちているなんて。
胸の奥に、じわじわと湧き上がる感情があった。
それは、ただの復讐心じゃなくて。
わたしはもっと……強くなったんだって、感じたかった。
***
午後になって、アルフレッド様が城に戻られたとき、わたしは声を震わせて言った。
「アルフレッド様……あの、ルーク子爵は、もう……完全に破滅したんでしょうか?」
彼は優しくわたしの手を握り、真剣な眼差しで答えてくれた。
「はい。もう取り返しのつかないところまできています。領地も没収され、爵位も剥奪されるでしょう」
「……それでも、かわいそう……なんて思ったりしますか?」
恥ずかしくて、でも素直な気持ちを隠せずに訊いた。
「最初はわたしもそう思いました。でも……リディア様、あなたがこれまで耐えたこと、傷ついたことを思い出してください」
アルフレッド様の言葉に、胸が締めつけられる。
「ルーク子爵は自分の都合だけで、あなたを傷つけました。そして今、自分の罪から逃げることもできずにいます」
そう、わたしはもう、泣いてばかりの弱い子じゃない。
「……わたしは、もう、負けません」
そう心の中で強く誓った。
***
夜。アルフレッド様と並んで庭を歩きながら、わたしはぽつりと言った。
「アルフレッド様。どうして……わたしを守ってくれるんですか?」
「リディア様の強さに惹かれたからです。あなたは誰よりも優しく、誰よりも真っ直ぐです。僕は、そのすべてを守りたい」
わたしの胸はあたたかくなって、涙が自然にこぼれた。
「ありがとう……アルフレッド様。わたし、本当に幸せです」
「リディア様、これからも一緒に歩きましょう。どんな困難も、僕が支えます」
その約束に、わたしは強くうなずいた。
そして、心の中に新しい光が灯った。
朝日がゆっくりと昇りはじめたころ、わたしは窓のそばに立っていた。
外の空気はまだひんやりしていて、草木の匂いがふわりと鼻をくすぐる。
「今日も、いい一日になりそうだな」
わたしは小さく笑った。
***
ここまで来るのに、たくさん泣いて、傷ついて、怖かった。
でも、もう大丈夫。
だって、アルフレッド様がそばにいてくれるから。
あの人のやさしい声を思い出すと、胸がぽかぽかあたたかくなる。
「リディア様」
庭に咲く花のそばで、アルフレッド様が笑いかけてくれた。
「おはようございます、アルフレッド様」
わたしは礼儀正しく答えるけど、心はドキドキしていた。
「今日は、あなたに伝えたいことがあるんです」
「な、なんでしょう?」
アルフレッド様の真剣なまなざしに、胸が高鳴った。
「リディア様、これからもずっと、一緒に歩んでほしい。結婚してください」
その言葉に、わたしは思わず目を見開いた。
「……えっ」
しばらく声が出なかった。
「わたしと……結婚してくれるんですか?」
「はい。あなたと未来を築きたい。どんなことも、二人で乗り越えられると思うから」
アルフレッド様の誠実な声に、涙がこぼれた。
「わたしも……アルフレッド様と一緒に歩みたい。ずっと、ずっと」
そう言って、わたしは彼の手を強く握った。
***
あのときのルーク子爵のことは、もう過去のこと。
彼がどんなに嫌なことを言っても、わたしの心はもう揺らがない。
それに、いまのわたしには、大切な人がいるから。
「アルフレッド様、ありがとう。わたし、あなたのことを心から信じてる」
「リディア様、これからも一緒に笑って、泣いて、幸せを分かち合おう」
そう誓った瞬間、わたしの胸の中に、新しい光が満ちていった。
***
これからどんなことがあっても、わたしは負けない。
過去に縛られず、自分の力で未来を選ぶ――そんな強さを手に入れたから。
そして何より、わたしは幸せになる権利がある。
「ありがとう、わたしの人生」
そう心の中でつぶやきながら、わたしは新しい一歩を踏み出した。
36
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説
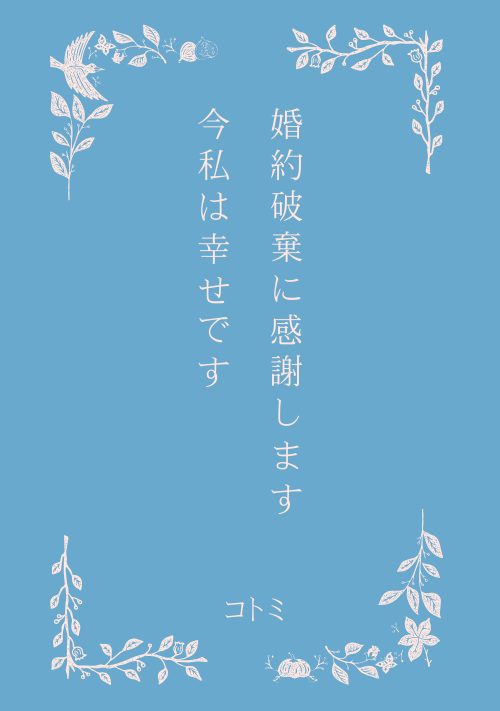
【完結】婚約破棄に感謝します。貴方のおかげで今私は幸せです
コトミ
恋愛
もうほとんど結婚は決まっているようなものだった。これほど唐突な婚約破棄は中々ない。そのためアンナはその瞬間酷く困惑していた。婚約者であったエリックは優秀な人間であった。公爵家の次男で眉目秀麗。おまけに騎士団の次期団長を言い渡されるほど強い。そんな彼の隣には自分よりも胸が大きく、顔が整っている女性が座っている。一つ一つに品があり、瞬きをする瞬間に長い睫毛が揺れ動いた。勝てる気がしない上に、張り合う気も失せていた。エリックに何とここぞとばかりに罵られた。今まで募っていた鬱憤を晴らすように。そしてアンナは婚約者の取り合いという女の闘いから速やかにその場を退いた。その後エリックは意中の相手と結婚し侯爵となった。しかしながら次期騎士団団長という命は解かれた。アンナと婚約破棄をした途端に負け知らずだった剣の腕は衰え、誰にも勝てなくなった。

その令嬢は祈りを捧げる
ユウキ
恋愛
エイディアーナは生まれてすぐに決められた婚約者がいる。婚約者である第一王子とは、激しい情熱こそないが、穏やかな関係を築いていた。このまま何事もなければ卒業後に結婚となる筈だったのだが、学園入学して2年目に事態は急変する。
エイディアーナは、その心中を神への祈りと共に吐露するのだった。

心を病んでいるという嘘をつかれ追放された私、調香の才能で見返したら調香が社交界追放されました
er
恋愛
心を病んだと濡れ衣を着せられ、夫アンドレに離縁されたセリーヌ。愛人と結婚したかった夫の陰謀だったが、誰も信じてくれない。失意の中、亡き母から受け継いだ調香の才能に目覚めた彼女は、東の別邸で香水作りに没頭する。やがて「春風の工房」として王都で評判になり、冷酷な北方公爵マグナスの目に留まる。マグナスの支援で宮廷調香師に推薦された矢先、元夫が妨害工作を仕掛けてきたのだが?

はじめまして、私の知らない婚約者様
有木珠乃@『ヒロ弟』コミカライズ配信中
ファンタジー
ミルドレッド・カーマイン公爵令嬢は突然、学園の食堂で話しかけられる。
見覚えのない男性。傍らには豊満な体型の女性がいる。
けれどその女性から発せられた男性の名前には、聞き覚えがあった。
ミルドレッドの婚約者であるブルーノ王子であることを。
けれどミルドレッドの反応は薄い。なぜなら彼女は……。
この世界を乙女ゲームだと知った人々による、悪役令嬢とヒロイン、魔女の入れ替え話です。
悪役令嬢を救いたかったはずなのに、どうしてこんなことに?
※他サイトにも掲載しています。

婚約破棄された伯爵令嬢は、かつて“月影の魔女”と呼ばれた存在でした ~今さら跪いても、貴方の席はありません~
有賀冬馬
恋愛
婚約者に「地味でつまらない」と言われ、婚約破棄された伯爵令嬢リディア。
だが、彼女の正体は、伝説として語られた“月影の魔女”。
婚約破棄の夜、彼女は笑って屋敷を去り、静かにその力を解放する。
数年後、王国に迫る未曾有の危機。
王族も貴族も頭を下げる中、かつての婚約者は涙ながらに復縁を懇願するが――

他人の婚約者を誘惑せずにはいられない令嬢に目をつけられましたが、私の婚約者を馬鹿にし過ぎだと思います
珠宮さくら
恋愛
ニヴェス・カスティリオーネは婚約者ができたのだが、あまり嬉しくない状況で婚約することになった。
最初は、ニヴェスの妹との婚約者にどうかと言う話だったのだ。その子息が、ニヴェスより年下で妹との方が歳が近いからだった。
それなのに妹はある理由で婚約したくないと言っていて、それをフォローしたニヴェスが、その子息に気に入られて婚約することになったのだが……。

捨てた私をもう一度拾うおつもりですか?
ミィタソ
恋愛
「みんな聞いてくれ! 今日をもって、エルザ・ローグアシュタルとの婚約を破棄する! そして、その妹——アイリス・ローグアシュタルと正式に婚約することを決めた! 今日という祝いの日に、みんなに伝えることができ、嬉しく思う……」
ローグアシュタル公爵家の長女――エルザは、マクーン・ザルカンド王子の誕生日記念パーティーで婚約破棄を言い渡される。
それどころか、王子の横には舌を出して笑うエルザの妹――アイリスの姿が。
傷心を癒すため、父親の勧めで隣国へ行くのだが……

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















