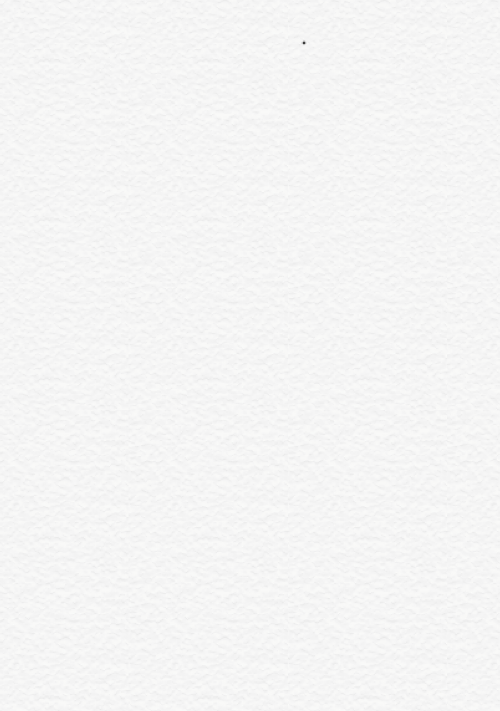1 / 1
短編
しおりを挟む
美と教養を兼ねた才女は、生まれた時から次期国王陛下である王子の婚約者である姉の代わりとして、幼い頃から帝国学を学び、王妃の教育を受けていた。
身体の弱い姉が王子に嫁げなくても、私──ディーナ・グリゼルダ・アチェールは、このヴィラン公国の宰相の要職につく、アチュール公爵の次女として生まれた。
2歳年上の姉のアリッサは生まれつき身体が弱く、ベッドの上にいるのが多い幼少期を過ごしていたため、アリッサが王子に嫁げない場合を想定して、私が王子の婚約者の第二候補として決まった。
私が成人を迎える18歳を過ぎると、姉は普通の人よりも体力はなかったが、積極的に社交界へ出るようになった。しかし、私の地位は相変わらず王子の第二候補に留まり、新たな婚約者をつけられる事はなかった。
まだ勉強をしたかった私の思いと、姉が元気になったとはいえ、まだ体力的に子供が産めるか不安が残るため、公爵家から王妃を出したい父の意向が一致した瞬間でもあった。
こんな歪な関係が2年も経つと、いつしか王子の方が私を離したくないのではないか──またはアチェール公爵の次女である私が勉学を共にしてきた王子に恋をしてしまって、王妃にはなれないが、王子のそばにいられる側妃を望んでいるのではないかと、社交界で噂が流れるようになった。
***************
長い銀色の髪が日に焼けていない真っ白な肌の腕に当たり、男はどきりとした。
マイナーすぎて誰も近寄らない、一番奥の一角にある地方の歴史の書物がある国立図書館で会った少女は、いつも綺麗な銀色の髪をポニーテールにして、大きな黒縁のメガネをかけて本を読んでいたり、書き物をしたりしていた。
最初に彼女を見かけたのは、もう2年も前で、たまたま地方の視察の帰りに調べ物をしたくなり立ち寄ったのがきっかけだった。一目で彼女から目が離せなくなった私──ルキアーノ・トロッツィは、なったばかりの公爵家の当主として、久しぶりに訪れた図書館で運命の出会いを果たした。
30歳前に当主になった途端に、周りからは世継ぎを求められて辟易していた。母の事を愛してはいるが、それでも仕事一筋でやって来た父と同じで、息子の私も女性よりも仕事の面白さに夢中になっていた。
天然ウェーブの癖毛の黒い髪に切れ長の目で、美男美女の夫婦として仲睦まじい父と母のいいところをとったような綺麗に配置された目鼻口と笑うと近寄りがたい冷たい印象から一転、一気に幼くなる甘いマスク、じっと見られると緊張すると出会う令嬢全てに言われてきた。
私が近づいただけで気分が悪くなったと寄りかかる令嬢や、あからさまに誘惑してくる女性に次第に嫌気が差し社交界にも参加しなくなった。
親が勧める縁談で結婚するのかもしれないと思い始めていたなか、ついには恋に落ちたのだ。それも、王子の第二婚約者候補、またの名を王子のお手つき令嬢である、アチェール公爵の娘のディーナ嬢に一目惚れをしたのだ。
貴族の身分がないと入ることは難しい国立図書館で、従者に命令して彼女を調べさせた。
『彼女が、王子の婚約者…だと?』
毎日のように図書館に行く彼女の正体を知った時の衝撃は今もなお、私の心にある。
彼女は、平日はほぼ毎日午前中に図書館で勉強をし、午後には自分の屋敷へ帰ってしまう。午後にはお茶会や用事がなければ部屋で読書や縫い物をしていると、アチェール公爵家で働く使用人から聴取した従者から報告を受けた私は、午前の業務を調整して、彼女のいる国立図書館へと足を運ぶようになった。生まれてこの方誰にも興味が沸かなかったのに、たまたま寄った図書館で一目見た彼女を忘れられず、無意識のうちに午前の仕事を中断していた。王子の婚約者候補と知ってもなお、彼女に会いたいと強く願うようになるのは必然なような気もする。
最初の頃の彼女は、私が近くに寄っても気が付かなかった。彼女がいる10人は座れる大きな机の前に、誰もいないのに敢えて対面で座って、適当に本棚から取った本を広げて読んでも、彼女の視線は下を向いたままで、本を読み終わった後の彼女は、ほぅっと紅潮した頬を緩めてため息を吐く艶かしい姿に、私の心の中がさらに騒めいた。2ヶ月、半年も過ぎても、あまりに私に気が付かないものだから、私の存在に気がついて欲しいと願うようになり、意を決して彼女の横に座ると、やっと彼女はやっと私に気がついた。
しかし、他の令嬢と違うのは、私を見ても頬を赤らめるわけでもなく、かといって喜ぶわけでもなく、何故隣に座るのかと困惑している顔をしている所だ。
「…こんにちは、いつもこの図書館にいますね」
彼女が私の存在に気がついてくれたのが嬉しくて、つい笑みが溢れると、彼女は固まってしまった。誰にもされたことのない新鮮な反応も、私を喜ばせるだけで、笑みを深めてしまう。ご令嬢に見せたら自分に気があるんじゃないかと誤解されてしまいそうな、心から愛おしいと思う笑顔を見せれば、彼女はさらに戸惑って、あろうことか本棚の先にある通路に視線を向けた。
──ショックだなぁ、これでもこの笑顔は他の令嬢には好評なんだけど
ショックを受けているなんて微塵も顔には出さずに、彼女にもう一度微笑むと、彼女はズレていないのに黒縁のメガネの位置を直した。
「こんにちは、いつも…は、いませんわ、今日はたまたま近くを通ったので時間を潰しているだけですわ」
「…へぇ、そうなんだ」
毎日図書館に来ているのに、嘘をついてまで私と話したくないと暗に言っている。
──うそつき
私が彼女の名前も、普段何をしているかも知っているなんて、ツユほども思っていない彼女がしらを切る姿が可愛くてしょうがない。声は思っていたよりも少し高く、だが耳障りでもない音色も話すトーンも、私の質問に即答しないで少し考えてから慎重に答える姿に好感が持てる。こんなにもわくわくするのは、何年ぶりだろうか、と幼少期に遊んだ過去を今は思い返す時間も惜しい。
──いや、もうとっくに彼女に惚れている
彼女と話して確信を得ると、私は彼女と図書館で会うと声を掛けるようになった。
「若、頼んますよ~、仕事を抜けられると仕事が溜まるんすよ」
「私は今、至急の仕事は抱えてないはずだが?」
最初は私の遅い初恋に暖かい眼差しを向けていた部下も、図書館に通うのが2年にも及ぶと、午後に溜まる仕事があると小言をいうようになった。抜けるのはせいぜい平日の週に3日、それ以外の日は従者に言って彼女の様子を見てもらっていたにも関わらず、もっと彼女と過ごす時間を増やしたいと思うようになっている。
当初は彼女を見かけるだけ、ほんの数分話せれば満足していたものの、今は2時間雑談しても物足りないくらいにはなっていた。
「そうまでするんでしたら、もう婚約者に名乗り出ればいいじゃないですか」
「そうしたいのは山々だが、彼女がまだ王子の第二婚約者候補なんだ、すでに婚約者がいる令嬢に直談判なんて出来るはずないだろ?」
「…そんな事言ったって」
それなら令嬢に会いに行かなければ、彼女の事を忘れられるじゃないか、と部下の冷めた眼差しが私に刺さる。
「それに相手は王子なんだ、公爵の力を利用してどうこう出来る話じゃない」
「…王子相手じゃなかったら、公爵の力を利用するってことか」
呆れた声の部下に、何を言っているのかわからなくなる。
「そんなの当たり前じゃないか、愛している女性と生涯添いたいと願うのは当然の考えさ」
たった数時間話しただけでも、こんなにも幸福感があるから、仕事から帰った時に、彼女が私を出迎えてくれたら…疲れも吹き飛ぶはずだ。
「だからって、31歳になる公爵がする事じゃないですが」
行動を起こさず、純粋な関係のまま彼女に会いに行く私から、ふぃっと視線を外した部下が見た先には、山盛りに置いてある仕事の書類があった。2時間彼女と過ごすのに加え、午前中は移動時間も含めて不在となる間も日々の仕事は待ってくれない。きっと今日も夜遅くまで仕事を片付ける羽目になるばすだが、明日になれば彼女と会える。
「…さあ、始めよう」
私がそう部下に告げると、彼はため息一つついて山盛りの書類に手を伸ばした。
***************
「一つは、疫病の蔓延を防ぐための処置でして」
「ほう、ではそのような対策をすれば、今の状態から脱却出来ると?」
「ええ、明日には…というくらいすぐには結果は出ませんが、数週間のうちに改善が認められますわ」
いつものように図書館の奥にある歴史書が並ぶ誰も近寄らない一角で彼女の隣に座り、小さな口を動かして一緒懸命私に力説する彼女と領地経営の意見交換をする。
彼女は幼き頃から帝国学も学んでいるから、過去の事例に対する解決策もぽんぽん出てくる。そのため他の令嬢のように面白くないと言われることもないし、深い経営の話が出来て実際に自分の領地で試せる選択肢が増えてとても勉強になる。
「…前から思っていましたが、ルキ様の字は綺麗ですね」
彼女の言った事を紙に書いていると、彼女は私の手元を見て呟いた。
「そうかい?君の文字も綺麗だよ」
図書館で顔を合わせてから、2人の呼び名もルキ様、ディーとお互いを愛称で呼ぶようになった。幼少の頃にしか呼ばれなかった愛称で呼ばれると、たまに照れ臭くなるが、嬉しい気持ちも大きい。
ここでは当主ではないただのルキ、ディーも王子の婚約者候補という立場から解放されて、友達といるかのように笑い、時には真面目な話をして、バカ話でふざけあえる。くすくすと笑う彼女は、本を読む時とは雰囲気が違って可愛い。
「そうだ、ルキ様に見せたい書物を発見しましたのっ」
両手を合わせてはしゃぐ彼女に釣られて、私も思わず笑ってしまう。
「なんだい?」
「以前ルキ様が仰っていた、ヴィラン公国の始まりを記した本を見つけましたのっ…こちらですわっ」
真剣な表情で本を読む時とは違い、髪と同じ色の銀瞳をキラキラと輝かせ立ち上がると、歴史書のコーナーの奥へと向かったので、私は彼女についていくことにした。
天井までつく細長い棚の壁際にある下から5段目──丁度彼女の視線と同じ高さに並ぶ本棚から濃緑のカバーの本を一冊取り出すと、私の前に表紙を見せた。
「…ヴィラン公国の農作物の歴史?」
「ええ!そうですわっ!こちらは、主に農作物の歴史が書いてあるのですが…ほらっ!ここっ!」
私が知りたかったのは、この国始まりの話だったのに、関係のなさそうな農産物の本を出されて、私が戸惑っていると、彼女は本を開いてパラパラと捲り、ある章を開いて指を指して教えてくれた。
「…ヴィラン公国は、国として成り立つ前に農作物が育たない痩せた土地だったが、のちの王族となった当時の…本当じゃないかっ!」
私の声に合わせて彼女の細くて美しい指が文字をなぞり、読み進めていくと、この国の始まりを知る。
「…っぁ」
私は目を見張り嬉しくなって喜びの声を上げながら彼女を見ると、思いの外近くにある彼女の顔に驚いた。彼女も驚いたみたいで、元々大きな目だと思っていた綺麗な瞳が更に溢れんばかりに開いている。2人の時間が止まったような気がして、私の口が開いて低い声で彼女の名前を読んだ。
「…ディー」
「ルキさ…ま」
彼女の頬に右手を添えて顔を寄せると、素早く彼女の唇に自分の唇を重ねて離れた。唇が重なったのが一瞬だったので、彼女の唇の柔らかさしか感じなかった…が、もう一度彼女の唇の柔らかさを感じたくなって、親指の腹で彼女の頬をなぞり、もう一度彼女の唇に自分の唇を重ねて、自分とは違う柔らかくてぷっくりと膨らんだ上唇を甘噛みした。
「…んっ」
甘い声が彼女の口から漏れると、頭がカッと熱くなる。口を開けて舌で彼女の唇のラインをなぞると、彼女は薄く口を開け、私は吸い込まれるように彼女の口内へと舌を入れた。彼女の持っていた本を取り上げると、本を持ったまま彼女の腰に腕を回し、私の方へ引き寄せて身体を密着させた。私よりもふた回りも小さな彼女は、私の腕の中にすっぽりと収まっている。
甘い声、熱い口内、彼女の息が口から漏れて、私の舌に当たって舌を彼女の口内で押し進めていると、さっきから私がする事にディーは硬直している。彼女がきっと初めてのキスだというのに、貪るようにキスを続けてしまった。彼女はカクンと膝の力が抜けて倒れそうになったため抱きしめた。
「…っ、ルキ様」
「ディー」
瞳を潤ませ見上げられるとまた彼女の唇が欲しくなり、彼女のメガネを外した。メガネの下の瞳は、溢れんばかりに大きくて、私を誘うように濡れていた。口を少し開けて息をする時も赤い舌がちろりと見えて、普段の彼女の清楚な雰囲気が一転して色っぽい。もう一度口を重ねた時には、本棚に彼女の背中を押し付けて思う存分彼女の口内を長い時間堪能した。
***************
「ルキ様」
「なんだい?ディー?」
彼女に甘い声で名前を呼ばれれば、腕の中にいる彼女を抱きしめる力を強めた。
初めてキスをしてから、数ヶ月。とても有意義な意見交換をする傍ら、一目見ればとても知り合いの男女の距離感ではなくなった。会えば開口前にキスをし、離れていた数日を埋めるようにお互いの口を求めた。たっぷりと堪能した後は、彼女の横に肩に手を回して座り、近況報告のような雑談をしつつ、言葉を交わす合間に口づけをしあう。彼女が私の肩に頭を乗せると、それは私からディーへとキスをして欲しい合図だと最近になって気がついた。私が毎回彼女のメガネを取ってキスをするものだから、いつからかメガネをしてこなくなった。彼女との隔たりがなくなり嬉しい反面、彼女の美しさがこの図書館にくるまでの間に何人もの目に触れたかと思うと、つい彼女の舌に強く吸い付いてしまうという醜いヤキモチの態度をとるようになった。彼女の日常の報告は受けているから、私以外とは過ごしていないと頭では分かっていても、面白くないものは面白くないのだ。
「その口紅毎日付けてるの?それとも私と会う時だけ?…とても似合っているね」
彼女の小さな唇に自分の親指の腹でなぞれば、私の指先に彼女の薄ピンク色の口紅が薄らと移った。
「…ありがとうございます、ルキ様が買ってくださいましたから、毎日付けておりますわ…毎日ルキ様をお側に感じたいので」
ディーは右腕を上げると、私がしたように指先で私の唇をなぞった。きっと彼女の口紅が私の唇に付いているのだろう、嬉しそうに微笑む姿はいつみても美しい。
「可愛い事を言うね、これ以上私を夢中にさせるなんて」
私の唇にある彼女の手を取り、私は彼女の口を塞ぐと、彼女は私のキスに自分の舌を絡ませて応えてくれる。
私は、会うたびに彼女に贈り物をしていた。最初は彼女の唇に合う口紅を、その次はいつも身につけて欲しくて私の髪と目と同じ色の黒い真珠を使ったブローチを、その次はブローチと同じデザインになるイヤリング、ブローチとイヤリングと一緒に付けても遜色のないブレスレットと、普段使いも出来る物をプレゼントした。未婚または婚約者のいない令嬢は、舞踏会などでは煌びやかな衣装にダイヤモンドや真珠といった透明または白いアクセサリーを身につけ、結婚ないし婚約するとその相手の特徴の色を身につける習わしとなっている。彼女は今、他の誰かではない私の色を身に纏っているため、彼女を見かけた人はディーが誰かと婚約していると思っているだろう。ディーもそのことを知っているはずなのに、何も言わず私の贈る品を受け取り身につけているのだから、私の気持ちにも気付いているはずだ。
──本当なら、ドレスも贈りたいが…楽しみは、もう少し先にとっておこう
彼女の頬を撫でると、嬉しそうに目を細めて私の腕の中に収まる。もう一度彼女の唇を啄むと、彼女の身体から香るコロンが私の鼻をかすめた。
──次は香水でもいいな
なんて、彼女に会う度に贈りたいものが次々と頭の中に浮かび、帰ったら調香師を呼ぼうと決めた。
「おかえりなさい!若っ」
彼女との短い逢瀬が終わると、私の帰りを待っていた部下がにやりと薄気味悪い顔をしていた。いつもは小言の一つや二つ、または不機嫌な顔をして私の事など無視をするのに、今日は何故か玄関先まで出迎えている上に笑っている。この表情の時は私が大体変な事が起こる前触れなんだが、部下は変な事が好きなので面白くてしょうがないみたいだ。
「若っ!聞いてくださいっ!なんと若の想いびとの次女殿がアチェール公爵に王子の婚約者候補から外れたいと直談判したとの報告がありました!」
「…本当か?」
「ええ、彼女に仕える侍女からの言葉なので確かな筋です…その事でアチェール公爵は頭を抱えているらしいですがな」
「…そうなのか」
真面目で堅実なアチェール公爵の姿を思い出し、ついに私も動く事に決めた。
「なら頼みたい事がある、まず──」
***************
国立図書館は国からもらう国民の税金で運用されてはいたが、貴族からの寄付も受け付けていた。
「新しいソファーの座り心地はどうだ?」
彼女の行動を報告されてから、数週間後。私は諸々の処理のため中々図書館へと行く事が出来なくなっていた。
「ルキ様っ!」
久しぶりに図書館のいつもの一角に行き、窓際に置かれたソファーに座って、ボーッと外を眺めていたディーが私の声に気がつくと、珍しく大きな声を上げて私の元へとやってきた。体当たりするように私の身体に抱きつくと、私は彼女を抱きしめ返した。
久しぶりに香る彼女の匂いを胸いっぱいに吸い込むと、疲れが吹き飛ぶのを感じた。
「…ごめんなさい、大きな声を上げてしまって…淑女としてあるまじき行為でしたわ」
恥ずかしそうに頬を赤らめて言い訳をする彼女も可愛くて、また一つディーの可愛い所を見れたと嬉しい気持ちになる。このままここで立っていてもしょうがないと、彼女を横抱きに抱き上げて歩きだすと、彼女は落ちないように私の肩に手を置いた。
新たに置かれたソファーに私が座り、その私の足の上に彼女を横向きのまま座らせると、彼女は私の首の後ろへと手を回してキツく抱きついてくる。
「…お会いしたかったですわ」
「私もだ」
私も彼女の背中に腕を回すと、お互いの身体が密着する。彼女の首筋に顔を埋めたら、会えなかった分を詫びるように彼女を抱きしめた。
**
初めて彼に気がついたのは、国立図書館で会った時だった。
夢中になって歴史書を読んでいるなか、爽やかなレモンとムスクが香って現実に引き戻された時だった。
隣からした匂いを知りたくて机をチラッと見ると、広げた本の上に、細長いのに角ばった陶器のような美しい手が見えた。ドキッとしたのは一瞬で、本のページを指先が宝物を扱うようにそっとページを捲る。
──隣に座ってる…?なんで
国立図書館の歴史の書物が置いてあるこの一角は専門書ばかりで大衆的な読み物が置いてないためか、あまり人気がないみたいで、この場所で人がいる所を見た事はなかった。静かに勉強出来るから気に入っていたけど、彼──ルキアーノ・トロッツイ公爵家当主が側にいても嫌な気持ちにならなかった。むしろ気さくで優しい人という印象でしかなくて、麗しい見た目に反して大変優秀で気難しい人と令嬢とのお茶会で聞いていたが、私の話にも真剣に耳を傾けてくださる、噂とは真逆の人だった。
彼と会える時は私の心臓が早鐘を打つみたいにうるさいし、彼に微笑まれると呼吸を忘れて息を止めてしまう。最初は何か心臓の病気になったかと思ったが…これが好きという気持ちだと、割と早い段階で知った。姉の部屋にある大衆恋愛小説を見つけて、姉に勧められるまま読むと、本の中の登場人物のヒロインが私と同じ症状を呈していたからだ。
それと同時に、彼は私のような醜聞の絶えない人とは合わないと瞬時に悟った。彼は将来を約束された尊い人で、正確には何の契約も交わしていないが、私は王子の側妃として過ごしているのだ。
例え王子と会っていなくても、その事実だけは変える事は出来ない。かと言って、父が側妃の話をなかった事にしたら、すぐに他の貴族から縁談が持ち込まれるだろう。彼以外の人と結婚するなんて、まっぴらごめんだった。
──この恋は誰にも言わないわ
だって、彼は私との会話で楽しそうにしてくれている。他の貴族とは違い愛称で呼び合うだけでも、それだけで充分だと、その時は本気でそう思っていたからだ。
だが…初めてキスをした時から、全てが変わってしまった。まるで私を愛しているかのように、彼は残酷に私に愛を囁く。より一層距離が近くなると彼の香水が私の空気のようになり、匂いを嗅がないと悲しくて上手く息が出来なくなると勘違いしてしまうほどになる。声のトーンも、しっとりと濡れた唇と厚い舌が私の口内を弄り、スッとしたスタイルの良い身体だと思っていたが、抱きしめられると分厚い胸板と力強い腕を知ってしまったら、もっともっとと欲しくなってしまう。彼から貰う彼の色が入った小物を身につけると、いつも側に居てくれていると幸せな気持ちになる。貰った当初は図書館にいる間だけ付けていたけど、父も母もきっと気づいているのに何も言って来ないのをいい事に、日常的に身につけるようになった。
キスをされ、抱きしめられ、他愛のない話の間にまた啄むようなキスをする。次の約束をする訳でもない僅かな逢瀬を、誰にも邪魔をされたくないと思い始めた。以前なら気分が乗らない時は図書館に行かなかったのに、彼がくるかわからなくても雨の日も意地でも行くようになった。
なるべく彼の負担にならないように、私の心の奥底にある気持ちに蓋をしていたのに、私の気持ちが重いのに気がついたのか、ついに彼が来なくなった。それは私の心に影を落とし、何の気力も湧かない日々が続いた。それでも図書館に行っては、彼がくるかも知れないと僅かな希望を抱いてしばらく過ごし、絶望的な気持ちで帰る。
彼と会わなくなって2週間が過ぎたある日、いつものように国立図書館に行くと、いつもいる受付の司書が新しい情報を教えてくれた。いつも、新しい本の入荷などを教えてくれる顔馴染みの女性だ。
「本日から各コーナーにソファーを設置する事になりました」
「まぁ、そうなの?」
司書が手を向けた先を見ると、確かに先週末きた時には空いていたスペースに2人掛けのソファーが置かれていた。
「はい、トロッツイ公爵ルキアーノ様よりご寄付を頂きました」
「ル…トロッツィ公爵の」
思わずルキ様と言おうとして言い直したが、幸いにも司書は私の変化に気がついていなかった。
「はい、アチェール様のいつものコーナーにもありますので、硬い木の椅子に疲れたら柔らかなソファーでお休みくださいね」
「ありがとう、すごく嬉しいわ」
司書とはにこにこと話すが、心の中では疑問ばかりが頭に浮かぶ。
──ソファーよりも、ルキ様にお会いしたいわ
むしろ、ソファーを見るたびに彼を思い出して、余計に惨めな気持ちになってしまう。
彼にとって私は"ひと時の遊び"だったから、いつもいる図書館で快適に過ごせるように、お詫びの品としてソファーを寄付した、と気がついた時には、ルキ様が図書館に来なくなって23日目となっていた。
やっとうじうじ悩む自分の気持ちに踏ん切りをつけようとしたその矢先、また彼が現れた。
「新しいソファーの座り心地はどうだ?」
久しぶりに聞く低音の声に、窓の外を見ていた私は頭よりも先に身体が動いた。彼に抱きつくと、感極まって涙が瞳に溢れる。感情を露わにするなんて淑女としてあるまじき行為だと恥じつつ、だけど彼の腕から離れる事は出来なかった。
──好きです…ううん、愛してます
嬉しい気持ち、彼への純粋な気持ち、置いていかれた寂しい気持ち、色々な感情が入り混じり、彼に伝えた言葉はシンプルに会いたかったと、それしか口から出なかった。
彼は簡単に私を横向きで抱き上げると、歩き出してソファーへと座った。彼の膝の上に横向きのまま座って、言葉よりも多く口づけをした。
「…それ、気に入ってるの?」
「っ、ぁっ」
「あぁ、すまない」
胸元にある黒い真珠のブローチは、彼からの贈り物だ。頬や首にキスをされ、ふっと笑う彼は、私の胸元にあるブローチをそっと撫でると、彼の右手の指先が私の胸元に当たった。思わず声を上げてしまうと、彼の手がさっと引いた。
「やっ…やめないでください…私…ンッ」
手を引いた彼の右手をとっさに取ると、彼は私の首の後ろへと左手を回して自分の方へ引き寄せると、私の口を塞いで噛み付くような荒々しいキスをした。
「いいのか…?ただの図書館で話す間柄には戻れなくなる」
「えぇ、もう私の心は決まってますわ」
彼の手を自分の胸元に戻すと、彼の手が私の胸に添えられた。最終確認するかのように、もう一度彼から告げられると、私は彼の首の後ろへと回して、自分から彼の口にキスをした。
──それにもうキスをしてしまったわ
キスを求める時点で、もう元の2人には戻れないし、戻りたくなかった。私の心は完全に彼を求めているし、なかった事には出来ない。それに今この時を逃して、彼が図書館に来なくなったら?そうしたら私はまた絶望的な気持ちを味わうのかと思うと、今このチャンスを逃したくなかった。
「…お慕いしております…心から」
本当なら愛していて、貴方がいないと生きていけないと彼に伝えたかったが、中途半端な立場にいる私が彼を縛る権利なんかない。公爵家の次期当主である彼を私のものにしたい──そんな自分勝手でわがままな話があるのだろうか。
──出会った場所が社交界だったならば
幾度となくそう思ったが、私なんかが彼に声を掛けることも、ましてや近づくなんて不可能に近いのだ。彼の麗しい外見なら、他の令嬢が黙っていないし、独身だけど婚約者もいない、誰かの候補じゃない令嬢が、彼には相応しいから。
「…今日だけ…ここだけでもいいから…私を愛してください」
「ここだけなんて…ディーは…ったく」
最大の譲歩を見せたのに、彼は呆れたようにため息を吐くと、私の胸を掴んだ。
「君を手放すなんて、私がするわけないだろう?」
一段声を落とした声色は、怒っているのかどうなのかわからない。
「…嬉しいですわ」
だけど、私のせいで笑う以外の感情を露わにする彼の怒った顔も見たいと、歪んだ心がそう告げた。
うっとりと彼の肩に頭を乗せると、彼は私の胸を揉み始める。ただコルセットをしているから、なかなか揉まれているという実感がわかない。
「即物的だが許してくれ」
彼はそう言って私のドレスの裾の中へと手を入れると、私の足首から順にふくらはぎから太ももを伝って手のひらを這わす。
「嫌か?」
本当なら恥ずかしくて死にそうだったけど、私の反応次第では止めてしまい、もう2度と彼は私に手を出さないだろうと瞬時に理解してしまって、私はふるふると首を横に振る。
「っ…平気ですっ」
本当はこのまま彼と結婚して結ばれたらと思うが、それはありえないと頭で否定する。最初は好きな人と、出来るなら一生を添えたい…が、叶わぬ夢となりそうだ。そもそも、過去に父に王子の第二候補から外して欲しいと言わなかった自分にも非があるのだ。
まさか彼に恋をしてしまって、こんな関係になるとは夢にも思わなかったと今更後悔しても遅い。
この先も結ばれないなら、ひと時の思い出を心にしまって、これからの未来を生きたい。だけど今彼の手を拒否したら、この機会はもう永遠にやってこないと感じた。
「ディー、今日じゃなくても…」
私の考えている事など、彼にはお見通しみたいだったが、私は今日どうしても彼の物になりたくなった。彼の右頬に左手を添えて私の方を向かせると、彼の口元に口づけをした。
「…もう心が離れてしまったと…思うのは嫌なんです…貴方が私の初めての人になって欲しい」
「ディー」
ルキ様は私の頬とこめかみにキスをすると、私の首に唇を押し付けた。まるで私が彼を拒否していないかどうか確認するように私の反応を見る。
「…ふふっ」
彼の胸に手を添えた私は、髪が私の首に当たって擽ったくて笑ってしまう。
張り詰めていた空気が霧散したような気がして、ルキ様は私の身体を抱きしめた。
「…愛してる…ディー」
「…私もですわ、ルキ様」
彼の言葉に返事をすると、彼は私の頬を親指の腹でさらりと撫でた。ゆっくり近づいてくる彼の顔が、薄く口を開けるのを見たのを最後に、私は瞼を閉じた。
「はっ…ぁ…っ」
ソファーに寝かされ、ドレスをたくし上げられた私は、淑女にあるまじき行為をしている。足を広げられ、履いていた下着などすでに太ももから足首へと落ちていたのにも構わず、ルキ様は床に膝をつけて私の下半身に顔を埋めていた。
さざ波のように引いては来る何かが怖くて、たくし上げられたドレスを掴んでいると、彼は私の右手を取り、手を繋いでくれた。
「ぁっ、っ」
「ああ、ここか、ディーの好きな所は」
一ヶ所彼の舌が蜜口を掠めると全身が強張り、繋いだ手を強く握った。舌を這わされた蜜壺は濡れており、彼は愛おしそうに吸う。最初は漏らしてしまったと涙が出てしまい、何も知らないんだね、嬉しいよと言いながらルキ様が一から説明してくださった。これは粗相でもないし、病気でもない、私の身体の中から生まれた快感で、2人の愛を深めて子孫を残す大事な行為で…と、丁寧に説明され、いずれは王子の妃となるかもしれないから、ちゃんと家庭教師から習っていたのに、それがこんなにも恥ずかしくてむず痒い感覚が快感だなんて知らなかった。文字で教わるのと実践とは全くの別物だと改めて思った。
「ここで、子種を注いだら私の子が生まれるんだよ、そうだね、子が宿るようにたっぷり注ごうか」
彼は私のお腹と下生えの際を少し強めに押しながら、うっとりとした声で独り言のように呟く。
私が返事をする前にまた彼は私の下半身へと顔を埋めると、蜜口からここと言っていた場所のした当たりを目掛けて指を入れた。
「あぁ、私の指をぎゅうぎゅうと締め付けて離さない、私のを入れたらどうなるのだろうか」
彼は指先を出し入れしながら、蜜口から太ももの付け根にまで舌を這わした。
──この指よりも大きなものが入るの?
充分に彼の指は太くて固いと思っているのに、これ以上大きなものが私の中に入らないと思っていたが、ルキ様は私の視線を感じたのか視線を上げた。
「…もうそろそろ、入れようか…私も早くディーの中に入りたいから」
彼は私の蜜壺の中に指を埋めたまま起き上がると、ソファーに片膝をついた。
私の口を塞ぎ熱い口づけを交わすと、彼の指が私の蜜壺の中からいなくなる。
「こっちを見て、ディー」
「んっ、ぁ」
蜜壺から指が無くなり、喪失感を感じて思わず下半身に視線を向けると、ルキ様が私の顎に指を添えて上を向けた。お互いの視線がぶつかると、彼の瞳に私が映る。甘噛みをされながら啄むキスを繰り返していると、指とは違う圧倒的な熱さと太さを持った何かが私の蜜口に当たり、ゆっくりと蜜壺の中へと入っていく。
「あ…ぁあ…っ」
「っ、ぐ…はっ、ディ…ッ」
燃えるような熱さの固いものが私の蜜壺の中を広げ、彼を離すまいと身体が勝手にきゅうきゅうと締め付ける。背中がのけ反ると、彼の腕が私の背中に回り、そのまま腰に下がると繋がった箇所が抜けないように固定した。
彼が私の中を進む度に、彼の身体が屈み重なりそうなくらい近くなる。
「はっ…っ、っん」
ぐんっと彼の腰が勢いよく蜜壺の中を進むと、最奥まで届いた熱い塊が私の中に留まる。
「っぐ、んっ」
やっと一つになれたと、彼は言わんばかりに私の顔中にキスの雨を降らせ、私の中にいる彼が馴染むまで待ってくれる。
「ル…キ様っ」
いつもよりも少し高く舌ったらずになった私の声に、彼は私の身体を抱きしめた。
「ディー」
彼はゆっくりと腰を引くと、ぴりぴりとした電流が身体の中に起こる。全てが無くなってしまうのかと思うと、蜜壺の中へと勢いよく戻る。少しずつ始まった抽送はやがて早くなると、ルキ様の背中に手を回して起こる快感に身を委ねる事しかできない。
「あっ、あ…っ、んぅっ」
「ディー、可愛らしい声を聞いていたいが、少しだけ抑えようか」
彼は快感でわけが分からなくなっている私の口を自分の口で塞ぐと、腰を一段と早くした。布の擦れる音だけが聞こえる気がして、ここがどこかを思い出してしまうと、さっと頬が赤くなって彼の胸に顔を埋めると、彼は、煽らないでよ、可愛くてめちゃくちゃにしちゃいそう、と耳元で囁きながら、私の中にいる固いものをぐんと大きくする。
「~~~っ!!」
「っ、っ、っ」
繋がった箇所から迫り上がる快感が、全身に巡るスピードが早くなり、ついには目を閉じているのに目の前がチカチカと光っている。全身が強張り、何も考えられない無の時となると、低い唸り声と共に蜜壺の中に注がれた…ルキ様のいう子種が注がれると一気に熱くなった。
彼は繋がったまま全力疾走したかのように肩で呼吸をし、私はしばらくの間全身の力を緩める事が出来なかった。
「さぁ、ディー、次の時間だ」
彼は初めての快感に、まだぼぅっとする私の頬にキスをすると、今度は何がどこに入って、私の身体を悦くしているのか実践を交えて教える。私が気持ちいい事を学び、声を抑える事が出来なくなると、彼は上等なネクタイを私の口に入れた。
「例え、誰もいないと分かっていても、君の声を誰にも聞かせたくない」
と、揺さぶられながら彼に言われても、彼の言葉を頭の中で理解する前に新たな快感の波にのまれ、ただ意味のない単語の羅列にしか聞こえなくなる。
ドロドロに愛し合って、もう私の身体は彼と離れられなくてくっついてしまったんじゃないかと思い始めた頃、やっと私たちの身体の繋がりが解けた。
「あっ」
「そんな顔をしないで、また中に戻りたくなる」
彼が抜けた後は酷い喪失感で、蜜口が浅ましくきゅんとなる。幾度も注がれた証の流れが蜜口から止まったため、彼には直ぐにバレてしまったが、彼は私の下半身をハンカチで拭った。
「は…」
成人してから下半身を拭かれた経験などなかった私は、羞恥で死にたくなったが彼は特に気にした様子はなかった。彼はハンカチを畳むと自分のポケットに入れ、私の下着を履かせドレスの裾を直した。
「さぁ、話をしようか…私たちの将来について」
私よりも彼の方が疲れているはずなのに、彼は私を楽々と持ち上げると、私をソファーに座った彼の膝の上へと横向きに座らせた。
「私はもう…あなたの物になりましたわ」
真剣な眼差しに、情事後の色気も出ているようで、私はうっとりと見惚れた。
***************
「従兄、お久しぶりです」
スッとした鼻筋で整った顔をして、自分よりも王族の風格のある従兄は、王族以外が入れない城の奥にある貴重な植物のある温室で、王族である自分を呼んで紅茶を飲んでいた。
足を組む姿はまるで一枚の絵画のように美しく、周りに植えられている世界の希少で心奪われる植物が彼の美しさを際立たせるためにあるアイテムのようだ。
「やぁ、次期国王陛下、公務の方は順調かい?」
王族が現れたらどの貴族も席を立ち、恭しく王族に賛称し挨拶をするのに、この従兄ときたら、王族が自分に挨拶をするのが当たり前だと思っている節がある。
「…突然呼び出してどうなされたのですか、城に居たからよかったものの、居なかったらどうなされていたんですか」
次期国王陛下になれるか分からない不安定な立場だった自分に対して、いつまでも変わらない従兄は、コロコロ態度を変える他の貴族よりかは信じられる存在なのも確かだ。成人したとはいえ、社会経験も少ない自分は、政策に忙しいと暗に伝えるために、分かりやすいため息を吐いてみるが、この従兄は気にもしないだろう。むしろ──
「おや?私も忙しいんだよ、君に構っている暇なんてないんだ、それにね、君が何処にいるかなんて知っているから、こうして私がここにいるんじゃないか」
などと、ちょっとした不満を零しただけで、2倍にも3倍にも返ってくるから厄介なんだ。幼い頃から叩き込まれた王族としてのやり方も、彼の前では意味を成さないと学んだ。
「…ええ、そうでしたね」
従兄に口でも実績でも勝った事がないから、これ以上のやり取りは不毛だと、諦めた僕は従兄の座る席の向かいに腰掛けた。
僕の前に淹れたての紅茶を給仕したメイドが居なくなると、従兄は徐に口を開いた。
「…他でもない、私の伴侶となる女性、つまり君の婚約者の妹なんだがね」
「…アリッサの妹…?ああ、アチェール公爵の娘、ディーナ令嬢ですか」
「そうだとも、ディーナ令嬢に関する事だが…いい加減、アリッサ嬢と結婚してくれないかね」
「…といいますと?」
「君がいつまで経っても、公務公務と言って式の一つも挙げないせいで、私が彼女と結婚出来ないじゃないか」
「…そんな事言われましても…こればかりは父と母…それから」
貴族達への通達も含めた準備期間が必要、と続けようとして、従兄の雰囲気がいつもと違う事に気がついた。
「私の天使がいつまでも他の奴の物だと、噂が広がっているのを黙って見ているほど、私の心は寛大ではないのだよ」
口元は笑っているのに鋭い眼差しをしている従兄が、地を這う低い声で話す言葉の節々から珍しく不機嫌だと悟る。
──従兄がこんな感情を露わにするなんて
いつも優しい笑顔で人々を魅了する従兄は、僕にも誰にも心のうちをそうそうに明かしたことがない…というか見たことがない。
「君の父上には私から伝えた…このひと月で式を挙げるんだ」
「そんな急にっ」
無理な話を持ち出した従兄に抗議をすると、従兄は他の貴族に向けるように微笑みを深くする。
「これは、国王陛下の命だよ…ああ、ウェディングドレスのデザイナーはこちらで用意するよ、国一番の腕で予約の取れない今流行りのデザイナーだから、君の婚約者も喜ぶだろう」
確かに従兄から聞かされたデザイナーの名前は、アリッサがドレスを作りたいのに、予約が取れなかったと言っていた人の名前で、彼女に伝えたらきっと泣いて喜ぶに違いない。
最高の従兄を持って良かった、と僕に言わせたいだろうけど、僕は知っているのだ。
「…そんなにディーナ令嬢と結婚したければ、僕たちの事など気にせずに、すれば良かったじゃないですか」
「彼女はね、とても繊細なんだよ…姉のために身代わりになると自分を追い詰めるほどに、ね」
姉が結婚していないのに、身代わりの予定だった自分が先に結婚出来ないという彼女の望みを叶えようとする…一見ディーナ令嬢の気持ちに寄り添った心優しい従兄となるが──つまりは、さっさと彼女と結婚して身も心も手にしたいだけである。
「そうだな…私にかかれば、デザイナーに頼んで、急ピッチでドレスを仕上げてもらうから、明日にでも結婚式を挙げられるよ」
僕が結婚をすると分かると、途端にご機嫌になった従兄は、また優雅に紅茶を飲み始めた。
「…ですからね」
今のうちに結婚式の日程を決めなければ、従兄が明日にでも式を仕切る勢いだ。どうしようかと、考えていると、従兄は胸ポケットから時計を出して、見たと思ったら突然席を立った。
「そろそろ、私の天使が起きる時間だ…全てが初めての今日くらいは側にいないとね」
と言い残して、温室から出て行ってしまった。
「…なんなんだ一体」
取り残された僕はそう零すが、誰もいない温室に声が消えた。
後日、大々的に発表された王子の結婚式の日程は、歴代の王族達よりも早い期間で準備され行われた。人気のデザイナーの手によって作られたドレスは、貴族令嬢の憧れの的となって、たちまち流行となった。
その後すぐに、ひっそりと行われたトロッツィ公爵の当主の結婚式は、異例の近親者のみが参列する質素な式となった。そして流行りのドレスの身体のラインを強調するデザインとは180度異なる、ゆったりとした大きめなサイズの純白のドレスを身につけたディーナ・グリゼルダ・アチェール公爵令嬢のお腹には、もう2人の愛の証があった。
ヴィラン公国では、苗字が短いほど王族に近しい立場の人であり、または王族の近親者となっている。その中でも、苗字を持たない王族の次にあたるトロッツィ公爵家は、どの貴族よりも高貴で尊い存在とされている。
なぜなら
大昔、国王陛下の弟だった当時のトロッツィは、爵位を賜ると、子孫までもが代々男児を産み続け、王族に一番近い血脈を守り続けているのだから。
身体の弱い姉が王子に嫁げなくても、私──ディーナ・グリゼルダ・アチェールは、このヴィラン公国の宰相の要職につく、アチュール公爵の次女として生まれた。
2歳年上の姉のアリッサは生まれつき身体が弱く、ベッドの上にいるのが多い幼少期を過ごしていたため、アリッサが王子に嫁げない場合を想定して、私が王子の婚約者の第二候補として決まった。
私が成人を迎える18歳を過ぎると、姉は普通の人よりも体力はなかったが、積極的に社交界へ出るようになった。しかし、私の地位は相変わらず王子の第二候補に留まり、新たな婚約者をつけられる事はなかった。
まだ勉強をしたかった私の思いと、姉が元気になったとはいえ、まだ体力的に子供が産めるか不安が残るため、公爵家から王妃を出したい父の意向が一致した瞬間でもあった。
こんな歪な関係が2年も経つと、いつしか王子の方が私を離したくないのではないか──またはアチェール公爵の次女である私が勉学を共にしてきた王子に恋をしてしまって、王妃にはなれないが、王子のそばにいられる側妃を望んでいるのではないかと、社交界で噂が流れるようになった。
***************
長い銀色の髪が日に焼けていない真っ白な肌の腕に当たり、男はどきりとした。
マイナーすぎて誰も近寄らない、一番奥の一角にある地方の歴史の書物がある国立図書館で会った少女は、いつも綺麗な銀色の髪をポニーテールにして、大きな黒縁のメガネをかけて本を読んでいたり、書き物をしたりしていた。
最初に彼女を見かけたのは、もう2年も前で、たまたま地方の視察の帰りに調べ物をしたくなり立ち寄ったのがきっかけだった。一目で彼女から目が離せなくなった私──ルキアーノ・トロッツィは、なったばかりの公爵家の当主として、久しぶりに訪れた図書館で運命の出会いを果たした。
30歳前に当主になった途端に、周りからは世継ぎを求められて辟易していた。母の事を愛してはいるが、それでも仕事一筋でやって来た父と同じで、息子の私も女性よりも仕事の面白さに夢中になっていた。
天然ウェーブの癖毛の黒い髪に切れ長の目で、美男美女の夫婦として仲睦まじい父と母のいいところをとったような綺麗に配置された目鼻口と笑うと近寄りがたい冷たい印象から一転、一気に幼くなる甘いマスク、じっと見られると緊張すると出会う令嬢全てに言われてきた。
私が近づいただけで気分が悪くなったと寄りかかる令嬢や、あからさまに誘惑してくる女性に次第に嫌気が差し社交界にも参加しなくなった。
親が勧める縁談で結婚するのかもしれないと思い始めていたなか、ついには恋に落ちたのだ。それも、王子の第二婚約者候補、またの名を王子のお手つき令嬢である、アチェール公爵の娘のディーナ嬢に一目惚れをしたのだ。
貴族の身分がないと入ることは難しい国立図書館で、従者に命令して彼女を調べさせた。
『彼女が、王子の婚約者…だと?』
毎日のように図書館に行く彼女の正体を知った時の衝撃は今もなお、私の心にある。
彼女は、平日はほぼ毎日午前中に図書館で勉強をし、午後には自分の屋敷へ帰ってしまう。午後にはお茶会や用事がなければ部屋で読書や縫い物をしていると、アチェール公爵家で働く使用人から聴取した従者から報告を受けた私は、午前の業務を調整して、彼女のいる国立図書館へと足を運ぶようになった。生まれてこの方誰にも興味が沸かなかったのに、たまたま寄った図書館で一目見た彼女を忘れられず、無意識のうちに午前の仕事を中断していた。王子の婚約者候補と知ってもなお、彼女に会いたいと強く願うようになるのは必然なような気もする。
最初の頃の彼女は、私が近くに寄っても気が付かなかった。彼女がいる10人は座れる大きな机の前に、誰もいないのに敢えて対面で座って、適当に本棚から取った本を広げて読んでも、彼女の視線は下を向いたままで、本を読み終わった後の彼女は、ほぅっと紅潮した頬を緩めてため息を吐く艶かしい姿に、私の心の中がさらに騒めいた。2ヶ月、半年も過ぎても、あまりに私に気が付かないものだから、私の存在に気がついて欲しいと願うようになり、意を決して彼女の横に座ると、やっと彼女はやっと私に気がついた。
しかし、他の令嬢と違うのは、私を見ても頬を赤らめるわけでもなく、かといって喜ぶわけでもなく、何故隣に座るのかと困惑している顔をしている所だ。
「…こんにちは、いつもこの図書館にいますね」
彼女が私の存在に気がついてくれたのが嬉しくて、つい笑みが溢れると、彼女は固まってしまった。誰にもされたことのない新鮮な反応も、私を喜ばせるだけで、笑みを深めてしまう。ご令嬢に見せたら自分に気があるんじゃないかと誤解されてしまいそうな、心から愛おしいと思う笑顔を見せれば、彼女はさらに戸惑って、あろうことか本棚の先にある通路に視線を向けた。
──ショックだなぁ、これでもこの笑顔は他の令嬢には好評なんだけど
ショックを受けているなんて微塵も顔には出さずに、彼女にもう一度微笑むと、彼女はズレていないのに黒縁のメガネの位置を直した。
「こんにちは、いつも…は、いませんわ、今日はたまたま近くを通ったので時間を潰しているだけですわ」
「…へぇ、そうなんだ」
毎日図書館に来ているのに、嘘をついてまで私と話したくないと暗に言っている。
──うそつき
私が彼女の名前も、普段何をしているかも知っているなんて、ツユほども思っていない彼女がしらを切る姿が可愛くてしょうがない。声は思っていたよりも少し高く、だが耳障りでもない音色も話すトーンも、私の質問に即答しないで少し考えてから慎重に答える姿に好感が持てる。こんなにもわくわくするのは、何年ぶりだろうか、と幼少期に遊んだ過去を今は思い返す時間も惜しい。
──いや、もうとっくに彼女に惚れている
彼女と話して確信を得ると、私は彼女と図書館で会うと声を掛けるようになった。
「若、頼んますよ~、仕事を抜けられると仕事が溜まるんすよ」
「私は今、至急の仕事は抱えてないはずだが?」
最初は私の遅い初恋に暖かい眼差しを向けていた部下も、図書館に通うのが2年にも及ぶと、午後に溜まる仕事があると小言をいうようになった。抜けるのはせいぜい平日の週に3日、それ以外の日は従者に言って彼女の様子を見てもらっていたにも関わらず、もっと彼女と過ごす時間を増やしたいと思うようになっている。
当初は彼女を見かけるだけ、ほんの数分話せれば満足していたものの、今は2時間雑談しても物足りないくらいにはなっていた。
「そうまでするんでしたら、もう婚約者に名乗り出ればいいじゃないですか」
「そうしたいのは山々だが、彼女がまだ王子の第二婚約者候補なんだ、すでに婚約者がいる令嬢に直談判なんて出来るはずないだろ?」
「…そんな事言ったって」
それなら令嬢に会いに行かなければ、彼女の事を忘れられるじゃないか、と部下の冷めた眼差しが私に刺さる。
「それに相手は王子なんだ、公爵の力を利用してどうこう出来る話じゃない」
「…王子相手じゃなかったら、公爵の力を利用するってことか」
呆れた声の部下に、何を言っているのかわからなくなる。
「そんなの当たり前じゃないか、愛している女性と生涯添いたいと願うのは当然の考えさ」
たった数時間話しただけでも、こんなにも幸福感があるから、仕事から帰った時に、彼女が私を出迎えてくれたら…疲れも吹き飛ぶはずだ。
「だからって、31歳になる公爵がする事じゃないですが」
行動を起こさず、純粋な関係のまま彼女に会いに行く私から、ふぃっと視線を外した部下が見た先には、山盛りに置いてある仕事の書類があった。2時間彼女と過ごすのに加え、午前中は移動時間も含めて不在となる間も日々の仕事は待ってくれない。きっと今日も夜遅くまで仕事を片付ける羽目になるばすだが、明日になれば彼女と会える。
「…さあ、始めよう」
私がそう部下に告げると、彼はため息一つついて山盛りの書類に手を伸ばした。
***************
「一つは、疫病の蔓延を防ぐための処置でして」
「ほう、ではそのような対策をすれば、今の状態から脱却出来ると?」
「ええ、明日には…というくらいすぐには結果は出ませんが、数週間のうちに改善が認められますわ」
いつものように図書館の奥にある歴史書が並ぶ誰も近寄らない一角で彼女の隣に座り、小さな口を動かして一緒懸命私に力説する彼女と領地経営の意見交換をする。
彼女は幼き頃から帝国学も学んでいるから、過去の事例に対する解決策もぽんぽん出てくる。そのため他の令嬢のように面白くないと言われることもないし、深い経営の話が出来て実際に自分の領地で試せる選択肢が増えてとても勉強になる。
「…前から思っていましたが、ルキ様の字は綺麗ですね」
彼女の言った事を紙に書いていると、彼女は私の手元を見て呟いた。
「そうかい?君の文字も綺麗だよ」
図書館で顔を合わせてから、2人の呼び名もルキ様、ディーとお互いを愛称で呼ぶようになった。幼少の頃にしか呼ばれなかった愛称で呼ばれると、たまに照れ臭くなるが、嬉しい気持ちも大きい。
ここでは当主ではないただのルキ、ディーも王子の婚約者候補という立場から解放されて、友達といるかのように笑い、時には真面目な話をして、バカ話でふざけあえる。くすくすと笑う彼女は、本を読む時とは雰囲気が違って可愛い。
「そうだ、ルキ様に見せたい書物を発見しましたのっ」
両手を合わせてはしゃぐ彼女に釣られて、私も思わず笑ってしまう。
「なんだい?」
「以前ルキ様が仰っていた、ヴィラン公国の始まりを記した本を見つけましたのっ…こちらですわっ」
真剣な表情で本を読む時とは違い、髪と同じ色の銀瞳をキラキラと輝かせ立ち上がると、歴史書のコーナーの奥へと向かったので、私は彼女についていくことにした。
天井までつく細長い棚の壁際にある下から5段目──丁度彼女の視線と同じ高さに並ぶ本棚から濃緑のカバーの本を一冊取り出すと、私の前に表紙を見せた。
「…ヴィラン公国の農作物の歴史?」
「ええ!そうですわっ!こちらは、主に農作物の歴史が書いてあるのですが…ほらっ!ここっ!」
私が知りたかったのは、この国始まりの話だったのに、関係のなさそうな農産物の本を出されて、私が戸惑っていると、彼女は本を開いてパラパラと捲り、ある章を開いて指を指して教えてくれた。
「…ヴィラン公国は、国として成り立つ前に農作物が育たない痩せた土地だったが、のちの王族となった当時の…本当じゃないかっ!」
私の声に合わせて彼女の細くて美しい指が文字をなぞり、読み進めていくと、この国の始まりを知る。
「…っぁ」
私は目を見張り嬉しくなって喜びの声を上げながら彼女を見ると、思いの外近くにある彼女の顔に驚いた。彼女も驚いたみたいで、元々大きな目だと思っていた綺麗な瞳が更に溢れんばかりに開いている。2人の時間が止まったような気がして、私の口が開いて低い声で彼女の名前を読んだ。
「…ディー」
「ルキさ…ま」
彼女の頬に右手を添えて顔を寄せると、素早く彼女の唇に自分の唇を重ねて離れた。唇が重なったのが一瞬だったので、彼女の唇の柔らかさしか感じなかった…が、もう一度彼女の唇の柔らかさを感じたくなって、親指の腹で彼女の頬をなぞり、もう一度彼女の唇に自分の唇を重ねて、自分とは違う柔らかくてぷっくりと膨らんだ上唇を甘噛みした。
「…んっ」
甘い声が彼女の口から漏れると、頭がカッと熱くなる。口を開けて舌で彼女の唇のラインをなぞると、彼女は薄く口を開け、私は吸い込まれるように彼女の口内へと舌を入れた。彼女の持っていた本を取り上げると、本を持ったまま彼女の腰に腕を回し、私の方へ引き寄せて身体を密着させた。私よりもふた回りも小さな彼女は、私の腕の中にすっぽりと収まっている。
甘い声、熱い口内、彼女の息が口から漏れて、私の舌に当たって舌を彼女の口内で押し進めていると、さっきから私がする事にディーは硬直している。彼女がきっと初めてのキスだというのに、貪るようにキスを続けてしまった。彼女はカクンと膝の力が抜けて倒れそうになったため抱きしめた。
「…っ、ルキ様」
「ディー」
瞳を潤ませ見上げられるとまた彼女の唇が欲しくなり、彼女のメガネを外した。メガネの下の瞳は、溢れんばかりに大きくて、私を誘うように濡れていた。口を少し開けて息をする時も赤い舌がちろりと見えて、普段の彼女の清楚な雰囲気が一転して色っぽい。もう一度口を重ねた時には、本棚に彼女の背中を押し付けて思う存分彼女の口内を長い時間堪能した。
***************
「ルキ様」
「なんだい?ディー?」
彼女に甘い声で名前を呼ばれれば、腕の中にいる彼女を抱きしめる力を強めた。
初めてキスをしてから、数ヶ月。とても有意義な意見交換をする傍ら、一目見ればとても知り合いの男女の距離感ではなくなった。会えば開口前にキスをし、離れていた数日を埋めるようにお互いの口を求めた。たっぷりと堪能した後は、彼女の横に肩に手を回して座り、近況報告のような雑談をしつつ、言葉を交わす合間に口づけをしあう。彼女が私の肩に頭を乗せると、それは私からディーへとキスをして欲しい合図だと最近になって気がついた。私が毎回彼女のメガネを取ってキスをするものだから、いつからかメガネをしてこなくなった。彼女との隔たりがなくなり嬉しい反面、彼女の美しさがこの図書館にくるまでの間に何人もの目に触れたかと思うと、つい彼女の舌に強く吸い付いてしまうという醜いヤキモチの態度をとるようになった。彼女の日常の報告は受けているから、私以外とは過ごしていないと頭では分かっていても、面白くないものは面白くないのだ。
「その口紅毎日付けてるの?それとも私と会う時だけ?…とても似合っているね」
彼女の小さな唇に自分の親指の腹でなぞれば、私の指先に彼女の薄ピンク色の口紅が薄らと移った。
「…ありがとうございます、ルキ様が買ってくださいましたから、毎日付けておりますわ…毎日ルキ様をお側に感じたいので」
ディーは右腕を上げると、私がしたように指先で私の唇をなぞった。きっと彼女の口紅が私の唇に付いているのだろう、嬉しそうに微笑む姿はいつみても美しい。
「可愛い事を言うね、これ以上私を夢中にさせるなんて」
私の唇にある彼女の手を取り、私は彼女の口を塞ぐと、彼女は私のキスに自分の舌を絡ませて応えてくれる。
私は、会うたびに彼女に贈り物をしていた。最初は彼女の唇に合う口紅を、その次はいつも身につけて欲しくて私の髪と目と同じ色の黒い真珠を使ったブローチを、その次はブローチと同じデザインになるイヤリング、ブローチとイヤリングと一緒に付けても遜色のないブレスレットと、普段使いも出来る物をプレゼントした。未婚または婚約者のいない令嬢は、舞踏会などでは煌びやかな衣装にダイヤモンドや真珠といった透明または白いアクセサリーを身につけ、結婚ないし婚約するとその相手の特徴の色を身につける習わしとなっている。彼女は今、他の誰かではない私の色を身に纏っているため、彼女を見かけた人はディーが誰かと婚約していると思っているだろう。ディーもそのことを知っているはずなのに、何も言わず私の贈る品を受け取り身につけているのだから、私の気持ちにも気付いているはずだ。
──本当なら、ドレスも贈りたいが…楽しみは、もう少し先にとっておこう
彼女の頬を撫でると、嬉しそうに目を細めて私の腕の中に収まる。もう一度彼女の唇を啄むと、彼女の身体から香るコロンが私の鼻をかすめた。
──次は香水でもいいな
なんて、彼女に会う度に贈りたいものが次々と頭の中に浮かび、帰ったら調香師を呼ぼうと決めた。
「おかえりなさい!若っ」
彼女との短い逢瀬が終わると、私の帰りを待っていた部下がにやりと薄気味悪い顔をしていた。いつもは小言の一つや二つ、または不機嫌な顔をして私の事など無視をするのに、今日は何故か玄関先まで出迎えている上に笑っている。この表情の時は私が大体変な事が起こる前触れなんだが、部下は変な事が好きなので面白くてしょうがないみたいだ。
「若っ!聞いてくださいっ!なんと若の想いびとの次女殿がアチェール公爵に王子の婚約者候補から外れたいと直談判したとの報告がありました!」
「…本当か?」
「ええ、彼女に仕える侍女からの言葉なので確かな筋です…その事でアチェール公爵は頭を抱えているらしいですがな」
「…そうなのか」
真面目で堅実なアチェール公爵の姿を思い出し、ついに私も動く事に決めた。
「なら頼みたい事がある、まず──」
***************
国立図書館は国からもらう国民の税金で運用されてはいたが、貴族からの寄付も受け付けていた。
「新しいソファーの座り心地はどうだ?」
彼女の行動を報告されてから、数週間後。私は諸々の処理のため中々図書館へと行く事が出来なくなっていた。
「ルキ様っ!」
久しぶりに図書館のいつもの一角に行き、窓際に置かれたソファーに座って、ボーッと外を眺めていたディーが私の声に気がつくと、珍しく大きな声を上げて私の元へとやってきた。体当たりするように私の身体に抱きつくと、私は彼女を抱きしめ返した。
久しぶりに香る彼女の匂いを胸いっぱいに吸い込むと、疲れが吹き飛ぶのを感じた。
「…ごめんなさい、大きな声を上げてしまって…淑女としてあるまじき行為でしたわ」
恥ずかしそうに頬を赤らめて言い訳をする彼女も可愛くて、また一つディーの可愛い所を見れたと嬉しい気持ちになる。このままここで立っていてもしょうがないと、彼女を横抱きに抱き上げて歩きだすと、彼女は落ちないように私の肩に手を置いた。
新たに置かれたソファーに私が座り、その私の足の上に彼女を横向きのまま座らせると、彼女は私の首の後ろへと手を回してキツく抱きついてくる。
「…お会いしたかったですわ」
「私もだ」
私も彼女の背中に腕を回すと、お互いの身体が密着する。彼女の首筋に顔を埋めたら、会えなかった分を詫びるように彼女を抱きしめた。
**
初めて彼に気がついたのは、国立図書館で会った時だった。
夢中になって歴史書を読んでいるなか、爽やかなレモンとムスクが香って現実に引き戻された時だった。
隣からした匂いを知りたくて机をチラッと見ると、広げた本の上に、細長いのに角ばった陶器のような美しい手が見えた。ドキッとしたのは一瞬で、本のページを指先が宝物を扱うようにそっとページを捲る。
──隣に座ってる…?なんで
国立図書館の歴史の書物が置いてあるこの一角は専門書ばかりで大衆的な読み物が置いてないためか、あまり人気がないみたいで、この場所で人がいる所を見た事はなかった。静かに勉強出来るから気に入っていたけど、彼──ルキアーノ・トロッツイ公爵家当主が側にいても嫌な気持ちにならなかった。むしろ気さくで優しい人という印象でしかなくて、麗しい見た目に反して大変優秀で気難しい人と令嬢とのお茶会で聞いていたが、私の話にも真剣に耳を傾けてくださる、噂とは真逆の人だった。
彼と会える時は私の心臓が早鐘を打つみたいにうるさいし、彼に微笑まれると呼吸を忘れて息を止めてしまう。最初は何か心臓の病気になったかと思ったが…これが好きという気持ちだと、割と早い段階で知った。姉の部屋にある大衆恋愛小説を見つけて、姉に勧められるまま読むと、本の中の登場人物のヒロインが私と同じ症状を呈していたからだ。
それと同時に、彼は私のような醜聞の絶えない人とは合わないと瞬時に悟った。彼は将来を約束された尊い人で、正確には何の契約も交わしていないが、私は王子の側妃として過ごしているのだ。
例え王子と会っていなくても、その事実だけは変える事は出来ない。かと言って、父が側妃の話をなかった事にしたら、すぐに他の貴族から縁談が持ち込まれるだろう。彼以外の人と結婚するなんて、まっぴらごめんだった。
──この恋は誰にも言わないわ
だって、彼は私との会話で楽しそうにしてくれている。他の貴族とは違い愛称で呼び合うだけでも、それだけで充分だと、その時は本気でそう思っていたからだ。
だが…初めてキスをした時から、全てが変わってしまった。まるで私を愛しているかのように、彼は残酷に私に愛を囁く。より一層距離が近くなると彼の香水が私の空気のようになり、匂いを嗅がないと悲しくて上手く息が出来なくなると勘違いしてしまうほどになる。声のトーンも、しっとりと濡れた唇と厚い舌が私の口内を弄り、スッとしたスタイルの良い身体だと思っていたが、抱きしめられると分厚い胸板と力強い腕を知ってしまったら、もっともっとと欲しくなってしまう。彼から貰う彼の色が入った小物を身につけると、いつも側に居てくれていると幸せな気持ちになる。貰った当初は図書館にいる間だけ付けていたけど、父も母もきっと気づいているのに何も言って来ないのをいい事に、日常的に身につけるようになった。
キスをされ、抱きしめられ、他愛のない話の間にまた啄むようなキスをする。次の約束をする訳でもない僅かな逢瀬を、誰にも邪魔をされたくないと思い始めた。以前なら気分が乗らない時は図書館に行かなかったのに、彼がくるかわからなくても雨の日も意地でも行くようになった。
なるべく彼の負担にならないように、私の心の奥底にある気持ちに蓋をしていたのに、私の気持ちが重いのに気がついたのか、ついに彼が来なくなった。それは私の心に影を落とし、何の気力も湧かない日々が続いた。それでも図書館に行っては、彼がくるかも知れないと僅かな希望を抱いてしばらく過ごし、絶望的な気持ちで帰る。
彼と会わなくなって2週間が過ぎたある日、いつものように国立図書館に行くと、いつもいる受付の司書が新しい情報を教えてくれた。いつも、新しい本の入荷などを教えてくれる顔馴染みの女性だ。
「本日から各コーナーにソファーを設置する事になりました」
「まぁ、そうなの?」
司書が手を向けた先を見ると、確かに先週末きた時には空いていたスペースに2人掛けのソファーが置かれていた。
「はい、トロッツイ公爵ルキアーノ様よりご寄付を頂きました」
「ル…トロッツィ公爵の」
思わずルキ様と言おうとして言い直したが、幸いにも司書は私の変化に気がついていなかった。
「はい、アチェール様のいつものコーナーにもありますので、硬い木の椅子に疲れたら柔らかなソファーでお休みくださいね」
「ありがとう、すごく嬉しいわ」
司書とはにこにこと話すが、心の中では疑問ばかりが頭に浮かぶ。
──ソファーよりも、ルキ様にお会いしたいわ
むしろ、ソファーを見るたびに彼を思い出して、余計に惨めな気持ちになってしまう。
彼にとって私は"ひと時の遊び"だったから、いつもいる図書館で快適に過ごせるように、お詫びの品としてソファーを寄付した、と気がついた時には、ルキ様が図書館に来なくなって23日目となっていた。
やっとうじうじ悩む自分の気持ちに踏ん切りをつけようとしたその矢先、また彼が現れた。
「新しいソファーの座り心地はどうだ?」
久しぶりに聞く低音の声に、窓の外を見ていた私は頭よりも先に身体が動いた。彼に抱きつくと、感極まって涙が瞳に溢れる。感情を露わにするなんて淑女としてあるまじき行為だと恥じつつ、だけど彼の腕から離れる事は出来なかった。
──好きです…ううん、愛してます
嬉しい気持ち、彼への純粋な気持ち、置いていかれた寂しい気持ち、色々な感情が入り混じり、彼に伝えた言葉はシンプルに会いたかったと、それしか口から出なかった。
彼は簡単に私を横向きで抱き上げると、歩き出してソファーへと座った。彼の膝の上に横向きのまま座って、言葉よりも多く口づけをした。
「…それ、気に入ってるの?」
「っ、ぁっ」
「あぁ、すまない」
胸元にある黒い真珠のブローチは、彼からの贈り物だ。頬や首にキスをされ、ふっと笑う彼は、私の胸元にあるブローチをそっと撫でると、彼の右手の指先が私の胸元に当たった。思わず声を上げてしまうと、彼の手がさっと引いた。
「やっ…やめないでください…私…ンッ」
手を引いた彼の右手をとっさに取ると、彼は私の首の後ろへと左手を回して自分の方へ引き寄せると、私の口を塞いで噛み付くような荒々しいキスをした。
「いいのか…?ただの図書館で話す間柄には戻れなくなる」
「えぇ、もう私の心は決まってますわ」
彼の手を自分の胸元に戻すと、彼の手が私の胸に添えられた。最終確認するかのように、もう一度彼から告げられると、私は彼の首の後ろへと回して、自分から彼の口にキスをした。
──それにもうキスをしてしまったわ
キスを求める時点で、もう元の2人には戻れないし、戻りたくなかった。私の心は完全に彼を求めているし、なかった事には出来ない。それに今この時を逃して、彼が図書館に来なくなったら?そうしたら私はまた絶望的な気持ちを味わうのかと思うと、今このチャンスを逃したくなかった。
「…お慕いしております…心から」
本当なら愛していて、貴方がいないと生きていけないと彼に伝えたかったが、中途半端な立場にいる私が彼を縛る権利なんかない。公爵家の次期当主である彼を私のものにしたい──そんな自分勝手でわがままな話があるのだろうか。
──出会った場所が社交界だったならば
幾度となくそう思ったが、私なんかが彼に声を掛けることも、ましてや近づくなんて不可能に近いのだ。彼の麗しい外見なら、他の令嬢が黙っていないし、独身だけど婚約者もいない、誰かの候補じゃない令嬢が、彼には相応しいから。
「…今日だけ…ここだけでもいいから…私を愛してください」
「ここだけなんて…ディーは…ったく」
最大の譲歩を見せたのに、彼は呆れたようにため息を吐くと、私の胸を掴んだ。
「君を手放すなんて、私がするわけないだろう?」
一段声を落とした声色は、怒っているのかどうなのかわからない。
「…嬉しいですわ」
だけど、私のせいで笑う以外の感情を露わにする彼の怒った顔も見たいと、歪んだ心がそう告げた。
うっとりと彼の肩に頭を乗せると、彼は私の胸を揉み始める。ただコルセットをしているから、なかなか揉まれているという実感がわかない。
「即物的だが許してくれ」
彼はそう言って私のドレスの裾の中へと手を入れると、私の足首から順にふくらはぎから太ももを伝って手のひらを這わす。
「嫌か?」
本当なら恥ずかしくて死にそうだったけど、私の反応次第では止めてしまい、もう2度と彼は私に手を出さないだろうと瞬時に理解してしまって、私はふるふると首を横に振る。
「っ…平気ですっ」
本当はこのまま彼と結婚して結ばれたらと思うが、それはありえないと頭で否定する。最初は好きな人と、出来るなら一生を添えたい…が、叶わぬ夢となりそうだ。そもそも、過去に父に王子の第二候補から外して欲しいと言わなかった自分にも非があるのだ。
まさか彼に恋をしてしまって、こんな関係になるとは夢にも思わなかったと今更後悔しても遅い。
この先も結ばれないなら、ひと時の思い出を心にしまって、これからの未来を生きたい。だけど今彼の手を拒否したら、この機会はもう永遠にやってこないと感じた。
「ディー、今日じゃなくても…」
私の考えている事など、彼にはお見通しみたいだったが、私は今日どうしても彼の物になりたくなった。彼の右頬に左手を添えて私の方を向かせると、彼の口元に口づけをした。
「…もう心が離れてしまったと…思うのは嫌なんです…貴方が私の初めての人になって欲しい」
「ディー」
ルキ様は私の頬とこめかみにキスをすると、私の首に唇を押し付けた。まるで私が彼を拒否していないかどうか確認するように私の反応を見る。
「…ふふっ」
彼の胸に手を添えた私は、髪が私の首に当たって擽ったくて笑ってしまう。
張り詰めていた空気が霧散したような気がして、ルキ様は私の身体を抱きしめた。
「…愛してる…ディー」
「…私もですわ、ルキ様」
彼の言葉に返事をすると、彼は私の頬を親指の腹でさらりと撫でた。ゆっくり近づいてくる彼の顔が、薄く口を開けるのを見たのを最後に、私は瞼を閉じた。
「はっ…ぁ…っ」
ソファーに寝かされ、ドレスをたくし上げられた私は、淑女にあるまじき行為をしている。足を広げられ、履いていた下着などすでに太ももから足首へと落ちていたのにも構わず、ルキ様は床に膝をつけて私の下半身に顔を埋めていた。
さざ波のように引いては来る何かが怖くて、たくし上げられたドレスを掴んでいると、彼は私の右手を取り、手を繋いでくれた。
「ぁっ、っ」
「ああ、ここか、ディーの好きな所は」
一ヶ所彼の舌が蜜口を掠めると全身が強張り、繋いだ手を強く握った。舌を這わされた蜜壺は濡れており、彼は愛おしそうに吸う。最初は漏らしてしまったと涙が出てしまい、何も知らないんだね、嬉しいよと言いながらルキ様が一から説明してくださった。これは粗相でもないし、病気でもない、私の身体の中から生まれた快感で、2人の愛を深めて子孫を残す大事な行為で…と、丁寧に説明され、いずれは王子の妃となるかもしれないから、ちゃんと家庭教師から習っていたのに、それがこんなにも恥ずかしくてむず痒い感覚が快感だなんて知らなかった。文字で教わるのと実践とは全くの別物だと改めて思った。
「ここで、子種を注いだら私の子が生まれるんだよ、そうだね、子が宿るようにたっぷり注ごうか」
彼は私のお腹と下生えの際を少し強めに押しながら、うっとりとした声で独り言のように呟く。
私が返事をする前にまた彼は私の下半身へと顔を埋めると、蜜口からここと言っていた場所のした当たりを目掛けて指を入れた。
「あぁ、私の指をぎゅうぎゅうと締め付けて離さない、私のを入れたらどうなるのだろうか」
彼は指先を出し入れしながら、蜜口から太ももの付け根にまで舌を這わした。
──この指よりも大きなものが入るの?
充分に彼の指は太くて固いと思っているのに、これ以上大きなものが私の中に入らないと思っていたが、ルキ様は私の視線を感じたのか視線を上げた。
「…もうそろそろ、入れようか…私も早くディーの中に入りたいから」
彼は私の蜜壺の中に指を埋めたまま起き上がると、ソファーに片膝をついた。
私の口を塞ぎ熱い口づけを交わすと、彼の指が私の蜜壺の中からいなくなる。
「こっちを見て、ディー」
「んっ、ぁ」
蜜壺から指が無くなり、喪失感を感じて思わず下半身に視線を向けると、ルキ様が私の顎に指を添えて上を向けた。お互いの視線がぶつかると、彼の瞳に私が映る。甘噛みをされながら啄むキスを繰り返していると、指とは違う圧倒的な熱さと太さを持った何かが私の蜜口に当たり、ゆっくりと蜜壺の中へと入っていく。
「あ…ぁあ…っ」
「っ、ぐ…はっ、ディ…ッ」
燃えるような熱さの固いものが私の蜜壺の中を広げ、彼を離すまいと身体が勝手にきゅうきゅうと締め付ける。背中がのけ反ると、彼の腕が私の背中に回り、そのまま腰に下がると繋がった箇所が抜けないように固定した。
彼が私の中を進む度に、彼の身体が屈み重なりそうなくらい近くなる。
「はっ…っ、っん」
ぐんっと彼の腰が勢いよく蜜壺の中を進むと、最奥まで届いた熱い塊が私の中に留まる。
「っぐ、んっ」
やっと一つになれたと、彼は言わんばかりに私の顔中にキスの雨を降らせ、私の中にいる彼が馴染むまで待ってくれる。
「ル…キ様っ」
いつもよりも少し高く舌ったらずになった私の声に、彼は私の身体を抱きしめた。
「ディー」
彼はゆっくりと腰を引くと、ぴりぴりとした電流が身体の中に起こる。全てが無くなってしまうのかと思うと、蜜壺の中へと勢いよく戻る。少しずつ始まった抽送はやがて早くなると、ルキ様の背中に手を回して起こる快感に身を委ねる事しかできない。
「あっ、あ…っ、んぅっ」
「ディー、可愛らしい声を聞いていたいが、少しだけ抑えようか」
彼は快感でわけが分からなくなっている私の口を自分の口で塞ぐと、腰を一段と早くした。布の擦れる音だけが聞こえる気がして、ここがどこかを思い出してしまうと、さっと頬が赤くなって彼の胸に顔を埋めると、彼は、煽らないでよ、可愛くてめちゃくちゃにしちゃいそう、と耳元で囁きながら、私の中にいる固いものをぐんと大きくする。
「~~~っ!!」
「っ、っ、っ」
繋がった箇所から迫り上がる快感が、全身に巡るスピードが早くなり、ついには目を閉じているのに目の前がチカチカと光っている。全身が強張り、何も考えられない無の時となると、低い唸り声と共に蜜壺の中に注がれた…ルキ様のいう子種が注がれると一気に熱くなった。
彼は繋がったまま全力疾走したかのように肩で呼吸をし、私はしばらくの間全身の力を緩める事が出来なかった。
「さぁ、ディー、次の時間だ」
彼は初めての快感に、まだぼぅっとする私の頬にキスをすると、今度は何がどこに入って、私の身体を悦くしているのか実践を交えて教える。私が気持ちいい事を学び、声を抑える事が出来なくなると、彼は上等なネクタイを私の口に入れた。
「例え、誰もいないと分かっていても、君の声を誰にも聞かせたくない」
と、揺さぶられながら彼に言われても、彼の言葉を頭の中で理解する前に新たな快感の波にのまれ、ただ意味のない単語の羅列にしか聞こえなくなる。
ドロドロに愛し合って、もう私の身体は彼と離れられなくてくっついてしまったんじゃないかと思い始めた頃、やっと私たちの身体の繋がりが解けた。
「あっ」
「そんな顔をしないで、また中に戻りたくなる」
彼が抜けた後は酷い喪失感で、蜜口が浅ましくきゅんとなる。幾度も注がれた証の流れが蜜口から止まったため、彼には直ぐにバレてしまったが、彼は私の下半身をハンカチで拭った。
「は…」
成人してから下半身を拭かれた経験などなかった私は、羞恥で死にたくなったが彼は特に気にした様子はなかった。彼はハンカチを畳むと自分のポケットに入れ、私の下着を履かせドレスの裾を直した。
「さぁ、話をしようか…私たちの将来について」
私よりも彼の方が疲れているはずなのに、彼は私を楽々と持ち上げると、私をソファーに座った彼の膝の上へと横向きに座らせた。
「私はもう…あなたの物になりましたわ」
真剣な眼差しに、情事後の色気も出ているようで、私はうっとりと見惚れた。
***************
「従兄、お久しぶりです」
スッとした鼻筋で整った顔をして、自分よりも王族の風格のある従兄は、王族以外が入れない城の奥にある貴重な植物のある温室で、王族である自分を呼んで紅茶を飲んでいた。
足を組む姿はまるで一枚の絵画のように美しく、周りに植えられている世界の希少で心奪われる植物が彼の美しさを際立たせるためにあるアイテムのようだ。
「やぁ、次期国王陛下、公務の方は順調かい?」
王族が現れたらどの貴族も席を立ち、恭しく王族に賛称し挨拶をするのに、この従兄ときたら、王族が自分に挨拶をするのが当たり前だと思っている節がある。
「…突然呼び出してどうなされたのですか、城に居たからよかったものの、居なかったらどうなされていたんですか」
次期国王陛下になれるか分からない不安定な立場だった自分に対して、いつまでも変わらない従兄は、コロコロ態度を変える他の貴族よりかは信じられる存在なのも確かだ。成人したとはいえ、社会経験も少ない自分は、政策に忙しいと暗に伝えるために、分かりやすいため息を吐いてみるが、この従兄は気にもしないだろう。むしろ──
「おや?私も忙しいんだよ、君に構っている暇なんてないんだ、それにね、君が何処にいるかなんて知っているから、こうして私がここにいるんじゃないか」
などと、ちょっとした不満を零しただけで、2倍にも3倍にも返ってくるから厄介なんだ。幼い頃から叩き込まれた王族としてのやり方も、彼の前では意味を成さないと学んだ。
「…ええ、そうでしたね」
従兄に口でも実績でも勝った事がないから、これ以上のやり取りは不毛だと、諦めた僕は従兄の座る席の向かいに腰掛けた。
僕の前に淹れたての紅茶を給仕したメイドが居なくなると、従兄は徐に口を開いた。
「…他でもない、私の伴侶となる女性、つまり君の婚約者の妹なんだがね」
「…アリッサの妹…?ああ、アチェール公爵の娘、ディーナ令嬢ですか」
「そうだとも、ディーナ令嬢に関する事だが…いい加減、アリッサ嬢と結婚してくれないかね」
「…といいますと?」
「君がいつまで経っても、公務公務と言って式の一つも挙げないせいで、私が彼女と結婚出来ないじゃないか」
「…そんな事言われましても…こればかりは父と母…それから」
貴族達への通達も含めた準備期間が必要、と続けようとして、従兄の雰囲気がいつもと違う事に気がついた。
「私の天使がいつまでも他の奴の物だと、噂が広がっているのを黙って見ているほど、私の心は寛大ではないのだよ」
口元は笑っているのに鋭い眼差しをしている従兄が、地を這う低い声で話す言葉の節々から珍しく不機嫌だと悟る。
──従兄がこんな感情を露わにするなんて
いつも優しい笑顔で人々を魅了する従兄は、僕にも誰にも心のうちをそうそうに明かしたことがない…というか見たことがない。
「君の父上には私から伝えた…このひと月で式を挙げるんだ」
「そんな急にっ」
無理な話を持ち出した従兄に抗議をすると、従兄は他の貴族に向けるように微笑みを深くする。
「これは、国王陛下の命だよ…ああ、ウェディングドレスのデザイナーはこちらで用意するよ、国一番の腕で予約の取れない今流行りのデザイナーだから、君の婚約者も喜ぶだろう」
確かに従兄から聞かされたデザイナーの名前は、アリッサがドレスを作りたいのに、予約が取れなかったと言っていた人の名前で、彼女に伝えたらきっと泣いて喜ぶに違いない。
最高の従兄を持って良かった、と僕に言わせたいだろうけど、僕は知っているのだ。
「…そんなにディーナ令嬢と結婚したければ、僕たちの事など気にせずに、すれば良かったじゃないですか」
「彼女はね、とても繊細なんだよ…姉のために身代わりになると自分を追い詰めるほどに、ね」
姉が結婚していないのに、身代わりの予定だった自分が先に結婚出来ないという彼女の望みを叶えようとする…一見ディーナ令嬢の気持ちに寄り添った心優しい従兄となるが──つまりは、さっさと彼女と結婚して身も心も手にしたいだけである。
「そうだな…私にかかれば、デザイナーに頼んで、急ピッチでドレスを仕上げてもらうから、明日にでも結婚式を挙げられるよ」
僕が結婚をすると分かると、途端にご機嫌になった従兄は、また優雅に紅茶を飲み始めた。
「…ですからね」
今のうちに結婚式の日程を決めなければ、従兄が明日にでも式を仕切る勢いだ。どうしようかと、考えていると、従兄は胸ポケットから時計を出して、見たと思ったら突然席を立った。
「そろそろ、私の天使が起きる時間だ…全てが初めての今日くらいは側にいないとね」
と言い残して、温室から出て行ってしまった。
「…なんなんだ一体」
取り残された僕はそう零すが、誰もいない温室に声が消えた。
後日、大々的に発表された王子の結婚式の日程は、歴代の王族達よりも早い期間で準備され行われた。人気のデザイナーの手によって作られたドレスは、貴族令嬢の憧れの的となって、たちまち流行となった。
その後すぐに、ひっそりと行われたトロッツィ公爵の当主の結婚式は、異例の近親者のみが参列する質素な式となった。そして流行りのドレスの身体のラインを強調するデザインとは180度異なる、ゆったりとした大きめなサイズの純白のドレスを身につけたディーナ・グリゼルダ・アチェール公爵令嬢のお腹には、もう2人の愛の証があった。
ヴィラン公国では、苗字が短いほど王族に近しい立場の人であり、または王族の近親者となっている。その中でも、苗字を持たない王族の次にあたるトロッツィ公爵家は、どの貴族よりも高貴で尊い存在とされている。
なぜなら
大昔、国王陛下の弟だった当時のトロッツィは、爵位を賜ると、子孫までもが代々男児を産み続け、王族に一番近い血脈を守り続けているのだから。
応援ありがとうございます!
222
お気に入りに追加
275
この作品の感想を投稿する
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる