4 / 33
その4
しおりを挟む
順調に侍女としての勉強を進めるマリエッテは、水面下で公爵家の中でカップルを見守りたい同志を増やしてきた。
温かく見守る女性使用人や行儀見習いたちの空気が伝わったのか、公爵家の仕える男性たちもどこか微笑ましくエフェリーンとチェールトを見ているようである。
また、婚約者たちのふわふわした幸せな空気にあてられたのか、結婚相手を探す人たちが増えた。行儀見習いで来ている貴族子女たちも、これまでなら「まだ適齢期だから」とおざなりにしていた社交に力を入れるようになったのだ。
どうやら、エフェリーンたちのあり方は間接的に周りの人たちの結婚願望を増幅させることになったようだ。
ちなみに、マリエッテのように推しカップルを見守るために自分の結婚の優先順位を最低限にまで下げてしまった人は他にはいなかった。
王城でのお茶会のときは、マリエッテがすることはほとんどない。
応接室やティールームで3人が語り合っている間は護衛も十分なので、その間はマリエッテの休憩にあてられることになった。
休憩といっても、王族のプライベート空間で働く使用人にあてがわれている休憩室でお茶をしたり、王城内にある図書館へ本を借りに行ったりする程度だが、気晴らしにはなる。
マリエッテ個人としては、いつでも2人を見守れる方が良いので休憩はいらないと伝えたのだが、エフェリーンが首を横に振った。
「マリエッテは、ただでさえ侍女として必要な知識を学んでいるところなのに、護衛としてもずっと働いているのよ?誰にだって休憩は必要なの。そう言ったのは貴女よ、マリエッテ」
以前、チェールトのためにと少しの休憩も取らずに予定を詰め込むエフェリーンに、休憩する方が効率が上がると説明したことがある。
見事に自分に返ってきたので、マリエッテは肯定する以外の答えを返すことはできなかった。
数回目の登城のとき、休憩時間に図書館へ行くことにした。
海運業に関わる勉強をする中で、これまで知らなかった海の向こうの国の言葉や文化を知りたいと思ったのだ。もちろん公爵家にも辞書や例文集などはあるのだが、もう少し強化したい。
そのためには、外国語に触れる機会を増やすしかない。
ありがたいことに、王城の図書館には別大陸の国の言語で書かれた本も複数並べられていた。
司書に聞いたところ、閉架図書にもいくつかあるという。こういう機会でもないと王城の図書館には来られないので、ありがたく利用させてもらうことにしていた。
経済棟の方を通って図書館へ向かう途中で、以前見かけたこげ茶色の髪の男性がいた。歩く姿を見ても、やはりただ者ではないようだ。なんなら、そのへんの騎士よりも使えるかもしれない。
背は高いがひょろっとした印象ではなく、しなやかな筋肉をつけていることがわかる。かといって威圧感があるほどではないので、スピード重視の剣術を身に付けているのかもしれない。
ふと眼鏡越しに緑の目と視線を交わしたときに、その考えはほぼ確信となった。
また目礼で通り過ぎようとしたのだが、男性がマリエッテの一歩前で立ち止まった。
何かあっただろうか、とマリエッテも男性に合わせて立ち止まった。
「えっと、マリエッテ嬢、ですよね?ディレン伯爵家の」
男性は、マリエッテを見下ろしながら軽く首をかしげた。
名前を知られていることに驚いたが、マリエッテには背の高い男性の知り合いがいたという記憶はない。
「はい、そうです。あの、申し訳ございません、私は貴方のことを覚えていないのですが」
眼鏡の向こうの緑色の瞳はどこか覚えがあるのだが、はっきりと思い出すことができないのだ。
「かなり昔のことですからね。僕は、ラウレンス。ラウレンス・ファン・リュールです。10年以上前かな、訓練を兼ねてディレン伯爵領でお世話になったことがあります」
「あ、……え?あの、ラウ?あのときの?」
「うん、思い出してくれた?」
「懐かしい!元気にしてた?って今、事務官をしているのね?あのとき私、適当なことを言ったと思うんだけど、本当に叶えちゃったのね。すごいわ!」
思い出した途端に口調の崩れたマリエッテに、ラウレンスは柔らかな笑みを向けた。
◆◇◆◇◆◇
15年ほど前のことだ。
マリエッテの領地に、父の知り合いの息子だという男の子が、伯爵家の騎士団で訓練するために来た。王都の剣術は合わないらしいので伯爵家の実践的な訓練をと依頼され、魔獣を相手にする騎士団に数か月滞在していたと思う。
しかし、ラウレンスは努力して形になってはいたものの、そもそもがあまり剣術に向いていなかった。長剣を振り回すのがあまり上手くなく、長い手足をもてあましているようだった。
当時10歳に満たないマリエッテは、周りにいないタイプのラウレンスが珍しく、時間があれば近づいてまとわりついていたように思う。その中で、ラウレンスがポロリと零したのだ。
「僕、あんまり剣に向いてないんだよね。勉強の方が好きだし。でもうちの家は剣術が必須だから、とにかく頑張ったんだ。だけど全然上達しなくて……父も兄たちも匙を投げた。それでここへ来たんだ」
「ふぅん。うちの剣術なら良さそうだってことね。じゃあ、慣れた?」
「ううん。あ、でもここでは色々なことを試せるから、それはよかったよ。短剣の使い方も、弓の引き方も教えてもらった。ここの騎士たちはいろんなことを知っていて、道が一つじゃないってことは気づけたんだ」
「短剣なら、いつも持ち歩けるものね。それに、ラウは勉強が好きなの?私は嫌いじゃないけどちょっと苦手。勉強ができればもっと別の方向からできることもあるって言われたけど、よくわからなかったわ。たとえば、国を支えるのは騎士だけじゃなくって王城に勤める事務官や財務官とか、侍女だってメイドだって、色々あるんですって」
口をとがらせて言うマリエッテに、ラウレンスは優しく微笑んだ。
「勉強は楽しいよ。知らないことを知っていくってすごくワクワクするから」
「あ!頭がいいなら、事務官なんかもいいんじゃないかしら?騎士の仕事だって、事務みたいな仕事がゼロじゃないんでしょう?だったら、騎士団の中で事務をする人だっているわよね。それに、短剣とか弓を使えるなら、戦う事務官にもなれるわよね。きっとかっこいいわ」
「事務官か……。考えたこともなかったよ。うちは騎士の家系だから、とにかく騎士になるべきって考えてた」
「そうなの?とってもいいと思うのよ。私も少しは勉強してみようかしら。あと、戦える事務官はすごくラウに合うと思うわ!そうは見えないのに実は護衛とか、ちょっと素敵じゃない?かっこいいわよ。勉強が好きなラウなら事務官の仕事もきちんとできそうね!私もそういうのを目指そうかしら」
マリエッテは、ただ思いつくまま、無責任にラウレンスに期待しただけであった。
勉強ができるなら、自分にはできない方法で誰かを支える仕事ができるだろう、と。
そして滞在期間が終わり、数か月滞在した彼のことは遠い記憶となっていた。
しかし、ラウレンスにはその期待こそが救いであった。
温かく見守る女性使用人や行儀見習いたちの空気が伝わったのか、公爵家の仕える男性たちもどこか微笑ましくエフェリーンとチェールトを見ているようである。
また、婚約者たちのふわふわした幸せな空気にあてられたのか、結婚相手を探す人たちが増えた。行儀見習いで来ている貴族子女たちも、これまでなら「まだ適齢期だから」とおざなりにしていた社交に力を入れるようになったのだ。
どうやら、エフェリーンたちのあり方は間接的に周りの人たちの結婚願望を増幅させることになったようだ。
ちなみに、マリエッテのように推しカップルを見守るために自分の結婚の優先順位を最低限にまで下げてしまった人は他にはいなかった。
王城でのお茶会のときは、マリエッテがすることはほとんどない。
応接室やティールームで3人が語り合っている間は護衛も十分なので、その間はマリエッテの休憩にあてられることになった。
休憩といっても、王族のプライベート空間で働く使用人にあてがわれている休憩室でお茶をしたり、王城内にある図書館へ本を借りに行ったりする程度だが、気晴らしにはなる。
マリエッテ個人としては、いつでも2人を見守れる方が良いので休憩はいらないと伝えたのだが、エフェリーンが首を横に振った。
「マリエッテは、ただでさえ侍女として必要な知識を学んでいるところなのに、護衛としてもずっと働いているのよ?誰にだって休憩は必要なの。そう言ったのは貴女よ、マリエッテ」
以前、チェールトのためにと少しの休憩も取らずに予定を詰め込むエフェリーンに、休憩する方が効率が上がると説明したことがある。
見事に自分に返ってきたので、マリエッテは肯定する以外の答えを返すことはできなかった。
数回目の登城のとき、休憩時間に図書館へ行くことにした。
海運業に関わる勉強をする中で、これまで知らなかった海の向こうの国の言葉や文化を知りたいと思ったのだ。もちろん公爵家にも辞書や例文集などはあるのだが、もう少し強化したい。
そのためには、外国語に触れる機会を増やすしかない。
ありがたいことに、王城の図書館には別大陸の国の言語で書かれた本も複数並べられていた。
司書に聞いたところ、閉架図書にもいくつかあるという。こういう機会でもないと王城の図書館には来られないので、ありがたく利用させてもらうことにしていた。
経済棟の方を通って図書館へ向かう途中で、以前見かけたこげ茶色の髪の男性がいた。歩く姿を見ても、やはりただ者ではないようだ。なんなら、そのへんの騎士よりも使えるかもしれない。
背は高いがひょろっとした印象ではなく、しなやかな筋肉をつけていることがわかる。かといって威圧感があるほどではないので、スピード重視の剣術を身に付けているのかもしれない。
ふと眼鏡越しに緑の目と視線を交わしたときに、その考えはほぼ確信となった。
また目礼で通り過ぎようとしたのだが、男性がマリエッテの一歩前で立ち止まった。
何かあっただろうか、とマリエッテも男性に合わせて立ち止まった。
「えっと、マリエッテ嬢、ですよね?ディレン伯爵家の」
男性は、マリエッテを見下ろしながら軽く首をかしげた。
名前を知られていることに驚いたが、マリエッテには背の高い男性の知り合いがいたという記憶はない。
「はい、そうです。あの、申し訳ございません、私は貴方のことを覚えていないのですが」
眼鏡の向こうの緑色の瞳はどこか覚えがあるのだが、はっきりと思い出すことができないのだ。
「かなり昔のことですからね。僕は、ラウレンス。ラウレンス・ファン・リュールです。10年以上前かな、訓練を兼ねてディレン伯爵領でお世話になったことがあります」
「あ、……え?あの、ラウ?あのときの?」
「うん、思い出してくれた?」
「懐かしい!元気にしてた?って今、事務官をしているのね?あのとき私、適当なことを言ったと思うんだけど、本当に叶えちゃったのね。すごいわ!」
思い出した途端に口調の崩れたマリエッテに、ラウレンスは柔らかな笑みを向けた。
◆◇◆◇◆◇
15年ほど前のことだ。
マリエッテの領地に、父の知り合いの息子だという男の子が、伯爵家の騎士団で訓練するために来た。王都の剣術は合わないらしいので伯爵家の実践的な訓練をと依頼され、魔獣を相手にする騎士団に数か月滞在していたと思う。
しかし、ラウレンスは努力して形になってはいたものの、そもそもがあまり剣術に向いていなかった。長剣を振り回すのがあまり上手くなく、長い手足をもてあましているようだった。
当時10歳に満たないマリエッテは、周りにいないタイプのラウレンスが珍しく、時間があれば近づいてまとわりついていたように思う。その中で、ラウレンスがポロリと零したのだ。
「僕、あんまり剣に向いてないんだよね。勉強の方が好きだし。でもうちの家は剣術が必須だから、とにかく頑張ったんだ。だけど全然上達しなくて……父も兄たちも匙を投げた。それでここへ来たんだ」
「ふぅん。うちの剣術なら良さそうだってことね。じゃあ、慣れた?」
「ううん。あ、でもここでは色々なことを試せるから、それはよかったよ。短剣の使い方も、弓の引き方も教えてもらった。ここの騎士たちはいろんなことを知っていて、道が一つじゃないってことは気づけたんだ」
「短剣なら、いつも持ち歩けるものね。それに、ラウは勉強が好きなの?私は嫌いじゃないけどちょっと苦手。勉強ができればもっと別の方向からできることもあるって言われたけど、よくわからなかったわ。たとえば、国を支えるのは騎士だけじゃなくって王城に勤める事務官や財務官とか、侍女だってメイドだって、色々あるんですって」
口をとがらせて言うマリエッテに、ラウレンスは優しく微笑んだ。
「勉強は楽しいよ。知らないことを知っていくってすごくワクワクするから」
「あ!頭がいいなら、事務官なんかもいいんじゃないかしら?騎士の仕事だって、事務みたいな仕事がゼロじゃないんでしょう?だったら、騎士団の中で事務をする人だっているわよね。それに、短剣とか弓を使えるなら、戦う事務官にもなれるわよね。きっとかっこいいわ」
「事務官か……。考えたこともなかったよ。うちは騎士の家系だから、とにかく騎士になるべきって考えてた」
「そうなの?とってもいいと思うのよ。私も少しは勉強してみようかしら。あと、戦える事務官はすごくラウに合うと思うわ!そうは見えないのに実は護衛とか、ちょっと素敵じゃない?かっこいいわよ。勉強が好きなラウなら事務官の仕事もきちんとできそうね!私もそういうのを目指そうかしら」
マリエッテは、ただ思いつくまま、無責任にラウレンスに期待しただけであった。
勉強ができるなら、自分にはできない方法で誰かを支える仕事ができるだろう、と。
そして滞在期間が終わり、数か月滞在した彼のことは遠い記憶となっていた。
しかし、ラウレンスにはその期待こそが救いであった。
1
あなたにおすすめの小説
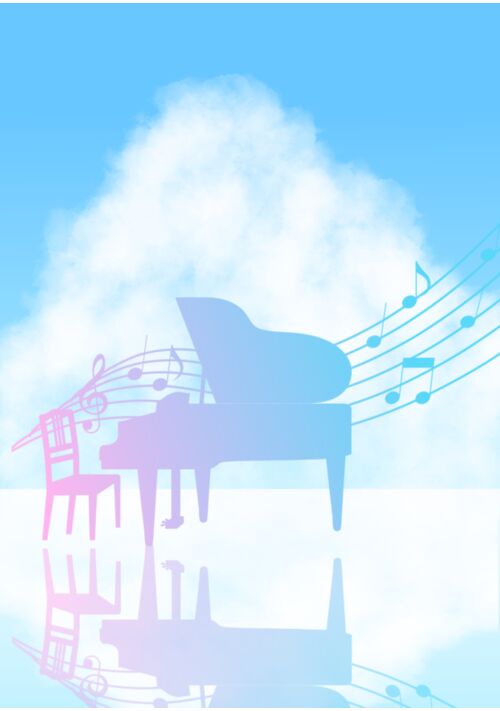
ピアニストは御曹司の盲愛から逃れられない
花里 美佐
恋愛
☆『君がたとえあいつの秘書でも離さない』スピンオフです☆
堂本コーポレーション御曹司の堂本黎は、英国でデビュー直後のピアニスト栗原百合と偶然出会った。
惹かれていくふたりだったが、百合は黎に隠していることがあった。
「俺と百合はもう友達になんて戻れない」

もつれた心、ほどいてあげる~カリスマ美容師御曹司の甘美な溺愛レッスン~
泉南佳那
恋愛
イケメンカリスマ美容師と内気で地味な書店員との、甘々溺愛ストーリーです!
どうぞお楽しみいただけますように。
〈あらすじ〉
加藤優紀は、現在、25歳の書店員。
東京の中心部ながら、昭和味たっぷりの裏町に位置する「高木書店」という名の本屋を、祖母とふたりで切り盛りしている。
彼女が高木書店で働きはじめたのは、3年ほど前から。
短大卒業後、不動産会社で営業事務をしていたが、同期の、親会社の重役令嬢からいじめに近い嫌がらせを受け、逃げるように会社を辞めた過去があった。
そのことは優紀の心に小さいながらも深い傷をつけた。
人付き合いを恐れるようになった優紀は、それ以来、つぶれかけの本屋で人の目につかない質素な生活に安んじていた。
一方、高木書店の目と鼻の先に、優紀の兄の幼なじみで、大企業の社長令息にしてカリスマ美容師の香坂玲伊が〈リインカネーション〉という総合ビューティーサロンを経営していた。
玲伊は優紀より4歳年上の29歳。
優紀も、兄とともに玲伊と一緒に遊んだ幼なじみであった。
店が近いこともあり、玲伊はしょっちゅう、優紀の本屋に顔を出していた。
子供のころから、かっこよくて優しかった玲伊は、優紀の初恋の人。
その気持ちは今もまったく変わっていなかったが、しがない書店員の自分が、カリスマ美容師にして御曹司の彼に釣り合うはずがないと、その恋心に蓋をしていた。
そんなある日、優紀は玲伊に「自分の店に来て」言われる。
優紀が〈リインカネーション〉を訪れると、人気のファッション誌『KALEN』の編集者が待っていた。
そして「シンデレラ・プロジェクト」のモデルをしてほしいと依頼される。
「シンデレラ・プロジェクト」とは、玲伊の店の1周年記念の企画で、〈リインカネーション〉のすべての施設を使い、2~3カ月でモデルの女性を美しく変身させ、それを雑誌の連載記事として掲載するというもの。
優紀は固辞したが、玲伊の熱心な誘いに負け、最終的に引き受けることとなる。
はじめての経験に戸惑いながらも、超一流の施術に心が満たされていく優紀。
そして、玲伊への恋心はいっそう募ってゆく。
玲伊はとても優しいが、それは親友の妹だから。
そんな切ない気持ちを抱えていた。
プロジェクトがはじまり、ひと月が過ぎた。
書店の仕事と〈リインカネーション〉の施術という二重生活に慣れてきた矢先、大問題が発生する。
突然、編集部に上層部から横やりが入り、優紀は「シンデレラ・プロジェクト」のモデルを下ろされることになった。
残念に思いながらも、やはり夢でしかなかったのだとあきらめる優紀だったが、そんなとき、玲伊から呼び出しを受けて……

社長に拾われた貧困女子、契約なのに溺愛されてます―現代シンデレラの逆転劇―
砂原紗藍
恋愛
――これは、CEOに愛された貧困女子、現代版シンデレラのラブストーリー。
両親を亡くし、継母と義姉の冷遇から逃れて家を出た深月カヤは、メイドカフェとお弁当屋のダブルワークで必死に生きる二十一歳。
日々を支えるのは、愛するペットのシマリス・シンちゃんだけだった。
ある深夜、酔客に絡まれたカヤを救ったのは、名前も知らないのに不思議と安心できる男性。
数日後、偶然バイト先のお弁当屋で再会したその男性は、若くして大企業を率いる社長・桐島柊也だった。
生活も心もぎりぎりまで追い詰められたカヤに、柊也からの突然の提案は――
「期間限定で、俺の恋人にならないか」
逃げ場を求めるカヤと、何かを抱える柊也。思惑の違う二人は、契約という形で同じ屋根の下で暮らし始める。
過保護な優しさ、困ったときに現れる温もりに、カヤの胸には小さな灯がともりはじめる。
だが、契約の先にある“本当の理由”はまだ霧の中。
落とした小さなガラスのヘアピンが導くのは——灰かぶり姫だった彼女の、新しい運命。

冷酷総長は、彼女を手中に収めて溺愛の檻から逃さない
彩空百々花
恋愛
誰もが恐れ、羨み、その瞳に映ることだけを渇望するほどに高貴で気高い、今世紀最強の見目麗しき完璧な神様。
酔いしれるほどに麗しく美しい女たちの愛に溺れ続けていた神様は、ある日突然。
「今日からこの女がおれの最愛のひと、ね」
そんなことを、言い出した。

病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜
来栖れいな
恋愛
――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。
望んでいたわけじゃない。
けれど、逃げられなかった。
生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。
親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。
無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。
それでも――彼だけは違った。
優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。
形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。
これは束縛? それとも、本当の愛?
穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

苦手な冷徹専務が義兄になったかと思ったら極あま顔で迫ってくるんですが、なんででしょう?~偽家族恋愛~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「こちら、再婚相手の息子の仁さん」
母に紹介され、なにかの間違いだと思った。
だってそこにいたのは、私が敵視している専務だったから。
それだけでもかなりな不安案件なのに。
私の住んでいるマンションに下着泥が出た話題から、さらに。
「そうだ、仁のマンションに引っ越せばいい」
なーんて義父になる人が言い出して。
結局、反対できないまま専務と同居する羽目に。
前途多難な同居生活。
相変わらず専務はなに考えているかわからない。
……かと思えば。
「兄妹ならするだろ、これくらい」
当たり前のように落とされる、額へのキス。
いったい、どうなってんのー!?
三ツ森涼夏
24歳
大手菓子メーカー『おろち製菓』営業戦略部勤務
背が低く、振り返ったら忘れられるくらい、特徴のない顔がコンプレックス。
小1の時に両親が離婚して以来、母親を支えてきた頑張り屋さん。
たまにその頑張りが空回りすることも?
恋愛、苦手というより、嫌い。
淋しい、をちゃんと言えずにきた人。
×
八雲仁
30歳
大手菓子メーカー『おろち製菓』専務
背が高く、眼鏡のイケメン。
ただし、いつも無表情。
集中すると周りが見えなくなる。
そのことで周囲には誤解を与えがちだが、弁明する気はない。
小さい頃に母親が他界し、それ以来、ひとりで淋しさを抱えてきた人。
ふたりはちゃんと義兄妹になれるのか、それとも……!?
*****
千里専務のその後→『絶対零度の、ハーフ御曹司の愛ブルーの瞳をゲーヲタの私に溶かせとか言っています?……』
*****
表紙画像 湯弐様 pixiv ID3989101

月城副社長うっかり結婚する 〜仮面夫婦は背中で泣く〜
白亜凛
恋愛
佐藤弥衣 25歳
yayoi
×
月城尊 29歳
takeru
母が亡くなり、失意の中現れた謎の御曹司
彼は、母が持っていた指輪を探しているという。
指輪を巡る秘密を探し、
私、弥衣は、愛のない結婚をしようと思います。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















