15 / 23
第十五話
しおりを挟む
ここまで素直になんでも言うことはなかったと反省し、すぐに背を向ける。
彼の言うとおり、待っていなくてもいいのに、待っていたいなんて言って、バカみたいだ。
「では、少し時間をください」
そう言って出て行ってしまうと、ガウェインは険しい顔でティールームを後にした。
急に寂しくなったイーニッドは、さっきまで食べていなかったクッキーを、なんとなく摘まんだ。そこはさっきまで、ガウェインが申し訳なさそうに摘まんでいたクッキーが並んでいたからだ。
(なんとなく……美味しそうに見えただけよ)
***
「で? ゴシップ記事がなんです?」
書斎に執事長とふたりきりになると、ガウェインは腹を立てて睨みつけた。
びくんと身体を震わせた年上の彼に、はっとしていきり立つ肩を落として笑みを見せる。
「すまない。楽しいティータイムを、そんな記事で邪魔するなど無礼でしょう?」
「申し訳ございません」
「悪いのは、その新聞社だ。見せてください」
最近流行りだした新聞社で、ゴシップ専門の記事が多かった。
人々が喜びそうな下品なネタを集めては、記事にして見出しに大きく書くのだ。
最近では、宮廷貴族の不倫がスキャンダルになったり、真面目で有名な侯爵が女遊びで私生児が沢山いたり、嘘か本当かもわからないものだった。
とはいえ、ガウェインはそのふたつのことを知らないわけではなく、一部の人間には有名な話ではあったのだ。ただ、公けにして楽しむことの意味が分からず、その新聞社はいつか潰してやろうと思っていた。
イライラしながら身だしを見れば、
『没落令嬢マッケンジー家のイーニッド嬢とガウェイン候の結婚の真意は!』
などと大きな見出しが躍っている。
その内容を読むと、マッケンジー家の復讐の一幕が上がったとか、ガウェインが愛人にするだとか、ろくな内容がない。
しかし、どれも本当のように書かれていて、何も知らなければ信じるだろう。
頭をかきむしりたい思いになるが、ここで冷静にならなければ父アランを追い落とすことなど出来はしない。
しかし――。
「嗅ぎまわっているのでしょうか?」
「大々的に結婚式を挙げましたし、お二人の結婚は皆さま腹の中では何を考えているか分からないと思います。このような記事は、そんな彼らの心理を満たすだけで、嘘でも本当でもどちらでも構いません」
執事の言うことはもっともで、ガウェインは余計に頭を抱えたくなる。
嘘だろうが本当だろうが、面白そうなことを書ければいいのだ。
イーニッドは元宮廷貴族であるし、そんな彼女がガウェインと結婚したらゴシップ記事としてはもってこいだろう。ただ、今のイーニッドにこんな記事を見せたくはない。
「分かっていますが。ここに、イーニッドの実家の領地のことが書いてあるし、彼女の得意なことは菓子作りだと書いてある。それは一部の者しか知らないことではありませんか?」
ガウェインは不信に思いながら執事長を見据えた。
彼にイーニッドの最近のことを調べさせたから、身内の者しか知らない内容も載っているのは、メイドか執事が口を滑らせていると考えるのが自然だ。
訝しげに彼を見つめるが、首を振られた。
「領地の人間に金を握らせれば、すぐに話すことでしょう。私はメイドや執事ではなく彼らにイーニッド様のことを聞きましたから。マッケンジー家が献身的に村や街に頑張っているとはいえ、元々は叔父の治めていた土地ですから、よそ者だと思っている者もいるかもしれません」
「なんてことだ。このまま黙っているわけにもいかない。イーニッドの家族を王都に呼び戻すのに」
ガウェインは苛々してきて、腕を組んだ。
今こうしてイーニッドと甘い時間を過ごせるのは嬉しいのだが、それは父アランが宮廷貴族として、一線に今だにいるということだ。
息子にその座を渡すことなく、派閥の長となり、王に好き勝手な進言をしている。
先日に言ったことは、庶民の学校など無駄でしかなく、取り壊すべき。
同様に、孤児院も街の景観や治安を悪くするという理由でなくすべきだと進言したそうだ。しかし、王は代々マッケンジー家のような発展的な意見を好み、首を縦に振ることはなく、アランの怒りの矛先は、追いやってもなお、マッケンジー家に向くばかりだ。
このゴシップ記事だって、誰の差し金かを突き止めたら、案外アランだったということだって考えられる。
息子の幸せなどどうでもいいのかと、新聞をぐしゃぐしゃにして捨てると、執事長が眉をぴくんとさせた。
普段怒らないガウェインが怒りを露わにしたからだろう。
「すぐに、父を宮廷から追いやり、マッケンジー家を王都に呼び戻します。その算段をつけたい。父の周辺に噂話がないか探してください。最近苛立っているでしょうから、女に手を付けているかもしれません」
「かしこまりました」
「私は自分に偽りがないことを、イーニッドに伝えます。もう時間がないようです」
もっとのんびりとふたりのゆったりとした時間が欲しかった。
彼女の気持ちを解きほぐし、深い関係になれるような時間が。
執事長が去るのを見送ると、ガウェインは慌ててティールームに急いだ。
彼女のことだから、待ってくれているような気がするのだ。
階下に降りて廊下を小走りに走ると、金色に光るノブを手にして回す。
「イーニッド。待たせて申し訳ありません!」
ティールームにいるだろうかと不安がある。
さっきまで楽しくしていたのだから、怒っても当然だ。
「ガウェイン。もういいの?」
ソファに腰かけた彼女がにこりと微笑み、自分の瞳を心配そうに覗き込でいた。
ブルーの瞳が、どこか寂し気でもあって、すぐに抱きしめたくなる。
「ええ、もう平気です」
衝動を抑えつつ、平然としてイーニッドの隣に腰かける。
上目で「本当に?」と見つめられて、どくんと胸が跳ねた。以前より甘えたように見つめられて、このまま抱きしめたくなる。理性を搔き集めて笑みを作った。
あの日、宮廷で会ったときよりも、確実に身近な存在になれていると実感する。彼女の優しさに触れて、すぐに好きになってしまったこと。家の対立なんてどうでもよくなったことを思い出す。
「大丈夫ですよ。それよりも、美味しいお菓子は堪能できましたか?」
「ひとりじゃ……多いわ」
寂し気に俯く彼女に、今にもキスをしたくなる。
しかし、それではいけないと必死にほほ笑みで誤魔化した。
自分は冷静で、笑顔の絶えない、優しい男なのだ。
父とは違う。
「イーニッド、食べましょうか」
「ええ! 実はね、ソルベやアイスだけは食べていたの。だって溶けてしまうでしょう?」
くすっと微笑む彼女を見て、ガウェインはたまらなくなってイーニッドを抱きしめていた。
胸の中で固まって、ガウェインの行動を理解出来ていないのが分かる。
自分だって同じだ。
冷静で、優しい男がこんなことをしてはいけないはずだ。
胸の中でイーニッドがもぞもぞと動いて、わずかに抵抗しているのが分かる。
それをぎゅっと強引に抱きしめた。
「何かあったの?」
顔が上がり、心配そうに見つめられる。
「イーニッド。すぐに領地から家族を呼びましょう。親戚はお住まいですよね、事情は説明しますから」
「でも……マッケンジー家は追放されたのよ。反逆罪に問われるわ。約束は嬉しいけれど、実際には無理でしょう?」
胸の中で、イーニッドの声が小さくなっていく。
か細くなる声を聞いて、ガウェインはたまらなく愛おしく思えてきて、尚更ぎゅっと抱きしめていた。
「俺は、父から守ると約束しました。手段は選びません」
「でも……それは……ソレク家への裏切りよ……? 分かるでしょう?」
ガウェインは何も言えなかった。
家族を裏切る男を、イーニッドは嫌うだろうかと不安になってしまう。
彼女は家庭を大事にしていたし、幼い弟と妹を可愛がっているのも知っている。
彼の言うとおり、待っていなくてもいいのに、待っていたいなんて言って、バカみたいだ。
「では、少し時間をください」
そう言って出て行ってしまうと、ガウェインは険しい顔でティールームを後にした。
急に寂しくなったイーニッドは、さっきまで食べていなかったクッキーを、なんとなく摘まんだ。そこはさっきまで、ガウェインが申し訳なさそうに摘まんでいたクッキーが並んでいたからだ。
(なんとなく……美味しそうに見えただけよ)
***
「で? ゴシップ記事がなんです?」
書斎に執事長とふたりきりになると、ガウェインは腹を立てて睨みつけた。
びくんと身体を震わせた年上の彼に、はっとしていきり立つ肩を落として笑みを見せる。
「すまない。楽しいティータイムを、そんな記事で邪魔するなど無礼でしょう?」
「申し訳ございません」
「悪いのは、その新聞社だ。見せてください」
最近流行りだした新聞社で、ゴシップ専門の記事が多かった。
人々が喜びそうな下品なネタを集めては、記事にして見出しに大きく書くのだ。
最近では、宮廷貴族の不倫がスキャンダルになったり、真面目で有名な侯爵が女遊びで私生児が沢山いたり、嘘か本当かもわからないものだった。
とはいえ、ガウェインはそのふたつのことを知らないわけではなく、一部の人間には有名な話ではあったのだ。ただ、公けにして楽しむことの意味が分からず、その新聞社はいつか潰してやろうと思っていた。
イライラしながら身だしを見れば、
『没落令嬢マッケンジー家のイーニッド嬢とガウェイン候の結婚の真意は!』
などと大きな見出しが躍っている。
その内容を読むと、マッケンジー家の復讐の一幕が上がったとか、ガウェインが愛人にするだとか、ろくな内容がない。
しかし、どれも本当のように書かれていて、何も知らなければ信じるだろう。
頭をかきむしりたい思いになるが、ここで冷静にならなければ父アランを追い落とすことなど出来はしない。
しかし――。
「嗅ぎまわっているのでしょうか?」
「大々的に結婚式を挙げましたし、お二人の結婚は皆さま腹の中では何を考えているか分からないと思います。このような記事は、そんな彼らの心理を満たすだけで、嘘でも本当でもどちらでも構いません」
執事の言うことはもっともで、ガウェインは余計に頭を抱えたくなる。
嘘だろうが本当だろうが、面白そうなことを書ければいいのだ。
イーニッドは元宮廷貴族であるし、そんな彼女がガウェインと結婚したらゴシップ記事としてはもってこいだろう。ただ、今のイーニッドにこんな記事を見せたくはない。
「分かっていますが。ここに、イーニッドの実家の領地のことが書いてあるし、彼女の得意なことは菓子作りだと書いてある。それは一部の者しか知らないことではありませんか?」
ガウェインは不信に思いながら執事長を見据えた。
彼にイーニッドの最近のことを調べさせたから、身内の者しか知らない内容も載っているのは、メイドか執事が口を滑らせていると考えるのが自然だ。
訝しげに彼を見つめるが、首を振られた。
「領地の人間に金を握らせれば、すぐに話すことでしょう。私はメイドや執事ではなく彼らにイーニッド様のことを聞きましたから。マッケンジー家が献身的に村や街に頑張っているとはいえ、元々は叔父の治めていた土地ですから、よそ者だと思っている者もいるかもしれません」
「なんてことだ。このまま黙っているわけにもいかない。イーニッドの家族を王都に呼び戻すのに」
ガウェインは苛々してきて、腕を組んだ。
今こうしてイーニッドと甘い時間を過ごせるのは嬉しいのだが、それは父アランが宮廷貴族として、一線に今だにいるということだ。
息子にその座を渡すことなく、派閥の長となり、王に好き勝手な進言をしている。
先日に言ったことは、庶民の学校など無駄でしかなく、取り壊すべき。
同様に、孤児院も街の景観や治安を悪くするという理由でなくすべきだと進言したそうだ。しかし、王は代々マッケンジー家のような発展的な意見を好み、首を縦に振ることはなく、アランの怒りの矛先は、追いやってもなお、マッケンジー家に向くばかりだ。
このゴシップ記事だって、誰の差し金かを突き止めたら、案外アランだったということだって考えられる。
息子の幸せなどどうでもいいのかと、新聞をぐしゃぐしゃにして捨てると、執事長が眉をぴくんとさせた。
普段怒らないガウェインが怒りを露わにしたからだろう。
「すぐに、父を宮廷から追いやり、マッケンジー家を王都に呼び戻します。その算段をつけたい。父の周辺に噂話がないか探してください。最近苛立っているでしょうから、女に手を付けているかもしれません」
「かしこまりました」
「私は自分に偽りがないことを、イーニッドに伝えます。もう時間がないようです」
もっとのんびりとふたりのゆったりとした時間が欲しかった。
彼女の気持ちを解きほぐし、深い関係になれるような時間が。
執事長が去るのを見送ると、ガウェインは慌ててティールームに急いだ。
彼女のことだから、待ってくれているような気がするのだ。
階下に降りて廊下を小走りに走ると、金色に光るノブを手にして回す。
「イーニッド。待たせて申し訳ありません!」
ティールームにいるだろうかと不安がある。
さっきまで楽しくしていたのだから、怒っても当然だ。
「ガウェイン。もういいの?」
ソファに腰かけた彼女がにこりと微笑み、自分の瞳を心配そうに覗き込でいた。
ブルーの瞳が、どこか寂し気でもあって、すぐに抱きしめたくなる。
「ええ、もう平気です」
衝動を抑えつつ、平然としてイーニッドの隣に腰かける。
上目で「本当に?」と見つめられて、どくんと胸が跳ねた。以前より甘えたように見つめられて、このまま抱きしめたくなる。理性を搔き集めて笑みを作った。
あの日、宮廷で会ったときよりも、確実に身近な存在になれていると実感する。彼女の優しさに触れて、すぐに好きになってしまったこと。家の対立なんてどうでもよくなったことを思い出す。
「大丈夫ですよ。それよりも、美味しいお菓子は堪能できましたか?」
「ひとりじゃ……多いわ」
寂し気に俯く彼女に、今にもキスをしたくなる。
しかし、それではいけないと必死にほほ笑みで誤魔化した。
自分は冷静で、笑顔の絶えない、優しい男なのだ。
父とは違う。
「イーニッド、食べましょうか」
「ええ! 実はね、ソルベやアイスだけは食べていたの。だって溶けてしまうでしょう?」
くすっと微笑む彼女を見て、ガウェインはたまらなくなってイーニッドを抱きしめていた。
胸の中で固まって、ガウェインの行動を理解出来ていないのが分かる。
自分だって同じだ。
冷静で、優しい男がこんなことをしてはいけないはずだ。
胸の中でイーニッドがもぞもぞと動いて、わずかに抵抗しているのが分かる。
それをぎゅっと強引に抱きしめた。
「何かあったの?」
顔が上がり、心配そうに見つめられる。
「イーニッド。すぐに領地から家族を呼びましょう。親戚はお住まいですよね、事情は説明しますから」
「でも……マッケンジー家は追放されたのよ。反逆罪に問われるわ。約束は嬉しいけれど、実際には無理でしょう?」
胸の中で、イーニッドの声が小さくなっていく。
か細くなる声を聞いて、ガウェインはたまらなく愛おしく思えてきて、尚更ぎゅっと抱きしめていた。
「俺は、父から守ると約束しました。手段は選びません」
「でも……それは……ソレク家への裏切りよ……? 分かるでしょう?」
ガウェインは何も言えなかった。
家族を裏切る男を、イーニッドは嫌うだろうかと不安になってしまう。
彼女は家庭を大事にしていたし、幼い弟と妹を可愛がっているのも知っている。
0
あなたにおすすめの小説

冷徹宰相様の嫁探し
菱沼あゆ
ファンタジー
あまり裕福でない公爵家の次女、マレーヌは、ある日突然、第一王子エヴァンの正妃となるよう、申し渡される。
その知らせを持って来たのは、若き宰相アルベルトだったが。
マレーヌは思う。
いやいやいやっ。
私が好きなのは、王子様じゃなくてあなたの方なんですけど~っ!?
実家が無害そう、という理由で王子の妃に選ばれたマレーヌと、冷徹宰相の恋物語。
(「小説家になろう」でも公開しています)

【完結】傷物令嬢は近衛騎士団長に同情されて……溺愛されすぎです。
朝日みらい
恋愛
王太子殿下との婚約から洩れてしまった伯爵令嬢のセーリーヌ。
宮廷の大広間で突然現れた賊に襲われた彼女は、殿下をかばって大けがを負ってしまう。
彼女に同情した近衛騎士団長のアドニス侯爵は熱心にお見舞いをしてくれるのだが、その熱意がセーリーヌの折れそうな心まで癒していく。
加えて、セーリーヌを振ったはずの王太子殿下が、親密な二人に絡んできて、ややこしい展開になり……。
果たして、セーリーヌとアドニス侯爵の関係はどうなるのでしょう?

【完結】孤高の皇帝は冷酷なはずなのに、王妃には甘過ぎです。
朝日みらい
恋愛
異国からやってきた第3王女のアリシアは、帝国の冷徹な皇帝カイゼルの元に王妃として迎えられた。しかし、冷酷な皇帝と呼ばれるカイゼルは周囲に心を許さず、心を閉ざしていた。しかし、アリシアのひたむきさと笑顔が、次第にカイゼルの心を溶かしていき――。

【完】出来損ない令嬢は、双子の娘を持つ公爵様と契約結婚する~いつの間にか公爵様と7歳のかわいい双子たちに、めいっぱい溺愛されていました~
夏芽空
恋愛
子爵令嬢のエレナは、常に優秀な妹と比較され家族からひどい扱いを受けてきた。
しかし彼女は7歳の双子の娘を持つ公爵――ジオルトと契約結婚したことで、最低な家族の元を離れることができた。
しかも、条件は最高。公の場で妻を演じる以外は自由に過ごしていい上に、さらには給料までも出してくてれるという。
夢のような生活を手に入れた――と、思ったのもつかの間。
いきなり事件が発生してしまう。
結婚したその翌日に、双子の姉が令嬢教育の教育係をやめさせてしまった。
しかもジオルトは仕事で出かけていて、帰ってくるのはなんと一週間後だ。
(こうなったら、私がなんとかするしかないわ!)
腹をくくったエレナは、おもいきった行動を起こす。
それがきっかけとなり、ちょっと癖のある美少女双子義娘と、彼女たちよりもさらに癖の強いジオルトとの距離が縮まっていくのだった――。

溺愛王子の甘すぎる花嫁~悪役令嬢を追放したら、毎日が新婚初夜になりました~
紅葉山参
恋愛
侯爵令嬢リーシャは、婚約者である第一王子ビヨンド様との結婚を心から待ち望んでいた。けれど、その幸福な未来を妬む者もいた。それが、リーシャの控えめな立場を馬鹿にし、王子を我が物にしようと画策した悪役令嬢ユーリーだった。
ある夜会で、ユーリーはビヨンド様の気を引こうと、リーシャを罠にかける。しかし、あなたの王子は、そんなつまらない小細工に騙されるほど愚かではなかった。愛するリーシャを信じ、王子はユーリーを即座に糾弾し、国外追放という厳しい処分を下す。
邪魔者が消え去った後、リーシャとビヨンド様の甘美な新婚生活が始まる。彼は、人前では厳格な王子として振る舞うけれど、私と二人きりになると、とろけるような甘さでリーシャを愛し尽くしてくれるの。
「私の可愛い妻よ、きみなしの人生なんて考えられない」
そう囁くビヨンド様に、私リーシャもまた、心も身体も預けてしまう。これは、障害が取り除かれたことで、むしろ加速度的に深まる、世界一甘くて幸せな夫婦の溺愛物語。新婚の王子妃として、私は彼の、そして王国の「最愛」として、毎日を幸福に満たされて生きていきます。

落ちこぼれで婚約破棄されて周りから醜いと言われる令嬢は学園で王子に溺愛される
つちのこうや
恋愛
貴族の中で身分が低く、落ちこぼれで婚約破棄されて周りから醜いと言われる令嬢の私。
そんな私の趣味は裁縫だった。そんな私が、ある日、宮殿の中の学園でぬいぐるみを拾った。
どうやら、近くの国から留学に来ているイケメン王子のもののようだけど…
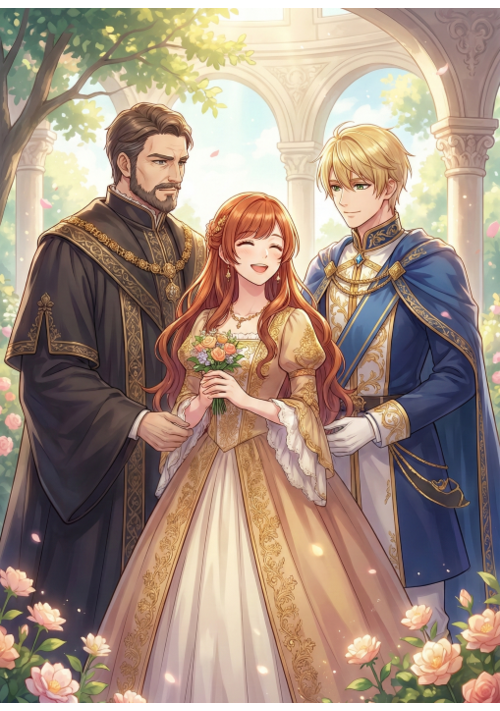
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

婚約破棄された辺境伯令嬢ノアは、冷血と呼ばれた帝国大提督に一瞬で溺愛されました〜政略結婚のはずが、なぜか甘やかされまくってます!?〜
夜桜
恋愛
辺境の地を治めるクレメンタイン辺境伯家の令嬢ノアは、帝国元老院から突然の召喚を受ける。
帝都で待っていたのは、婚約者である若きエリート議員、マグヌス・ローレンス。――しかし彼は、帝国中枢の面前でノアとの婚約を一方的に破棄する。
「君のような“辺境育ち”では、帝国の未来にふさわしくない」
誰もがノアを笑い、見下し、軽んじる中、ひとりの男が静かに立ち上がった。
「その令嬢が不要なら、私がもらおう」
そう言ったのは、“冷血の大提督”と恐れられる帝国軍最高司令官――レックス・エヴァンス。
冷たく厳しい眼差しの奥に宿る、深い誠実さとあたたかさ。
彼の隣で、ノアは帝都の陰謀に立ち向かい、誇りと未来を取り戻していく。
これは、婚約破棄された辺境伯令嬢が、帝国最強の大提督に“一瞬で”溺愛され、
やがて帝国そのものを揺るがす人生逆転の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















