19 / 23
第十九話
しおりを挟む
「そんなに泣いて。俺は案外信用されていたのですね?」
「そう……みたい……。だって、私は妻だと思っていたから。あなたに愛されるものだと思い込んでいたから。両親はいがみ合っているけれど、私たちは違うんじゃないかって、思っていたから」
「いつか愛し合えると?」
イーニッドが恥ずかしそうに胸の中で頷いている。
思わぬ告白に、イーニッドが照れたように笑みを見せてくれた。
「私、心のどこかで期待していたの。でも、もしも信じて拒絶されたら、もしも裏切られたら。そうしたら、私、父の顔に泥を塗るわ。自分の気持ちだって、永遠にふさぎ込むだけ。それが怖くて、近寄れなかった」
イーニッドは初めて自分の気持ちを吐露した。告白なんて初めてだが、ガウェインに聞いて欲しかったのだ。
「俺が悪いんです。強引な手を使ったから。イーニッドに嫌われても良いと思っても、あなたを手に入れたかった」
「どうして? 私、あなたにそこまで愛される意味が分からないわ」
「そうでしょうね……。ごく自然に、声を掛けてくれましたから」
「……声を掛けた……? 私が?」
「ええ。でも、その話はまた今度。今はあなたにキスをしたい」
ガウェインは顎を掬うと、唇を重ねた。
触れる程度なのに、とても深く綱がるような想いになる。
それに、彼女の温もりを感じて身体中があつくなっていた。
(ああ、これ以上はいけない)
そっと離れると、イーニッドから潤んだ瞳で見つめられた。
そんな顔をされたら、ソファでもベッドも構わずに押し倒してしまいそうだ。
「イーニッド。私は王に父の事を暴露します。明日にでも。今、王に手紙を渡したいと申し出ているところです。王に父についてお話があると伝えました。宮中で熟慮されている間に、旅行に行きませんか? 別邸に向かい、ふたりきりの時間を過ごしましょう」
「で、でも……」
「怖いですか? 私が」
イーニッドが小さく首を振ってくれた。
彼女の気持ちが融解し、自分の元に来てくれたことが嬉しい。
それだけじゃなく、王への進言が通れば、父を追い落とすことだって出来る。
「メイドに言って、支度してください。俺は今すぐ、宮廷に向かいます」
「本当にいいの? お父さまよ」
「俺はもう、とっくの昔に父とは縁を切っていると思って生きてきました。そうでもしなければ、父の道具として、扱われていたでしょう。父の命が尽きるまで自由がないなど、俺は待てない」
ガウェインは強い意志を持って、イーニッドに伝えた。
彼女はこくりと頷いて、微笑んでくれる。
自分だけの戦いじゃないことに安堵して、ふわっとした倦怠感が襲ってきた。
慌てて背を伸ばすと、部屋を出て馬車を用意させた。
慌てて用意された馬車に乗り込むと、瞼が落ちてきた。
***
靄のかかるような現実に、これは夢の中だとガウェインは自分に言った。
宮廷前の噴水広場、豪華な造りの宮廷の前には広い階段がある。
足の悪い老人には辛いと、若いうちから長男に宮廷貴族での地位を譲る物が多いなか、ソレク家とマッケンジー家は老いてもなお、この階段を何度も昇り、王に進言する力を得ていた。
ライバルではなく、互いに敵としてガウェインの父アランはマッケンジー家を恨んでいた。
マッケンジー家に長男がいないことを嘲笑い、いつか王都を追放してやると、よく言っていたものだ。
イーニッドがどこかの侯爵家に嫁ぐ前に、宮廷を追い出してやると言っていたが、そんな都合よくいくものかと、ガウェインはのんびりと構えていた。
今日は父の為に資料を持ってきた。その帰りだ。
噴水の段さに腰を下ろすと、どっと疲れも出る。
(ふう)
王に会ってもいないのに、宮廷に入るだけでも緊張してしまった。
父の苛立つような顔を見て、余計に胃が痛くなる。
しばらくぼんやりと雲でも眺めていたいものだと、空を眺めていたときだ。
「あの」
「はい?」
くりんとしたブルーの目の美人が、ガウェインを見つめていた。
髪の毛は金髪を結い上げて、太陽に当たると光り輝くように見える。
「これ、大事なものでは。落としていかれましたが」
すっと出されたものは、父の為に持っていけと言われたきつけ薬だった。
資料の事で頭がいっぱいで、渡し忘れているどころか落としていたなんて。
「すみません。大事なもので」
「いいのです。私も父に用があって、ここに参りました」
くすっと笑みを見せられて、ガウェインは胸が跳ねた。
女性にときめくような事は今までなく、淡々と過ごすことの方が多かったのに、その笑みを見た瞬間に、心が解かされるような思いになったのだ。
「なにか?」
女性は首を傾げている。
ガウェインがじっと見つめ過ぎたのだろう。
まだ胸がどくどくと鳴っていた。
(名前を聞いて、夜会でダンスを申し入れよう)
「お名前は。お礼がしたいのですが」
「イーニッド・マッケンジーと申します。宮廷に来るのは初めてで。とても緊張しております。父からは余計な人と話すなと命じられていたのですが。大切な落し物ですものね」
イーニッドが口元に手を当ててまた微笑むと、その所作が可愛らしい。
父の言いつけよりも、相手を思いやることが好感が持てた。
しかしガウェインは落ち着くことが出来なかった。
マッケンジーと言えば、敵でもある侯爵の娘。
自分は父とは違うと誓っているとはいえ、余計な接触は好ましくない。
そう思いつつ、ガウェインはイーニッドを見つめてしまった。あまりの美しさに思わず見入ってしまうのだ。ブルーの瞳を見ていると吸い込まれるような錯覚に陥る。透き通った肌は触れてみたいほど透明さのある白い肌だ。
「あの、お名前は?」
「ああ、『パトリック』と申します。王都には少し用があって」
咄嗟に嘘をついて、なんとかごまかした。
自分がマッケンジー家から離れろ命じられているのに、彼女がそう躾られていないわけがない。
少なくとも、彼女は余計な人間とは関わるなと命じられているのがその証拠だ。
「あの、俺はもう行きます。ありがとうございます」
「私も、父の忘れものを届けないといけないの」
イーニッドはそう言うと、会釈をして去っていった。
後を着いて行くわけにもいかず、ガウェインはきつけ薬を持って、邸に帰った。
帰ってくるなり、父の怒りに触れたが、イーニッドのことが忘れられず、夜会に積極的に出て、彼女を探しだした。
でも、イーニッドはいつも壁際で夜会の様子を見ているだけだった。
そんな彼女に声を掛けるべきか、すぐに声を掛けなければ、相手が見つかってしまうと思うのだが足が動かない。
うまくいかない恋ほど、泥沼に足を突っ込んでいるように、はまっていく。
彼女をよく知らないせいもあり、余計に気になって仕方なく、好意は膨らんだ。
イーニッドを見て、とても芯が通った女性だと感じたし、素直だとも思った。
夜会に出れば誰もが男性にすり寄るものだが、彼女はそれをせずに、自分の好きな相手をじっと見定めているようにも見える。
勿論、誘われればダンスをしていたが、浮ついた男性と軽率に踊ることもない。
噂話に興じる令嬢に群がることもない。
それだけでも充分に魅力的に思えるのだが、調べさせるとオペラや読書が好きだという。
なんとか一度でも話せればと思うのだが、名乗った瞬間にイーニッドの嫌悪の表情が目に浮かんで、踏み切れなかった。
ガウェインだって、令嬢と形だけでもダンスを踊り、暇ではない。
それでも、イーニッドを忘れさせてくれるほどの女性はいないのだから仕方がない。
結局、夜会で会っても遠目から見るだけで、接点もなく、マッケンジー家は王都から追放された。
そして、ガウェインはイーニッドを手に入れる為なら、何でもすると決めたのだ。
靄が晴れるように、ガウェインの瞼がゆっくりと開いていく。
「そう……みたい……。だって、私は妻だと思っていたから。あなたに愛されるものだと思い込んでいたから。両親はいがみ合っているけれど、私たちは違うんじゃないかって、思っていたから」
「いつか愛し合えると?」
イーニッドが恥ずかしそうに胸の中で頷いている。
思わぬ告白に、イーニッドが照れたように笑みを見せてくれた。
「私、心のどこかで期待していたの。でも、もしも信じて拒絶されたら、もしも裏切られたら。そうしたら、私、父の顔に泥を塗るわ。自分の気持ちだって、永遠にふさぎ込むだけ。それが怖くて、近寄れなかった」
イーニッドは初めて自分の気持ちを吐露した。告白なんて初めてだが、ガウェインに聞いて欲しかったのだ。
「俺が悪いんです。強引な手を使ったから。イーニッドに嫌われても良いと思っても、あなたを手に入れたかった」
「どうして? 私、あなたにそこまで愛される意味が分からないわ」
「そうでしょうね……。ごく自然に、声を掛けてくれましたから」
「……声を掛けた……? 私が?」
「ええ。でも、その話はまた今度。今はあなたにキスをしたい」
ガウェインは顎を掬うと、唇を重ねた。
触れる程度なのに、とても深く綱がるような想いになる。
それに、彼女の温もりを感じて身体中があつくなっていた。
(ああ、これ以上はいけない)
そっと離れると、イーニッドから潤んだ瞳で見つめられた。
そんな顔をされたら、ソファでもベッドも構わずに押し倒してしまいそうだ。
「イーニッド。私は王に父の事を暴露します。明日にでも。今、王に手紙を渡したいと申し出ているところです。王に父についてお話があると伝えました。宮中で熟慮されている間に、旅行に行きませんか? 別邸に向かい、ふたりきりの時間を過ごしましょう」
「で、でも……」
「怖いですか? 私が」
イーニッドが小さく首を振ってくれた。
彼女の気持ちが融解し、自分の元に来てくれたことが嬉しい。
それだけじゃなく、王への進言が通れば、父を追い落とすことだって出来る。
「メイドに言って、支度してください。俺は今すぐ、宮廷に向かいます」
「本当にいいの? お父さまよ」
「俺はもう、とっくの昔に父とは縁を切っていると思って生きてきました。そうでもしなければ、父の道具として、扱われていたでしょう。父の命が尽きるまで自由がないなど、俺は待てない」
ガウェインは強い意志を持って、イーニッドに伝えた。
彼女はこくりと頷いて、微笑んでくれる。
自分だけの戦いじゃないことに安堵して、ふわっとした倦怠感が襲ってきた。
慌てて背を伸ばすと、部屋を出て馬車を用意させた。
慌てて用意された馬車に乗り込むと、瞼が落ちてきた。
***
靄のかかるような現実に、これは夢の中だとガウェインは自分に言った。
宮廷前の噴水広場、豪華な造りの宮廷の前には広い階段がある。
足の悪い老人には辛いと、若いうちから長男に宮廷貴族での地位を譲る物が多いなか、ソレク家とマッケンジー家は老いてもなお、この階段を何度も昇り、王に進言する力を得ていた。
ライバルではなく、互いに敵としてガウェインの父アランはマッケンジー家を恨んでいた。
マッケンジー家に長男がいないことを嘲笑い、いつか王都を追放してやると、よく言っていたものだ。
イーニッドがどこかの侯爵家に嫁ぐ前に、宮廷を追い出してやると言っていたが、そんな都合よくいくものかと、ガウェインはのんびりと構えていた。
今日は父の為に資料を持ってきた。その帰りだ。
噴水の段さに腰を下ろすと、どっと疲れも出る。
(ふう)
王に会ってもいないのに、宮廷に入るだけでも緊張してしまった。
父の苛立つような顔を見て、余計に胃が痛くなる。
しばらくぼんやりと雲でも眺めていたいものだと、空を眺めていたときだ。
「あの」
「はい?」
くりんとしたブルーの目の美人が、ガウェインを見つめていた。
髪の毛は金髪を結い上げて、太陽に当たると光り輝くように見える。
「これ、大事なものでは。落としていかれましたが」
すっと出されたものは、父の為に持っていけと言われたきつけ薬だった。
資料の事で頭がいっぱいで、渡し忘れているどころか落としていたなんて。
「すみません。大事なもので」
「いいのです。私も父に用があって、ここに参りました」
くすっと笑みを見せられて、ガウェインは胸が跳ねた。
女性にときめくような事は今までなく、淡々と過ごすことの方が多かったのに、その笑みを見た瞬間に、心が解かされるような思いになったのだ。
「なにか?」
女性は首を傾げている。
ガウェインがじっと見つめ過ぎたのだろう。
まだ胸がどくどくと鳴っていた。
(名前を聞いて、夜会でダンスを申し入れよう)
「お名前は。お礼がしたいのですが」
「イーニッド・マッケンジーと申します。宮廷に来るのは初めてで。とても緊張しております。父からは余計な人と話すなと命じられていたのですが。大切な落し物ですものね」
イーニッドが口元に手を当ててまた微笑むと、その所作が可愛らしい。
父の言いつけよりも、相手を思いやることが好感が持てた。
しかしガウェインは落ち着くことが出来なかった。
マッケンジーと言えば、敵でもある侯爵の娘。
自分は父とは違うと誓っているとはいえ、余計な接触は好ましくない。
そう思いつつ、ガウェインはイーニッドを見つめてしまった。あまりの美しさに思わず見入ってしまうのだ。ブルーの瞳を見ていると吸い込まれるような錯覚に陥る。透き通った肌は触れてみたいほど透明さのある白い肌だ。
「あの、お名前は?」
「ああ、『パトリック』と申します。王都には少し用があって」
咄嗟に嘘をついて、なんとかごまかした。
自分がマッケンジー家から離れろ命じられているのに、彼女がそう躾られていないわけがない。
少なくとも、彼女は余計な人間とは関わるなと命じられているのがその証拠だ。
「あの、俺はもう行きます。ありがとうございます」
「私も、父の忘れものを届けないといけないの」
イーニッドはそう言うと、会釈をして去っていった。
後を着いて行くわけにもいかず、ガウェインはきつけ薬を持って、邸に帰った。
帰ってくるなり、父の怒りに触れたが、イーニッドのことが忘れられず、夜会に積極的に出て、彼女を探しだした。
でも、イーニッドはいつも壁際で夜会の様子を見ているだけだった。
そんな彼女に声を掛けるべきか、すぐに声を掛けなければ、相手が見つかってしまうと思うのだが足が動かない。
うまくいかない恋ほど、泥沼に足を突っ込んでいるように、はまっていく。
彼女をよく知らないせいもあり、余計に気になって仕方なく、好意は膨らんだ。
イーニッドを見て、とても芯が通った女性だと感じたし、素直だとも思った。
夜会に出れば誰もが男性にすり寄るものだが、彼女はそれをせずに、自分の好きな相手をじっと見定めているようにも見える。
勿論、誘われればダンスをしていたが、浮ついた男性と軽率に踊ることもない。
噂話に興じる令嬢に群がることもない。
それだけでも充分に魅力的に思えるのだが、調べさせるとオペラや読書が好きだという。
なんとか一度でも話せればと思うのだが、名乗った瞬間にイーニッドの嫌悪の表情が目に浮かんで、踏み切れなかった。
ガウェインだって、令嬢と形だけでもダンスを踊り、暇ではない。
それでも、イーニッドを忘れさせてくれるほどの女性はいないのだから仕方がない。
結局、夜会で会っても遠目から見るだけで、接点もなく、マッケンジー家は王都から追放された。
そして、ガウェインはイーニッドを手に入れる為なら、何でもすると決めたのだ。
靄が晴れるように、ガウェインの瞼がゆっくりと開いていく。
0
あなたにおすすめの小説

婚約破棄された公爵令嬢と、処方箋を無視する天才薬師 ――正しい医療は、二人で始めます
ふわふわ
恋愛
「その医療は、本当に正しいと言えますか?」
医療体制への疑問を口にしたことで、
公爵令嬢ミーシャ・ゲートは、
医会の頂点に立つ婚約者ウッド・マウント公爵から
一方的に婚約を破棄される。
――素人の戯言。
――体制批判は不敬。
そう断じられ、
“医療を否定した危険な令嬢”として社交界からも排斥されたミーシャは、
それでも引かなかった。
ならば私は、正しい医療を制度として作る。
一方その頃、国営薬局に現れた謎の新人薬師・ギ・メイ。
彼女は転生者であり、前世の知識を持つ薬師だった。
画一的な万能薬が当然とされる現場で、
彼女は処方箋に書かれたわずかな情報から、
最適な調剤を次々と生み出していく。
「決められた万能薬を使わず、
問題が起きたら、どうするつもりだ?」
そう問われても、彼女は即答する。
「私、失敗しませんから」
(……一度言ってみたかったのよね。このドラマの台詞)
結果は明らかだった。
患者は回復し、評判は広がる。
だが――
制度は、個人の“正
制度を変えようとする令嬢。
現場で結果を出し続ける薬師。
医師、薬局、医会、王宮。
それぞれの立場と正義が衝突する中、
医療改革はやがて「裁き」の局面へと進んでいく。
これは、
転生者の知識で無双するだけでは終わらない医療改革ファンタジー。
正しさとは何か。
責任は誰が負うべきか。
最後に裁かれるのは――
人か、制度か。

冷徹宰相様の嫁探し
菱沼あゆ
ファンタジー
あまり裕福でない公爵家の次女、マレーヌは、ある日突然、第一王子エヴァンの正妃となるよう、申し渡される。
その知らせを持って来たのは、若き宰相アルベルトだったが。
マレーヌは思う。
いやいやいやっ。
私が好きなのは、王子様じゃなくてあなたの方なんですけど~っ!?
実家が無害そう、という理由で王子の妃に選ばれたマレーヌと、冷徹宰相の恋物語。
(「小説家になろう」でも公開しています)

【完結】傷物令嬢は近衛騎士団長に同情されて……溺愛されすぎです。
朝日みらい
恋愛
王太子殿下との婚約から洩れてしまった伯爵令嬢のセーリーヌ。
宮廷の大広間で突然現れた賊に襲われた彼女は、殿下をかばって大けがを負ってしまう。
彼女に同情した近衛騎士団長のアドニス侯爵は熱心にお見舞いをしてくれるのだが、その熱意がセーリーヌの折れそうな心まで癒していく。
加えて、セーリーヌを振ったはずの王太子殿下が、親密な二人に絡んできて、ややこしい展開になり……。
果たして、セーリーヌとアドニス侯爵の関係はどうなるのでしょう?

【完】出来損ない令嬢は、双子の娘を持つ公爵様と契約結婚する~いつの間にか公爵様と7歳のかわいい双子たちに、めいっぱい溺愛されていました~
夏芽空
恋愛
子爵令嬢のエレナは、常に優秀な妹と比較され家族からひどい扱いを受けてきた。
しかし彼女は7歳の双子の娘を持つ公爵――ジオルトと契約結婚したことで、最低な家族の元を離れることができた。
しかも、条件は最高。公の場で妻を演じる以外は自由に過ごしていい上に、さらには給料までも出してくてれるという。
夢のような生活を手に入れた――と、思ったのもつかの間。
いきなり事件が発生してしまう。
結婚したその翌日に、双子の姉が令嬢教育の教育係をやめさせてしまった。
しかもジオルトは仕事で出かけていて、帰ってくるのはなんと一週間後だ。
(こうなったら、私がなんとかするしかないわ!)
腹をくくったエレナは、おもいきった行動を起こす。
それがきっかけとなり、ちょっと癖のある美少女双子義娘と、彼女たちよりもさらに癖の強いジオルトとの距離が縮まっていくのだった――。
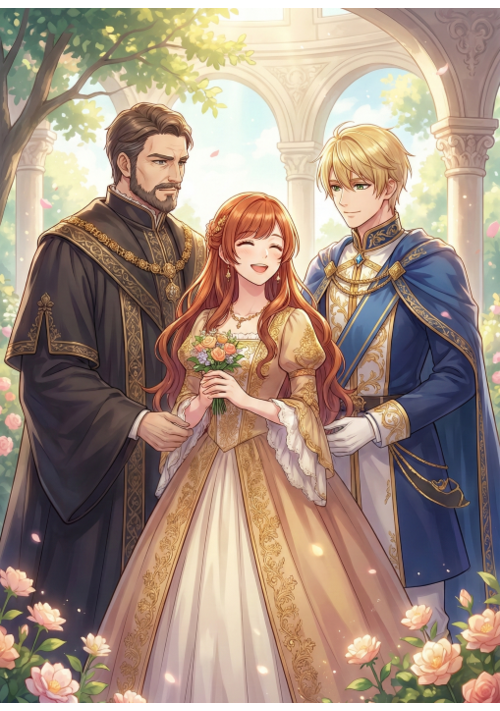
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

溺愛王子の甘すぎる花嫁~悪役令嬢を追放したら、毎日が新婚初夜になりました~
紅葉山参
恋愛
侯爵令嬢リーシャは、婚約者である第一王子ビヨンド様との結婚を心から待ち望んでいた。けれど、その幸福な未来を妬む者もいた。それが、リーシャの控えめな立場を馬鹿にし、王子を我が物にしようと画策した悪役令嬢ユーリーだった。
ある夜会で、ユーリーはビヨンド様の気を引こうと、リーシャを罠にかける。しかし、あなたの王子は、そんなつまらない小細工に騙されるほど愚かではなかった。愛するリーシャを信じ、王子はユーリーを即座に糾弾し、国外追放という厳しい処分を下す。
邪魔者が消え去った後、リーシャとビヨンド様の甘美な新婚生活が始まる。彼は、人前では厳格な王子として振る舞うけれど、私と二人きりになると、とろけるような甘さでリーシャを愛し尽くしてくれるの。
「私の可愛い妻よ、きみなしの人生なんて考えられない」
そう囁くビヨンド様に、私リーシャもまた、心も身体も預けてしまう。これは、障害が取り除かれたことで、むしろ加速度的に深まる、世界一甘くて幸せな夫婦の溺愛物語。新婚の王子妃として、私は彼の、そして王国の「最愛」として、毎日を幸福に満たされて生きていきます。

【完結】孤高の皇帝は冷酷なはずなのに、王妃には甘過ぎです。
朝日みらい
恋愛
異国からやってきた第3王女のアリシアは、帝国の冷徹な皇帝カイゼルの元に王妃として迎えられた。しかし、冷酷な皇帝と呼ばれるカイゼルは周囲に心を許さず、心を閉ざしていた。しかし、アリシアのひたむきさと笑顔が、次第にカイゼルの心を溶かしていき――。

落ちこぼれで婚約破棄されて周りから醜いと言われる令嬢は学園で王子に溺愛される
つちのこうや
恋愛
貴族の中で身分が低く、落ちこぼれで婚約破棄されて周りから醜いと言われる令嬢の私。
そんな私の趣味は裁縫だった。そんな私が、ある日、宮殿の中の学園でぬいぐるみを拾った。
どうやら、近くの国から留学に来ているイケメン王子のもののようだけど…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















