38 / 80
執着心 後編
18話
しおりを挟む
俺は満緒を前にはっきりあの伝票が「偽物」だと言い切った。
満緒はそれが気にいらなかったらしく、しつこく絡んできた。
「は? お前が言ったんだろ、この商品名は違法薬物だって」
「ああ、言ったよ。だから偽物なんだよ」
「はぁ?」
満緒はますます理解ができないといった風に、顔を顰める。
「普通で考えたら分かるだろ。あの伝票に書かれている商品は日本では違法なものだ。所持さえ許されないものが、そもそも入管審査に通るはずがないし、商品名にそのものズバリ記載しているなら没収されるはずだ。下手をしたら京香さんのもとへ警察がやってくる案件だよ」
「…………」
「君は俺に京香さんが薬を買っているという既成事実を作りたくて、チープな方法をとったんだろうけどあまりにも杜撰すぎるよ。伝票くらい印刷機があれば簡単に作れるし、コピーしたものなら尚更簡単だろう」
「…………」
満緒はしばらく黙り込んでいたが、唇の端を吊り上げて微笑む。
「なるほどな。お前は俺が金目当てに昔の女に罪を着せて、父親を殺そうとしている、そう言いたいんだな」
俺は首を振る。
「いいや、君が欲しいものはもっと他にあるんだろ? 喉から手が出るほど欲しくて、父親から奪い取りたいほど執着を持っているものが」
俺はそう言って京香を見た。
京香は体を震わせ、俯いた。
「バカかお前は。俺は京香と親父が結婚する時に賛成したんだ。最初は昔の女が家に出入りするって聞いてぞっとしたけど、親父が幸せならと納得したんだ。俺と京香の関係は親父も知ってる、そうだろ?」
住職は青ざめた顔をして満緒を見ていた。
さっきから一言も言葉を発しない。まるで声を奪われた哀れな老人のように、住職は唇をプルプルと痙攣させ必死にちゃぶ台にしがみついている。
「君はどうしても京香さんを手に入れたかったんだ。自分の恋人にすることができないのなら、せめて<家族>になろうと」
「さっきから聞いてりゃ、俺がえらい京香に夢中になってるみたいじゃねぇか。こんな年増、ちょっと遊んだだけだよ」
その言葉を聞き、京香の眉が吊り上がる。
「あなた、最低よ! 隆さんにあんなことしておきながら!」
叫び声をあげる京香を前に、満緒は面倒くさそうに耳に指を突っ込み、その声を受け流す。
俺は冷静に2人を見比べ、ある人物の名前を口に出す。
「矢島隆さん、それが満緒さんの当時の担任で、京香さんの婚約者だった方ですね」
その名前が出た途端、明らかに場の空気が変わった。俺以外の全員が、はっとしたように体を強張らせ、警戒心を募らせていった。
俺はその様子を感じながらも、淡々と話を続けた。
「実は満緒さんの同級生の塩田雄太さんに会った後、矢島隆さんの住所を聞いて会いに行ったんだ」
満緒が小さく舌打ちする。
「彼は隣の県に住んでいてね、現在も一人暮らしだそうだよ」
そう言うと、京香の瞳が揺れた。
「驚いたよ、チャイムを鳴らして出て来た矢島さんが車いすだったからね」
住職は真っ青な顔をして両手で顔を覆った。
「彼が全部話してくれたよ、どうして自分が車いす生活になったのか、何が原因なのかもね」
俺は無言で満緒を見た後、話を続けた。
「高校1年生の担任をやっていた時、とんでもない問題児がいたそうなんだ。寺の息子のくせして、恐喝、万引き、ケンカは日常茶飯事。とにかく荒れてひどかったって。何度も指導を続けたが全然聞き入れてもらえない。そうこうしているうちに矢島さんの方が精神的に不安定になってしまい、うつ状態になったそうだよ」
笑顔で当時の話を語ってくれた矢島だが、あの当時は大変な思いをしたのだろう。
「やがて彼一人で手が回らなかったところを婚約者の吉田京香さんがサポートしてくれるようになった。彼女は親身になってその子のケアをし、相手の状態も少しづつ落ち着いてきていたんだ。矢島先生は安心していたそうだけど、矢島先生と吉田先生が結婚間近だという噂が学校中に広まってその子の態度が一変したそうだ」
京香は俯いて拳を握り締める。
「彼は京香さんを無理やり襲い自分のものにしようとした。その事実を知った矢島さんが彼を問い詰めたところ、ひどいケガを負わされたそうだよ」
「あいつが俺に飛び掛かって来たんだ。正当防衛ってやつだよ」
「だろうね、だから君はすぐに少年院を出てこれた。でも実際は違った。矢島さんは全身を殴打され、体には5カ所の深い刺し傷があった。とても普通のケンカだとは思えない。彼はその時に脊髄を損傷して車いす生活を余儀なくされているんだ」
「ふん、ご愁傷様」
小馬鹿にしたような満緒の言葉に、住職が厳しい叱責を浴びせる。
「やめるんだ満緒。お前は矢島先生にどれだけひどいことをしたのか理解する必要がある。何度も話をしたが、全く理解できていないんだな」
疲れ果てたように顔を覆った住職を見て、俺は彼が心の底から疲弊しているのを感じ取った。
病室で会話した時、満緒の非行のせいで当時は謝罪の日々だったと語っていたが、本当にその通りだったのだろう。あの頃の住職に気の休まる日などなかったはずだ。
俺は真顔で満緒に言った。
「――君は異常だよ」
満緒はそれが気にいらなかったらしく、しつこく絡んできた。
「は? お前が言ったんだろ、この商品名は違法薬物だって」
「ああ、言ったよ。だから偽物なんだよ」
「はぁ?」
満緒はますます理解ができないといった風に、顔を顰める。
「普通で考えたら分かるだろ。あの伝票に書かれている商品は日本では違法なものだ。所持さえ許されないものが、そもそも入管審査に通るはずがないし、商品名にそのものズバリ記載しているなら没収されるはずだ。下手をしたら京香さんのもとへ警察がやってくる案件だよ」
「…………」
「君は俺に京香さんが薬を買っているという既成事実を作りたくて、チープな方法をとったんだろうけどあまりにも杜撰すぎるよ。伝票くらい印刷機があれば簡単に作れるし、コピーしたものなら尚更簡単だろう」
「…………」
満緒はしばらく黙り込んでいたが、唇の端を吊り上げて微笑む。
「なるほどな。お前は俺が金目当てに昔の女に罪を着せて、父親を殺そうとしている、そう言いたいんだな」
俺は首を振る。
「いいや、君が欲しいものはもっと他にあるんだろ? 喉から手が出るほど欲しくて、父親から奪い取りたいほど執着を持っているものが」
俺はそう言って京香を見た。
京香は体を震わせ、俯いた。
「バカかお前は。俺は京香と親父が結婚する時に賛成したんだ。最初は昔の女が家に出入りするって聞いてぞっとしたけど、親父が幸せならと納得したんだ。俺と京香の関係は親父も知ってる、そうだろ?」
住職は青ざめた顔をして満緒を見ていた。
さっきから一言も言葉を発しない。まるで声を奪われた哀れな老人のように、住職は唇をプルプルと痙攣させ必死にちゃぶ台にしがみついている。
「君はどうしても京香さんを手に入れたかったんだ。自分の恋人にすることができないのなら、せめて<家族>になろうと」
「さっきから聞いてりゃ、俺がえらい京香に夢中になってるみたいじゃねぇか。こんな年増、ちょっと遊んだだけだよ」
その言葉を聞き、京香の眉が吊り上がる。
「あなた、最低よ! 隆さんにあんなことしておきながら!」
叫び声をあげる京香を前に、満緒は面倒くさそうに耳に指を突っ込み、その声を受け流す。
俺は冷静に2人を見比べ、ある人物の名前を口に出す。
「矢島隆さん、それが満緒さんの当時の担任で、京香さんの婚約者だった方ですね」
その名前が出た途端、明らかに場の空気が変わった。俺以外の全員が、はっとしたように体を強張らせ、警戒心を募らせていった。
俺はその様子を感じながらも、淡々と話を続けた。
「実は満緒さんの同級生の塩田雄太さんに会った後、矢島隆さんの住所を聞いて会いに行ったんだ」
満緒が小さく舌打ちする。
「彼は隣の県に住んでいてね、現在も一人暮らしだそうだよ」
そう言うと、京香の瞳が揺れた。
「驚いたよ、チャイムを鳴らして出て来た矢島さんが車いすだったからね」
住職は真っ青な顔をして両手で顔を覆った。
「彼が全部話してくれたよ、どうして自分が車いす生活になったのか、何が原因なのかもね」
俺は無言で満緒を見た後、話を続けた。
「高校1年生の担任をやっていた時、とんでもない問題児がいたそうなんだ。寺の息子のくせして、恐喝、万引き、ケンカは日常茶飯事。とにかく荒れてひどかったって。何度も指導を続けたが全然聞き入れてもらえない。そうこうしているうちに矢島さんの方が精神的に不安定になってしまい、うつ状態になったそうだよ」
笑顔で当時の話を語ってくれた矢島だが、あの当時は大変な思いをしたのだろう。
「やがて彼一人で手が回らなかったところを婚約者の吉田京香さんがサポートしてくれるようになった。彼女は親身になってその子のケアをし、相手の状態も少しづつ落ち着いてきていたんだ。矢島先生は安心していたそうだけど、矢島先生と吉田先生が結婚間近だという噂が学校中に広まってその子の態度が一変したそうだ」
京香は俯いて拳を握り締める。
「彼は京香さんを無理やり襲い自分のものにしようとした。その事実を知った矢島さんが彼を問い詰めたところ、ひどいケガを負わされたそうだよ」
「あいつが俺に飛び掛かって来たんだ。正当防衛ってやつだよ」
「だろうね、だから君はすぐに少年院を出てこれた。でも実際は違った。矢島さんは全身を殴打され、体には5カ所の深い刺し傷があった。とても普通のケンカだとは思えない。彼はその時に脊髄を損傷して車いす生活を余儀なくされているんだ」
「ふん、ご愁傷様」
小馬鹿にしたような満緒の言葉に、住職が厳しい叱責を浴びせる。
「やめるんだ満緒。お前は矢島先生にどれだけひどいことをしたのか理解する必要がある。何度も話をしたが、全く理解できていないんだな」
疲れ果てたように顔を覆った住職を見て、俺は彼が心の底から疲弊しているのを感じ取った。
病室で会話した時、満緒の非行のせいで当時は謝罪の日々だったと語っていたが、本当にその通りだったのだろう。あの頃の住職に気の休まる日などなかったはずだ。
俺は真顔で満緒に言った。
「――君は異常だよ」
0
あなたにおすすめの小説
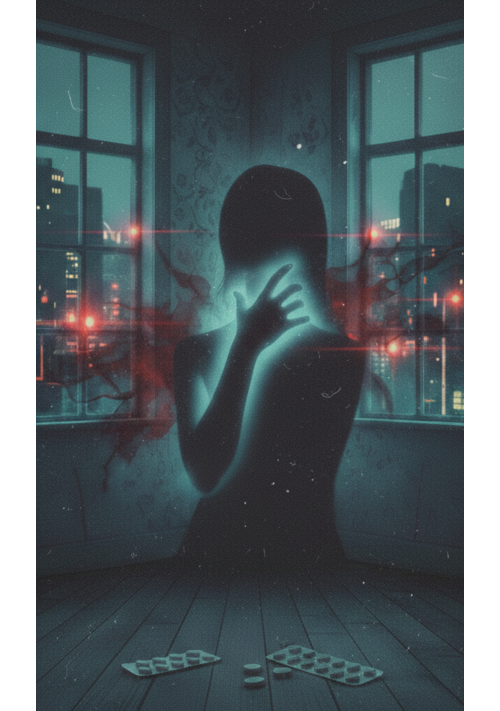
洒落にならない怖い話【短編集】
鍵谷端哉
ホラー
その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。
意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。
隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

「お前のカメラ、ずっと映ってるよ」〜ホラースポット配信者が気づいた時には、もう遅かった〜
まさき
ホラー
ホラースポット専門のYouTuber・桐島悠は、霊も怪異も一切信じない合理主義者だ。
ある廃病院での配信中、今まで感じたことのない「違和感」を覚えた。しかし撮影は無事終了。その後も普通に配信を続け、あの夜のことなど忘れかけていた頃——深夜、金縛りにあう。
疲れてるだけだ。
しかし、それは始まりに過ぎなかった。
記憶の空白。知らない足跡。動画に毎回映り込む、同じ女の姿。そして——「やっと、見つけた」という声。
カメラが映し続けていたのは、心霊スポットではなかった。もっとずっと、近いところにいるものだった。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

(ほぼ)1分で読める怖い話
涼宮さん
ホラー
ほぼ1分で読める怖い話!
【ホラー・ミステリーでTOP10入りありがとうございます!】
1分で読めないのもあるけどね
主人公はそれぞれ別という設定です
フィクションの話やノンフィクションの話も…。
サクサク読めて楽しい!(矛盾してる)
⚠︎この物語で出てくる場所は実在する場所とは全く関係御座いません
⚠︎他の人の作品と酷似している場合はお知らせください


JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















