6 / 11
第6話 僕と遊んでよ
しおりを挟む
「愛人だの何だのと言いながら、実質ペット扱いか?筋の通らん奴め……」
「可愛いがってるのは同じだよ?」
ベヘモットは、レヴィから手付かずのままのケーキ皿をそっと預かり、テーブルへ戻した。そしてソファにいた彼女を軽々と持ち上げると、自分の膝の上に乗せる。
「ふふーっ♡」
ベヘモットはレヴィを腕の中に囲うと、満面の笑みを浮かべた。彼女の細い肩に鼻先を寄せ、流れる黒髪にキスをする。
「うう~……」
ベヘモットの膝の上、精悍な腕の囲いの中で――レヴィは心底居心地悪そうに唸った。浅く座り、腰を浮かせ、身を仰け反らせ。なんとかベヘモットから距離を置こうとする。まるで檻に閉じ込められた小動物のように、逃げ場を探す仕草。
「ククッ……、
貴方、全ッ然懐かれてないじゃないですか」
そんな2人の様子を見て、ジズが堪えきれずに吹き出した。ペストマスクの奥で、愉快そうな笑い声が響く。
「まだ慣れてないだけだもん!これから仲良くなるよ!
ねっ」
「……」
レヴィは黙り込み、ベヘモットの膝の上で、向かい合うように身を丸めた。互いの顔が少し近くなる。
「わっ♡
なぁにーレヴィにゃん?ご主人様と遊ぶ?」
ベヘモットはレヴィを見つめ、嬉しそうに猫撫で声を出す。レヴィも、軽く身を寄せ、微笑んで見つめ返す――フリをして。
ひょい、と。
曲げた膝をバネにして立ち上がり、ベヘモットの腕から素早く抜け出した。そのまま背もたれごと飛び越え――ソファの裏へと、鮮やかに着地する。
「あーっ!」
完全に油断していたのか、ベヘモットの手は遅れて宙を掴む。
監禁されてからの数日間、レヴィは自分に掛けられた拘束術の性質を探っていた。
ベヘモットの至近距離に居れば、多少動けることは確認済み。背後に回り込めば、撹乱できるかもしれない――そう踏んでの実験的な行動。
魔術師ゆえ肉弾戦は苦手だが、小手先の回避術くらいは身体が覚えている。
「おやっ、脱出成功ですねぇ~」
その身のこなしを見て、ジズが面白そうに拍手を送る。まるで演目を終えたサーカスの動物へ、称賛を贈るような態度だ。
「もーレヴィひどい!なんで逃げるのー?」
ベヘモットは振り返ると、背後のレヴィへ恨めしそうな視線を向ける。
「気難しい動物を手乗りにするには……幼い頃から慣らし、訓練する必要がありますからねぇ。人間も、似たようなものではないですか?」
「そんなぁ!子供を攫ってこいってこと?
僕、飼うならレヴィがいいのに……」
ベヘモットは残念そうな顔をする。流石の魔族でも、時を遡ることはできないらしい。
「……しっかし、貴方の性癖も変わりませんね。
こういう、お高くとまっておられる……生意気な小娘?お好きですよねぇ、昔から」
レヴィは、その言葉を聞いて苦々しく思う。貴様ら魔族の方が、余程尊大だろと。
「珍しく仕事熱心だったのも納得です。
余程この獲物が欲しかったんですね、コココ……」
ジズは肩を揺らして笑った。まるで気の知れた友人の趣味を茶化すかのような軽さだ。ペストマスクの奥から、鶏じみた笑い声が響く。
ベヘモットは肩を竦める。レヴィの温もりが残る膝をゆるりと組み直し、少し照れくさそうに言う。
「別にいいじゃん。僕がこの子を退治……もとい、優しく保護したおかげで。あの辺の下級魔族達も、落ち着いて暮らせるようになったでしょ」
手持ち無沙汰にワイングラスを回しながら、ベヘモットは言い訳のように続ける。グラスの中で液体がゆるやかに渦を巻き、血のような赤が妖しく揺れた。
「あのまま放置して、議会の風向きが変わっても怠いし。それに『討伐対象の人間』を引き込めた『前例』になれば……今後の僕の発言にも、説得力が出るかなーって」
議会。ベヘモットの口ぶりから察するに、魔族にも同族間のコミュニティや、ギルドのような繋がりが存在するようだ。そして『魔術師退治』――魔族にとって危険な魔術師は、ブラックリストのようなものに載り、共有されているのかもしれない。
恐らく、レヴィが下級魔族を狩りすぎたせいで、ベヘモットのような――高位魔族にまで話が広がったのだろう。
レヴィは理解すると同時に、僅かな絶望も感じた。組織立った魔族のネットワーク。そんなものがあるとするなら、個人で対抗するにはあまりに強大すぎる。
「どうやって仕留めたんです?」
ジズが興味深そうに尋ねる。ペストマスクを傾け、まるで医者が珍しい症例を見聞きするように。
ベヘモットは得意げに答えた。
「結界の中――衝撃波で、耳の奥を揺らして気絶させた」
「ほう?」
「この前、君が聞かせてくれた――人間の身体の仕組みを利用したの。身体に傷は残したくなかったし」
ベヘモットの声音には、確かな所有欲が滲んでいた。まるで、大切なコレクションの扱いに神経を尖らせる蒐集家のようだ。
「なるほど。貴方ならそういった芸当も可能ですか。私ならどう攻略しましたかね……?
咄嗟に取れる戦法となると――」
魔族2人の無神経な会話を浴びせられ、レヴィも身を固くする。
「ああ、そう怯えないで下さい」
ジズはすかさず両手を開き、宥めるようなジェスチャーをする。
「なかなか厄介な……コホン、腕の立つ魔術師だったとの噂で。今後の戦いの参考に、ですよ。
私も自分の身くらいは守りたいですから。
……できるだけ?穏便な対処法があるなら?
備えておくに越したことはありません」
レヴィは無言で睨み返す。魔族が人間を捕らえる手口。それが分かったところで、この足で直接学会まで報告しに行けないのが歯がゆい。
「めでたく友人の眷属に下られた身なら……手出しはしませんってば」
レヴィからすれば、全くめでたくはない。高位魔族の玩具にされ、さらに別の魔族からは、人間相手の戦法の研究材料として扱われているのだから。
『敵対する魔術師を生け捕りにした』という妙な成功体験を与えてしまった気がして――悔しさのあまり、静かな溜息が漏れた。
「なんだか、レヴィも余所行きの態度で可愛いね」
ベヘモットが軽妙に割って入る。
「僕と2人きりの時もそのくらい、しおらしくしてて欲しいなー……」
しおらしいというよりは、魔族2人を前にしての警戒からくる疲弊である。
「おや、貴女様もウンザリされてますか」
ジズがマスクを傾け、語りかけてくる。同情するような、しかしどこか楽しんでいるような声音。
「この男の煩い顔に」
「うるさい……?」
ベヘモットが、形のいい眉をぴくりと寄せた。
ジズは芝居がかった動作で、ヒソヒソ話でもするかのようにマスクの頬へ手を添えて囁く。
「煩いでしょう?キラッキラ」
レヴィは再びベヘモットに目を向け、その姿を確認する。
応接間のシャンデリアの光を浴び、混じりけのない金髪が眩しく輝いている。シトリンを嵌め込んだような瞳に、染みひとつない滑らかな肌、過度に整った左右対称な顔。
人間というより、むしろ精巧に作られた人形に近い――美しさを超えて、どこか不気味ささえ感じさせる姿だった。
「いくら擬態に自信があるとはいえ……」
ジズは呆れたように溜息をつく。
「無っ駄に目立つんですよ、隠密に狩りなんてする気がないんですかねぇ……?」
確かに――魔族が人間社会に紛れ込む際、目立たないことは重要なはずだ。しかしベヘモットは、むしろ注目を集めたがっているかのような外見をしている。
「君も目立つよ、その鳥頭」
ベヘモットはジズのペストマスクを顎で指し、言い返す。近頃の医者としては珍しくない格好だが、街中を歩けば、それなりに目を引く姿だ。
例えるなら、警官を見かけたときの緊張感のように。本人に怪しさが一切なくても――どこか不穏な事件の予感が、彼の背後から漂ってくる。
「これは目立つから良いのです」
ジズは自信に満ちた声で答える。
「人間のほうから、ご親切に……弱った仲間の居場所を教えに来て下さるのですから。
特に、孤独な病人は最高ですねぇ!」
ジズの声に、陶酔めいた響きが混じる。レヴィは背筋に冷たいものが走るのを感じた。
「突然フッと消えても誰も気にしません……むしろ埋葬の手間が省けたと。周りは密かに喜ぶ」
冷酷な言葉。静かに自身の命が狙われていると悟ったとして。その犯人は医者だなどと――周囲に話したところで、信じてもらえるだろうか?
病床に臥せっていれば、逃げることすら難しい。まさに高位魔族らしい、狡猾な狩りのスタイルだ。
「ここまでコスパの良い擬態はそうそうありませんよ」
得意げに胸を張るジズへ、ベヘモットが軽口を飛ばす。
「ハゲタカ~……」
死肉を漁る鳥の名。確かに、弱った人間を狙うという点では、言い得て妙かもしれない。
ジズも負けじと言い返す。
「いいじゃないですか、この女誑し」
ベヘモットは慌てたように、弁解する。
「たらしてない。
女の子が勝手に寄って来ちゃうだけ」
ジズがレヴィへ向き直り、まるで証人を求めるかのようにひそひそと囁いてくる。
「聞きましたか?典型的な女の敵ですよ」
芝居がかった告発。しかし、その裏には本音も混じっているような気がした。
ベヘモットは更に弁解を重ねる。身を乗り出し、どこか必死さすら感じられる声音で。
「やめてよ、レヴィが誤解するでしょ」
ベヘモットはむすっと口をとがらせ、心外だと言いたげに腕を組む。
「僕は綺麗に遊んでるよ?
飽きたらきちんとお別れしてるもん!」
あまり言い訳にならない反論。むしろ軽薄さを正当化するかのようだ。
「……それで?
人間の若い女を狩るのに有利だから、貴様もそんな面妖な姿に擬態しているのか?」
レヴィは呆れた眼差しで尋ねる。
「まぁ、そりゃ……生きてくためだし。
狩りもしてたけど……
むしろ、そういう女の子に近寄ってくる、不埒な輩を退治してたの!」
最後は、まるで正義の味方のような口調。
ジズも呆れたようにマスクを振る。
「効率は良さそうですねー……」
皮肉たっぷりの相槌。
「色恋の恨みというのは、酒以上に……人間から冷静さを奪う劇薬ですからねぇ。
伝説に消えた勇者御一行だって、案外そんな平和な理由で瓦解した――なんて噂もあるくらいですし?」
なるほど、とレヴィは理解した。美しい餌で獲物を集め、まとめて狩る。実に魔族らしい、効率的で冷酷な手法だ。
レヴィは怪訝に言う。
「新手の美人局か……?」
「むしろ美人局の……元締めの組織ごと刈り取る男ですねぇ」
ジズはやれやれと肩を竦めて言う。
「逆に治安を改善します」
確かに、ある意味では治安改善かもしれない。悪党が消えるという点では。しかし、それを食料として狩る魔族がいるというのは、別の恐怖だった。
ベヘモットは開き直ったように寛いでいる。ソファに深く腰掛け、キョトンとした表情で言い放つ。
「何が悪いの?」
良くも悪くも……巧妙に世俗に紛れ、人間を振り回しているらしい魔族たち。
片や、まるで銀幕から抜け出してきたかのような優男。その隣には、天使の如き翼を隠し持つ医者。
だが――彼らが語るのは、狡猾な人間狩りの手法ばかり。
どうか悪い夢であってくれ――と。
さほど信心深くないレヴィでさえ、思わず神へと祈りたくなった。
「可愛いがってるのは同じだよ?」
ベヘモットは、レヴィから手付かずのままのケーキ皿をそっと預かり、テーブルへ戻した。そしてソファにいた彼女を軽々と持ち上げると、自分の膝の上に乗せる。
「ふふーっ♡」
ベヘモットはレヴィを腕の中に囲うと、満面の笑みを浮かべた。彼女の細い肩に鼻先を寄せ、流れる黒髪にキスをする。
「うう~……」
ベヘモットの膝の上、精悍な腕の囲いの中で――レヴィは心底居心地悪そうに唸った。浅く座り、腰を浮かせ、身を仰け反らせ。なんとかベヘモットから距離を置こうとする。まるで檻に閉じ込められた小動物のように、逃げ場を探す仕草。
「ククッ……、
貴方、全ッ然懐かれてないじゃないですか」
そんな2人の様子を見て、ジズが堪えきれずに吹き出した。ペストマスクの奥で、愉快そうな笑い声が響く。
「まだ慣れてないだけだもん!これから仲良くなるよ!
ねっ」
「……」
レヴィは黙り込み、ベヘモットの膝の上で、向かい合うように身を丸めた。互いの顔が少し近くなる。
「わっ♡
なぁにーレヴィにゃん?ご主人様と遊ぶ?」
ベヘモットはレヴィを見つめ、嬉しそうに猫撫で声を出す。レヴィも、軽く身を寄せ、微笑んで見つめ返す――フリをして。
ひょい、と。
曲げた膝をバネにして立ち上がり、ベヘモットの腕から素早く抜け出した。そのまま背もたれごと飛び越え――ソファの裏へと、鮮やかに着地する。
「あーっ!」
完全に油断していたのか、ベヘモットの手は遅れて宙を掴む。
監禁されてからの数日間、レヴィは自分に掛けられた拘束術の性質を探っていた。
ベヘモットの至近距離に居れば、多少動けることは確認済み。背後に回り込めば、撹乱できるかもしれない――そう踏んでの実験的な行動。
魔術師ゆえ肉弾戦は苦手だが、小手先の回避術くらいは身体が覚えている。
「おやっ、脱出成功ですねぇ~」
その身のこなしを見て、ジズが面白そうに拍手を送る。まるで演目を終えたサーカスの動物へ、称賛を贈るような態度だ。
「もーレヴィひどい!なんで逃げるのー?」
ベヘモットは振り返ると、背後のレヴィへ恨めしそうな視線を向ける。
「気難しい動物を手乗りにするには……幼い頃から慣らし、訓練する必要がありますからねぇ。人間も、似たようなものではないですか?」
「そんなぁ!子供を攫ってこいってこと?
僕、飼うならレヴィがいいのに……」
ベヘモットは残念そうな顔をする。流石の魔族でも、時を遡ることはできないらしい。
「……しっかし、貴方の性癖も変わりませんね。
こういう、お高くとまっておられる……生意気な小娘?お好きですよねぇ、昔から」
レヴィは、その言葉を聞いて苦々しく思う。貴様ら魔族の方が、余程尊大だろと。
「珍しく仕事熱心だったのも納得です。
余程この獲物が欲しかったんですね、コココ……」
ジズは肩を揺らして笑った。まるで気の知れた友人の趣味を茶化すかのような軽さだ。ペストマスクの奥から、鶏じみた笑い声が響く。
ベヘモットは肩を竦める。レヴィの温もりが残る膝をゆるりと組み直し、少し照れくさそうに言う。
「別にいいじゃん。僕がこの子を退治……もとい、優しく保護したおかげで。あの辺の下級魔族達も、落ち着いて暮らせるようになったでしょ」
手持ち無沙汰にワイングラスを回しながら、ベヘモットは言い訳のように続ける。グラスの中で液体がゆるやかに渦を巻き、血のような赤が妖しく揺れた。
「あのまま放置して、議会の風向きが変わっても怠いし。それに『討伐対象の人間』を引き込めた『前例』になれば……今後の僕の発言にも、説得力が出るかなーって」
議会。ベヘモットの口ぶりから察するに、魔族にも同族間のコミュニティや、ギルドのような繋がりが存在するようだ。そして『魔術師退治』――魔族にとって危険な魔術師は、ブラックリストのようなものに載り、共有されているのかもしれない。
恐らく、レヴィが下級魔族を狩りすぎたせいで、ベヘモットのような――高位魔族にまで話が広がったのだろう。
レヴィは理解すると同時に、僅かな絶望も感じた。組織立った魔族のネットワーク。そんなものがあるとするなら、個人で対抗するにはあまりに強大すぎる。
「どうやって仕留めたんです?」
ジズが興味深そうに尋ねる。ペストマスクを傾け、まるで医者が珍しい症例を見聞きするように。
ベヘモットは得意げに答えた。
「結界の中――衝撃波で、耳の奥を揺らして気絶させた」
「ほう?」
「この前、君が聞かせてくれた――人間の身体の仕組みを利用したの。身体に傷は残したくなかったし」
ベヘモットの声音には、確かな所有欲が滲んでいた。まるで、大切なコレクションの扱いに神経を尖らせる蒐集家のようだ。
「なるほど。貴方ならそういった芸当も可能ですか。私ならどう攻略しましたかね……?
咄嗟に取れる戦法となると――」
魔族2人の無神経な会話を浴びせられ、レヴィも身を固くする。
「ああ、そう怯えないで下さい」
ジズはすかさず両手を開き、宥めるようなジェスチャーをする。
「なかなか厄介な……コホン、腕の立つ魔術師だったとの噂で。今後の戦いの参考に、ですよ。
私も自分の身くらいは守りたいですから。
……できるだけ?穏便な対処法があるなら?
備えておくに越したことはありません」
レヴィは無言で睨み返す。魔族が人間を捕らえる手口。それが分かったところで、この足で直接学会まで報告しに行けないのが歯がゆい。
「めでたく友人の眷属に下られた身なら……手出しはしませんってば」
レヴィからすれば、全くめでたくはない。高位魔族の玩具にされ、さらに別の魔族からは、人間相手の戦法の研究材料として扱われているのだから。
『敵対する魔術師を生け捕りにした』という妙な成功体験を与えてしまった気がして――悔しさのあまり、静かな溜息が漏れた。
「なんだか、レヴィも余所行きの態度で可愛いね」
ベヘモットが軽妙に割って入る。
「僕と2人きりの時もそのくらい、しおらしくしてて欲しいなー……」
しおらしいというよりは、魔族2人を前にしての警戒からくる疲弊である。
「おや、貴女様もウンザリされてますか」
ジズがマスクを傾け、語りかけてくる。同情するような、しかしどこか楽しんでいるような声音。
「この男の煩い顔に」
「うるさい……?」
ベヘモットが、形のいい眉をぴくりと寄せた。
ジズは芝居がかった動作で、ヒソヒソ話でもするかのようにマスクの頬へ手を添えて囁く。
「煩いでしょう?キラッキラ」
レヴィは再びベヘモットに目を向け、その姿を確認する。
応接間のシャンデリアの光を浴び、混じりけのない金髪が眩しく輝いている。シトリンを嵌め込んだような瞳に、染みひとつない滑らかな肌、過度に整った左右対称な顔。
人間というより、むしろ精巧に作られた人形に近い――美しさを超えて、どこか不気味ささえ感じさせる姿だった。
「いくら擬態に自信があるとはいえ……」
ジズは呆れたように溜息をつく。
「無っ駄に目立つんですよ、隠密に狩りなんてする気がないんですかねぇ……?」
確かに――魔族が人間社会に紛れ込む際、目立たないことは重要なはずだ。しかしベヘモットは、むしろ注目を集めたがっているかのような外見をしている。
「君も目立つよ、その鳥頭」
ベヘモットはジズのペストマスクを顎で指し、言い返す。近頃の医者としては珍しくない格好だが、街中を歩けば、それなりに目を引く姿だ。
例えるなら、警官を見かけたときの緊張感のように。本人に怪しさが一切なくても――どこか不穏な事件の予感が、彼の背後から漂ってくる。
「これは目立つから良いのです」
ジズは自信に満ちた声で答える。
「人間のほうから、ご親切に……弱った仲間の居場所を教えに来て下さるのですから。
特に、孤独な病人は最高ですねぇ!」
ジズの声に、陶酔めいた響きが混じる。レヴィは背筋に冷たいものが走るのを感じた。
「突然フッと消えても誰も気にしません……むしろ埋葬の手間が省けたと。周りは密かに喜ぶ」
冷酷な言葉。静かに自身の命が狙われていると悟ったとして。その犯人は医者だなどと――周囲に話したところで、信じてもらえるだろうか?
病床に臥せっていれば、逃げることすら難しい。まさに高位魔族らしい、狡猾な狩りのスタイルだ。
「ここまでコスパの良い擬態はそうそうありませんよ」
得意げに胸を張るジズへ、ベヘモットが軽口を飛ばす。
「ハゲタカ~……」
死肉を漁る鳥の名。確かに、弱った人間を狙うという点では、言い得て妙かもしれない。
ジズも負けじと言い返す。
「いいじゃないですか、この女誑し」
ベヘモットは慌てたように、弁解する。
「たらしてない。
女の子が勝手に寄って来ちゃうだけ」
ジズがレヴィへ向き直り、まるで証人を求めるかのようにひそひそと囁いてくる。
「聞きましたか?典型的な女の敵ですよ」
芝居がかった告発。しかし、その裏には本音も混じっているような気がした。
ベヘモットは更に弁解を重ねる。身を乗り出し、どこか必死さすら感じられる声音で。
「やめてよ、レヴィが誤解するでしょ」
ベヘモットはむすっと口をとがらせ、心外だと言いたげに腕を組む。
「僕は綺麗に遊んでるよ?
飽きたらきちんとお別れしてるもん!」
あまり言い訳にならない反論。むしろ軽薄さを正当化するかのようだ。
「……それで?
人間の若い女を狩るのに有利だから、貴様もそんな面妖な姿に擬態しているのか?」
レヴィは呆れた眼差しで尋ねる。
「まぁ、そりゃ……生きてくためだし。
狩りもしてたけど……
むしろ、そういう女の子に近寄ってくる、不埒な輩を退治してたの!」
最後は、まるで正義の味方のような口調。
ジズも呆れたようにマスクを振る。
「効率は良さそうですねー……」
皮肉たっぷりの相槌。
「色恋の恨みというのは、酒以上に……人間から冷静さを奪う劇薬ですからねぇ。
伝説に消えた勇者御一行だって、案外そんな平和な理由で瓦解した――なんて噂もあるくらいですし?」
なるほど、とレヴィは理解した。美しい餌で獲物を集め、まとめて狩る。実に魔族らしい、効率的で冷酷な手法だ。
レヴィは怪訝に言う。
「新手の美人局か……?」
「むしろ美人局の……元締めの組織ごと刈り取る男ですねぇ」
ジズはやれやれと肩を竦めて言う。
「逆に治安を改善します」
確かに、ある意味では治安改善かもしれない。悪党が消えるという点では。しかし、それを食料として狩る魔族がいるというのは、別の恐怖だった。
ベヘモットは開き直ったように寛いでいる。ソファに深く腰掛け、キョトンとした表情で言い放つ。
「何が悪いの?」
良くも悪くも……巧妙に世俗に紛れ、人間を振り回しているらしい魔族たち。
片や、まるで銀幕から抜け出してきたかのような優男。その隣には、天使の如き翼を隠し持つ医者。
だが――彼らが語るのは、狡猾な人間狩りの手法ばかり。
どうか悪い夢であってくれ――と。
さほど信心深くないレヴィでさえ、思わず神へと祈りたくなった。
0
あなたにおすすめの小説
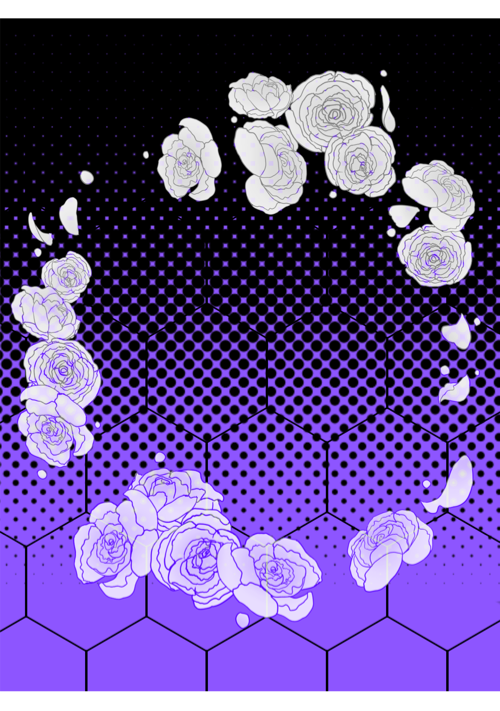
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?

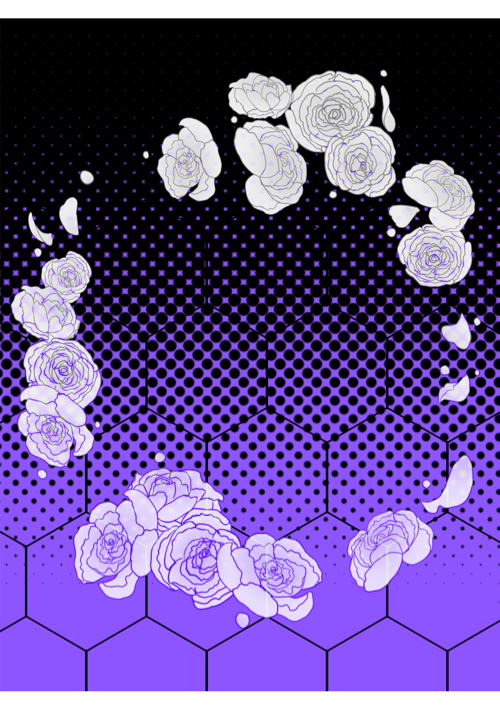


ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。


転生したら4人のヤンデレ彼氏に溺愛される日々が待っていた。
aika
恋愛
主人公まゆは冴えないOL。
ある日ちょっとした事故で命を落とし転生したら・・・
4人のイケメン俳優たちと同棲するという神展開が待っていた。
それぞれタイプの違うイケメンたちに囲まれながら、
生活することになったまゆだが、彼らはまゆを溺愛するあまり
どんどんヤンデレ男になっていき・・・・
ヤンデレ、溺愛、執着、取り合い・・・♡
何でもありのドタバタ恋愛逆ハーレムコメディです。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















