あなたにおすすめの小説
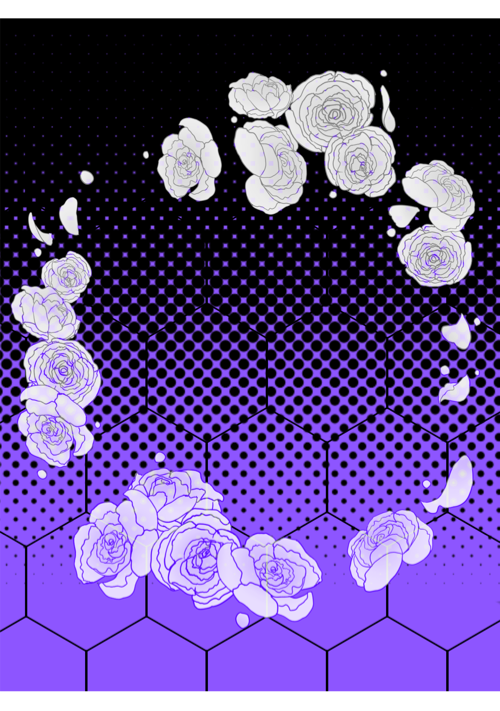
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?


転生したら4人のヤンデレ彼氏に溺愛される日々が待っていた。
aika
恋愛
主人公まゆは冴えないOL。
ある日ちょっとした事故で命を落とし転生したら・・・
4人のイケメン俳優たちと同棲するという神展開が待っていた。
それぞれタイプの違うイケメンたちに囲まれながら、
生活することになったまゆだが、彼らはまゆを溺愛するあまり
どんどんヤンデレ男になっていき・・・・
ヤンデレ、溺愛、執着、取り合い・・・♡
何でもありのドタバタ恋愛逆ハーレムコメディです。
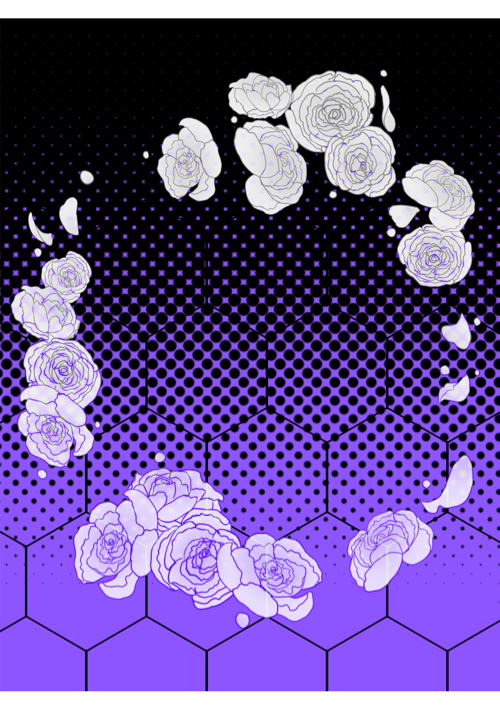



ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















