10 / 11
第10話 もっと撫でて
しおりを挟む
夕暮れの光が、応接間のカーテンをほんのりと染めている。
レヴィは鏡の前に立ち、着替えを済ませた自分の姿を確認する。金色のベルベットドレス。胸元には控えめなレースがあしらわれ、袖も手首まできちんと覆われている。裾も足首近くまで届く、型自体は慎ましやかなデザインだった。
(ベヘモットにしては、まともなセレクトだな)
内心で呟きながら、生地の感触を確かめる。重厚かつ滑らか。悪くない手触りだ。金色という派手な色合いはさておき、上質な一着と言えるだろう。
先ほどまで(無理矢理)着せられていた、透けた布地のベビードールに比べれば……心理的抵抗感も物理的防御力も、雲泥の差がある。
「うーん、やっぱりレヴィはそういう色が似合うよ~」
背後から、満足げなベヘモットの声が聞こえる。
「この黒髪との対比が最高!」
金色の瞳が愛おしげに細められる。まるで、お気に入りの美術品にぴったりな額縁を見つけた、蒐集家のような態度だった。
「……また客か?」
レヴィは、話題を変えるように尋ねる。
前回の経験から、極端な服装の変化には理由があることを学んでいた。妖艷な踊り子の衣装から……シックなワンピースに着替えさせられた時も、ジズの訪問があった。
「さすがレヴィにゃん。察しがいいね。
アイツ、お酒飲みたい時はここに来るんだよ。魔族の棲家なら――擬態が緩んでも問題ないし。
ジズはお医者さんしてて、人間や街のことにも詳しいからさ。僕も、情報料がわりにワインを奢ってるってわけ」
ベヘモットはそう語るが、その声音には……取引相手へというよりは、やはり長年の友人へ対する親しみが込められていた。
「魔族も酒で酔っ払うのか?……擬態が緩むくらいに?」
レヴィは、僅かな期待を込めて聞く。もしそうなら、出し抜くチャンスになりうる。彼らが酒盛りをして、油断している隙に――
しかし。
「んふふー、大丈夫だよレヴィ!
僕は酔っててもちゃーんと格好いいから」
ベヘモットは、ドヤ顔で全く参考にならない返答をしてきた。
「そういう事を聞いているのではなーい!」
ふざけた答えに、レヴィも眉をきゅっと寄せて苛立ちを示す。ベヘモットは、そんなレヴィを抱きしめて頬ずりをする。
「レヴィも酔っぱらったら、僕にめろめろしてくれる?」
ベヘモットは、にまにまとレヴィを見つめて囁く。何かよからぬ事を考えているのは明白だ。
「……しない。必要のない酒は飲まん、飲みすぎると頭痛がするから嫌いだ」
レヴィは冷たく答える。仕事に差し支えるのを嫌うため、ポーションの類に属する薬用酒しか飲まない主義だった。
探索中にどうしても清潔な飲み水が確保できない時など、必要に迫られた場合は別だが。そうでなければ、自ら進んで酒を煽ることはない。
「むーっ、つまんない~……。
人間用のマタタビとか、ないのかなぁ」
ベヘモットは残念そうだ。どうにかしてレヴィの気を引きたいらしい。手懐けるための小道具として、反応の良い食べ物や酒、薬などをチラチラと探っている様子が伺えた。
ベヘモットがうんうん唸っていると……規則正しく、ドアをノックする音が響く。
「あっ、入っていいよー」
彼が気楽に返事をすると、扉がゆっくりと開いた。
現れたのは、やはりジズだった。
今日の装いは、前回よりも更に格式張っている。クラシックな紳士風の三つ揃えスーツに、絹のネクタイ、シルクハット。
しかし――頭には、相変わらずのペストマスク。
そして背中には、巨大な翼が行儀良く畳まれていた。魔族の翼とは思えないほどの純白で、どこか神々しささえ感じさせる二対の翼。
「ごきげんよう」
ジズは恭しく一礼する。シルクハットを軽く持ち上げる仕草が、芝居めいている。
赤いレンズが、部屋の中を見回す。そしてレヴィの姿を認めると、僅かに首を傾げた。
「おやっ、レヴィ嬢も。今日も素敵なお召し物で」
慇懃な口調。しかし、その裏には皮肉も混じっているような気がした。
「今日は早かったんだねぇ」
「ええまぁ、ゲートを少々近場に移しまして。これでゆっくり酒が飲めます」
ジズは優雅に部屋に入り、定位置のソファに腰を下ろす。背もたれを避けるように、翼が僅かに横へ広げられる。
「しかし……相変わらず、趣味の悪い部屋ですねぇ。私の院の待合室より混んでません?」
ジズが早々に軽口を叩く。ペストマスクを左右に振り、大理石の彫刻群を眺める。壁際にずらりと並べられた彫刻の群れは、なかなか異様な光景だ。
「失礼な~」
ベヘモットが反論するが、その声に怒りはない。むしろ楽しんでいるような響きがあった。
「これは芸術だよ、芸術っ!
僕はパトロンとして、人間の文化の発展を陰ながら支えてるの!」
ベヘモットは腕を組み、誇らしげに言う。
「はぁ、ですが……この彫刻の作者の方、人間であれば――とっくに亡くなってますよ?」
だがジズは、彫刻を眺めて首を傾げる。確かに保存状態は良いものの、かなり古い様式の作品だった。台座に掘られた制作年からも察するに、作者本人はおろか、その弟子や孫すら死んでいてもおかしくない。
「それでもー!ちゃんとコレクターの存在感を示すのが重要なの!高値がついたって噂が広まれば、他の作品も市場に出てきやすくなるし。
お弟子さんが頑張ってくれれば、似た様式が再流行するかもしれないし……っ!」
ベヘモットは必死に熱弁する。
「なるほど……生きているうちに出会いたかった、というやつですねぇ」
「本当だよぉ~……作品を管理してる人達まで、すーぐ死んじゃうしさ。所在を追いかけるのが大変!」
ソファにもたれ、肩を落とす。長命種の魔族として、人間の命のサイクルの短さを痛感している様子だ。
「ああ、そうでしたレヴィ嬢。
今日の分のお土産です」
するとジズが思い出したように、医療鞄を漁る。硬そうな鞄の口から、手品の如く差し出されたのは……やはり花束だった。
前回とは違う花々で構成されている。白いチューリップに、薄紫のスイートピー。さりげなくスミレの花も添えられており、柔らかく静謐な印象のブーケだった。
「む……う、ありがとう」
レヴィは礼儀として受け取り、ぎこちなく礼を言う。
花の香りが鼻腔をくすぐり、束の間の安らぎを与えてくれる。その自然な匂いは、生花から発せられる天然のものだ。
ベヘモットは魔力を持て余しているのか、ひしめく美術品やインテリアにも何らかの術を掛けている。そんな彼の巣の中では、こうした『ごく普通のもの』は貴重であった。
「お前も意外にマメだよなー」
ベヘモットが横から口を挟む。金色の瞳に、からかうような光が宿っていた。
ジズは肩を竦める。その動きに合わせて、翼も僅かに動いた。
「マメでないと、医者なんて務まりませんよ」
「ヤブのくせにー」
即座の反撃。しかし、その声には親しみが滲んでいる。
ジズの肩がクックッと震えた。ペストマスクの下から、抑えた笑い声が漏れる。
「ホホホ、その辺のヤブ医者よりは……人間のお身体には詳しいですよ?」
不穏な自慢。魔族として人間を「診察」してきた経験は、並の医者の比ではないのだろう。
レヴィは花束を膝に抱えたまま、二人の魔族の世間話に耳を傾けた。
「そういえば、北から疫病が入ってきているという噂を聞きましたね……」
「えっ、まさか――」
ベヘモットが怪訝な顔をし、やんわりと腰を浮かせた。
「幸い、ペスト程ではないようですが。致死性は低いとはいえ――幼児や身体の弱った方には、十分脅威となりうる話でしょうねぇ」
ジズはマスクの顎を掻きつつ、真面目な声音で語る。
「それ……大丈夫なの?また、あの時みたいにさ……」
「コココ、むしろこれは――我々にとってチャンスですよ!」
不安げなベヘモットに反し……ジズは立ち上がると、企んだような笑い声を響かせる。
「ここで、聖職者達より先に――事態を終息させられれば!我々医師の株が上がり、逆に奴らを陳腐化させられるというもの……!いや~腕が鳴りますねぇ!」
「相変わらず聖職者アンチしてるな~」
ベヘモットは呆れた目でジズを見る。
「何百年経とうと、私は忘れませんよ。
あの日奴らに着せられた濡れ衣……キッチリ仕立て直して、買い戻させてやりますとも!」
ジズは恨めしそうに宣言すると、脚を組んでソファに座り直した。猛禽の如き翼が、どこか虚空を威嚇するように横に広げられている。
その大きな動きに巻き込まれるように――羽の先端が、レヴィの頬をふわりと掠めた。
柔らかい。
思わず、レヴィは息を呑んだ。綿毛のような……いや、それ以上に滑らかな感触。そして何より、懐かしい感覚が蘇る。
(カナリアの羽に……似ている)
かつて飼っていた金色の小鳥。その小さな羽を撫でた時の感触が、記憶の底から浮かび上がってきた。大きさは全く違うが、羽毛特有の柔らかさは同じだった。
ジズは会話に夢中で、レヴィに羽が触れたことに気づいていないようだった。ベヘモットと魔族らしい世間話を続けている。
レヴィは誘惑に勝てなかった。
隣のソファのひじ掛けへ――そっと手を伸ばし、指先でジズの翼に触れてみる。
大きくて、真っ白で、ふわふわだった。羽先はすべすべと滑らかで、根元にはぽぁぽぁとした柔らかな羽毛が密生している。
レヴィは思わず見入ってしまう。普段、これほど大型の鳥類の翼を間近で観察する機会などない。
(何の鳥だろう?)
鳥の翼を持つ魔族だからといって、鳥である確証もないが……。単なる擬態の一部かもしれない。しかしその感触は、本物の羽毛と遜色ない心地よさだった。
レヴィはつい夢中になって、羽を撫でていた。かつてカナリアにしていたように、優しく、丁寧に。羽の流れに沿って指を滑らせる。懐かしい感覚に、心が僅かに和らいだ。
「……おや、レヴィ嬢?」
突然、ジズが振り返った。
レヴィは慌てて手を引っ込める。
「うっ」
バツの悪い顔をする。まるで悪戯を見つかった子供のような表情。
「退屈されていますか?これは失敬」
しかし、ジズの声に怒りはなかった。むしろ、友人宅のペットにじゃれつかれて満更でもない、といった風情。
「別に……」
レヴィはそっぽを向く。
「わ、悪かったな……勝手に触って」
プライドが邪魔をし、素っ気ない言葉しか出てこない。
ジズは愉快そうに笑った。
「お好きにどうぞ?減るものでもなし」
鷹揚な態度。ペストマスクを僅かに傾け、レヴィを見る。
「触り心地はいかがです?」
まるで、自慢の品を褒められて嬉しい職人のような口調だった。
横からベヘモットが口を挟む。
「へぇー。レヴィ、ダウン素材好きなの?」
急に興味を示したような声。
「寝具変えてあげようか?」
まるで、ペットの新しい巣材を検討するような調子。レヴィは呆れたが、ベヘモットの思考回路は常にこんな調子だった。
「いいですねぇ~」
ジズも呑気な相槌を打つ。特に、鳥が寝具に使われることへの忌避感は無いようだった。鳥に同族意識を持っているかは怪しいが、少なくとも気にしてはいないらしい。
ふと、レヴィの視線がソファに落ちた。
白い羽が一枚、クッションの上に落ちている。ジズの翼から抜け落ちたものだろう。立派な風切羽で、羽根ペンが作れそうなほど大きい。
何となく、レヴィはそれを拾い上げた。
指先で羽をくるくる回しながら観察する。軸はしっかりとしていて、羽枝も密に生えている。なにより、この抜けるような白さ。染色しても美しく仕上がりそうな色合いだ。
(魔族由来の素材なら……)
ギルドや魔道具屋に持ち込めば、それなりの値がつくだろう。上位魔族から採取した素材となれば、希少価値もある。もっとも、ここから出られない今となっては――無意味な皮算用だが。
「レヴィ?僕のことも撫でてよー」
ベヘモットが甘えた声を出す。金色の瞳を、期待で輝かせながらレヴィを見つめてくる。
「仕方ないな……」
レヴィは呆れる。しかし、この飼い主をあまり邪険にしすぎて機嫌を損ねても面倒だ。独善的な笑顔を浮かべつつ、凶行を仕掛けてくるタイプなのだから。
仕方なく立ち上がり、ベヘモットの背中を軽く擦った。
服の上からだが、その下にある筋肉の感触が伝わってくる。人間への擬態として……顔立ちは優男に化けているが、体つきはそれなりに精悍な男性のもの。もしかすると、部屋に飾られた彫刻達の肉体を参考にしているのかもしれない。
「ね~、もうちょっとこう……
気持ちいいとこも撫でてよぉ」
レヴィの控えめな手つきに、ベヘモットは物足りなさそうに言う。
「ククッ、まるで悪酔いした患者への介抱みたいですねぇ」
ジズも冷やかすように言う。確かに、背中を擦って吐き気を宥めているようにも見える。甘い触れ合いというよりは、義務的な接触だ。
「注文の多いやつめ……」
レヴィはやれやれと思いつつ、今度は頭を撫でてみる。ベヘモットの金髪は絹のように滑らかで、指がするすると通る。だが……レヴィも、これまで大人の男の頭など撫でた経験はなく、かなり妙な感覚だ。
すると、ベヘモットは一瞬で表情を変えた。
「ふふ~っ♡」
至福の笑みを浮かべ、目を細める。褒められた大型犬のような、無防備で幸せそうな顔。デレデレという擬音が似合いそうなほど、緩みきった表情だった。
レヴィは、ふと思いつく。
(これは使えるかも……)
コイツを喜ばせるためではなく。油断させ、隙を作るための実験として。魔族にも弱点があるはずだ。それを探る良い機会かもしれない。
試しに、手をうなじの方へ下ろしていき……首筋を軽く撫でてみる。
指先が、耳の後ろから首のラインをなぞった瞬間――
「んゎっ♡」
ベヘモットが堪らなそうな声を漏らした。
甘い吐息と共に、体が僅かに震える。顔は更に蕩けたような表情になり、金色の瞳が潤んだようにも見えた。
「やだもーレヴィ……♡
こそばゆいよー、んふふ」
名前を呼ぶ声まで、普段とは違う響きを帯びている。
(なるほど、ここが弱点か……?)
レヴィは内心でメモを取る。
「人間の雄って、正直そんな手触り良くないですけどねぇ~……」
ジズが横から茶々を入れる。まるで、自分の翼の方が撫で心地が良いぞ、と言いたげな口調。
「ふふーん、なーにジズ?嫉妬ー?」
ベヘモットが余裕の声で返す。しかし、その表情は相変わらず。レヴィに喉元を撫でられ、間抜けに蕩けてている。
その時、床でキラリと何かが光った。
レヴィの視線が、反射的にそちらへ向く。撫でる手を止め、光るものを拾い上げた。
かなり大きな――鱗。
光に透かして観察する。黄金色に輝く、掌ほどの大きさの鱗だ。表面は滑らかで、まるで研磨された金属のような光沢を放っている。
大きさからしても、放たれる魔力からしても……見るからに、普通の生物の鱗ではない。
レヴィは記憶から、学会で得た魔族の知識を思い起こす。鱗を持つ魔族といえば、魚型や蛇型、鰐型の他に――…
一つの心当たりに辿り着き、はっと息を呑んだ。
(これは……まさか)
魔術師として学んだ知識が、頭の中で急速に繋がっていく。この独特の質感。そして何より、触れた瞬間に感じる強大な魔力の残滓。
幻の高級素材として知られる――『バハムートの鱗』。
最強の魔術耐性を持ち、殆どの攻撃術を弾き返すという伝説の素材。その希少性ゆえ、市場に出た記録も少ないが――……売り払えば、魔術師であるレヴィが数年は遊んで暮らせるほどの金額になるだろう。
「あ~っ……」
ベヘモットはそれを見て、面倒臭そうな声を漏らした。
「また鱗落ちてる~」
ゆるく眉を顰め、まるで自分の抜け毛を見つけた人間のような反応を見せる。
「はぁ、お掃除しなきゃ……」
気怠いベヘモットの手招きに応じ、金色のコウモリの使い魔が飛んできた。慣れた動きで屑籠を掴んで持ってくる。
レヴィの思考が、凍りついた。
「まさかこれ、お前の……?」
震える声を抑えつつ、ベヘモットを見つめる。
放蕩な道楽者にしか見えぬ優男。その正体は――
魔族の中でも『最強』と名高いドラゴン、
バハムート。
伝承によれば……一国を一夜で滅ぼすほどの力を持つとされる――強大な邪竜。その鱗は魔法を弾き返し、吐息は山を溶かし、翼の一振りで嵐を巻き起こすという。
道理で、それなりの実力を持つ魔術師であったレヴィを、いとも簡単に捕らえられたわけだ。勇者や英雄と呼ばれるような存在ならまだしも……普通の人間が、太刀打ちできる次元の存在ではなかったのだ。
「レヴィ?それ貸して。ポイするから」
ベヘモットがひらひらと掌を差し出す。屑籠の上で、使い魔も待ち構えるようにこちらを見ている。
「えっ、いや……しかし、」
だが、レヴィも流石に躊躇する。これが本物のバハムートの鱗ならば、魔術師からすれば垂涎もののお宝だ。それをみすみす廃棄するなど、勿体なさすぎる。
「――もしかして、それ欲しいの?僕の鱗だけど……」
鱗を手放さないレヴィを見て、ベヘモットがキョトンと小首を傾げる。ゆるい表情は相変わらずだが、今やそれがかえって恐ろしく見えた。
「ぐっ、その……」
ぞくぞくと湧き上がる畏怖に、レヴィの膝が静かに震えた。散々悪態をついてきた相手が――まさか、それほどに恐ろしい存在だったとは。
「ふふ……じゃあいいよ。それあげる。
怪我しないよう、気をつけて遊んでね」
ベヘモットは、少し照れくさそうに笑いながら、あっさりと許可を出す。まるで、大したものではないかのように。
「そろそろ、レヴィ用の玩具をしまう箱も必要かな~?どれにしようかなぁ~」
ベヘモットは、使い魔から百貨店のカタログを受け取ると、膝の上でぱらぱらとめくり始めた。
実際バハムート本人にとっては、自分の鱗などどうでも良いモノなのだろう。人間が伸びた爪を切るように。時折髪が抜けているように。生きていれば、肉体から自然と剥がれ落ちるものなのだから。
「……そうやって贔屓の人間へ寄越すから、たまーに魔族キラーな勇者が爆誕するんですよ」
ジズは肘をつき、迷惑そうにこぼす。
「大丈夫大丈夫」
だが、ベヘモットは気楽に答える。
「レヴィはお外に出さないから」
自分の棲家の中で飼い殺しておけば、魔族側への脅威にはならない、という意味だろう。
レヴィは鱗を見つめながら、各地で語り継がれる『勇者』の話を思い出していた。
神の加護を受け……敵の強力な呪術をも退けた、と語られる英雄たち。
その実態は、もしかすると――
ベヘモットのように物好きな魔族が、気まぐれに人間へ与えた鱗や牙を使っていただけ……なのかもしれない。崇高な神の加護などではなく、酔狂な魔族からのおこぼれ。
何という皮肉だろう。
人間が崇める勇者の力の源が、魔族の戯れに過ぎなかったなんて。
傷一つなく、完璧な輝きを放つ――巨竜の鱗。
レヴィは震える指で、それを握りしめた。
レヴィは鏡の前に立ち、着替えを済ませた自分の姿を確認する。金色のベルベットドレス。胸元には控えめなレースがあしらわれ、袖も手首まできちんと覆われている。裾も足首近くまで届く、型自体は慎ましやかなデザインだった。
(ベヘモットにしては、まともなセレクトだな)
内心で呟きながら、生地の感触を確かめる。重厚かつ滑らか。悪くない手触りだ。金色という派手な色合いはさておき、上質な一着と言えるだろう。
先ほどまで(無理矢理)着せられていた、透けた布地のベビードールに比べれば……心理的抵抗感も物理的防御力も、雲泥の差がある。
「うーん、やっぱりレヴィはそういう色が似合うよ~」
背後から、満足げなベヘモットの声が聞こえる。
「この黒髪との対比が最高!」
金色の瞳が愛おしげに細められる。まるで、お気に入りの美術品にぴったりな額縁を見つけた、蒐集家のような態度だった。
「……また客か?」
レヴィは、話題を変えるように尋ねる。
前回の経験から、極端な服装の変化には理由があることを学んでいた。妖艷な踊り子の衣装から……シックなワンピースに着替えさせられた時も、ジズの訪問があった。
「さすがレヴィにゃん。察しがいいね。
アイツ、お酒飲みたい時はここに来るんだよ。魔族の棲家なら――擬態が緩んでも問題ないし。
ジズはお医者さんしてて、人間や街のことにも詳しいからさ。僕も、情報料がわりにワインを奢ってるってわけ」
ベヘモットはそう語るが、その声音には……取引相手へというよりは、やはり長年の友人へ対する親しみが込められていた。
「魔族も酒で酔っ払うのか?……擬態が緩むくらいに?」
レヴィは、僅かな期待を込めて聞く。もしそうなら、出し抜くチャンスになりうる。彼らが酒盛りをして、油断している隙に――
しかし。
「んふふー、大丈夫だよレヴィ!
僕は酔っててもちゃーんと格好いいから」
ベヘモットは、ドヤ顔で全く参考にならない返答をしてきた。
「そういう事を聞いているのではなーい!」
ふざけた答えに、レヴィも眉をきゅっと寄せて苛立ちを示す。ベヘモットは、そんなレヴィを抱きしめて頬ずりをする。
「レヴィも酔っぱらったら、僕にめろめろしてくれる?」
ベヘモットは、にまにまとレヴィを見つめて囁く。何かよからぬ事を考えているのは明白だ。
「……しない。必要のない酒は飲まん、飲みすぎると頭痛がするから嫌いだ」
レヴィは冷たく答える。仕事に差し支えるのを嫌うため、ポーションの類に属する薬用酒しか飲まない主義だった。
探索中にどうしても清潔な飲み水が確保できない時など、必要に迫られた場合は別だが。そうでなければ、自ら進んで酒を煽ることはない。
「むーっ、つまんない~……。
人間用のマタタビとか、ないのかなぁ」
ベヘモットは残念そうだ。どうにかしてレヴィの気を引きたいらしい。手懐けるための小道具として、反応の良い食べ物や酒、薬などをチラチラと探っている様子が伺えた。
ベヘモットがうんうん唸っていると……規則正しく、ドアをノックする音が響く。
「あっ、入っていいよー」
彼が気楽に返事をすると、扉がゆっくりと開いた。
現れたのは、やはりジズだった。
今日の装いは、前回よりも更に格式張っている。クラシックな紳士風の三つ揃えスーツに、絹のネクタイ、シルクハット。
しかし――頭には、相変わらずのペストマスク。
そして背中には、巨大な翼が行儀良く畳まれていた。魔族の翼とは思えないほどの純白で、どこか神々しささえ感じさせる二対の翼。
「ごきげんよう」
ジズは恭しく一礼する。シルクハットを軽く持ち上げる仕草が、芝居めいている。
赤いレンズが、部屋の中を見回す。そしてレヴィの姿を認めると、僅かに首を傾げた。
「おやっ、レヴィ嬢も。今日も素敵なお召し物で」
慇懃な口調。しかし、その裏には皮肉も混じっているような気がした。
「今日は早かったんだねぇ」
「ええまぁ、ゲートを少々近場に移しまして。これでゆっくり酒が飲めます」
ジズは優雅に部屋に入り、定位置のソファに腰を下ろす。背もたれを避けるように、翼が僅かに横へ広げられる。
「しかし……相変わらず、趣味の悪い部屋ですねぇ。私の院の待合室より混んでません?」
ジズが早々に軽口を叩く。ペストマスクを左右に振り、大理石の彫刻群を眺める。壁際にずらりと並べられた彫刻の群れは、なかなか異様な光景だ。
「失礼な~」
ベヘモットが反論するが、その声に怒りはない。むしろ楽しんでいるような響きがあった。
「これは芸術だよ、芸術っ!
僕はパトロンとして、人間の文化の発展を陰ながら支えてるの!」
ベヘモットは腕を組み、誇らしげに言う。
「はぁ、ですが……この彫刻の作者の方、人間であれば――とっくに亡くなってますよ?」
だがジズは、彫刻を眺めて首を傾げる。確かに保存状態は良いものの、かなり古い様式の作品だった。台座に掘られた制作年からも察するに、作者本人はおろか、その弟子や孫すら死んでいてもおかしくない。
「それでもー!ちゃんとコレクターの存在感を示すのが重要なの!高値がついたって噂が広まれば、他の作品も市場に出てきやすくなるし。
お弟子さんが頑張ってくれれば、似た様式が再流行するかもしれないし……っ!」
ベヘモットは必死に熱弁する。
「なるほど……生きているうちに出会いたかった、というやつですねぇ」
「本当だよぉ~……作品を管理してる人達まで、すーぐ死んじゃうしさ。所在を追いかけるのが大変!」
ソファにもたれ、肩を落とす。長命種の魔族として、人間の命のサイクルの短さを痛感している様子だ。
「ああ、そうでしたレヴィ嬢。
今日の分のお土産です」
するとジズが思い出したように、医療鞄を漁る。硬そうな鞄の口から、手品の如く差し出されたのは……やはり花束だった。
前回とは違う花々で構成されている。白いチューリップに、薄紫のスイートピー。さりげなくスミレの花も添えられており、柔らかく静謐な印象のブーケだった。
「む……う、ありがとう」
レヴィは礼儀として受け取り、ぎこちなく礼を言う。
花の香りが鼻腔をくすぐり、束の間の安らぎを与えてくれる。その自然な匂いは、生花から発せられる天然のものだ。
ベヘモットは魔力を持て余しているのか、ひしめく美術品やインテリアにも何らかの術を掛けている。そんな彼の巣の中では、こうした『ごく普通のもの』は貴重であった。
「お前も意外にマメだよなー」
ベヘモットが横から口を挟む。金色の瞳に、からかうような光が宿っていた。
ジズは肩を竦める。その動きに合わせて、翼も僅かに動いた。
「マメでないと、医者なんて務まりませんよ」
「ヤブのくせにー」
即座の反撃。しかし、その声には親しみが滲んでいる。
ジズの肩がクックッと震えた。ペストマスクの下から、抑えた笑い声が漏れる。
「ホホホ、その辺のヤブ医者よりは……人間のお身体には詳しいですよ?」
不穏な自慢。魔族として人間を「診察」してきた経験は、並の医者の比ではないのだろう。
レヴィは花束を膝に抱えたまま、二人の魔族の世間話に耳を傾けた。
「そういえば、北から疫病が入ってきているという噂を聞きましたね……」
「えっ、まさか――」
ベヘモットが怪訝な顔をし、やんわりと腰を浮かせた。
「幸い、ペスト程ではないようですが。致死性は低いとはいえ――幼児や身体の弱った方には、十分脅威となりうる話でしょうねぇ」
ジズはマスクの顎を掻きつつ、真面目な声音で語る。
「それ……大丈夫なの?また、あの時みたいにさ……」
「コココ、むしろこれは――我々にとってチャンスですよ!」
不安げなベヘモットに反し……ジズは立ち上がると、企んだような笑い声を響かせる。
「ここで、聖職者達より先に――事態を終息させられれば!我々医師の株が上がり、逆に奴らを陳腐化させられるというもの……!いや~腕が鳴りますねぇ!」
「相変わらず聖職者アンチしてるな~」
ベヘモットは呆れた目でジズを見る。
「何百年経とうと、私は忘れませんよ。
あの日奴らに着せられた濡れ衣……キッチリ仕立て直して、買い戻させてやりますとも!」
ジズは恨めしそうに宣言すると、脚を組んでソファに座り直した。猛禽の如き翼が、どこか虚空を威嚇するように横に広げられている。
その大きな動きに巻き込まれるように――羽の先端が、レヴィの頬をふわりと掠めた。
柔らかい。
思わず、レヴィは息を呑んだ。綿毛のような……いや、それ以上に滑らかな感触。そして何より、懐かしい感覚が蘇る。
(カナリアの羽に……似ている)
かつて飼っていた金色の小鳥。その小さな羽を撫でた時の感触が、記憶の底から浮かび上がってきた。大きさは全く違うが、羽毛特有の柔らかさは同じだった。
ジズは会話に夢中で、レヴィに羽が触れたことに気づいていないようだった。ベヘモットと魔族らしい世間話を続けている。
レヴィは誘惑に勝てなかった。
隣のソファのひじ掛けへ――そっと手を伸ばし、指先でジズの翼に触れてみる。
大きくて、真っ白で、ふわふわだった。羽先はすべすべと滑らかで、根元にはぽぁぽぁとした柔らかな羽毛が密生している。
レヴィは思わず見入ってしまう。普段、これほど大型の鳥類の翼を間近で観察する機会などない。
(何の鳥だろう?)
鳥の翼を持つ魔族だからといって、鳥である確証もないが……。単なる擬態の一部かもしれない。しかしその感触は、本物の羽毛と遜色ない心地よさだった。
レヴィはつい夢中になって、羽を撫でていた。かつてカナリアにしていたように、優しく、丁寧に。羽の流れに沿って指を滑らせる。懐かしい感覚に、心が僅かに和らいだ。
「……おや、レヴィ嬢?」
突然、ジズが振り返った。
レヴィは慌てて手を引っ込める。
「うっ」
バツの悪い顔をする。まるで悪戯を見つかった子供のような表情。
「退屈されていますか?これは失敬」
しかし、ジズの声に怒りはなかった。むしろ、友人宅のペットにじゃれつかれて満更でもない、といった風情。
「別に……」
レヴィはそっぽを向く。
「わ、悪かったな……勝手に触って」
プライドが邪魔をし、素っ気ない言葉しか出てこない。
ジズは愉快そうに笑った。
「お好きにどうぞ?減るものでもなし」
鷹揚な態度。ペストマスクを僅かに傾け、レヴィを見る。
「触り心地はいかがです?」
まるで、自慢の品を褒められて嬉しい職人のような口調だった。
横からベヘモットが口を挟む。
「へぇー。レヴィ、ダウン素材好きなの?」
急に興味を示したような声。
「寝具変えてあげようか?」
まるで、ペットの新しい巣材を検討するような調子。レヴィは呆れたが、ベヘモットの思考回路は常にこんな調子だった。
「いいですねぇ~」
ジズも呑気な相槌を打つ。特に、鳥が寝具に使われることへの忌避感は無いようだった。鳥に同族意識を持っているかは怪しいが、少なくとも気にしてはいないらしい。
ふと、レヴィの視線がソファに落ちた。
白い羽が一枚、クッションの上に落ちている。ジズの翼から抜け落ちたものだろう。立派な風切羽で、羽根ペンが作れそうなほど大きい。
何となく、レヴィはそれを拾い上げた。
指先で羽をくるくる回しながら観察する。軸はしっかりとしていて、羽枝も密に生えている。なにより、この抜けるような白さ。染色しても美しく仕上がりそうな色合いだ。
(魔族由来の素材なら……)
ギルドや魔道具屋に持ち込めば、それなりの値がつくだろう。上位魔族から採取した素材となれば、希少価値もある。もっとも、ここから出られない今となっては――無意味な皮算用だが。
「レヴィ?僕のことも撫でてよー」
ベヘモットが甘えた声を出す。金色の瞳を、期待で輝かせながらレヴィを見つめてくる。
「仕方ないな……」
レヴィは呆れる。しかし、この飼い主をあまり邪険にしすぎて機嫌を損ねても面倒だ。独善的な笑顔を浮かべつつ、凶行を仕掛けてくるタイプなのだから。
仕方なく立ち上がり、ベヘモットの背中を軽く擦った。
服の上からだが、その下にある筋肉の感触が伝わってくる。人間への擬態として……顔立ちは優男に化けているが、体つきはそれなりに精悍な男性のもの。もしかすると、部屋に飾られた彫刻達の肉体を参考にしているのかもしれない。
「ね~、もうちょっとこう……
気持ちいいとこも撫でてよぉ」
レヴィの控えめな手つきに、ベヘモットは物足りなさそうに言う。
「ククッ、まるで悪酔いした患者への介抱みたいですねぇ」
ジズも冷やかすように言う。確かに、背中を擦って吐き気を宥めているようにも見える。甘い触れ合いというよりは、義務的な接触だ。
「注文の多いやつめ……」
レヴィはやれやれと思いつつ、今度は頭を撫でてみる。ベヘモットの金髪は絹のように滑らかで、指がするすると通る。だが……レヴィも、これまで大人の男の頭など撫でた経験はなく、かなり妙な感覚だ。
すると、ベヘモットは一瞬で表情を変えた。
「ふふ~っ♡」
至福の笑みを浮かべ、目を細める。褒められた大型犬のような、無防備で幸せそうな顔。デレデレという擬音が似合いそうなほど、緩みきった表情だった。
レヴィは、ふと思いつく。
(これは使えるかも……)
コイツを喜ばせるためではなく。油断させ、隙を作るための実験として。魔族にも弱点があるはずだ。それを探る良い機会かもしれない。
試しに、手をうなじの方へ下ろしていき……首筋を軽く撫でてみる。
指先が、耳の後ろから首のラインをなぞった瞬間――
「んゎっ♡」
ベヘモットが堪らなそうな声を漏らした。
甘い吐息と共に、体が僅かに震える。顔は更に蕩けたような表情になり、金色の瞳が潤んだようにも見えた。
「やだもーレヴィ……♡
こそばゆいよー、んふふ」
名前を呼ぶ声まで、普段とは違う響きを帯びている。
(なるほど、ここが弱点か……?)
レヴィは内心でメモを取る。
「人間の雄って、正直そんな手触り良くないですけどねぇ~……」
ジズが横から茶々を入れる。まるで、自分の翼の方が撫で心地が良いぞ、と言いたげな口調。
「ふふーん、なーにジズ?嫉妬ー?」
ベヘモットが余裕の声で返す。しかし、その表情は相変わらず。レヴィに喉元を撫でられ、間抜けに蕩けてている。
その時、床でキラリと何かが光った。
レヴィの視線が、反射的にそちらへ向く。撫でる手を止め、光るものを拾い上げた。
かなり大きな――鱗。
光に透かして観察する。黄金色に輝く、掌ほどの大きさの鱗だ。表面は滑らかで、まるで研磨された金属のような光沢を放っている。
大きさからしても、放たれる魔力からしても……見るからに、普通の生物の鱗ではない。
レヴィは記憶から、学会で得た魔族の知識を思い起こす。鱗を持つ魔族といえば、魚型や蛇型、鰐型の他に――…
一つの心当たりに辿り着き、はっと息を呑んだ。
(これは……まさか)
魔術師として学んだ知識が、頭の中で急速に繋がっていく。この独特の質感。そして何より、触れた瞬間に感じる強大な魔力の残滓。
幻の高級素材として知られる――『バハムートの鱗』。
最強の魔術耐性を持ち、殆どの攻撃術を弾き返すという伝説の素材。その希少性ゆえ、市場に出た記録も少ないが――……売り払えば、魔術師であるレヴィが数年は遊んで暮らせるほどの金額になるだろう。
「あ~っ……」
ベヘモットはそれを見て、面倒臭そうな声を漏らした。
「また鱗落ちてる~」
ゆるく眉を顰め、まるで自分の抜け毛を見つけた人間のような反応を見せる。
「はぁ、お掃除しなきゃ……」
気怠いベヘモットの手招きに応じ、金色のコウモリの使い魔が飛んできた。慣れた動きで屑籠を掴んで持ってくる。
レヴィの思考が、凍りついた。
「まさかこれ、お前の……?」
震える声を抑えつつ、ベヘモットを見つめる。
放蕩な道楽者にしか見えぬ優男。その正体は――
魔族の中でも『最強』と名高いドラゴン、
バハムート。
伝承によれば……一国を一夜で滅ぼすほどの力を持つとされる――強大な邪竜。その鱗は魔法を弾き返し、吐息は山を溶かし、翼の一振りで嵐を巻き起こすという。
道理で、それなりの実力を持つ魔術師であったレヴィを、いとも簡単に捕らえられたわけだ。勇者や英雄と呼ばれるような存在ならまだしも……普通の人間が、太刀打ちできる次元の存在ではなかったのだ。
「レヴィ?それ貸して。ポイするから」
ベヘモットがひらひらと掌を差し出す。屑籠の上で、使い魔も待ち構えるようにこちらを見ている。
「えっ、いや……しかし、」
だが、レヴィも流石に躊躇する。これが本物のバハムートの鱗ならば、魔術師からすれば垂涎もののお宝だ。それをみすみす廃棄するなど、勿体なさすぎる。
「――もしかして、それ欲しいの?僕の鱗だけど……」
鱗を手放さないレヴィを見て、ベヘモットがキョトンと小首を傾げる。ゆるい表情は相変わらずだが、今やそれがかえって恐ろしく見えた。
「ぐっ、その……」
ぞくぞくと湧き上がる畏怖に、レヴィの膝が静かに震えた。散々悪態をついてきた相手が――まさか、それほどに恐ろしい存在だったとは。
「ふふ……じゃあいいよ。それあげる。
怪我しないよう、気をつけて遊んでね」
ベヘモットは、少し照れくさそうに笑いながら、あっさりと許可を出す。まるで、大したものではないかのように。
「そろそろ、レヴィ用の玩具をしまう箱も必要かな~?どれにしようかなぁ~」
ベヘモットは、使い魔から百貨店のカタログを受け取ると、膝の上でぱらぱらとめくり始めた。
実際バハムート本人にとっては、自分の鱗などどうでも良いモノなのだろう。人間が伸びた爪を切るように。時折髪が抜けているように。生きていれば、肉体から自然と剥がれ落ちるものなのだから。
「……そうやって贔屓の人間へ寄越すから、たまーに魔族キラーな勇者が爆誕するんですよ」
ジズは肘をつき、迷惑そうにこぼす。
「大丈夫大丈夫」
だが、ベヘモットは気楽に答える。
「レヴィはお外に出さないから」
自分の棲家の中で飼い殺しておけば、魔族側への脅威にはならない、という意味だろう。
レヴィは鱗を見つめながら、各地で語り継がれる『勇者』の話を思い出していた。
神の加護を受け……敵の強力な呪術をも退けた、と語られる英雄たち。
その実態は、もしかすると――
ベヘモットのように物好きな魔族が、気まぐれに人間へ与えた鱗や牙を使っていただけ……なのかもしれない。崇高な神の加護などではなく、酔狂な魔族からのおこぼれ。
何という皮肉だろう。
人間が崇める勇者の力の源が、魔族の戯れに過ぎなかったなんて。
傷一つなく、完璧な輝きを放つ――巨竜の鱗。
レヴィは震える指で、それを握りしめた。
0
あなたにおすすめの小説
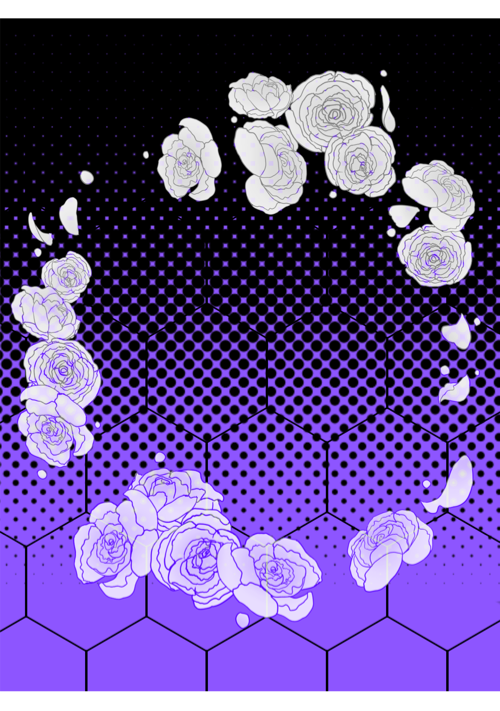
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?

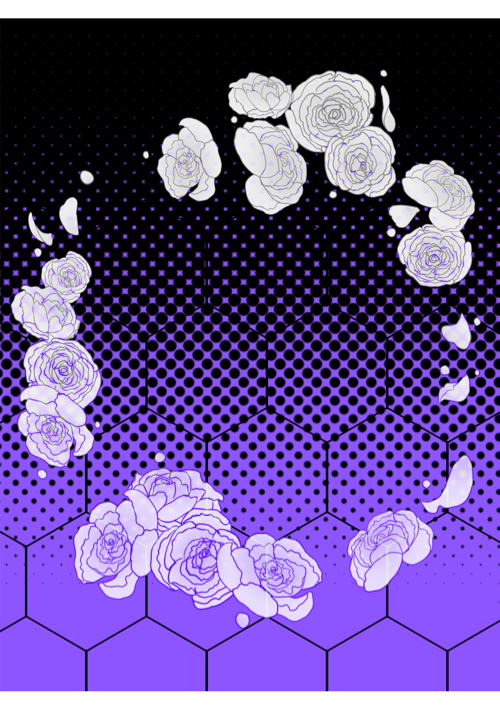


ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。


転生したら4人のヤンデレ彼氏に溺愛される日々が待っていた。
aika
恋愛
主人公まゆは冴えないOL。
ある日ちょっとした事故で命を落とし転生したら・・・
4人のイケメン俳優たちと同棲するという神展開が待っていた。
それぞれタイプの違うイケメンたちに囲まれながら、
生活することになったまゆだが、彼らはまゆを溺愛するあまり
どんどんヤンデレ男になっていき・・・・
ヤンデレ、溺愛、執着、取り合い・・・♡
何でもありのドタバタ恋愛逆ハーレムコメディです。

【ヤンデレ蛇神様に溺愛された貴方は そのまま囲われてしまいました】
一ノ瀬 瞬
恋愛
貴方が小さな頃から毎日通う神社の社には
陽の光に照らされて綺麗に輝く美しい鱗と髪を持つ
それはそれはとても美しい神様がおりました
これはそんな神様と
貴方のお話ー…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















