11 / 27
青い本と棺
捜索会議
しおりを挟む
「…引退してから数年、私は魔術とともに少しだけ眠る事にした。ざっと1000年くらいは眠りたい。後のことは2人に任せることにした。何をするのも自由だと、双子に告げた。蒼月と紅月は何も言わず「分かりました」と言って、次いで「私が棺を守ります」と紅月が言い、「私が後のことをします」と蒼月が言った。何も心配することは無いだろう。おやすみ」
紅月は目を伏せて、ふぅ、と短い息と共に本をパタリと両手で閉じた。
大全と言うにはあまりに不完全で、3名の吸血鬼の事しか書いていない。が、彼にとっては全てだったのだろう。
ふと、蒼柊が頭に浮かんだ単語を口に出してみた。
「もしかしてだけど…目が覚めたから…とか。それか、その魔術を狙われたとか…。どちらにせよ、場所の検討はつきませんが…」
「目覚めたのだとしたら、真っ先に紅月に会うのではないか?棺ごとだと考えると後者の可能性が高いな…」
「父上本体って可能性もあるよね?だとしたら無謀な挑戦だとは思うけど…」
「どちらかと言えば私タイプだからな…素直に人の言うことなど聞かんだろう」
蒼月はまた眉間に皺を寄せた。この店を空けるのもまた不安要素のひとつだ。
何を目的に紅月の店からのみ盗みや偽装を働いているのかが分からない以上は、下手に動けない。
「…うーん、父上の棺も探したいけど、なんにせよこのお店どうするぅ…?」
「ふむ…。困ったな、ここに置いておいて安心出来るやつが1人もおらん。誰か暇な知り合いでもおらんのか」
「…んー、ミーハー女子なら食いつきそうですけど…」
「はっ…!アルバイト雇えばいいんだ!短期で!」
「だからそうしろと前から言っていただろうが」
腕組みをして呆れた声と顔を実兄へ向ける。かなり急がなければならないため、募集してる時間もない。
蒼月は蒼柊に言い、蒼柊の知り合いを探すことにした。
「んん…でるかなぁ…」
「アオト…girl…friend…イル…?」
「え!?い、居ないよ、あ!女の子のお友達は多いけどか、か、彼女じゃ!あ」
「彼女じゃ!」と言ったタイミングで電話の相手が出たようで、あっ、と声を出してしまった。その声に、電話先の相手はすこし不機嫌そうな声で答えてくる。
「なによ。彼女じゃないけど?陰キャがなんの用?」
「ひどいなあ!陰キャじゃないじゃんっ、大人しいだけだよっ」
「なんでもいいけどぉ~。で?なに?」
「んねぇ、モデルの朱月さん知ってる?」
隣でニコニコする吸血鬼を横目に、クラスメイトで仲の良い、気の強い女子に話を通す。一方、反対隣の方ではフラヴィアーナが不機嫌な顔をしていた。
「当たり前でしょ、知らないわけなくない?」
「だよね!その人のところでバイトしない?迎えに行くからさ!今日から!」
「は?」
これぞ普通の反応である。まず意味がわからない。が、蒼柊は押し通して「支度しておいて!」と一方的に電話を切った。
あまりの強引さに蒼月も若干引いている。
「人と関わるのが苦手な私でもわかる。今のは強引だろう…」
「いいんですようあの人は!じゃ僕!その子のこと迎えに行ってきます!紅月さんも行きましょう!」
「はぁーい。じゃあフラヴィアーナちゃん、蒼月、お留守番よろしくねっ」
「…わかた…」
「あぁ。わかった」
2人は店に、気まずいメンバーを残してクラスメイトの家へ向かった。ここからは近いらしい。
街中を、紅月は帽子を深く被り歩く。が、背も高ければ和服なのもあり、かなり目立っている。隣を歩く蒼柊はきまずくなった。
「なんで普段と違うのにこんな視線浴びるんですか…!」
「いやぁ、私が美しくってごめん…」
「聞かなきゃ良かった」
そんな会話をして、暫く歩くと目的地に着いた。普通の一軒家だ。クリーム色の外壁に、茶色い柱、黒い屋根、二階建てだ。
「ところで、女の子のおうちだけど来たことあるの?」
「ありますよ?気は強いですけど、読書仲間なんです」
「へぇ~、女の子に囲まれるなんて、モテるねぇ~」
「? 囲まれてませんけど…」
「ほぉ~」
蒼柊は首をひねりながら、インターホンを押した。ピンポーンという音と共に、インターホンから声がする。
『あ、きた。今出る待って』
一言それだけ言うと、しばらくの間の後に扉が開いた。
扉からは、赤茶色の髪の毛をポニーテールにした気の強そうな少女が出てきた。
とても本を読みそうには見えない。
「こんにちは清麗ちゃん!こっちが例の朱月さんだよ」
「はぁ?本物なわけ」
「ところが生憎、本物なんだ。ごめんよ?」
そう言って紅月は帽子を取り、清麗に向かってニコリと微笑みかけた。写真集に載ってたあのスマイルだと、蒼柊は記憶の隅から画像を見つけて照らし合わせていた。
「ほ、本物!?!?」
「シーっ…ふふ、私のことは外で呼んではいけないよ。さぁ、私のお店を手伝ってくれるかな?」
「は、はい!!いつまでもお手伝いします!」
「あは、1、2週間でいいよ」
2人は、大興奮の清麗を連れて店への帰路をまた辿った。
一方、その紅月の店では、フラヴィアーナと蒼月が押し黙っていた。
「……」
「………」
「…ソ…ソウ、ゲツ?…サン?」
「…なんだ」
先程血液を飲んだカップを洗い、中に紅茶を淹れてまた同じ場所で飲む。フラヴィアーナが嫌いな様子でも無いが、好きな様子でもなく、興味などないと言った風だった。
だがフラヴィアーナは、一応興味があるようだ。不自由ながら、日本語で恐る恐る話し掛ける。
「ァう…ソー、ゲツって、どーかくの?」
「蒼い月だ。ぁー…。書いた方が早いな。説明の仕方が分からん」
そう言うとソファから立ち上がり、紅月が普段使う仕事用のテーブルに近づく。裏の白いチラシを切って小さい長方形になったメモ用紙を1枚拝借し、同時に万年筆も引き抜いてくる。
テーブルの上にメモ用紙を置くと、フラヴィアーナが右隣から覗き込む。
蒼月は左手でペンを持ち、紙に「蒼月」と書いた。
「むずかしー、じ!」
「書いてみろ。ちなみに、蒼柊はこうだ。紅月はこう」
「スゴい!ソーゲツ、やさしい!」
「そうか…?私は字を教えただけだ」
「ンーン!やさしい!」
「…そうか」
珍しく「優しい」という人間の少女に、少しだけは優しくしてやっても良かろうと、蒼月は暖かい紅茶を口へ運んだ。
フラヴィアーナは必死に3人の名前を練習した。が、蒼月や紅月は書けたものの、蒼柊だけを紙いっぱいに書き連ねている。
「…蒼柊は難しいか」
「ぅ…アオ、書けた…ト、書けない…」
「…」
蒼月は紅茶をまたひと飲みし、暖かい息を小さく吐くと、フラヴィアーナに語りかけた。
「蒼柊の「と」はな、ヒイラギという文字だ」
「ひー、らぎ?」
「ヒイラギの英語名は知らん。が、日本のヒイラギと、西洋のヒイラギには違いがあってな」
「ち、がい…」
長く生きている分、人に何かを説明するのは苦手ではない。が、蒼月は人との関わりを極力断ちたい性格のせいで、口が下手だった。それでも説明しようと思った心理は、蒼月自身も分からないでいた。
「西洋のヒイラギは赤い実を付けるそうだ。それはなんだ…クリスマスとやら、それをする時に飾るという」
「…ァ!わかる!ソレ!」
「ということはだ。ヒイラギは冬の木だろう?」
「うん!」
「だから、木の隣に、冬という字でヒイラギ。そう覚えれば良い。覚えたか?」
「Thanks!コレで、かける!アオト、喜ぶ、かなぁ…」
フラヴィアーナはメモを見て、ニコニコとした。蒼月にその表情の意図はよく分からなかった。自分の持ち合わせていない感情だということが分かった程度で、そんなもの沢山あると。
だが一つだけ、その顔と声に似た感情を向けられることがあると思い出した。
「…ふらび…。ふ…ら…ゔぃあーな…言えた…」
「? ナァニ!ソーゲツ!」
「お前は、蒼柊に惚れたのか?」
「ヘッ!?!?!?ち、チガゥ!NO!あ、き、キョウ?あったばかり!だから、ちがう!…maybe…」
「…時間など関係ない。惚れる時など一瞬だと聞く。私には分からんがな。ガールフレンドと言うものは、女の友人ではなく恋仲の女を指すのだろう。お前は、すこしあの電話の後不機嫌そうだった。蒼柊を取られたくない顔だった」
店に来る常連の女。あんなもの、ただの餌だ。食いはしないが、あの目が苦手だった。自分は狩られる側になど回りたくなかった。
遠い昔の記憶、もう100年も前の話を思い出したからだろうか。少しだけ蒼月にも、フラヴィアーナの不機嫌な理由が思い当たっただけだった。
「100年も前、もうあの女も死んでいるだろうが…。昔、美味そうと思った訳でもない、食いたいと思った訳でもない。が、私の店に足繁く通う女が居た」
「たくさん、くる、ひと?」
「そうだ。そのような女沢山いた。だが、あの女は控えめで、私はあの女が来る時だけは何故か平穏に店に居られたものだ。…だがな、あの女がとある日、男とやってきた。あまり嬉しくはなさそうな顔をしていたが…。…私も、隣の男に何をされた訳でもないのに、なぜだか嫌いだと思ったものだよ」
そう語る蒼月の顔を、隣からフラヴィアーナは眺めた。常に、何を考えているのか分からない顔だった。綺麗な人形のようで、だが、その時だけは、少しだけ感情が見えたような気がした。
紅月は目を伏せて、ふぅ、と短い息と共に本をパタリと両手で閉じた。
大全と言うにはあまりに不完全で、3名の吸血鬼の事しか書いていない。が、彼にとっては全てだったのだろう。
ふと、蒼柊が頭に浮かんだ単語を口に出してみた。
「もしかしてだけど…目が覚めたから…とか。それか、その魔術を狙われたとか…。どちらにせよ、場所の検討はつきませんが…」
「目覚めたのだとしたら、真っ先に紅月に会うのではないか?棺ごとだと考えると後者の可能性が高いな…」
「父上本体って可能性もあるよね?だとしたら無謀な挑戦だとは思うけど…」
「どちらかと言えば私タイプだからな…素直に人の言うことなど聞かんだろう」
蒼月はまた眉間に皺を寄せた。この店を空けるのもまた不安要素のひとつだ。
何を目的に紅月の店からのみ盗みや偽装を働いているのかが分からない以上は、下手に動けない。
「…うーん、父上の棺も探したいけど、なんにせよこのお店どうするぅ…?」
「ふむ…。困ったな、ここに置いておいて安心出来るやつが1人もおらん。誰か暇な知り合いでもおらんのか」
「…んー、ミーハー女子なら食いつきそうですけど…」
「はっ…!アルバイト雇えばいいんだ!短期で!」
「だからそうしろと前から言っていただろうが」
腕組みをして呆れた声と顔を実兄へ向ける。かなり急がなければならないため、募集してる時間もない。
蒼月は蒼柊に言い、蒼柊の知り合いを探すことにした。
「んん…でるかなぁ…」
「アオト…girl…friend…イル…?」
「え!?い、居ないよ、あ!女の子のお友達は多いけどか、か、彼女じゃ!あ」
「彼女じゃ!」と言ったタイミングで電話の相手が出たようで、あっ、と声を出してしまった。その声に、電話先の相手はすこし不機嫌そうな声で答えてくる。
「なによ。彼女じゃないけど?陰キャがなんの用?」
「ひどいなあ!陰キャじゃないじゃんっ、大人しいだけだよっ」
「なんでもいいけどぉ~。で?なに?」
「んねぇ、モデルの朱月さん知ってる?」
隣でニコニコする吸血鬼を横目に、クラスメイトで仲の良い、気の強い女子に話を通す。一方、反対隣の方ではフラヴィアーナが不機嫌な顔をしていた。
「当たり前でしょ、知らないわけなくない?」
「だよね!その人のところでバイトしない?迎えに行くからさ!今日から!」
「は?」
これぞ普通の反応である。まず意味がわからない。が、蒼柊は押し通して「支度しておいて!」と一方的に電話を切った。
あまりの強引さに蒼月も若干引いている。
「人と関わるのが苦手な私でもわかる。今のは強引だろう…」
「いいんですようあの人は!じゃ僕!その子のこと迎えに行ってきます!紅月さんも行きましょう!」
「はぁーい。じゃあフラヴィアーナちゃん、蒼月、お留守番よろしくねっ」
「…わかた…」
「あぁ。わかった」
2人は店に、気まずいメンバーを残してクラスメイトの家へ向かった。ここからは近いらしい。
街中を、紅月は帽子を深く被り歩く。が、背も高ければ和服なのもあり、かなり目立っている。隣を歩く蒼柊はきまずくなった。
「なんで普段と違うのにこんな視線浴びるんですか…!」
「いやぁ、私が美しくってごめん…」
「聞かなきゃ良かった」
そんな会話をして、暫く歩くと目的地に着いた。普通の一軒家だ。クリーム色の外壁に、茶色い柱、黒い屋根、二階建てだ。
「ところで、女の子のおうちだけど来たことあるの?」
「ありますよ?気は強いですけど、読書仲間なんです」
「へぇ~、女の子に囲まれるなんて、モテるねぇ~」
「? 囲まれてませんけど…」
「ほぉ~」
蒼柊は首をひねりながら、インターホンを押した。ピンポーンという音と共に、インターホンから声がする。
『あ、きた。今出る待って』
一言それだけ言うと、しばらくの間の後に扉が開いた。
扉からは、赤茶色の髪の毛をポニーテールにした気の強そうな少女が出てきた。
とても本を読みそうには見えない。
「こんにちは清麗ちゃん!こっちが例の朱月さんだよ」
「はぁ?本物なわけ」
「ところが生憎、本物なんだ。ごめんよ?」
そう言って紅月は帽子を取り、清麗に向かってニコリと微笑みかけた。写真集に載ってたあのスマイルだと、蒼柊は記憶の隅から画像を見つけて照らし合わせていた。
「ほ、本物!?!?」
「シーっ…ふふ、私のことは外で呼んではいけないよ。さぁ、私のお店を手伝ってくれるかな?」
「は、はい!!いつまでもお手伝いします!」
「あは、1、2週間でいいよ」
2人は、大興奮の清麗を連れて店への帰路をまた辿った。
一方、その紅月の店では、フラヴィアーナと蒼月が押し黙っていた。
「……」
「………」
「…ソ…ソウ、ゲツ?…サン?」
「…なんだ」
先程血液を飲んだカップを洗い、中に紅茶を淹れてまた同じ場所で飲む。フラヴィアーナが嫌いな様子でも無いが、好きな様子でもなく、興味などないと言った風だった。
だがフラヴィアーナは、一応興味があるようだ。不自由ながら、日本語で恐る恐る話し掛ける。
「ァう…ソー、ゲツって、どーかくの?」
「蒼い月だ。ぁー…。書いた方が早いな。説明の仕方が分からん」
そう言うとソファから立ち上がり、紅月が普段使う仕事用のテーブルに近づく。裏の白いチラシを切って小さい長方形になったメモ用紙を1枚拝借し、同時に万年筆も引き抜いてくる。
テーブルの上にメモ用紙を置くと、フラヴィアーナが右隣から覗き込む。
蒼月は左手でペンを持ち、紙に「蒼月」と書いた。
「むずかしー、じ!」
「書いてみろ。ちなみに、蒼柊はこうだ。紅月はこう」
「スゴい!ソーゲツ、やさしい!」
「そうか…?私は字を教えただけだ」
「ンーン!やさしい!」
「…そうか」
珍しく「優しい」という人間の少女に、少しだけは優しくしてやっても良かろうと、蒼月は暖かい紅茶を口へ運んだ。
フラヴィアーナは必死に3人の名前を練習した。が、蒼月や紅月は書けたものの、蒼柊だけを紙いっぱいに書き連ねている。
「…蒼柊は難しいか」
「ぅ…アオ、書けた…ト、書けない…」
「…」
蒼月は紅茶をまたひと飲みし、暖かい息を小さく吐くと、フラヴィアーナに語りかけた。
「蒼柊の「と」はな、ヒイラギという文字だ」
「ひー、らぎ?」
「ヒイラギの英語名は知らん。が、日本のヒイラギと、西洋のヒイラギには違いがあってな」
「ち、がい…」
長く生きている分、人に何かを説明するのは苦手ではない。が、蒼月は人との関わりを極力断ちたい性格のせいで、口が下手だった。それでも説明しようと思った心理は、蒼月自身も分からないでいた。
「西洋のヒイラギは赤い実を付けるそうだ。それはなんだ…クリスマスとやら、それをする時に飾るという」
「…ァ!わかる!ソレ!」
「ということはだ。ヒイラギは冬の木だろう?」
「うん!」
「だから、木の隣に、冬という字でヒイラギ。そう覚えれば良い。覚えたか?」
「Thanks!コレで、かける!アオト、喜ぶ、かなぁ…」
フラヴィアーナはメモを見て、ニコニコとした。蒼月にその表情の意図はよく分からなかった。自分の持ち合わせていない感情だということが分かった程度で、そんなもの沢山あると。
だが一つだけ、その顔と声に似た感情を向けられることがあると思い出した。
「…ふらび…。ふ…ら…ゔぃあーな…言えた…」
「? ナァニ!ソーゲツ!」
「お前は、蒼柊に惚れたのか?」
「ヘッ!?!?!?ち、チガゥ!NO!あ、き、キョウ?あったばかり!だから、ちがう!…maybe…」
「…時間など関係ない。惚れる時など一瞬だと聞く。私には分からんがな。ガールフレンドと言うものは、女の友人ではなく恋仲の女を指すのだろう。お前は、すこしあの電話の後不機嫌そうだった。蒼柊を取られたくない顔だった」
店に来る常連の女。あんなもの、ただの餌だ。食いはしないが、あの目が苦手だった。自分は狩られる側になど回りたくなかった。
遠い昔の記憶、もう100年も前の話を思い出したからだろうか。少しだけ蒼月にも、フラヴィアーナの不機嫌な理由が思い当たっただけだった。
「100年も前、もうあの女も死んでいるだろうが…。昔、美味そうと思った訳でもない、食いたいと思った訳でもない。が、私の店に足繁く通う女が居た」
「たくさん、くる、ひと?」
「そうだ。そのような女沢山いた。だが、あの女は控えめで、私はあの女が来る時だけは何故か平穏に店に居られたものだ。…だがな、あの女がとある日、男とやってきた。あまり嬉しくはなさそうな顔をしていたが…。…私も、隣の男に何をされた訳でもないのに、なぜだか嫌いだと思ったものだよ」
そう語る蒼月の顔を、隣からフラヴィアーナは眺めた。常に、何を考えているのか分からない顔だった。綺麗な人形のようで、だが、その時だけは、少しだけ感情が見えたような気がした。
0
あなたにおすすめの小説

私のドレスを奪った異母妹に、もう大事なものは奪わせない
文野多咲
恋愛
優月(ゆづき)が自宅屋敷に帰ると、異母妹が優月のウェディングドレスを試着していた。その日縫い上がったばかりで、優月もまだ袖を通していなかった。
使用人たちが「まるで、異母妹のためにあつらえたドレスのよう」と褒め称えており、優月の婚約者まで「異母妹の方が似合う」と褒めている。
優月が異母妹に「どうして勝手に着たの?」と訊けば「ちょっと着てみただけよ」と言う。
婚約者は「異母妹なんだから、ちょっとくらいいじゃないか」と言う。
「ちょっとじゃないわ。私はドレスを盗られたも同じよ!」と言えば、父の後妻は「悪気があったわけじゃないのに、心が狭い」と優月の頬をぶった。
優月は父親に婚約解消を願い出た。婚約者は父親が決めた相手で、優月にはもう彼を信頼できない。
父親に事情を説明すると、「大げさだなあ」と取り合わず、「優月は異母妹に嫉妬しているだけだ、婚約者には異母妹を褒めないように言っておく」と言われる。
嫉妬じゃないのに、どうしてわかってくれないの?
優月は父親をも信頼できなくなる。
婚約者は優月を手に入れるために、優月を襲おうとした。絶体絶命の優月の前に現れたのは、叔父だった。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

里帰りをしていたら離婚届が送られてきたので今から様子を見に行ってきます
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
<離婚届?納得いかないので今から内密に帰ります>
政略結婚で2年もの間「白い結婚」を続ける最中、妹の出産祝いで里帰りしていると突然届いた離婚届。あまりに理不尽で到底受け入れられないので内緒で帰ってみた結果・・・?
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月
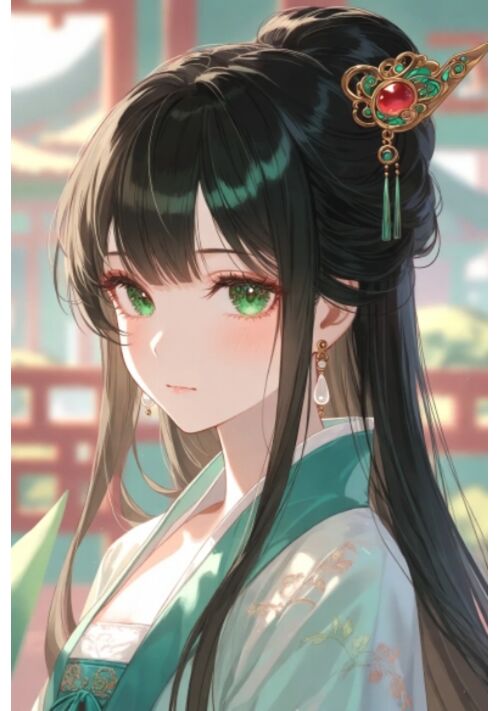
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す―2人の皇子と失われた記憶【1/23本編完結】
雪城 冴
キャラ文芸
本編完結‼️【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた。
「その眼で見るな――」
特殊な眼を持つ少女・翠蓮は、忌み嫌われ、村を追われた。
居場所を失った彼女が頼れたのは、歌だけ。
宮廷歌姫を目指して辿り着いた都でも、待っていたのは差別と孤立。
そんな翠蓮に近づいたのは、
危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
だが、その出会いをきっかけに皇位争い、皇后の執着、命を狙われる日々。
追い詰められる中で、翠蓮の忘れていた記憶が揺り動く。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
声を隠して生き延びるか。
それとも、すべてを賭けて歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――?
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

サレ妻の娘なので、母の敵にざまぁします
二階堂まりい
大衆娯楽
大衆娯楽部門最高記録1位!
※この物語はフィクションです
流行のサレ妻ものを眺めていて、私ならどうする? と思ったので、短編でしたためてみました。
当方未婚なので、妻目線ではなく娘目線で失礼します。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















