16 / 27
青い本と棺
紅家
しおりを挟む
2人を抱えて、蒼月は月の下を走る。蒼柊の服の中、襟から顔を出して、3匹がギイギイと鳴きながら抱えれている。
「あ、こら、落ちるよ」
「落としたら死ぬからな、気を付けろよ」
「ホントに脆いんだなあ…」
寒さを感じるのかどうなのか、服の中で3匹は身を寄せて丸まっていた。フラヴィアーナにパーカーを貸しているし、今着ている服もニットとはいえあまり暖かくはないため、多分いちばん寒いのは蒼柊だろう。
成れの果て達は温もりが無いのがまた、寒さを上乗せしてくる。
しばらく寒さに耐えていると、見慣れた町に出た。そこから道に降りて、そこからは普通に徒歩で蒼月の店へと向かう。
「おい蒼柊、その3匹持ってやるから、コイツ持て」
「え、あ、はい!」
蒼柊は3匹を1度雪の上に降ろし、蒼月が背負っているフラヴィアーナを代わりに請け負った。
流石におんぶは気が引けたので、姫抱きで抱える事にした。
「軽…ご飯ちゃんと食べてるのかな…」
「あの親だ、兄以外まともにこの女に飯を作ってるとは思えないな」
「……。うちにずっといればいい」
「ふん、人間はそうもいかんのだろう」
「………」
ザクザクと、雪をふみしめる音が響く。閑静な住宅街には、音を吸収する雪が積もって更に静けさを増していた。
ふと、蒼柊の腕に抱えられていたフラヴィアーナが身動ぎ声を出す。
「ゥー…?…んァ、アオト…?」
「あ、起きちゃった?もう少しで、蒼月さんのお店だよ」
「…?……ァ」
目が覚め、状況がつかめずにいたようだがやっと理解したようだ。自分が蒼柊に抱えられている。
「ァ、アオト!?おもく、ナイ?!ぁゎゎ…」
「全然?軽いから心配なくらいだよ」
爽やかに、フラヴィアーナへ笑顔を向ける。それを見てか、フラヴィアーナは大人しくなってしまった。
ふと前を見ると、蒼月は3匹を抱えていたはずが腕を降ろしている。
だが、3匹は探す必要も無く、蒼月の肩と頭に1匹ずつのぼり蒼柊の方を見つめていた。
「お前、懐かれるのが早すぎるぞ。何したんだ」
「え、何もしてないですけど…」
「存外お前の血が美味かったのかもしれんな」
抱えなくて良いから楽だと言って、そのまま店へと入る。
すると、中では椅子に腰かけ居眠りしていた柊平が目を覚ました。
「おうおかえ…。蒼月なんでそんなもん乗せてんだ」
「お前の孫が殺したくないと喚いたんでな」
「喚いてません」
フラヴィアーナを姫抱きして入ってきた孫を見て、柊平はニヤニヤとしだす。
「お?気に入ったんか~蒼柊ォ~」
「ち、ちが!寒そうだったからパーカー着せただけ、だし!寝てたから、抱いてるだけだし…!!」
「ふ~~~~ん?」
「あ!あと、フラヴィアーナちゃんは、き、今日っていうか、もう、休みの間は紅家の子です!!」
「………ほぉ~~~~~~~~~~~!!」
柊平の顔のニヤニヤ度が増していく。それに比例するように、蒼柊の照れたような、怒ったような顔が増していく。
フラヴィアーナが起きたので、ゆっくりと降ろす。パーカーを返すべきか悩み脱ぐが、蒼柊に制止される。
「いいよ、そのまま着てて。どうせまた、うちに帰るから。あ、ちょっと電話するから待っててね」
「あ、そういや蒼月、お前に渡し忘れてたけどよ、ほれ、息子の嫁が海外の菓子作ってくれたんだ。おめー甘いもん好きだろ」
「…好きだが。…ありがとう。これなんて言う菓子だ」
「なんだったかな。小難しい名前だったな」
「ダックワーズだよ。メレンゲのサクサクしたお菓子。僕もよく作るでしょ、じーちゃん」
おうそれだ!と柊平はニコニコする。蒼月はそれをとりあえず受け取り、早く帰って明日も早く来いと3人を家へと返した。
「なんか急いでなかった?蒼月さん」
「ありゃあ、あの菓子早く食いたかったんだな」
「え、そんな理由なの?」
「蒼月、ああ見えて甘いもんすげぇ好きなんだ」
「ソーゲツ、sweetsスキ?」
「おう!そりゃあもう大好きよ!」
寒空の下、3人で雑談をしながら歩く。もちろんあの3匹は蒼月の店に置いてきた。
店を出る時、取り残され出ていくのが見えたのか、着いてこようとしていた。そして、引き剥がして蒼月に押し付けて出ると、悲痛な鳴き声で後ろ髪引かれる思いをした。
「にしてもお前、あの成れの果てに懐かれてんのか」
「いや、なんか知らないけどそうみたい。血が美味しかったのかな…」
「さぁな。誰の血だったなんてアイツらが分かるかどうかは知らねぇが、お前優しいからなぁ」
「んん…まぁ、見た目は気持ち悪いけど、懐かれて悪い気はしないかも…」
そう言う蒼柊の腕に、フラヴィアーナはひしっとしがみついて震えていた。やはり寒いのだろう。
生脚ではないが、寒空の下、厚手のタイツ1枚でスカートでは寒いに違いない。
だが、それのお陰で自分の腕に可愛い女の子が引っ付いてると思うと、寒さに感謝せざるを得ない。
しばらく歩を進め、やっと自宅の門に辿り着いた。玄関まではあと少しだ。
「ワ…おっきい!gate?ワフウ!」
「でしょー、うち、おっきいんだってさ」
「ほれ、寒いから早く入るぞ」
3人で家の中に入ると、父と母が出てきて出迎えてくれる。
「オカエリ!ァラ、そのこガ、フラヴィアーナちゃん?」
「は、ハイ!Flavianaデス!ニホンゴ、まだ、ニガテ…デス、ケド、ヨロシクお願いします!」
「Wow!!あおと、あおと、カワイイねコノコ!」
自分と同じくらいの拙さに、母は親近感を覚えてフラヴィアーナに抱きついた。抱きつかれても満更でもなさそうで、2人は仲良くなったようだった。
隣に立つ父親は、蒼柊とフラヴィアーナを交互に見て、柊平によく似たニヤニヤ顔を蒼柊に向ける。
「と、とーさんっ、そういうのじゃないからね!!」
「おーわかったわかったァ!そういう事にしとこうな!」
「もーーっ」
家の中に入ると、既に夕飯が準備されていた。いつもより1人分多い夕飯と、自然に5人分用意されている椅子。いつもは4人分だが、さも元から5人ですと言わんばかりの自然さだった。
「…?アオト、キョーダイ、いる?」
「いないよー、ひとりっこ!」
「でも…ご…」
「…ああ!ふふ、椅子のこと?気にしないで、さっ、座って~!」
椅子に座り、目の前にあるいつもより少し豪華な夕食にワクワクしながら手を合わせる。
「いただきます!」というと、まだフラヴィアーナはこの文化に慣れていないのか、見様見真似でたどたどしく「いた、だき、マス?」と言った。その様子が微笑ましくて、蒼柊はつい微笑んでしまう。
当のフラヴィアーナは気付いていないようだ。
ふと、蒼柊の脳裏に移動中の蒼月の言葉が思い浮かんだ。
「んねぇじーちゃん。ウチってさ、父さんは社長だけど、元からデカいし何百年もコレなんでしょ?どんなうちなの?」
「あ。…あー…。言うの忘れてたな…」
「…じーちゃん~…???」
じとーっとした視線を祖父に向ける。父の柊夜もきょとんとした顔をしていた。確かに、そういえば聞いたことがないなと呟く。
「まぁなんだ、うちはアレだ!簡単に言えば~あの~、ご先祖様の代からな、祓い屋なんだ!蒼柊だって見えてんだがな、おめーが生の気が強すぎて悪いのが近寄ってこねぇせいで、残りの霊を人と同じだと思ってっから気づいてねぇんだ…よ」
「…じーちゃん?なんでそういう大事なこと言わないの?なんか確かにじいちゃん夜出掛けていくもんね。あれ祓い屋の仕事してるの?なんでそんなこと言うの忘れるわけ?」
「いやぁ…言ったもんだとばっかり…」
後ろ頭をやりづらそうに掻くと、柊平は夕飯をまた食べ始める。そして、思い出したように蒼柊に向き直る。
「おぉそうだ!蔵に連れてってやる!入ったことねぇだろお前!」
「あぁ裏の…確かに無い…。鍵かかってるし…」
「あっこには" 友達 "がいんだよ!昔のこともついでに調べろ~。フラヴィアーナちゃんも、蒼柊と2人で日本語の勉強にもなるだろうし来たらどうだい」
「ンゥ!わかり、ましタ!」
フラヴィアーナは嬉しそうに頷くと、蒼柊に笑顔を向けた。その笑顔が何かは分からなかったが、蒼柊も微笑み返す。
そんな会話はあったが、夕飯は和やかな空気だった。
「あ、こら、落ちるよ」
「落としたら死ぬからな、気を付けろよ」
「ホントに脆いんだなあ…」
寒さを感じるのかどうなのか、服の中で3匹は身を寄せて丸まっていた。フラヴィアーナにパーカーを貸しているし、今着ている服もニットとはいえあまり暖かくはないため、多分いちばん寒いのは蒼柊だろう。
成れの果て達は温もりが無いのがまた、寒さを上乗せしてくる。
しばらく寒さに耐えていると、見慣れた町に出た。そこから道に降りて、そこからは普通に徒歩で蒼月の店へと向かう。
「おい蒼柊、その3匹持ってやるから、コイツ持て」
「え、あ、はい!」
蒼柊は3匹を1度雪の上に降ろし、蒼月が背負っているフラヴィアーナを代わりに請け負った。
流石におんぶは気が引けたので、姫抱きで抱える事にした。
「軽…ご飯ちゃんと食べてるのかな…」
「あの親だ、兄以外まともにこの女に飯を作ってるとは思えないな」
「……。うちにずっといればいい」
「ふん、人間はそうもいかんのだろう」
「………」
ザクザクと、雪をふみしめる音が響く。閑静な住宅街には、音を吸収する雪が積もって更に静けさを増していた。
ふと、蒼柊の腕に抱えられていたフラヴィアーナが身動ぎ声を出す。
「ゥー…?…んァ、アオト…?」
「あ、起きちゃった?もう少しで、蒼月さんのお店だよ」
「…?……ァ」
目が覚め、状況がつかめずにいたようだがやっと理解したようだ。自分が蒼柊に抱えられている。
「ァ、アオト!?おもく、ナイ?!ぁゎゎ…」
「全然?軽いから心配なくらいだよ」
爽やかに、フラヴィアーナへ笑顔を向ける。それを見てか、フラヴィアーナは大人しくなってしまった。
ふと前を見ると、蒼月は3匹を抱えていたはずが腕を降ろしている。
だが、3匹は探す必要も無く、蒼月の肩と頭に1匹ずつのぼり蒼柊の方を見つめていた。
「お前、懐かれるのが早すぎるぞ。何したんだ」
「え、何もしてないですけど…」
「存外お前の血が美味かったのかもしれんな」
抱えなくて良いから楽だと言って、そのまま店へと入る。
すると、中では椅子に腰かけ居眠りしていた柊平が目を覚ました。
「おうおかえ…。蒼月なんでそんなもん乗せてんだ」
「お前の孫が殺したくないと喚いたんでな」
「喚いてません」
フラヴィアーナを姫抱きして入ってきた孫を見て、柊平はニヤニヤとしだす。
「お?気に入ったんか~蒼柊ォ~」
「ち、ちが!寒そうだったからパーカー着せただけ、だし!寝てたから、抱いてるだけだし…!!」
「ふ~~~~ん?」
「あ!あと、フラヴィアーナちゃんは、き、今日っていうか、もう、休みの間は紅家の子です!!」
「………ほぉ~~~~~~~~~~~!!」
柊平の顔のニヤニヤ度が増していく。それに比例するように、蒼柊の照れたような、怒ったような顔が増していく。
フラヴィアーナが起きたので、ゆっくりと降ろす。パーカーを返すべきか悩み脱ぐが、蒼柊に制止される。
「いいよ、そのまま着てて。どうせまた、うちに帰るから。あ、ちょっと電話するから待っててね」
「あ、そういや蒼月、お前に渡し忘れてたけどよ、ほれ、息子の嫁が海外の菓子作ってくれたんだ。おめー甘いもん好きだろ」
「…好きだが。…ありがとう。これなんて言う菓子だ」
「なんだったかな。小難しい名前だったな」
「ダックワーズだよ。メレンゲのサクサクしたお菓子。僕もよく作るでしょ、じーちゃん」
おうそれだ!と柊平はニコニコする。蒼月はそれをとりあえず受け取り、早く帰って明日も早く来いと3人を家へと返した。
「なんか急いでなかった?蒼月さん」
「ありゃあ、あの菓子早く食いたかったんだな」
「え、そんな理由なの?」
「蒼月、ああ見えて甘いもんすげぇ好きなんだ」
「ソーゲツ、sweetsスキ?」
「おう!そりゃあもう大好きよ!」
寒空の下、3人で雑談をしながら歩く。もちろんあの3匹は蒼月の店に置いてきた。
店を出る時、取り残され出ていくのが見えたのか、着いてこようとしていた。そして、引き剥がして蒼月に押し付けて出ると、悲痛な鳴き声で後ろ髪引かれる思いをした。
「にしてもお前、あの成れの果てに懐かれてんのか」
「いや、なんか知らないけどそうみたい。血が美味しかったのかな…」
「さぁな。誰の血だったなんてアイツらが分かるかどうかは知らねぇが、お前優しいからなぁ」
「んん…まぁ、見た目は気持ち悪いけど、懐かれて悪い気はしないかも…」
そう言う蒼柊の腕に、フラヴィアーナはひしっとしがみついて震えていた。やはり寒いのだろう。
生脚ではないが、寒空の下、厚手のタイツ1枚でスカートでは寒いに違いない。
だが、それのお陰で自分の腕に可愛い女の子が引っ付いてると思うと、寒さに感謝せざるを得ない。
しばらく歩を進め、やっと自宅の門に辿り着いた。玄関まではあと少しだ。
「ワ…おっきい!gate?ワフウ!」
「でしょー、うち、おっきいんだってさ」
「ほれ、寒いから早く入るぞ」
3人で家の中に入ると、父と母が出てきて出迎えてくれる。
「オカエリ!ァラ、そのこガ、フラヴィアーナちゃん?」
「は、ハイ!Flavianaデス!ニホンゴ、まだ、ニガテ…デス、ケド、ヨロシクお願いします!」
「Wow!!あおと、あおと、カワイイねコノコ!」
自分と同じくらいの拙さに、母は親近感を覚えてフラヴィアーナに抱きついた。抱きつかれても満更でもなさそうで、2人は仲良くなったようだった。
隣に立つ父親は、蒼柊とフラヴィアーナを交互に見て、柊平によく似たニヤニヤ顔を蒼柊に向ける。
「と、とーさんっ、そういうのじゃないからね!!」
「おーわかったわかったァ!そういう事にしとこうな!」
「もーーっ」
家の中に入ると、既に夕飯が準備されていた。いつもより1人分多い夕飯と、自然に5人分用意されている椅子。いつもは4人分だが、さも元から5人ですと言わんばかりの自然さだった。
「…?アオト、キョーダイ、いる?」
「いないよー、ひとりっこ!」
「でも…ご…」
「…ああ!ふふ、椅子のこと?気にしないで、さっ、座って~!」
椅子に座り、目の前にあるいつもより少し豪華な夕食にワクワクしながら手を合わせる。
「いただきます!」というと、まだフラヴィアーナはこの文化に慣れていないのか、見様見真似でたどたどしく「いた、だき、マス?」と言った。その様子が微笑ましくて、蒼柊はつい微笑んでしまう。
当のフラヴィアーナは気付いていないようだ。
ふと、蒼柊の脳裏に移動中の蒼月の言葉が思い浮かんだ。
「んねぇじーちゃん。ウチってさ、父さんは社長だけど、元からデカいし何百年もコレなんでしょ?どんなうちなの?」
「あ。…あー…。言うの忘れてたな…」
「…じーちゃん~…???」
じとーっとした視線を祖父に向ける。父の柊夜もきょとんとした顔をしていた。確かに、そういえば聞いたことがないなと呟く。
「まぁなんだ、うちはアレだ!簡単に言えば~あの~、ご先祖様の代からな、祓い屋なんだ!蒼柊だって見えてんだがな、おめーが生の気が強すぎて悪いのが近寄ってこねぇせいで、残りの霊を人と同じだと思ってっから気づいてねぇんだ…よ」
「…じーちゃん?なんでそういう大事なこと言わないの?なんか確かにじいちゃん夜出掛けていくもんね。あれ祓い屋の仕事してるの?なんでそんなこと言うの忘れるわけ?」
「いやぁ…言ったもんだとばっかり…」
後ろ頭をやりづらそうに掻くと、柊平は夕飯をまた食べ始める。そして、思い出したように蒼柊に向き直る。
「おぉそうだ!蔵に連れてってやる!入ったことねぇだろお前!」
「あぁ裏の…確かに無い…。鍵かかってるし…」
「あっこには" 友達 "がいんだよ!昔のこともついでに調べろ~。フラヴィアーナちゃんも、蒼柊と2人で日本語の勉強にもなるだろうし来たらどうだい」
「ンゥ!わかり、ましタ!」
フラヴィアーナは嬉しそうに頷くと、蒼柊に笑顔を向けた。その笑顔が何かは分からなかったが、蒼柊も微笑み返す。
そんな会話はあったが、夕飯は和やかな空気だった。
0
あなたにおすすめの小説

私のドレスを奪った異母妹に、もう大事なものは奪わせない
文野多咲
恋愛
優月(ゆづき)が自宅屋敷に帰ると、異母妹が優月のウェディングドレスを試着していた。その日縫い上がったばかりで、優月もまだ袖を通していなかった。
使用人たちが「まるで、異母妹のためにあつらえたドレスのよう」と褒め称えており、優月の婚約者まで「異母妹の方が似合う」と褒めている。
優月が異母妹に「どうして勝手に着たの?」と訊けば「ちょっと着てみただけよ」と言う。
婚約者は「異母妹なんだから、ちょっとくらいいじゃないか」と言う。
「ちょっとじゃないわ。私はドレスを盗られたも同じよ!」と言えば、父の後妻は「悪気があったわけじゃないのに、心が狭い」と優月の頬をぶった。
優月は父親に婚約解消を願い出た。婚約者は父親が決めた相手で、優月にはもう彼を信頼できない。
父親に事情を説明すると、「大げさだなあ」と取り合わず、「優月は異母妹に嫉妬しているだけだ、婚約者には異母妹を褒めないように言っておく」と言われる。
嫉妬じゃないのに、どうしてわかってくれないの?
優月は父親をも信頼できなくなる。
婚約者は優月を手に入れるために、優月を襲おうとした。絶体絶命の優月の前に現れたのは、叔父だった。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

里帰りをしていたら離婚届が送られてきたので今から様子を見に行ってきます
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
<離婚届?納得いかないので今から内密に帰ります>
政略結婚で2年もの間「白い結婚」を続ける最中、妹の出産祝いで里帰りしていると突然届いた離婚届。あまりに理不尽で到底受け入れられないので内緒で帰ってみた結果・・・?
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています
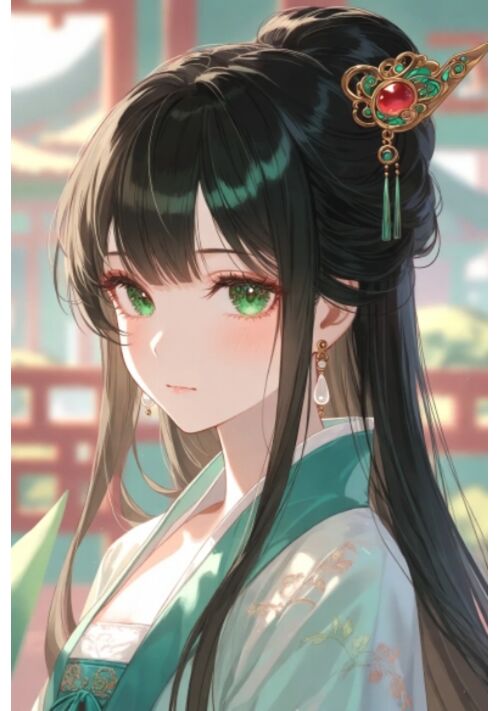
完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す―2人の皇子と失われた記憶【1/23本編完結】
雪城 冴
キャラ文芸
本編完結‼️【中華サスペンス】
皇帝が隠した禁忌の秘密。
それを“思い出してはいけない少女”がいた。
「その眼で見るな――」
特殊な眼を持つ少女・翠蓮は、忌み嫌われ、村を追われた。
居場所を失った彼女が頼れたのは、歌だけ。
宮廷歌姫を目指して辿り着いた都でも、待っていたのは差別と孤立。
そんな翠蓮に近づいたのは、
危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。
だが、その出会いをきっかけに皇位争い、皇后の執着、命を狙われる日々。
追い詰められる中で、翠蓮の忘れていた記憶が揺り動く。
かつて王家が封じた“力”とは?
翠蓮の正体とは?
声を隠して生き延びるか。
それとも、すべてを賭けて歌うのか。
運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――?
※架空の中華風ファンタジーです
※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています
※表紙絵はAI生成

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

サレ妻の娘なので、母の敵にざまぁします
二階堂まりい
大衆娯楽
大衆娯楽部門最高記録1位!
※この物語はフィクションです
流行のサレ妻ものを眺めていて、私ならどうする? と思ったので、短編でしたためてみました。
当方未婚なので、妻目線ではなく娘目線で失礼します。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















