6 / 17
第2章 2-1 形式だけの結婚式
しおりを挟む
第2章 2-1 形式だけの結婚式
婚姻契約書にサインをしてから、わずか三日後。
レティシアとセドリックの“結婚式”は、驚くほど静かに行われた。
それは王都でも滅多に見られぬほどの簡素な式だった。
貴族社会では、婚礼は派手であればあるほど家の名誉になる。
だが、アークハート侯爵は、誰の目も避けるようにして小さな私邸の礼拝堂を選んだ。
参列者はわずか六名。
セドリックの側近である執事ヴァルドと侍従のリネア、そしてレティシアの実家から派遣された護衛二人と侍女。
神父が静かに祈祷書を開き、二人の前に立つ。
聖堂の中は、外の喧噪とはまるで別世界だった。
白い花が祭壇に並べられ、窓から差し込む光が二人を包む。
けれど、その神々しい空気の中に、緊張とも静寂ともつかぬ透明な距離があった。
---
「セドリック・アークハート侯爵。あなたは、この女性を妻として迎え、良き伴侶として支え合うことを誓いますか?」
神父の声が響く。
セドリックはわずかに頷き、低く答えた。
「誓います」
それは、氷のように澄んだ声だった。
だがその奥には、確かな力と誠実さがあった。
彼が口にする「誓い」は、愛ではなく――責任だった。
次に、神父はレティシアに問う。
「レティシア・ドラン。あなたは、この男性を夫として受け入れ、共に歩むことを誓いますか?」
レティシアはゆっくりと息を吸う。
胸の奥で、なぜか鼓動が速くなっていた。
――これは、愛を誓う式ではない。
――形式だけの結婚。
そう言い聞かせながらも、彼女の瞳はまっすぐにセドリックを見た。
その瞳の奥に、一瞬だけ揺れる光が映る。
「……誓います」
その声は静かで、しかし揺るぎなかった。
神父が微笑み、手を掲げる。
「この誓いは、神と民の前において有効とされます。
セドリック・アークハート侯爵とレティシア・ドラン――いえ、これよりは“アークハート侯爵夫人”として、
あなた方の結婚が成立したことを、ここに宣言します」
---
拍手も歓声もなかった。
祝福の音楽も鳴らない。
ただ、白い花弁が一枚、窓から差し込む風に乗って舞い落ちる。
それを見た瞬間、レティシアはふと息を呑んだ。
まるでその一枚の花が、彼女に「これでいい」と囁いているようだった。
セドリックは彼女に向かって小さく頭を下げた。
「これで、契約は成立です」
「はい。……ありがとうございます、旦那様」
“旦那様”という響きに、セドリックの眉が一瞬だけ動く。
それは拒絶ではなく、どこか照れ隠しのようなものだった。
「あなたの部屋は、屋敷の東棟に用意しました。
必要なものは執事ヴァルドに言ってください。
不便なことがあれば――遠慮なく」
「承知しましたわ。お気遣い、痛み入ります」
儀礼的な言葉。けれど、どちらもそれ以上は続けなかった。
---
式のあと、馬車で侯爵邸に戻る道すがら。
窓の外には春の終わりを告げる花々が揺れていた。
しかし、車内にはほとんど言葉がなかった。
レティシアはふと、彼の横顔を見た。
セドリックは目を閉じ、静かに呼吸している。
その表情は、凛としているのにどこか疲れて見えた。
(……この人も、きっと何かを背負っている)
噂では「心を凍らせた男」と呼ばれている。
だが、彼の沈黙の奥には、氷ではなく傷があるように思えた。
そのことに気づいた瞬間、レティシアの胸が少しだけ締めつけられた。
---
侯爵邸に戻ると、屋敷の使用人たちが一斉に出迎えた。
皆、一糸乱れぬ動きで深く礼をする。
「ご帰宅を歓迎いたします、侯爵閣下。そして――侯爵夫人」
その言葉に、レティシアは一瞬だけ息を呑んだ。
――“夫人”。
形式的であっても、その呼び名の重さが、胸にずしりと響く。
「初めまして、皆さま。これからお世話になります」
礼儀正しく頭を下げると、執事のヴァルドが一歩前へ出た。
白髪交じりの髪をきっちり撫でつけ、無表情ながら温かみのある声で言う。
「閣下のご命令により、東棟の一室をすべて新しく整えました。
お好みの香や調度があれば、すぐに手配いたします」
「ありがとうございます。……とても心強いですわ」
ヴァルドが静かに微笑む。
その微笑みには、主に仕える忠誠と同時に、どこか彼女を気遣う優しさがあった。
---
東棟の部屋は、思ったよりも広かった。
壁は白く塗られ、天井の梁には繊細な彫刻が施されている。
豪奢というよりは、上品で落ち着いた雰囲気だった。
窓を開けると、庭園のバラが見える。
季節は初夏に差しかかっており、淡いピンクと白の花が咲き乱れていた。
「……きれい」
思わず漏れた言葉に、背後から声がした。
「気に入ったようですね」
セドリックが、いつの間にか扉の前に立っていた。
彼は相変わらず表情を変えない。だが、ほんのわずかに口元が柔らいでいた。
「はい。とても落ち着く部屋です」
「良かった。……この邸は、もともと私の母が設計したものです。
東棟は、母がよく過ごしていた場所でね。
だから――女性が静かに暮らすには、最も適している」
その言葉に、レティシアは小さく頷いた。
セドリックの声が、今までよりも少しだけ温かく聞こえた。
「……あなたの母上も、穏やかな方だったのですね」
「いや、むしろ厳しかった」
セドリックが珍しく微笑を浮かべる。
「ただ、厳しさの中に愛情があった。――それが、母の強さだった」
その横顔を見つめながら、レティシアは思う。
彼は冷たい人ではない。
ただ、優しさをどう表現していいか分からない人なのだ、と。
---
夕刻。
式の報告を終えたあと、二人は晩餐を共にした。
長いテーブルに、二人きり。
銀の燭台が灯り、蝋燭の炎がゆらゆらと影を揺らす。
「こうして食事を共にするのも、これが最初で最後になるかもしれませんね」
レティシアが穏やかに言うと、セドリックはグラスを手に取って答えた。
「契約上はそうだが、私は無理に避けるつもりはない。
食卓を囲むことまで禁じる条項は、なかったはずです」
「……それもそうですわね」
くすりと笑う。
氷の侯爵が、そんな冗談めいたことを言うとは思わなかった。
ワインを口に運び、芳醇な香りを味わいながら、レティシアはふと思った。
(この人となら、静かに生きられるかもしれない)
王太子との婚約生活では、いつも息苦しかった。
完璧を求められ、笑顔すら指導された。
だがセドリックは違う。
彼は何も求めない。
――ただ、そこに“居ること”を許してくれる。
その静かな優しさが、何より心地よかった。
---
夜。
レティシアが部屋に戻ると、暖炉に火が灯っていた。
香の匂いが微かに漂い、白い寝具が整えられている。
その中央に、一輪の花が置かれていた。
白いバラ。
その花びらには、わずかに露が光っている。
カードも手紙もない。
けれど――誰が置いたのか、分かる。
「……あの方、まさか自分で?」
小さく笑う。
氷の侯爵と呼ばれる男が、こんな粋な真似をするなんて。
ベッドの縁に腰を下ろし、レティシアは花をそっと抱きしめた。
白い結婚。
色のない関係のはずが、いつの間にか心に淡い色が灯り始めていた。
---
> 恋ではない。
けれど確かに、彼の優しさが、彼女の心を温めていた。
名ばかりの妻――そのはずが、白い花びらに、ほんのり紅が滲み始めていた。
婚姻契約書にサインをしてから、わずか三日後。
レティシアとセドリックの“結婚式”は、驚くほど静かに行われた。
それは王都でも滅多に見られぬほどの簡素な式だった。
貴族社会では、婚礼は派手であればあるほど家の名誉になる。
だが、アークハート侯爵は、誰の目も避けるようにして小さな私邸の礼拝堂を選んだ。
参列者はわずか六名。
セドリックの側近である執事ヴァルドと侍従のリネア、そしてレティシアの実家から派遣された護衛二人と侍女。
神父が静かに祈祷書を開き、二人の前に立つ。
聖堂の中は、外の喧噪とはまるで別世界だった。
白い花が祭壇に並べられ、窓から差し込む光が二人を包む。
けれど、その神々しい空気の中に、緊張とも静寂ともつかぬ透明な距離があった。
---
「セドリック・アークハート侯爵。あなたは、この女性を妻として迎え、良き伴侶として支え合うことを誓いますか?」
神父の声が響く。
セドリックはわずかに頷き、低く答えた。
「誓います」
それは、氷のように澄んだ声だった。
だがその奥には、確かな力と誠実さがあった。
彼が口にする「誓い」は、愛ではなく――責任だった。
次に、神父はレティシアに問う。
「レティシア・ドラン。あなたは、この男性を夫として受け入れ、共に歩むことを誓いますか?」
レティシアはゆっくりと息を吸う。
胸の奥で、なぜか鼓動が速くなっていた。
――これは、愛を誓う式ではない。
――形式だけの結婚。
そう言い聞かせながらも、彼女の瞳はまっすぐにセドリックを見た。
その瞳の奥に、一瞬だけ揺れる光が映る。
「……誓います」
その声は静かで、しかし揺るぎなかった。
神父が微笑み、手を掲げる。
「この誓いは、神と民の前において有効とされます。
セドリック・アークハート侯爵とレティシア・ドラン――いえ、これよりは“アークハート侯爵夫人”として、
あなた方の結婚が成立したことを、ここに宣言します」
---
拍手も歓声もなかった。
祝福の音楽も鳴らない。
ただ、白い花弁が一枚、窓から差し込む風に乗って舞い落ちる。
それを見た瞬間、レティシアはふと息を呑んだ。
まるでその一枚の花が、彼女に「これでいい」と囁いているようだった。
セドリックは彼女に向かって小さく頭を下げた。
「これで、契約は成立です」
「はい。……ありがとうございます、旦那様」
“旦那様”という響きに、セドリックの眉が一瞬だけ動く。
それは拒絶ではなく、どこか照れ隠しのようなものだった。
「あなたの部屋は、屋敷の東棟に用意しました。
必要なものは執事ヴァルドに言ってください。
不便なことがあれば――遠慮なく」
「承知しましたわ。お気遣い、痛み入ります」
儀礼的な言葉。けれど、どちらもそれ以上は続けなかった。
---
式のあと、馬車で侯爵邸に戻る道すがら。
窓の外には春の終わりを告げる花々が揺れていた。
しかし、車内にはほとんど言葉がなかった。
レティシアはふと、彼の横顔を見た。
セドリックは目を閉じ、静かに呼吸している。
その表情は、凛としているのにどこか疲れて見えた。
(……この人も、きっと何かを背負っている)
噂では「心を凍らせた男」と呼ばれている。
だが、彼の沈黙の奥には、氷ではなく傷があるように思えた。
そのことに気づいた瞬間、レティシアの胸が少しだけ締めつけられた。
---
侯爵邸に戻ると、屋敷の使用人たちが一斉に出迎えた。
皆、一糸乱れぬ動きで深く礼をする。
「ご帰宅を歓迎いたします、侯爵閣下。そして――侯爵夫人」
その言葉に、レティシアは一瞬だけ息を呑んだ。
――“夫人”。
形式的であっても、その呼び名の重さが、胸にずしりと響く。
「初めまして、皆さま。これからお世話になります」
礼儀正しく頭を下げると、執事のヴァルドが一歩前へ出た。
白髪交じりの髪をきっちり撫でつけ、無表情ながら温かみのある声で言う。
「閣下のご命令により、東棟の一室をすべて新しく整えました。
お好みの香や調度があれば、すぐに手配いたします」
「ありがとうございます。……とても心強いですわ」
ヴァルドが静かに微笑む。
その微笑みには、主に仕える忠誠と同時に、どこか彼女を気遣う優しさがあった。
---
東棟の部屋は、思ったよりも広かった。
壁は白く塗られ、天井の梁には繊細な彫刻が施されている。
豪奢というよりは、上品で落ち着いた雰囲気だった。
窓を開けると、庭園のバラが見える。
季節は初夏に差しかかっており、淡いピンクと白の花が咲き乱れていた。
「……きれい」
思わず漏れた言葉に、背後から声がした。
「気に入ったようですね」
セドリックが、いつの間にか扉の前に立っていた。
彼は相変わらず表情を変えない。だが、ほんのわずかに口元が柔らいでいた。
「はい。とても落ち着く部屋です」
「良かった。……この邸は、もともと私の母が設計したものです。
東棟は、母がよく過ごしていた場所でね。
だから――女性が静かに暮らすには、最も適している」
その言葉に、レティシアは小さく頷いた。
セドリックの声が、今までよりも少しだけ温かく聞こえた。
「……あなたの母上も、穏やかな方だったのですね」
「いや、むしろ厳しかった」
セドリックが珍しく微笑を浮かべる。
「ただ、厳しさの中に愛情があった。――それが、母の強さだった」
その横顔を見つめながら、レティシアは思う。
彼は冷たい人ではない。
ただ、優しさをどう表現していいか分からない人なのだ、と。
---
夕刻。
式の報告を終えたあと、二人は晩餐を共にした。
長いテーブルに、二人きり。
銀の燭台が灯り、蝋燭の炎がゆらゆらと影を揺らす。
「こうして食事を共にするのも、これが最初で最後になるかもしれませんね」
レティシアが穏やかに言うと、セドリックはグラスを手に取って答えた。
「契約上はそうだが、私は無理に避けるつもりはない。
食卓を囲むことまで禁じる条項は、なかったはずです」
「……それもそうですわね」
くすりと笑う。
氷の侯爵が、そんな冗談めいたことを言うとは思わなかった。
ワインを口に運び、芳醇な香りを味わいながら、レティシアはふと思った。
(この人となら、静かに生きられるかもしれない)
王太子との婚約生活では、いつも息苦しかった。
完璧を求められ、笑顔すら指導された。
だがセドリックは違う。
彼は何も求めない。
――ただ、そこに“居ること”を許してくれる。
その静かな優しさが、何より心地よかった。
---
夜。
レティシアが部屋に戻ると、暖炉に火が灯っていた。
香の匂いが微かに漂い、白い寝具が整えられている。
その中央に、一輪の花が置かれていた。
白いバラ。
その花びらには、わずかに露が光っている。
カードも手紙もない。
けれど――誰が置いたのか、分かる。
「……あの方、まさか自分で?」
小さく笑う。
氷の侯爵と呼ばれる男が、こんな粋な真似をするなんて。
ベッドの縁に腰を下ろし、レティシアは花をそっと抱きしめた。
白い結婚。
色のない関係のはずが、いつの間にか心に淡い色が灯り始めていた。
---
> 恋ではない。
けれど確かに、彼の優しさが、彼女の心を温めていた。
名ばかりの妻――そのはずが、白い花びらに、ほんのり紅が滲み始めていた。
1
あなたにおすすめの小説

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

で、お前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか?
Debby
恋愛
ヴェルトが友人からの手紙を手に辺境伯令嬢であるレィディアンスの元を訪れたのは、その手紙に「詳細は彼女に聞け」と書いてあったからだ。
簡単にいうと、手紙の内容は「学園で問題を起こした平民──エボニーを妻として引き取ってくれ」というものだった。
一方その話を聞いてしまった伯爵令嬢のオリーブは動揺していた。
ヴェルトとは静かに愛を育んできた。そんな自分を差し置いて、言われるがまま平民を妻に迎えてしまうのだろうか。
そんなオリーブの気持ちを知るはずもないエボニーは、辺境伯邸で行儀見習いをすることになる。
オリーブは何とかしてヴェルトを取り戻そうと画策し、そのことを咎められてしまう。もう後は無い。
オリーブが最後の望みをかけてヴェルトに自分を選んで欲しいと懇願する中、レィディアンスが静かに口を開いた。
「で、そろそろお前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか」
「はい?」
ヴェルトは自分が何を言われたのか全く理解が出来なかった。
*--*--*
覗いてくださりありがとうございます。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
★全31話7時19時更新で、全話予約投稿済みです。
★★「このお話だけ読んでいただいてもOKです!」という前提のもと↓↓↓
このお話は独立した一つのお話ですが、「で。」シリーズのサイドストーリーでもあり、第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」の「エボニーその後」でもあります(あるいは「最終話」のその後)。
第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」
第二弾「で、あなたが私に嫌がらせをする理由を伺っても?」
第三弾「で、あなたが彼に嫌がらせをする理由をお話しいただいても?」
どれも女性向けHOTランキングに入り、特に第二弾はHOT一位になることが出来ました!(*´▽`人)アリガトウ
もしよかったら宜しくお願いしますね!

結婚30年、契約満了したので離婚しませんか?
おもちのかたまり
恋愛
恋愛・小説 11位になりました!
皆様ありがとうございます。
「私、旦那様とお付き合いも甘いやり取りもしたことが無いから…ごめんなさい、ちょっと他人事なのかも。もちろん、貴方達の事は心から愛しているし、命より大事よ。」
眉根を下げて笑う母様に、一発じゃあ足りないなこれは。と確信した。幸い僕も姉さん達も祝福持ちだ。父様のような力極振りではないけれど、三対一なら勝ち目はある。
「じゃあ母様は、父様が嫌で離婚するわけではないんですか?」
ケーキを幸せそうに頬張っている母様は、僕の言葉にきょとん。と目を見開いて。…もしかすると、母様にとって父様は、関心を向ける程の相手ではないのかもしれない。嫌な予感に、今日一番の寒気がする。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
20年前に攻略対象だった父親と、悪役令嬢の取り巻きだった母親の現在のお話。
ハッピーエンド・バットエンド・メリーバットエンド・女性軽視・女性蔑視
上記に当てはまりますので、苦手な方、ご不快に感じる方はお気を付けください。
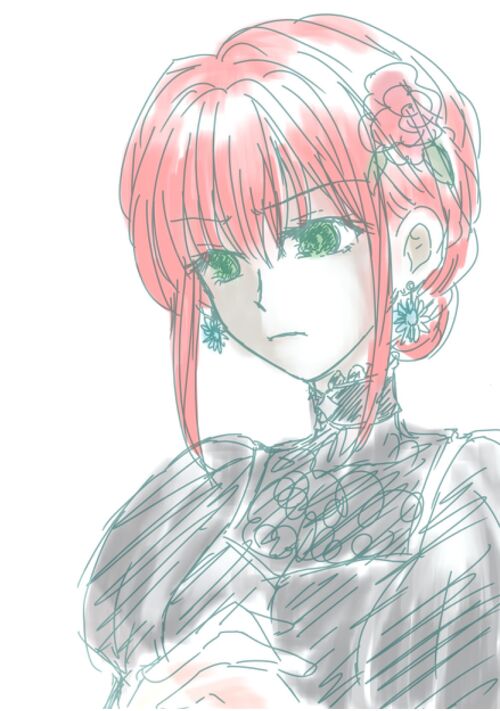
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

戦う聖女さま
有栖多于佳
恋愛
エニウェア大陸にある聖教国で、千年ぶりに行われた聖女召喚。
聖女として呼ばれた魂の佐藤愛(さとうめぐみ)は、魂の器として選ばれた孤児の少女タビタと混じり、聖教国を聖教皇から乗っ取り理想の国作りをしながら、周辺国も巻き込んだ改革を行っていく。
佐藤愛は、生前ある地方都市の最年少市長として改革を進めていたが、志半ばで病に倒れて死んでしまった。
やり残した後悔を、今度は異世界でタビタと一緒に解決していこうと張り切っている。悩んだら走る、困ったらスクワットという筋肉は裏切らない主義だが、そこそこインテリでもある。
タビタは、修道院の門前に捨てられていた孤児で、微力ながら光の属性があったため、聖女の器として育てられてきた。自己犠牲を生まれた時から叩き込まれてきたので、自己肯定感低めで、現実的でシニカルな物の見方もする。
東西南北の神官服の女たち、それぞれ聖教国の周辺国から選ばれて送り込まれた光の属性の巫女で、それぞれ国と個人が問題を抱えている。
小説家になろうにも掲載してます。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

わたしたちの庭
犬飼ハルノ
恋愛
「おい、ウェスト伯。いくらなんでもこんなみすぼらしい子どもに金を払えと?」
「まあまあ、ブルーノ伯爵。この子の母親もこんな感じでしたが、年ごろになると見違えるように成熟しましたよ。後妻のアリスは元妻の従妹です。あの一族の女は容姿も良いし、ぽんぽんと子どもを産みますよ」
「ふうん。そうか」
「直系の跡継ぎをお望みでしょう」
「まあな」
「しかも伯爵以上の正妻の子で年ごろの娘に婚約者がいないのは、この国ではこの子くらいしかもう残っていませんよ」
「ふ……。口が上手いなウェスト伯。なら、買い取ってやろうか、その子を」
目の前で醜悪な会話が繰り広げられる中、フィリスは思った。
まるで山羊の売買のようだと。
かくして。
フィリスの嫁ぎ先が決まった。
------------------------------------------
安定の見切り発車ですが、二月中に一日一回更新と完結に挑みます。
ヒロインのフィリスが自らの力と人々に支えられて幸せをつかむ話ですが、
序盤は暗く重い展開です。
タグを途中から追加します。
他サイトでも公開中。

「やはり鍛えることは、大切だな」
イチイ アキラ
恋愛
「こんなブスと結婚なんていやだ!」
その日、一つのお見合いがあった。
ヤロール伯爵家の三男、ライアンと。
クラレンス辺境伯家の跡取り娘、リューゼットの。
そして互いに挨拶を交わすその場にて。
ライアンが開幕早々、ぶちかましたのであった。
けれども……――。
「そうか。私も貴様のような生っ白くてか弱そうな、女みたいな顔の屑はごめんだ。気が合うな」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















