8 / 17
第2章 2-3 仮面の舞踏会と夫婦の噂
しおりを挟む
第2章 2-3 仮面の舞踏会と夫婦の噂
王都では、初夏の恒例行事である「仮面舞踏会」が開かれる季節になっていた。
貴族たちが顔を隠し、身分を超えて語らうその夜は、政治的駆け引きと恋の火花が入り混じる華やかな社交の場。
アークハート侯爵にも当然、招待状が届いていた。
銀の封蝋には王家の紋章。
文面には「ご夫人とともにお越しください」と丁寧に書かれている。
それを読んだセドリックは、少しだけ眉をひそめた。
「……どうやら、行かねばならぬようだ」
書斎で書類を整理していたレティシアが、顔を上げる。
「王家主催のものですのね」
「ああ。断るわけにはいかない。
……形式上の夫婦であっても、“妻”を同伴せねば不自然だ」
その言葉に、レティシアは小さく微笑んだ。
「つまり、私も“演じる”必要があるということですね」
「……すまない。負担をかける」
「いいえ。形式だけでも、妻としての務めを果たしますわ」
彼女の穏やかな返答に、セドリックはほんの一瞬だけ視線を逸らした。
淡い月明かりのような笑み――それが、妙に胸の奥に残った。
---
舞踏会の夜。
王都の中心にある大理石の宮殿は、光と音楽に包まれていた。
天井から吊り下げられた無数のシャンデリアが輝き、貴族たちは仮面越しに互いを探り合う。
レティシアが姿を現すと、会場のざわめきが一瞬だけ止んだ。
純白のドレスに銀糸の刺繍、顔には白銀の仮面。
その姿は、まるで雪の精のように幻想的だった。
人々が息を呑む中、彼女の隣に黒衣の男――セドリック・アークハート侯爵が立つ。
黒と白。
対照的な二人が並ぶ姿は、まるで絵画のようだった。
「アークハート侯爵夫妻だ……」「噂以上の美しさだ」「あの二人、本当に契約結婚なのか?」
囁きが広がる。
セドリックは無表情のままレティシアの手を取った。
「……大丈夫か?」
「ええ。少し緊張しているだけです」
「心配いらない。私がいる」
その低い声に、鼓動が一瞬だけ跳ねた。
彼の手は冷たいはずなのに、不思議と温かかった。
---
舞踏が始まると、仮面をつけた貴族たちが次々に踊り出る。
レティシアもセドリックに導かれ、ゆっくりとステップを踏んだ。
初めて踊るはずなのに、なぜか息が合う。
「意外ですわね」
「何が?」
「踊りはお好きでないと思っていました」
「嫌いではない。ただ……相手がいなかっただけだ」
「まあ、侯爵様にもそんな時代が?」
レティシアが微笑むと、彼の口元もわずかに緩む。
周囲から、再び囁きが起こった。
「見たか? 二人が笑っている……」「あれが氷の侯爵か?」「あの微笑は初めて見た」
レティシアはその声に気づき、ふと顔を伏せた。
仮面の下で、頬がわずかに熱を帯びる。
(……私たちは、契約夫婦なのに)
それでも、彼の手が自分を支えてくれる限り、その事実を忘れたくなった。
---
舞踏が終わると、貴族たちは次々に二人へ挨拶を寄せた。
「アークハート侯爵閣下、奥方様のご美貌には王都中が息を呑んでおります」
「ご夫婦仲がよろしいと伺いました。羨ましい限りですわ」
そんな言葉を聞くたび、レティシアは丁寧に微笑んで応じた。
一方で、セドリックは静かに頷くだけ。
だが、その無言がかえって「愛妻家」としての印象を強めていた。
「ふふ、まるで本当に――」
そう口にした瞬間、レティシアは我に返った。
“本当に”――その言葉が、胸の奥で妙に響いた。
---
夜が更ける頃、会場の隅で一人の令嬢が声をかけてきた。
赤い仮面に深紅のドレス。派手な装いの女――侯爵家の縁戚、エルナ夫人だった。
「まあ、レティシア夫人。今宵もお美しいわ」
「ごきげんよう、エルナ夫人」
「ねえ、ひとつだけ気になっていたの。……あなたと侯爵閣下、本当に“形式だけ”のご結婚なの?」
その問いに、レティシアは一瞬、言葉を失った。
周囲には他の貴族もいる。
この場で下手なことを言えば、翌日には王都中の噂になる。
「それは――」
と、その時。
「夫人、探しました」
背後から声がした。
振り返ると、セドリックが立っていた。
彼は何も言わず、レティシアの肩に手を置く。
「申し訳ない、エルナ夫人。妻は少し疲れている。失礼する」
そのまま彼は、彼女の手を取って会場を離れた。
背後で「まあ……なんて情熱的」「やっぱり本物だったのね」と囁く声が聞こえた。
レティシアは、引かれるまま廊下を歩きながら、小さく息を吐いた。
「……助けてくださったのですね」
「放っておけば、君が困る」
「“妻が困る”とは言わなかったのですね」
「……言うべきだったか?」
その答えに、レティシアは思わず笑ってしまった。
彼は少しだけ困ったように眉を寄せる。
「笑うことか?」
「ええ。侯爵様らしいと思って」
その笑顔を見たセドリックの表情が、わずかに緩んだ。
仮面の下に、確かに柔らかな笑みが宿る。
---
馬車に乗り込み、帰路につく。
車内には沈黙が漂っていたが、心地よい沈黙だった。
「……君は、社交の場が得意なのだな」
「ええ。昔は好きでしたわ。けれど今は、人の噂話ばかりで少し疲れます」
「私もだ。だが、今日の君は堂々としていた。……美しかった」
「……え?」
思わず言葉を失う。
セドリックは視線を窓に向けたまま、淡々と続けた。
「噂に惑わされず、己を曲げない女性は、美しいと思う」
胸の奥がじんわりと熱を帯びた。
それは、ただの称賛の言葉――それ以上でも以下でもない。
けれど、彼の声に嘘がなかった。
レティシアはそっと瞳を伏せた。
「……ありがとうございます。あなたも、少し笑えば素敵なのに」
彼がふとこちらを見る。
その金の瞳に、柔らかな光が宿っていた。
「笑うことを、忘れていたのかもしれない」
「では、これから少しずつ思い出してくださいね」
そう言って微笑むと、彼の唇がわずかに動いた。
まるで、ほんの少しだけ笑ったように。
---
屋敷に戻ると、夜風が二人を迎えた。
東棟と西棟――別々の道へ向かう前に、セドリックが口を開いた。
「……今日の君は、立派だった」
「ありがとうございます、旦那様。……貴方も、少しだけ優しかったですわ」
その言葉に、彼は驚いたように瞬きをした。
そして、ほんの短い沈黙のあとで答える。
「……気をつけよう」
「ふふ、それは褒め言葉です」
二人の間に、かすかな笑いが生まれた。
その音は、広い廊下に静かに溶けていく。
扉が閉まる瞬間、レティシアは胸に手を当てた。
心臓が早鐘のように鳴っている。
(おかしいわね。これは契約の関係のはずなのに……)
けれど、胸の奥に灯った小さな光は、もう消せそうになかった。
---
翌朝。
王都の新聞には、こんな見出しが躍っていた。
> 『氷の侯爵、ついに氷解す。
舞踏会で夫人に微笑みを――理想の夫婦、ここに誕生』
レティシアはその記事を見て、呆れたようにため息をついた。
「……理想の夫婦、ですって。困りましたわね」
机の上には、一輪の白いバラ。
前夜、彼が自ら庭から摘んだものだった。
記事を読んだセドリックがどんな顔をしているか――
想像しただけで、胸の奥がくすぐったくなる。
---
> 噂が真実になるのは、いつだろう。
形式だけの関係のはずが、
その夜の微笑みが、二人の距離を確かに近づけていた。
王都では、初夏の恒例行事である「仮面舞踏会」が開かれる季節になっていた。
貴族たちが顔を隠し、身分を超えて語らうその夜は、政治的駆け引きと恋の火花が入り混じる華やかな社交の場。
アークハート侯爵にも当然、招待状が届いていた。
銀の封蝋には王家の紋章。
文面には「ご夫人とともにお越しください」と丁寧に書かれている。
それを読んだセドリックは、少しだけ眉をひそめた。
「……どうやら、行かねばならぬようだ」
書斎で書類を整理していたレティシアが、顔を上げる。
「王家主催のものですのね」
「ああ。断るわけにはいかない。
……形式上の夫婦であっても、“妻”を同伴せねば不自然だ」
その言葉に、レティシアは小さく微笑んだ。
「つまり、私も“演じる”必要があるということですね」
「……すまない。負担をかける」
「いいえ。形式だけでも、妻としての務めを果たしますわ」
彼女の穏やかな返答に、セドリックはほんの一瞬だけ視線を逸らした。
淡い月明かりのような笑み――それが、妙に胸の奥に残った。
---
舞踏会の夜。
王都の中心にある大理石の宮殿は、光と音楽に包まれていた。
天井から吊り下げられた無数のシャンデリアが輝き、貴族たちは仮面越しに互いを探り合う。
レティシアが姿を現すと、会場のざわめきが一瞬だけ止んだ。
純白のドレスに銀糸の刺繍、顔には白銀の仮面。
その姿は、まるで雪の精のように幻想的だった。
人々が息を呑む中、彼女の隣に黒衣の男――セドリック・アークハート侯爵が立つ。
黒と白。
対照的な二人が並ぶ姿は、まるで絵画のようだった。
「アークハート侯爵夫妻だ……」「噂以上の美しさだ」「あの二人、本当に契約結婚なのか?」
囁きが広がる。
セドリックは無表情のままレティシアの手を取った。
「……大丈夫か?」
「ええ。少し緊張しているだけです」
「心配いらない。私がいる」
その低い声に、鼓動が一瞬だけ跳ねた。
彼の手は冷たいはずなのに、不思議と温かかった。
---
舞踏が始まると、仮面をつけた貴族たちが次々に踊り出る。
レティシアもセドリックに導かれ、ゆっくりとステップを踏んだ。
初めて踊るはずなのに、なぜか息が合う。
「意外ですわね」
「何が?」
「踊りはお好きでないと思っていました」
「嫌いではない。ただ……相手がいなかっただけだ」
「まあ、侯爵様にもそんな時代が?」
レティシアが微笑むと、彼の口元もわずかに緩む。
周囲から、再び囁きが起こった。
「見たか? 二人が笑っている……」「あれが氷の侯爵か?」「あの微笑は初めて見た」
レティシアはその声に気づき、ふと顔を伏せた。
仮面の下で、頬がわずかに熱を帯びる。
(……私たちは、契約夫婦なのに)
それでも、彼の手が自分を支えてくれる限り、その事実を忘れたくなった。
---
舞踏が終わると、貴族たちは次々に二人へ挨拶を寄せた。
「アークハート侯爵閣下、奥方様のご美貌には王都中が息を呑んでおります」
「ご夫婦仲がよろしいと伺いました。羨ましい限りですわ」
そんな言葉を聞くたび、レティシアは丁寧に微笑んで応じた。
一方で、セドリックは静かに頷くだけ。
だが、その無言がかえって「愛妻家」としての印象を強めていた。
「ふふ、まるで本当に――」
そう口にした瞬間、レティシアは我に返った。
“本当に”――その言葉が、胸の奥で妙に響いた。
---
夜が更ける頃、会場の隅で一人の令嬢が声をかけてきた。
赤い仮面に深紅のドレス。派手な装いの女――侯爵家の縁戚、エルナ夫人だった。
「まあ、レティシア夫人。今宵もお美しいわ」
「ごきげんよう、エルナ夫人」
「ねえ、ひとつだけ気になっていたの。……あなたと侯爵閣下、本当に“形式だけ”のご結婚なの?」
その問いに、レティシアは一瞬、言葉を失った。
周囲には他の貴族もいる。
この場で下手なことを言えば、翌日には王都中の噂になる。
「それは――」
と、その時。
「夫人、探しました」
背後から声がした。
振り返ると、セドリックが立っていた。
彼は何も言わず、レティシアの肩に手を置く。
「申し訳ない、エルナ夫人。妻は少し疲れている。失礼する」
そのまま彼は、彼女の手を取って会場を離れた。
背後で「まあ……なんて情熱的」「やっぱり本物だったのね」と囁く声が聞こえた。
レティシアは、引かれるまま廊下を歩きながら、小さく息を吐いた。
「……助けてくださったのですね」
「放っておけば、君が困る」
「“妻が困る”とは言わなかったのですね」
「……言うべきだったか?」
その答えに、レティシアは思わず笑ってしまった。
彼は少しだけ困ったように眉を寄せる。
「笑うことか?」
「ええ。侯爵様らしいと思って」
その笑顔を見たセドリックの表情が、わずかに緩んだ。
仮面の下に、確かに柔らかな笑みが宿る。
---
馬車に乗り込み、帰路につく。
車内には沈黙が漂っていたが、心地よい沈黙だった。
「……君は、社交の場が得意なのだな」
「ええ。昔は好きでしたわ。けれど今は、人の噂話ばかりで少し疲れます」
「私もだ。だが、今日の君は堂々としていた。……美しかった」
「……え?」
思わず言葉を失う。
セドリックは視線を窓に向けたまま、淡々と続けた。
「噂に惑わされず、己を曲げない女性は、美しいと思う」
胸の奥がじんわりと熱を帯びた。
それは、ただの称賛の言葉――それ以上でも以下でもない。
けれど、彼の声に嘘がなかった。
レティシアはそっと瞳を伏せた。
「……ありがとうございます。あなたも、少し笑えば素敵なのに」
彼がふとこちらを見る。
その金の瞳に、柔らかな光が宿っていた。
「笑うことを、忘れていたのかもしれない」
「では、これから少しずつ思い出してくださいね」
そう言って微笑むと、彼の唇がわずかに動いた。
まるで、ほんの少しだけ笑ったように。
---
屋敷に戻ると、夜風が二人を迎えた。
東棟と西棟――別々の道へ向かう前に、セドリックが口を開いた。
「……今日の君は、立派だった」
「ありがとうございます、旦那様。……貴方も、少しだけ優しかったですわ」
その言葉に、彼は驚いたように瞬きをした。
そして、ほんの短い沈黙のあとで答える。
「……気をつけよう」
「ふふ、それは褒め言葉です」
二人の間に、かすかな笑いが生まれた。
その音は、広い廊下に静かに溶けていく。
扉が閉まる瞬間、レティシアは胸に手を当てた。
心臓が早鐘のように鳴っている。
(おかしいわね。これは契約の関係のはずなのに……)
けれど、胸の奥に灯った小さな光は、もう消せそうになかった。
---
翌朝。
王都の新聞には、こんな見出しが躍っていた。
> 『氷の侯爵、ついに氷解す。
舞踏会で夫人に微笑みを――理想の夫婦、ここに誕生』
レティシアはその記事を見て、呆れたようにため息をついた。
「……理想の夫婦、ですって。困りましたわね」
机の上には、一輪の白いバラ。
前夜、彼が自ら庭から摘んだものだった。
記事を読んだセドリックがどんな顔をしているか――
想像しただけで、胸の奥がくすぐったくなる。
---
> 噂が真実になるのは、いつだろう。
形式だけの関係のはずが、
その夜の微笑みが、二人の距離を確かに近づけていた。
1
あなたにおすすめの小説

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

で、お前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか?
Debby
恋愛
ヴェルトが友人からの手紙を手に辺境伯令嬢であるレィディアンスの元を訪れたのは、その手紙に「詳細は彼女に聞け」と書いてあったからだ。
簡単にいうと、手紙の内容は「学園で問題を起こした平民──エボニーを妻として引き取ってくれ」というものだった。
一方その話を聞いてしまった伯爵令嬢のオリーブは動揺していた。
ヴェルトとは静かに愛を育んできた。そんな自分を差し置いて、言われるがまま平民を妻に迎えてしまうのだろうか。
そんなオリーブの気持ちを知るはずもないエボニーは、辺境伯邸で行儀見習いをすることになる。
オリーブは何とかしてヴェルトを取り戻そうと画策し、そのことを咎められてしまう。もう後は無い。
オリーブが最後の望みをかけてヴェルトに自分を選んで欲しいと懇願する中、レィディアンスが静かに口を開いた。
「で、そろそろお前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか」
「はい?」
ヴェルトは自分が何を言われたのか全く理解が出来なかった。
*--*--*
覗いてくださりありがとうございます。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
★全31話7時19時更新で、全話予約投稿済みです。
★★「このお話だけ読んでいただいてもOKです!」という前提のもと↓↓↓
このお話は独立した一つのお話ですが、「で。」シリーズのサイドストーリーでもあり、第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」の「エボニーその後」でもあります(あるいは「最終話」のその後)。
第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」
第二弾「で、あなたが私に嫌がらせをする理由を伺っても?」
第三弾「で、あなたが彼に嫌がらせをする理由をお話しいただいても?」
どれも女性向けHOTランキングに入り、特に第二弾はHOT一位になることが出来ました!(*´▽`人)アリガトウ
もしよかったら宜しくお願いしますね!
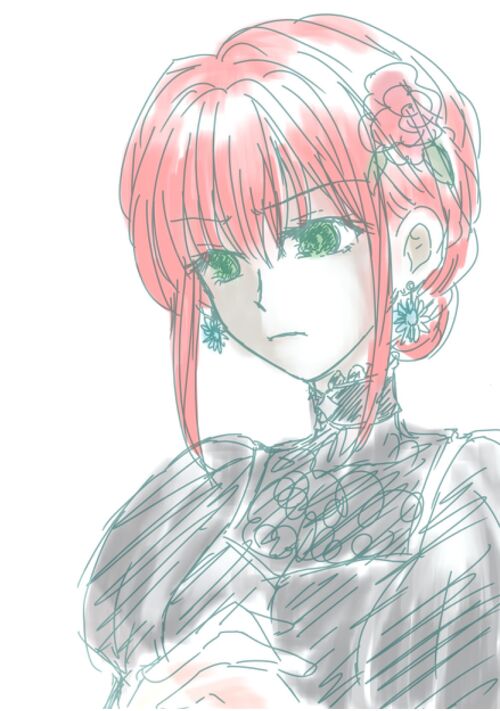
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

戦う聖女さま
有栖多于佳
恋愛
エニウェア大陸にある聖教国で、千年ぶりに行われた聖女召喚。
聖女として呼ばれた魂の佐藤愛(さとうめぐみ)は、魂の器として選ばれた孤児の少女タビタと混じり、聖教国を聖教皇から乗っ取り理想の国作りをしながら、周辺国も巻き込んだ改革を行っていく。
佐藤愛は、生前ある地方都市の最年少市長として改革を進めていたが、志半ばで病に倒れて死んでしまった。
やり残した後悔を、今度は異世界でタビタと一緒に解決していこうと張り切っている。悩んだら走る、困ったらスクワットという筋肉は裏切らない主義だが、そこそこインテリでもある。
タビタは、修道院の門前に捨てられていた孤児で、微力ながら光の属性があったため、聖女の器として育てられてきた。自己犠牲を生まれた時から叩き込まれてきたので、自己肯定感低めで、現実的でシニカルな物の見方もする。
東西南北の神官服の女たち、それぞれ聖教国の周辺国から選ばれて送り込まれた光の属性の巫女で、それぞれ国と個人が問題を抱えている。
小説家になろうにも掲載してます。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

天才魔術師の仮面令嬢は王弟に執着されてます
白羽 雪乃
恋愛
姉の悪意で顔半分に大火傷をしてしまった主人公、大火傷をしてから顔が隠れる仮面をするようになった。
たけど仮面の下には大きい秘密があり、それを知ってるのは主人公が信頼してる人だけ
仮面の下の秘密とは?

わたしたちの庭
犬飼ハルノ
恋愛
「おい、ウェスト伯。いくらなんでもこんなみすぼらしい子どもに金を払えと?」
「まあまあ、ブルーノ伯爵。この子の母親もこんな感じでしたが、年ごろになると見違えるように成熟しましたよ。後妻のアリスは元妻の従妹です。あの一族の女は容姿も良いし、ぽんぽんと子どもを産みますよ」
「ふうん。そうか」
「直系の跡継ぎをお望みでしょう」
「まあな」
「しかも伯爵以上の正妻の子で年ごろの娘に婚約者がいないのは、この国ではこの子くらいしかもう残っていませんよ」
「ふ……。口が上手いなウェスト伯。なら、買い取ってやろうか、その子を」
目の前で醜悪な会話が繰り広げられる中、フィリスは思った。
まるで山羊の売買のようだと。
かくして。
フィリスの嫁ぎ先が決まった。
------------------------------------------
安定の見切り発車ですが、二月中に一日一回更新と完結に挑みます。
ヒロインのフィリスが自らの力と人々に支えられて幸せをつかむ話ですが、
序盤は暗く重い展開です。
タグを途中から追加します。
他サイトでも公開中。

「やはり鍛えることは、大切だな」
イチイ アキラ
恋愛
「こんなブスと結婚なんていやだ!」
その日、一つのお見合いがあった。
ヤロール伯爵家の三男、ライアンと。
クラレンス辺境伯家の跡取り娘、リューゼットの。
そして互いに挨拶を交わすその場にて。
ライアンが開幕早々、ぶちかましたのであった。
けれども……――。
「そうか。私も貴様のような生っ白くてか弱そうな、女みたいな顔の屑はごめんだ。気が合うな」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















