9 / 17
2-4 小さな嫉妬と、初めての名前呼び
しおりを挟む
第2章 2-4 小さな嫉妬と、初めての名前呼び
仮面舞踏会から数日が経った。
その夜の記事――『氷の侯爵、ついに氷解す』――は王都中の話題となり、貴族たちの間で噂が絶えなかった。
「侯爵夫妻は理想の夫婦」「あの微笑みは真実の愛の証」――そんな憶測が飛び交い、彼らの知らぬところで“完璧な愛妻家”という称号が勝手に定着していく。
もちろん、当の本人たちは困惑していた。
「……困りましたわね、旦那様。もう買い物にも出られません」
新聞を畳みながら、レティシアが苦笑する。
「まったく……王都の記者は筆が軽すぎる」
セドリックはため息をついた。
「次に外に出れば、また妙な記事にされるだろう」
「“氷の侯爵、ついに溶けて愛に溺れる”――なんて見出しが出たらどうしましょう」
「冗談ではない」
セドリックの苦々しい表情に、レティシアは思わず吹き出した。
「ふふ……失礼。けれど、皆様がそう信じてくださるのなら、それも悪くありませんわ。
少なくとも、私たちの“形式結婚”を疑う人はいなくなる」
「……それはそうだな」
彼の口調は冷静だが、どこか不機嫌に聞こえた。
レティシアはその違和感に首をかしげる。
(どうしたのかしら……まるで、何か気にしているような)
翌日。
侯爵邸には、社交界の有力者たちからの手紙が山のように届いた。
招待状、祝辞、そして――噂の真偽を確かめたいという下心混じりの訪問依頼。
レティシアはそれらを整理していたが、その中にひときわ鮮やかな封筒を見つけた。
金の縁取りに、薔薇の紋章。差出人は――第二王子ハーヴェイ。
「……第二王子殿下?」
文面を開くと、流麗な筆跡でこう記されていた。
“先日の舞踏会にて、貴殿の夫人のご姿を拝見し、深く感銘を受けました。
ぜひ次回の晩餐会にご夫婦でご臨席願いたい。”
――夫人のご姿に感銘、という一文に、レティシアはわずかに眉をひそめる。
それでも、丁寧な文体に悪意は感じられなかった。
「侯爵様にお見せしなければ」
そう思って書斎を訪れると、セドリックはすでにその手紙を読んでいた。
「……殿下からの招待か」
「ええ。出席なさるおつもりですか?」
彼は無言のまま、手紙を机に置いた。
そして、低い声で言った。
「……あの男の目は信用できん」
「殿下を、ですか?」
「昔から、気に入ったものは何でも自分のものにしようとする癖がある。
特に、美しいものには目がない」
その言葉に、レティシアの胸がわずかに跳ねた。
“美しいもの”――それは今、彼女のことを指している。
「ふふ……まさか、私が奪われるとでも?」
「油断は禁物だ」
短い返答。
それは護るようでもあり、どこか苛立ちを含んでいた。
(……もしかして、嫉妬?)
そう思った瞬間、胸の奥が熱くなる。
まさか、氷の侯爵が嫉妬を――?
彼が顔を背けたのを見て、確信に変わった。
晩餐会の夜。
レティシアは淡い青のドレスに身を包み、髪には白い小花を飾った。
セドリックは黒の燕尾服に青のタイ。
二人並ぶと、まるで月と夜空のように調和していた。
王子主催の晩餐会は、思ったよりも形式ばったものだった。
長いテーブルに並ぶ貴族たち。
第二王子ハーヴェイは中央に座り、穏やかに微笑んでいる。
「おお、アークハート侯爵。ようこそ」
彼は立ち上がり、両手を広げた。
「そして――レティシア夫人。あなたの美しさは、まるで夜明けの女神のようだ」
その口ぶりに、セドリックの眉がわずかに動いた。
「光栄に存じます、殿下」
レティシアは完璧な笑みで応じる。
だが、彼の隣でセドリックのグラスがわずかに鳴った。
周囲の視線が集まる中、ハーヴェイは構わず続ける。
「侯爵、ご夫人を少しお借りしても?」
「……何のご用でしょうか」
「この会の主催として、夫人に乾杯の音頭をお願いしたいのです」
一瞬の沈黙。
セドリックは明らかに不快そうに目を細めたが、レティシアが先に微笑んだ。
「もちろん、光栄ですわ。――旦那様?」
その一言で、彼は小さく息を吐いた。
彼女を信じるように、頷く。
レティシアはグラスを掲げ、優雅に立ち上がった。
「皆様、本日はこの素晴らしい場にお招きいただき、誠にありがとうございます。
夫として、そして臣下として、侯爵が国を支えていることを、妻として誇りに思っております」
その言葉に、会場が静まり返った。
そして拍手が起こる。
ハーヴェイでさえ、言葉を失っていた。
レティシアが席に戻ると、セドリックは低く囁いた。
「……見事だ」
「お褒めいただけて光栄です、旦那様」
彼の声が、わずかに掠れていた。
帰りの馬車の中。
レティシアは、外の夜景を眺めながら微笑んでいた。
彼の横顔が窓の光に照らされる。
いつもより、少しだけ険しい。
「旦那様。まさか、本当に嫉妬なさったの?」
唐突な問いに、セドリックはわずかに肩を強張らせた。
「……何の話だ」
「ふふ。顔に出ていますわよ」
彼はしばらく沈黙した後、低く呟いた。
「……もし、君が他の男に笑いかけたら――私は不快だ。
それが何と呼ばれる感情なのかは、私にも分からない」
その言葉に、レティシアの胸が一気に熱を帯びた。
言葉にならないほど、心が震える。
「……それは、嫉妬ですわ、旦那様」
「……そうか」
彼の指が、そっと彼女の手に触れる。
その一瞬のぬくもりが、すべてを語っていた。
屋敷に戻ると、夜の風がひんやりと頬を撫でた。
東棟へ向かう途中、レティシアは足を止めた。
「旦那様」
「何だ?」
「……名前で呼んでいただけませんか?」
「名前、を?」
「ええ。“夫人”でも“妻”でもなく、私自身として。
この結婚が形式だけだとしても、せめて――名前で呼ばれたいのです」
セドリックは目を伏せ、しばらく何も言わなかった。
静かな夜気が流れ、遠くでフクロウの声が響く。
そして――
「……レティシア」
その声は驚くほど優しく、低く響いた。
まるで、長い冬を越えた春の風のようだった。
レティシアは息を呑み、そして微笑んだ。
「はい、旦那様」
彼はゆっくりと首を振る。
「……今は、“旦那様”ではなく、セドリックでいい」
「――セドリック」
名前を呼んだ瞬間、二人の間の距離が、確かに一歩、近づいた。
その夜、レティシアの寝室の机には一輪の白いバラがあった。
だが、いつもと違い――その花弁の中心には、淡い赤が差していた。
彼が摘んだのだろう。
“白い契約”の象徴に、初めて色が宿る。
レティシアは花を胸に抱き、静かに目を閉じた。
(――これは、恋ではない。
でも、恋よりも確かな何かが、私たちの間に生まれ始めている)
形式だけの結婚が、少しずつ色を帯びていく。
氷の侯爵が呼んだ、たった一言の名前。
それは、レティシアの心に灯った“初恋”の音だった。
🌹
仮面舞踏会から数日が経った。
その夜の記事――『氷の侯爵、ついに氷解す』――は王都中の話題となり、貴族たちの間で噂が絶えなかった。
「侯爵夫妻は理想の夫婦」「あの微笑みは真実の愛の証」――そんな憶測が飛び交い、彼らの知らぬところで“完璧な愛妻家”という称号が勝手に定着していく。
もちろん、当の本人たちは困惑していた。
「……困りましたわね、旦那様。もう買い物にも出られません」
新聞を畳みながら、レティシアが苦笑する。
「まったく……王都の記者は筆が軽すぎる」
セドリックはため息をついた。
「次に外に出れば、また妙な記事にされるだろう」
「“氷の侯爵、ついに溶けて愛に溺れる”――なんて見出しが出たらどうしましょう」
「冗談ではない」
セドリックの苦々しい表情に、レティシアは思わず吹き出した。
「ふふ……失礼。けれど、皆様がそう信じてくださるのなら、それも悪くありませんわ。
少なくとも、私たちの“形式結婚”を疑う人はいなくなる」
「……それはそうだな」
彼の口調は冷静だが、どこか不機嫌に聞こえた。
レティシアはその違和感に首をかしげる。
(どうしたのかしら……まるで、何か気にしているような)
翌日。
侯爵邸には、社交界の有力者たちからの手紙が山のように届いた。
招待状、祝辞、そして――噂の真偽を確かめたいという下心混じりの訪問依頼。
レティシアはそれらを整理していたが、その中にひときわ鮮やかな封筒を見つけた。
金の縁取りに、薔薇の紋章。差出人は――第二王子ハーヴェイ。
「……第二王子殿下?」
文面を開くと、流麗な筆跡でこう記されていた。
“先日の舞踏会にて、貴殿の夫人のご姿を拝見し、深く感銘を受けました。
ぜひ次回の晩餐会にご夫婦でご臨席願いたい。”
――夫人のご姿に感銘、という一文に、レティシアはわずかに眉をひそめる。
それでも、丁寧な文体に悪意は感じられなかった。
「侯爵様にお見せしなければ」
そう思って書斎を訪れると、セドリックはすでにその手紙を読んでいた。
「……殿下からの招待か」
「ええ。出席なさるおつもりですか?」
彼は無言のまま、手紙を机に置いた。
そして、低い声で言った。
「……あの男の目は信用できん」
「殿下を、ですか?」
「昔から、気に入ったものは何でも自分のものにしようとする癖がある。
特に、美しいものには目がない」
その言葉に、レティシアの胸がわずかに跳ねた。
“美しいもの”――それは今、彼女のことを指している。
「ふふ……まさか、私が奪われるとでも?」
「油断は禁物だ」
短い返答。
それは護るようでもあり、どこか苛立ちを含んでいた。
(……もしかして、嫉妬?)
そう思った瞬間、胸の奥が熱くなる。
まさか、氷の侯爵が嫉妬を――?
彼が顔を背けたのを見て、確信に変わった。
晩餐会の夜。
レティシアは淡い青のドレスに身を包み、髪には白い小花を飾った。
セドリックは黒の燕尾服に青のタイ。
二人並ぶと、まるで月と夜空のように調和していた。
王子主催の晩餐会は、思ったよりも形式ばったものだった。
長いテーブルに並ぶ貴族たち。
第二王子ハーヴェイは中央に座り、穏やかに微笑んでいる。
「おお、アークハート侯爵。ようこそ」
彼は立ち上がり、両手を広げた。
「そして――レティシア夫人。あなたの美しさは、まるで夜明けの女神のようだ」
その口ぶりに、セドリックの眉がわずかに動いた。
「光栄に存じます、殿下」
レティシアは完璧な笑みで応じる。
だが、彼の隣でセドリックのグラスがわずかに鳴った。
周囲の視線が集まる中、ハーヴェイは構わず続ける。
「侯爵、ご夫人を少しお借りしても?」
「……何のご用でしょうか」
「この会の主催として、夫人に乾杯の音頭をお願いしたいのです」
一瞬の沈黙。
セドリックは明らかに不快そうに目を細めたが、レティシアが先に微笑んだ。
「もちろん、光栄ですわ。――旦那様?」
その一言で、彼は小さく息を吐いた。
彼女を信じるように、頷く。
レティシアはグラスを掲げ、優雅に立ち上がった。
「皆様、本日はこの素晴らしい場にお招きいただき、誠にありがとうございます。
夫として、そして臣下として、侯爵が国を支えていることを、妻として誇りに思っております」
その言葉に、会場が静まり返った。
そして拍手が起こる。
ハーヴェイでさえ、言葉を失っていた。
レティシアが席に戻ると、セドリックは低く囁いた。
「……見事だ」
「お褒めいただけて光栄です、旦那様」
彼の声が、わずかに掠れていた。
帰りの馬車の中。
レティシアは、外の夜景を眺めながら微笑んでいた。
彼の横顔が窓の光に照らされる。
いつもより、少しだけ険しい。
「旦那様。まさか、本当に嫉妬なさったの?」
唐突な問いに、セドリックはわずかに肩を強張らせた。
「……何の話だ」
「ふふ。顔に出ていますわよ」
彼はしばらく沈黙した後、低く呟いた。
「……もし、君が他の男に笑いかけたら――私は不快だ。
それが何と呼ばれる感情なのかは、私にも分からない」
その言葉に、レティシアの胸が一気に熱を帯びた。
言葉にならないほど、心が震える。
「……それは、嫉妬ですわ、旦那様」
「……そうか」
彼の指が、そっと彼女の手に触れる。
その一瞬のぬくもりが、すべてを語っていた。
屋敷に戻ると、夜の風がひんやりと頬を撫でた。
東棟へ向かう途中、レティシアは足を止めた。
「旦那様」
「何だ?」
「……名前で呼んでいただけませんか?」
「名前、を?」
「ええ。“夫人”でも“妻”でもなく、私自身として。
この結婚が形式だけだとしても、せめて――名前で呼ばれたいのです」
セドリックは目を伏せ、しばらく何も言わなかった。
静かな夜気が流れ、遠くでフクロウの声が響く。
そして――
「……レティシア」
その声は驚くほど優しく、低く響いた。
まるで、長い冬を越えた春の風のようだった。
レティシアは息を呑み、そして微笑んだ。
「はい、旦那様」
彼はゆっくりと首を振る。
「……今は、“旦那様”ではなく、セドリックでいい」
「――セドリック」
名前を呼んだ瞬間、二人の間の距離が、確かに一歩、近づいた。
その夜、レティシアの寝室の机には一輪の白いバラがあった。
だが、いつもと違い――その花弁の中心には、淡い赤が差していた。
彼が摘んだのだろう。
“白い契約”の象徴に、初めて色が宿る。
レティシアは花を胸に抱き、静かに目を閉じた。
(――これは、恋ではない。
でも、恋よりも確かな何かが、私たちの間に生まれ始めている)
形式だけの結婚が、少しずつ色を帯びていく。
氷の侯爵が呼んだ、たった一言の名前。
それは、レティシアの心に灯った“初恋”の音だった。
🌹
1
あなたにおすすめの小説

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

で、お前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか?
Debby
恋愛
ヴェルトが友人からの手紙を手に辺境伯令嬢であるレィディアンスの元を訪れたのは、その手紙に「詳細は彼女に聞け」と書いてあったからだ。
簡単にいうと、手紙の内容は「学園で問題を起こした平民──エボニーを妻として引き取ってくれ」というものだった。
一方その話を聞いてしまった伯爵令嬢のオリーブは動揺していた。
ヴェルトとは静かに愛を育んできた。そんな自分を差し置いて、言われるがまま平民を妻に迎えてしまうのだろうか。
そんなオリーブの気持ちを知るはずもないエボニーは、辺境伯邸で行儀見習いをすることになる。
オリーブは何とかしてヴェルトを取り戻そうと画策し、そのことを咎められてしまう。もう後は無い。
オリーブが最後の望みをかけてヴェルトに自分を選んで欲しいと懇願する中、レィディアンスが静かに口を開いた。
「で、そろそろお前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか」
「はい?」
ヴェルトは自分が何を言われたのか全く理解が出来なかった。
*--*--*
覗いてくださりありがとうございます。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
★全31話7時19時更新で、全話予約投稿済みです。
★★「このお話だけ読んでいただいてもOKです!」という前提のもと↓↓↓
このお話は独立した一つのお話ですが、「で。」シリーズのサイドストーリーでもあり、第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」の「エボニーその後」でもあります(あるいは「最終話」のその後)。
第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」
第二弾「で、あなたが私に嫌がらせをする理由を伺っても?」
第三弾「で、あなたが彼に嫌がらせをする理由をお話しいただいても?」
どれも女性向けHOTランキングに入り、特に第二弾はHOT一位になることが出来ました!(*´▽`人)アリガトウ
もしよかったら宜しくお願いしますね!

結婚30年、契約満了したので離婚しませんか?
おもちのかたまり
恋愛
恋愛・小説 11位になりました!
皆様ありがとうございます。
「私、旦那様とお付き合いも甘いやり取りもしたことが無いから…ごめんなさい、ちょっと他人事なのかも。もちろん、貴方達の事は心から愛しているし、命より大事よ。」
眉根を下げて笑う母様に、一発じゃあ足りないなこれは。と確信した。幸い僕も姉さん達も祝福持ちだ。父様のような力極振りではないけれど、三対一なら勝ち目はある。
「じゃあ母様は、父様が嫌で離婚するわけではないんですか?」
ケーキを幸せそうに頬張っている母様は、僕の言葉にきょとん。と目を見開いて。…もしかすると、母様にとって父様は、関心を向ける程の相手ではないのかもしれない。嫌な予感に、今日一番の寒気がする。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
20年前に攻略対象だった父親と、悪役令嬢の取り巻きだった母親の現在のお話。
ハッピーエンド・バットエンド・メリーバットエンド・女性軽視・女性蔑視
上記に当てはまりますので、苦手な方、ご不快に感じる方はお気を付けください。
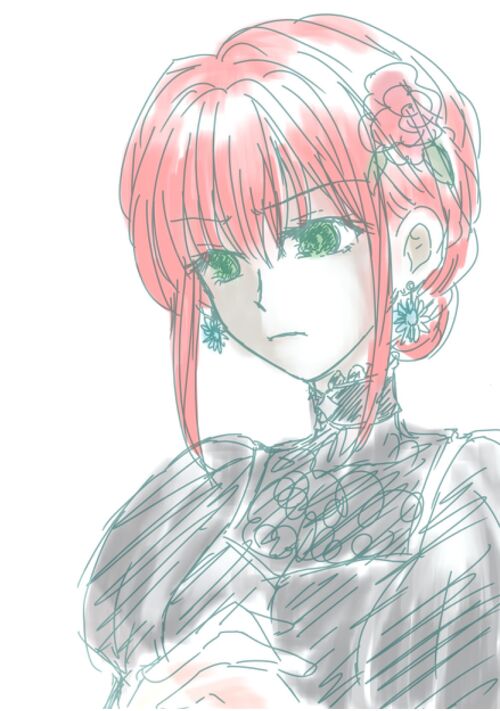
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

戦う聖女さま
有栖多于佳
恋愛
エニウェア大陸にある聖教国で、千年ぶりに行われた聖女召喚。
聖女として呼ばれた魂の佐藤愛(さとうめぐみ)は、魂の器として選ばれた孤児の少女タビタと混じり、聖教国を聖教皇から乗っ取り理想の国作りをしながら、周辺国も巻き込んだ改革を行っていく。
佐藤愛は、生前ある地方都市の最年少市長として改革を進めていたが、志半ばで病に倒れて死んでしまった。
やり残した後悔を、今度は異世界でタビタと一緒に解決していこうと張り切っている。悩んだら走る、困ったらスクワットという筋肉は裏切らない主義だが、そこそこインテリでもある。
タビタは、修道院の門前に捨てられていた孤児で、微力ながら光の属性があったため、聖女の器として育てられてきた。自己犠牲を生まれた時から叩き込まれてきたので、自己肯定感低めで、現実的でシニカルな物の見方もする。
東西南北の神官服の女たち、それぞれ聖教国の周辺国から選ばれて送り込まれた光の属性の巫女で、それぞれ国と個人が問題を抱えている。
小説家になろうにも掲載してます。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

わたしたちの庭
犬飼ハルノ
恋愛
「おい、ウェスト伯。いくらなんでもこんなみすぼらしい子どもに金を払えと?」
「まあまあ、ブルーノ伯爵。この子の母親もこんな感じでしたが、年ごろになると見違えるように成熟しましたよ。後妻のアリスは元妻の従妹です。あの一族の女は容姿も良いし、ぽんぽんと子どもを産みますよ」
「ふうん。そうか」
「直系の跡継ぎをお望みでしょう」
「まあな」
「しかも伯爵以上の正妻の子で年ごろの娘に婚約者がいないのは、この国ではこの子くらいしかもう残っていませんよ」
「ふ……。口が上手いなウェスト伯。なら、買い取ってやろうか、その子を」
目の前で醜悪な会話が繰り広げられる中、フィリスは思った。
まるで山羊の売買のようだと。
かくして。
フィリスの嫁ぎ先が決まった。
------------------------------------------
安定の見切り発車ですが、二月中に一日一回更新と完結に挑みます。
ヒロインのフィリスが自らの力と人々に支えられて幸せをつかむ話ですが、
序盤は暗く重い展開です。
タグを途中から追加します。
他サイトでも公開中。

「やはり鍛えることは、大切だな」
イチイ アキラ
恋愛
「こんなブスと結婚なんていやだ!」
その日、一つのお見合いがあった。
ヤロール伯爵家の三男、ライアンと。
クラレンス辺境伯家の跡取り娘、リューゼットの。
そして互いに挨拶を交わすその場にて。
ライアンが開幕早々、ぶちかましたのであった。
けれども……――。
「そうか。私も貴様のような生っ白くてか弱そうな、女みたいな顔の屑はごめんだ。気が合うな」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















