10 / 17
3-1 夫婦の距離と、不意のぬくもり
しおりを挟む
第3章 3-1 夫婦の距離と、不意のぬくもり
春の風がやわらかく侯爵邸の庭を撫でていた。
冬の間、眠っていたバラが少しずつ蕾をつけ始め、温室では新芽が顔を覗かせている。
レティシアは庭師たちの作業を見守りながら、そっと笑みをこぼした。
「……この庭も、だいぶ息を吹き返しましたわね」
「貴女が世話をしてくれたおかげだ」
背後から穏やかな声がした。
振り向けば、セドリックが立っていた。
黒い執務服のまま、朝の光を受けてその銀灰色の瞳がきらめいている。
「お忙しいのに、こんな時間に?」
「視察のついでだ。屋敷の者たちが最近、生き生きとしている。……君の影響だろう」
「まあ、恐れ多いお言葉ですわ」
軽く会釈するレティシアに、セドリックはわずかに微笑んだ。
以前は、彼が微笑むなど考えられなかった。
冷徹と呼ばれるほど表情を崩さなかった彼が、今はこうして穏やかに言葉を交わしてくれる。
それが不思議で、そして嬉しかった。
---
昼過ぎ、書斎の机には山のような書類が積まれていた。
レティシアは手伝いのために入室したが、セドリックの目の下には濃い影が見える。
「旦那様、少しお休みになってくださいませ」
「これを片づけてからだ。報告書の確認が遅れれば、部下が困る」
「ですが、無理をすれば余計に仕事が滞りますわ」
言いながら、彼の手から書類をすっと取り上げる。
セドリックは驚いたように瞬きをした。
「……君、私の机に手を出すのは初めてだな」
「奥様ですもの。多少の越権はお許しいただけるでしょう?」
にっこりと笑ってみせると、彼は口元を押さえて苦笑した。
「……勝てないな」
結局、レティシアは彼を半ば強引にソファへ座らせ、紅茶を用意した。
香り高いカモミールティー。
彼女の手から湯気の立つカップを受け取った彼は、静かに息をついた。
「……温かいな」
「お茶がですか?」
「いや――君の心遣いが、だ」
その言葉に、レティシアの胸がどくんと跳ねた。
何気ない一言なのに、まるで恋人に囁かれたように甘い響きだった。
(な、何を考えているの……わたくし、落ち着きなさい! これはただの社交辞令……)
自分に言い聞かせながらも、頬の熱は下がらない。
---
その夜。
書斎での仕事を終えたセドリックが自室へ戻ると、廊下の窓辺でレティシアが月を見上げていた。
彼女の金糸の髪が月光を受けて輝いている。
まるで、白い花のようだった。
「こんな時間にどうした」
「眠れなくて……。少し、夜風に当たっておりました」
「風が冷える。体を冷やすな」
そう言いながら、彼は自分の上着を彼女の肩にかけた。
突然のことで、レティシアは小さく息を呑んだ。
「せ、セドリック様……?」
「君が風邪をひいたら、屋敷が混乱する」
「……それだけ、ですの?」
自分でも意地のような言葉だった。
けれど、セドリックは真っ直ぐに彼女を見つめる。
「それだけではない。君に何かあると――私が、嫌だ」
短い言葉だったが、その中にどれだけの感情が詰まっているか、レティシアには分かった。
胸の奥で何かが溶ける音がした。
あの夜に聞いた名前呼びから、確かに何かが変わり始めている。
---
翌朝。
執務中にセドリックがふと目を上げると、窓の外でレティシアがメイドと一緒に花の世話をしていた。
風に揺れる金髪が光に包まれ、笑うたびに花よりも美しく見える。
彼は知らず知らず手を止め、しばらく見惚れていた。
だが、ドアのノックで現実に引き戻される。
秘書官が書類を差し出しながら、にやりと笑った。
「旦那様、最近お優しいですね。夫人の影響でしょうか?」
「……仕事に集中しろ」
咳払いをしながら書類を受け取る。
だが、顔の熱は隠せなかった。
---
その日の午後、事件が起きた。
温室で花の剪定をしていたレティシアが、誤って指を切ってしまったのだ。
小さな傷だったが、血を見た瞬間にセドリックの表情が変わった。
「大丈夫ですわ、少し切っただけです」
「放っておけるか」
彼は即座に手を取り、ハンカチを巻きつける。
その手つきは驚くほど丁寧で、そして――震えていた。
「……申し訳ありません。わざわざ」
「謝るな。君が傷つくのは……見たくない」
その言葉に、レティシアの胸が締めつけられた。
彼の声は静かだが、どこか必死だった。
「セドリック様……」
「もう“様”はつけるなと言っただろう」
「……セドリック」
名前を呼ぶと、彼はふっと目を細めた。
その瞬間、彼女の手を包む指が少し強くなった。
「その方が、ずっといい」
心臓が跳ねる。
彼の言葉は、まるで恋の告白のように響いた。
---
夕暮れ、レティシアは一人、温室の中で息を整えていた。
指の痛みよりも、胸の鼓動の方が落ち着かない。
(あの人は、どうしてあんなに優しいの? 契約の結婚なのに……)
思えば、最初は冷たくて、必要最低限の会話しかなかった。
それが今では、目が合うたびに微笑んでくれる。
名前を呼んでくれる。
気づけば、その声が一日の楽しみになっていた。
(……私、まさか、恋を……?)
自分の頬が熱い。
答えを出すのが怖かった。
---
一方そのころ、セドリックは寝室で机に向かっていた。
だが、手元の書類はまったく頭に入らない。
レティシアの笑顔が脳裏から離れないのだ。
「……おかしいな」
独りごちる。
これまで、どんな美女を見ても心が動いたことなどなかった。
政治的な婚約、形式的な愛。それが貴族の常だった。
だが今――彼は、たった一人の笑顔に心を奪われている。
「形式のはずだったのに……」
その言葉は、静かな夜に溶けた。
---
夜更け。
レティシアが寝室へ戻ると、机の上にまた一輪の花が置かれていた。
昨日と同じ白薔薇――だが、今夜の花は蕾の中心が深紅に染まっている。
そして、その花弁の下に小さな紙片が添えられていた。
> 『今日は、ありがとう。
どうか無理をするな。
――セドリック』
その短い一文を見た瞬間、レティシアの目が潤んだ。
指先で花を撫で、胸に抱きしめる。
「……不器用な人ですわね」
けれど、その不器用さが、愛おしかった。
---
侯爵と令嬢。
形式のはずだった二人の結婚は、もう“形式”の枠を超え始めていた。
名前を呼ぶこと、手を包むこと、花を贈ること――
そのどれもが、心の距離を縮めていく。
そして、レティシアはまだ知らなかった。
その夜、セドリックもまた、同じ白薔薇を手にして、同じ月を見上げていたことを――。
---
> 契約の夫婦が、互いを想い合うようになった瞬間。
それは恋の始まりでもあり、運命の歯車が回り出す音でもあった。
春の風がやわらかく侯爵邸の庭を撫でていた。
冬の間、眠っていたバラが少しずつ蕾をつけ始め、温室では新芽が顔を覗かせている。
レティシアは庭師たちの作業を見守りながら、そっと笑みをこぼした。
「……この庭も、だいぶ息を吹き返しましたわね」
「貴女が世話をしてくれたおかげだ」
背後から穏やかな声がした。
振り向けば、セドリックが立っていた。
黒い執務服のまま、朝の光を受けてその銀灰色の瞳がきらめいている。
「お忙しいのに、こんな時間に?」
「視察のついでだ。屋敷の者たちが最近、生き生きとしている。……君の影響だろう」
「まあ、恐れ多いお言葉ですわ」
軽く会釈するレティシアに、セドリックはわずかに微笑んだ。
以前は、彼が微笑むなど考えられなかった。
冷徹と呼ばれるほど表情を崩さなかった彼が、今はこうして穏やかに言葉を交わしてくれる。
それが不思議で、そして嬉しかった。
---
昼過ぎ、書斎の机には山のような書類が積まれていた。
レティシアは手伝いのために入室したが、セドリックの目の下には濃い影が見える。
「旦那様、少しお休みになってくださいませ」
「これを片づけてからだ。報告書の確認が遅れれば、部下が困る」
「ですが、無理をすれば余計に仕事が滞りますわ」
言いながら、彼の手から書類をすっと取り上げる。
セドリックは驚いたように瞬きをした。
「……君、私の机に手を出すのは初めてだな」
「奥様ですもの。多少の越権はお許しいただけるでしょう?」
にっこりと笑ってみせると、彼は口元を押さえて苦笑した。
「……勝てないな」
結局、レティシアは彼を半ば強引にソファへ座らせ、紅茶を用意した。
香り高いカモミールティー。
彼女の手から湯気の立つカップを受け取った彼は、静かに息をついた。
「……温かいな」
「お茶がですか?」
「いや――君の心遣いが、だ」
その言葉に、レティシアの胸がどくんと跳ねた。
何気ない一言なのに、まるで恋人に囁かれたように甘い響きだった。
(な、何を考えているの……わたくし、落ち着きなさい! これはただの社交辞令……)
自分に言い聞かせながらも、頬の熱は下がらない。
---
その夜。
書斎での仕事を終えたセドリックが自室へ戻ると、廊下の窓辺でレティシアが月を見上げていた。
彼女の金糸の髪が月光を受けて輝いている。
まるで、白い花のようだった。
「こんな時間にどうした」
「眠れなくて……。少し、夜風に当たっておりました」
「風が冷える。体を冷やすな」
そう言いながら、彼は自分の上着を彼女の肩にかけた。
突然のことで、レティシアは小さく息を呑んだ。
「せ、セドリック様……?」
「君が風邪をひいたら、屋敷が混乱する」
「……それだけ、ですの?」
自分でも意地のような言葉だった。
けれど、セドリックは真っ直ぐに彼女を見つめる。
「それだけではない。君に何かあると――私が、嫌だ」
短い言葉だったが、その中にどれだけの感情が詰まっているか、レティシアには分かった。
胸の奥で何かが溶ける音がした。
あの夜に聞いた名前呼びから、確かに何かが変わり始めている。
---
翌朝。
執務中にセドリックがふと目を上げると、窓の外でレティシアがメイドと一緒に花の世話をしていた。
風に揺れる金髪が光に包まれ、笑うたびに花よりも美しく見える。
彼は知らず知らず手を止め、しばらく見惚れていた。
だが、ドアのノックで現実に引き戻される。
秘書官が書類を差し出しながら、にやりと笑った。
「旦那様、最近お優しいですね。夫人の影響でしょうか?」
「……仕事に集中しろ」
咳払いをしながら書類を受け取る。
だが、顔の熱は隠せなかった。
---
その日の午後、事件が起きた。
温室で花の剪定をしていたレティシアが、誤って指を切ってしまったのだ。
小さな傷だったが、血を見た瞬間にセドリックの表情が変わった。
「大丈夫ですわ、少し切っただけです」
「放っておけるか」
彼は即座に手を取り、ハンカチを巻きつける。
その手つきは驚くほど丁寧で、そして――震えていた。
「……申し訳ありません。わざわざ」
「謝るな。君が傷つくのは……見たくない」
その言葉に、レティシアの胸が締めつけられた。
彼の声は静かだが、どこか必死だった。
「セドリック様……」
「もう“様”はつけるなと言っただろう」
「……セドリック」
名前を呼ぶと、彼はふっと目を細めた。
その瞬間、彼女の手を包む指が少し強くなった。
「その方が、ずっといい」
心臓が跳ねる。
彼の言葉は、まるで恋の告白のように響いた。
---
夕暮れ、レティシアは一人、温室の中で息を整えていた。
指の痛みよりも、胸の鼓動の方が落ち着かない。
(あの人は、どうしてあんなに優しいの? 契約の結婚なのに……)
思えば、最初は冷たくて、必要最低限の会話しかなかった。
それが今では、目が合うたびに微笑んでくれる。
名前を呼んでくれる。
気づけば、その声が一日の楽しみになっていた。
(……私、まさか、恋を……?)
自分の頬が熱い。
答えを出すのが怖かった。
---
一方そのころ、セドリックは寝室で机に向かっていた。
だが、手元の書類はまったく頭に入らない。
レティシアの笑顔が脳裏から離れないのだ。
「……おかしいな」
独りごちる。
これまで、どんな美女を見ても心が動いたことなどなかった。
政治的な婚約、形式的な愛。それが貴族の常だった。
だが今――彼は、たった一人の笑顔に心を奪われている。
「形式のはずだったのに……」
その言葉は、静かな夜に溶けた。
---
夜更け。
レティシアが寝室へ戻ると、机の上にまた一輪の花が置かれていた。
昨日と同じ白薔薇――だが、今夜の花は蕾の中心が深紅に染まっている。
そして、その花弁の下に小さな紙片が添えられていた。
> 『今日は、ありがとう。
どうか無理をするな。
――セドリック』
その短い一文を見た瞬間、レティシアの目が潤んだ。
指先で花を撫で、胸に抱きしめる。
「……不器用な人ですわね」
けれど、その不器用さが、愛おしかった。
---
侯爵と令嬢。
形式のはずだった二人の結婚は、もう“形式”の枠を超え始めていた。
名前を呼ぶこと、手を包むこと、花を贈ること――
そのどれもが、心の距離を縮めていく。
そして、レティシアはまだ知らなかった。
その夜、セドリックもまた、同じ白薔薇を手にして、同じ月を見上げていたことを――。
---
> 契約の夫婦が、互いを想い合うようになった瞬間。
それは恋の始まりでもあり、運命の歯車が回り出す音でもあった。
0
あなたにおすすめの小説

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

で、お前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか?
Debby
恋愛
ヴェルトが友人からの手紙を手に辺境伯令嬢であるレィディアンスの元を訪れたのは、その手紙に「詳細は彼女に聞け」と書いてあったからだ。
簡単にいうと、手紙の内容は「学園で問題を起こした平民──エボニーを妻として引き取ってくれ」というものだった。
一方その話を聞いてしまった伯爵令嬢のオリーブは動揺していた。
ヴェルトとは静かに愛を育んできた。そんな自分を差し置いて、言われるがまま平民を妻に迎えてしまうのだろうか。
そんなオリーブの気持ちを知るはずもないエボニーは、辺境伯邸で行儀見習いをすることになる。
オリーブは何とかしてヴェルトを取り戻そうと画策し、そのことを咎められてしまう。もう後は無い。
オリーブが最後の望みをかけてヴェルトに自分を選んで欲しいと懇願する中、レィディアンスが静かに口を開いた。
「で、そろそろお前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか」
「はい?」
ヴェルトは自分が何を言われたのか全く理解が出来なかった。
*--*--*
覗いてくださりありがとうございます。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
★全31話7時19時更新で、全話予約投稿済みです。
★★「このお話だけ読んでいただいてもOKです!」という前提のもと↓↓↓
このお話は独立した一つのお話ですが、「で。」シリーズのサイドストーリーでもあり、第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」の「エボニーその後」でもあります(あるいは「最終話」のその後)。
第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」
第二弾「で、あなたが私に嫌がらせをする理由を伺っても?」
第三弾「で、あなたが彼に嫌がらせをする理由をお話しいただいても?」
どれも女性向けHOTランキングに入り、特に第二弾はHOT一位になることが出来ました!(*´▽`人)アリガトウ
もしよかったら宜しくお願いしますね!

結婚30年、契約満了したので離婚しませんか?
おもちのかたまり
恋愛
恋愛・小説 11位になりました!
皆様ありがとうございます。
「私、旦那様とお付き合いも甘いやり取りもしたことが無いから…ごめんなさい、ちょっと他人事なのかも。もちろん、貴方達の事は心から愛しているし、命より大事よ。」
眉根を下げて笑う母様に、一発じゃあ足りないなこれは。と確信した。幸い僕も姉さん達も祝福持ちだ。父様のような力極振りではないけれど、三対一なら勝ち目はある。
「じゃあ母様は、父様が嫌で離婚するわけではないんですか?」
ケーキを幸せそうに頬張っている母様は、僕の言葉にきょとん。と目を見開いて。…もしかすると、母様にとって父様は、関心を向ける程の相手ではないのかもしれない。嫌な予感に、今日一番の寒気がする。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
20年前に攻略対象だった父親と、悪役令嬢の取り巻きだった母親の現在のお話。
ハッピーエンド・バットエンド・メリーバットエンド・女性軽視・女性蔑視
上記に当てはまりますので、苦手な方、ご不快に感じる方はお気を付けください。
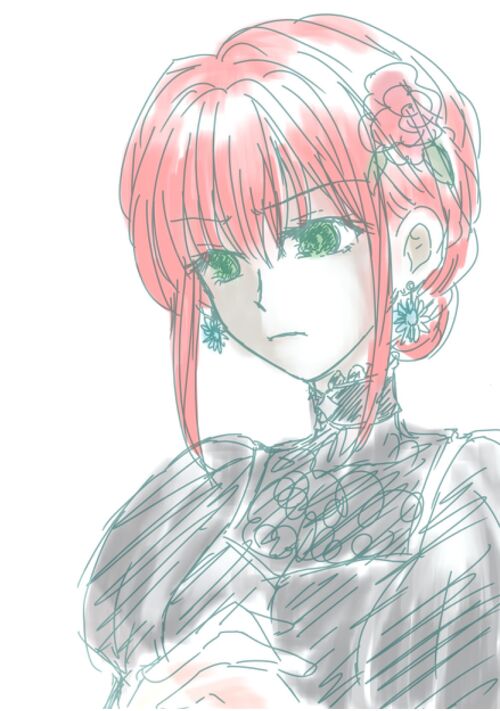
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

戦う聖女さま
有栖多于佳
恋愛
エニウェア大陸にある聖教国で、千年ぶりに行われた聖女召喚。
聖女として呼ばれた魂の佐藤愛(さとうめぐみ)は、魂の器として選ばれた孤児の少女タビタと混じり、聖教国を聖教皇から乗っ取り理想の国作りをしながら、周辺国も巻き込んだ改革を行っていく。
佐藤愛は、生前ある地方都市の最年少市長として改革を進めていたが、志半ばで病に倒れて死んでしまった。
やり残した後悔を、今度は異世界でタビタと一緒に解決していこうと張り切っている。悩んだら走る、困ったらスクワットという筋肉は裏切らない主義だが、そこそこインテリでもある。
タビタは、修道院の門前に捨てられていた孤児で、微力ながら光の属性があったため、聖女の器として育てられてきた。自己犠牲を生まれた時から叩き込まれてきたので、自己肯定感低めで、現実的でシニカルな物の見方もする。
東西南北の神官服の女たち、それぞれ聖教国の周辺国から選ばれて送り込まれた光の属性の巫女で、それぞれ国と個人が問題を抱えている。
小説家になろうにも掲載してます。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

わたしたちの庭
犬飼ハルノ
恋愛
「おい、ウェスト伯。いくらなんでもこんなみすぼらしい子どもに金を払えと?」
「まあまあ、ブルーノ伯爵。この子の母親もこんな感じでしたが、年ごろになると見違えるように成熟しましたよ。後妻のアリスは元妻の従妹です。あの一族の女は容姿も良いし、ぽんぽんと子どもを産みますよ」
「ふうん。そうか」
「直系の跡継ぎをお望みでしょう」
「まあな」
「しかも伯爵以上の正妻の子で年ごろの娘に婚約者がいないのは、この国ではこの子くらいしかもう残っていませんよ」
「ふ……。口が上手いなウェスト伯。なら、買い取ってやろうか、その子を」
目の前で醜悪な会話が繰り広げられる中、フィリスは思った。
まるで山羊の売買のようだと。
かくして。
フィリスの嫁ぎ先が決まった。
------------------------------------------
安定の見切り発車ですが、二月中に一日一回更新と完結に挑みます。
ヒロインのフィリスが自らの力と人々に支えられて幸せをつかむ話ですが、
序盤は暗く重い展開です。
タグを途中から追加します。
他サイトでも公開中。

「やはり鍛えることは、大切だな」
イチイ アキラ
恋愛
「こんなブスと結婚なんていやだ!」
その日、一つのお見合いがあった。
ヤロール伯爵家の三男、ライアンと。
クラレンス辺境伯家の跡取り娘、リューゼットの。
そして互いに挨拶を交わすその場にて。
ライアンが開幕早々、ぶちかましたのであった。
けれども……――。
「そうか。私も貴様のような生っ白くてか弱そうな、女みたいな顔の屑はごめんだ。気が合うな」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















