14 / 17
4-3 紅の指輪が告げる真実
しおりを挟む
第4章 4-3 紅の指輪が告げる真実
――夜が、静かに降りていた。
レティシアは侯爵邸のバルコニーに立ち尽くしていた。
風は冷たく、満月が雲の隙間から覗く。
手には、紅く光を放つ指輪。
それは、セドリックとの愛の証であり――同時に、彼を王の陰謀から救う唯一の鍵でもあった。
(あの言葉……「選びなさい、愛する夫を救うか、国の真実を暴くか」)
セレーネの声が頭から離れない。
彼女が消えた後、修道院の祭壇の前に残っていたのは、焦げ跡と血のように赤い花弁。
あれは、幻ではなかった。
王が“聖女の儀”を再び行おうとしている。
その中心に、夫セドリックが選ばれようとしている。
――すべては、彼の知らぬところで。
レティシアは指輪を見つめ、胸の奥で静かに呟いた。
「お願い……教えて。どうすれば、彼を守れるの?」
紅玉は微かに輝き、淡い光を放った。
まるで答えるように、脈を打つ。
---
その夜遅く、執務室の扉が開いた。
セドリックが現れたのは、月が天頂に昇った頃だった。
彼の制服は軍務帰りのまま、肩には白い塵が積もっている。
「まだ起きていたのか」
「ええ……眠れなくて」
レティシアの声は少し掠れていた。
セドリックは彼女の前に立ち、柔らかく笑んだ。
「君のことを考えていた。……式のあとから、少し様子が違う」
彼は紅茶を二つ淹れ、カップを差し出した。
その香りは懐かしく、心を落ち着かせる。
けれど、レティシアの手は震えていた。
「……セドリック。わたくし、あなたに伝えなければならないことがあります」
その声に、彼の瞳が鋭く光る。
「何かあったのか」
彼女は深呼吸をして、言葉を紡いだ。
「三日前、わたくしのもとに一通の手紙が届きました。
差出人は……滅んだはずのドラギア帝国の皇女、セレーネ様です」
セドリックはカップを置き、無言のまま彼女を見つめた。
その視線は冷たくはなかった。むしろ、これから聞く真実を受け止めようとする覚悟のようだった。
「続けてくれ」
「……セレーネ様は、王国が“聖女の力”を偽って利用していると言いました。
王が造り上げた“新聖女リリア”は、本物ではなく、人工的な存在だと」
セドリックの眉がわずかに動く。
だが、驚きではなく、確信を得たような表情だった。
「やはり……そうか」
「……知っていたのですか?」
「噂はあった。だが、確証は得られなかった。……君がそれを聞いたのか」
レティシアは頷き、さらに口を開いた。
「そして……王は“新たな聖女の儀”を行うつもりです。
次の聖女を守護する騎士――つまり、儀式の“供物”として選ばれるのが、あなただと」
その瞬間、セドリックの表情が変わった。
氷のような静けさの中に、激しい怒りが宿る。
「供物……? 王は、私を利用する気か」
拳を握る音が、部屋に響く。
紅茶のカップがかすかに揺れ、皿の上で音を立てた。
レティシアは立ち上がり、彼の手を取った。
「わたくし、止めたいの。あなたが犠牲になるなんて、絶対に許せない!」
「落ち着け、レティシア。……その話、誰かに聞かれたか?」
「いいえ。セレーネ様とわたくしだけです」
「ならば、まだ間に合う」
セドリックは机の上の地図を広げ、北部の軍区を指でなぞる。
「王が儀式を行うなら、北の神殿――聖遺晶の保管地が怪しい。
そこには“封印の間”がある。おそらく、聖女の血を用いた実験が続いているはずだ」
レティシアは息を呑む。
「では、あなたは……調べに行くつもり?」
「いや、私が動けば王に察知される。――君に行ってほしい」
「わたくしが……?」
「“聖女の血”を持つ君なら、聖遺晶に近づける。
そして何より、君の存在そのものが“偽りの聖女”を暴く鍵になる」
彼の瞳が、真剣に光る。
レティシアは震える唇で問う。
「でも、それは危険すぎますわ。わたくしが捕まったら……!」
「その時は、命を賭けてでも君を助ける」
言い切るその声に、迷いはなかった。
だが、その言葉が余計に胸を締め付けた。
(この人は、わたくしを守るために、命を投げ出してしまう……)
沈黙。
そして、二人の間に流れる緊張を破るように、扉がノックされた。
「失礼します! 王都より急報です!」
執事が駆け込む。
手にした王室の封書を差し出した。
金の封蝋――王命を意味する印。
セドリックは封を切り、書状を読む。
その表情が、次第に硬くなっていく。
「……まさか」
レティシアが不安そうに覗き込む。
セドリックは息を詰め、読み上げた。
> 『アークハート侯爵、並びにその夫人レティシアを、王宮へ召喚する。
“聖女の儀”における神託の確認のため、両名の立会いを命ず。
期日は明朝。王命に背けば、反逆と見なす。』
「……召喚令?」
レティシアの声が震える。
まるで“罠”のような文面だった。
セドリックは書状を握りしめ、炎のような瞳で呟いた。
「王はもう、我々の動きを察知している……!」
「どうすればいいの……?」
「行くしかない。逃げれば本当に反逆になる」
彼は立ち上がり、軍服の上着を羽織った。
その動作一つ一つが、決意に満ちている。
「だが、王の思い通りにはさせない。
“聖女の儀”の真実を暴き、奴らの偽りを終わらせる」
レティシアは唇を噛み、彼の背に手を伸ばした。
「わたくしも、一緒に行きます」
「危険だ」
「それでも行きます。あなたと共に立ちたい」
その瞬間、紅の指輪が強く光を放った。
赤い光が二人の手を包み込み、まるで二つの命を結ぶ糸のように絡み合う。
「……見て」
レティシアが囁く。
「まるで、わたしたちの決意を見届けているみたい」
セドリックはその光を見つめ、穏やかに微笑んだ。
「なら、これは“神”が与えた導きだ」
彼はレティシアの頬に手を当て、低く囁く。
「恐れるな。君が信じる真実こそ、我々の武器だ」
その言葉に、レティシアの瞳に涙が浮かぶ。
「……わたくし、あなたを信じます」
夜風が吹き抜け、紅い光が一層強く輝いた。
――それは、二人が運命に立ち向かう誓いの灯。
愛と真実を天秤にかける戦いの幕が、静かに上がった。
---
> 🌹次節・第4章 4-4「聖女の儀と真紅の裁き」では、
王都の大聖堂にて行われる“聖女の儀”の真実が明かされる。
愛を試される二人、そして明かされる“偽りの神託”――
白と紅、光と影が交錯する最終決戦へ。
――夜が、静かに降りていた。
レティシアは侯爵邸のバルコニーに立ち尽くしていた。
風は冷たく、満月が雲の隙間から覗く。
手には、紅く光を放つ指輪。
それは、セドリックとの愛の証であり――同時に、彼を王の陰謀から救う唯一の鍵でもあった。
(あの言葉……「選びなさい、愛する夫を救うか、国の真実を暴くか」)
セレーネの声が頭から離れない。
彼女が消えた後、修道院の祭壇の前に残っていたのは、焦げ跡と血のように赤い花弁。
あれは、幻ではなかった。
王が“聖女の儀”を再び行おうとしている。
その中心に、夫セドリックが選ばれようとしている。
――すべては、彼の知らぬところで。
レティシアは指輪を見つめ、胸の奥で静かに呟いた。
「お願い……教えて。どうすれば、彼を守れるの?」
紅玉は微かに輝き、淡い光を放った。
まるで答えるように、脈を打つ。
---
その夜遅く、執務室の扉が開いた。
セドリックが現れたのは、月が天頂に昇った頃だった。
彼の制服は軍務帰りのまま、肩には白い塵が積もっている。
「まだ起きていたのか」
「ええ……眠れなくて」
レティシアの声は少し掠れていた。
セドリックは彼女の前に立ち、柔らかく笑んだ。
「君のことを考えていた。……式のあとから、少し様子が違う」
彼は紅茶を二つ淹れ、カップを差し出した。
その香りは懐かしく、心を落ち着かせる。
けれど、レティシアの手は震えていた。
「……セドリック。わたくし、あなたに伝えなければならないことがあります」
その声に、彼の瞳が鋭く光る。
「何かあったのか」
彼女は深呼吸をして、言葉を紡いだ。
「三日前、わたくしのもとに一通の手紙が届きました。
差出人は……滅んだはずのドラギア帝国の皇女、セレーネ様です」
セドリックはカップを置き、無言のまま彼女を見つめた。
その視線は冷たくはなかった。むしろ、これから聞く真実を受け止めようとする覚悟のようだった。
「続けてくれ」
「……セレーネ様は、王国が“聖女の力”を偽って利用していると言いました。
王が造り上げた“新聖女リリア”は、本物ではなく、人工的な存在だと」
セドリックの眉がわずかに動く。
だが、驚きではなく、確信を得たような表情だった。
「やはり……そうか」
「……知っていたのですか?」
「噂はあった。だが、確証は得られなかった。……君がそれを聞いたのか」
レティシアは頷き、さらに口を開いた。
「そして……王は“新たな聖女の儀”を行うつもりです。
次の聖女を守護する騎士――つまり、儀式の“供物”として選ばれるのが、あなただと」
その瞬間、セドリックの表情が変わった。
氷のような静けさの中に、激しい怒りが宿る。
「供物……? 王は、私を利用する気か」
拳を握る音が、部屋に響く。
紅茶のカップがかすかに揺れ、皿の上で音を立てた。
レティシアは立ち上がり、彼の手を取った。
「わたくし、止めたいの。あなたが犠牲になるなんて、絶対に許せない!」
「落ち着け、レティシア。……その話、誰かに聞かれたか?」
「いいえ。セレーネ様とわたくしだけです」
「ならば、まだ間に合う」
セドリックは机の上の地図を広げ、北部の軍区を指でなぞる。
「王が儀式を行うなら、北の神殿――聖遺晶の保管地が怪しい。
そこには“封印の間”がある。おそらく、聖女の血を用いた実験が続いているはずだ」
レティシアは息を呑む。
「では、あなたは……調べに行くつもり?」
「いや、私が動けば王に察知される。――君に行ってほしい」
「わたくしが……?」
「“聖女の血”を持つ君なら、聖遺晶に近づける。
そして何より、君の存在そのものが“偽りの聖女”を暴く鍵になる」
彼の瞳が、真剣に光る。
レティシアは震える唇で問う。
「でも、それは危険すぎますわ。わたくしが捕まったら……!」
「その時は、命を賭けてでも君を助ける」
言い切るその声に、迷いはなかった。
だが、その言葉が余計に胸を締め付けた。
(この人は、わたくしを守るために、命を投げ出してしまう……)
沈黙。
そして、二人の間に流れる緊張を破るように、扉がノックされた。
「失礼します! 王都より急報です!」
執事が駆け込む。
手にした王室の封書を差し出した。
金の封蝋――王命を意味する印。
セドリックは封を切り、書状を読む。
その表情が、次第に硬くなっていく。
「……まさか」
レティシアが不安そうに覗き込む。
セドリックは息を詰め、読み上げた。
> 『アークハート侯爵、並びにその夫人レティシアを、王宮へ召喚する。
“聖女の儀”における神託の確認のため、両名の立会いを命ず。
期日は明朝。王命に背けば、反逆と見なす。』
「……召喚令?」
レティシアの声が震える。
まるで“罠”のような文面だった。
セドリックは書状を握りしめ、炎のような瞳で呟いた。
「王はもう、我々の動きを察知している……!」
「どうすればいいの……?」
「行くしかない。逃げれば本当に反逆になる」
彼は立ち上がり、軍服の上着を羽織った。
その動作一つ一つが、決意に満ちている。
「だが、王の思い通りにはさせない。
“聖女の儀”の真実を暴き、奴らの偽りを終わらせる」
レティシアは唇を噛み、彼の背に手を伸ばした。
「わたくしも、一緒に行きます」
「危険だ」
「それでも行きます。あなたと共に立ちたい」
その瞬間、紅の指輪が強く光を放った。
赤い光が二人の手を包み込み、まるで二つの命を結ぶ糸のように絡み合う。
「……見て」
レティシアが囁く。
「まるで、わたしたちの決意を見届けているみたい」
セドリックはその光を見つめ、穏やかに微笑んだ。
「なら、これは“神”が与えた導きだ」
彼はレティシアの頬に手を当て、低く囁く。
「恐れるな。君が信じる真実こそ、我々の武器だ」
その言葉に、レティシアの瞳に涙が浮かぶ。
「……わたくし、あなたを信じます」
夜風が吹き抜け、紅い光が一層強く輝いた。
――それは、二人が運命に立ち向かう誓いの灯。
愛と真実を天秤にかける戦いの幕が、静かに上がった。
---
> 🌹次節・第4章 4-4「聖女の儀と真紅の裁き」では、
王都の大聖堂にて行われる“聖女の儀”の真実が明かされる。
愛を試される二人、そして明かされる“偽りの神託”――
白と紅、光と影が交錯する最終決戦へ。
0
あなたにおすすめの小説

で、お前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか?
Debby
恋愛
ヴェルトが友人からの手紙を手に辺境伯令嬢であるレィディアンスの元を訪れたのは、その手紙に「詳細は彼女に聞け」と書いてあったからだ。
簡単にいうと、手紙の内容は「学園で問題を起こした平民──エボニーを妻として引き取ってくれ」というものだった。
一方その話を聞いてしまった伯爵令嬢のオリーブは動揺していた。
ヴェルトとは静かに愛を育んできた。そんな自分を差し置いて、言われるがまま平民を妻に迎えてしまうのだろうか。
そんなオリーブの気持ちを知るはずもないエボニーは、辺境伯邸で行儀見習いをすることになる。
オリーブは何とかしてヴェルトを取り戻そうと画策し、そのことを咎められてしまう。もう後は無い。
オリーブが最後の望みをかけてヴェルトに自分を選んで欲しいと懇願する中、レィディアンスが静かに口を開いた。
「で、そろそろお前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか」
「はい?」
ヴェルトは自分が何を言われたのか全く理解が出来なかった。
*--*--*
覗いてくださりありがとうございます。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
★全31話7時19時更新で、全話予約投稿済みです。
★★「このお話だけ読んでいただいてもOKです!」という前提のもと↓↓↓
このお話は独立した一つのお話ですが、「で。」シリーズのサイドストーリーでもあり、第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」の「エボニーその後」でもあります(あるいは「最終話」のその後)。
第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」
第二弾「で、あなたが私に嫌がらせをする理由を伺っても?」
第三弾「で、あなたが彼に嫌がらせをする理由をお話しいただいても?」
どれも女性向けHOTランキングに入り、特に第二弾はHOT一位になることが出来ました!(*´▽`人)アリガトウ
もしよかったら宜しくお願いしますね!
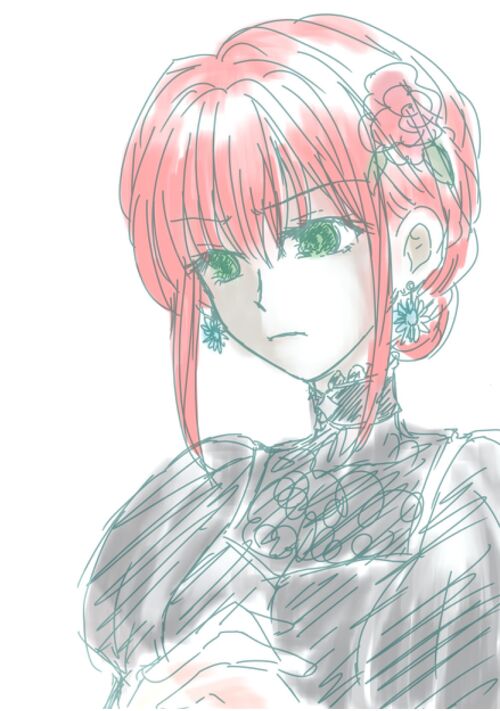
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

一途に愛した1周目は殺されて終わったので、2周目は王子様を嫌いたいのに、なぜか婚約者がヤンデレ化して離してくれません!
夢咲 アメ
恋愛
「君の愛が煩わしいんだ」
婚約者である王太子の冷たい言葉に、私の心は砕け散った。
それから間もなく、私は謎の襲撃者に命を奪われ死んだ――はずだった。
死の間際に見えたのは、絶望に顔を歪ませ、私の名を叫びながら駆け寄る彼の姿。
……けれど、次に目を覚ました時、私は18歳の自分に戻っていた。
「今世こそ、彼を愛するのを辞めよう」
そう決意して距離を置く私。しかし、1周目であれほど冷酷だった彼は、なぜか焦ったように私を追いかけ、甘い言葉で縛り付けようとしてきて……?
「どこへ行くつもり? 君が愛してくれるまで、僕は君を離さないよ」
不器用すぎて愛を間違えたヤンデレ王子×今世こそ静かに暮らしたい令嬢。
死から始まる、執着愛の二周目が幕を開ける!

皆様ありがとう!今日で王妃、やめます!〜十三歳で王妃に、十八歳でこのたび離縁いたしました〜
百門一新
恋愛
セレスティーヌは、たった十三歳という年齢でアルフレッド・デュガウスと結婚し、国王と王妃になった。彼が王になる多には必要な結婚だった――それから五年、ようやく吉報がきた。
「君には苦労をかけた。王妃にする相手が決まった」
ということは……もうつらい仕事はしなくていいのねっ? 夫婦だと偽装する日々からも解放されるのね!?
ありがとうアルフレッド様! さすが私のことよく分かってるわ! セレスティーヌは離縁を大喜びで受け入れてバカンスに出かけたのだが、夫、いや元夫の様子が少しおかしいようで……?
サクッと読める読み切りの短編となっていります!お楽しみいただけましたら嬉しく思います!
※他サイト様にも掲載

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
私は、夫にも子供にも選ばれなかった。
その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。
そこで待っていたのは、最悪の出来事――
けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。
夫は愛人と共に好きに生きればいい。
今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。
でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。
妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。
過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――

何も決めなかった王国は、静かに席を失う』
ふわふわ
恋愛
王太子の婚約者として、
表には立たず、裏で国を支えてきた公爵令嬢ネフェリア。
だが――
彼女が追い出されたのは、嫉妬でも陰謀でもなかった。
ただ一つ、「決める役割」を、国が彼女一人に押しつけていたからだ。
婚約破棄の後、ネフェリアを失った王国は変わろうとする。
制度を整え、会議を重ね、慎重に、正しく――
けれどその“正しさ”は、何一つ決断を生まなかった。
一方、帝国は違った。
完璧ではなくとも、期限内に返事をする。
責任を分け、判断を止めない。
その差は、やがて「呼ばれない会議」「残らない席」「知らされない決定」となって現れる。
王国は滅びない。
だが、何も決めない国は、静かに舞台の外へ追いやられていく。
――そして迎える、最後の選択。
これは、
剣も魔法も振るわない“静かなざまぁ”。
何も決めなかった過去に、国そのものが向き合う物語。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















