15 / 17
4-2 黒き使者と秘密の招待状
しおりを挟む
第4章 4-2 黒き使者と秘密の招待状
王都を包む祝賀の喧騒が、ようやく静まり返った夜。
侯爵邸の廊下には、まだ花びらと香水の香りが残っていた。
“紅の誓い”を交わした夫妻の再婚式は、王国中の話題となっていた。
――氷の侯爵が、紅の花嫁を娶った。
それは、愛の奇跡であり、同時に王国の象徴でもあった。
けれど、歓喜の裏側で、静かに別の歯車が回り始めていた。
---
その夜更け。
屋敷の裏門に、一台の黒い馬車が停まった。
御者台には誰もおらず、まるで闇から生まれた影のように静まり返っている。
扉が開き、黒衣の使者が現れた。
顔を深くフードで覆い、手には一通の封書。
黒い蝋が押されたその封蝋には、三つの竜が絡み合う紋章が刻まれていた。
それは――滅びたはずの隣国「ドラギア帝国」の王家の印。
使者は一言も発さず、門番に封書を差し出した。
「アークハート侯爵夫人、レティシア様へ」
そう告げると、姿を闇に溶かして消えた。
---
翌朝、レティシアは小鳥のさえずりで目を覚ました。
新婚の朝、彼女はまだ紅のドレスの余韻が残る寝間着姿で、窓辺に立つ。
「昨日の花火、綺麗でしたわね……」
鏡の中の自分は、あの日の“断罪令嬢”とは別人のようだった。
穏やかで、柔らかな光を帯びた顔。
けれど――その平穏を打ち砕くように、扉をノックする音がした。
「奥様、早朝に奇妙な手紙が届きました」
執事が恭しく差し出した封書には、見覚えのない紋章。
黒い封蝋、絡み合う三頭の竜。
レティシアの瞳が揺れる。
「この紋章……まさか……」
彼女はそのまま手紙を受け取り、震える指で封を切った。
中から現れた羊皮紙には、流麗な筆致でこう記されていた。
> ――親愛なるレティシア・アークハート侯爵夫人へ。
あなたが“王太子に断罪された夜”のことを、私は忘れません。
あの時のあなたの一言、「真実の愛が腐らないように祈っております」――
あれは皮肉ではなく、誇りでした。
あなたと私は同じです。
王に利用され、真実を奪われた者。
どうか、三日後の黄昏、王都北の“聖アレシア修道院跡”へお越しください。
私はあなたに、“真実の聖女”の血について語らねばなりません。
――旧ドラギア帝国皇女 セレーネ・リュシアン
読み終えた瞬間、レティシアの手が震えた。
「……セレーネ様。生きて……?」
かつて外交の場で出会った少女。
銀の髪、紅の瞳、静かな笑み。
ドラギア帝国の崩壊とともに命を落としたはずの皇女。
その彼女が、なぜ今――?
---
朝の執務室で、セドリックは新たな王命に目を通していた。
王国北部の治安再建と、軍の再編。
再婚式の翌日だというのに、彼の机にはすでに戦略地図が広げられている。
「君が王に気に入られた証拠だな」
「気に入られるのは構わない。ただ、王は静かな人間を嫌う」
彼はペンを置き、窓の外を見つめた。
王国の上空に漂う薄い靄――それが不穏に見えた。
そこへ、レティシアが手紙を隠したまま現れる。
「お仕事中に失礼いたしますわ」
「いや、ちょうど休憩しようと思っていた。……顔色が優れないな?」
「いえ……昨夜、少し考え事をしていて」
セドリックは彼女を椅子に座らせ、紅茶を注いだ。
穏やかな香りが広がる。
だが、レティシアの胸の中は穏やかではなかった。
(この人には言えない。王命を帯びている以上、わたくしの話は混乱を招く……)
「何か隠している顔だ」
「まあ……夫に隠し事をする妻なんて、おかしいですわね」
苦笑でごまかしながら、彼の手を取る。
セドリックはその温もりを感じながらも、何かを察していた。
彼は彼女の瞳を見つめ、低く呟く。
「……何があっても、私は君を信じる」
その言葉に、レティシアの胸が痛んだ。
――だからこそ、言えない。
---
三日後の夕刻。
王都の北端に広がる廃修道院。
そこはかつて“聖アレシア”が祀られた神聖な地だったが、いまは荒廃し、鳥の声すら聞こえない。
廃墟のような回廊に、ひとりの女が歩を進める。
赤いマントのフードを深く被ったレティシア。
背後には、信頼する侍女マルタの影。
「奥様、本当に……ここに来てよろしいのですか」
「ええ。真実を知るために」
彼女の指先には、セドリックから贈られた“紅の指輪”が輝いている。
その輝きが、どこか不安げに揺れていた。
---
廃堂の中央。
崩れた祭壇の前に、ひとつの灯火がともっていた。
その光の向こうに、白いローブの女が立っている。
――銀髪、紅の瞳。
「来てくれたのね、レティシア」
声は柔らかく、それでいて底冷えするような美しさを帯びていた。
「セレーネ様……本当に生きていらしたのですね」
「生きて、そして見ていたの。王国がどうやって“聖女”という名を利用しているかを」
セレーネは近づき、レティシアの手を取った。
その冷たさに、思わず息を呑む。
「あなたの婚約破棄――あれは偶然ではないわ。
王家は、“聖女の血”を継ぐあなたを王太子妃にできなかった。
なぜなら、“王より上の存在”になってしまうから」
「わたくしが……聖女の血を?」
セレーネは頷いた。
「あなたの母方の祖母は、ドラギア帝国の分家の姫。
つまり、あなたは“本物の聖女”の直系。
王国はそれを隠し、あなたを断罪することで“血の真実”を封じたのよ」
レティシアの唇が震える。
「そんな……では、あの“新聖女リリア”は……?」
「造られた偽り。
王国の魔導師たちが、我が帝国の遺物――“聖遺晶”を使って創り出した人形の聖女よ」
衝撃に、レティシアは言葉を失った。
あの夜、王太子が誇らしげに「真実の愛」と宣言したあの瞬間――
すべてが仕組まれた芝居だったのか。
セレーネは静かに彼女の肩に手を置いた。
「王国は再び“聖女の儀式”を行うつもり。
けれど、その中心に立たされるのは、あなたの夫――アークハート侯爵よ」
「セドリックが……!?」
「彼は知らない。だが、王は利用するつもりよ。
“氷の侯爵”を聖女の守護騎士として表舞台に立たせ、民の信仰を操る。
その裏で、聖遺晶を用いた“血の儀”を完成させる気なの」
レティシアは立ち尽くした。
頭の中で、鐘の音が鳴り響くようだった。
(セドリックが……利用される? わたくしのせいで……?)
セレーネが微笑む。
「止められるのは、あなたしかいない。
“真なる聖女”としての血を覚醒させなさい。
あなたが祈れば、王国の偽りの聖女は消える」
「……わたくしに、そんなことができるの?」
「できますとも。
あなたが愛のために涙を流したとき、その紅の指輪が道を開く」
セレーネは炎の中に姿を溶かすように消えていった。
残されたのは、香のような甘い匂いと、ただ一言。
> 「――選びなさい、レティシア。
愛する夫を救うか、国の真実を暴くか」
---
廃堂を出たとき、空は夕闇に沈んでいた。
マルタが駆け寄る。
「奥様! お顔が真っ青です……!」
「……大丈夫よ」
そう答えながら、レティシアは指輪を握りしめた。
紅の宝石が、まるで心臓の鼓動に呼応するように脈打っている。
(愛か、真実か――)
紅の誓いを立てたばかりの彼女の瞳に、決意の光が宿った。
王都を包む祝賀の喧騒が、ようやく静まり返った夜。
侯爵邸の廊下には、まだ花びらと香水の香りが残っていた。
“紅の誓い”を交わした夫妻の再婚式は、王国中の話題となっていた。
――氷の侯爵が、紅の花嫁を娶った。
それは、愛の奇跡であり、同時に王国の象徴でもあった。
けれど、歓喜の裏側で、静かに別の歯車が回り始めていた。
---
その夜更け。
屋敷の裏門に、一台の黒い馬車が停まった。
御者台には誰もおらず、まるで闇から生まれた影のように静まり返っている。
扉が開き、黒衣の使者が現れた。
顔を深くフードで覆い、手には一通の封書。
黒い蝋が押されたその封蝋には、三つの竜が絡み合う紋章が刻まれていた。
それは――滅びたはずの隣国「ドラギア帝国」の王家の印。
使者は一言も発さず、門番に封書を差し出した。
「アークハート侯爵夫人、レティシア様へ」
そう告げると、姿を闇に溶かして消えた。
---
翌朝、レティシアは小鳥のさえずりで目を覚ました。
新婚の朝、彼女はまだ紅のドレスの余韻が残る寝間着姿で、窓辺に立つ。
「昨日の花火、綺麗でしたわね……」
鏡の中の自分は、あの日の“断罪令嬢”とは別人のようだった。
穏やかで、柔らかな光を帯びた顔。
けれど――その平穏を打ち砕くように、扉をノックする音がした。
「奥様、早朝に奇妙な手紙が届きました」
執事が恭しく差し出した封書には、見覚えのない紋章。
黒い封蝋、絡み合う三頭の竜。
レティシアの瞳が揺れる。
「この紋章……まさか……」
彼女はそのまま手紙を受け取り、震える指で封を切った。
中から現れた羊皮紙には、流麗な筆致でこう記されていた。
> ――親愛なるレティシア・アークハート侯爵夫人へ。
あなたが“王太子に断罪された夜”のことを、私は忘れません。
あの時のあなたの一言、「真実の愛が腐らないように祈っております」――
あれは皮肉ではなく、誇りでした。
あなたと私は同じです。
王に利用され、真実を奪われた者。
どうか、三日後の黄昏、王都北の“聖アレシア修道院跡”へお越しください。
私はあなたに、“真実の聖女”の血について語らねばなりません。
――旧ドラギア帝国皇女 セレーネ・リュシアン
読み終えた瞬間、レティシアの手が震えた。
「……セレーネ様。生きて……?」
かつて外交の場で出会った少女。
銀の髪、紅の瞳、静かな笑み。
ドラギア帝国の崩壊とともに命を落としたはずの皇女。
その彼女が、なぜ今――?
---
朝の執務室で、セドリックは新たな王命に目を通していた。
王国北部の治安再建と、軍の再編。
再婚式の翌日だというのに、彼の机にはすでに戦略地図が広げられている。
「君が王に気に入られた証拠だな」
「気に入られるのは構わない。ただ、王は静かな人間を嫌う」
彼はペンを置き、窓の外を見つめた。
王国の上空に漂う薄い靄――それが不穏に見えた。
そこへ、レティシアが手紙を隠したまま現れる。
「お仕事中に失礼いたしますわ」
「いや、ちょうど休憩しようと思っていた。……顔色が優れないな?」
「いえ……昨夜、少し考え事をしていて」
セドリックは彼女を椅子に座らせ、紅茶を注いだ。
穏やかな香りが広がる。
だが、レティシアの胸の中は穏やかではなかった。
(この人には言えない。王命を帯びている以上、わたくしの話は混乱を招く……)
「何か隠している顔だ」
「まあ……夫に隠し事をする妻なんて、おかしいですわね」
苦笑でごまかしながら、彼の手を取る。
セドリックはその温もりを感じながらも、何かを察していた。
彼は彼女の瞳を見つめ、低く呟く。
「……何があっても、私は君を信じる」
その言葉に、レティシアの胸が痛んだ。
――だからこそ、言えない。
---
三日後の夕刻。
王都の北端に広がる廃修道院。
そこはかつて“聖アレシア”が祀られた神聖な地だったが、いまは荒廃し、鳥の声すら聞こえない。
廃墟のような回廊に、ひとりの女が歩を進める。
赤いマントのフードを深く被ったレティシア。
背後には、信頼する侍女マルタの影。
「奥様、本当に……ここに来てよろしいのですか」
「ええ。真実を知るために」
彼女の指先には、セドリックから贈られた“紅の指輪”が輝いている。
その輝きが、どこか不安げに揺れていた。
---
廃堂の中央。
崩れた祭壇の前に、ひとつの灯火がともっていた。
その光の向こうに、白いローブの女が立っている。
――銀髪、紅の瞳。
「来てくれたのね、レティシア」
声は柔らかく、それでいて底冷えするような美しさを帯びていた。
「セレーネ様……本当に生きていらしたのですね」
「生きて、そして見ていたの。王国がどうやって“聖女”という名を利用しているかを」
セレーネは近づき、レティシアの手を取った。
その冷たさに、思わず息を呑む。
「あなたの婚約破棄――あれは偶然ではないわ。
王家は、“聖女の血”を継ぐあなたを王太子妃にできなかった。
なぜなら、“王より上の存在”になってしまうから」
「わたくしが……聖女の血を?」
セレーネは頷いた。
「あなたの母方の祖母は、ドラギア帝国の分家の姫。
つまり、あなたは“本物の聖女”の直系。
王国はそれを隠し、あなたを断罪することで“血の真実”を封じたのよ」
レティシアの唇が震える。
「そんな……では、あの“新聖女リリア”は……?」
「造られた偽り。
王国の魔導師たちが、我が帝国の遺物――“聖遺晶”を使って創り出した人形の聖女よ」
衝撃に、レティシアは言葉を失った。
あの夜、王太子が誇らしげに「真実の愛」と宣言したあの瞬間――
すべてが仕組まれた芝居だったのか。
セレーネは静かに彼女の肩に手を置いた。
「王国は再び“聖女の儀式”を行うつもり。
けれど、その中心に立たされるのは、あなたの夫――アークハート侯爵よ」
「セドリックが……!?」
「彼は知らない。だが、王は利用するつもりよ。
“氷の侯爵”を聖女の守護騎士として表舞台に立たせ、民の信仰を操る。
その裏で、聖遺晶を用いた“血の儀”を完成させる気なの」
レティシアは立ち尽くした。
頭の中で、鐘の音が鳴り響くようだった。
(セドリックが……利用される? わたくしのせいで……?)
セレーネが微笑む。
「止められるのは、あなたしかいない。
“真なる聖女”としての血を覚醒させなさい。
あなたが祈れば、王国の偽りの聖女は消える」
「……わたくしに、そんなことができるの?」
「できますとも。
あなたが愛のために涙を流したとき、その紅の指輪が道を開く」
セレーネは炎の中に姿を溶かすように消えていった。
残されたのは、香のような甘い匂いと、ただ一言。
> 「――選びなさい、レティシア。
愛する夫を救うか、国の真実を暴くか」
---
廃堂を出たとき、空は夕闇に沈んでいた。
マルタが駆け寄る。
「奥様! お顔が真っ青です……!」
「……大丈夫よ」
そう答えながら、レティシアは指輪を握りしめた。
紅の宝石が、まるで心臓の鼓動に呼応するように脈打っている。
(愛か、真実か――)
紅の誓いを立てたばかりの彼女の瞳に、決意の光が宿った。
1
あなたにおすすめの小説

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

で、お前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか?
Debby
恋愛
ヴェルトが友人からの手紙を手に辺境伯令嬢であるレィディアンスの元を訪れたのは、その手紙に「詳細は彼女に聞け」と書いてあったからだ。
簡単にいうと、手紙の内容は「学園で問題を起こした平民──エボニーを妻として引き取ってくれ」というものだった。
一方その話を聞いてしまった伯爵令嬢のオリーブは動揺していた。
ヴェルトとは静かに愛を育んできた。そんな自分を差し置いて、言われるがまま平民を妻に迎えてしまうのだろうか。
そんなオリーブの気持ちを知るはずもないエボニーは、辺境伯邸で行儀見習いをすることになる。
オリーブは何とかしてヴェルトを取り戻そうと画策し、そのことを咎められてしまう。もう後は無い。
オリーブが最後の望みをかけてヴェルトに自分を選んで欲しいと懇願する中、レィディアンスが静かに口を開いた。
「で、そろそろお前が彼女に嫌がらせをしている理由を聞かせてもらおうか」
「はい?」
ヴェルトは自分が何を言われたのか全く理解が出来なかった。
*--*--*
覗いてくださりありがとうございます。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
★全31話7時19時更新で、全話予約投稿済みです。
★★「このお話だけ読んでいただいてもOKです!」という前提のもと↓↓↓
このお話は独立した一つのお話ですが、「で。」シリーズのサイドストーリーでもあり、第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」の「エボニーその後」でもあります(あるいは「最終話」のその後)。
第一弾「で、私がその方に嫌がらせをする理由をお聞かせいただいても?」
第二弾「で、あなたが私に嫌がらせをする理由を伺っても?」
第三弾「で、あなたが彼に嫌がらせをする理由をお話しいただいても?」
どれも女性向けHOTランキングに入り、特に第二弾はHOT一位になることが出来ました!(*´▽`人)アリガトウ
もしよかったら宜しくお願いしますね!
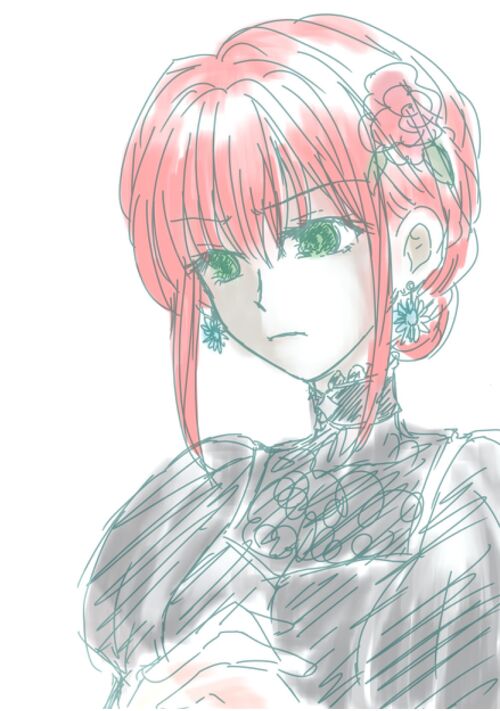
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

戦う聖女さま
有栖多于佳
恋愛
エニウェア大陸にある聖教国で、千年ぶりに行われた聖女召喚。
聖女として呼ばれた魂の佐藤愛(さとうめぐみ)は、魂の器として選ばれた孤児の少女タビタと混じり、聖教国を聖教皇から乗っ取り理想の国作りをしながら、周辺国も巻き込んだ改革を行っていく。
佐藤愛は、生前ある地方都市の最年少市長として改革を進めていたが、志半ばで病に倒れて死んでしまった。
やり残した後悔を、今度は異世界でタビタと一緒に解決していこうと張り切っている。悩んだら走る、困ったらスクワットという筋肉は裏切らない主義だが、そこそこインテリでもある。
タビタは、修道院の門前に捨てられていた孤児で、微力ながら光の属性があったため、聖女の器として育てられてきた。自己犠牲を生まれた時から叩き込まれてきたので、自己肯定感低めで、現実的でシニカルな物の見方もする。
東西南北の神官服の女たち、それぞれ聖教国の周辺国から選ばれて送り込まれた光の属性の巫女で、それぞれ国と個人が問題を抱えている。
小説家になろうにも掲載してます。

悪役令嬢としての役目を果たしたので、スローライフを楽しんでもよろしいでしょうか
月原 裕
恋愛
黒の令嬢という称号を持つアリシア・アシュリー。
それは黒曜石の髪と瞳を揶揄したもの。
王立魔法学園、ティアードに通っていたが、断罪イベントが始まり。
王宮と巫女姫という役割、第一王子の婚約者としての立ち位置も失う。

天才魔術師の仮面令嬢は王弟に執着されてます
白羽 雪乃
恋愛
姉の悪意で顔半分に大火傷をしてしまった主人公、大火傷をしてから顔が隠れる仮面をするようになった。
たけど仮面の下には大きい秘密があり、それを知ってるのは主人公が信頼してる人だけ
仮面の下の秘密とは?

わたしたちの庭
犬飼ハルノ
恋愛
「おい、ウェスト伯。いくらなんでもこんなみすぼらしい子どもに金を払えと?」
「まあまあ、ブルーノ伯爵。この子の母親もこんな感じでしたが、年ごろになると見違えるように成熟しましたよ。後妻のアリスは元妻の従妹です。あの一族の女は容姿も良いし、ぽんぽんと子どもを産みますよ」
「ふうん。そうか」
「直系の跡継ぎをお望みでしょう」
「まあな」
「しかも伯爵以上の正妻の子で年ごろの娘に婚約者がいないのは、この国ではこの子くらいしかもう残っていませんよ」
「ふ……。口が上手いなウェスト伯。なら、買い取ってやろうか、その子を」
目の前で醜悪な会話が繰り広げられる中、フィリスは思った。
まるで山羊の売買のようだと。
かくして。
フィリスの嫁ぎ先が決まった。
------------------------------------------
安定の見切り発車ですが、二月中に一日一回更新と完結に挑みます。
ヒロインのフィリスが自らの力と人々に支えられて幸せをつかむ話ですが、
序盤は暗く重い展開です。
タグを途中から追加します。
他サイトでも公開中。

「やはり鍛えることは、大切だな」
イチイ アキラ
恋愛
「こんなブスと結婚なんていやだ!」
その日、一つのお見合いがあった。
ヤロール伯爵家の三男、ライアンと。
クラレンス辺境伯家の跡取り娘、リューゼットの。
そして互いに挨拶を交わすその場にて。
ライアンが開幕早々、ぶちかましたのであった。
けれども……――。
「そうか。私も貴様のような生っ白くてか弱そうな、女みたいな顔の屑はごめんだ。気が合うな」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















