2 / 4
2章
2
しおりを挟む
2-1
婚約の発表から、あっという間に十日以上が過ぎ去った頃――ステラリア家の内外は、いよいよ迫る「無彩の婚礼」に向けて慌ただしさを増していた。実際には結婚式という呼び名を与えられてはいるものの、カリナ・ステラリアにとっては全く心躍る催しとは思えない。名家同士の縁組、それもヴェイル公爵家の若き後継者エドリック・ヴェイルとの結びつきは、彼女の自由を奪い去る鎖に他ならないからだ。それでも、父ハロルド伯爵の命令に背くなど、現状のカリナにはとてもできないことだった。
式の前段として取り行われる「前儀式」が行われる日、朝早くからステラリア家の屋敷には多数の使用人が集い、最終的な確認作業に追われていた。礼拝堂の飾り付け、来賓の受付の手配、食事の手順や進行役の調整にいたるまで、すべてが完璧に進められなければならない。カリナは着付け係に勧められるまま、いつもよりも豪勢なドレスに袖を通し、鏡越しに映る自分の姿をぼんやりと眺める。そこには、どこか憔悴した面差しの少女がいるだけだった。
「失礼いたします、カリナお嬢様。礼拝堂にお越しくださいとのことです。エドリック・ヴェイル様もすでに到着されております。」
侍女長の報告に従い、カリナは重たい足取りで屋敷を出る。馬車に乗り込むと、車窓から見える澄んだ青空が恨めしく感じられた。本来ならば、祝福の証しとも呼べるような晴れ渡った空なのに、カリナの心は曇天よりもなお重い。ゆっくりとした馬車の振動に身を委ねながら、彼女は自分がこれからまさに“形式だけ”の結婚式を迎えるという現実を改めて思い知るのだった。
礼拝堂に降り立つと、すでに伯爵や親戚筋の貴族たちが顔を揃えており、カリナが入ってきたのを見計らうようにひそひそとした声が飛び交う。だが、それらの言葉は「美しい花嫁になること」「ステラリア家とヴェイル公爵家の結びつきを大いに祝う」という、表面的な祝辞ばかり。カリナは心底それに応える気など起きず、ただ生返事を繰り返して静かに礼拝堂の祭壇へと歩み寄る。
そこには、既に到着していたエドリックが待ち構えていた。黒の礼服に身を包む彼は、あまりにも冷たい表情で、カリナに目を向けることすらほとんどしない。直立不動のまま、ただ儀式の進行を待っているかのようだ。その横には、エドリックの愛人だという噂を持つ妖艶な女性の姿すら見え隠れしていて、カリナは一瞬、胸が痛む。いや、最初から分かっていたことだ――エドリックにとって、カリナとの婚礼は「必要条件」でしかないのだ、と。まるで将棋の駒のように扱われる自分を自覚しながら、それでも伯爵家の名誉を守るため、カリナはここに立っている。
儀式を司る神官が、穏やかな声で導師の書を読み上げ、二人に対して誓いの言葉を交わすよう促す。こうした場には数多く参列してきたはずなのに、いざ自分がその中心に立つと、ただ息苦しさだけが募っていく。「汝、エドリック・ヴェイルは生涯にわたり、この者を慈しみ、守ることを誓うか」――神官の問いに、エドリックはわずかに瞼を伏せるだけで、抑揚のない声を出す。「誓う」――その一言に、仮面のような敬虔さと揺るぎなさが共存しているのがわかる。だが、そこに愛など微塵も感じられない。
同じ問いがカリナにも向けられる。周囲の視線を一身に浴びながら、彼女は喉が詰まる思いで声を震わせる。「……はい。誓います」。これでいいのだろうか――そんな疑問が脳裏を掠めるが、今更どうにもならない。父の期待、そしてステラリア家の再興という重責が、カリナの意志を封じ込めている。
形式的な誓いの言葉と、互いの手を取り合う芝居じみた仕草。礼拝堂を包む厳かな空気の中、人々は拍手をもって二人を祝福する。ただし、その拍手に熱はなく、どこか事務的であるようにも感じる。カリナとエドリック、それぞれの周囲に控える貴族たちは、そんな「義務のための婚礼」を当たり前のように受け止めているのだから。
こうして前儀式は滞りなく終わり、午後には大広間での披露会が控えていた。カリナにとっては、ただの通過儀礼に過ぎないとわかっていながらも、再びドレスを着替え、客人たちの前で微笑まなくてはならない。だが、その足元には、隠しようのない重さが纏わりついている。いつまで自分は「伯爵家の娘」としてしか存在を許されないのか――どれほど辛くても、今の彼女には答えが見つからない。
屋敷へ戻る馬車の中、カリナは小さな窓から見える景色を眺めながら、ふとあの日のことを思い出す。そう、美術市で出会った青年、リース・アルファードの優しい笑顔。自由に絵を描き続ける彼の言葉に触れた瞬間、氷のようになっていたカリナの心は溶けかけていた。それでも、逃れられない現実に再び押し潰されるような感覚が、今まさに襲いかかる。けれど、その記憶を無理に追い払ってしまうのも、何かを失うようで怖かった。
(あの人は今頃、どこでどんな絵を描いているんだろう……)
そう思うだけで、一瞬だけ心が軽くなる。しかし、馬車が重々しく石畳を通り抜け、ステラリア家の屋敷が見えてくると、現実がまるで分厚い壁となって行く手を遮るのだった。ドアを開けた先には、父の怒声や、家令の冷たい視線、そして来客を迎えるための慌ただしい準備が待ち受けている。
――無彩の婚礼は、まだ始まったばかり。この先も連なる儀式を経て、カリナはまるで大切なものを消し去るように、「夫婦」という形を受け入れなくてはならない。それでも彼女の心の奥には、絵を描くことへの小さな熱がかすかに燻り続けていた。どれほど規則や常識、そして周囲の期待に縛られようとも、その炎が完全に消えることはきっとない。その夜、カリナはベッドに沈み込む寸前、枕元に置かれたスケッチブックを撫でながら小さく呟くのだった。
「私……まだ、諦めたくない……」
2-2
午後の礼拝堂での前儀式を終え、ステラリア家の馬車が屋敷へ戻ってきた頃には、日はすでに高い位置からやや傾き始めていた。カリナ・ステラリアが玄関ホールへ足を踏み入れると、そこには結婚の披露宴――いわゆる“婚礼パーティ”の準備に追われる使用人たちが何人も行き来している。皆、目まぐるしく動いては大きなテーブルを運んだり、絢爛豪華な装飾品を配したりと大忙しだ。まるでほんの少し前まで“前儀式”を取り仕切っていたのが嘘のように、ここではまったく別の催しが行われるかのようにすら見える。
カリナはその光景を眺めながら、深い息をひとつ吐いた。これから先、ヴェイル家の婚礼を祝うために多くの来賓が訪れる予定となっている。とはいえ、家同士の結びつきを強調するために行われるものに過ぎず、真の意味で“祝福される”空気はどこにも感じられなかった。豪奢な装飾も、山のように届けられた花束も、すべては「こうあるべきだ」という型どおりの演出にしか思えない。しかも、当のエドリック・ヴェイルは馬車から降りた直後、さっさと公爵家の執事に伴われていずこかへ姿を消してしまったらしい。まるで「婚礼パーティ」の主役であるはずの相手が、これ以上ないほど無関心だという事実が、カリナの胸をひどく痛ませる。
「お嬢様、お戻りなさいませ。こちらでドレスを再チェックしていただけますか? 披露宴ではまた別の装いが必要とのことですので……」
侍女長が丁寧に頭を下げながら、鏡張りの部屋へカリナを促す。この部屋は、結婚式に向けた準備が始まって以来、試着や打ち合わせのために使われてきた場所だ。足を踏み入れるや否や、カリナの視界には真っ白なドレスがいくつも掛けられているのが映る。どれもこれも高価なレースや宝石がふんだんにあしらわれていて、見た目の美しさに抜かりはない。けれど、まるで彼女の意志など介在しないまま勝手に選ばれたようなそれらは、カリナにとってはもはや重苦しいだけだ。
「こちらが新たに仕立てました“お色直し”用のドレスでございます。先ほどの礼拝堂用とは違い、スカートの裾に大ぶりのフリルが加わっておりますので、華やかさがいっそう際立ちますわ」
仕立て担当の女性が胸を張って紹介するが、カリナはどこか上の空のまま生返事しかできない。美しさを競うのは嫌いではなかったはずなのに、今の状況ではドレスを着飾るたびに「自分が人形のように扱われる」という思いが増していく。とはいえ、この場で不機嫌そうに拒んだところで何も変わらない――結局、彼女は侍女たちの手を借りて淡々と着替えを進めるだけだった。
鏡越しに映る自分の姿を見ても、そこに“花嫁”としての幸せが感じられないのは周知のこと。横に立つ侍女の一人が「お嬢様、少し顔色が優れないように見えますが、ご気分はいかがですか?」と気遣ってくれるが、カリナは慌ててかすかな笑みを取り繕う。伯爵家の令嬢として“弱音”を吐くなど許されるはずもないし、そもそも婚約者のエドリックですら「形式だけ」の婚礼に興味を示していない。周囲へ不満や悲しみを打ち明けられるはずがなかった。
やがて、準備を終えたカリナが大広間の前までやってくると、すでに伯爵である父が貴族仲間と何やら会話を交わしているのが見える。豪奢な扉から漏れ聞こえてくる音は、華やかな弦楽の演奏。どうやら着々と宴は始まろうとしているようだ。父が彼女に気づくと、すぐさま視線を向けて強い口調で言い放つ。
「カリナ、時間だ。まもなく開宴となるから、余計なことは言わず、愛想よく振る舞うのを忘れるな。ステラリア家の面目に泥を塗るなよ」
まるで脅しにも似たその言い方に、カリナは小さく身をすくめる。けれど、父の言うとおり、この“婚礼パーティ”はステラリア家が王国最強と呼ばれるヴェイル家に認められるための大切な舞台なのだ。すべてを演出し、すべてを整え、少しでもステラリア家の権威が高まるように……それが伯爵の望みであり、同時にカリナの“義務”でもある。
深呼吸をして、大広間の扉を開けると、そこにはきらびやかなシャンデリアがいくつも灯され、眩しいほどの光彩が広がっている。フロアには既に多くの貴族や名士が集まり、それぞれが様々な思惑を抱きながら会話をしている様子だ。招待客たちは一斉にカリナの方を振り向き、「おめでとうございます」「さすがに美しい花嫁ですね」などと称賛の声を投げかける。形式上の“お祝い”の言葉ばかりが耳に入ってくるが、そこにこもる熱はどれほどのものか。カリナは呆然としながら、それでも微笑みを返すしかない。
肝心のエドリックの姿を探そうと人波を見渡しても、やはり彼は見当たらない。代わりに目に飛び込んできたのは、かの妖艶な愛人と噂される女性だ。真紅のドレスを纏った彼女が、まるでこの場を支配する女王のように、堂々とした態度で招待客たちと談笑している。ちらりとカリナを捉えた眼差しは、まるで「あなたなど形だけの花嫁」と言わんばかりの嘲笑を含んでいるようにも感じられた。
「カリナ様、こちらへどうぞ。ご挨拶をしたいという方が列をなしていらっしゃいます」
使用人に促されるがまま、カリナは次々に客人から祝福の言葉を受ける。中には「ヴェイル公爵家との縁組は、ステラリア家にとっても大変素晴らしい機会ですね」などと露骨に家同士の利害関係を取り沙汰する者もいて、それが一層、彼女の虚無感を煽る。酒杯や料理をすすめられても、まるで喉を通らない。薄く微笑みを浮かべては礼を言い、またすぐに次の客へ――と動き回るうちに、カリナは頭がぼんやりとしてくるのを感じる。
「お嬢様、ご気分が悪そうですが……大丈夫ですか?」
近くにいた侍女が心配げに声をかけると、カリナは何とか笑顔を取り繕いながら首を振る。弱音を吐けば、すぐに父から「余計な騒ぎを起こすな」と叱責されるだろうし、そんな姿を見せること自体が恥だと教えられてきたからだ。心がきしむような痛みに耐えながら、ただ形ばかりの“祝福”を浴び続けるしかない。
そのうち、カリナは人混みの奥に見知った顔を見つけて、驚きに瞳を見開いた。リース・アルファード――先日、美術市で出会った青年が、なぜかこの場にいる。あのときは小さな画廊を手伝いながら、自身の絵を売っていると語っていたのに、こんな華やかなパーティへ招かれる立場なのだろうか。リースの傍らには壮年の紳士が控えており、どうやら彼が案内役らしい。二人とも貴族というよりは、美術関係の賓客として呼ばれたのかもしれない――そう直感しながらも、カリナはどこか嬉しさに似た安堵を覚える。
と同時に、彼女ははたと我に返った。自分は“ヴェイル公爵家の花嫁”としてここにいる。もしリースと直接言葉を交わし、芸術談義などに花を咲かせようものなら、周囲の目をひどく気にする父がただで済ませるはずはない。何より、この婚礼パーティで“本当の関心”を見せる相手に会うことはカリナ自身の心を揺るがしてしまう。今は――そう、今は耐え忍ばなければならないのだ。
しかし、リースの方もすぐにカリナに気づいたのか、何やら複雑そうな表情を浮かべて会釈してくる。彼の瞳には、あの日と同じ優しさがあった。それだけで、カリナの胸に再び暖かな光がともる。しかし彼女は視線を反らすように、小さく礼を返すだけで歩み去った。彼に近づいてはいけない。それが今の“義務”だと思ったから。
――こうして、華やかな披露宴の最中にも関わらず、カリナの心はどこまでも沈んでいく。客人たちの興味は、果たして“新婦”としての彼女自身に向いているのか、それとも“ステラリア家とヴェイル家”を繋ぐ儀礼の中心としての道具なのか。答えなど分かりきっているというのに、ふとした瞬間に胸が苦しくなる。リースを見た瞬間の揺らぎは、その苦しさにまた別の色彩を与えてしまう。
あまりに耐えがたい息苦しさに、カリナは大広間の端に置かれた椅子へ腰を下ろす。人々は皆、誰かと利害を計りながら、もしくは単なる社交としての歓談に没頭している。微笑と華やかさに満ちあふれた場のはずが、カリナには冷たく空々しい空気がまとわりつくようにしか感じられない。果たして、この“無彩の婚礼”に“色”が灯る日はやってくるのだろうか――その疑問が、じわりと彼女の心を覆い尽くす。
遠く聞こえる音楽と、偽りの祝福。父や周囲の視線を恐れて話しかけることさえ叶わない、唯一の“理解者”かもしれない人物。エドリックの姿は依然として見当たらず、愛人の女が嘲笑するように真紅のドレスを揺らしている。まるで演じられた劇を見ているかのように、カリナは微動だにできない。それでも、心のどこかでは、かすかに灯る火が消えぬように――あの夜に思い描いた“私は道具になりたくない”という決意を、ただ必死に抱きしめていた。
2-3
ステラリア家の大広間で繰り広げられる「婚礼パーティ」は、いっそう熱を帯びていた。招かれた貴族や名士たちが、煌びやかな装いで思い思いに会話を交わし、あちこちでグラスを傾け合っている。入口近くに並べられた豪華な食事やワインは次々に空となり、給仕係は忙しなく補充のために動き回っていた。
一見すれば、まさに祝福の宴――ところが、その場の中心であるはずのカリナ・ステラリアは、まるで自分が舞台の脇役に追いやられたような疎外感に苛まれていた。窮屈なドレスの重みと不慣れなハイヒールで足が痛み、誰と話しても決まりきった祝辞ばかりが返ってくる。ましてやエドリック・ヴェイル本人はどこかへ姿を消したまま。形だけの祝福の渦の中、カリナはただ虚空を見つめながら、胸の奥で燻る感情をどう処理すればいいのか分からないでいた。
「――カリナ様、おめでとうございます。ヴェイル家とステラリア家のご縁、誠に喜ばしいことですわね」
そう言いながら近づいてきたのは、どこかで見たような派手な装飾を纏った中年の婦人だった。顔立ちから察するに、伯爵家に縁のある貴婦人なのだろう。カリナはとっさに作り笑いを浮かべ、「ありがとうございます」と返す。けれど、その声には張りがなかった。相手はそんな気配に気づいたのか、あるいは最初からカリナの心中など気にも留めていないのか――舌先だけの祝辞を告げると、さっさと次の人のもとへと去ってしまう。
華やかな衣服と笑顔に彩られた“祝福の場”は、カリナにとってただの空々しい見世物に等しかった。拍手や笑い声が大広間に充満しているのにもかかわらず、自分だけが微かな寒さに包まれているように思えてならない。
そんなとき、視界の端に目立つ赤いドレスが入る。エドリックの愛人と噂される妖艶な女性が、貴族たちの輪の中心で微笑んでいた。彼女のそばを通り過ぎた人が、カリナに気づいて軽く会釈するが、赤いドレスの女のほうはまるで無関心。あるいは意図的に“彼女を無視する”という意思表示にも見える。
もしかしたら、あの女はすでに“妻の座”を手に入れたかのように振る舞っているのかもしれない――そう思った瞬間、カリナの心はひどく乱される。実際、すでに何度かエドリックとの噂が立っている彼女を、誰も咎める様子を見せない。それどころか、一部の貴族たちが彼女をさりげなく持ち上げ、彼女もまたそれを当然のように受け止めているようだ。
カリナは唇を引き結んで、大広間の壁際へと足を運ぶ。人の波から少しでも逃れたい一心だった。壁に背を預けながら、金と銀の煌めきに満ちた空間を眺めると、その美しさがむしろ眩しすぎて目が痛い。いや、まるで自分がここの景色に溶け込んでいないような感覚に囚われるのだ。
「カリナ様、失礼いたします」
ふいに声をかけてきたのは侍女長だった。心配そうに小さく眉を寄せながら、そっと言葉を続ける。
「やはりお疲れのご様子ですね。もしよろしければ、しばらく控室で休まれてはいかがでしょう。父上様には私がうまくご説明いたしますので……」
その提案は、カリナにとって酷く魅力的だった。少しでも人目を離れ、足を休めたいという思いはある。しかし同時に、「婚礼パーティの最中に姿を消すなんて、父が許すはずがない」という恐れも頭をよぎる。
侍女長もその事情は承知しているのか、言葉を探すように口ごもる。「お嬢様がお辛そうですし、ご体調がすぐれないようですと皆様にも示しが立ちません。ここは私に任せて……」
それを聞いたカリナは、押し寄せる罪悪感と安堵感の狭間で揺れる。だが、いずれにしてもこのまま“大勢の客から形だけの祝福を受ける人形”で居続けるほうが、心を壊してしまいそうだった。意を決した彼女は、侍女長に小さく頷き返す。
「……ごめんなさい。では少しだけ、控室で休むことにします。お手数をかけて申し訳ないわ」
「いえ、どうかお気になさらず。私がうまく場を取り繕いますので、どうぞご安心ください」
こうしてカリナは侍女長に先導され、さほど広くない控室へと入っていった。石造りの壁と最低限の調度品だけが置かれた、質素ではあるが静かな空間だ。ドアを閉めると、外からの喧騒は幾分か遮られ、少しだけ呼吸が楽になる。
「お疲れかもしれませんが、何か温かいお飲み物をご用意しましょうか?」
侍女長がそう申し出ると、カリナは少し考えた末に「じゃあ、ハーブティーをいただけるかしら」と答える。体を温めたいというよりは、せめて落ち着きたかったのだ。まもなく侍女長は深く頭を下げて、ドアの外へと足早に立ち去っていく。
控室にひとり取り残されたカリナは、気だるい体を椅子に沈める。ドレスのコルセット部分がやけに胸元を締め付けて苦しいが、慌ただしい場から逃れられただけでも幾分か救われる思いだった。
(あぁ、ずっとこうしていられたら、どんなに楽かしら……でも、そんなわけにはいかないのよね)
重い息をついて目を閉じると、脳裏に浮かぶのはリース・アルファードの姿だった。美術市で初めて出会ったときのあの穏やかな笑顔、そして先ほどほんの一瞬だけ視線を交わしたときの戸惑いが混ざった表情――彼は今ごろ、あの賑やかな大広間でどんな思いを抱えているのだろう。
まさかこの婚礼パーティにまで来ているとは予想していなかった。どうして呼ばれたのか、誰の紹介なのかも分からない。しかし、絵を志す者として時折貴族のパーティに招かれることは珍しくないとも聞く。大手の画廊関係者が来ているなら、リースが同行していても不思議ではない。
(あの人に……少しだけでも、話をしたい。今の私が、どれほど孤独か、そして本当は絵を描きたいのに描けないでいるか……なんてね)
何とも弱々しい独り言に、思わず涙が滲みそうになる。けれど、それを許せばきっと“弱音”が止まらなくなってしまう。父の期待と家名を背負っている以上、“エドリック・ヴェイルの婚約者”としての仮面を外すわけにはいかないからだ。
と、そのとき、扉の向こうから控えめなノックの音が聞こえた。侍女長がハーブティーを持ってきたのかもしれない。カリナは「どうぞ」と声をかける。ところが、そこに現れたのは、侍女長ではなかった。控室のドアを少しだけ開け、ひっそりと中をうかがう青年――リース・アルファードその人だった。
「……失礼、いたします。大丈夫でしょうか、今……?」
彼もまた緊張しているのか、微かに眉根を寄せながら声を落とす。カリナは驚きのあまり一瞬言葉を失うが、やがて小さく頷き、扉を開けて中へと招き入れる。
「どうして、ここに……?」
「先ほど、大広間であなたを見かけました。でもどこか辛そうで……それに、さっき別の女性から“カリナ・ステラリアお嬢様が具合を崩されたかもしれない”って聞いて……心配になったんです」
リースの瞳に宿る純粋な思いやりが、カリナの心を溶かしていく。けれど同時に、この場で彼と二人きりで会話しているところをもし父や他の貴族に見られたら、どれほどの騒ぎになるだろう――そんな恐れもよぎる。しかし、今のカリナはそれでもいいと感じてしまうほどに限界だった。
「ごめんなさい、こんな姿を見せるつもりはなかったのに……」
そう言いかけた途端、堰を切ったように涙が込み上げる。リースは慌てて近寄り、テーブルの上にあった清潔なハンカチを手渡す。
「落ち着いて……大丈夫、誰にも言わない。あなたが本当に辛いなら、僕で良ければ話を聞きます。無理はしないで」
その言葉に救われるように、カリナは声を押し殺しながらも涙をこぼす。絢爛豪華なパーティの最中、伯爵令嬢がこっそりと隠れて泣いているなど、本来あってはならないことかもしれない。だけど、こうして誰かに心を預けられる時間があるだけで、どれだけ救われるだろう。
やがて、嗚咽を噛み殺すように息を整えたカリナは、リースに向けてほんの少しだけ笑みを返す。
「ありがとう……あなたがここに来てくれて、本当に嬉しいわ。いつか……いつか、私も――また絵を描きたい。今は難しいけれど、でもそれを夢見ている自分がいるって……思い出させてくれたの」
リースはまっすぐな眼差しでカリナを見つめ、静かに頷く。
「僕はあなたの絵を、いつか必ず見たいと思ってる。誰の目も気にせず、自由に描ける日がきっと来ます。……だから、どうか諦めないで」
その優しい声に、カリナの心は確かな力を取り戻し始める。儚い火種だった“絵を描きたい”という願いが、ほんの少しだけ明るく揺れ動いた気がした。
――だが、その瞬間、外から聞こえる慌ただしい足音が静寂を破る。どうやら誰かがカリナの所在を探してここへ向かっているらしい。リースが顔色を変えたのと同時に、カリナもまた手早く涙を拭い、立ち上がる。二人でこっそり出入りしているところを見られれば、あまりにも不自然だ。
「行って……! すぐに……! 誰かが来るわ」
「……分かりました。大丈夫ですか?」
「ええ、あなたは先に出て。私は侍女長を待つから……」
短い会話を交わすやいなや、リースは控室の裏手にある小さなドアから素早く姿を消した。入れ替わるようにして部屋の正面ドアが勢いよく開く。現れたのは、侍女長ともう一人、ステラリア家の家令だった。家令は険しい表情で「お嬢様、どちらにいらっしゃいました?」と厳しい口調で問いただしてくる。
「少し休むようにと侍女長が勧めてくれたの。……ごめんなさい、すぐに戻りますから」
カリナは頭を下げながらも、先ほどまでの涙の痕跡が残らないように必死で目をそらす。家令は納得したのかしていないのか、「分かりました。お父上様が大広間でお待ちです」とだけ短く告げる。侍女長は心配そうにカリナの様子を窺うが、彼女が「もう大丈夫です」と微笑むと、それ以上は何も言わなかった。
こうして、カリナは控室を後にする。父と客人たちのいる大広間へ戻らなくてはならないが、その足取りは先ほどよりもいくぶん軽い気がした。重苦しいドレスの締めつけと、絶え間ない虚無感に耐え続ける自分――それでも、リースの励ましは確かに心の闇を照らしてくれた。
(私は道具じゃない。いつかきっと、自由に絵を描ける日が来る……)
胸の奥に宿る小さな炎を、今だけは守り抜こう。父の怒りも、愛人を侍らせる婚約者の冷たさも、何ひとつ変わらない現実かもしれない。だけど、せめて己の夢を捨てることだけはしたくない――そう心に誓いながら、カリナはもう一度、大広間の扉を押し開く。演奏と歓声が耳を打ち、作りものの祝福が彼女を取り囲む。
しかし、その偽りの華やかさにも、ほんのわずかな抵抗を示せるだけの力を、カリナは手に入れつつあった。いつかこの“無彩の婚礼”が燃え上がるときが来るならば――その時には、今とは違う色彩が溢れ出してほしい。リースの言葉がくれた温かな光を頼りに、カリナは再び人々の視線に身を晒しに行く。それが、彼女にできる精一杯の“逆らい方”だった。
2-4
「婚礼パーティ」がひとまずの最高潮を迎え、客人たちも酒や音楽に酔いしれている頃――カリナ・ステラリアは大広間の中央付近に立ちながら、どこか遠くを眺めていた。先ほど控室でリース・アルファードと交わした短い言葉の余韻はまだ残っている。ほんのわずかな時間だったとはいえ、あの穏やかな声と、何より「あなたの絵を見たい」という励ましが、カリナの心を支えていたのだ。とはいえ、この圧倒的な虚飾と形式ばかりを押しつける宴からは、もう逃げ出したい思いが募っていく。それでも、父ハロルド伯爵の視線がある限り、カリナはこの場を離れることが許されない。
実際、父は大広間の一角で貴族仲間と盛んに会話を交わしている。その話題の中心は、もっぱら「ヴェイル公爵家との縁組がもたらす利得」であるようだ。財政の話、新たな商会との取引、王都からの政治的信用――どれもこれも伯爵にとって喉から手が出るほど欲しい“恩恵”なのだろう。ちらりとこちらを窺うように目をやった彼は、常に「ステラリア家の顔」を意識しているのか、カリナが怪しまれないよう監視しているようにも見える。
(父様にとって、私はどう映っているんだろう……)
そんな疑問が胸をかすめるが、答えは既にわかっている気がする。自分はただの「交渉の駒」であり、「家を支える手段」に過ぎない。いくらドレスで飾り立てられ、今宵の主役であると周囲に称えられたところで、真実は何も変わらない。
視線を左右に巡らせると、ひときわ華やかな赤いドレスが目に入る。エドリック・ヴェイルの愛人と噂される女性だ。彼女はどこかの公爵夫人や伯爵夫人らと気さくに談笑しながら、ワイングラスを優雅に傾けている。笑みを絶やさぬ横顔には絶対の自信が宿っており、周囲の目をまるで気にも留めない。“正妻”となるはずのカリナをよそに、まるでこのパーティの真の女主人かのように振る舞っているのだから、見ているだけで息苦しさを感じる。
さらに、彼女の笑顔の奥には薄ら寒い影もちらついていた。カリナと視線が合うや否や、ほんのわずかに口元を歪めてみせた気がする。それは「あなたが“形だけの花嫁”であることなど、とっくにお見通しよ」と言わんばかりの嘲笑にも見えた。もしかすると、エドリック自身が彼女をこのパーティへ招いたのだろうか。そう思うと、不思議と怒りよりも虚しさが込み上げる。
(なぜ私は、こんなにも報われない立場にいるのかしら――)
そう胸中で呟いた瞬間、人込みをかき分けて再びリースの姿が見えた。彼が豪華な調度品や格式ばった貴族たちを前に、少し居心地の悪そうに立ち尽くしているのがわかる。先ほど控室に来てくれたときの面影とは打って変わって、今は人前で自分の立場を誤魔化すように隠そうとしているようにも見えた。画廊の主や支援者とともに招待されたらしいが、周囲の雰囲気に溶け込むのは容易ではないだろう。それでも彼は、その場にふさわしい作法を守りつつ、時折カリナの様子を探るように目線を送ってきた。
もちろん、カリナも心の中ではリースに近づきたいと思う。だが、今は伯爵家の娘として振る舞わなければならない以上、軽々しく談笑するわけにもいかない。父の命令は絶対だし、何より彼女自身が「これ以上騒ぎを起こしてはいけない」と強く感じているからだ。
客人たちが絶え間なくカリナを囲み、「おめでとうございます」「あなたほどの美女が、国随一の公爵家の妻になるなんて運命的ですわ」などと口々に述べる。もはやそのどれもが借り物の言葉であるかのようにしか聞こえない。実際、エドリックと共に並び立ったのは礼拝堂の“前儀式”と婚礼パーティ開始の直後だけで、それ以降は一度も顔を合わせていないのだから。
(いったいエドリックは、どこに行ったの?)
そんな疑問が生まれたと同時に、視界の片隅で、問題の人物を捉えた。彼は大広間の奥まった場所で数人の貴族と談笑している。やはり、こちらに向ける視線は皆無に等しく、まるで最初から“自分の婚礼パーティ”など興味がない、と言わんばかりだ。カリナをちらりと見ることさえなく、冷然とした横顔を客人たちに向けている。
そのとき、彼の隣にすっと寄り添うように赤いドレスの女性が姿を見せた。愛人――そう呼ばれて久しいその女性は、エドリックの腕にさりげなく触れ、にこやかに笑みを交わす。並んで立つ二人の姿は、まるで“婚礼”にふさわしい新郎新婦のようにさえ見えた。それは、傍目にも「公然の仲」であると悟らせるに十分な光景だ。
カリナはぞっとするほどの疎外感に襲われ、ドレスの裾をぎゅっと握りしめる。しかし、どれほど胸がかき乱されても、ここで騒ぐわけにはいかない。周囲の客が見ている以上、“ステラリア伯爵家の令嬢”である自分が取り乱すなど、あってはならないことだ。まるで深い沼に足を取られているような感覚の中で、彼女は吐き出せない感情をぐっと堪える。
「――カリナ、こっちへ来い。お前を紹介したい方がいらっしゃる」
唐突に父が呼びかけてきた。傍には、肥満体の紳士とそれに付き従うらしき従者が立っている。聞けば、この紳士は王都に近い街で多くの画商を束ねる大富豪だという。伯爵家にとっては新たな“スポンサー”になり得る存在らしく、父は上機嫌な様子で「婚姻を通してさらにステラリア家は発展を目指す所存です」と力説している。もちろん、そこにカリナの意見や意思が入る隙などない。
挨拶が済むと、富豪は何やら腑に落ちないような表情でカリナを一瞥する。その視線には純粋な祝福など微塵もなく、「なるほど、話には聞いていましたが……まあ、私に利益がもたらされるなら協力しましょう」とでも言いたげな雰囲気だ。父はそれを歓喜の色を滲ませて受け止め、「では後日、改めて詳しい話を――」と熱心に食い下がっている。
(すべてがお金や権力、利害関係で動いているんだわ――)
そう思うと、自分がさらに惨めに思えてくる。伯爵家は落ちぶれかけているとはいえ、昔はもう少し誇り高さを保っていたはずだ。いつからこんなにも露骨に“何かを得るための取引”に奔走するようになったのか。もしかすると、あまりにも長く続いた財政難が父を焦らせ、このような手段に走らせたのかもしれない。しかし、その皺寄せを一身に背負っているのは、娘であるカリナなのだ。
立ち話を終え、富豪とその従者が去っていくと、父はちらりとカリナに視線をやる。
「いいか、ここでの態度一つが我が家の将来を左右しかねん。余計な口をきくな、分かったな」
カリナは形だけ頷きながら、心の中で反発の炎が燃え上がりそうになるのをどうにか抑え込む。そんな自分に嫌気がさしつつも、これが今の“現実”なのだと思い知らされる。
再び人波の中に戻ると、客人の誰かが音楽隊にリクエストをしたのか、優雅な舞曲が広間に響き始める。貴族たちが楽しげに踊りの輪を作り、華麗なステップを踏んでいる。通常ならば、こうした婚礼の場では新郎新婦が先頭に立って踊るのが常だが、エドリックは目もくれないどころか、赤いドレスの女と一緒に笑い合っている。カリナはそんな情景を横目に見ながら、まるで息をする場所さえ与えられていないような窮屈さに支配されていた。
そのとき、不意に誰かがそっと腕を引いた。驚いて振り返ると、そこにはリースの姿があった。彼は何か声をかけようと口を開きかけるが、すぐに思い直すかのように小さく首を振る。そして視線だけで「このままではあまりに辛いのではないか」と問いかけてくる。
けれど、今は言葉を交わすわけにはいかない――そう察したカリナは、申し訳なさそうに目を伏せる。周囲の客人は踊りや歓談に夢中で彼らを注視してはいないが、さすがにあまり長く会話を続ければ目立ってしまう。リースもまた、ここで騒ぎになることは望んでいないだろう。結局、彼は軽く頭を下げるだけで、すぐに人混みの奥へ消えていった。
(本当なら、こんな派手な場所じゃなくて、穏やかに絵のことを話したいのに……)
音楽がより熱を帯び、歓声と拍手が重なり合う中、カリナはふと感じた。――この場には「祝福」の色がない。派手な装飾や美酒、楽しげな笑い声さえ、すべては利害や形ばかりの体裁で彩られているだけ。婚礼とは名ばかりの“無彩の宴”だと痛感し、心がひどく冷たくなる。
そんな中、父がまた別の客人を捕まえては談笑を始める様子を、カリナは呆然と眺める。彼女に与えられた役割は「そこにいるだけ」であり、それ以上でも以下でもない。遠目に見えるエドリックと愛人の親しげな姿が、今の彼女の悲惨さをさらに浮き彫りにしていた。だが、絶望の縁に立ちながらも、カリナの中には確かに小さな炎がくすぶっている。――先ほどリースがくれた優しい眼差しを思い出すだけで、まだ自分は完全に壊れていないと思えるのだ。
(いつか、この婚礼が終わったら……絶対にもう一度、絵を描く。私は道具なんかじゃない……)
大広間の扉が開き、新しく到着した客人の姿がちらほら見える。まだ宴は続くのだろう。どこまでも夜が深まり、やがて朝を迎えれば、この白々しい祝福の宴も幕を閉じるかもしれない。だが、カリナの戦いはそこからが本番だ。ヴェイル家に嫁ぐ先で待ち受ける未来は、さらに厳しいものになるだろう。エドリックの冷たさと公然の愛人、ステラリア家の重圧――どれ一つとして救いの光は見えない。
だからこそ、彼女はまだ諦められないのだ。リースと交わした約束――「いつかあなたの絵を見たい」「自由に描ける日がきっと来る」という言葉を胸に、カリナは必死に自分を奮い立たせる。それこそが、今の彼女にとって唯一の“色彩”だった。どんなに華麗な会場であろうと、愛人に囲まれた冷酷な婚約者がいようと、自分の意志だけは塗り潰されてはいけない。
――こうして、虚飾にまみれた“無彩の婚礼”の宴は続いていく。にぎわう人々と、まったく相容れない疎外感。愛のない婚約者と、“花嫁”として祭り上げられながら何も得られない自分。けれど、胸の奥で小さな炎がたしかに燃えていることを、カリナは感じていた。いつか、あの冷たい指輪を外す時が来るならば、その瞬間こそ、この白い――しかし限りなく灰色に近い結婚の世界を突き破れるはずだ。
それを信じながら、カリナはまた一人の客に微笑みかける。馴れない笑顔でも、この場を乗り切るしかない。どれほど偽りの祝福を浴びても、自分の本心までは支配されてたまるものか。心に宿った小さな抵抗を糧に、彼女は歪んだ夜の中を歩き続ける。たとえここが“無彩”の舞台であっても、いつか自分の手で、鮮やかな色を取り戻すために――。
婚約の発表から、あっという間に十日以上が過ぎ去った頃――ステラリア家の内外は、いよいよ迫る「無彩の婚礼」に向けて慌ただしさを増していた。実際には結婚式という呼び名を与えられてはいるものの、カリナ・ステラリアにとっては全く心躍る催しとは思えない。名家同士の縁組、それもヴェイル公爵家の若き後継者エドリック・ヴェイルとの結びつきは、彼女の自由を奪い去る鎖に他ならないからだ。それでも、父ハロルド伯爵の命令に背くなど、現状のカリナにはとてもできないことだった。
式の前段として取り行われる「前儀式」が行われる日、朝早くからステラリア家の屋敷には多数の使用人が集い、最終的な確認作業に追われていた。礼拝堂の飾り付け、来賓の受付の手配、食事の手順や進行役の調整にいたるまで、すべてが完璧に進められなければならない。カリナは着付け係に勧められるまま、いつもよりも豪勢なドレスに袖を通し、鏡越しに映る自分の姿をぼんやりと眺める。そこには、どこか憔悴した面差しの少女がいるだけだった。
「失礼いたします、カリナお嬢様。礼拝堂にお越しくださいとのことです。エドリック・ヴェイル様もすでに到着されております。」
侍女長の報告に従い、カリナは重たい足取りで屋敷を出る。馬車に乗り込むと、車窓から見える澄んだ青空が恨めしく感じられた。本来ならば、祝福の証しとも呼べるような晴れ渡った空なのに、カリナの心は曇天よりもなお重い。ゆっくりとした馬車の振動に身を委ねながら、彼女は自分がこれからまさに“形式だけ”の結婚式を迎えるという現実を改めて思い知るのだった。
礼拝堂に降り立つと、すでに伯爵や親戚筋の貴族たちが顔を揃えており、カリナが入ってきたのを見計らうようにひそひそとした声が飛び交う。だが、それらの言葉は「美しい花嫁になること」「ステラリア家とヴェイル公爵家の結びつきを大いに祝う」という、表面的な祝辞ばかり。カリナは心底それに応える気など起きず、ただ生返事を繰り返して静かに礼拝堂の祭壇へと歩み寄る。
そこには、既に到着していたエドリックが待ち構えていた。黒の礼服に身を包む彼は、あまりにも冷たい表情で、カリナに目を向けることすらほとんどしない。直立不動のまま、ただ儀式の進行を待っているかのようだ。その横には、エドリックの愛人だという噂を持つ妖艶な女性の姿すら見え隠れしていて、カリナは一瞬、胸が痛む。いや、最初から分かっていたことだ――エドリックにとって、カリナとの婚礼は「必要条件」でしかないのだ、と。まるで将棋の駒のように扱われる自分を自覚しながら、それでも伯爵家の名誉を守るため、カリナはここに立っている。
儀式を司る神官が、穏やかな声で導師の書を読み上げ、二人に対して誓いの言葉を交わすよう促す。こうした場には数多く参列してきたはずなのに、いざ自分がその中心に立つと、ただ息苦しさだけが募っていく。「汝、エドリック・ヴェイルは生涯にわたり、この者を慈しみ、守ることを誓うか」――神官の問いに、エドリックはわずかに瞼を伏せるだけで、抑揚のない声を出す。「誓う」――その一言に、仮面のような敬虔さと揺るぎなさが共存しているのがわかる。だが、そこに愛など微塵も感じられない。
同じ問いがカリナにも向けられる。周囲の視線を一身に浴びながら、彼女は喉が詰まる思いで声を震わせる。「……はい。誓います」。これでいいのだろうか――そんな疑問が脳裏を掠めるが、今更どうにもならない。父の期待、そしてステラリア家の再興という重責が、カリナの意志を封じ込めている。
形式的な誓いの言葉と、互いの手を取り合う芝居じみた仕草。礼拝堂を包む厳かな空気の中、人々は拍手をもって二人を祝福する。ただし、その拍手に熱はなく、どこか事務的であるようにも感じる。カリナとエドリック、それぞれの周囲に控える貴族たちは、そんな「義務のための婚礼」を当たり前のように受け止めているのだから。
こうして前儀式は滞りなく終わり、午後には大広間での披露会が控えていた。カリナにとっては、ただの通過儀礼に過ぎないとわかっていながらも、再びドレスを着替え、客人たちの前で微笑まなくてはならない。だが、その足元には、隠しようのない重さが纏わりついている。いつまで自分は「伯爵家の娘」としてしか存在を許されないのか――どれほど辛くても、今の彼女には答えが見つからない。
屋敷へ戻る馬車の中、カリナは小さな窓から見える景色を眺めながら、ふとあの日のことを思い出す。そう、美術市で出会った青年、リース・アルファードの優しい笑顔。自由に絵を描き続ける彼の言葉に触れた瞬間、氷のようになっていたカリナの心は溶けかけていた。それでも、逃れられない現実に再び押し潰されるような感覚が、今まさに襲いかかる。けれど、その記憶を無理に追い払ってしまうのも、何かを失うようで怖かった。
(あの人は今頃、どこでどんな絵を描いているんだろう……)
そう思うだけで、一瞬だけ心が軽くなる。しかし、馬車が重々しく石畳を通り抜け、ステラリア家の屋敷が見えてくると、現実がまるで分厚い壁となって行く手を遮るのだった。ドアを開けた先には、父の怒声や、家令の冷たい視線、そして来客を迎えるための慌ただしい準備が待ち受けている。
――無彩の婚礼は、まだ始まったばかり。この先も連なる儀式を経て、カリナはまるで大切なものを消し去るように、「夫婦」という形を受け入れなくてはならない。それでも彼女の心の奥には、絵を描くことへの小さな熱がかすかに燻り続けていた。どれほど規則や常識、そして周囲の期待に縛られようとも、その炎が完全に消えることはきっとない。その夜、カリナはベッドに沈み込む寸前、枕元に置かれたスケッチブックを撫でながら小さく呟くのだった。
「私……まだ、諦めたくない……」
2-2
午後の礼拝堂での前儀式を終え、ステラリア家の馬車が屋敷へ戻ってきた頃には、日はすでに高い位置からやや傾き始めていた。カリナ・ステラリアが玄関ホールへ足を踏み入れると、そこには結婚の披露宴――いわゆる“婚礼パーティ”の準備に追われる使用人たちが何人も行き来している。皆、目まぐるしく動いては大きなテーブルを運んだり、絢爛豪華な装飾品を配したりと大忙しだ。まるでほんの少し前まで“前儀式”を取り仕切っていたのが嘘のように、ここではまったく別の催しが行われるかのようにすら見える。
カリナはその光景を眺めながら、深い息をひとつ吐いた。これから先、ヴェイル家の婚礼を祝うために多くの来賓が訪れる予定となっている。とはいえ、家同士の結びつきを強調するために行われるものに過ぎず、真の意味で“祝福される”空気はどこにも感じられなかった。豪奢な装飾も、山のように届けられた花束も、すべては「こうあるべきだ」という型どおりの演出にしか思えない。しかも、当のエドリック・ヴェイルは馬車から降りた直後、さっさと公爵家の執事に伴われていずこかへ姿を消してしまったらしい。まるで「婚礼パーティ」の主役であるはずの相手が、これ以上ないほど無関心だという事実が、カリナの胸をひどく痛ませる。
「お嬢様、お戻りなさいませ。こちらでドレスを再チェックしていただけますか? 披露宴ではまた別の装いが必要とのことですので……」
侍女長が丁寧に頭を下げながら、鏡張りの部屋へカリナを促す。この部屋は、結婚式に向けた準備が始まって以来、試着や打ち合わせのために使われてきた場所だ。足を踏み入れるや否や、カリナの視界には真っ白なドレスがいくつも掛けられているのが映る。どれもこれも高価なレースや宝石がふんだんにあしらわれていて、見た目の美しさに抜かりはない。けれど、まるで彼女の意志など介在しないまま勝手に選ばれたようなそれらは、カリナにとってはもはや重苦しいだけだ。
「こちらが新たに仕立てました“お色直し”用のドレスでございます。先ほどの礼拝堂用とは違い、スカートの裾に大ぶりのフリルが加わっておりますので、華やかさがいっそう際立ちますわ」
仕立て担当の女性が胸を張って紹介するが、カリナはどこか上の空のまま生返事しかできない。美しさを競うのは嫌いではなかったはずなのに、今の状況ではドレスを着飾るたびに「自分が人形のように扱われる」という思いが増していく。とはいえ、この場で不機嫌そうに拒んだところで何も変わらない――結局、彼女は侍女たちの手を借りて淡々と着替えを進めるだけだった。
鏡越しに映る自分の姿を見ても、そこに“花嫁”としての幸せが感じられないのは周知のこと。横に立つ侍女の一人が「お嬢様、少し顔色が優れないように見えますが、ご気分はいかがですか?」と気遣ってくれるが、カリナは慌ててかすかな笑みを取り繕う。伯爵家の令嬢として“弱音”を吐くなど許されるはずもないし、そもそも婚約者のエドリックですら「形式だけ」の婚礼に興味を示していない。周囲へ不満や悲しみを打ち明けられるはずがなかった。
やがて、準備を終えたカリナが大広間の前までやってくると、すでに伯爵である父が貴族仲間と何やら会話を交わしているのが見える。豪奢な扉から漏れ聞こえてくる音は、華やかな弦楽の演奏。どうやら着々と宴は始まろうとしているようだ。父が彼女に気づくと、すぐさま視線を向けて強い口調で言い放つ。
「カリナ、時間だ。まもなく開宴となるから、余計なことは言わず、愛想よく振る舞うのを忘れるな。ステラリア家の面目に泥を塗るなよ」
まるで脅しにも似たその言い方に、カリナは小さく身をすくめる。けれど、父の言うとおり、この“婚礼パーティ”はステラリア家が王国最強と呼ばれるヴェイル家に認められるための大切な舞台なのだ。すべてを演出し、すべてを整え、少しでもステラリア家の権威が高まるように……それが伯爵の望みであり、同時にカリナの“義務”でもある。
深呼吸をして、大広間の扉を開けると、そこにはきらびやかなシャンデリアがいくつも灯され、眩しいほどの光彩が広がっている。フロアには既に多くの貴族や名士が集まり、それぞれが様々な思惑を抱きながら会話をしている様子だ。招待客たちは一斉にカリナの方を振り向き、「おめでとうございます」「さすがに美しい花嫁ですね」などと称賛の声を投げかける。形式上の“お祝い”の言葉ばかりが耳に入ってくるが、そこにこもる熱はどれほどのものか。カリナは呆然としながら、それでも微笑みを返すしかない。
肝心のエドリックの姿を探そうと人波を見渡しても、やはり彼は見当たらない。代わりに目に飛び込んできたのは、かの妖艶な愛人と噂される女性だ。真紅のドレスを纏った彼女が、まるでこの場を支配する女王のように、堂々とした態度で招待客たちと談笑している。ちらりとカリナを捉えた眼差しは、まるで「あなたなど形だけの花嫁」と言わんばかりの嘲笑を含んでいるようにも感じられた。
「カリナ様、こちらへどうぞ。ご挨拶をしたいという方が列をなしていらっしゃいます」
使用人に促されるがまま、カリナは次々に客人から祝福の言葉を受ける。中には「ヴェイル公爵家との縁組は、ステラリア家にとっても大変素晴らしい機会ですね」などと露骨に家同士の利害関係を取り沙汰する者もいて、それが一層、彼女の虚無感を煽る。酒杯や料理をすすめられても、まるで喉を通らない。薄く微笑みを浮かべては礼を言い、またすぐに次の客へ――と動き回るうちに、カリナは頭がぼんやりとしてくるのを感じる。
「お嬢様、ご気分が悪そうですが……大丈夫ですか?」
近くにいた侍女が心配げに声をかけると、カリナは何とか笑顔を取り繕いながら首を振る。弱音を吐けば、すぐに父から「余計な騒ぎを起こすな」と叱責されるだろうし、そんな姿を見せること自体が恥だと教えられてきたからだ。心がきしむような痛みに耐えながら、ただ形ばかりの“祝福”を浴び続けるしかない。
そのうち、カリナは人混みの奥に見知った顔を見つけて、驚きに瞳を見開いた。リース・アルファード――先日、美術市で出会った青年が、なぜかこの場にいる。あのときは小さな画廊を手伝いながら、自身の絵を売っていると語っていたのに、こんな華やかなパーティへ招かれる立場なのだろうか。リースの傍らには壮年の紳士が控えており、どうやら彼が案内役らしい。二人とも貴族というよりは、美術関係の賓客として呼ばれたのかもしれない――そう直感しながらも、カリナはどこか嬉しさに似た安堵を覚える。
と同時に、彼女ははたと我に返った。自分は“ヴェイル公爵家の花嫁”としてここにいる。もしリースと直接言葉を交わし、芸術談義などに花を咲かせようものなら、周囲の目をひどく気にする父がただで済ませるはずはない。何より、この婚礼パーティで“本当の関心”を見せる相手に会うことはカリナ自身の心を揺るがしてしまう。今は――そう、今は耐え忍ばなければならないのだ。
しかし、リースの方もすぐにカリナに気づいたのか、何やら複雑そうな表情を浮かべて会釈してくる。彼の瞳には、あの日と同じ優しさがあった。それだけで、カリナの胸に再び暖かな光がともる。しかし彼女は視線を反らすように、小さく礼を返すだけで歩み去った。彼に近づいてはいけない。それが今の“義務”だと思ったから。
――こうして、華やかな披露宴の最中にも関わらず、カリナの心はどこまでも沈んでいく。客人たちの興味は、果たして“新婦”としての彼女自身に向いているのか、それとも“ステラリア家とヴェイル家”を繋ぐ儀礼の中心としての道具なのか。答えなど分かりきっているというのに、ふとした瞬間に胸が苦しくなる。リースを見た瞬間の揺らぎは、その苦しさにまた別の色彩を与えてしまう。
あまりに耐えがたい息苦しさに、カリナは大広間の端に置かれた椅子へ腰を下ろす。人々は皆、誰かと利害を計りながら、もしくは単なる社交としての歓談に没頭している。微笑と華やかさに満ちあふれた場のはずが、カリナには冷たく空々しい空気がまとわりつくようにしか感じられない。果たして、この“無彩の婚礼”に“色”が灯る日はやってくるのだろうか――その疑問が、じわりと彼女の心を覆い尽くす。
遠く聞こえる音楽と、偽りの祝福。父や周囲の視線を恐れて話しかけることさえ叶わない、唯一の“理解者”かもしれない人物。エドリックの姿は依然として見当たらず、愛人の女が嘲笑するように真紅のドレスを揺らしている。まるで演じられた劇を見ているかのように、カリナは微動だにできない。それでも、心のどこかでは、かすかに灯る火が消えぬように――あの夜に思い描いた“私は道具になりたくない”という決意を、ただ必死に抱きしめていた。
2-3
ステラリア家の大広間で繰り広げられる「婚礼パーティ」は、いっそう熱を帯びていた。招かれた貴族や名士たちが、煌びやかな装いで思い思いに会話を交わし、あちこちでグラスを傾け合っている。入口近くに並べられた豪華な食事やワインは次々に空となり、給仕係は忙しなく補充のために動き回っていた。
一見すれば、まさに祝福の宴――ところが、その場の中心であるはずのカリナ・ステラリアは、まるで自分が舞台の脇役に追いやられたような疎外感に苛まれていた。窮屈なドレスの重みと不慣れなハイヒールで足が痛み、誰と話しても決まりきった祝辞ばかりが返ってくる。ましてやエドリック・ヴェイル本人はどこかへ姿を消したまま。形だけの祝福の渦の中、カリナはただ虚空を見つめながら、胸の奥で燻る感情をどう処理すればいいのか分からないでいた。
「――カリナ様、おめでとうございます。ヴェイル家とステラリア家のご縁、誠に喜ばしいことですわね」
そう言いながら近づいてきたのは、どこかで見たような派手な装飾を纏った中年の婦人だった。顔立ちから察するに、伯爵家に縁のある貴婦人なのだろう。カリナはとっさに作り笑いを浮かべ、「ありがとうございます」と返す。けれど、その声には張りがなかった。相手はそんな気配に気づいたのか、あるいは最初からカリナの心中など気にも留めていないのか――舌先だけの祝辞を告げると、さっさと次の人のもとへと去ってしまう。
華やかな衣服と笑顔に彩られた“祝福の場”は、カリナにとってただの空々しい見世物に等しかった。拍手や笑い声が大広間に充満しているのにもかかわらず、自分だけが微かな寒さに包まれているように思えてならない。
そんなとき、視界の端に目立つ赤いドレスが入る。エドリックの愛人と噂される妖艶な女性が、貴族たちの輪の中心で微笑んでいた。彼女のそばを通り過ぎた人が、カリナに気づいて軽く会釈するが、赤いドレスの女のほうはまるで無関心。あるいは意図的に“彼女を無視する”という意思表示にも見える。
もしかしたら、あの女はすでに“妻の座”を手に入れたかのように振る舞っているのかもしれない――そう思った瞬間、カリナの心はひどく乱される。実際、すでに何度かエドリックとの噂が立っている彼女を、誰も咎める様子を見せない。それどころか、一部の貴族たちが彼女をさりげなく持ち上げ、彼女もまたそれを当然のように受け止めているようだ。
カリナは唇を引き結んで、大広間の壁際へと足を運ぶ。人の波から少しでも逃れたい一心だった。壁に背を預けながら、金と銀の煌めきに満ちた空間を眺めると、その美しさがむしろ眩しすぎて目が痛い。いや、まるで自分がここの景色に溶け込んでいないような感覚に囚われるのだ。
「カリナ様、失礼いたします」
ふいに声をかけてきたのは侍女長だった。心配そうに小さく眉を寄せながら、そっと言葉を続ける。
「やはりお疲れのご様子ですね。もしよろしければ、しばらく控室で休まれてはいかがでしょう。父上様には私がうまくご説明いたしますので……」
その提案は、カリナにとって酷く魅力的だった。少しでも人目を離れ、足を休めたいという思いはある。しかし同時に、「婚礼パーティの最中に姿を消すなんて、父が許すはずがない」という恐れも頭をよぎる。
侍女長もその事情は承知しているのか、言葉を探すように口ごもる。「お嬢様がお辛そうですし、ご体調がすぐれないようですと皆様にも示しが立ちません。ここは私に任せて……」
それを聞いたカリナは、押し寄せる罪悪感と安堵感の狭間で揺れる。だが、いずれにしてもこのまま“大勢の客から形だけの祝福を受ける人形”で居続けるほうが、心を壊してしまいそうだった。意を決した彼女は、侍女長に小さく頷き返す。
「……ごめんなさい。では少しだけ、控室で休むことにします。お手数をかけて申し訳ないわ」
「いえ、どうかお気になさらず。私がうまく場を取り繕いますので、どうぞご安心ください」
こうしてカリナは侍女長に先導され、さほど広くない控室へと入っていった。石造りの壁と最低限の調度品だけが置かれた、質素ではあるが静かな空間だ。ドアを閉めると、外からの喧騒は幾分か遮られ、少しだけ呼吸が楽になる。
「お疲れかもしれませんが、何か温かいお飲み物をご用意しましょうか?」
侍女長がそう申し出ると、カリナは少し考えた末に「じゃあ、ハーブティーをいただけるかしら」と答える。体を温めたいというよりは、せめて落ち着きたかったのだ。まもなく侍女長は深く頭を下げて、ドアの外へと足早に立ち去っていく。
控室にひとり取り残されたカリナは、気だるい体を椅子に沈める。ドレスのコルセット部分がやけに胸元を締め付けて苦しいが、慌ただしい場から逃れられただけでも幾分か救われる思いだった。
(あぁ、ずっとこうしていられたら、どんなに楽かしら……でも、そんなわけにはいかないのよね)
重い息をついて目を閉じると、脳裏に浮かぶのはリース・アルファードの姿だった。美術市で初めて出会ったときのあの穏やかな笑顔、そして先ほどほんの一瞬だけ視線を交わしたときの戸惑いが混ざった表情――彼は今ごろ、あの賑やかな大広間でどんな思いを抱えているのだろう。
まさかこの婚礼パーティにまで来ているとは予想していなかった。どうして呼ばれたのか、誰の紹介なのかも分からない。しかし、絵を志す者として時折貴族のパーティに招かれることは珍しくないとも聞く。大手の画廊関係者が来ているなら、リースが同行していても不思議ではない。
(あの人に……少しだけでも、話をしたい。今の私が、どれほど孤独か、そして本当は絵を描きたいのに描けないでいるか……なんてね)
何とも弱々しい独り言に、思わず涙が滲みそうになる。けれど、それを許せばきっと“弱音”が止まらなくなってしまう。父の期待と家名を背負っている以上、“エドリック・ヴェイルの婚約者”としての仮面を外すわけにはいかないからだ。
と、そのとき、扉の向こうから控えめなノックの音が聞こえた。侍女長がハーブティーを持ってきたのかもしれない。カリナは「どうぞ」と声をかける。ところが、そこに現れたのは、侍女長ではなかった。控室のドアを少しだけ開け、ひっそりと中をうかがう青年――リース・アルファードその人だった。
「……失礼、いたします。大丈夫でしょうか、今……?」
彼もまた緊張しているのか、微かに眉根を寄せながら声を落とす。カリナは驚きのあまり一瞬言葉を失うが、やがて小さく頷き、扉を開けて中へと招き入れる。
「どうして、ここに……?」
「先ほど、大広間であなたを見かけました。でもどこか辛そうで……それに、さっき別の女性から“カリナ・ステラリアお嬢様が具合を崩されたかもしれない”って聞いて……心配になったんです」
リースの瞳に宿る純粋な思いやりが、カリナの心を溶かしていく。けれど同時に、この場で彼と二人きりで会話しているところをもし父や他の貴族に見られたら、どれほどの騒ぎになるだろう――そんな恐れもよぎる。しかし、今のカリナはそれでもいいと感じてしまうほどに限界だった。
「ごめんなさい、こんな姿を見せるつもりはなかったのに……」
そう言いかけた途端、堰を切ったように涙が込み上げる。リースは慌てて近寄り、テーブルの上にあった清潔なハンカチを手渡す。
「落ち着いて……大丈夫、誰にも言わない。あなたが本当に辛いなら、僕で良ければ話を聞きます。無理はしないで」
その言葉に救われるように、カリナは声を押し殺しながらも涙をこぼす。絢爛豪華なパーティの最中、伯爵令嬢がこっそりと隠れて泣いているなど、本来あってはならないことかもしれない。だけど、こうして誰かに心を預けられる時間があるだけで、どれだけ救われるだろう。
やがて、嗚咽を噛み殺すように息を整えたカリナは、リースに向けてほんの少しだけ笑みを返す。
「ありがとう……あなたがここに来てくれて、本当に嬉しいわ。いつか……いつか、私も――また絵を描きたい。今は難しいけれど、でもそれを夢見ている自分がいるって……思い出させてくれたの」
リースはまっすぐな眼差しでカリナを見つめ、静かに頷く。
「僕はあなたの絵を、いつか必ず見たいと思ってる。誰の目も気にせず、自由に描ける日がきっと来ます。……だから、どうか諦めないで」
その優しい声に、カリナの心は確かな力を取り戻し始める。儚い火種だった“絵を描きたい”という願いが、ほんの少しだけ明るく揺れ動いた気がした。
――だが、その瞬間、外から聞こえる慌ただしい足音が静寂を破る。どうやら誰かがカリナの所在を探してここへ向かっているらしい。リースが顔色を変えたのと同時に、カリナもまた手早く涙を拭い、立ち上がる。二人でこっそり出入りしているところを見られれば、あまりにも不自然だ。
「行って……! すぐに……! 誰かが来るわ」
「……分かりました。大丈夫ですか?」
「ええ、あなたは先に出て。私は侍女長を待つから……」
短い会話を交わすやいなや、リースは控室の裏手にある小さなドアから素早く姿を消した。入れ替わるようにして部屋の正面ドアが勢いよく開く。現れたのは、侍女長ともう一人、ステラリア家の家令だった。家令は険しい表情で「お嬢様、どちらにいらっしゃいました?」と厳しい口調で問いただしてくる。
「少し休むようにと侍女長が勧めてくれたの。……ごめんなさい、すぐに戻りますから」
カリナは頭を下げながらも、先ほどまでの涙の痕跡が残らないように必死で目をそらす。家令は納得したのかしていないのか、「分かりました。お父上様が大広間でお待ちです」とだけ短く告げる。侍女長は心配そうにカリナの様子を窺うが、彼女が「もう大丈夫です」と微笑むと、それ以上は何も言わなかった。
こうして、カリナは控室を後にする。父と客人たちのいる大広間へ戻らなくてはならないが、その足取りは先ほどよりもいくぶん軽い気がした。重苦しいドレスの締めつけと、絶え間ない虚無感に耐え続ける自分――それでも、リースの励ましは確かに心の闇を照らしてくれた。
(私は道具じゃない。いつかきっと、自由に絵を描ける日が来る……)
胸の奥に宿る小さな炎を、今だけは守り抜こう。父の怒りも、愛人を侍らせる婚約者の冷たさも、何ひとつ変わらない現実かもしれない。だけど、せめて己の夢を捨てることだけはしたくない――そう心に誓いながら、カリナはもう一度、大広間の扉を押し開く。演奏と歓声が耳を打ち、作りものの祝福が彼女を取り囲む。
しかし、その偽りの華やかさにも、ほんのわずかな抵抗を示せるだけの力を、カリナは手に入れつつあった。いつかこの“無彩の婚礼”が燃え上がるときが来るならば――その時には、今とは違う色彩が溢れ出してほしい。リースの言葉がくれた温かな光を頼りに、カリナは再び人々の視線に身を晒しに行く。それが、彼女にできる精一杯の“逆らい方”だった。
2-4
「婚礼パーティ」がひとまずの最高潮を迎え、客人たちも酒や音楽に酔いしれている頃――カリナ・ステラリアは大広間の中央付近に立ちながら、どこか遠くを眺めていた。先ほど控室でリース・アルファードと交わした短い言葉の余韻はまだ残っている。ほんのわずかな時間だったとはいえ、あの穏やかな声と、何より「あなたの絵を見たい」という励ましが、カリナの心を支えていたのだ。とはいえ、この圧倒的な虚飾と形式ばかりを押しつける宴からは、もう逃げ出したい思いが募っていく。それでも、父ハロルド伯爵の視線がある限り、カリナはこの場を離れることが許されない。
実際、父は大広間の一角で貴族仲間と盛んに会話を交わしている。その話題の中心は、もっぱら「ヴェイル公爵家との縁組がもたらす利得」であるようだ。財政の話、新たな商会との取引、王都からの政治的信用――どれもこれも伯爵にとって喉から手が出るほど欲しい“恩恵”なのだろう。ちらりとこちらを窺うように目をやった彼は、常に「ステラリア家の顔」を意識しているのか、カリナが怪しまれないよう監視しているようにも見える。
(父様にとって、私はどう映っているんだろう……)
そんな疑問が胸をかすめるが、答えは既にわかっている気がする。自分はただの「交渉の駒」であり、「家を支える手段」に過ぎない。いくらドレスで飾り立てられ、今宵の主役であると周囲に称えられたところで、真実は何も変わらない。
視線を左右に巡らせると、ひときわ華やかな赤いドレスが目に入る。エドリック・ヴェイルの愛人と噂される女性だ。彼女はどこかの公爵夫人や伯爵夫人らと気さくに談笑しながら、ワイングラスを優雅に傾けている。笑みを絶やさぬ横顔には絶対の自信が宿っており、周囲の目をまるで気にも留めない。“正妻”となるはずのカリナをよそに、まるでこのパーティの真の女主人かのように振る舞っているのだから、見ているだけで息苦しさを感じる。
さらに、彼女の笑顔の奥には薄ら寒い影もちらついていた。カリナと視線が合うや否や、ほんのわずかに口元を歪めてみせた気がする。それは「あなたが“形だけの花嫁”であることなど、とっくにお見通しよ」と言わんばかりの嘲笑にも見えた。もしかすると、エドリック自身が彼女をこのパーティへ招いたのだろうか。そう思うと、不思議と怒りよりも虚しさが込み上げる。
(なぜ私は、こんなにも報われない立場にいるのかしら――)
そう胸中で呟いた瞬間、人込みをかき分けて再びリースの姿が見えた。彼が豪華な調度品や格式ばった貴族たちを前に、少し居心地の悪そうに立ち尽くしているのがわかる。先ほど控室に来てくれたときの面影とは打って変わって、今は人前で自分の立場を誤魔化すように隠そうとしているようにも見えた。画廊の主や支援者とともに招待されたらしいが、周囲の雰囲気に溶け込むのは容易ではないだろう。それでも彼は、その場にふさわしい作法を守りつつ、時折カリナの様子を探るように目線を送ってきた。
もちろん、カリナも心の中ではリースに近づきたいと思う。だが、今は伯爵家の娘として振る舞わなければならない以上、軽々しく談笑するわけにもいかない。父の命令は絶対だし、何より彼女自身が「これ以上騒ぎを起こしてはいけない」と強く感じているからだ。
客人たちが絶え間なくカリナを囲み、「おめでとうございます」「あなたほどの美女が、国随一の公爵家の妻になるなんて運命的ですわ」などと口々に述べる。もはやそのどれもが借り物の言葉であるかのようにしか聞こえない。実際、エドリックと共に並び立ったのは礼拝堂の“前儀式”と婚礼パーティ開始の直後だけで、それ以降は一度も顔を合わせていないのだから。
(いったいエドリックは、どこに行ったの?)
そんな疑問が生まれたと同時に、視界の片隅で、問題の人物を捉えた。彼は大広間の奥まった場所で数人の貴族と談笑している。やはり、こちらに向ける視線は皆無に等しく、まるで最初から“自分の婚礼パーティ”など興味がない、と言わんばかりだ。カリナをちらりと見ることさえなく、冷然とした横顔を客人たちに向けている。
そのとき、彼の隣にすっと寄り添うように赤いドレスの女性が姿を見せた。愛人――そう呼ばれて久しいその女性は、エドリックの腕にさりげなく触れ、にこやかに笑みを交わす。並んで立つ二人の姿は、まるで“婚礼”にふさわしい新郎新婦のようにさえ見えた。それは、傍目にも「公然の仲」であると悟らせるに十分な光景だ。
カリナはぞっとするほどの疎外感に襲われ、ドレスの裾をぎゅっと握りしめる。しかし、どれほど胸がかき乱されても、ここで騒ぐわけにはいかない。周囲の客が見ている以上、“ステラリア伯爵家の令嬢”である自分が取り乱すなど、あってはならないことだ。まるで深い沼に足を取られているような感覚の中で、彼女は吐き出せない感情をぐっと堪える。
「――カリナ、こっちへ来い。お前を紹介したい方がいらっしゃる」
唐突に父が呼びかけてきた。傍には、肥満体の紳士とそれに付き従うらしき従者が立っている。聞けば、この紳士は王都に近い街で多くの画商を束ねる大富豪だという。伯爵家にとっては新たな“スポンサー”になり得る存在らしく、父は上機嫌な様子で「婚姻を通してさらにステラリア家は発展を目指す所存です」と力説している。もちろん、そこにカリナの意見や意思が入る隙などない。
挨拶が済むと、富豪は何やら腑に落ちないような表情でカリナを一瞥する。その視線には純粋な祝福など微塵もなく、「なるほど、話には聞いていましたが……まあ、私に利益がもたらされるなら協力しましょう」とでも言いたげな雰囲気だ。父はそれを歓喜の色を滲ませて受け止め、「では後日、改めて詳しい話を――」と熱心に食い下がっている。
(すべてがお金や権力、利害関係で動いているんだわ――)
そう思うと、自分がさらに惨めに思えてくる。伯爵家は落ちぶれかけているとはいえ、昔はもう少し誇り高さを保っていたはずだ。いつからこんなにも露骨に“何かを得るための取引”に奔走するようになったのか。もしかすると、あまりにも長く続いた財政難が父を焦らせ、このような手段に走らせたのかもしれない。しかし、その皺寄せを一身に背負っているのは、娘であるカリナなのだ。
立ち話を終え、富豪とその従者が去っていくと、父はちらりとカリナに視線をやる。
「いいか、ここでの態度一つが我が家の将来を左右しかねん。余計な口をきくな、分かったな」
カリナは形だけ頷きながら、心の中で反発の炎が燃え上がりそうになるのをどうにか抑え込む。そんな自分に嫌気がさしつつも、これが今の“現実”なのだと思い知らされる。
再び人波の中に戻ると、客人の誰かが音楽隊にリクエストをしたのか、優雅な舞曲が広間に響き始める。貴族たちが楽しげに踊りの輪を作り、華麗なステップを踏んでいる。通常ならば、こうした婚礼の場では新郎新婦が先頭に立って踊るのが常だが、エドリックは目もくれないどころか、赤いドレスの女と一緒に笑い合っている。カリナはそんな情景を横目に見ながら、まるで息をする場所さえ与えられていないような窮屈さに支配されていた。
そのとき、不意に誰かがそっと腕を引いた。驚いて振り返ると、そこにはリースの姿があった。彼は何か声をかけようと口を開きかけるが、すぐに思い直すかのように小さく首を振る。そして視線だけで「このままではあまりに辛いのではないか」と問いかけてくる。
けれど、今は言葉を交わすわけにはいかない――そう察したカリナは、申し訳なさそうに目を伏せる。周囲の客人は踊りや歓談に夢中で彼らを注視してはいないが、さすがにあまり長く会話を続ければ目立ってしまう。リースもまた、ここで騒ぎになることは望んでいないだろう。結局、彼は軽く頭を下げるだけで、すぐに人混みの奥へ消えていった。
(本当なら、こんな派手な場所じゃなくて、穏やかに絵のことを話したいのに……)
音楽がより熱を帯び、歓声と拍手が重なり合う中、カリナはふと感じた。――この場には「祝福」の色がない。派手な装飾や美酒、楽しげな笑い声さえ、すべては利害や形ばかりの体裁で彩られているだけ。婚礼とは名ばかりの“無彩の宴”だと痛感し、心がひどく冷たくなる。
そんな中、父がまた別の客人を捕まえては談笑を始める様子を、カリナは呆然と眺める。彼女に与えられた役割は「そこにいるだけ」であり、それ以上でも以下でもない。遠目に見えるエドリックと愛人の親しげな姿が、今の彼女の悲惨さをさらに浮き彫りにしていた。だが、絶望の縁に立ちながらも、カリナの中には確かに小さな炎がくすぶっている。――先ほどリースがくれた優しい眼差しを思い出すだけで、まだ自分は完全に壊れていないと思えるのだ。
(いつか、この婚礼が終わったら……絶対にもう一度、絵を描く。私は道具なんかじゃない……)
大広間の扉が開き、新しく到着した客人の姿がちらほら見える。まだ宴は続くのだろう。どこまでも夜が深まり、やがて朝を迎えれば、この白々しい祝福の宴も幕を閉じるかもしれない。だが、カリナの戦いはそこからが本番だ。ヴェイル家に嫁ぐ先で待ち受ける未来は、さらに厳しいものになるだろう。エドリックの冷たさと公然の愛人、ステラリア家の重圧――どれ一つとして救いの光は見えない。
だからこそ、彼女はまだ諦められないのだ。リースと交わした約束――「いつかあなたの絵を見たい」「自由に描ける日がきっと来る」という言葉を胸に、カリナは必死に自分を奮い立たせる。それこそが、今の彼女にとって唯一の“色彩”だった。どんなに華麗な会場であろうと、愛人に囲まれた冷酷な婚約者がいようと、自分の意志だけは塗り潰されてはいけない。
――こうして、虚飾にまみれた“無彩の婚礼”の宴は続いていく。にぎわう人々と、まったく相容れない疎外感。愛のない婚約者と、“花嫁”として祭り上げられながら何も得られない自分。けれど、胸の奥で小さな炎がたしかに燃えていることを、カリナは感じていた。いつか、あの冷たい指輪を外す時が来るならば、その瞬間こそ、この白い――しかし限りなく灰色に近い結婚の世界を突き破れるはずだ。
それを信じながら、カリナはまた一人の客に微笑みかける。馴れない笑顔でも、この場を乗り切るしかない。どれほど偽りの祝福を浴びても、自分の本心までは支配されてたまるものか。心に宿った小さな抵抗を糧に、彼女は歪んだ夜の中を歩き続ける。たとえここが“無彩”の舞台であっても、いつか自分の手で、鮮やかな色を取り戻すために――。
0
あなたにおすすめの小説

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。
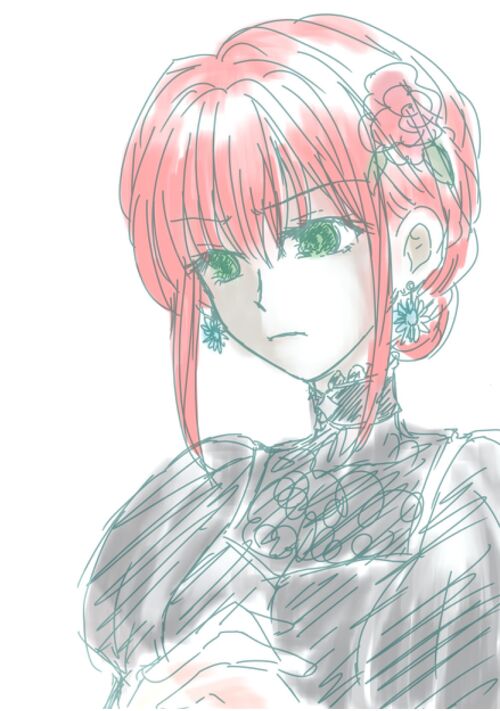
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

地味な私を捨てた元婚約者にざまぁ返し!私の才能に惚れたハイスペ社長にスカウトされ溺愛されてます
久遠翠
恋愛
「君は、可愛げがない。いつも数字しか見ていないじゃないか」
大手商社に勤める地味なOL・相沢美月は、エリートの婚約者・高遠彰から突然婚約破棄を告げられる。
彼の心変わりと社内での孤立に傷つき、退職を選んだ美月。
しかし、彼らは知らなかった。彼女には、IT業界で“K”という名で知られる伝説的なデータアナリストという、もう一つの顔があったことを。
失意の中、足を運んだ交流会で美月が出会ったのは、急成長中のIT企業「ホライゾン・テクノロジーズ」の若き社長・一条蓮。
彼女が何気なく口にした市場分析の鋭さに衝撃を受けた蓮は、すぐさま彼女を破格の条件でスカウトする。
「君のその目で、俺と未来を見てほしい」──。
蓮の情熱に心を動かされ、新たな一歩を踏み出した美月は、その才能を遺憾なく発揮していく。
地味なOLから、誰もが注目するキャリアウーマンへ。
そして、仕事のパートナーである蓮の、真っ直ぐで誠実な愛情に、凍てついていた心は次第に溶かされていく。
これは、才能というガラスの靴を見出された、一人の女性のシンデレラストーリー。
数字の奥に隠された真実を見抜く彼女が、本当の愛と幸せを掴むまでの、最高にドラマチックな逆転ラブストーリー。

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

完結 愚王の側妃として嫁ぐはずの姉が逃げました
らむ
恋愛
とある国に食欲に色欲に娯楽に遊び呆け果てには金にもがめついと噂の、見た目も醜い王がいる。
そんな愚王の側妃として嫁ぐのは姉のはずだったのに、失踪したために代わりに嫁ぐことになった妹の私。
しかしいざ対面してみると、なんだか噂とは違うような…
完結決定済み

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

婚約破棄された夜、最強魔導師に「番」だと告げられました
有賀冬馬
恋愛
学院の祝宴で告げられた、無慈悲な婚約破棄。
魔力が弱い私には、価値がないという現実。
泣きながら逃げた先で、私は古代の遺跡に迷い込む。
そこで目覚めた彼は、私を見て言った。
「やっと見つけた。私の番よ」
彼の前でだけ、私の魔力は輝く。
奪われた尊厳、歪められた運命。
すべてを取り戻した先にあるのは……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















