3 / 4
3章
3
しおりを挟む
3-1
ステラリア家の屋敷で催された「婚礼パーティ」から数日が経過した。冷ややかで嘘に塗り固められた祝福の夜の余波は、今なおカリナ・ステラリアの胸を締めつけている。けれど、そんな彼女を取り巻く状況は、一見して以前とさほど変わらないように見えた。父ハロルド伯爵は、ヴェイル公爵家との縁組が決定事項となったことに気を良くし、相変わらず「我が家の復興は目の前だ」と豪語しているし、エドリック・ヴェイルはほとんど屋敷に顔を出さない。結婚式当日こそ多くの人々の前で“形ばかりの誓い”を立てたものの、それ以降、夫婦として何らかの交流を深めようとする気配は微塵も感じられなかった。
もっとも、それはカリナにとっても都合が悪いことではなかった。エドリックの存在を意識する機会が少ない分だけ、あの“愛人”の妖艶な影に胸をかき乱されることも減る。それでも事態はまったく好転せず、遠くないうちに“正式な結婚生活”が始まれば、彼女はヴェイル家へと移り住み、あの冷たい婚約者と過ごさねばならなくなる。かりそめの宴が終わりを告げても、カリナの未来は相変わらず暗雲に覆われていた。
しかし、そんな閉ざされた日々のなかにも、かすかな変化の種は芽吹き始める。婚礼パーティの夜にわずかとはいえ言葉を交わし、翌日には屋敷へ見舞いの手紙を送ってきた人物――そう、カリナが唯一心を許しかけている青年、リース・アルファードからだった。彼は「パーティの席でご体調を崩されたと聞き、ひどく心配しております。もし差し支えなければ、改めてお見舞いに伺いたい」と綴ってくれていたのだ。画廊を手伝う身分でありながら、このステラリア家に“客人”として連絡をよこすなど、常識的にはあり得ない行為かもしれない。しかし、カリナは手紙を読みながら自分でも驚くほど胸が弾んでいることを感じた。
「……きっと、私のことを真剣に気遣ってくれているんだわ」
そう呟いたとき、自分の内側で小さな炎がふっと灯るのをカリナははっきりと意識した。政略結婚の道具としか扱われず、エドリックからは無視同然の態度を受け、父からは“家を盛り立てるための存在”としか見られない。このまま何も変わらないなら、自分は本当に壊れてしまう――そんな恐怖の中にあって、リースの言葉はまさに救いだった。もちろん、彼との交流が公になれば、父や周囲から厳しい目を向けられるかもしれない。だが、それでもなお、カリナは彼と話すことで辛うじて“自分”を取り戻せる気がする。
とはいえ、これまでのように無防備に会いに行くわけにはいかなかった。父は婚礼パーティ以来、自分が取りこぼすはずだった大きな得点を堂々と手に入れた気分なのだろう。カリナの外出を以前より厳しく制限し、来客の相手をさせるときも家令や侍女長を必ず同席させるようにしている。貴族の慣習とはいえ、これではリースとゆっくり話をすることなど到底かないそうにない。それでも、“少しずつ変えていく”ための方法がきっとあるのではないか――そんな漠然とした期待が、カリナの中で静かに膨らみ始めていた。
やがて、思いがけない形でその“期待”が具現化する。ある日、カリナが屋敷の図書室を訪れた際、書棚と書棚のあいだで熱心に本を探しているリースの姿を見つけたのだ。一瞬何かの見間違いかと思ったが、まぎれもなく本人である。驚きに目を見開くカリナに気づいたリースは、気まずそうに微笑みながら片手を挙げる。
「お久しぶりです、カリナお嬢様。実は伯爵さま――お父上のご依頼で、今度開く展覧会の参考資料を探すよう頼まれまして……」
何でも父は、画商や美術関係者とのコネクションを一層強めるべく、近々屋敷の一室をギャラリーとして開放しようと考えているらしい。そこに展示する絵画のセレクトや、展覧会の段取りを手伝うため、リースが招かれたのだという。その“公的”な用事があるため、家令や侍女長も彼が図書室で資料を探すことを許可し、特に警戒の目も光らせていないようだ。言い換えれば、これはカリナがリースと遠慮なく接することのできる数少ない機会ということになる。
「まさか、あなたが父様の依頼を受けるなんて……」
カリナは胸の奥で期待と戸惑いが入り混じる感情を抱えつつ、声を落として続ける。「でも、その……ありがとうございます。私のこと、気づかってくださっていたんですよね……?」 遠回しな言い回しだったが、リースは柔らかな笑みを浮かべてはっきりと頷いた。
「ええ、あの晩、控室でお会いしたときからずっと心配でした。お見舞いの手紙をお送りしたものの、返事をいただくのも難しいかもしれないと思っていたので……こうしてまたお話しできるなんて、嬉しいです」
その言葉だけで、カリナの心に微かな光が差す。周囲を気にしながらも彼と目線を合わせると、いつもの冷たい屋敷の空気が少しだけやわらかく感じられた。
図書室には家令の姿もなく、侍女たちは離れた場所で蔵書の整理をしている。さらに父は客間で貴族仲間との会談中で、ここへ来る気配はない。ほんのわずかな間なら――そう思ったカリナは、少しだけ声量を下げてリースに問いかける。
「……今、少しお話ししてもいいかしら。じっくり話をする機会がずっとなかったから、私……あなたに伝えたいことがあって」
リースは周囲に誰もいないことを確認し、落ち着いた声で答えた。「もちろんです。僕もいろいろお伝えしたいことがあります。よろしければ、一緒にこの辺りの本を探すふりをしながら……」 穏やかな提案に、カリナはほっと微笑む。こうして二人は、書棚に隠れるようにして小声の会話を始めた。
「婚礼パーティのあと、いろいろと思い悩んでいたの。ヴェイル家に嫁ぐことが決まって……エドリック様は私に興味を持っていないし、私も……あの人には何も……」
言いかけて、カリナは目を伏せる。結婚相手に愛情のかけらも感じず、それどころか公然の愛人までいるという現実。だが、リースが落ち着いた声で言葉を返してくれた。
「正直、その噂は僕も聞いていました。けれど、あなたがそこに苦しんでいるのなら、少しでも力になりたい。……失礼を承知で言うけれど、あなたは決して道具なんかじゃない。描く才能も、感じる心も、きっとあなたのものなんだ」
そのまっすぐな励ましが、カリナの胸に深く沁みる。今まで誰も言ってくれなかった言葉。父からは“家を立てる存在”としか期待されず、エドリックからは“何も求められない”。そんな孤独の中で、リースだけが“カリナ自身”の力を信じてくれているのだと実感した。
ふと、カリナは思い出したように声を落とす。「……あなたはギャラリーの準備を手伝うために来てくれたのよね。もしかして、私の絵も出品できるのかしら?」 聞いてしまってから、これは危険な提案かもしれないと思う。伯爵家の面目を保つ展覧会に、未熟な自分の作品を並べるなど前代未聞の行為だ。だが、リースは目を輝かせて頷いた。
「もちろんです。僕もそれができたらいいなって、実は考えていました。ただ、あなたのお父上や使用人たちが何と言うか……そこが問題ですね。ですが、もし何らかの形で説得できれば、あるいは“ステラリア家の令嬢の趣味”という名目でもいいから、あなたの作品を飾れるかもしれない」
その言葉にカリナの心は一気に躍る。同時に、かつての自分が抱いていた“夢”の感覚が蘇ってくる気がした。まだ現実味は薄いけれど、自分が筆を取り、何かを描き、それを誰かに見てもらう――そんな日が訪れる可能性がゼロではないのだ。
「……ありがとう、本当に。私、こんなふうに思えるの、久しぶり」
そう微笑んだ瞬間、遠くから侍女たちの話し声が近づいてくる気配がした。名残惜しいが、これ以上目立ってはいけない。二人はさっと離れて、別々の棚を探るフリに移る。そして、すれ違いざまにリースがカリナにだけ聞こえる小さな声で告げた。
「また改めて、詳しく相談しましょう。きっと今のままではいられないはずですから」
“今のままではいられない”――その一言が、カリナの胸を大きく揺さぶった。閉塞的だった日々が、少しずつ変化していく兆し。それは同時に、自ら動かなければ何も始まらないという警告でもあったが、カリナはなぜかそれを怖いと思わなかった。むしろ、静かに燃える決意のようなものが心のどこかに芽生えるのをはっきりと感じたのだ。
(父様やエドリック様に一方的に振り回されるだけじゃ、何も変わらない。私の力で、私が何かをしなくちゃ――)
図書室を出たあとも、カリナはしばらく胸の高鳴りが収まらなかった。“反撃の兆し”とも呼べる小さな炎が、自分の中で力強く燃え始めている。これまでただ耐え忍ぶだけだった少女が、まるで嵐に向かう船の帆を張るかのように、覚悟を固めつつあった。愛のない婚礼、形だけの夫婦生活、家の重圧――すべてを受け入れるよう強要されても、自分だけの夢を見失うわけにはいかない。リースがくれた勇気と、この心に宿る小さな炎を頼りに、カリナは未来へ踏み出そうとしていた。
――これはまだ始まりの段階に過ぎない。どんな困難が待ち受けていても、“今のままではいられない”という意志さえ失わなければ、きっと道は切り拓ける。カリナはそう信じながら、人気のない廊下を一人歩く。外から差し込む夕日の色が、彼女の金の髪を静かに照らしていた。自分が変わり始めたことを証明するかのように、周囲の空気がわずかに揺れて見える。その揺らぎこそが、長かった沈黙の日々に差し込んだ“反撃”の予兆なのだ――と、カリナはかすかな笑みを浮かべるのだった。
3-2
カリナ・ステラリアが図書室でリース・アルファードと密かに言葉を交わしてから、まだ数日しか経っていない。それでも彼女の心境には、小さくとも確かな変化が芽生えつつあった。かつてはただ“嫁ぐこと”を既定路線として受け入れ、父ハロルド伯爵やエドリック・ヴェイルの意向に従うだけだった。しかし今や、彼女の中には「何かを行動に移さなければ、いずれ本当に自分を失ってしまう」という、切実な思いが生まれている。
かといって、急にすべてを覆せるわけでもない。リースが言うように、ステラリア家の人間関係や、ヴェイル公爵家との結びつきには、強固な利害が張り巡らされている。迂闊に波風を立てれば、父の怒りを買うばかりか、屋敷の使用人たちやリース自身にまで不利益が及ぶかもしれない。だからこそカリナは、まず“小さな行動”から始めようと決めた。自分にできる範囲で、絵を描く準備を少しずつ進めてみること。リースが関与するギャラリーの企画に、少しでも自分の作品を滑り込ませる可能性を探ること。それが今の彼女にとって、最初の一歩だった。
その日、カリナは珍しく早起きをした。夜明け前の薄暗い空気を感じながら、自室の机に向かう。前日は父が貴族仲間との会合を夜更けまで続けていたおかげで、まだ屋敷内が起き出す気配はない。まどろむような静けさの中、カリナは筆と紙を取り出した。最後にまともに絵を描いたのは、婚約話が本格化する前――ずいぶん遠い記憶になりかけていた。慣れ親しんだ筆の触感が愛おしいと同時に、ぎこちなさも感じる。しかし、一度色を置き始めれば、かつて身体に染み付いていた感覚がゆっくりと蘇ってきた。
「……花……描いてみようかしら」
カリナは目を閉じ、昨晩庭に咲いていた白い花々を思い浮かべる。形を捉えるというよりは、頭の中にある淡いイメージをそのまま紙に移していくように筆を走らせる。花びらの質感や、夜露に濡れるときの儚げな光を思い出す――かつては何の苦もなくできていたはずの作業なのに、今は少し指先が震える。それでも、時間を忘れて筆を動かしているうちに、やがて紙の上にぼんやりとした白と微かな青の入り混じった世界が浮かび上がってきた。
「……まだまだ、うまく描けてはいないけれど……」
筆を置いたとき、カリナの胸には不思議な高揚感が残っていた。完璧からはほど遠いスケッチ――それでも、自分で色を生み出す感覚を久々に味わい、「まだ私は絵を描きたい」と心から感じられたのだ。父に見つかれば「そんな無駄なことをしている暇があるのか」と叱責されるかもしれないし、エドリックには馬鹿馬鹿しいと一蹴されるかもしれない。けれど、たとえ一瞬でも自由に表現する時間が持てたことは、今のカリナにとって何物にも代えがたい“小さな希望”だった。
やがて朝を告げる鐘が鳴り、屋敷が徐々に動き始める。カリナはすぐに筆と紙を片付け、ほかの者に見られないよう本棚の奥へそっとしまい込んだ。今日もまた、伯爵令嬢としての儀礼や客人対応が待ち受けているだろう。それでも、一度でもこうして絵を描けた――その事実が、彼女の足取りをわずかに軽くする。
朝食の場では、父が珍しく上機嫌だった。どうやら最近、何人かの貴族や豪商から「婚礼にまつわる新たな投資話」が持ち込まれているらしく、ステラリア家の懐具合も少しずつ潤い始めているのだという。
「やはりヴェイル公爵家との縁組は大正解だったな。カリナ、お前の貢献は大きいぞ」
父は顔を上げずにパンをかじりながらそう言い放つ。そこに“娘を気遣う親”としての優しさなどかけらもないのが、もはやカリナには分かりきっていた。
「ありがとうございます、父様……」
とだけ返事をすると、父はさらに得意気に話を続ける。
「近々、屋敷の改装を少し進めるつもりだ。画商や有力者を呼んで、ギャラリーを設けるとなれば、それ相応の体裁が必要だろう。親切にもヴェイル公爵家の執事がアドバイザーを紹介してくれたからな。アルファードという青年も手伝ってくれるらしいが……そうだ、お前も何か用があるなら彼に頼めばいい。絵がどうのこうのと聞いたが、せいぜい屋敷の飾り付けに協力する程度にしておけ」
“アルファード”――まさにリースのことである。つい先日、図書室で密かに話をしたばかりなのに、父の口からも彼の名が出るとは思わなかった。思わず胸が高鳴り、同時に「自分の動きが父に知られすぎてはまずい」という警戒も走る。それでも、半ば公然とリースと関わりを持てるのは大きな前進かもしれない。カリナは微妙な感情を噛みしめながら、はい、とだけ答えた。
朝食後、カリナが侍女たちとともに廊下を移動していると、奥から侍女長が足早にやってきて声をかける。
「お嬢様、本日は屋敷の改装計画に関する打ち合わせがあるとのことで、伯爵さまが大広間まで来るようにと仰っております。リース・アルファード様もお見えになるようですので、合わせてご相談されたらいかがでしょう」
まさしく渡りに船、と言わんばかりの展開だ。しかし、下手に喜びを表に出せば、周囲の人々に余計な勘繰りをされる可能性がある。カリナはできるだけ平静を装いながら、「わかりました」とだけ返事をした。
大広間へ向かうと、父と家令、そしてリースがすでに何冊かの資料を広げながら話をしているところだった。リースも、仕事用なのか落ち着いた色合いの上着とパンツを身に付け、きちんと髪をまとめている。相変わらず温和そうな笑みを浮かべながら、父の指示を熱心に聞いていたが、カリナの姿に気づくとほのかに目尻を緩める。そのわずかな仕草を見逃さないまいと、カリナもまたさりげなく彼に微笑み返した。
「それで、私を呼び出したのは何でしょうか、父様」
伯爵はやはり上機嫌な様子で、地図のような書面を指し示す。そこには屋敷の見取り図が描かれており、一部の部屋や廊下に丸印が記されていた。
「ここを改装して、ここに新しい調度品を置く。そして、この奥をギャラリーとして活用する予定だ。アルファード氏にも意見をもらいながら、展示する絵画のセレクトを進める。お前も礼儀作法の一環として、訪れる客人の案内をできるようにしておくんだ。……それから、だ」
伯爵はちらっとリースに視線を投げ、続ける。
「お前が昔からちょろちょろと落書き程度に絵を描いていたのは知っているが、もしどうしても飾りたい作品があるなら、アルファード氏と相談してみるといい。ただし、ステラリア家の恥をさらすようなものは勘弁だぞ。名家にふさわしい体裁が整うなら構わんが、出来損ないの趣味を押し出されちゃ困るからな」
その言葉はカリナにとって一種の衝撃だった。伯爵が“絵を飾る”という可能性を許容しているのは、極めて珍しい。もっとも、そこには彼の打算――「令嬢が描いた絵を展示するなんて洒落た演出だ」と客人に思わせる目的――があるのかもしれない。だが、伯爵の真意がどうであれ、これを利用しない手はないとカリナは瞬時に悟る。彼女は表情を崩さないよう注意しながら、静かに頷いた。
「ありがとうございます。……ただ、私の絵は拙いですし、父様の望む“名家の体裁”に合わないかもしれません。なので、アルファード様のご意見をお借りして、一度仕上がりを見ていただきたいのです」
そう口にすると、父は「ふん」とわざとらしく鼻を鳴らす。しかし特に反対はしなかった。家令も黙っている。そこへリースが控えめに一礼しながら口を開く。
「では、私の方でお嬢様の絵を拝見し、展示にふさわしいかどうか、また飾り方なども含めてご提案させていただければと思います。それが屋敷の品位を高めるものであれば、きっと良い効果が得られるでしょう」
こうして自然な流れのまま、カリナは伯爵公認でリースと“作品の相談”をする機会を手に入れた。まるで信じられないほど上手くことが運んでいるが、その裏には父の“名家のアピール”という打算があり、彼女が本当に表現したいものを自由に描けるかどうかは、まだわからない。それでも、ほんの少しでも“道具”以外の自分を示せる可能性が残されたのは大きい。
その日の夕方、カリナは廊下で偶然を装ってリースに近づいた。周囲を伺いながら、極力自然な口調で彼に声をかける。
「先ほどはありがとうございました。父様の前で言ってくれたこと、心強かったわ……」
リースもまた、周囲に警戒しながら小声で応じる。
「お役に立てたなら何よりです。こちらこそ、あなたの作品をぜひ見たい。実は僕も、いいアイデアがありそうなんです。展示するとなれば、ただ『名家の飾り』としてではなく、あなたの本当の魅力が伝わるような形を目指したいと思っていて……」
その先の言葉は、誰かが廊下を横切ったため遮られてしまうが、カリナの胸には高揚感が広がっていく。屋敷のあちこちに敷かれた規律や、エドリックとの結婚がもたらす束縛は、依然として重苦しい現実としてのしかかっている。愛のない婚礼、形ばかりの夫婦生活――まるで冷たい牢獄のような未来が待ち受けていると想像するだけで息が詰まる。
けれど、その暗闇の中に微かな光を探し出せるかもしれない。“絵を描く”という自分の意思を証明することで、ほんの少しでも道が拓けるなら――その希望だけが、カリナを新しい行動へと駆り立てるのだ。
(今の私には、やるべきことがある。とにかく描かなくちゃ……)
心の奥で固く誓いながら、カリナは屋敷の奥まった階段を上がっていく。もうすぐ夜が訪れる頃合いだが、彼女は疲れを感じるどころか、不思議と高揚したままだ。父の思惑やヴェイル公爵家の権威を逆手に取りながら、リースとともに少しずつ未来を変えていく――“燃え上がる逆転劇”の火種は、間違いなく彼女の胸で燻り始めているのだから。
――こうして、ステラリア家という大きな檻の中で、カリナは“本来の自分”を取り戻すための小さな行動を起こし始めた。次に訪れるのは、きっとさらなる障害や葛藤かもしれない。だが、もはや何もしないまま押し流される人生を受け入れられるほど、彼女は弱くない。自分で描く色彩を信じ、冷たい結婚の檻を打ち破るために――その決意が胸の奥で静かに熱を帯びてゆくのを、カリナは確かに感じていた。
3-3
ステラリア家に新たに設けられる“ギャラリー”に、自分の絵を飾る――カリナ・ステラリアがその可能性を得てから、まだ数日。朝晩の空気には夏の名残が漂いつつも、どこか早めの秋の気配が忍び寄っている。昼間は伯爵令嬢として来客の応対や書状の確認などに追われるカリナだが、夜が更けて使用人たちの足音が途絶える頃になると、彼女は少しずつ自室の机に向かい始めていた。
薄明かりのランプを頼りに、机上にはイーゼルを簡素に立て、小ぶりのキャンバスと絵具を用意する。以前なら、絵筆を握るだけで心浮き立つ感覚があったが、今はそれ以上に「父や周囲に知られてはいけない」という緊張感が混ざる。それでも、ひとかけらの自由を味わえる時間を失いたくはなかった。筆先に静かに色を乗せ、ゆっくりとキャンバスに触れていくと、まるで水底に沈んでいた思いがふわりと浮上してくるような感覚を覚える。
(ああ、私……こんなにも“描くこと”が好きだったのね)
少しずつ輪郭を描き、淡い色を重ねていく。モチーフは白い花と薄青の空――かつて庭先で心奪われた景色を思い出しながら、自分なりに“どこにもない世界”を描き出していく。まるで荒涼とした現実から離れ、ほんのひととき幻想の中へ逃げ込むかのような作業。しかし、それは決してただの逃避ではなく、「自分自身を取り戻す」ための大切な行為でもあった。
だが、そんな夜の静寂はある晩、不意に破られることになる。いつものように書斎で残務をこなし、廊下を巡回していた家令が、カリナの部屋の前を通りかかったのだ。普段なら灯りを落としているはずの時間帯に、隙間から微かな光が漏れていることを不審に思ったのだろう。「お嬢様、まだ起きておいでですか?」――低い声が扉越しに響き、カリナは思わず筆を落としかける。
「あ、はい。少し読書をしていただけですわ」
そう取り繕いながら慌ててキャンバスを衝立の陰に隠し、絵具類を布で覆い隠す。家令はしばらく沈黙していたが、扉を開ける気配はない。代わりに「遅くまでご熱心ですね。ご体調を崩されませんよう、ほどほどに」とだけ言い残し、足音が遠ざかっていくのが聞こえた。
(危なかった……)
胸を撫で下ろすと同時に、カリナは心のどこかで小さな罪悪感を覚える。自分は伯爵令嬢として“正しい振る舞い”をしているわけではないのだ、と。しかし、その一方で「絵を描きたい」という意志が、どれだけ自分にとって大事なことかを再認識してもいた。周囲には秘密にせざるを得ない窮屈さと、それでも捨てられない大切な夢――その二つの狭間で揺れる夜が、彼女の日常となりつつあった。
翌朝、カリナはいつものように早めに起床し、伯爵家の日課である朝食に臨む。テーブルの席には、すでに父ハロルド伯爵と母、そして家令が揃っていた。エドリック・ヴェイルがここに顔を出すことは、相変わらず滅多にない。もともと彼は一度婚礼パーティが終わると、すぐに公爵家の公務へ戻ってしまい、また愛人の存在を隠そうともしない。母も伯爵の命令に逆らえる立場ではなく、ただ俯きがちに夫の話を聞いている。そんな光景にカリナは暗い息苦しさを覚えながらも、父の機嫌を損ねぬよう努めて箸を進める。
その朝、父はやや甲高い調子で話し始めた。
「お前、ギャラリーの件はちゃんと進めているのだろうな? アルファード氏からまだ具体的な展示計画が上がってこないと聞いているが」
「……はい。リース――いえ、アルファード様からは、いくつかの下準備を進めていると伺っています。どの絵を飾るか、周囲の反応を考慮しているとのことで」
父は「ふん」と鼻を鳴らしながら続ける。
「せっかくだから、ヴェイル公爵家との縁を連想させるような、荘厳な絵が欲しいものだ。庶民の描いた絵では風格に欠ける。そこらの芸術家を集めるだけではなく、ステラリア家のメンツにも配慮しろ。お前の描く絵とやらも、“恥ずかしくない程度”に仕上げておけ。分かったな」
最後の一言で刺すような目を向けられ、カリナは応えに詰まる。どこまでも形式や体裁にこだわり、娘の作品を「ただの飾り」程度にしか見ていない父。そんな現実に、しばし悔しさが込み上げるが、今はこらえるしかない。
食事を終え、カリナが侍女たちと身支度をしていると、家令が「アルファード様がお越しです」と告げに来た。ほどなくして大広間へ向かうと、そこにはリースが落ち着いた紺色の上着をまとい、資料らしきファイルを抱えて待っている。周囲には数人の使用人が所在なさげに立ち尽くしているだけで、伯爵は別の客人の相手で忙しいらしい。家令は「少々のあいだお嬢様のご意向を確認してください」と述べると、奥へ姿を消した。
「カリナお嬢様、失礼いたします」
リースが深々と頭を下げる。二人きりではないが、ここなら多少は会話の自由がきくだろう。
「リース、わざわざありがとうございます。父様からは“計画が遅れている”と責められてばかりで……大丈夫かしら?」
リースは苦笑まじりに「ご心配なく、順調に進んでいます。ただ伯爵殿は少々お急ぎのご様子で……」と告げると、手にしたファイルを開いて数枚のスケッチを見せた。そこには壁面の配置や照明の当て方、展示する作品のテーマ構成などが、簡潔に描かれている。
「実は、いくつかあなたの作品を紛れ込ませたいと思っています。もちろん、正式には伯爵殿の承認が必要ですが、『ステラリア家の令嬢が描いた優雅な絵』という名目なら、意外とすんなり通るかもしれません」
リースが声を潜めながら言う。カリナは思わず胸が熱くなるが、一方で一抹の不安も拭えない。「父様が“荘厳で格式高い作品”を望んでいるみたいだから、私の絵じゃ足りないって言われそうで……」
しかしリースはきっぱりと首を振った。
「大丈夫です。あなたの絵には繊細な美しさがある。むしろ、形式ばった絵画が多い中で、そういう瑞々しい感性が際立つはずです。伯爵殿にも“やわらかい印象の作品”があることでメリハリが出ると説明すれば、説得できるかもしれません」
その言葉に背中を押されるように、カリナは小さく頷いた。そして、まだ誰にも見せていない夜明けの花の絵を、ひとまずリースに見てもらいたいと申し出る。「でも、あれはまだ描きかけで……仕上げにはもう少し時間が必要なの。夜中にしか作業できないし」
リースは笑みを返し、声のトーンを落とす。
「すべてを一度に進めるのは難しいでしょう。少しずつで構いません。あなたが納得できる絵を完成させるまで、僕も協力を惜しみません。……ただ、できれば誰にも気づかれずに、あなたが自由に筆を握れる環境を作りたいのですが……」
それこそが最大の障壁だった。伯爵家の目を盗み、かつ家令や使用人たちの監視をかわすには、それなりの知恵がいる。さらに、エドリックの動向も予測不能だ。彼がふとした思いつきで屋敷を訪れたとき、もし“隠れて絵を描く伯爵令嬢”などという場面を目撃してしまえば、どれほどの騒ぎになるか想像もつかない。
(だけど、今ここで諦めたら……本当に何も変わらない)
カリナは、ぎこちなくも強い決意の込められた眼差しでリースを見つめる。彼もまた、その瞳に応えるようにゆっくりと頷いてくれた。自分たちが成すべきことははっきりしている――「絵を完成させ、ギャラリーに飾り、新しい道を切り開く」。たとえそれが、ほんの小さな“逆転劇”の始まりに過ぎないとしても、カリナはこの機会を絶対に逃したくなかった。
そこへ、父ハロルド伯爵と家令が戻ってくる足音が聞こえてきた。二人は気まずさを悟られないよう距離を取り、あくまで「仕事上の相談」という体裁を装ってファイルを閉じる。伯爵は露骨にリースを値踏みするような視線を向け、「どうだ、進展は?」とせっつく。リースはやや緊張した面持ちで「はい、問題なく進行しております。具体的な展示案を近々まとめますので、ご安心を」と答えた。
「ふん。まぁいい。カリナ、お前も真面目に取り組むんだぞ。ヴェイル公爵家の名に恥じぬようにな」
父の言葉にカリナは静かに目を伏せ、「かしこまりました」と返事をする。いつかこの“名門の仮面”を剝ぎ取って、本当の自分の色を取り戻せる日が来るように――その願いを胸に抱きながら。
――こうして、“ギャラリー計画”を通じて、カリナが自分の絵を堂々と披露するための準備は着実に進んでいく。しかし、それは同時に、彼女とリースが少しずつ“反撃”の兆しを見せ始めたという証でもあった。果たして伯爵家の監視や、いつか訪れるであろうエドリックとの衝突をどう乗り越えていくのか。冷たい婚礼に閉ざされた世界に、新たな炎が確実に燃え上がり始めている――カリナはその熱を、もう決して見失わないと誓うのだった。
3-4
ステラリア家に新設されるギャラリーの準備は、少しずつ形になろうとしていた。伯爵がほぼ強引に引っ張ってきた画商や出資者、さらには社交界の名士たちが、日を追うごとに屋敷を出入りするようになり、大広間や廊下には仰々しい下見や打ち合わせの姿が散見される。リース・アルファードもまた、伯爵の“アドバイザー”として、頻繁に訪問を繰り返していた。
一見すると、それらはすべて「名家の面子を保つための華やかな企画」に過ぎない。だが、その裏ではリースとカリナ・ステラリアのささやかな“計画”も、着実に進行しつつあった。
カリナ自身の描いた絵をギャラリーに出品する――伯爵は体裁さえ整えばと容認したが、具体的な作品についてはまだ知らされていない。それでいい、とカリナは考えている。自分が描くのは形式ばかりの荘厳な絵ではない。彼女が筆を走らせる夜明けの花や、淡くにじむ空の色彩は、ステラリア家の下で強要されてきた“華やかさ”とも、“ヴェイル家の威光”ともまるで無縁の世界だ。だからこそ、堂々と胸を張れるだけの“本当の自分”を封じ込めた作品にしたい。そう強く思っていた。
もっとも、夜な夜な絵を描くのは容易ではない。夜更けに絵具の匂いを漂わせていれば、家令や侍女たちの不審を買いかねない。そこでカリナは、昼間のわずかな空き時間にもスケッチや色の試し塗りを進めるようになった。誰かが扉の外を通る気配を感じたら、即座に道具を引き出しの奥へ隠す。まるでスパイのような日々が続くが、それでも筆を握るたびに感じる心の解放こそが、彼女にとっては生きる支えでもあった。
そんなある日の午後、カリナはいつものように父の命令で来賓へのお茶を振る舞い、馬車で送り出す役目を終えた後、ほっと息をついて廊下を歩いていた。すると、曲がり角からリースが姿を見せる。彼もまた、伯爵に呼びつけられて打ち合わせをしたところらしく、やや疲れた表情だった。
「やあ、カリナお嬢様……少しだけお時間を頂けませんか? 伯爵殿のご要望を聞きつつ、具体的な展示の流れを整理していたのですが、ぜひあなたの意見も伺いたい」
そう言いながらリースは、手にしたノートを軽く掲げてみせる。タイミングを見計らったかのように家令が横切ったが、「アルファード様がお嬢様と打ち合わせをされたいとのことです」と言うと、家令はわずかに頷いて「では、応接室をお使いください」とだけ告げて去っていった。慌ただしい屋敷の空気の中にあって、二人が言葉を交わすには好都合だった。
応接室へ入ると、そこには来客用のソファが二つ向かい合うように置かれ、壁際には棚と数枚の絵画。ふだんは名だたる貴族をもてなす場所だけに、調度品が豪華で重厚な印象を与える。それでも、今日に限っては客もおらず、侍女も誰もいない。カリナはドアをそっと閉め、リースと向かい合って腰を下ろす。
「父様、またたくさん要望を出してきたのでしょう? 結局、どんな展示を望んでいるのかしら……」
リースは苦笑を浮かべながらノートを開く。
「はい、華やかさを重視して、“ヴェイル公爵家の名前にふさわしい威厳を演出せよ”とのことですね。あと、“ステラリア家の伝統も強調するように”とか。正直、形式優先の意見が多くて、なかなかまとめるのが大変です」
カリナは溜息をつきつつも、「私の絵を飾る件は……?」と小声で尋ねた。
「伯爵殿には“令嬢の作品もアクセントとして使うと良いでしょう”と伝えています。評価次第で採用を判断したいとのこと。飾る場所や作品数など、最終的には僕とあなたで決める形になりそうです」
リースがそう言ってノートのページをめくると、展示レイアウトの案がいくつも描かれている。その中の一角に“カリナの作品”と書き添えられたスペースがあった。見れば壁際に大きめのキャンバスをかけ、天井からはスポットライトを当てるような図面が引かれている。
「こんなふうに、一角をあなたの世界にしてみたいと思っているんです。仰々しい荘厳な絵ばかりじゃ息が詰まるから、あなたの淡い色彩を引き立てるようなレイアウトにしてみたくて」
それはリースの作り上げる“舞台装置”の一部かもしれない。けれど、その一部だけは伯爵やエドリックの意向を真っ向から気にする必要がない“自由な空間”になり得るのだ。イメージを膨らませるほどに、カリナの胸は高鳴る。自分の絵がこの場所に堂々と飾られ、それを観る人が少しでも何かを感じ取ってくれたら――彼女にとって、それこそが生きている意味を再発見する瞬間になるだろう。
「素敵……ありがとう、リース。こんなにも真剣に私の絵を大切に扱おうとしてくれるなんて……」
思わずこぼれた言葉に、リースは微笑み返す。
「僕の方こそ、あなたが描く世界に救われている気がするんですよ。ステラリア家やヴェイル公爵家の圧力って相当なものだし、それに負けず描き続けているあなたが、僕にはとても輝いて見える。……だから、一度きりではなく、いつか本当にあなたが自由に絵を描ける環境を作ってあげたい」
その静かな決意を聞いて、カリナは胸が熱くなる。ほんの数ヶ月前までは想像もしなかった光景――“結婚は政略でしかない”と割り切っていた頃の自分に、こんな希望が訪れるとは思わなかった。もっとも、愛のない婚礼がやがて本格的に始まれば、彼女はヴェイル家へ移り、さらに厳しい制約を強いられるだろう。それでも、このわずかなチャンスを捨てるわけにはいかない。
会話がひと段落し、二人が作業のためノートに視線を落とした瞬間――唐突に扉が開く音がして、カリナははっと顔を上げる。そこには、さほど貴族らしからぬ軽い足取りで入ってきた一人の男……エドリック・ヴェイル本人だった。
普段めったに姿を見せないエドリックが、まさかこの応接室に不意打ちのように現れるとは想定外だ。カリナとリースは即座に立ち上がり、軽く頭を下げる。エドリックはちらりと二人を見やり、あからさまに興味のなさそうな瞳で言い放った。
「フン、ここで何の話をしている。ギャラリーの件か? 父上や伯爵から、“婚礼の記念に盛大な催しをする”と聞いていたが……」
リースがあわてて説明を始める。「はい、ヴェイル公爵家のお名も借りて、ステラリア家で大きな展覧会を開催する予定でして……わたくしは、その企画の補佐を――」
ところが、エドリックは最後まで聞かずに「どうでもいい。俺には関係のないことだ」と冷ややかに切り捨てる。それだけならまだしも、カリナに向かって一歩近づき、嘲るような笑みを浮かべた。
「おまえも忙しそうだな、カリナ。まるで自分が重要人物にでもなったつもりか。俺はただの義務でここに来ただけだが――なぁ、聞いているか?」
エドリックは顎をしゃくってリースを見やる。暗に“引き下がれ”と命じているのが明白だった。リースは苦々しい表情を浮かべながら、「失礼します」と軽く一礼し、資料を抱えて部屋を出て行く。
扉が閉まると、応接室にはカリナとエドリックの二人だけが残った。彼は見るからに不機嫌そうな顔で、テーブルの上に置かれたノートを乱暴に手に取る。
「興味はないが、一応目を通してやるか……へえ、絵を展示してどうこう……そんなものに労力を注ぐとは、伯爵も暇なんだな」
投げやりな態度は変わらない。カリナの心には、怒りや悲しみがない交ぜになった複雑な感情が湧き上がるが、ここで正面から反論しても得られるものは何もない。だからこそ、冷静さを保ちつつ言葉を選ぶ。
「……ステラリア家にとっては、大切な行事なんです。ヴェイル家とのご縁を示す意味でも、父様は気合いを入れているんですよ」
すると、エドリックは“ヴェイル家”という単語にわずかに反応し、鼻で笑った。
「俺は別にステラリア家に何も期待していないがね。おまえが俺の妻になることなど、正直どうでもいい。父上の意志があるから従っているだけだ。ただし――」
突如としてエドリックの声の調子が変わる。カリナは身構えながら、一体何を言われるのかと息をのんだ。
「ただし、俺の立場を悪くするような動きはするなよ。伯爵の娘として大人しくしていればいい。屋敷の改装だのギャラリーだの、おまえに何ができる? むしろ邪魔だけはするな」
言い切ると、エドリックはノートを放り投げるようにテーブルへ戻し、踵を返して出て行こうとする。カリナは怒りを飲み込みながら、一言だけ返した。
「……あなたこそ、いったい何を求めているんですか? 私に何の感情もないのに、なぜわざわざここへ?」
彼は振り向かないまま、静かな声で言い捨てる。
「俺は義務を果たしに来ただけだ。おまえに興味はない。――以上だ」
重苦しい沈黙の中、エドリックは部屋から出て行った。残されたカリナは、震える手でノートを拾い上げる。リースが大切に描いたギャラリー案の紙が少しだけ折れ曲がっていた。じっとりと嫌な汗が背中を伝い、冷ややかな怒りが込み上げる。
(これが私の“夫”になる人……あまりにも冷たく、何も感じられない人。それでも私は、家の名のために嫁ぐしかないの?)
しかし、悔しさと同時にカリナの中で一層強くなるものがあった。リースが用意した“自由な空間”を必ず実現させたい。エドリックの冷笑に屈服するわけにはいかない。
――その夜、カリナは再び机に向かい、そっと筆を握る。エドリックと向き合うほど、父の思惑を知るほど、息苦しさが増していく。けれど、その苦しさは“色”を生み出す力にも変えられる。
(私には、私の描く世界がある。そこだけは誰にも汚されたくない)
そう胸に誓い、キャンバスに色を落とすたびに、夜明けの花が少しずつ輪郭を増していく。その筆先には、エドリックの冷たい瞳を跳ね返すような、確固たる意志が刻み込まれていた。リースが与えてくれた舞台で、この絵を堂々と披露できる日が来るならば、きっと“無彩の婚礼”にも火が灯るだろう。今はまだ小さな炎に過ぎない。だけど、必ず燃え上がる――カリナはそう信じながら、夜の闇に向かって色彩を紡ぎ続けるのである。
ステラリア家の屋敷で催された「婚礼パーティ」から数日が経過した。冷ややかで嘘に塗り固められた祝福の夜の余波は、今なおカリナ・ステラリアの胸を締めつけている。けれど、そんな彼女を取り巻く状況は、一見して以前とさほど変わらないように見えた。父ハロルド伯爵は、ヴェイル公爵家との縁組が決定事項となったことに気を良くし、相変わらず「我が家の復興は目の前だ」と豪語しているし、エドリック・ヴェイルはほとんど屋敷に顔を出さない。結婚式当日こそ多くの人々の前で“形ばかりの誓い”を立てたものの、それ以降、夫婦として何らかの交流を深めようとする気配は微塵も感じられなかった。
もっとも、それはカリナにとっても都合が悪いことではなかった。エドリックの存在を意識する機会が少ない分だけ、あの“愛人”の妖艶な影に胸をかき乱されることも減る。それでも事態はまったく好転せず、遠くないうちに“正式な結婚生活”が始まれば、彼女はヴェイル家へと移り住み、あの冷たい婚約者と過ごさねばならなくなる。かりそめの宴が終わりを告げても、カリナの未来は相変わらず暗雲に覆われていた。
しかし、そんな閉ざされた日々のなかにも、かすかな変化の種は芽吹き始める。婚礼パーティの夜にわずかとはいえ言葉を交わし、翌日には屋敷へ見舞いの手紙を送ってきた人物――そう、カリナが唯一心を許しかけている青年、リース・アルファードからだった。彼は「パーティの席でご体調を崩されたと聞き、ひどく心配しております。もし差し支えなければ、改めてお見舞いに伺いたい」と綴ってくれていたのだ。画廊を手伝う身分でありながら、このステラリア家に“客人”として連絡をよこすなど、常識的にはあり得ない行為かもしれない。しかし、カリナは手紙を読みながら自分でも驚くほど胸が弾んでいることを感じた。
「……きっと、私のことを真剣に気遣ってくれているんだわ」
そう呟いたとき、自分の内側で小さな炎がふっと灯るのをカリナははっきりと意識した。政略結婚の道具としか扱われず、エドリックからは無視同然の態度を受け、父からは“家を盛り立てるための存在”としか見られない。このまま何も変わらないなら、自分は本当に壊れてしまう――そんな恐怖の中にあって、リースの言葉はまさに救いだった。もちろん、彼との交流が公になれば、父や周囲から厳しい目を向けられるかもしれない。だが、それでもなお、カリナは彼と話すことで辛うじて“自分”を取り戻せる気がする。
とはいえ、これまでのように無防備に会いに行くわけにはいかなかった。父は婚礼パーティ以来、自分が取りこぼすはずだった大きな得点を堂々と手に入れた気分なのだろう。カリナの外出を以前より厳しく制限し、来客の相手をさせるときも家令や侍女長を必ず同席させるようにしている。貴族の慣習とはいえ、これではリースとゆっくり話をすることなど到底かないそうにない。それでも、“少しずつ変えていく”ための方法がきっとあるのではないか――そんな漠然とした期待が、カリナの中で静かに膨らみ始めていた。
やがて、思いがけない形でその“期待”が具現化する。ある日、カリナが屋敷の図書室を訪れた際、書棚と書棚のあいだで熱心に本を探しているリースの姿を見つけたのだ。一瞬何かの見間違いかと思ったが、まぎれもなく本人である。驚きに目を見開くカリナに気づいたリースは、気まずそうに微笑みながら片手を挙げる。
「お久しぶりです、カリナお嬢様。実は伯爵さま――お父上のご依頼で、今度開く展覧会の参考資料を探すよう頼まれまして……」
何でも父は、画商や美術関係者とのコネクションを一層強めるべく、近々屋敷の一室をギャラリーとして開放しようと考えているらしい。そこに展示する絵画のセレクトや、展覧会の段取りを手伝うため、リースが招かれたのだという。その“公的”な用事があるため、家令や侍女長も彼が図書室で資料を探すことを許可し、特に警戒の目も光らせていないようだ。言い換えれば、これはカリナがリースと遠慮なく接することのできる数少ない機会ということになる。
「まさか、あなたが父様の依頼を受けるなんて……」
カリナは胸の奥で期待と戸惑いが入り混じる感情を抱えつつ、声を落として続ける。「でも、その……ありがとうございます。私のこと、気づかってくださっていたんですよね……?」 遠回しな言い回しだったが、リースは柔らかな笑みを浮かべてはっきりと頷いた。
「ええ、あの晩、控室でお会いしたときからずっと心配でした。お見舞いの手紙をお送りしたものの、返事をいただくのも難しいかもしれないと思っていたので……こうしてまたお話しできるなんて、嬉しいです」
その言葉だけで、カリナの心に微かな光が差す。周囲を気にしながらも彼と目線を合わせると、いつもの冷たい屋敷の空気が少しだけやわらかく感じられた。
図書室には家令の姿もなく、侍女たちは離れた場所で蔵書の整理をしている。さらに父は客間で貴族仲間との会談中で、ここへ来る気配はない。ほんのわずかな間なら――そう思ったカリナは、少しだけ声量を下げてリースに問いかける。
「……今、少しお話ししてもいいかしら。じっくり話をする機会がずっとなかったから、私……あなたに伝えたいことがあって」
リースは周囲に誰もいないことを確認し、落ち着いた声で答えた。「もちろんです。僕もいろいろお伝えしたいことがあります。よろしければ、一緒にこの辺りの本を探すふりをしながら……」 穏やかな提案に、カリナはほっと微笑む。こうして二人は、書棚に隠れるようにして小声の会話を始めた。
「婚礼パーティのあと、いろいろと思い悩んでいたの。ヴェイル家に嫁ぐことが決まって……エドリック様は私に興味を持っていないし、私も……あの人には何も……」
言いかけて、カリナは目を伏せる。結婚相手に愛情のかけらも感じず、それどころか公然の愛人までいるという現実。だが、リースが落ち着いた声で言葉を返してくれた。
「正直、その噂は僕も聞いていました。けれど、あなたがそこに苦しんでいるのなら、少しでも力になりたい。……失礼を承知で言うけれど、あなたは決して道具なんかじゃない。描く才能も、感じる心も、きっとあなたのものなんだ」
そのまっすぐな励ましが、カリナの胸に深く沁みる。今まで誰も言ってくれなかった言葉。父からは“家を立てる存在”としか期待されず、エドリックからは“何も求められない”。そんな孤独の中で、リースだけが“カリナ自身”の力を信じてくれているのだと実感した。
ふと、カリナは思い出したように声を落とす。「……あなたはギャラリーの準備を手伝うために来てくれたのよね。もしかして、私の絵も出品できるのかしら?」 聞いてしまってから、これは危険な提案かもしれないと思う。伯爵家の面目を保つ展覧会に、未熟な自分の作品を並べるなど前代未聞の行為だ。だが、リースは目を輝かせて頷いた。
「もちろんです。僕もそれができたらいいなって、実は考えていました。ただ、あなたのお父上や使用人たちが何と言うか……そこが問題ですね。ですが、もし何らかの形で説得できれば、あるいは“ステラリア家の令嬢の趣味”という名目でもいいから、あなたの作品を飾れるかもしれない」
その言葉にカリナの心は一気に躍る。同時に、かつての自分が抱いていた“夢”の感覚が蘇ってくる気がした。まだ現実味は薄いけれど、自分が筆を取り、何かを描き、それを誰かに見てもらう――そんな日が訪れる可能性がゼロではないのだ。
「……ありがとう、本当に。私、こんなふうに思えるの、久しぶり」
そう微笑んだ瞬間、遠くから侍女たちの話し声が近づいてくる気配がした。名残惜しいが、これ以上目立ってはいけない。二人はさっと離れて、別々の棚を探るフリに移る。そして、すれ違いざまにリースがカリナにだけ聞こえる小さな声で告げた。
「また改めて、詳しく相談しましょう。きっと今のままではいられないはずですから」
“今のままではいられない”――その一言が、カリナの胸を大きく揺さぶった。閉塞的だった日々が、少しずつ変化していく兆し。それは同時に、自ら動かなければ何も始まらないという警告でもあったが、カリナはなぜかそれを怖いと思わなかった。むしろ、静かに燃える決意のようなものが心のどこかに芽生えるのをはっきりと感じたのだ。
(父様やエドリック様に一方的に振り回されるだけじゃ、何も変わらない。私の力で、私が何かをしなくちゃ――)
図書室を出たあとも、カリナはしばらく胸の高鳴りが収まらなかった。“反撃の兆し”とも呼べる小さな炎が、自分の中で力強く燃え始めている。これまでただ耐え忍ぶだけだった少女が、まるで嵐に向かう船の帆を張るかのように、覚悟を固めつつあった。愛のない婚礼、形だけの夫婦生活、家の重圧――すべてを受け入れるよう強要されても、自分だけの夢を見失うわけにはいかない。リースがくれた勇気と、この心に宿る小さな炎を頼りに、カリナは未来へ踏み出そうとしていた。
――これはまだ始まりの段階に過ぎない。どんな困難が待ち受けていても、“今のままではいられない”という意志さえ失わなければ、きっと道は切り拓ける。カリナはそう信じながら、人気のない廊下を一人歩く。外から差し込む夕日の色が、彼女の金の髪を静かに照らしていた。自分が変わり始めたことを証明するかのように、周囲の空気がわずかに揺れて見える。その揺らぎこそが、長かった沈黙の日々に差し込んだ“反撃”の予兆なのだ――と、カリナはかすかな笑みを浮かべるのだった。
3-2
カリナ・ステラリアが図書室でリース・アルファードと密かに言葉を交わしてから、まだ数日しか経っていない。それでも彼女の心境には、小さくとも確かな変化が芽生えつつあった。かつてはただ“嫁ぐこと”を既定路線として受け入れ、父ハロルド伯爵やエドリック・ヴェイルの意向に従うだけだった。しかし今や、彼女の中には「何かを行動に移さなければ、いずれ本当に自分を失ってしまう」という、切実な思いが生まれている。
かといって、急にすべてを覆せるわけでもない。リースが言うように、ステラリア家の人間関係や、ヴェイル公爵家との結びつきには、強固な利害が張り巡らされている。迂闊に波風を立てれば、父の怒りを買うばかりか、屋敷の使用人たちやリース自身にまで不利益が及ぶかもしれない。だからこそカリナは、まず“小さな行動”から始めようと決めた。自分にできる範囲で、絵を描く準備を少しずつ進めてみること。リースが関与するギャラリーの企画に、少しでも自分の作品を滑り込ませる可能性を探ること。それが今の彼女にとって、最初の一歩だった。
その日、カリナは珍しく早起きをした。夜明け前の薄暗い空気を感じながら、自室の机に向かう。前日は父が貴族仲間との会合を夜更けまで続けていたおかげで、まだ屋敷内が起き出す気配はない。まどろむような静けさの中、カリナは筆と紙を取り出した。最後にまともに絵を描いたのは、婚約話が本格化する前――ずいぶん遠い記憶になりかけていた。慣れ親しんだ筆の触感が愛おしいと同時に、ぎこちなさも感じる。しかし、一度色を置き始めれば、かつて身体に染み付いていた感覚がゆっくりと蘇ってきた。
「……花……描いてみようかしら」
カリナは目を閉じ、昨晩庭に咲いていた白い花々を思い浮かべる。形を捉えるというよりは、頭の中にある淡いイメージをそのまま紙に移していくように筆を走らせる。花びらの質感や、夜露に濡れるときの儚げな光を思い出す――かつては何の苦もなくできていたはずの作業なのに、今は少し指先が震える。それでも、時間を忘れて筆を動かしているうちに、やがて紙の上にぼんやりとした白と微かな青の入り混じった世界が浮かび上がってきた。
「……まだまだ、うまく描けてはいないけれど……」
筆を置いたとき、カリナの胸には不思議な高揚感が残っていた。完璧からはほど遠いスケッチ――それでも、自分で色を生み出す感覚を久々に味わい、「まだ私は絵を描きたい」と心から感じられたのだ。父に見つかれば「そんな無駄なことをしている暇があるのか」と叱責されるかもしれないし、エドリックには馬鹿馬鹿しいと一蹴されるかもしれない。けれど、たとえ一瞬でも自由に表現する時間が持てたことは、今のカリナにとって何物にも代えがたい“小さな希望”だった。
やがて朝を告げる鐘が鳴り、屋敷が徐々に動き始める。カリナはすぐに筆と紙を片付け、ほかの者に見られないよう本棚の奥へそっとしまい込んだ。今日もまた、伯爵令嬢としての儀礼や客人対応が待ち受けているだろう。それでも、一度でもこうして絵を描けた――その事実が、彼女の足取りをわずかに軽くする。
朝食の場では、父が珍しく上機嫌だった。どうやら最近、何人かの貴族や豪商から「婚礼にまつわる新たな投資話」が持ち込まれているらしく、ステラリア家の懐具合も少しずつ潤い始めているのだという。
「やはりヴェイル公爵家との縁組は大正解だったな。カリナ、お前の貢献は大きいぞ」
父は顔を上げずにパンをかじりながらそう言い放つ。そこに“娘を気遣う親”としての優しさなどかけらもないのが、もはやカリナには分かりきっていた。
「ありがとうございます、父様……」
とだけ返事をすると、父はさらに得意気に話を続ける。
「近々、屋敷の改装を少し進めるつもりだ。画商や有力者を呼んで、ギャラリーを設けるとなれば、それ相応の体裁が必要だろう。親切にもヴェイル公爵家の執事がアドバイザーを紹介してくれたからな。アルファードという青年も手伝ってくれるらしいが……そうだ、お前も何か用があるなら彼に頼めばいい。絵がどうのこうのと聞いたが、せいぜい屋敷の飾り付けに協力する程度にしておけ」
“アルファード”――まさにリースのことである。つい先日、図書室で密かに話をしたばかりなのに、父の口からも彼の名が出るとは思わなかった。思わず胸が高鳴り、同時に「自分の動きが父に知られすぎてはまずい」という警戒も走る。それでも、半ば公然とリースと関わりを持てるのは大きな前進かもしれない。カリナは微妙な感情を噛みしめながら、はい、とだけ答えた。
朝食後、カリナが侍女たちとともに廊下を移動していると、奥から侍女長が足早にやってきて声をかける。
「お嬢様、本日は屋敷の改装計画に関する打ち合わせがあるとのことで、伯爵さまが大広間まで来るようにと仰っております。リース・アルファード様もお見えになるようですので、合わせてご相談されたらいかがでしょう」
まさしく渡りに船、と言わんばかりの展開だ。しかし、下手に喜びを表に出せば、周囲の人々に余計な勘繰りをされる可能性がある。カリナはできるだけ平静を装いながら、「わかりました」とだけ返事をした。
大広間へ向かうと、父と家令、そしてリースがすでに何冊かの資料を広げながら話をしているところだった。リースも、仕事用なのか落ち着いた色合いの上着とパンツを身に付け、きちんと髪をまとめている。相変わらず温和そうな笑みを浮かべながら、父の指示を熱心に聞いていたが、カリナの姿に気づくとほのかに目尻を緩める。そのわずかな仕草を見逃さないまいと、カリナもまたさりげなく彼に微笑み返した。
「それで、私を呼び出したのは何でしょうか、父様」
伯爵はやはり上機嫌な様子で、地図のような書面を指し示す。そこには屋敷の見取り図が描かれており、一部の部屋や廊下に丸印が記されていた。
「ここを改装して、ここに新しい調度品を置く。そして、この奥をギャラリーとして活用する予定だ。アルファード氏にも意見をもらいながら、展示する絵画のセレクトを進める。お前も礼儀作法の一環として、訪れる客人の案内をできるようにしておくんだ。……それから、だ」
伯爵はちらっとリースに視線を投げ、続ける。
「お前が昔からちょろちょろと落書き程度に絵を描いていたのは知っているが、もしどうしても飾りたい作品があるなら、アルファード氏と相談してみるといい。ただし、ステラリア家の恥をさらすようなものは勘弁だぞ。名家にふさわしい体裁が整うなら構わんが、出来損ないの趣味を押し出されちゃ困るからな」
その言葉はカリナにとって一種の衝撃だった。伯爵が“絵を飾る”という可能性を許容しているのは、極めて珍しい。もっとも、そこには彼の打算――「令嬢が描いた絵を展示するなんて洒落た演出だ」と客人に思わせる目的――があるのかもしれない。だが、伯爵の真意がどうであれ、これを利用しない手はないとカリナは瞬時に悟る。彼女は表情を崩さないよう注意しながら、静かに頷いた。
「ありがとうございます。……ただ、私の絵は拙いですし、父様の望む“名家の体裁”に合わないかもしれません。なので、アルファード様のご意見をお借りして、一度仕上がりを見ていただきたいのです」
そう口にすると、父は「ふん」とわざとらしく鼻を鳴らす。しかし特に反対はしなかった。家令も黙っている。そこへリースが控えめに一礼しながら口を開く。
「では、私の方でお嬢様の絵を拝見し、展示にふさわしいかどうか、また飾り方なども含めてご提案させていただければと思います。それが屋敷の品位を高めるものであれば、きっと良い効果が得られるでしょう」
こうして自然な流れのまま、カリナは伯爵公認でリースと“作品の相談”をする機会を手に入れた。まるで信じられないほど上手くことが運んでいるが、その裏には父の“名家のアピール”という打算があり、彼女が本当に表現したいものを自由に描けるかどうかは、まだわからない。それでも、ほんの少しでも“道具”以外の自分を示せる可能性が残されたのは大きい。
その日の夕方、カリナは廊下で偶然を装ってリースに近づいた。周囲を伺いながら、極力自然な口調で彼に声をかける。
「先ほどはありがとうございました。父様の前で言ってくれたこと、心強かったわ……」
リースもまた、周囲に警戒しながら小声で応じる。
「お役に立てたなら何よりです。こちらこそ、あなたの作品をぜひ見たい。実は僕も、いいアイデアがありそうなんです。展示するとなれば、ただ『名家の飾り』としてではなく、あなたの本当の魅力が伝わるような形を目指したいと思っていて……」
その先の言葉は、誰かが廊下を横切ったため遮られてしまうが、カリナの胸には高揚感が広がっていく。屋敷のあちこちに敷かれた規律や、エドリックとの結婚がもたらす束縛は、依然として重苦しい現実としてのしかかっている。愛のない婚礼、形ばかりの夫婦生活――まるで冷たい牢獄のような未来が待ち受けていると想像するだけで息が詰まる。
けれど、その暗闇の中に微かな光を探し出せるかもしれない。“絵を描く”という自分の意思を証明することで、ほんの少しでも道が拓けるなら――その希望だけが、カリナを新しい行動へと駆り立てるのだ。
(今の私には、やるべきことがある。とにかく描かなくちゃ……)
心の奥で固く誓いながら、カリナは屋敷の奥まった階段を上がっていく。もうすぐ夜が訪れる頃合いだが、彼女は疲れを感じるどころか、不思議と高揚したままだ。父の思惑やヴェイル公爵家の権威を逆手に取りながら、リースとともに少しずつ未来を変えていく――“燃え上がる逆転劇”の火種は、間違いなく彼女の胸で燻り始めているのだから。
――こうして、ステラリア家という大きな檻の中で、カリナは“本来の自分”を取り戻すための小さな行動を起こし始めた。次に訪れるのは、きっとさらなる障害や葛藤かもしれない。だが、もはや何もしないまま押し流される人生を受け入れられるほど、彼女は弱くない。自分で描く色彩を信じ、冷たい結婚の檻を打ち破るために――その決意が胸の奥で静かに熱を帯びてゆくのを、カリナは確かに感じていた。
3-3
ステラリア家に新たに設けられる“ギャラリー”に、自分の絵を飾る――カリナ・ステラリアがその可能性を得てから、まだ数日。朝晩の空気には夏の名残が漂いつつも、どこか早めの秋の気配が忍び寄っている。昼間は伯爵令嬢として来客の応対や書状の確認などに追われるカリナだが、夜が更けて使用人たちの足音が途絶える頃になると、彼女は少しずつ自室の机に向かい始めていた。
薄明かりのランプを頼りに、机上にはイーゼルを簡素に立て、小ぶりのキャンバスと絵具を用意する。以前なら、絵筆を握るだけで心浮き立つ感覚があったが、今はそれ以上に「父や周囲に知られてはいけない」という緊張感が混ざる。それでも、ひとかけらの自由を味わえる時間を失いたくはなかった。筆先に静かに色を乗せ、ゆっくりとキャンバスに触れていくと、まるで水底に沈んでいた思いがふわりと浮上してくるような感覚を覚える。
(ああ、私……こんなにも“描くこと”が好きだったのね)
少しずつ輪郭を描き、淡い色を重ねていく。モチーフは白い花と薄青の空――かつて庭先で心奪われた景色を思い出しながら、自分なりに“どこにもない世界”を描き出していく。まるで荒涼とした現実から離れ、ほんのひととき幻想の中へ逃げ込むかのような作業。しかし、それは決してただの逃避ではなく、「自分自身を取り戻す」ための大切な行為でもあった。
だが、そんな夜の静寂はある晩、不意に破られることになる。いつものように書斎で残務をこなし、廊下を巡回していた家令が、カリナの部屋の前を通りかかったのだ。普段なら灯りを落としているはずの時間帯に、隙間から微かな光が漏れていることを不審に思ったのだろう。「お嬢様、まだ起きておいでですか?」――低い声が扉越しに響き、カリナは思わず筆を落としかける。
「あ、はい。少し読書をしていただけですわ」
そう取り繕いながら慌ててキャンバスを衝立の陰に隠し、絵具類を布で覆い隠す。家令はしばらく沈黙していたが、扉を開ける気配はない。代わりに「遅くまでご熱心ですね。ご体調を崩されませんよう、ほどほどに」とだけ言い残し、足音が遠ざかっていくのが聞こえた。
(危なかった……)
胸を撫で下ろすと同時に、カリナは心のどこかで小さな罪悪感を覚える。自分は伯爵令嬢として“正しい振る舞い”をしているわけではないのだ、と。しかし、その一方で「絵を描きたい」という意志が、どれだけ自分にとって大事なことかを再認識してもいた。周囲には秘密にせざるを得ない窮屈さと、それでも捨てられない大切な夢――その二つの狭間で揺れる夜が、彼女の日常となりつつあった。
翌朝、カリナはいつものように早めに起床し、伯爵家の日課である朝食に臨む。テーブルの席には、すでに父ハロルド伯爵と母、そして家令が揃っていた。エドリック・ヴェイルがここに顔を出すことは、相変わらず滅多にない。もともと彼は一度婚礼パーティが終わると、すぐに公爵家の公務へ戻ってしまい、また愛人の存在を隠そうともしない。母も伯爵の命令に逆らえる立場ではなく、ただ俯きがちに夫の話を聞いている。そんな光景にカリナは暗い息苦しさを覚えながらも、父の機嫌を損ねぬよう努めて箸を進める。
その朝、父はやや甲高い調子で話し始めた。
「お前、ギャラリーの件はちゃんと進めているのだろうな? アルファード氏からまだ具体的な展示計画が上がってこないと聞いているが」
「……はい。リース――いえ、アルファード様からは、いくつかの下準備を進めていると伺っています。どの絵を飾るか、周囲の反応を考慮しているとのことで」
父は「ふん」と鼻を鳴らしながら続ける。
「せっかくだから、ヴェイル公爵家との縁を連想させるような、荘厳な絵が欲しいものだ。庶民の描いた絵では風格に欠ける。そこらの芸術家を集めるだけではなく、ステラリア家のメンツにも配慮しろ。お前の描く絵とやらも、“恥ずかしくない程度”に仕上げておけ。分かったな」
最後の一言で刺すような目を向けられ、カリナは応えに詰まる。どこまでも形式や体裁にこだわり、娘の作品を「ただの飾り」程度にしか見ていない父。そんな現実に、しばし悔しさが込み上げるが、今はこらえるしかない。
食事を終え、カリナが侍女たちと身支度をしていると、家令が「アルファード様がお越しです」と告げに来た。ほどなくして大広間へ向かうと、そこにはリースが落ち着いた紺色の上着をまとい、資料らしきファイルを抱えて待っている。周囲には数人の使用人が所在なさげに立ち尽くしているだけで、伯爵は別の客人の相手で忙しいらしい。家令は「少々のあいだお嬢様のご意向を確認してください」と述べると、奥へ姿を消した。
「カリナお嬢様、失礼いたします」
リースが深々と頭を下げる。二人きりではないが、ここなら多少は会話の自由がきくだろう。
「リース、わざわざありがとうございます。父様からは“計画が遅れている”と責められてばかりで……大丈夫かしら?」
リースは苦笑まじりに「ご心配なく、順調に進んでいます。ただ伯爵殿は少々お急ぎのご様子で……」と告げると、手にしたファイルを開いて数枚のスケッチを見せた。そこには壁面の配置や照明の当て方、展示する作品のテーマ構成などが、簡潔に描かれている。
「実は、いくつかあなたの作品を紛れ込ませたいと思っています。もちろん、正式には伯爵殿の承認が必要ですが、『ステラリア家の令嬢が描いた優雅な絵』という名目なら、意外とすんなり通るかもしれません」
リースが声を潜めながら言う。カリナは思わず胸が熱くなるが、一方で一抹の不安も拭えない。「父様が“荘厳で格式高い作品”を望んでいるみたいだから、私の絵じゃ足りないって言われそうで……」
しかしリースはきっぱりと首を振った。
「大丈夫です。あなたの絵には繊細な美しさがある。むしろ、形式ばった絵画が多い中で、そういう瑞々しい感性が際立つはずです。伯爵殿にも“やわらかい印象の作品”があることでメリハリが出ると説明すれば、説得できるかもしれません」
その言葉に背中を押されるように、カリナは小さく頷いた。そして、まだ誰にも見せていない夜明けの花の絵を、ひとまずリースに見てもらいたいと申し出る。「でも、あれはまだ描きかけで……仕上げにはもう少し時間が必要なの。夜中にしか作業できないし」
リースは笑みを返し、声のトーンを落とす。
「すべてを一度に進めるのは難しいでしょう。少しずつで構いません。あなたが納得できる絵を完成させるまで、僕も協力を惜しみません。……ただ、できれば誰にも気づかれずに、あなたが自由に筆を握れる環境を作りたいのですが……」
それこそが最大の障壁だった。伯爵家の目を盗み、かつ家令や使用人たちの監視をかわすには、それなりの知恵がいる。さらに、エドリックの動向も予測不能だ。彼がふとした思いつきで屋敷を訪れたとき、もし“隠れて絵を描く伯爵令嬢”などという場面を目撃してしまえば、どれほどの騒ぎになるか想像もつかない。
(だけど、今ここで諦めたら……本当に何も変わらない)
カリナは、ぎこちなくも強い決意の込められた眼差しでリースを見つめる。彼もまた、その瞳に応えるようにゆっくりと頷いてくれた。自分たちが成すべきことははっきりしている――「絵を完成させ、ギャラリーに飾り、新しい道を切り開く」。たとえそれが、ほんの小さな“逆転劇”の始まりに過ぎないとしても、カリナはこの機会を絶対に逃したくなかった。
そこへ、父ハロルド伯爵と家令が戻ってくる足音が聞こえてきた。二人は気まずさを悟られないよう距離を取り、あくまで「仕事上の相談」という体裁を装ってファイルを閉じる。伯爵は露骨にリースを値踏みするような視線を向け、「どうだ、進展は?」とせっつく。リースはやや緊張した面持ちで「はい、問題なく進行しております。具体的な展示案を近々まとめますので、ご安心を」と答えた。
「ふん。まぁいい。カリナ、お前も真面目に取り組むんだぞ。ヴェイル公爵家の名に恥じぬようにな」
父の言葉にカリナは静かに目を伏せ、「かしこまりました」と返事をする。いつかこの“名門の仮面”を剝ぎ取って、本当の自分の色を取り戻せる日が来るように――その願いを胸に抱きながら。
――こうして、“ギャラリー計画”を通じて、カリナが自分の絵を堂々と披露するための準備は着実に進んでいく。しかし、それは同時に、彼女とリースが少しずつ“反撃”の兆しを見せ始めたという証でもあった。果たして伯爵家の監視や、いつか訪れるであろうエドリックとの衝突をどう乗り越えていくのか。冷たい婚礼に閉ざされた世界に、新たな炎が確実に燃え上がり始めている――カリナはその熱を、もう決して見失わないと誓うのだった。
3-4
ステラリア家に新設されるギャラリーの準備は、少しずつ形になろうとしていた。伯爵がほぼ強引に引っ張ってきた画商や出資者、さらには社交界の名士たちが、日を追うごとに屋敷を出入りするようになり、大広間や廊下には仰々しい下見や打ち合わせの姿が散見される。リース・アルファードもまた、伯爵の“アドバイザー”として、頻繁に訪問を繰り返していた。
一見すると、それらはすべて「名家の面子を保つための華やかな企画」に過ぎない。だが、その裏ではリースとカリナ・ステラリアのささやかな“計画”も、着実に進行しつつあった。
カリナ自身の描いた絵をギャラリーに出品する――伯爵は体裁さえ整えばと容認したが、具体的な作品についてはまだ知らされていない。それでいい、とカリナは考えている。自分が描くのは形式ばかりの荘厳な絵ではない。彼女が筆を走らせる夜明けの花や、淡くにじむ空の色彩は、ステラリア家の下で強要されてきた“華やかさ”とも、“ヴェイル家の威光”ともまるで無縁の世界だ。だからこそ、堂々と胸を張れるだけの“本当の自分”を封じ込めた作品にしたい。そう強く思っていた。
もっとも、夜な夜な絵を描くのは容易ではない。夜更けに絵具の匂いを漂わせていれば、家令や侍女たちの不審を買いかねない。そこでカリナは、昼間のわずかな空き時間にもスケッチや色の試し塗りを進めるようになった。誰かが扉の外を通る気配を感じたら、即座に道具を引き出しの奥へ隠す。まるでスパイのような日々が続くが、それでも筆を握るたびに感じる心の解放こそが、彼女にとっては生きる支えでもあった。
そんなある日の午後、カリナはいつものように父の命令で来賓へのお茶を振る舞い、馬車で送り出す役目を終えた後、ほっと息をついて廊下を歩いていた。すると、曲がり角からリースが姿を見せる。彼もまた、伯爵に呼びつけられて打ち合わせをしたところらしく、やや疲れた表情だった。
「やあ、カリナお嬢様……少しだけお時間を頂けませんか? 伯爵殿のご要望を聞きつつ、具体的な展示の流れを整理していたのですが、ぜひあなたの意見も伺いたい」
そう言いながらリースは、手にしたノートを軽く掲げてみせる。タイミングを見計らったかのように家令が横切ったが、「アルファード様がお嬢様と打ち合わせをされたいとのことです」と言うと、家令はわずかに頷いて「では、応接室をお使いください」とだけ告げて去っていった。慌ただしい屋敷の空気の中にあって、二人が言葉を交わすには好都合だった。
応接室へ入ると、そこには来客用のソファが二つ向かい合うように置かれ、壁際には棚と数枚の絵画。ふだんは名だたる貴族をもてなす場所だけに、調度品が豪華で重厚な印象を与える。それでも、今日に限っては客もおらず、侍女も誰もいない。カリナはドアをそっと閉め、リースと向かい合って腰を下ろす。
「父様、またたくさん要望を出してきたのでしょう? 結局、どんな展示を望んでいるのかしら……」
リースは苦笑を浮かべながらノートを開く。
「はい、華やかさを重視して、“ヴェイル公爵家の名前にふさわしい威厳を演出せよ”とのことですね。あと、“ステラリア家の伝統も強調するように”とか。正直、形式優先の意見が多くて、なかなかまとめるのが大変です」
カリナは溜息をつきつつも、「私の絵を飾る件は……?」と小声で尋ねた。
「伯爵殿には“令嬢の作品もアクセントとして使うと良いでしょう”と伝えています。評価次第で採用を判断したいとのこと。飾る場所や作品数など、最終的には僕とあなたで決める形になりそうです」
リースがそう言ってノートのページをめくると、展示レイアウトの案がいくつも描かれている。その中の一角に“カリナの作品”と書き添えられたスペースがあった。見れば壁際に大きめのキャンバスをかけ、天井からはスポットライトを当てるような図面が引かれている。
「こんなふうに、一角をあなたの世界にしてみたいと思っているんです。仰々しい荘厳な絵ばかりじゃ息が詰まるから、あなたの淡い色彩を引き立てるようなレイアウトにしてみたくて」
それはリースの作り上げる“舞台装置”の一部かもしれない。けれど、その一部だけは伯爵やエドリックの意向を真っ向から気にする必要がない“自由な空間”になり得るのだ。イメージを膨らませるほどに、カリナの胸は高鳴る。自分の絵がこの場所に堂々と飾られ、それを観る人が少しでも何かを感じ取ってくれたら――彼女にとって、それこそが生きている意味を再発見する瞬間になるだろう。
「素敵……ありがとう、リース。こんなにも真剣に私の絵を大切に扱おうとしてくれるなんて……」
思わずこぼれた言葉に、リースは微笑み返す。
「僕の方こそ、あなたが描く世界に救われている気がするんですよ。ステラリア家やヴェイル公爵家の圧力って相当なものだし、それに負けず描き続けているあなたが、僕にはとても輝いて見える。……だから、一度きりではなく、いつか本当にあなたが自由に絵を描ける環境を作ってあげたい」
その静かな決意を聞いて、カリナは胸が熱くなる。ほんの数ヶ月前までは想像もしなかった光景――“結婚は政略でしかない”と割り切っていた頃の自分に、こんな希望が訪れるとは思わなかった。もっとも、愛のない婚礼がやがて本格的に始まれば、彼女はヴェイル家へ移り、さらに厳しい制約を強いられるだろう。それでも、このわずかなチャンスを捨てるわけにはいかない。
会話がひと段落し、二人が作業のためノートに視線を落とした瞬間――唐突に扉が開く音がして、カリナははっと顔を上げる。そこには、さほど貴族らしからぬ軽い足取りで入ってきた一人の男……エドリック・ヴェイル本人だった。
普段めったに姿を見せないエドリックが、まさかこの応接室に不意打ちのように現れるとは想定外だ。カリナとリースは即座に立ち上がり、軽く頭を下げる。エドリックはちらりと二人を見やり、あからさまに興味のなさそうな瞳で言い放った。
「フン、ここで何の話をしている。ギャラリーの件か? 父上や伯爵から、“婚礼の記念に盛大な催しをする”と聞いていたが……」
リースがあわてて説明を始める。「はい、ヴェイル公爵家のお名も借りて、ステラリア家で大きな展覧会を開催する予定でして……わたくしは、その企画の補佐を――」
ところが、エドリックは最後まで聞かずに「どうでもいい。俺には関係のないことだ」と冷ややかに切り捨てる。それだけならまだしも、カリナに向かって一歩近づき、嘲るような笑みを浮かべた。
「おまえも忙しそうだな、カリナ。まるで自分が重要人物にでもなったつもりか。俺はただの義務でここに来ただけだが――なぁ、聞いているか?」
エドリックは顎をしゃくってリースを見やる。暗に“引き下がれ”と命じているのが明白だった。リースは苦々しい表情を浮かべながら、「失礼します」と軽く一礼し、資料を抱えて部屋を出て行く。
扉が閉まると、応接室にはカリナとエドリックの二人だけが残った。彼は見るからに不機嫌そうな顔で、テーブルの上に置かれたノートを乱暴に手に取る。
「興味はないが、一応目を通してやるか……へえ、絵を展示してどうこう……そんなものに労力を注ぐとは、伯爵も暇なんだな」
投げやりな態度は変わらない。カリナの心には、怒りや悲しみがない交ぜになった複雑な感情が湧き上がるが、ここで正面から反論しても得られるものは何もない。だからこそ、冷静さを保ちつつ言葉を選ぶ。
「……ステラリア家にとっては、大切な行事なんです。ヴェイル家とのご縁を示す意味でも、父様は気合いを入れているんですよ」
すると、エドリックは“ヴェイル家”という単語にわずかに反応し、鼻で笑った。
「俺は別にステラリア家に何も期待していないがね。おまえが俺の妻になることなど、正直どうでもいい。父上の意志があるから従っているだけだ。ただし――」
突如としてエドリックの声の調子が変わる。カリナは身構えながら、一体何を言われるのかと息をのんだ。
「ただし、俺の立場を悪くするような動きはするなよ。伯爵の娘として大人しくしていればいい。屋敷の改装だのギャラリーだの、おまえに何ができる? むしろ邪魔だけはするな」
言い切ると、エドリックはノートを放り投げるようにテーブルへ戻し、踵を返して出て行こうとする。カリナは怒りを飲み込みながら、一言だけ返した。
「……あなたこそ、いったい何を求めているんですか? 私に何の感情もないのに、なぜわざわざここへ?」
彼は振り向かないまま、静かな声で言い捨てる。
「俺は義務を果たしに来ただけだ。おまえに興味はない。――以上だ」
重苦しい沈黙の中、エドリックは部屋から出て行った。残されたカリナは、震える手でノートを拾い上げる。リースが大切に描いたギャラリー案の紙が少しだけ折れ曲がっていた。じっとりと嫌な汗が背中を伝い、冷ややかな怒りが込み上げる。
(これが私の“夫”になる人……あまりにも冷たく、何も感じられない人。それでも私は、家の名のために嫁ぐしかないの?)
しかし、悔しさと同時にカリナの中で一層強くなるものがあった。リースが用意した“自由な空間”を必ず実現させたい。エドリックの冷笑に屈服するわけにはいかない。
――その夜、カリナは再び机に向かい、そっと筆を握る。エドリックと向き合うほど、父の思惑を知るほど、息苦しさが増していく。けれど、その苦しさは“色”を生み出す力にも変えられる。
(私には、私の描く世界がある。そこだけは誰にも汚されたくない)
そう胸に誓い、キャンバスに色を落とすたびに、夜明けの花が少しずつ輪郭を増していく。その筆先には、エドリックの冷たい瞳を跳ね返すような、確固たる意志が刻み込まれていた。リースが与えてくれた舞台で、この絵を堂々と披露できる日が来るならば、きっと“無彩の婚礼”にも火が灯るだろう。今はまだ小さな炎に過ぎない。だけど、必ず燃え上がる――カリナはそう信じながら、夜の闇に向かって色彩を紡ぎ続けるのである。
0
あなたにおすすめの小説

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。
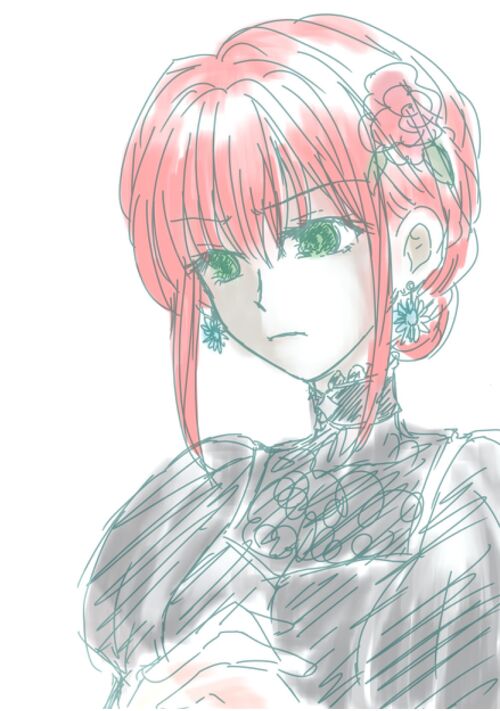
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

地味な私を捨てた元婚約者にざまぁ返し!私の才能に惚れたハイスペ社長にスカウトされ溺愛されてます
久遠翠
恋愛
「君は、可愛げがない。いつも数字しか見ていないじゃないか」
大手商社に勤める地味なOL・相沢美月は、エリートの婚約者・高遠彰から突然婚約破棄を告げられる。
彼の心変わりと社内での孤立に傷つき、退職を選んだ美月。
しかし、彼らは知らなかった。彼女には、IT業界で“K”という名で知られる伝説的なデータアナリストという、もう一つの顔があったことを。
失意の中、足を運んだ交流会で美月が出会ったのは、急成長中のIT企業「ホライゾン・テクノロジーズ」の若き社長・一条蓮。
彼女が何気なく口にした市場分析の鋭さに衝撃を受けた蓮は、すぐさま彼女を破格の条件でスカウトする。
「君のその目で、俺と未来を見てほしい」──。
蓮の情熱に心を動かされ、新たな一歩を踏み出した美月は、その才能を遺憾なく発揮していく。
地味なOLから、誰もが注目するキャリアウーマンへ。
そして、仕事のパートナーである蓮の、真っ直ぐで誠実な愛情に、凍てついていた心は次第に溶かされていく。
これは、才能というガラスの靴を見出された、一人の女性のシンデレラストーリー。
数字の奥に隠された真実を見抜く彼女が、本当の愛と幸せを掴むまでの、最高にドラマチックな逆転ラブストーリー。

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

完結 愚王の側妃として嫁ぐはずの姉が逃げました
らむ
恋愛
とある国に食欲に色欲に娯楽に遊び呆け果てには金にもがめついと噂の、見た目も醜い王がいる。
そんな愚王の側妃として嫁ぐのは姉のはずだったのに、失踪したために代わりに嫁ぐことになった妹の私。
しかしいざ対面してみると、なんだか噂とは違うような…
完結決定済み

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

偽りの愛の終焉〜サレ妻アイナの冷徹な断罪〜
紅葉山参
恋愛
貧しいけれど、愛と笑顔に満ちた生活。それが、私(アイナ)が夫と築き上げた全てだと思っていた。築40年のボロアパートの一室。安いスーパーの食材。それでも、あの人の「愛してる」の言葉一つで、アイナは満たされていた。
しかし、些細な変化が、穏やかな日々にヒビを入れる。
私の配偶者の帰宅時間が遅くなった。仕事のメールだと誤魔化す、頻繁に確認されるスマートフォン。その違和感の正体が、アイナのすぐそばにいた。
近所に住むシンママのユリエ。彼女の愛らしい笑顔の裏に、私の全てを奪う魔女の顔が隠されていた。夫とユリエの、不貞の証拠を握ったアイナの心は、凍てつく怒りに支配される。
泣き崩れるだけの弱々しい妻は、もういない。
私は、彼と彼女が築いた「偽りの愛」を、社会的な地獄へと突き落とす、冷徹な復讐を誓う。一歩ずつ、緻密に、二人からすべてを奪い尽くす、断罪の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















