4 / 4
4章
4
しおりを挟む
4-1
婚礼の準備とステラリア家のギャラリー計画が同時進行するなか、屋敷の雰囲気は日に日にあわただしさを増していた。伯爵ハロルドは、画商や出資者との交渉を続けながら、目に見えるかたちで“名家の復興”を印象づけようと奔走している。カリナ・ステラリア自身も、父の命令で貴族たちをもてなし、遠方から訪れる客人への対応に追われる日々を送ることになった。だが、その役目をこなしながらも、彼女の胸には「本当にこのまま婚礼を迎えていいのだろうか」という迷いが渦巻いていた。
エドリック・ヴェイル――彼との冷たいやり取りが続くたびに、カリナの心は“結婚”という言葉に対する嫌悪と不安を増幅させていく。婚礼パーティが行われたあの日からすでに幾月か過ぎ、形式的な儀礼はひととおり終えているはずなのに、エドリックは一向に“夫”としての情を見せない。彼が屋敷に訪れるのは義務感に突き動かされたときだけで、その際には容赦ない侮蔑の言葉を投げかけてきたり、愛人を平然と連れてくることもある。
「どうして私が、こんな相手と一生をともにしなければならないの……」
夜中、ベッドに横たわりながら、そう呟くことも珍しくなくなった。いっそ早く式を挙げて“嫁入り”が済んでしまったほうが、心の整理がつくのかもしれない。しかし、ヴェイル公爵家での生活を思えば、そこに待ち受けるのはさらなる侮蔑と無視、そして愛人の存在を公然と見せつけられる日々――考えるだけで息苦しくなる。
だが、そんな現実の暗い影と同時に、カリナの中では一筋の光が確かに育っていた。リース・アルファードが進めているギャラリー企画は、伯爵家にとってただの体面づくりに過ぎない一方、カリナにとっては「自分の絵を公に示せる」という大きな意味を持つ。夜明けの花を描いたキャンバスは完成に近づいており、彼女はさらに別のモチーフにも挑戦し始めていた。描くたびに感じる“生きている手ごたえ”――それこそが、結婚という牢獄を前にしても、自分自身を見失わずにいられる唯一の支えだった。
そんなある朝、カリナはいつになく早い時間に庭へ出た。薄曇りの空模様が、近づく秋の気配を帯びて肌をひんやりと撫でていく。結婚前の最後の季節を思うと、どこか物悲しさがこみ上げてくるが、ここで立ち止まってはいけない――そう自らに言い聞かせ、彼女は以前から気になっていた“屋敷の裏庭”へ足を運んだ。
この裏庭は使用人たちの通用路があるだけで、普段はほとんど人が立ち入らない。手入れも行き届かず、雑草が伸び放題になった区画もある。それでも、建物の影になって視線を遮れるのが大きな利点だった。ここなら、少しのあいだ筆を握っていても屋敷の者から怪しまれずに済むかもしれない――そう考えたカリナは、カバンに忍ばせてきたスケッチブックと鉛筆を取り出すと、木陰に腰を下ろした。
「……リースに見せるには、もう少しラフなデッサンも描いておきたいわね」
彼女はそう呟きながら、雑草と蔦が絡まった古い石壁に目を向ける。朝の淡い光に照らされた蔦の葉は、まだ夏の名残を宿しながらも、ところどころ黄変しかけている。そのわずかな色合いの変化が、カリナには儚く美しく思えた。丁寧に輪郭を取り、葉脈の走り方をスケッチするうちに、彼女の心は無心の境地へと溶け込んでいく。
しばらく描き続けていると、遠くで聞き慣れた足音がした。カリナは慌ててスケッチブックを閉じかけるが、そこに現れたのは予想外の人物――なんと母だった。伯爵の妻として長らくステラリア家を支えてきた彼女は、病弱というわけではないものの、普段はあまり人前に出ることを好まず、常に夫の威光に遠慮している印象があった。
「お母様……どうして、ここに?」
母は一瞬足を止め、少し驚いたような表情を浮かべたが、すぐに穏やかな微笑みをカリナに向けた。
「たまには静かに庭を散歩したくてね。あなたこそ、こんな裏庭で何をしているの?」
カリナは動揺を抑えながら、スケッチブックをそっと隠すように抱え込む。母は昔から伯爵の言うことに絶対服従しており、彼女に夢を打ち明けたところで理解してくれるかどうか分からない。それでも、母の瞳にはどこか優しい光が宿っていて、カリナは意を決して切り出すことにした。
「私、絵を描いていたの。……子どもの頃からずっと好きで、でも婚約話が決まってからは、父様に“無駄なことをするな”と叱られるばかりで……」
母は黙って耳を傾け、そっとカリナの手元に目をやる。スケッチブックに残った筆跡や鉛筆の削りかす、微妙に指先に付着した薄い絵具の痕跡。すべてが彼女が“何をしてきたか”を物語っている。
「そう……あなたは、絵を描きたいのね」
母の声は低く、しかしどこか安堵にも似た響きを含んでいた。それは伯爵の妻として長く生きてきた彼女の“諦め”とも、“遠い憧れ”ともつかない色合いを帯びていて、カリナの胸が苦しくなる。
「お母様は……父様に従うしかなかったの? 自分のやりたいことは、本当になかったの?」
思わず踏み込んだ質問をしてしまい、カリナは少し後悔する。だが、母は驚くほど穏やかに笑って首を横に振った。
「私の時代には、選択肢なんてなかったわ。伯爵に嫁ぐことも、華やかな場で“理想の夫婦”を演じることも、すべて当然の運命だと思い込まされてきた。でもね、あなたは……私よりもずっと強い子だと思うの。描きたいなら、描いてもいいんじゃないかしら」
カリナは、その母の言葉に思わず胸が詰まる。ステラリア家の母として、夫ハロルドの厳格な支配を受けながらも、最後に見せてくれたのは娘への一抹の助力だったのかもしれない。
「ありがとう……でも、お母様がこうして許してくださっても、父様やエドリック様はきっと……」
母は娘の言葉をそっと遮り、静かに続ける。
「この世には“許される選択”もあれば、“許されない選択”もある。けれど、あなたがどうしても手放せないものがあるなら、諦めないで。私が言えるのは、それだけ……」
言い終わると、母は軽く目を伏せて一礼し、「あなたが戻るときのために、玄関のほうを見ておくわね」と囁いて去っていった。まるで、少しでもカリナに“描く時間”を与えてあげようという気遣いだったのかもしれない。
残されたカリナは、心の中に小さな感謝と、母に向けた切なさが入り混じるのを感じる。誰にも干渉されない裏庭の一角で、あらためてスケッチブックを開き、今度は蔦の葉だけでなく、その向こうに広がる空の色も微妙なニュアンスで描き始める。そこには「結婚」「家名」「義務」のどれも存在しない、ありのままの美しさがあった。
――こうして、カリナはようやく“家の女性”としてしか存在できない母の心のうちを、ほんの少しだけ知ることができた。彼女もまた、いつかは夢を見たかもしれないし、それを伯爵家の制度の中で失ったのかもしれない。だからこそ、「あなたは諦めないで」と言ってくれたのだ。
(お母様のためにも、私がこの壁を壊してみせる……)
婚礼が迫る日々の中で、カリナの決意は確固たる形を帯びつつある。エドリックから向けられる冷淡さも、父ハロルドが求める“名家の体裁”も、いつかは乗り越えねばならないだろう。そうしなければ、彼女は“本当に大切なもの”を失ったまま、形ばかりの結婚を余儀なくされてしまう。
(私は自分の手で色彩を取り戻す。この婚礼がいくら“無彩”でも、いつか色を灯してみせるんだ)
その意志こそが、カリナにとって“新たな旅立ち”の合図だった。結婚式は不本意にも近づいてきているし、ヴェイル公爵家での生活は想像を絶する閉塞感に満ちているかもしれない。しかし、少なくとも今のカリナは、自分の意志で筆を握り、自分の目で世界を見つめ、描き留める力をまだ失ってはいない。家の伝統も、夫となるはずの男の冷酷さも、乗り越える手段を模索しながら、彼女は一歩ずつ歩み始める。
――遠くの空に一筋の光が差し込む。曇天の下でも、雲の切れ間から日差しがこぼれるように、カリナはこの先を信じて筆を走らせた。手の中に描き続ける“色彩の未来”は、今まさに幕を開けようとしている。自分で立ち上がり、行動すれば、きっと世界は変わるに違いない――そう確信できるほどの力が、彼女の胸には満ち始めていたのである。
4-2
秋の訪れを感じさせる涼しい風が、ステラリア家の庭を揺らし始めた頃――屋敷内では、ギャラリーと結婚式の準備がより一層本格化していた。伯爵ハロルドは招待客のリストを増やし、さらに画商や芸術家を頻繁に呼びつけては「名家の威光にふさわしい展示」を厳しく問いただしている。家令や使用人たちも、朝から晩まで屋敷中を走り回り、新たな調度品の搬入や部屋の模様替えに追われていた。来るべき式典――それは本来ならばカリナ・ステラリアにとって生涯最高の晴れ舞台であるはずだが、少なくとも彼女の胸には、晴れやかな感情は微塵も芽生えていない。
一方、伯爵の“アドバイザー”として招かれているリース・アルファードは、あくまでも仕事の顔を保ちながら、カリナとの“秘密の計画”も着々と進めていた。彼女の描きかけの作品をいかにギャラリーへと紛れ込ませるか、伯爵に疑念を持たせず、かつステラリア家の客人が「面白い」と思うような演出をどう組み込むか――そのための入念な打ち合わせは、もはや日課といえるほど頻繁に行われている。もっとも、伯爵や家令の前では「展示テーマの最終確認」「装飾の配置」などと形式的に説明し、肝心の“カリナの絵”についてはあいまいな表現で済ませていた。
ある日の午後、カリナは屋敷の控えめな応接室でリースと顔を合わせていた。父ハロルドは別の部屋で大事な客をもてなしており、しばらく戻る気配はない。侍女長も廊下の手配に忙しく、ここ数分間はふたりきりで話すことができる貴重な時間となっていた。
「リース、あの……キャンバスの絵、もう少しで完成しそうなの。夜明けの花をメインにしたものと、今度は昼下がりの庭をイメージして描いたものの、二点。どちらか一方だけでも、ギャラリーに出せないかしら」
カリナは控えめに小声で話しながら、さりげなくドアのほうに目をやる。いつ誰が入ってくるか分からない状況に、心臓が高鳴るのを感じる。それでも、自分の絵を人前に出すという行為が、どれほど大きな一歩かを思うと、彼女の瞳にはわずかな決意の色が宿っていた。
リースは穏やかな笑みを浮かべ、カリナが差し出すスケッチの断片に目を落とす。そこには花びらや葉の重なり、そして柔らかな光と影の表現が繊細なタッチで描かれている。
「すごくいいですね。あなたの絵は、見る人を優しい気持ちにさせるんですよ。僕としては二点とも飾りたいくらいですが……伯爵殿の反応が少し怖いですね。せめて一枚は確実に配置したいけれど」
伯爵の好みや期待は、ギャラリー全体に“荘厳な雰囲気”や“格式”を求めるものだ。淡く柔らかい色彩を持つカリナの絵は、明らかにそれとは対極にあると言っていい。だが、それこそがむしろ大事なポイントだ――リースはそう考えている。「硬い絵画ばかりが並ぶより、ひとつ異質な作品があることで、むしろ来客の興味を惹けるはず」。この提案を伯爵に飲ませるため、リースは毎日のように展示レイアウトの案を修正し、「若い感性の作品が1枚あることでアクセントになる」と説明している。
「……父様を納得させるのは難しいかもしれないけれど、やるだけやってみるわ。私ももう後には引けないもの」
カリナはそう言いながら、リースが広げている資料の中に目を落とす。そこには展示壁面の配置図が細かく記されており、一角がまだ未定のまま空白になっていた。まるで、カリナの作品が差し込まれるのを待っているかのように思えて、彼女の胸は少し高鳴る。
話をまとめ終えたところで、ふと扉の外から足音が聞こえた。すぐに二人は打ち合わせの資料を整え、いつ伯爵や家令が入ってきても不自然にならないように備える。だが、応接室に現れたのはカリナの母だった。前日、裏庭でささやかな言葉を交わしたばかりだが、こんな場で母と対面するのは珍しい。
「お母様……どうなさったの?」
母は微笑を湛えたまま、娘とリースに視線をやる。伯爵夫人らしい端正な装いではあるが、どこか落ち着かない面持ちを見せていた。
「伯爵がもうすぐこちらへ見えるとのことよ。大事なお客様をお見送りして、応接室でギャラリーについての話をなさるんですって。アルファード様、しばらくここでお待ちになっていただけるかしら」
リースが礼儀正しく頭を下げると、母はカリナにだけ聞こえるような小さな声で続けた。
「それから、カリナ……もしものときは“私のせい”にして構わないわ。あなたが描いた絵を飾る件も含めて、私から伯爵にそれとなく伝えてみます。父親の怒りを一身に受けるのは、もう慣れているもの」
カリナはその言葉を聞いて、一瞬言葉を失う。母が伯爵に逆らうなど、今まで想像もしなかった。常に夫の後ろで大人しく微笑んでいる女性という印象しかなかったのに――だが思えば、あの日裏庭で交わした会話で、母ははっきり「諦めないで」と言ってくれたのだ。
「お母様……でも、それでは……」
「大丈夫。たとえ怒りを買っても、あなたまで巻き込ませないわ。私にとってはそれがせめてもの……親としての役目だと思うの。エドリック様のことも、家のことも、全部背負わされているあなたには、これくらい手を貸したい」
母がそう言い終わるか終わらないかのうちに、廊下から伯爵ハロルドの声が聞こえてきた。どうやら客人を送り出して、次なる打ち合わせのためにここへ向かっているらしい。母は瞬時に表情を引き締め、カリナとリースに無言で一礼すると、すぐさま部屋を出て行った。
少しして伯爵が応接室へ入ってくると、リースはいつものように流れるような口調で作業の進捗を報告し、展示プランの最新案を示した。伯爵は地図やメモをなぞりながら、あれこれと細かい要望を述べ始める。
「ここには大ぶりの歴代肖像画を飾れ。あちら側には公爵家ゆかりの絵を借りたいから手配しろ。……ステラリア家の令嬢の作品? ああ、カリナの……そういうのは端のコーナーにでもまとめておくように。無理に強調する必要はない」
カリナは伯爵の冷淡な物言いに胸を突かれるが、今ここで反論すれば逆効果だろう。リースも同様に察しているのか、「はい、承知しました。あまり大きく扱わずとも、若い感性の作品が加わることで華やかさが出るかと思います」と上手くまとめる。
ところが伯爵は、カリナの母が自分に進言したであろう話を思い出したのか、急に険しい顔で娘を見やる。
「そうだ、カリナ。お前の母が、お前の描いた絵をもう少し目立つ場所に飾れと言ってきたが、本気か? お前は自分の腕前にそんな自信があるのか?」
母の一言が、早くも伯爵の癇に障ったようだ。伯爵はあからさまに疑いの目を向け、リースにも視線を投げる。
「アルファード氏、あまり甘い考えを吹き込まないでくれよ。未熟な作品を無理に人前に出して、ステラリア家の評判を落とすわけにはいかんのだ」
リースは一瞬ぎくりとした表情を浮かべるが、すぐに平静を取り戻す。
「もちろん、伯爵殿のお考えはごもっともです。もし作品が不十分な出来であれば、むしろこちらが責任を持って差し止める所存です。ただ、一見して“未熟”に見える作品でも、若さゆえの新鮮な魅力があることも確かですし、見る方によっては好評を得るかもしれません。それを完全に無視してしまうのは、少々もったいないかと……」
伯爵はしばし沈黙し、険しい顔のまま唸るように息をつく。カリナは立ち上がり、一歩踏み出して父の前に頭を下げた。
「……お父様。失礼を承知で言わせてください。私ももう子どもではありません。結婚を控えている身として、いずれはヴェイル家での社交に挑むことになります。そこで“自分の描いた絵”を守り抜くことも含め、私なりの挑戦をしてみたいのです。もしそれで失敗したなら、すべて私の責任として甘んじて受けます」
これまで幾度となく伯爵に従順な態度しか示してこなかったカリナが、ここまで堂々と言い切るのは初めてかもしれない。伯爵は驚いたように眉を上げ、娘の表情をまじまじと見つめる。だが、その口調には以前ほどの勢いがない。「ふん……そこまで言うなら、お前の母に免じて少しだけ自由を与えてやろう。だが、もし恥をかけば、お前の責任だと心得ろ」
父の言葉は相変わらず冷たいが、それでも“完全拒否”ではなかった。ほんの小さな一歩。カリナはそのチャンスを手に入れたことを実感する。隣で見守っていたリースも、こっそり安堵の表情を浮かべていた。
伯爵がさらに口を開き、「今週末までに作品を仕上げてみろ。そこから判断して配置場所を決める」と告げると、打ち合わせは唐突に終了した。短いながらも、いくつかの障壁を越えた手応えがカリナの胸に広がる。この道は依然として険しいが、母とリース、そしてわずかながらの自分自身への信頼があれば前に進める気がした。
その夜、カリナは自室の机に向かい、慣れた手つきで筆を握る。昼下がりの庭をモチーフにした絵は、あと少し色の調整が必要だ。葉の陰の色味を深くし、光の当たる部分をほんの少し明るくする。それだけで絵がぐっと生き生きとする――そんな確信を得ながら、カリナは夜も更けるのを忘れて筆を走らせた。
(絶対に、恥をかかせるような仕上がりにはしない。私はここで諦めるわけにはいかないんだから)
伯爵家の寝静まる深夜、屋敷の外では秋の虫がかすかな音を響かせ、空には雲間から星が瞬いている。まるで、カリナの小さな“反逆”を見守るかのように――彼女はそう感じた。いつかこの夜闇が明ける頃、完成した作品がギャラリーに堂々と飾られる日が来る。エドリックの冷笑や、伯爵の支配的な態度を跳ね返し、母の秘かな期待に応える。その未来のために、カリナはすべてを懸けて絵筆を動かし続けるのだ。
――何度も塗り重ねるうち、キャンバスの景色はゆっくりと“生きた”表情へ変化していく。かつてのカリナが持っていた純粋な喜びと、今のカリナが抱える強い意志が、そこに混ざり合っているようにも思える。このまま夜明けを迎えても構わない――そう思えるほどの集中力をたたきつけながら、彼女は自分の未来と向き合い続ける。冷たい婚礼の檻に閉じ込められるだけで終わらない、己の“色彩の物語”を、自らの手で描くために。
4-3
カリナ・ステラリアが描きかけのキャンバスに向き合い始めてから数日が経過した。伯爵ハロルドは「週末までに作品を見せろ」と言い残し、ギャラリーの準備を巡って画商や有力者との交渉に奔走している。屋敷にはいつも以上に人の出入りが激しく、カリナのもとへやってくる使用人や侍女たちも、落ち着いた会話をする余裕などほとんどない。
しかし、そうした慌ただしさは、かえってカリナにとっては都合が良かった。誰もが多忙を極めるからこそ、彼女は昼間のわずかな隙間や深夜の静寂を縫って絵筆を握ることができる。昼下がりの庭をイメージした絵も、夜明けの花を描いた絵も、いよいよ仕上げの段階に入っており、「あともうひと押しで完成」という実感が湧き始めていた。
カリナの部屋の扉をノックする音が聞こえたのは、ちょうど午後の日が傾き始めたころである。机いっぱいにスケッチブックや絵具を広げていたカリナは、慌ててそれらを脇へ寄せ、扉のほうへ注意を向けた。
「はい……どなたですか?」
控えめに答えると、扉の向こうから小さな声がした。
「私よ、カリナ。入ってもいいかしら」
母だった。ここ数日、カリナの母は伯爵の目を盗むようにして、娘の様子を気にかけている。裏庭で出会った朝以来、母は以前とは打って変わって“娘の味方”を積極的に買って出ようとしているようだった。
カリナが「どうぞ」と声をかけると、母はそっと部屋へ入り、必要以上に周囲を警戒するかのように扉を閉める。
「お父様は、まだ来賓の相手をしていて、しばらく戻らないでしょう。……もしかして、絵を描いていたのね?」
カリナの視線を追って、母は机の端に置かれたスケッチブックや、わずかに絵具の色が付いた筆を見つめる。その目は優しげで、どこか懐かしさも宿していた。
「ごめんなさい、こんなことばかりしていて……でも、どうしても仕上げたいの。父様に“週末まで”と言われてから、ずっと焦っていて……」
母は首を横に振り、穏やかに微笑む。
「謝ることなんてないわ。むしろ誇りに思う。こんなにまで真剣に何かに打ち込んでいるあなたの姿を見たのは、もしかしたら初めてかもしれないわね」
それは伯爵夫人として生きてきた母の本音であり、同時にカリナへの賛辞でもあった。かつて彼女自身も、何かしらの夢を抱いていたのだろうか――その問いはカリナの胸にかすかな痛みを伴う。母は続けて小さな包みを差し出す。
「これ、昔あなたが使っていた古い筆だけど、私が奥の物置から見つけたの。新しいものと比べたら使い勝手は悪いかもしれないけれど……もし必要なら使ってちょうだい」
包みを開くと、懐かしい記憶が蘇るような淡い青の筆が数本入っていた。毛先こそ少し痛んでいるが、子どもの頃にカリナが好んで使っていた道具だ。指でそっとなぞれば、その頃の喜びや夢中になっていた感覚が手の中に戻ってくるようだった。
「ありがとう、お母様……」
母はそれだけ言うと、もう一度室内を見回してから、こっそりカリナの手を取る。
「あなたが仕上げた絵、私も早く見たいわ。伯爵が何と言おうと、私はあなたを応援しているの。あの人も、“もし失敗したら娘の責任”なんて言い方をしているけれど、内心はどうなのかしら……」
そこに母の遠い目が重なる。伯爵に隷属しているように見える彼女も、夫の本心を読みきれない部分があるらしい。カリナは唇を噛みながら、淡々とした声で返す。
「きっと父様は、心から私を応援しているわけじゃないと思うわ。家の面子を損なわない程度に、私を利用できればそれでいい……そんな感じ」
「それでも、あなたは諦めないんでしょう?」
母の問いかけに、カリナははっきりと頷く。
「ええ。もう、引き返せないもの。後はやるしかない……リースも、私の作品を絶対に飾るって言ってくれているし、お母様も応援してくれている。ならば私、失敗を恐れて止まるわけにはいかないわ」
その言葉に、母は静かに微笑み返す。まるで「それでこそ私の娘」とでも言わんばかりの表情だ。短い会話を終えると、母は「あなたの父様が戻る前に部屋を出るわね」と言い残して去っていった。
戸が閉じられ、足音が遠ざかると、部屋には再びカリナ一人。新たに手に入れた古い筆を見つめながら、彼女は軽く息をつく。
(今の私には、これ以上迷う余地なんてない。描きたいものを描いて、伯爵を――そしてヴェイル家を――納得させるしかないんだわ)
その晩、カリナは寝室の灯りを落としてから、机上のランプだけをつけて筆を握る。一枚目の“夜明けの花”はほぼ完成しており、今夜は“昼下がりの庭”を仕上げる予定だ。父が“週末まで”と期限を区切った以上、もう一日の猶予も残されていないかもしれない。
緊張の汗が手のひらを湿らせる。それでも、筆をキャンバスに触れさせるたびに、一瞬一瞬が研ぎ澄まされていくような快感を覚える。まだ誰にも見せていない“私だけの世界”――その核心へと踏み込む感覚があるのだ。
葉の輪郭をもう少し鮮明にする。木漏れ日の射す角度を意識しながら、光の差し込み方を微調整する。筆先に載る絵具の量に気をつけて塗り重ねるうち、緑の中にかすかな黄金色が浮かび上がってくる。まるで、本物の太陽光がそこに宿ったような錯覚に襲われ、カリナは一瞬呼吸を止めた。
(こんなにも……美しいものを、生み出せるんだ)
深夜、時計が一巡りしようとするころ、ようやくカリナは筆を置く。キャンバスに広がるのは、生き生きとした昼の庭の一瞬を封じ込めたかのような世界。息を呑むほど穏やかで、それでいてどこか力強い光を放っている。思わず「ああ……」と声が漏れた。
満足したと同時に、これで終わらせてはいけないという衝動も胸に湧く。明日の早朝、もう一度見直して、微調整できるところがあれば手を加えよう――そう考えつつ、カリナは慎重に道具を片付け、キャンバスを布で覆って椅子を立った。
翌朝、夜が明けきらないうちに起床したカリナは、机に向かい、ほとんど無意識のままに最後の筆を走らせた。ほんの数筆だが、そこに“決定的な輝き”が加わったように感じる。
「これで……完成」
すぐに侍女たちが朝食の準備を知らせにやってくる。カリナはキャンバスを隠すように絹布をかけ直し、鏡の前で身なりを整えた。ドレスを着て髪を結い上げるあいだも、胸の奥は早鐘を打っている。父がどんな言葉を浴びせようと、エドリックやヴェイル家がどんな顔をしようと――この絵だけは、守り抜く。
食卓に着くと、すでに伯爵は座っていた。機嫌が良いのか悪いのか、端正な顔立ちにまったく感情が読めない。だが、その低く威圧的な声がカリナの耳に届く。
「今日の午後、画商たちが揃う。お前の作品をここで見せてもらおう。もし陳腐なものなら、いくら母親がかばおうと関係ない。即刻却下だ。分かったな」
テーブルに運ばれるパンとスープの香りが漂うが、カリナは食欲よりも強い緊張感を抱える。とはいえ、正面から怯んでは始まらない。
「……かしこまりました。午後にお見せします。ご判断はお任せしますが、私は全力で描きました。それだけは信じていただきたい」
父が言葉を返すことはなく、無言でナプキンを置いて席を立つ。一触即発の空気を残して、広い食堂には母と使用人が立ち尽くすばかりだった。
(ここからが正念場ね。もう、どんな結果になろうと逃げるわけにはいかない)
朝食を終えたカリナは、胸を締めつけるような感覚を抱えながら自室へ引き返す。キャンバスにかけられた布をそっとめくり、改めて絵を見つめる。夜明けの花と昼下がりの庭――二枚の絵は、彼女自身の“夢”と“決意”を詰めこんだ大切な分身だった。
もし伯爵が「展示には不適切だ」と言えば、すべてが水泡に帰すかもしれない。だが、たとえそうなったとしても、カリナはもう二度と筆を捨てたりはしないだろう。ここまで絵にかけた情熱は、彼女を確かな意志へと導いている。結婚という形の冷たさも、エドリックの愛人が嘲笑するような日々も、乗り越える方法はきっとある――そう信じるための力が、これらの作品には宿っているからだ。
(お父様は何を言うかしら。リースはどう動いてくれる? お母様はどんな表情で見守ってくれるの? ……そして、エドリック様は?)
さまざまな思いが渦を巻く中、カリナは絵を大切に梱包する準備を始める。間もなく画商や出資者たちが集まる“審判の場”が待ち受けているのだ。ステラリア家の廊下は、すでに朝の光が差し込み、出入りする人々の足音が交差している。その雑踏の中心へ向かうのは容易ではない。けれど、もう足を止められない――そう自分を奮い立たせながら、彼女は意を決して扉を開いた。
――こうして、カリナが大切に育んできた二枚の絵は、いよいよ世に出る運命を迎えようとしている。果たして伯爵はどんな評価を下し、画商たちは何を思うのか。エドリックが冷たい目で見下ろそうとも、彼女の決意は揺るぎない。薄暗い婚礼の道を照らす“自分だけの光”を掴み取るために、カリナは全身で立ち向かう覚悟を固めるのだった。
4-4
カリナ・ステラリアが丹精を込めた二枚の絵――“夜明けの花”と“昼下がりの庭”――その行方を決する瞬間が、ついに訪れようとしていた。週末の午後、伯爵ハロルドは画商や出資者、さらには芸術家を名乗る何人かを屋敷に集め、一足先にギャラリーの見取り図や展示候補の作品を披露する会合を開いている。今回の集まりは完全な“内覧”というわけではなく、あくまでも「正式なお披露目に先立つ意見交換」が目的らしい。もっとも、その実態は伯爵にとって「後々の投資を狙うためのデモンストレーション」に近く、彼は終始上機嫌でゲストたちと談笑を続けている。
大広間には、まだ額に収められていない大小のキャンバスがいくつも運び込まれ、その合間にステラリア家に伝わる古い肖像画が置かれている。壁には展示予定の説明書きや飾り付けの設計図が貼られ、招かれた人々はそれを品定めするように眺めていた。リース・アルファードもまた、資料を片手に会場を行き来し、伯爵からの質問や要望に的確に応じている。そんな熱気に包まれた場所へ、カリナはそっと足を踏み入れた。
いつもなら遠目に見守るだけの立場だった彼女だが、今日は大切な“勝負の日”である。抱きかかえるようにして部屋へ持ち込んだ二枚の絵は、まだ布で覆われており、その正体を知らない人々が興味深げに視線を投げかけてくる。「あれはなんだ?」「ステラリア家の新作か?」――そんな囁きが聞こえるたびに、カリナの心臓は嫌でも高鳴ったが、それを表情には出さないよう、必死に呼吸を整える。
「カリナ、お前も来たか。ちょうどいい、皆の前で作品を見せてもらおうか」
伯爵の力強い声が大広間に響いた。彼は客人たちと話をしていたが、カリナの姿を見つけるや否や、その視線を鋭く向けてくる。周囲も「あれが噂の“伯爵令嬢の作品”か」「まだ若いのだろう?」などと興味深そうだ。一方、リースは落ち着いた表情を保ちつつ、視線だけでカリナを励ましている。
「……失礼いたします。父様のご指示どおり、週末までに仕上げましたので、本日お持ちしました」
そう告げると、カリナは胸の奥で“意志”を奮い立たせるかのように布の端をつかんだ。人々の視線が集まる中、ゆっくりとそれをめくる――まずは一枚目、“夜明けの花”。淡い光の中で白い花が開きかけている情景が、ぼんやりと幻想的に描かれている。塗り重ねられた柔らかな色彩は、見る者の目をすべるように誘い込み、静かな朝の息吹を感じさせた。
「あら……これはまた珍しいタッチだな」 「ずいぶん優しい色づかいですね。貴族の絵といえば、もっと豪奢なものを想像していましたが……」
周囲からは様々な声が上がる。中には「もう少し迫力が欲しい」と難癖をつける者もいれば、「意外な魅力を感じる」と興味を示す者もいる。伯爵は客人たちの反応を一瞥していたが、特にリアクションを示さず、次の絵を見るように顎でカリナを促した。カリナは一度深呼吸し、二枚目――“昼下がりの庭”――の布を外す。こちらは青々とした草木の合間から漏れる日差しが、優しくも力強いコントラストを生み出していた。太陽の光が、緑の葉を透かして黄金色の輝きを帯びている。遠くに見える花壇には小さな花々が点々と配され、かすかな風の動きまで想像できるようだった。
「こっちの方がさらに面白いな。光の当たり方が巧みというか……」 「この柔らかいタッチ、なかなか貴重だ。完成度も意外と高いかもしれんぞ」
今度は肯定的な声が比較的多く、カリナは内心でほっと胸を撫で下ろす。もちろん、全員が好評価というわけではなく、「あくまで“素人にしては”の域だろう」「伯爵家の名を冠して飾るには地味だ」という声も聞こえてくる。しかし、完全に酷評というほどでもない。むしろ、この場にいる人間の中には、本当に興味をそそられたらしく、絵に顔を近づけて色彩の重なりや筆使いを観察する者もいる。
「ふん……どうだ、皆の意見は」
伯爵が客人たちに問いかける。画商の一人が、一歩前に出て言葉を継いだ。 「伯爵さま、正直に申し上げて、技術的にはまだ荒削りな部分も感じます。けれど、この柔らかなタッチと自然光の表現には、確かに若い感性の魅力がありますね。格式ばった作品と組み合わせれば、お客様の目を惹く一角になるかもしれません。もちろん、大々的に“目玉”として売り出すにはやや力不足かと……」 それでも決して悪い評価ではない。むしろ、こうして“新しい風”として期待を示すあたり、画商としては前向きな姿勢といえるだろう。伯爵は腕を組んでいたが、どうやらこの意見を重視しているようだ。
「なるほどな……アルファード氏、どう思う。展示のアクセントになるという話だが」 リースは、待ってましたとばかりに落ち着いた声で答える。 「私も同感です。ステラリア家やヴェイル公爵家の荘厳な作品ばかりでは、どうしても重苦しい印象になる可能性があります。そこに、この瑞々しい情景を差し込むことで、メリハリが出ます。若い女性ならではの繊細さを見いだす方も多いでしょう」 周囲がそれに頷きはじめると、伯爵はしばし考え込むように無言で絵を睨む。カリナは緊張で呼吸が浅くなりかけていたが、ここで下手に口を挟むと逆効果だ。母もやや離れた場所から見守っているようで、視線を合わせたとき、うなずくように微笑み返してくれた。
「……まぁいい。せいぜい“家の恥”にならない程度に飾っておけ。画商殿や客人たちが言うように、多少の新味にはなるかもしれん」 伯爵の言葉は素っ気ないが、少なくとも“却下”ではない。大広間に軽い安堵の空気が漂い、カリナは全身の力が抜けそうになるのをこらえた。リースの目は微かに笑みを含んでいる。数日前まではこの場にすら出せず、まして飾ることなど夢のまた夢だったのだ。それを思えば、伯爵が渋々ながらも「飾ることを許可した」のは大きな前進と言える。
「よかったわね、カリナお嬢様。これであなたの絵をギャラリーに……」 耳元で侍女の一人が囁く。カリナはぎこちなく微笑み返し、「ありがとうございます……」と小声で答えた。本当なら跳び上がるほど嬉しいはずなのに、エドリックの存在を思い出すたび、どうしても心が晴れきらない。結婚を控えた彼は今日も姿を見せておらず、公爵家からの使者すら来ていない。伯爵が奮闘して“名家の力”を示そうとしているのも、エドリックが関心を示さない限り、何の意味があるのか――そんな疑問が頭をもたげる。
「それにしても、エドリック殿はずいぶんと冷淡なものだな。結婚前の娘婿なら、こういう機会にも顔を出してしかるべきだろうに」 周囲の画商や貴族たちの一部が、そんな噂話をひそひそと交わしているのが聞こえる。伯爵はそんな声には耳を貸さず、あくまで「ステラリア家が主体」であるかのように会を進める。カリナはこの成功を素直に喜びたい気持ちを抑え、少しだけうつむいたまま胸の奥で言葉にならない悔しさを噛みしめていた。自分の絵が展示を許されたのは良いが、これで婚礼やヴェイル家との関係が好転する保証などどこにもないのだ。
それでも、母が微笑み、リースがさりげなく目で「大丈夫ですよ」と合図を送ってくれる。カリナは二人の存在に救われる思いで、周囲の貴族たちに向かって一礼した。客人たちも「伯爵令嬢が描く絵とは面白い」「これは意外に見応えがあるかもしれん」と口々に感想を述べながら散っていく。伯爵は「まだ若いからな。これから鍛えればそれなりに使い物になるやもしれん」などと、まるで我が子というより部下を評価するような言葉を漏らす。それでも“展示決定”という事実は大きかった。
こうしてカリナの二枚の作品は、正式にステラリア家のギャラリーで飾られることになった。だが、同時に彼女の結婚へ向けた準備はさらに加速していく。式典の時期や招待客の選定、そしてエドリック側からの指示もいずれ飛んでくるだろう。それを思うと、展示の成功が「束の間の光」に過ぎないのではないかという不安が頭をもたげる。冷たい婚礼は避けられないのかもしれない――けれど、それでも、カリナは自分の色彩をあきらめたくない。
会合が終わり、大広間から客人たちが続々と退出するなか、リースがカリナのそばへ寄ってきた。 「お疲れ様でした。ひとまず、あなたの絵はここで日の目を見ることになりますね」 「ええ……すべてリースのおかげよ。本当にありがとう。父様が取り下げると言い出さないうちに、早く額装をしてしまわないと」 カリナが半ば冗談めかして言うと、リースは柔らかな笑みを返す。 「ええ、準備なら任せてください。こちらでしっかり保管し、会期までに何があっても大丈夫なようにします。それから……展示当日までの間に、もしも伯爵が難癖をつけてこようとも、僕たちでなんとか防ぎましょう」
頼もしさと同時に、カリナは胸の痛みも感じる。リースがここまで協力してくれるのは嬉しいが、彼自身もステラリア家のことに深入りしすぎれば、いつか父やヴェイル公爵家から罰を受けるかもしれない。それでも彼は一歩も引かないつもりのようだった。母が遠巻きに見守る中、カリナはぎこちなく微笑みつつ「ありがとう、私も頑張る」とだけ返す。
――こうして、カリナは一つの壁を越えた。伯爵の前に作品を差し出し、たとえ軽んじられてもなお、正式に展示を許されたのは大きな前進だ。だが、未来はまだ霧の中。婚礼の日は刻一刻と近づいている。エドリックの冷たさは相変わらずで、愛人の存在も依然として公然の秘密のまま。カリナの絵がギャラリーで称賛を浴びようとも、その先に待ち受ける運命を覆せる保証など何一つない。
それでも――だからこそ、カリナは筆を置かない。父から与えられたわずかな隙を突いてでも絵を描き続けようと思う。いつか、この“無彩”の婚礼を燃え上がらせ、形だけの夫婦関係を嘲笑う瞬間を手に入れるために。リースという協力者や、母のひそかな支えを力に変えて、彼女はさらに強くなる。たとえヴェイル公爵家の門が冷たく閉ざされていようとも、そこに鮮やかな色彩を灯す方法を探し続けるのだ。
――そんな決意を胸に、カリナは改めてキャンバスを見つめる。夜明けの花も、昼下がりの庭も、自分の内なる希望と意志を象徴する大切な存在だ。どんなに伯爵やエドリックが冷たい態度をとろうとも、絵を描くことだけは奪わせない――そう強く心に刻みながら、カリナは微笑みを浮かべて大広間を後にするのだった。
婚礼の準備とステラリア家のギャラリー計画が同時進行するなか、屋敷の雰囲気は日に日にあわただしさを増していた。伯爵ハロルドは、画商や出資者との交渉を続けながら、目に見えるかたちで“名家の復興”を印象づけようと奔走している。カリナ・ステラリア自身も、父の命令で貴族たちをもてなし、遠方から訪れる客人への対応に追われる日々を送ることになった。だが、その役目をこなしながらも、彼女の胸には「本当にこのまま婚礼を迎えていいのだろうか」という迷いが渦巻いていた。
エドリック・ヴェイル――彼との冷たいやり取りが続くたびに、カリナの心は“結婚”という言葉に対する嫌悪と不安を増幅させていく。婚礼パーティが行われたあの日からすでに幾月か過ぎ、形式的な儀礼はひととおり終えているはずなのに、エドリックは一向に“夫”としての情を見せない。彼が屋敷に訪れるのは義務感に突き動かされたときだけで、その際には容赦ない侮蔑の言葉を投げかけてきたり、愛人を平然と連れてくることもある。
「どうして私が、こんな相手と一生をともにしなければならないの……」
夜中、ベッドに横たわりながら、そう呟くことも珍しくなくなった。いっそ早く式を挙げて“嫁入り”が済んでしまったほうが、心の整理がつくのかもしれない。しかし、ヴェイル公爵家での生活を思えば、そこに待ち受けるのはさらなる侮蔑と無視、そして愛人の存在を公然と見せつけられる日々――考えるだけで息苦しくなる。
だが、そんな現実の暗い影と同時に、カリナの中では一筋の光が確かに育っていた。リース・アルファードが進めているギャラリー企画は、伯爵家にとってただの体面づくりに過ぎない一方、カリナにとっては「自分の絵を公に示せる」という大きな意味を持つ。夜明けの花を描いたキャンバスは完成に近づいており、彼女はさらに別のモチーフにも挑戦し始めていた。描くたびに感じる“生きている手ごたえ”――それこそが、結婚という牢獄を前にしても、自分自身を見失わずにいられる唯一の支えだった。
そんなある朝、カリナはいつになく早い時間に庭へ出た。薄曇りの空模様が、近づく秋の気配を帯びて肌をひんやりと撫でていく。結婚前の最後の季節を思うと、どこか物悲しさがこみ上げてくるが、ここで立ち止まってはいけない――そう自らに言い聞かせ、彼女は以前から気になっていた“屋敷の裏庭”へ足を運んだ。
この裏庭は使用人たちの通用路があるだけで、普段はほとんど人が立ち入らない。手入れも行き届かず、雑草が伸び放題になった区画もある。それでも、建物の影になって視線を遮れるのが大きな利点だった。ここなら、少しのあいだ筆を握っていても屋敷の者から怪しまれずに済むかもしれない――そう考えたカリナは、カバンに忍ばせてきたスケッチブックと鉛筆を取り出すと、木陰に腰を下ろした。
「……リースに見せるには、もう少しラフなデッサンも描いておきたいわね」
彼女はそう呟きながら、雑草と蔦が絡まった古い石壁に目を向ける。朝の淡い光に照らされた蔦の葉は、まだ夏の名残を宿しながらも、ところどころ黄変しかけている。そのわずかな色合いの変化が、カリナには儚く美しく思えた。丁寧に輪郭を取り、葉脈の走り方をスケッチするうちに、彼女の心は無心の境地へと溶け込んでいく。
しばらく描き続けていると、遠くで聞き慣れた足音がした。カリナは慌ててスケッチブックを閉じかけるが、そこに現れたのは予想外の人物――なんと母だった。伯爵の妻として長らくステラリア家を支えてきた彼女は、病弱というわけではないものの、普段はあまり人前に出ることを好まず、常に夫の威光に遠慮している印象があった。
「お母様……どうして、ここに?」
母は一瞬足を止め、少し驚いたような表情を浮かべたが、すぐに穏やかな微笑みをカリナに向けた。
「たまには静かに庭を散歩したくてね。あなたこそ、こんな裏庭で何をしているの?」
カリナは動揺を抑えながら、スケッチブックをそっと隠すように抱え込む。母は昔から伯爵の言うことに絶対服従しており、彼女に夢を打ち明けたところで理解してくれるかどうか分からない。それでも、母の瞳にはどこか優しい光が宿っていて、カリナは意を決して切り出すことにした。
「私、絵を描いていたの。……子どもの頃からずっと好きで、でも婚約話が決まってからは、父様に“無駄なことをするな”と叱られるばかりで……」
母は黙って耳を傾け、そっとカリナの手元に目をやる。スケッチブックに残った筆跡や鉛筆の削りかす、微妙に指先に付着した薄い絵具の痕跡。すべてが彼女が“何をしてきたか”を物語っている。
「そう……あなたは、絵を描きたいのね」
母の声は低く、しかしどこか安堵にも似た響きを含んでいた。それは伯爵の妻として長く生きてきた彼女の“諦め”とも、“遠い憧れ”ともつかない色合いを帯びていて、カリナの胸が苦しくなる。
「お母様は……父様に従うしかなかったの? 自分のやりたいことは、本当になかったの?」
思わず踏み込んだ質問をしてしまい、カリナは少し後悔する。だが、母は驚くほど穏やかに笑って首を横に振った。
「私の時代には、選択肢なんてなかったわ。伯爵に嫁ぐことも、華やかな場で“理想の夫婦”を演じることも、すべて当然の運命だと思い込まされてきた。でもね、あなたは……私よりもずっと強い子だと思うの。描きたいなら、描いてもいいんじゃないかしら」
カリナは、その母の言葉に思わず胸が詰まる。ステラリア家の母として、夫ハロルドの厳格な支配を受けながらも、最後に見せてくれたのは娘への一抹の助力だったのかもしれない。
「ありがとう……でも、お母様がこうして許してくださっても、父様やエドリック様はきっと……」
母は娘の言葉をそっと遮り、静かに続ける。
「この世には“許される選択”もあれば、“許されない選択”もある。けれど、あなたがどうしても手放せないものがあるなら、諦めないで。私が言えるのは、それだけ……」
言い終わると、母は軽く目を伏せて一礼し、「あなたが戻るときのために、玄関のほうを見ておくわね」と囁いて去っていった。まるで、少しでもカリナに“描く時間”を与えてあげようという気遣いだったのかもしれない。
残されたカリナは、心の中に小さな感謝と、母に向けた切なさが入り混じるのを感じる。誰にも干渉されない裏庭の一角で、あらためてスケッチブックを開き、今度は蔦の葉だけでなく、その向こうに広がる空の色も微妙なニュアンスで描き始める。そこには「結婚」「家名」「義務」のどれも存在しない、ありのままの美しさがあった。
――こうして、カリナはようやく“家の女性”としてしか存在できない母の心のうちを、ほんの少しだけ知ることができた。彼女もまた、いつかは夢を見たかもしれないし、それを伯爵家の制度の中で失ったのかもしれない。だからこそ、「あなたは諦めないで」と言ってくれたのだ。
(お母様のためにも、私がこの壁を壊してみせる……)
婚礼が迫る日々の中で、カリナの決意は確固たる形を帯びつつある。エドリックから向けられる冷淡さも、父ハロルドが求める“名家の体裁”も、いつかは乗り越えねばならないだろう。そうしなければ、彼女は“本当に大切なもの”を失ったまま、形ばかりの結婚を余儀なくされてしまう。
(私は自分の手で色彩を取り戻す。この婚礼がいくら“無彩”でも、いつか色を灯してみせるんだ)
その意志こそが、カリナにとって“新たな旅立ち”の合図だった。結婚式は不本意にも近づいてきているし、ヴェイル公爵家での生活は想像を絶する閉塞感に満ちているかもしれない。しかし、少なくとも今のカリナは、自分の意志で筆を握り、自分の目で世界を見つめ、描き留める力をまだ失ってはいない。家の伝統も、夫となるはずの男の冷酷さも、乗り越える手段を模索しながら、彼女は一歩ずつ歩み始める。
――遠くの空に一筋の光が差し込む。曇天の下でも、雲の切れ間から日差しがこぼれるように、カリナはこの先を信じて筆を走らせた。手の中に描き続ける“色彩の未来”は、今まさに幕を開けようとしている。自分で立ち上がり、行動すれば、きっと世界は変わるに違いない――そう確信できるほどの力が、彼女の胸には満ち始めていたのである。
4-2
秋の訪れを感じさせる涼しい風が、ステラリア家の庭を揺らし始めた頃――屋敷内では、ギャラリーと結婚式の準備がより一層本格化していた。伯爵ハロルドは招待客のリストを増やし、さらに画商や芸術家を頻繁に呼びつけては「名家の威光にふさわしい展示」を厳しく問いただしている。家令や使用人たちも、朝から晩まで屋敷中を走り回り、新たな調度品の搬入や部屋の模様替えに追われていた。来るべき式典――それは本来ならばカリナ・ステラリアにとって生涯最高の晴れ舞台であるはずだが、少なくとも彼女の胸には、晴れやかな感情は微塵も芽生えていない。
一方、伯爵の“アドバイザー”として招かれているリース・アルファードは、あくまでも仕事の顔を保ちながら、カリナとの“秘密の計画”も着々と進めていた。彼女の描きかけの作品をいかにギャラリーへと紛れ込ませるか、伯爵に疑念を持たせず、かつステラリア家の客人が「面白い」と思うような演出をどう組み込むか――そのための入念な打ち合わせは、もはや日課といえるほど頻繁に行われている。もっとも、伯爵や家令の前では「展示テーマの最終確認」「装飾の配置」などと形式的に説明し、肝心の“カリナの絵”についてはあいまいな表現で済ませていた。
ある日の午後、カリナは屋敷の控えめな応接室でリースと顔を合わせていた。父ハロルドは別の部屋で大事な客をもてなしており、しばらく戻る気配はない。侍女長も廊下の手配に忙しく、ここ数分間はふたりきりで話すことができる貴重な時間となっていた。
「リース、あの……キャンバスの絵、もう少しで完成しそうなの。夜明けの花をメインにしたものと、今度は昼下がりの庭をイメージして描いたものの、二点。どちらか一方だけでも、ギャラリーに出せないかしら」
カリナは控えめに小声で話しながら、さりげなくドアのほうに目をやる。いつ誰が入ってくるか分からない状況に、心臓が高鳴るのを感じる。それでも、自分の絵を人前に出すという行為が、どれほど大きな一歩かを思うと、彼女の瞳にはわずかな決意の色が宿っていた。
リースは穏やかな笑みを浮かべ、カリナが差し出すスケッチの断片に目を落とす。そこには花びらや葉の重なり、そして柔らかな光と影の表現が繊細なタッチで描かれている。
「すごくいいですね。あなたの絵は、見る人を優しい気持ちにさせるんですよ。僕としては二点とも飾りたいくらいですが……伯爵殿の反応が少し怖いですね。せめて一枚は確実に配置したいけれど」
伯爵の好みや期待は、ギャラリー全体に“荘厳な雰囲気”や“格式”を求めるものだ。淡く柔らかい色彩を持つカリナの絵は、明らかにそれとは対極にあると言っていい。だが、それこそがむしろ大事なポイントだ――リースはそう考えている。「硬い絵画ばかりが並ぶより、ひとつ異質な作品があることで、むしろ来客の興味を惹けるはず」。この提案を伯爵に飲ませるため、リースは毎日のように展示レイアウトの案を修正し、「若い感性の作品が1枚あることでアクセントになる」と説明している。
「……父様を納得させるのは難しいかもしれないけれど、やるだけやってみるわ。私ももう後には引けないもの」
カリナはそう言いながら、リースが広げている資料の中に目を落とす。そこには展示壁面の配置図が細かく記されており、一角がまだ未定のまま空白になっていた。まるで、カリナの作品が差し込まれるのを待っているかのように思えて、彼女の胸は少し高鳴る。
話をまとめ終えたところで、ふと扉の外から足音が聞こえた。すぐに二人は打ち合わせの資料を整え、いつ伯爵や家令が入ってきても不自然にならないように備える。だが、応接室に現れたのはカリナの母だった。前日、裏庭でささやかな言葉を交わしたばかりだが、こんな場で母と対面するのは珍しい。
「お母様……どうなさったの?」
母は微笑を湛えたまま、娘とリースに視線をやる。伯爵夫人らしい端正な装いではあるが、どこか落ち着かない面持ちを見せていた。
「伯爵がもうすぐこちらへ見えるとのことよ。大事なお客様をお見送りして、応接室でギャラリーについての話をなさるんですって。アルファード様、しばらくここでお待ちになっていただけるかしら」
リースが礼儀正しく頭を下げると、母はカリナにだけ聞こえるような小さな声で続けた。
「それから、カリナ……もしものときは“私のせい”にして構わないわ。あなたが描いた絵を飾る件も含めて、私から伯爵にそれとなく伝えてみます。父親の怒りを一身に受けるのは、もう慣れているもの」
カリナはその言葉を聞いて、一瞬言葉を失う。母が伯爵に逆らうなど、今まで想像もしなかった。常に夫の後ろで大人しく微笑んでいる女性という印象しかなかったのに――だが思えば、あの日裏庭で交わした会話で、母ははっきり「諦めないで」と言ってくれたのだ。
「お母様……でも、それでは……」
「大丈夫。たとえ怒りを買っても、あなたまで巻き込ませないわ。私にとってはそれがせめてもの……親としての役目だと思うの。エドリック様のことも、家のことも、全部背負わされているあなたには、これくらい手を貸したい」
母がそう言い終わるか終わらないかのうちに、廊下から伯爵ハロルドの声が聞こえてきた。どうやら客人を送り出して、次なる打ち合わせのためにここへ向かっているらしい。母は瞬時に表情を引き締め、カリナとリースに無言で一礼すると、すぐさま部屋を出て行った。
少しして伯爵が応接室へ入ってくると、リースはいつものように流れるような口調で作業の進捗を報告し、展示プランの最新案を示した。伯爵は地図やメモをなぞりながら、あれこれと細かい要望を述べ始める。
「ここには大ぶりの歴代肖像画を飾れ。あちら側には公爵家ゆかりの絵を借りたいから手配しろ。……ステラリア家の令嬢の作品? ああ、カリナの……そういうのは端のコーナーにでもまとめておくように。無理に強調する必要はない」
カリナは伯爵の冷淡な物言いに胸を突かれるが、今ここで反論すれば逆効果だろう。リースも同様に察しているのか、「はい、承知しました。あまり大きく扱わずとも、若い感性の作品が加わることで華やかさが出るかと思います」と上手くまとめる。
ところが伯爵は、カリナの母が自分に進言したであろう話を思い出したのか、急に険しい顔で娘を見やる。
「そうだ、カリナ。お前の母が、お前の描いた絵をもう少し目立つ場所に飾れと言ってきたが、本気か? お前は自分の腕前にそんな自信があるのか?」
母の一言が、早くも伯爵の癇に障ったようだ。伯爵はあからさまに疑いの目を向け、リースにも視線を投げる。
「アルファード氏、あまり甘い考えを吹き込まないでくれよ。未熟な作品を無理に人前に出して、ステラリア家の評判を落とすわけにはいかんのだ」
リースは一瞬ぎくりとした表情を浮かべるが、すぐに平静を取り戻す。
「もちろん、伯爵殿のお考えはごもっともです。もし作品が不十分な出来であれば、むしろこちらが責任を持って差し止める所存です。ただ、一見して“未熟”に見える作品でも、若さゆえの新鮮な魅力があることも確かですし、見る方によっては好評を得るかもしれません。それを完全に無視してしまうのは、少々もったいないかと……」
伯爵はしばし沈黙し、険しい顔のまま唸るように息をつく。カリナは立ち上がり、一歩踏み出して父の前に頭を下げた。
「……お父様。失礼を承知で言わせてください。私ももう子どもではありません。結婚を控えている身として、いずれはヴェイル家での社交に挑むことになります。そこで“自分の描いた絵”を守り抜くことも含め、私なりの挑戦をしてみたいのです。もしそれで失敗したなら、すべて私の責任として甘んじて受けます」
これまで幾度となく伯爵に従順な態度しか示してこなかったカリナが、ここまで堂々と言い切るのは初めてかもしれない。伯爵は驚いたように眉を上げ、娘の表情をまじまじと見つめる。だが、その口調には以前ほどの勢いがない。「ふん……そこまで言うなら、お前の母に免じて少しだけ自由を与えてやろう。だが、もし恥をかけば、お前の責任だと心得ろ」
父の言葉は相変わらず冷たいが、それでも“完全拒否”ではなかった。ほんの小さな一歩。カリナはそのチャンスを手に入れたことを実感する。隣で見守っていたリースも、こっそり安堵の表情を浮かべていた。
伯爵がさらに口を開き、「今週末までに作品を仕上げてみろ。そこから判断して配置場所を決める」と告げると、打ち合わせは唐突に終了した。短いながらも、いくつかの障壁を越えた手応えがカリナの胸に広がる。この道は依然として険しいが、母とリース、そしてわずかながらの自分自身への信頼があれば前に進める気がした。
その夜、カリナは自室の机に向かい、慣れた手つきで筆を握る。昼下がりの庭をモチーフにした絵は、あと少し色の調整が必要だ。葉の陰の色味を深くし、光の当たる部分をほんの少し明るくする。それだけで絵がぐっと生き生きとする――そんな確信を得ながら、カリナは夜も更けるのを忘れて筆を走らせた。
(絶対に、恥をかかせるような仕上がりにはしない。私はここで諦めるわけにはいかないんだから)
伯爵家の寝静まる深夜、屋敷の外では秋の虫がかすかな音を響かせ、空には雲間から星が瞬いている。まるで、カリナの小さな“反逆”を見守るかのように――彼女はそう感じた。いつかこの夜闇が明ける頃、完成した作品がギャラリーに堂々と飾られる日が来る。エドリックの冷笑や、伯爵の支配的な態度を跳ね返し、母の秘かな期待に応える。その未来のために、カリナはすべてを懸けて絵筆を動かし続けるのだ。
――何度も塗り重ねるうち、キャンバスの景色はゆっくりと“生きた”表情へ変化していく。かつてのカリナが持っていた純粋な喜びと、今のカリナが抱える強い意志が、そこに混ざり合っているようにも思える。このまま夜明けを迎えても構わない――そう思えるほどの集中力をたたきつけながら、彼女は自分の未来と向き合い続ける。冷たい婚礼の檻に閉じ込められるだけで終わらない、己の“色彩の物語”を、自らの手で描くために。
4-3
カリナ・ステラリアが描きかけのキャンバスに向き合い始めてから数日が経過した。伯爵ハロルドは「週末までに作品を見せろ」と言い残し、ギャラリーの準備を巡って画商や有力者との交渉に奔走している。屋敷にはいつも以上に人の出入りが激しく、カリナのもとへやってくる使用人や侍女たちも、落ち着いた会話をする余裕などほとんどない。
しかし、そうした慌ただしさは、かえってカリナにとっては都合が良かった。誰もが多忙を極めるからこそ、彼女は昼間のわずかな隙間や深夜の静寂を縫って絵筆を握ることができる。昼下がりの庭をイメージした絵も、夜明けの花を描いた絵も、いよいよ仕上げの段階に入っており、「あともうひと押しで完成」という実感が湧き始めていた。
カリナの部屋の扉をノックする音が聞こえたのは、ちょうど午後の日が傾き始めたころである。机いっぱいにスケッチブックや絵具を広げていたカリナは、慌ててそれらを脇へ寄せ、扉のほうへ注意を向けた。
「はい……どなたですか?」
控えめに答えると、扉の向こうから小さな声がした。
「私よ、カリナ。入ってもいいかしら」
母だった。ここ数日、カリナの母は伯爵の目を盗むようにして、娘の様子を気にかけている。裏庭で出会った朝以来、母は以前とは打って変わって“娘の味方”を積極的に買って出ようとしているようだった。
カリナが「どうぞ」と声をかけると、母はそっと部屋へ入り、必要以上に周囲を警戒するかのように扉を閉める。
「お父様は、まだ来賓の相手をしていて、しばらく戻らないでしょう。……もしかして、絵を描いていたのね?」
カリナの視線を追って、母は机の端に置かれたスケッチブックや、わずかに絵具の色が付いた筆を見つめる。その目は優しげで、どこか懐かしさも宿していた。
「ごめんなさい、こんなことばかりしていて……でも、どうしても仕上げたいの。父様に“週末まで”と言われてから、ずっと焦っていて……」
母は首を横に振り、穏やかに微笑む。
「謝ることなんてないわ。むしろ誇りに思う。こんなにまで真剣に何かに打ち込んでいるあなたの姿を見たのは、もしかしたら初めてかもしれないわね」
それは伯爵夫人として生きてきた母の本音であり、同時にカリナへの賛辞でもあった。かつて彼女自身も、何かしらの夢を抱いていたのだろうか――その問いはカリナの胸にかすかな痛みを伴う。母は続けて小さな包みを差し出す。
「これ、昔あなたが使っていた古い筆だけど、私が奥の物置から見つけたの。新しいものと比べたら使い勝手は悪いかもしれないけれど……もし必要なら使ってちょうだい」
包みを開くと、懐かしい記憶が蘇るような淡い青の筆が数本入っていた。毛先こそ少し痛んでいるが、子どもの頃にカリナが好んで使っていた道具だ。指でそっとなぞれば、その頃の喜びや夢中になっていた感覚が手の中に戻ってくるようだった。
「ありがとう、お母様……」
母はそれだけ言うと、もう一度室内を見回してから、こっそりカリナの手を取る。
「あなたが仕上げた絵、私も早く見たいわ。伯爵が何と言おうと、私はあなたを応援しているの。あの人も、“もし失敗したら娘の責任”なんて言い方をしているけれど、内心はどうなのかしら……」
そこに母の遠い目が重なる。伯爵に隷属しているように見える彼女も、夫の本心を読みきれない部分があるらしい。カリナは唇を噛みながら、淡々とした声で返す。
「きっと父様は、心から私を応援しているわけじゃないと思うわ。家の面子を損なわない程度に、私を利用できればそれでいい……そんな感じ」
「それでも、あなたは諦めないんでしょう?」
母の問いかけに、カリナははっきりと頷く。
「ええ。もう、引き返せないもの。後はやるしかない……リースも、私の作品を絶対に飾るって言ってくれているし、お母様も応援してくれている。ならば私、失敗を恐れて止まるわけにはいかないわ」
その言葉に、母は静かに微笑み返す。まるで「それでこそ私の娘」とでも言わんばかりの表情だ。短い会話を終えると、母は「あなたの父様が戻る前に部屋を出るわね」と言い残して去っていった。
戸が閉じられ、足音が遠ざかると、部屋には再びカリナ一人。新たに手に入れた古い筆を見つめながら、彼女は軽く息をつく。
(今の私には、これ以上迷う余地なんてない。描きたいものを描いて、伯爵を――そしてヴェイル家を――納得させるしかないんだわ)
その晩、カリナは寝室の灯りを落としてから、机上のランプだけをつけて筆を握る。一枚目の“夜明けの花”はほぼ完成しており、今夜は“昼下がりの庭”を仕上げる予定だ。父が“週末まで”と期限を区切った以上、もう一日の猶予も残されていないかもしれない。
緊張の汗が手のひらを湿らせる。それでも、筆をキャンバスに触れさせるたびに、一瞬一瞬が研ぎ澄まされていくような快感を覚える。まだ誰にも見せていない“私だけの世界”――その核心へと踏み込む感覚があるのだ。
葉の輪郭をもう少し鮮明にする。木漏れ日の射す角度を意識しながら、光の差し込み方を微調整する。筆先に載る絵具の量に気をつけて塗り重ねるうち、緑の中にかすかな黄金色が浮かび上がってくる。まるで、本物の太陽光がそこに宿ったような錯覚に襲われ、カリナは一瞬呼吸を止めた。
(こんなにも……美しいものを、生み出せるんだ)
深夜、時計が一巡りしようとするころ、ようやくカリナは筆を置く。キャンバスに広がるのは、生き生きとした昼の庭の一瞬を封じ込めたかのような世界。息を呑むほど穏やかで、それでいてどこか力強い光を放っている。思わず「ああ……」と声が漏れた。
満足したと同時に、これで終わらせてはいけないという衝動も胸に湧く。明日の早朝、もう一度見直して、微調整できるところがあれば手を加えよう――そう考えつつ、カリナは慎重に道具を片付け、キャンバスを布で覆って椅子を立った。
翌朝、夜が明けきらないうちに起床したカリナは、机に向かい、ほとんど無意識のままに最後の筆を走らせた。ほんの数筆だが、そこに“決定的な輝き”が加わったように感じる。
「これで……完成」
すぐに侍女たちが朝食の準備を知らせにやってくる。カリナはキャンバスを隠すように絹布をかけ直し、鏡の前で身なりを整えた。ドレスを着て髪を結い上げるあいだも、胸の奥は早鐘を打っている。父がどんな言葉を浴びせようと、エドリックやヴェイル家がどんな顔をしようと――この絵だけは、守り抜く。
食卓に着くと、すでに伯爵は座っていた。機嫌が良いのか悪いのか、端正な顔立ちにまったく感情が読めない。だが、その低く威圧的な声がカリナの耳に届く。
「今日の午後、画商たちが揃う。お前の作品をここで見せてもらおう。もし陳腐なものなら、いくら母親がかばおうと関係ない。即刻却下だ。分かったな」
テーブルに運ばれるパンとスープの香りが漂うが、カリナは食欲よりも強い緊張感を抱える。とはいえ、正面から怯んでは始まらない。
「……かしこまりました。午後にお見せします。ご判断はお任せしますが、私は全力で描きました。それだけは信じていただきたい」
父が言葉を返すことはなく、無言でナプキンを置いて席を立つ。一触即発の空気を残して、広い食堂には母と使用人が立ち尽くすばかりだった。
(ここからが正念場ね。もう、どんな結果になろうと逃げるわけにはいかない)
朝食を終えたカリナは、胸を締めつけるような感覚を抱えながら自室へ引き返す。キャンバスにかけられた布をそっとめくり、改めて絵を見つめる。夜明けの花と昼下がりの庭――二枚の絵は、彼女自身の“夢”と“決意”を詰めこんだ大切な分身だった。
もし伯爵が「展示には不適切だ」と言えば、すべてが水泡に帰すかもしれない。だが、たとえそうなったとしても、カリナはもう二度と筆を捨てたりはしないだろう。ここまで絵にかけた情熱は、彼女を確かな意志へと導いている。結婚という形の冷たさも、エドリックの愛人が嘲笑するような日々も、乗り越える方法はきっとある――そう信じるための力が、これらの作品には宿っているからだ。
(お父様は何を言うかしら。リースはどう動いてくれる? お母様はどんな表情で見守ってくれるの? ……そして、エドリック様は?)
さまざまな思いが渦を巻く中、カリナは絵を大切に梱包する準備を始める。間もなく画商や出資者たちが集まる“審判の場”が待ち受けているのだ。ステラリア家の廊下は、すでに朝の光が差し込み、出入りする人々の足音が交差している。その雑踏の中心へ向かうのは容易ではない。けれど、もう足を止められない――そう自分を奮い立たせながら、彼女は意を決して扉を開いた。
――こうして、カリナが大切に育んできた二枚の絵は、いよいよ世に出る運命を迎えようとしている。果たして伯爵はどんな評価を下し、画商たちは何を思うのか。エドリックが冷たい目で見下ろそうとも、彼女の決意は揺るぎない。薄暗い婚礼の道を照らす“自分だけの光”を掴み取るために、カリナは全身で立ち向かう覚悟を固めるのだった。
4-4
カリナ・ステラリアが丹精を込めた二枚の絵――“夜明けの花”と“昼下がりの庭”――その行方を決する瞬間が、ついに訪れようとしていた。週末の午後、伯爵ハロルドは画商や出資者、さらには芸術家を名乗る何人かを屋敷に集め、一足先にギャラリーの見取り図や展示候補の作品を披露する会合を開いている。今回の集まりは完全な“内覧”というわけではなく、あくまでも「正式なお披露目に先立つ意見交換」が目的らしい。もっとも、その実態は伯爵にとって「後々の投資を狙うためのデモンストレーション」に近く、彼は終始上機嫌でゲストたちと談笑を続けている。
大広間には、まだ額に収められていない大小のキャンバスがいくつも運び込まれ、その合間にステラリア家に伝わる古い肖像画が置かれている。壁には展示予定の説明書きや飾り付けの設計図が貼られ、招かれた人々はそれを品定めするように眺めていた。リース・アルファードもまた、資料を片手に会場を行き来し、伯爵からの質問や要望に的確に応じている。そんな熱気に包まれた場所へ、カリナはそっと足を踏み入れた。
いつもなら遠目に見守るだけの立場だった彼女だが、今日は大切な“勝負の日”である。抱きかかえるようにして部屋へ持ち込んだ二枚の絵は、まだ布で覆われており、その正体を知らない人々が興味深げに視線を投げかけてくる。「あれはなんだ?」「ステラリア家の新作か?」――そんな囁きが聞こえるたびに、カリナの心臓は嫌でも高鳴ったが、それを表情には出さないよう、必死に呼吸を整える。
「カリナ、お前も来たか。ちょうどいい、皆の前で作品を見せてもらおうか」
伯爵の力強い声が大広間に響いた。彼は客人たちと話をしていたが、カリナの姿を見つけるや否や、その視線を鋭く向けてくる。周囲も「あれが噂の“伯爵令嬢の作品”か」「まだ若いのだろう?」などと興味深そうだ。一方、リースは落ち着いた表情を保ちつつ、視線だけでカリナを励ましている。
「……失礼いたします。父様のご指示どおり、週末までに仕上げましたので、本日お持ちしました」
そう告げると、カリナは胸の奥で“意志”を奮い立たせるかのように布の端をつかんだ。人々の視線が集まる中、ゆっくりとそれをめくる――まずは一枚目、“夜明けの花”。淡い光の中で白い花が開きかけている情景が、ぼんやりと幻想的に描かれている。塗り重ねられた柔らかな色彩は、見る者の目をすべるように誘い込み、静かな朝の息吹を感じさせた。
「あら……これはまた珍しいタッチだな」 「ずいぶん優しい色づかいですね。貴族の絵といえば、もっと豪奢なものを想像していましたが……」
周囲からは様々な声が上がる。中には「もう少し迫力が欲しい」と難癖をつける者もいれば、「意外な魅力を感じる」と興味を示す者もいる。伯爵は客人たちの反応を一瞥していたが、特にリアクションを示さず、次の絵を見るように顎でカリナを促した。カリナは一度深呼吸し、二枚目――“昼下がりの庭”――の布を外す。こちらは青々とした草木の合間から漏れる日差しが、優しくも力強いコントラストを生み出していた。太陽の光が、緑の葉を透かして黄金色の輝きを帯びている。遠くに見える花壇には小さな花々が点々と配され、かすかな風の動きまで想像できるようだった。
「こっちの方がさらに面白いな。光の当たり方が巧みというか……」 「この柔らかいタッチ、なかなか貴重だ。完成度も意外と高いかもしれんぞ」
今度は肯定的な声が比較的多く、カリナは内心でほっと胸を撫で下ろす。もちろん、全員が好評価というわけではなく、「あくまで“素人にしては”の域だろう」「伯爵家の名を冠して飾るには地味だ」という声も聞こえてくる。しかし、完全に酷評というほどでもない。むしろ、この場にいる人間の中には、本当に興味をそそられたらしく、絵に顔を近づけて色彩の重なりや筆使いを観察する者もいる。
「ふん……どうだ、皆の意見は」
伯爵が客人たちに問いかける。画商の一人が、一歩前に出て言葉を継いだ。 「伯爵さま、正直に申し上げて、技術的にはまだ荒削りな部分も感じます。けれど、この柔らかなタッチと自然光の表現には、確かに若い感性の魅力がありますね。格式ばった作品と組み合わせれば、お客様の目を惹く一角になるかもしれません。もちろん、大々的に“目玉”として売り出すにはやや力不足かと……」 それでも決して悪い評価ではない。むしろ、こうして“新しい風”として期待を示すあたり、画商としては前向きな姿勢といえるだろう。伯爵は腕を組んでいたが、どうやらこの意見を重視しているようだ。
「なるほどな……アルファード氏、どう思う。展示のアクセントになるという話だが」 リースは、待ってましたとばかりに落ち着いた声で答える。 「私も同感です。ステラリア家やヴェイル公爵家の荘厳な作品ばかりでは、どうしても重苦しい印象になる可能性があります。そこに、この瑞々しい情景を差し込むことで、メリハリが出ます。若い女性ならではの繊細さを見いだす方も多いでしょう」 周囲がそれに頷きはじめると、伯爵はしばし考え込むように無言で絵を睨む。カリナは緊張で呼吸が浅くなりかけていたが、ここで下手に口を挟むと逆効果だ。母もやや離れた場所から見守っているようで、視線を合わせたとき、うなずくように微笑み返してくれた。
「……まぁいい。せいぜい“家の恥”にならない程度に飾っておけ。画商殿や客人たちが言うように、多少の新味にはなるかもしれん」 伯爵の言葉は素っ気ないが、少なくとも“却下”ではない。大広間に軽い安堵の空気が漂い、カリナは全身の力が抜けそうになるのをこらえた。リースの目は微かに笑みを含んでいる。数日前まではこの場にすら出せず、まして飾ることなど夢のまた夢だったのだ。それを思えば、伯爵が渋々ながらも「飾ることを許可した」のは大きな前進と言える。
「よかったわね、カリナお嬢様。これであなたの絵をギャラリーに……」 耳元で侍女の一人が囁く。カリナはぎこちなく微笑み返し、「ありがとうございます……」と小声で答えた。本当なら跳び上がるほど嬉しいはずなのに、エドリックの存在を思い出すたび、どうしても心が晴れきらない。結婚を控えた彼は今日も姿を見せておらず、公爵家からの使者すら来ていない。伯爵が奮闘して“名家の力”を示そうとしているのも、エドリックが関心を示さない限り、何の意味があるのか――そんな疑問が頭をもたげる。
「それにしても、エドリック殿はずいぶんと冷淡なものだな。結婚前の娘婿なら、こういう機会にも顔を出してしかるべきだろうに」 周囲の画商や貴族たちの一部が、そんな噂話をひそひそと交わしているのが聞こえる。伯爵はそんな声には耳を貸さず、あくまで「ステラリア家が主体」であるかのように会を進める。カリナはこの成功を素直に喜びたい気持ちを抑え、少しだけうつむいたまま胸の奥で言葉にならない悔しさを噛みしめていた。自分の絵が展示を許されたのは良いが、これで婚礼やヴェイル家との関係が好転する保証などどこにもないのだ。
それでも、母が微笑み、リースがさりげなく目で「大丈夫ですよ」と合図を送ってくれる。カリナは二人の存在に救われる思いで、周囲の貴族たちに向かって一礼した。客人たちも「伯爵令嬢が描く絵とは面白い」「これは意外に見応えがあるかもしれん」と口々に感想を述べながら散っていく。伯爵は「まだ若いからな。これから鍛えればそれなりに使い物になるやもしれん」などと、まるで我が子というより部下を評価するような言葉を漏らす。それでも“展示決定”という事実は大きかった。
こうしてカリナの二枚の作品は、正式にステラリア家のギャラリーで飾られることになった。だが、同時に彼女の結婚へ向けた準備はさらに加速していく。式典の時期や招待客の選定、そしてエドリック側からの指示もいずれ飛んでくるだろう。それを思うと、展示の成功が「束の間の光」に過ぎないのではないかという不安が頭をもたげる。冷たい婚礼は避けられないのかもしれない――けれど、それでも、カリナは自分の色彩をあきらめたくない。
会合が終わり、大広間から客人たちが続々と退出するなか、リースがカリナのそばへ寄ってきた。 「お疲れ様でした。ひとまず、あなたの絵はここで日の目を見ることになりますね」 「ええ……すべてリースのおかげよ。本当にありがとう。父様が取り下げると言い出さないうちに、早く額装をしてしまわないと」 カリナが半ば冗談めかして言うと、リースは柔らかな笑みを返す。 「ええ、準備なら任せてください。こちらでしっかり保管し、会期までに何があっても大丈夫なようにします。それから……展示当日までの間に、もしも伯爵が難癖をつけてこようとも、僕たちでなんとか防ぎましょう」
頼もしさと同時に、カリナは胸の痛みも感じる。リースがここまで協力してくれるのは嬉しいが、彼自身もステラリア家のことに深入りしすぎれば、いつか父やヴェイル公爵家から罰を受けるかもしれない。それでも彼は一歩も引かないつもりのようだった。母が遠巻きに見守る中、カリナはぎこちなく微笑みつつ「ありがとう、私も頑張る」とだけ返す。
――こうして、カリナは一つの壁を越えた。伯爵の前に作品を差し出し、たとえ軽んじられてもなお、正式に展示を許されたのは大きな前進だ。だが、未来はまだ霧の中。婚礼の日は刻一刻と近づいている。エドリックの冷たさは相変わらずで、愛人の存在も依然として公然の秘密のまま。カリナの絵がギャラリーで称賛を浴びようとも、その先に待ち受ける運命を覆せる保証など何一つない。
それでも――だからこそ、カリナは筆を置かない。父から与えられたわずかな隙を突いてでも絵を描き続けようと思う。いつか、この“無彩”の婚礼を燃え上がらせ、形だけの夫婦関係を嘲笑う瞬間を手に入れるために。リースという協力者や、母のひそかな支えを力に変えて、彼女はさらに強くなる。たとえヴェイル公爵家の門が冷たく閉ざされていようとも、そこに鮮やかな色彩を灯す方法を探し続けるのだ。
――そんな決意を胸に、カリナは改めてキャンバスを見つめる。夜明けの花も、昼下がりの庭も、自分の内なる希望と意志を象徴する大切な存在だ。どんなに伯爵やエドリックが冷たい態度をとろうとも、絵を描くことだけは奪わせない――そう強く心に刻みながら、カリナは微笑みを浮かべて大広間を後にするのだった。
10
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

私を簡単に捨てられるとでも?―君が望んでも、離さない―
喜雨と悲雨
恋愛
私の名前はミラン。街でしがない薬師をしている。
そして恋人は、王宮騎士団長のルイスだった。
二年前、彼は魔物討伐に向けて遠征に出発。
最初は手紙も返ってきていたのに、
いつからか音信不通に。
あんなにうっとうしいほど構ってきた男が――
なぜ突然、私を無視するの?
不安を抱えながらも待ち続けた私の前に、
突然ルイスが帰還した。
ボロボロの身体。
そして隣には――見知らぬ女。
勝ち誇ったように彼の隣に立つその女を見て、
私の中で何かが壊れた。
混乱、絶望、そして……再起。
すがりつく女は、みっともないだけ。
私は、潔く身を引くと決めた――つもりだったのに。
「私を簡単に捨てられるとでも?
――君が望んでも、離さない」
呪いを自ら解き放ち、
彼は再び、執着の目で私を見つめてきた。
すれ違い、誤解、呪い、執着、
そして狂おしいほどの愛――
二人の恋のゆくえは、誰にもわからない。
過去に書いた作品を修正しました。再投稿です。

政略結婚した夫に殺される夢を見た翌日、裏庭に深い穴が掘られていました
伊織
恋愛
夫に殺される夢を見た。
冷え切った青い瞳で見下ろされ、血に染まった寝室で命を奪われる――あまりにも生々しい悪夢。
夢から覚めたセレナは、政略結婚した騎士団長の夫・ルシアンとの冷えた関係を改めて実感する。
彼は宝石ばかり買う妻を快く思っておらず、セレナもまた、愛のない結婚に期待などしていなかった。
だがその日、夢の中で自分が埋められていたはずの屋敷の裏庭で、
「深い穴を掘るために用意されたようなスコップ」を目にしてしまう。
これは、ただの悪夢なのか。
それとも――現実に起こる未来の予兆なのか。
闇魔法を受け継ぐ公爵令嬢と、彼女を疎む騎士団長。
不穏な夢から始まる、夫婦の物語。
男女の恋愛小説に挑戦しています。
楽しんでいただけたら嬉しいです。
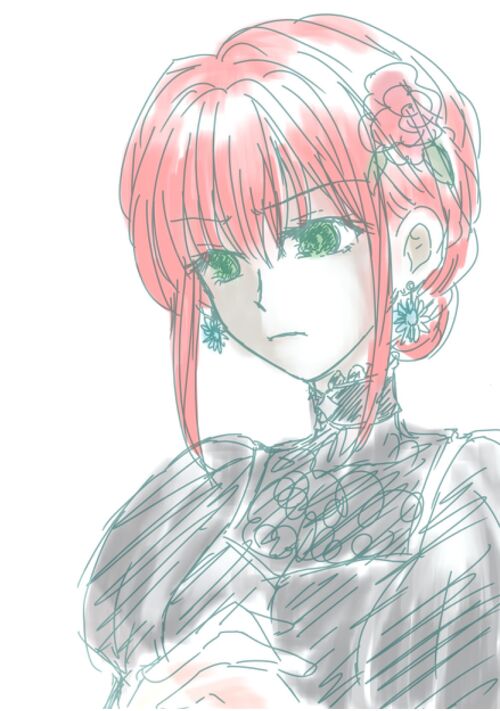
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

地味な私を捨てた元婚約者にざまぁ返し!私の才能に惚れたハイスペ社長にスカウトされ溺愛されてます
久遠翠
恋愛
「君は、可愛げがない。いつも数字しか見ていないじゃないか」
大手商社に勤める地味なOL・相沢美月は、エリートの婚約者・高遠彰から突然婚約破棄を告げられる。
彼の心変わりと社内での孤立に傷つき、退職を選んだ美月。
しかし、彼らは知らなかった。彼女には、IT業界で“K”という名で知られる伝説的なデータアナリストという、もう一つの顔があったことを。
失意の中、足を運んだ交流会で美月が出会ったのは、急成長中のIT企業「ホライゾン・テクノロジーズ」の若き社長・一条蓮。
彼女が何気なく口にした市場分析の鋭さに衝撃を受けた蓮は、すぐさま彼女を破格の条件でスカウトする。
「君のその目で、俺と未来を見てほしい」──。
蓮の情熱に心を動かされ、新たな一歩を踏み出した美月は、その才能を遺憾なく発揮していく。
地味なOLから、誰もが注目するキャリアウーマンへ。
そして、仕事のパートナーである蓮の、真っ直ぐで誠実な愛情に、凍てついていた心は次第に溶かされていく。
これは、才能というガラスの靴を見出された、一人の女性のシンデレラストーリー。
数字の奥に隠された真実を見抜く彼女が、本当の愛と幸せを掴むまでの、最高にドラマチックな逆転ラブストーリー。

完結 愚王の側妃として嫁ぐはずの姉が逃げました
らむ
恋愛
とある国に食欲に色欲に娯楽に遊び呆け果てには金にもがめついと噂の、見た目も醜い王がいる。
そんな愚王の側妃として嫁ぐのは姉のはずだったのに、失踪したために代わりに嫁ぐことになった妹の私。
しかしいざ対面してみると、なんだか噂とは違うような…
完結決定済み

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

王子様への置き手紙
あおき華
恋愛
フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯
小説家になろうにも掲載しています。

偽りの愛の終焉〜サレ妻アイナの冷徹な断罪〜
紅葉山参
恋愛
貧しいけれど、愛と笑顔に満ちた生活。それが、私(アイナ)が夫と築き上げた全てだと思っていた。築40年のボロアパートの一室。安いスーパーの食材。それでも、あの人の「愛してる」の言葉一つで、アイナは満たされていた。
しかし、些細な変化が、穏やかな日々にヒビを入れる。
私の配偶者の帰宅時間が遅くなった。仕事のメールだと誤魔化す、頻繁に確認されるスマートフォン。その違和感の正体が、アイナのすぐそばにいた。
近所に住むシンママのユリエ。彼女の愛らしい笑顔の裏に、私の全てを奪う魔女の顔が隠されていた。夫とユリエの、不貞の証拠を握ったアイナの心は、凍てつく怒りに支配される。
泣き崩れるだけの弱々しい妻は、もういない。
私は、彼と彼女が築いた「偽りの愛」を、社会的な地獄へと突き落とす、冷徹な復讐を誓う。一歩ずつ、緻密に、二人からすべてを奪い尽くす、断罪の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















