8 / 28
8
しおりを挟む
「……見てなさい、アンナ。今日はこの『角砂糖』が、私の自由への鍵になるわ」
学園のテラス席。心地よい風が吹き抜ける絶好のティータイムに、私は邪悪な笑みを浮かべていた。
テーブルの上には、最高級の茶葉で淹れた紅茶。
そして、山盛りに積まれた角砂糖の容器。
「お嬢様、それは鍵というより、糖尿病への片道切符に見えますが」
「失礼ね! これは嫌がらせよ! 殿下は甘いものがそれほど得意ではないという情報を掴んだの。だから、この紅茶を『飲む宝石箱』……じゃなくて、『砂糖の地獄』に変えてやるわ!」
王子の好みから外れたものを提供し、無理強いする。
これこそが、傲慢な婚約者による「無神経な押し付け」という完璧な悪行だ。
「あ、来たわね。ターゲット一号が!」
アレン王子が、今日も今日とて後光を背負いながら歩いてくる。
私は慌てて、角砂糖のトングを構えた。
「やあ、ロニエ! 今日は君がティータイムに誘ってくれるなんて、僕は朝から落ち着かなかったよ。カイルも驚いていた」
「ええ、殿下。日頃の感謝を込めて、私が直々に紅茶をお淹れしますわ。さあ、お座りになって?」
私は引き攣った笑みを浮かべ、王子のカップに紅茶を注いだ。
そして、ここからが本番だ。
「殿下は甘いのがお好きでしたわよね? たーっぷり、入れて差し上げますわ!」
ポチャン、ポチャン、ポチャン……。
一個、二個では甘すぎる程度。
私は五個、十個……さらには容器をひっくり返す勢いで、角砂糖をカップの中に放り込んだ。
「……お、お嬢様? もうカップの底が砂糖で埋まって、紅茶が溢れそうですが」
「黙っててアンナ! ほら、殿下。愛の結晶(砂糖)をこれでもかと詰め込みましたわ。一滴残さず、召し上がってくださいまし。オーホッホッホ!」
紅茶の色が明らかに白濁し、ドロリとした粘り気を持っている。
これはもはや飲み物ではない。液状の砂糖だ。
さあ、一口飲んで「不味い! 君の神経を疑うよ!」とカップを叩きつけて!
アレン王子は、その「泥沼のような紅茶」をじっと見つめていた。
数秒の沈黙。……ついに、彼が口を開く。
「…………ロニエ」
「はい、殿下! お口に合いませんこと?」
「……なんて、深いんだ」
「はい?」
王子は震える手でカップを持ち上げると、熱い視線を私に向けた。
「君は僕に、この国の『豊かさ』を教えてくれているんだね。砂糖は貴重な交易品だ。それをこれほど贅沢に使うということは、我が国が、そして僕たちの愛が、枯渇することのない富に満ちているという象徴……!」
「いえ、ただの嫌がらせですけれど」
「それだけじゃない! この強烈な甘さは、僕に対する君の『情熱』そのものだ! 『言葉では言い尽くせないほどの甘い時間を共に過ごしたい』……そんな君の心の叫びが、この一杯に凝縮されている!」
王子は覚悟を決めたような顔で、そのドロドロの液体を一気に飲み干した。
ゴクッ、ゴクッ、と喉が鳴る。
「……っ! くっ、あ、甘い……! だが、これがロニエの愛の重さだというなら、僕は喜んで受け止めよう!」
王子の顔が、糖分の過剰摂取でわずかに青ざめている気がするが、その瞳はかつてないほどキラキラと輝いている。
「……カ、カイル。至急、王宮のシェフに伝えろ。これからはすべての料理に、ロニエの愛(砂糖)を今の十倍は加えるようにと……」
「殿下、それはさすがに死者が出ます。……お嬢様、またしても殿下の限界に挑戦してくださり、ありがとうございます。殿下の精神力が一段階上がったようです」
カイルが半泣きで王子の背中をさすっている。
私の作戦は、またしても「王子の精神修行」へと昇華されてしまった。
「エヴァンズ様! 素敵ですわ!」
いつの間にか、隣の席で見ていたリリアさんが拍手をしていた。
「愛する人のために、貴重な砂糖を惜しみなく使う……。なんてスケールの大きな愛の表現でしょう! 私もいつか、あんな濃厚な紅茶を淹れられる女性になりたいです!」
「リリアさんまで! あれ、絶対不味かったわよ!? 私だって一口も飲みたくないもの!」
「ふふ、照れなくていいよ、ロニエ。おかげで、僕の脳が今までになく活性化されている。今なら、どんな難しい政務もこなせそうだ!」
王子は立ち上がると、鼻血が出そうなほどハイテンションで「さあ、カイル! 仕事に戻るぞ!」と去っていった。
私は空になったカップを見つめ、ガックリと肩を落とした。
「(……嘘でしょう。砂糖責めにしたのに、やる気スイッチを入れちゃったの?)」
「お嬢様、お疲れ様です。次は塩でも入れてみますか? 『人生の辛さを共に乗り越えようというメッセージ』だと解釈されるでしょうけれど」
アンナが片付けをしながら、冷酷な予言を口にする。
「……もういいわよ。次は、もっと物理的に……そう、魔法実習で大失敗して、王子の顔を真っ黒にしてやるんだから!」
私の「婚約破棄への道」は、甘すぎる紅茶のせいで、より一層ベタベタした溺愛ルートへと引きずり込まれていくのだった。
学園のテラス席。心地よい風が吹き抜ける絶好のティータイムに、私は邪悪な笑みを浮かべていた。
テーブルの上には、最高級の茶葉で淹れた紅茶。
そして、山盛りに積まれた角砂糖の容器。
「お嬢様、それは鍵というより、糖尿病への片道切符に見えますが」
「失礼ね! これは嫌がらせよ! 殿下は甘いものがそれほど得意ではないという情報を掴んだの。だから、この紅茶を『飲む宝石箱』……じゃなくて、『砂糖の地獄』に変えてやるわ!」
王子の好みから外れたものを提供し、無理強いする。
これこそが、傲慢な婚約者による「無神経な押し付け」という完璧な悪行だ。
「あ、来たわね。ターゲット一号が!」
アレン王子が、今日も今日とて後光を背負いながら歩いてくる。
私は慌てて、角砂糖のトングを構えた。
「やあ、ロニエ! 今日は君がティータイムに誘ってくれるなんて、僕は朝から落ち着かなかったよ。カイルも驚いていた」
「ええ、殿下。日頃の感謝を込めて、私が直々に紅茶をお淹れしますわ。さあ、お座りになって?」
私は引き攣った笑みを浮かべ、王子のカップに紅茶を注いだ。
そして、ここからが本番だ。
「殿下は甘いのがお好きでしたわよね? たーっぷり、入れて差し上げますわ!」
ポチャン、ポチャン、ポチャン……。
一個、二個では甘すぎる程度。
私は五個、十個……さらには容器をひっくり返す勢いで、角砂糖をカップの中に放り込んだ。
「……お、お嬢様? もうカップの底が砂糖で埋まって、紅茶が溢れそうですが」
「黙っててアンナ! ほら、殿下。愛の結晶(砂糖)をこれでもかと詰め込みましたわ。一滴残さず、召し上がってくださいまし。オーホッホッホ!」
紅茶の色が明らかに白濁し、ドロリとした粘り気を持っている。
これはもはや飲み物ではない。液状の砂糖だ。
さあ、一口飲んで「不味い! 君の神経を疑うよ!」とカップを叩きつけて!
アレン王子は、その「泥沼のような紅茶」をじっと見つめていた。
数秒の沈黙。……ついに、彼が口を開く。
「…………ロニエ」
「はい、殿下! お口に合いませんこと?」
「……なんて、深いんだ」
「はい?」
王子は震える手でカップを持ち上げると、熱い視線を私に向けた。
「君は僕に、この国の『豊かさ』を教えてくれているんだね。砂糖は貴重な交易品だ。それをこれほど贅沢に使うということは、我が国が、そして僕たちの愛が、枯渇することのない富に満ちているという象徴……!」
「いえ、ただの嫌がらせですけれど」
「それだけじゃない! この強烈な甘さは、僕に対する君の『情熱』そのものだ! 『言葉では言い尽くせないほどの甘い時間を共に過ごしたい』……そんな君の心の叫びが、この一杯に凝縮されている!」
王子は覚悟を決めたような顔で、そのドロドロの液体を一気に飲み干した。
ゴクッ、ゴクッ、と喉が鳴る。
「……っ! くっ、あ、甘い……! だが、これがロニエの愛の重さだというなら、僕は喜んで受け止めよう!」
王子の顔が、糖分の過剰摂取でわずかに青ざめている気がするが、その瞳はかつてないほどキラキラと輝いている。
「……カ、カイル。至急、王宮のシェフに伝えろ。これからはすべての料理に、ロニエの愛(砂糖)を今の十倍は加えるようにと……」
「殿下、それはさすがに死者が出ます。……お嬢様、またしても殿下の限界に挑戦してくださり、ありがとうございます。殿下の精神力が一段階上がったようです」
カイルが半泣きで王子の背中をさすっている。
私の作戦は、またしても「王子の精神修行」へと昇華されてしまった。
「エヴァンズ様! 素敵ですわ!」
いつの間にか、隣の席で見ていたリリアさんが拍手をしていた。
「愛する人のために、貴重な砂糖を惜しみなく使う……。なんてスケールの大きな愛の表現でしょう! 私もいつか、あんな濃厚な紅茶を淹れられる女性になりたいです!」
「リリアさんまで! あれ、絶対不味かったわよ!? 私だって一口も飲みたくないもの!」
「ふふ、照れなくていいよ、ロニエ。おかげで、僕の脳が今までになく活性化されている。今なら、どんな難しい政務もこなせそうだ!」
王子は立ち上がると、鼻血が出そうなほどハイテンションで「さあ、カイル! 仕事に戻るぞ!」と去っていった。
私は空になったカップを見つめ、ガックリと肩を落とした。
「(……嘘でしょう。砂糖責めにしたのに、やる気スイッチを入れちゃったの?)」
「お嬢様、お疲れ様です。次は塩でも入れてみますか? 『人生の辛さを共に乗り越えようというメッセージ』だと解釈されるでしょうけれど」
アンナが片付けをしながら、冷酷な予言を口にする。
「……もういいわよ。次は、もっと物理的に……そう、魔法実習で大失敗して、王子の顔を真っ黒にしてやるんだから!」
私の「婚約破棄への道」は、甘すぎる紅茶のせいで、より一層ベタベタした溺愛ルートへと引きずり込まれていくのだった。
0
あなたにおすすめの小説

これって私の断罪じゃなくて公開プロポーズですか!?
桃瀬ももな
恋愛
「カタリーナ・フォン・シュバルツ! 貴様との婚約を破棄し、国外追放に処す!」
卒業パーティーの最中、第一王子アルフォンスから非情な宣告を突きつけられた公爵令嬢カタリーナ。
生まれつきの鋭い目つきと、緊張すると顔が強張る不器用さゆえに「悪役令嬢」として孤立していた彼女は、ついに訪れた「お決まりの断罪劇」に絶望……するかと思いきや。
(……あれ? 殿下、いま小さく「よっしゃあ!」ってガッツポーズしませんでした!?)
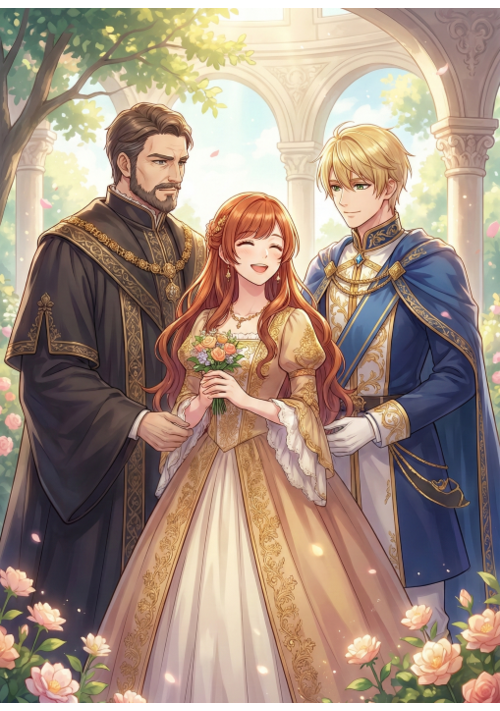
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

悪役令嬢は婚約破棄の後、氷の騎士に溺愛される〜裏切られた令嬢の逆転劇〜
nacat
恋愛
第一王子から一方的な婚約破棄を告げられ、公衆の面前で嘲笑された“悪役令嬢”クラリス。
だが彼女を冷たく見つめていた王国随一の“氷の騎士”オルフェンが、その手を差し伸べる。
「君が傷つく理由など、どこにもない」
絶望の淵で拾われた心は、いつしか凍てついた騎士を溶かし始めていた。
華やかな社交界の裏で繰り広げられる復讐と癒やし、そして溺愛の物語。
運命に弄ばれた令嬢が、真実の愛と共に見返す――ざまぁと幸福の逆転劇。

悪役令嬢のはずですが、年上王子が幼い頃から私を甘やかす気でいました
ria_alphapolis
恋愛
私は、悪役令嬢なのかもしれない。
王子の婚約者としては少し我儘で、周囲からは気が強いと思われている――
そんな自分に気づいた日から、私は“断罪される未来”を恐れるようになった。
婚約者である年上の王子は、今日も変わらず優しい。
けれどその優しさが、義務なのか、同情なのか、私にはわからない。
距離を取ろうとする私と、何も言わずに見守る王子。
両思いなのに、想いはすれ違っていく。
けれど彼は知っている。
五歳下の婚約者が「我儘だ」と言われていた幼い頃から、
そのすべてが可愛くて仕方なかったことを。
――我儘でいい。
そう決めたのは、ずっと昔のことだった。
悪役令嬢だと勘違いしている少女と、
溺愛を隠し続ける年上王子の、すれ違い恋愛ファンタジー。
※溺愛保証/王子視点あり/幼少期エピソードあり

悪役令嬢を断罪したくせに、今さら溺愛とか都合が良すぎますわ!
nacat
恋愛
侯爵令嬢リディアは、無実の罪で婚約者の王太子に断罪された。
冷笑を浮かべ、すべてを捨てて国外へ去った彼女が、数年後、驚くべき姿で帰ってくる。
誰もが羨む天才魔導師として──。
今さら後悔する王太子、ざまぁを噛みしめる貴族令嬢たち。
そして、リディアをひそかに守ってきた公爵の青年が、ようやく想いを告げる時が来た。
これは、不当な断罪を受けた少女が、自分の誇りと愛を取り戻す溺愛系ロマンス。
すべての「裏切られた少女」たちに捧ぐ、痛快で甘く切ない逆転劇。

気付けば名も知らぬ悪役令嬢に憑依して、見知らぬヒロインに手をあげていました
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
私が憑依した身体の持ちは不幸のどん底に置かれた悪役令嬢でした
ある日、妹の部屋で見つけた不思議な指輪。その指輪をはめた途端、私は見知らぬ少女の前に立っていた。目の前には赤く腫れた頬で涙ぐみ、こちらをじっと見つめる可憐な美少女。そして何故か右手の平が痛む私。もしかして・・今私、この少女を引っ叩いたの?!そして何故か頭の中で響き渡る謎の声の人物と心と体を共存することになってしまう。憑依した身体の持ち主はいじめられっ娘の上に悪役令嬢のポジションに置かれている。見るに見かねた私は彼女を幸せにする為、そして自分の快適な生活を手に入れる為に自ら身体を張って奮闘する事にした―。
※ 「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています。

婚約破棄された令嬢ですが、今さら愛されたって遅いですわ。~冷徹宰相殿下の溺愛が止まりません~
nacat
恋愛
王立学院の卒業式で、婚約者の王太子に「悪女」と断罪された公爵令嬢リリアナ。
全ての罪を着せられ、婚約を破棄された彼女は、冷徹と名高い宰相殿下のもとへ嫁ぐことになった。
「政略結婚ですから、愛など必要ございませんわ」そう言い放ったリリアナ。
だが宰相殿下は、彼女を宝物のように扱い、誰よりも深く愛し始める――。
やがて明らかになる“陰謀”と、“真実の愛”。
すべてを失った令嬢が、愛と誇りをもって世界を見返す、痛快ざまぁ&溺愛ロマンス!

『お前の顔は見飽きた!』内心ガッツポーズで辺境へ
夏乃みのり
恋愛
「リーナ・フォン・アトラス! 貴様との婚約を破棄する!」
華やかな王宮の夜会で、第一王子ジュリアンに突きつけられた非情な宣告。冤罪を被せられ、冷酷な悪役令嬢として追放を言い渡されたリーナだったが、彼女の内心は……「やったーーー! これでやっとトレーニングに専念できるわ!」と歓喜に震えていた!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















