10 / 10
ぬくもりのティールーム
しおりを挟む
その辞令を受け取ったのは、三十歳の誕生日を迎える少し前のことだった。
【赴任先:横浜支社】
生まれも育ちも、そして今の職場も関西。
辞令を持つ手は、少し震えていた。
慣れた街を離れる不安と、新しい生活への期待が、胸の中でせめぎ合っていた。
会社から四駅ほど離れたこのアパートを選んだのは、家賃の手頃さが一番の理由だった。
少し古びた街並みは、新たな地での耳新しさは薄れるかもしれない。
けれど落ち着いた匂いがして、新参者には心地よいだろうと思えた。
その店は、駅へ向かう途中の道に、ひっそりと佇んでいた。
丸い木製の看板と、手書きの小さな黒板。
アイキャッチはごく控えめなのに、なぜか目を惹いた。
白いレンガ壁、緑のツタ、そして重厚な木製の扉。
軽やかなレースのカーテンがかかっていて、窓から店内を窺うことはできない。
けれど――。
(きっと、ステキなカフェなんだろうな……)
カフェだと思った理由は、通り際に目に入る黒板の内容からだ。
『本日のサンドウィッチ ローストビーフ、クレソン入り玉子サラダ』
『本日のスープ 乾燥えんどう豆とハム』
毎日変わるそれは、馴染みのないものもあるけれど、どこか家庭的な匂いがした。
(……いつか入ってみたいな)
そう思いつつ――。
新しい職場に慣れるために必死だったこと、そして多少の気後れから、気づけば半年が過ぎていた。
***
(はぁ……やってしまった……)
金曜日の夜。
いつもより遅くなり、ぽつり、ぽつりと街灯が光る道を、とぼとぼと歩く。
新しい職場にも慣れてきて、ちょっと気が緩んでいたのか――仕事でミスをした。
同僚がカバーしてくれたおかげで大事故にはならなかったものの、横浜に来てここまで落ち込んだのは初めてだ。
(……何やってるんだろう、私)
ため息を一つ。
角を曲がろうとして――ここが『あの店』の前だと気付いた。
(さすがにこんな時間には開いてないか)
ふと見上げると、二階の窓から明かりが漏れている。
温かなその色が胸に沁みた。
(いいな、あの光……)
両親と暮らした関西の実家を思い出す。
今の私を見たら、きっと優しく慰めてくれるだろう。
(……明日、来てみようかな)
軒下にぶら下がった看板を見遣る。
「……ローズメリー……」
口に出しただけで、心が少し軽くなった気がした。
***
オフィス・カジュアル以外はあまり揃っていないクローゼットから、どうにかこうにかセットアップした勝負服を着て、石畳の歩道を歩く。
早鐘を打つ心臓は、扉の前に立つときには痛いほどで、いざ真鍮の取っ手に指をかけて――息が詰まった。
ごくりと喉を鳴らし、そっと扉を引くと。
チリン。
涼やかなベルの音。そして。
「いらっしゃいませ」
柔らかな声が、私を出迎えた。
「あら、初めてのお客様かしら?」
黒い詰襟のワンピースと、白いエプロン。後ろでひとつにまとめた髪。
年齢は――よくわからないけれど、私よりは上だろう。
ふんわりと物腰の柔らかい女性が、カウンターの前に立っていた。
「あの。は、初めてです!」
緊張で軽く裏返った声でそう言うと、女性――恐らく店主だろう――はにこりと笑った。
「ふふっ、お越しいただきありがとうございます。どうぞこちらへ」
店主の後について、店の奥へと歩を進める。
磨き抜かれた木の床がこつこつと、小気味よい音を立てた。
あまり広くはない店内は、半分ほどが客で埋まっている。
じろじろ見るのは無作法だと思い、さっと見渡すに止めたが――それでも客層が日本人だけではないことは、一目瞭然だった。
(うわーっ! もしかして、場違いなお店に来ちゃったのかな!?)
後悔が過ぎるが、今さらどうしようもない。
「こちらのお席はいかがですか?」
明るい窓際の二人掛けのテーブルを示され、無言で頷く。
私が腰掛けるのを見届けてから、女性は「メニューをお持ちしますね」と言ってカウンターへ戻っていった。
(ど、どうしよう……)
身の置き場に困り縮こまっていると、こつこつという足音がこちらへ向かってくる。
店主がメニューを持って来たのだ。
「当店は紅茶専門店です。茶葉は好きなものをお選びください。ストレート、ミルクなど、お好みでご用意します」
「じゃあ……ミルクティーをお願いします」
右から左へ流れていく説明の、どうにか半分を理解して注文する。
すると女性は、一拍置いて優しい声で尋ねた。
「茶葉はどうされますか?」
(えっ、茶葉!? そんなの……知らないっ!)
紅茶といえば、私にとってはペットボトルのそれか、せいぜいがティーバッグだ。
銘柄が存在することくらいは知っているが、気にして飲んだことなどない。
どう答えていいかわからず戸惑っていると、それを察したのか、店主が言葉を継いでくれた。
「今日のおすすめは、イングリッシュ・ブレックファーストです」
「なら、それを……」
「かしこまりました。それから、今のお時間でしたら、おすすめのケーキもご用意できますよ」
おすすめのケーキ――その言葉に、胸が躍る。
何しろ今日は、昨日の失敗の気晴らしなのだ。ケーキのひとつやふたつ、食べないでどうする。
「それもお願いします!」
「かしこまりました。では、少々お待ちください」
去ってゆく背中を眺めながら、ほっと息を吐く。
なんとか無事にオーダーできた。
余裕ができた私は、あらためて店内を見渡した。
壁に掛けられた大きな振り子時計からは、コチ、コチと密かな音が響いている。
棚にはレトロな缶やティーポット、赤い二階建てバスのミニチュアといった小物が飾られていた。
他の客が囁く声は、日本語ではない。
(……なんか、非日常って感じのお店だな)
両手を膝の上に乗せて、つい畏まっていると。
チリン。
入口の扉が開いて、外の空気をまとった三人連れの客が入ってきた。
「……っ!?」
そのうちのひとりを見止めた瞬間、私は驚きのあまり声を上げそうになった。
というのも。
(す、すごいハンサム!)
すらりとした高身長、一目で上質とわかる洗練された服装。
何より一番目を惹いたのは、その容貌。
(もしかして、外国の俳優さん……かな?)
そこにいたのは、スクリーンでもちょっと見ないような完璧な美貌の、外国人男性だった。
連れ立っているのは、大学生くらいに見える男の子と女の子。
男の子は幼さが残る風貌で、かわいいと表現するのがぴったりだ。
髪をポニーテールにした女の子は、明るく快活そうだ。
「ただいま、翠さん!」
女の子が声を上げると、店主はカウンターから出てきて三人を迎えた。
「みんな、おかえりなさい。後からお茶とスコーンを持っていくわね」
「ありがとうございます」
男の子は礼儀正しく頭を下げてから、先を行く二人を追う。
しかし。
(あ、あれ?)
てっきりこちらにやってくると思っていた三人は、カウンターの脇を抜け、店の奥に入っていった。
(お客、じゃないのかな……)
非日常の中で、さらに不思議な光景を見てしまい、頭の中に疑問符がいくつも浮かぶ。
首を捻ってあれこれ想像していると、再び木の床を踏む足音が近付いてきた。
「お待たせしました。ミルクティーと、おすすめのケーキ、ヴィクトリア・サンドウィッチです」
銀色の盆を持った女性は、柔らかく微笑んだ。
思わず見とれている間に、ポットやカップ、そしてケーキが乗った皿がテーブルに並べられていく。
「どうぞごゆっくり」
その声を聞きながら、あらためてケーキの皿を見遣る。
(……これが、おすすめ?)
小花が描かれたアンティーク調の皿に乗っているのは、デコレーションや細工のない、素朴な焼き菓子だった。
きつね色に焼けた二枚のスポンジで、赤いジャムと白いクリームを挟んである。
飾りといえば、ケーキの上面にかけられた白い粉末――砂糖だろう、それだけ。
(こんな素敵なお店なのに……なんだか地味で冴えないケーキ)
紙ナプキンの上に置かれたフォークを手に取り、そっとケーキに差し込んだ。
(あれ?フワフワじゃない。フォークが沈むような、しっとりした感じ……)
カットした一切れを口元に運ぶと、甘酸っぱいジャムの匂いとバターの香りが鼻先を掠めた。
(いい匂い……)
口に含むと――。
「……っ!!」
一番に感じたのは、ジャムの華やかな酸味。
味に色があるのなら、まさに――深紅。
こんなにも鮮烈な味のジャムを、私はこれまでに食べたことがない。
次に口に広がったのは、クリームのまろやかな味わいだ。
生クリームよりもコクのあるミルクの風味が、ねっとりとジャムの酸味を包み込む。
最後にしっとりとしたスポンジが、それらをまとめて浚っていった。
(……すごい……)
味の余韻を逃がしたくなくて、鼻から息が漏れることすら惜しくなる。
飲み込んで、すぐに次のひと口を……と思ったところで、ティーポットが目に入った。
頼んだのはミルクティーだから、これに入っているのだろう。
そっと蓋を開けると、琥珀色の液体がなみなみと入っていた。
(あれ? ミルクは……)
テーブルの上をぐるりと見ると、空のカップの隣に、白い液体で満たされたピッチャーが置かれていた。
(これを混ぜて飲むのか……)
ポットの紅茶をカップに注ぎ、ピッチャーを傾ける。
紅茶とミルクがマーブル模様を描くそれをスプーンでひとまぜして、口に運んだ。
「えっ!?」
思わず声が漏れた。――美味しい。
(なに、これ……これが紅茶なの?)
ティーカップに揺蕩う液体は、いつも飲んでいるペットボトルのそれとは比べ物にならないくらい、香りも味も濃厚だった。
(砂糖を入れてないのに、甘い)
香りの強い紅茶は、けれどミルクのこっくりとした味を殺しはしない。
「……絶妙だわ」
それ以外の言葉が見つからない。
私は夢中で、目の前に差し出された奇跡のような紅茶とケーキを楽しんだ。
***
「ありがとうございました」
女主人の穏やかな声と笑顔に送り出されて、私は店を後にした。
宣言通りというか、なんというか――結局私は、ケーキをおかわりした。
「いいのよ、今日はね!」
誰に言うでもなく、強気に言い放つ。
その声に、私は気が付いた。
(……あれ、元気になってる?)
まるで魔法のようだ。
この店に流れる空気も、妖精のような女主人も、そして絶世の美男も。
全てが子どもの頃に読んだ、お伽話の世界。
(まさか振り返ったら消えてる、なんてこと……ないよね?)
しかし振り返った目線の先に、間違いなくその店はあった。
「ローズメリー……推せるわ、このお店」
家を出るときは重かった足取りが、今は嘘のように軽い。
(疲れたらまた来よう。あの扉の向こうは、私史上最高の癒しスポットよ!)
これから先、この地で過ごす日々に希望が灯る。
一歩を踏み出した靴音は、青く晴れ渡った空に高らかに響いた。
秘密はいつもティーカップの向こう側 BONUS TRACK
ぬくもりのティールーム / 完
◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側
本編もアルファポリスで連載中です☕
ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」
シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」
シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」
シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
【赴任先:横浜支社】
生まれも育ちも、そして今の職場も関西。
辞令を持つ手は、少し震えていた。
慣れた街を離れる不安と、新しい生活への期待が、胸の中でせめぎ合っていた。
会社から四駅ほど離れたこのアパートを選んだのは、家賃の手頃さが一番の理由だった。
少し古びた街並みは、新たな地での耳新しさは薄れるかもしれない。
けれど落ち着いた匂いがして、新参者には心地よいだろうと思えた。
その店は、駅へ向かう途中の道に、ひっそりと佇んでいた。
丸い木製の看板と、手書きの小さな黒板。
アイキャッチはごく控えめなのに、なぜか目を惹いた。
白いレンガ壁、緑のツタ、そして重厚な木製の扉。
軽やかなレースのカーテンがかかっていて、窓から店内を窺うことはできない。
けれど――。
(きっと、ステキなカフェなんだろうな……)
カフェだと思った理由は、通り際に目に入る黒板の内容からだ。
『本日のサンドウィッチ ローストビーフ、クレソン入り玉子サラダ』
『本日のスープ 乾燥えんどう豆とハム』
毎日変わるそれは、馴染みのないものもあるけれど、どこか家庭的な匂いがした。
(……いつか入ってみたいな)
そう思いつつ――。
新しい職場に慣れるために必死だったこと、そして多少の気後れから、気づけば半年が過ぎていた。
***
(はぁ……やってしまった……)
金曜日の夜。
いつもより遅くなり、ぽつり、ぽつりと街灯が光る道を、とぼとぼと歩く。
新しい職場にも慣れてきて、ちょっと気が緩んでいたのか――仕事でミスをした。
同僚がカバーしてくれたおかげで大事故にはならなかったものの、横浜に来てここまで落ち込んだのは初めてだ。
(……何やってるんだろう、私)
ため息を一つ。
角を曲がろうとして――ここが『あの店』の前だと気付いた。
(さすがにこんな時間には開いてないか)
ふと見上げると、二階の窓から明かりが漏れている。
温かなその色が胸に沁みた。
(いいな、あの光……)
両親と暮らした関西の実家を思い出す。
今の私を見たら、きっと優しく慰めてくれるだろう。
(……明日、来てみようかな)
軒下にぶら下がった看板を見遣る。
「……ローズメリー……」
口に出しただけで、心が少し軽くなった気がした。
***
オフィス・カジュアル以外はあまり揃っていないクローゼットから、どうにかこうにかセットアップした勝負服を着て、石畳の歩道を歩く。
早鐘を打つ心臓は、扉の前に立つときには痛いほどで、いざ真鍮の取っ手に指をかけて――息が詰まった。
ごくりと喉を鳴らし、そっと扉を引くと。
チリン。
涼やかなベルの音。そして。
「いらっしゃいませ」
柔らかな声が、私を出迎えた。
「あら、初めてのお客様かしら?」
黒い詰襟のワンピースと、白いエプロン。後ろでひとつにまとめた髪。
年齢は――よくわからないけれど、私よりは上だろう。
ふんわりと物腰の柔らかい女性が、カウンターの前に立っていた。
「あの。は、初めてです!」
緊張で軽く裏返った声でそう言うと、女性――恐らく店主だろう――はにこりと笑った。
「ふふっ、お越しいただきありがとうございます。どうぞこちらへ」
店主の後について、店の奥へと歩を進める。
磨き抜かれた木の床がこつこつと、小気味よい音を立てた。
あまり広くはない店内は、半分ほどが客で埋まっている。
じろじろ見るのは無作法だと思い、さっと見渡すに止めたが――それでも客層が日本人だけではないことは、一目瞭然だった。
(うわーっ! もしかして、場違いなお店に来ちゃったのかな!?)
後悔が過ぎるが、今さらどうしようもない。
「こちらのお席はいかがですか?」
明るい窓際の二人掛けのテーブルを示され、無言で頷く。
私が腰掛けるのを見届けてから、女性は「メニューをお持ちしますね」と言ってカウンターへ戻っていった。
(ど、どうしよう……)
身の置き場に困り縮こまっていると、こつこつという足音がこちらへ向かってくる。
店主がメニューを持って来たのだ。
「当店は紅茶専門店です。茶葉は好きなものをお選びください。ストレート、ミルクなど、お好みでご用意します」
「じゃあ……ミルクティーをお願いします」
右から左へ流れていく説明の、どうにか半分を理解して注文する。
すると女性は、一拍置いて優しい声で尋ねた。
「茶葉はどうされますか?」
(えっ、茶葉!? そんなの……知らないっ!)
紅茶といえば、私にとってはペットボトルのそれか、せいぜいがティーバッグだ。
銘柄が存在することくらいは知っているが、気にして飲んだことなどない。
どう答えていいかわからず戸惑っていると、それを察したのか、店主が言葉を継いでくれた。
「今日のおすすめは、イングリッシュ・ブレックファーストです」
「なら、それを……」
「かしこまりました。それから、今のお時間でしたら、おすすめのケーキもご用意できますよ」
おすすめのケーキ――その言葉に、胸が躍る。
何しろ今日は、昨日の失敗の気晴らしなのだ。ケーキのひとつやふたつ、食べないでどうする。
「それもお願いします!」
「かしこまりました。では、少々お待ちください」
去ってゆく背中を眺めながら、ほっと息を吐く。
なんとか無事にオーダーできた。
余裕ができた私は、あらためて店内を見渡した。
壁に掛けられた大きな振り子時計からは、コチ、コチと密かな音が響いている。
棚にはレトロな缶やティーポット、赤い二階建てバスのミニチュアといった小物が飾られていた。
他の客が囁く声は、日本語ではない。
(……なんか、非日常って感じのお店だな)
両手を膝の上に乗せて、つい畏まっていると。
チリン。
入口の扉が開いて、外の空気をまとった三人連れの客が入ってきた。
「……っ!?」
そのうちのひとりを見止めた瞬間、私は驚きのあまり声を上げそうになった。
というのも。
(す、すごいハンサム!)
すらりとした高身長、一目で上質とわかる洗練された服装。
何より一番目を惹いたのは、その容貌。
(もしかして、外国の俳優さん……かな?)
そこにいたのは、スクリーンでもちょっと見ないような完璧な美貌の、外国人男性だった。
連れ立っているのは、大学生くらいに見える男の子と女の子。
男の子は幼さが残る風貌で、かわいいと表現するのがぴったりだ。
髪をポニーテールにした女の子は、明るく快活そうだ。
「ただいま、翠さん!」
女の子が声を上げると、店主はカウンターから出てきて三人を迎えた。
「みんな、おかえりなさい。後からお茶とスコーンを持っていくわね」
「ありがとうございます」
男の子は礼儀正しく頭を下げてから、先を行く二人を追う。
しかし。
(あ、あれ?)
てっきりこちらにやってくると思っていた三人は、カウンターの脇を抜け、店の奥に入っていった。
(お客、じゃないのかな……)
非日常の中で、さらに不思議な光景を見てしまい、頭の中に疑問符がいくつも浮かぶ。
首を捻ってあれこれ想像していると、再び木の床を踏む足音が近付いてきた。
「お待たせしました。ミルクティーと、おすすめのケーキ、ヴィクトリア・サンドウィッチです」
銀色の盆を持った女性は、柔らかく微笑んだ。
思わず見とれている間に、ポットやカップ、そしてケーキが乗った皿がテーブルに並べられていく。
「どうぞごゆっくり」
その声を聞きながら、あらためてケーキの皿を見遣る。
(……これが、おすすめ?)
小花が描かれたアンティーク調の皿に乗っているのは、デコレーションや細工のない、素朴な焼き菓子だった。
きつね色に焼けた二枚のスポンジで、赤いジャムと白いクリームを挟んである。
飾りといえば、ケーキの上面にかけられた白い粉末――砂糖だろう、それだけ。
(こんな素敵なお店なのに……なんだか地味で冴えないケーキ)
紙ナプキンの上に置かれたフォークを手に取り、そっとケーキに差し込んだ。
(あれ?フワフワじゃない。フォークが沈むような、しっとりした感じ……)
カットした一切れを口元に運ぶと、甘酸っぱいジャムの匂いとバターの香りが鼻先を掠めた。
(いい匂い……)
口に含むと――。
「……っ!!」
一番に感じたのは、ジャムの華やかな酸味。
味に色があるのなら、まさに――深紅。
こんなにも鮮烈な味のジャムを、私はこれまでに食べたことがない。
次に口に広がったのは、クリームのまろやかな味わいだ。
生クリームよりもコクのあるミルクの風味が、ねっとりとジャムの酸味を包み込む。
最後にしっとりとしたスポンジが、それらをまとめて浚っていった。
(……すごい……)
味の余韻を逃がしたくなくて、鼻から息が漏れることすら惜しくなる。
飲み込んで、すぐに次のひと口を……と思ったところで、ティーポットが目に入った。
頼んだのはミルクティーだから、これに入っているのだろう。
そっと蓋を開けると、琥珀色の液体がなみなみと入っていた。
(あれ? ミルクは……)
テーブルの上をぐるりと見ると、空のカップの隣に、白い液体で満たされたピッチャーが置かれていた。
(これを混ぜて飲むのか……)
ポットの紅茶をカップに注ぎ、ピッチャーを傾ける。
紅茶とミルクがマーブル模様を描くそれをスプーンでひとまぜして、口に運んだ。
「えっ!?」
思わず声が漏れた。――美味しい。
(なに、これ……これが紅茶なの?)
ティーカップに揺蕩う液体は、いつも飲んでいるペットボトルのそれとは比べ物にならないくらい、香りも味も濃厚だった。
(砂糖を入れてないのに、甘い)
香りの強い紅茶は、けれどミルクのこっくりとした味を殺しはしない。
「……絶妙だわ」
それ以外の言葉が見つからない。
私は夢中で、目の前に差し出された奇跡のような紅茶とケーキを楽しんだ。
***
「ありがとうございました」
女主人の穏やかな声と笑顔に送り出されて、私は店を後にした。
宣言通りというか、なんというか――結局私は、ケーキをおかわりした。
「いいのよ、今日はね!」
誰に言うでもなく、強気に言い放つ。
その声に、私は気が付いた。
(……あれ、元気になってる?)
まるで魔法のようだ。
この店に流れる空気も、妖精のような女主人も、そして絶世の美男も。
全てが子どもの頃に読んだ、お伽話の世界。
(まさか振り返ったら消えてる、なんてこと……ないよね?)
しかし振り返った目線の先に、間違いなくその店はあった。
「ローズメリー……推せるわ、このお店」
家を出るときは重かった足取りが、今は嘘のように軽い。
(疲れたらまた来よう。あの扉の向こうは、私史上最高の癒しスポットよ!)
これから先、この地で過ごす日々に希望が灯る。
一歩を踏み出した靴音は、青く晴れ渡った空に高らかに響いた。
秘密はいつもティーカップの向こう側 BONUS TRACK
ぬくもりのティールーム / 完
◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側
本編もアルファポリスで連載中です☕
ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」
シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」
シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」
シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

秘密はいつもティーカップの向こう側 ~追憶の英国式スコーン~
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
紅茶がつなぐのは、人の想いと、まだ癒えぬ記憶。
大学生・湊と英国紳士・亜嵐が紡ぐ、心を温めるハートフル・ストーリー。
――つまり料理とは、単なる習慣ではなく、歴史の語り部でもあるのだよ――
その言葉に心を揺らした大学生・藤宮湊は、食文化研究家にしてフードライターの西園寺亜嵐と出会う。
ひょんな縁から彼と同じテーブルで紅茶を飲むうちに、湊は『食と心』に秘められた物語へと惹かれていく。
舞台は、ティーハウス<ローズメリー>
紅茶の香りが、人々の過去と未来を優しく包み込み、二人の絆を静かに育んでいく――。
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

秘密はいつもティーカップの向こう側 ~サマープディングと癒しのレシピ~
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
紅茶とともに、人の心に寄り添う『食』の物語、再び。
「栄養学なんて、大嫌い!」
大学の図書館で出会った、看護学部の女学生・白石美緒。
彼女が抱える苦手意識の裏には、彼女の『過去』が絡んでいた。
大学生・藤宮湊と、フードライター・西園寺亜嵐が、食の知恵と温かさで心のすれ違いを解きほぐしていく――。
ティーハウス<ローズメリー>を舞台に贈る、『秘密はいつもティーカップの向こう側』シリーズ第2弾。
紅茶と食が導く、優しくてちょっぴり切ないハートフル・キャラ文芸。
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
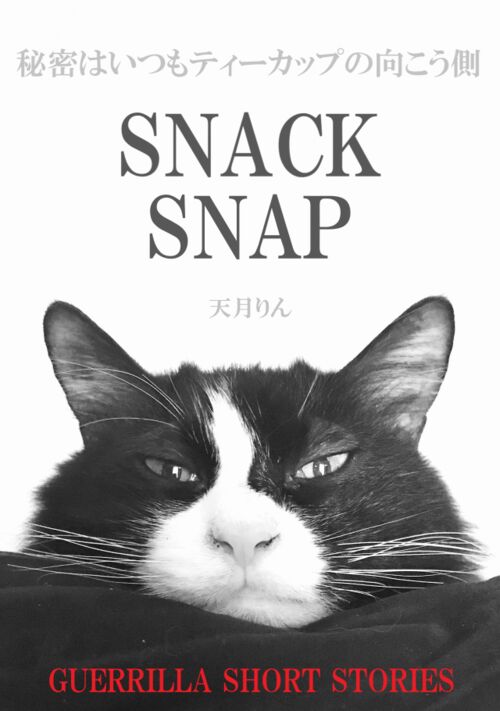
秘密はいつもティーカップの向こう側 ―SNACK SNAP―
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
ティーハウス<ローズメリー>に集う面々に起きる、ほんの些細な出来事。
楽しかったり、ちょっぴり悲しかったり。
悔しかったり、ちょっぴり喜んだり。
彼らの日常をそっと覗き込んで、写し撮った一枚のスナップ――。
『秘密はいつもティーカップの向こう側』SNACK SNAPシリーズ。
気まぐれ更新。
ティーカップの紅茶に、ちょっとミルクを入れるようなSHORT STORYです☕
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側(本編) ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月

妻が通う邸の中に
月山 歩
恋愛
最近妻の様子がおかしい。昼間一人で出掛けているようだ。二人に子供はできなかったけれども、妻と愛し合っていると思っている。僕は妻を誰にも奪われたくない。だから僕は、妻の向かう先を調べることににした。


『後宮祓いの巫女は、鬼将軍に嫁ぐことになりました』
由香
キャラ文芸
後宮で怪異を祓う下級巫女・紗月は、ある日突然、「鬼」と噂される将軍・玄耀の妻になれと命じられる。
それは愛のない政略結婚――
人ならざる力を持つ将軍を、巫女の力で制御するための契約だった。
後宮の思惑に翻弄されながらも、二人は「契約」ではなく「選んだ縁」として、共に生きる道を選ぶ――。

〖完結〗終着駅のパッセージ
苺迷音
恋愛
分厚い眼鏡と、ひっつめた髪を毛糸帽で覆う女性・カレン。
彼女はとある想いを胸に北へ向かう蒸気機関車に乗っていた。
王都から離れてゆく車窓を眺めながら、カレンは振り返る。
夫と婚姻してから三年という長い時間。
その間に夫が帰宅したのは数えるほどだった。
※ご覧いただけましたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















