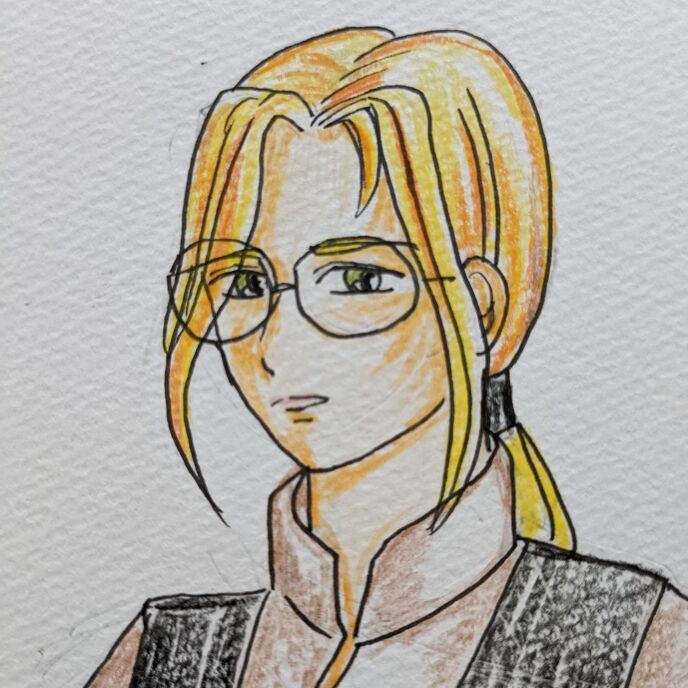10 / 15
第十章 崩御
しおりを挟む
アスケニア歴五四四年十月ーー。
十八代国王の御世になって十二年。国民の許される催しや娯楽と言えば、結婚式ぐらいしかない。
今の王様は人を信用せず、とても嫉妬深い御方と噂に聞いていた。彼が即位してから多くの国民が粛清され、命を落としていた。
粛清の対象になったのは、今の王様に退位を求める官僚や貴族。
王様よりも才能や知識のある学者。宗教家。研究者。芸術家。ギルドの長たち。なかには無実の罪を着せられて処刑された者もいた。
かつての王都は、海外からの交易船で運ばれた異国からの舶来品。食材。香辛料などが市場に並び、町には大道芸人や路上演奏家で賑わっていた。今はその面影もなく、人々から笑顔と華やかさが消えて、もう何年になるだろう。
このままでは、今の王様に国の希望はないと、国民の誰もが噂していた。
※
先代の十七代国王が、首相だった頃、アスケニア国で『男女社会平等宣言』という、政策が打ち出された。今から十五年程前の事である。
世襲と、多民族国家であるこの国において、身分格差や人種、男女差別を廃止し、貴族も庶民も、ひとつの職業として互いを尊重し、女性も親の稼業や土地。仕事。財産を引き継ぐことができるという平等政策。
これにおいて、女性は結婚後もこれまでと同じように、職場で働けて、出産後は三年間の育休と、保育所も充実した。
これまでの女性は、結婚後、家事や子育てに専念し、家で仕事することが当たり前とされていた。しかし、夫に早く先立たれた場合、その後の妻の暮らしは、『再婚』か『修道院』しか居場所がなかった。
女性に財産の相続権は無く、息子のいない家計だと、親族に財産を没収され、嫁や娘は追い出されるのが貴族でも当たり前の社会とされた。
夫が死別しても、実家に戻る事が許されず、母子心中という事件も多発した。
『女性は、跡取りを産んでくれる大切な人財であり、自立、独立、自由、平等を得る権利がある。』と、国は職業訓練学舎を作り、寡婦や、職人、商人が男女関係なく自立して学べる専門校を各地方に幾つも作って、国の人材を向上させた。
あれから十年過ぎた今、この国では女性の労働者が八割を締めている。
出生率は二・八と、一世帯に二、三人の子供が普通で、男女の結婚年齢の平均は、二十三歳前後。当時の国民には頑張ればそれだけ報われるという希望があった。
しかし、今の王様の御時世、結婚、出生率が年々、減少傾向にある。
失業者の増加と、治安悪化。重税も国民の生活に影響している。
いづれにしても、この独裁政権に歯止めをかけなくてはならない所まで国は追い詰められていた。
※
結婚式から一夜が明けた。
初夜の甘い一時を引きずっていたい気分ではあるが、今日から二人の新たな人生が始まる。
目を覚ますと、自分の腕の中には妻となったノアーサがいた。彼女の肌の温もりが人肌を通して伝わってくる。
三年前に両親を失い、天涯孤独になってしまった自分を、側でいつも支え、励ましてくれたノアーサ。これからはもう一人ではない。彼女と夫婦になった。その事が何よりも嬉しい。
「おはようございます。お目覚めでしょうか。」
扉の向こう側から、侍従の声が聞こえてきた。普段はノックして返事をすれば扉が開くのだか、初夜から一夜明けた今朝は配慮してくれているようだ。
カノイは扉越しに返事をする。
扉を挟んで、侍従が風呂と朝食を用意している事を伝えた。その声にノアーサが目を覚ましたようである。
考えて見れば、山岳の村から王都に戻ってまだ、一月しか経っていないのに、亡き親の領地を引き継ぐと同時に、十年共に訓練を積んできた、ノアーサと結婚までしてしまうとは。
自分の両親が生きていたなら、この結婚は、もう少し後になっていただろう。
ノアーサの母親も、恐らく、離れていた娘との時間を埋めるように、常に側にいて、手放そうとはしなかったに違いない。
ノアーサが起きたのを確認すると、二人は風呂と朝食を共にする。夫婦になると、一緒というのが、当たり前のようだ。
暗殺者として、子供の頃から一緒に訓練を受け、暮らして来た。日常生活に於いてはあの頃と何も変わらない。
ノアーサは、朝食を済ませた後、結婚式で届いた祝いの品を侍従のメアリと整理している。
『主君』が二人に贈った祝いの品は「称号」と二人のために誂えた制服。今後は彼の元に「護衛騎士」として仕える事になりそうだ。
ノアーサは、昨夜読み出せなかったアンの手紙を思いだし、読み始めた。
王女アンジェリカとしてでなく、義姉のアンとして、ノアーサ個人に宛てられた手紙である。
私の愛する妹 ノアーサへ
ノアーサ。結婚おめでとう。私は看護師として、貴方たち二人のお母さんを見てきたから解る。二人はきっと貴方たちを祝福していると思うわ。私も嬉しい。
貴方たちと共に過ごした村での生活は、今でも良い思い出よ。
私は、身内同士で争う王族の環境に嫌気が指して、数年前に、従兄弟であるウィルフォンス卿を頼り、この国で、看護師の勉強を始めました。
騎士団の看護師に配属されて、ノルマンと出逢った。運命って不思議ね。ウィルが育てていた子が、まさか、ノルマンの妹だったなんて。
母国タルタハを捨てた私が再び、国に戻ったのは、曾祖父の危篤と、王位継承者として、私が選ばれたから。
私は辞退を願い出たけど、危篤の王様を介護するうちに、国の事情を知り、連れて来た「村人」たちやノルマンの協力もあって、私は、王位を継承する覚悟ができました。
ノアーサ。私のお腹に、新たな命が育っています。順調にゆけば、春には産まれる予定よ。貴女も早く、授かると良いわね。
貴方たちの『主君』であるウィルは、とても親しみやすい方よ。きっと良い国に導いてくれる。彼を王様へと導いてね。
貴方たちに、気楽に逢う事は叶わなくなってしまうけど、アスケニアとタルタハが、かつてのように往来し親睦を深めるように私も努力する。近いうちに良い知らせがあることを願っています。
貴方の姉 アンより
手紙を読んで、ノアーサは胸が熱くなった。義姉であったアンの国、タルタハは今、王様が危篤と聞いている。崩御も時間の問題だ。兄もそんな彼女を支え、即位させるため、彼女の体を気遣い、懸命に働いている事だろう。
「奥様。祝いのお手紙ですか?」
侍従のメアリの声に自分の事かと、気付く。改めて、自分が既婚者になったのだと思った。
「ええ、私の大切な親族から」
ノアーサはそう、伝えた。
「それより、書斎にお客様がお見えのようだけど、私も挨拶した方が良いかしら」
ノアーサは先程、村の教会で教鞭をとっているシリウスが屋敷に入ってゆくのを見かけた。
農地で訪ねたい事があって呼んだのかも知れない。
カノイは領主としての仕事に慣れようと必死なようだ。領地相続の手続きに負われ、ノアーサの父親が今日、休日を利用して、加勢に来ていた。
「大切なお話のようです。奥様は、お見送りだけでよろしいかと」
メアリはそう告げながら、手際よく祝いの品を片付けてゆく。
「その、奥様という言葉、まだ慣れないわ。カノイも夫というより、同胞だったから」
ノアーサはメアリにそう伝えた。
「大旦那様と大奥様も夫婦というより、同胞でしたよ。お勤め先は、ご一緒と聞いておりますが」
そう言いながら、二人に届いた制服を手入れしている。
「とても洒落た軍服。お仕えする主様から、お二方は大切にされているのですね」
黒の生地に赤い縁の入った制服を着た二人は、その後、ウィルフォンス卿の側近として、その十数年後に、歴史書に記される存在となった。
※
カノイは、書斎でノアーサの父親と、領地で教鞭を取るシリウスと話をしていた。
「父、亡き後も、領民を指導して下さり感謝します」
カノイはシリウスに礼を述べた。
「領主様から御礼を頂けるなんて。私は、先代の領主様から命を救って頂いた御恩があります」
かつて王宮が管理する農業試験所で作物の研究をしていた彼は、今の王様からの粛清を逃れ、この領地に匿われていた。
「あなたのお陰で、領民は飢えずに暮らしてゆける。僕は領主を引き継いだばかりなので、心強いです」
「義息子を頼みます。先代の領主、カエサルとは親友で、王国騎士団の同胞です」
ノアーサの父親がシリウスに挨拶する。両親亡き今、義理の親を立て、自身の後ろ楯があることを領民に知らせる必要があった。
「早速ですが、式の参列ありがとうございます」
シリウスはその言葉で、自分がこの屋敷に呼ばれた理由を悟った
「近いうちに国は変わりますよ。あの御方によって」
カノイはシリウスを信用できる人と見込んで話した。義理の父親である王国騎士団総長、ノルディックを挟んでの会話だけに、シリウスは緊張が走る。
「私が、王宮の農業試験所にいたのは過去のこと。式の日に『あの御方』から直接、話しかけられはしましたが」
彼は怯えた口調で話した。
「ご安心下さい。罪人として罰するのではなく、王宮での真実が知りたいだけです」
ノルディックがそう尋ねた。彼は王様の不正を掴もうとしている。
「王様は、私に芥子の栽培をするようにと。宮中の温室で密かに育てておりました」
国で厳しく取り締まっている薬物を、王様自らが 所持。薬物中毒との噂は本当らしい。
「芥子は痛み止め薬として栽培されますが、王様は煙草の製造を我々に頼みました」
かつては高級煙草として貴族たちの間で普及した『阿片』。吸引中毒に陥り、堕落していった人たちが多くいた。
国は阿片を禁止して、密輸の取り締まりを強化。見つかれば身分に関係なく厳罰に課せられる。
「あなたの協力に感謝します」
ノアーサの父親がそう答えた。
「貴方は村にとって、大切な人材です。これからも領民を指導していって欲しい。」
カノイはシリウスに語りかける。
「ありがとうございます」
シリウスは、挙式の日にウィルフォンスに出逢い、彼が王国を変えてくれる人物であると悟ったという。
「僕は前王の国家を知りません。しかし、前王に仕えた人たちの教育を、妻と受けました。身分相応に豊かで、自由な社会であったと」
「はい。先代の王様は気さくで、ウィルフォンス卿にどこか性格が似ております。『良き叔父だった』と彼が挙式で、私に直接、話してくださりました」
シリウスは昔を懐かしむように語った。彼は前国王と同い年。当時、王宮の植物園で研究員をしていたという。
ウィル卿の母親は、前王とは兄妹で第三王女。十六歳でタルタハに嫁いでいた。
前王は植物から、薬や精油を採取する工程が面白いと、研究室を訪れては熱心にその工程を見学していたという。
「前王は植物園での出来事を、ウィル卿に、話されていたようです。当時は、タルタハとアスケニアの交易が盛んでしたから」
「素晴らしいですね」
カノイがそう呟く。彼自身もそういう時代がまた、戻って来て欲しいと願った。
※
「お帰りになったようですね」
シリウスの帰りを見送り、ノアーサはカノイと父親のいる書斎へと顔を出した。
「お仕事は片付いた?」
「一応。仕事内容は、何とか理解できたよ」
カノイは、ノアーサの父親が指導してくれて助かったと話した。
「では、お父さんに個人的な話をしても良いかしら」
そういって二人が座る前のテーブルに兄夫婦の手紙を置いた。
「兄さんたちから、結婚を祝福する手紙が届いたわ。お父さんに報告しておこうと思って」
ノアーサは、この手紙から、アンと『主君』が従兄弟同士であることや、兄夫婦に子供が授かった事を父親に話した。
「王国騎士団にも二人の情報は入って来たが、まさか嫁のアンが隣国の王女で、息子が王配になるとはな」
ノルディックからは、少し複雑で寂しげな思いが伝わってくる。
「あいつはアンがいたことで、随分、救われたと思う」
「僕は、ノルマンに救われました。両親が亡くなって天涯孤独になってしまった僕に『これからは俺たちがお前の家族だ。』と言ってくれた。あの時は嬉しかった」
カノイはノルマン夫妻と、村の生活を送る中で、剣の手合わせも含め、多くの事を教わったと義父のノルディックに伝えた。
「お父さん、兄さんなら、きっと王配としての役目も果たせると思う」
「そう、信じて今は見守るしかないだろう」
ノアーサの父はそれ以外の言葉が見つからないようだ。
「どうやら、私の子供たちは、二人とも王族と御縁があるようだ。だが、お前たちは王族に仕える騎士であって、王族ではない。今後は騎士として、『主君』を御守りするんだ」
ノアーサの父親は二人に言い聞かせた。
昨日の二人の結婚式の裏側で、ウィル卿はこの国に今後、必要な人材に改革を呼びかけた事だろう。
十年近く、粛清や圧政により国民を苦しめていた王様の時代が終わりを告げようとしていた。
※
タルタハの国王、ジークベネディクト八世 崩御 享年九十二歳ーーー
隣国、タルタハの国王崩御の知らせが入ったのは、二人の結婚式から二週間後の事であった。
結婚式の後、二人は暫く領地に滞在し、領民との交流を深め、新婚生活を過ごした。
ウィル卿に呼び出されたのは、昨日の夕刻。翌朝には出勤するように言われ、昨夜のうちに王都の屋敷に戻って来ていた。
一夜明けて、二人はウィル卿から送られた制服に身を包み、王都の屋敷で朝食をとっている。
「ご主人様。奥様。昨夜は良くお休みになられましたか」
執事のロバートが、二人にお茶を注ぎながら、話しかける。
「お陰様で。領地が落ち着いたら、次は王都。父さんたちも、領地と王国騎士団を往復していたのかな」
カノイは、屋敷で両親のいた頃から、執事を勤めているロバートに訪ねた。
「はい。カノイ様もご一緒に、ご家族で移動されてましたよ。覚えておりますでしょうか」
朧気ながらだが、両親と過ごした日々の記憶がある。父が領地の葡萄畑に連れて行ってくれた。領民たちに倅だと、紹介され恥ずかしくて俯いた子供時代。父の肩車で、領地の葡萄を一房積んだ記憶がある。
「覚えているよ。僕は両親から、沢山の愛情を受けて育った。そして、両親を知る皆が、『いい人だった』といってくれる事が嬉しい。ノアーサ、僕もそんな父親になりたい」
カノイはノアーサを見る。
「それって、子供が欲しいって事かしら」
ノアーサが、困ったように言葉を返す。
「いづれにしても仲睦まじい。そろそろお時間ですよ。ご主人様。奥様」
執事のロバートに見送られながら、二人はウィル卿の勤める内閣府へと向かった。
※
国の政治。財政等を扱う内閣府は王宮の一角にあり、二人は政府の役人に、ウィル卿の執務室へと通された。
「我が子らよ。待っていたよ。制服も似合っている」
そう言うと、二人を側の椅子へと座らせる。
「タルタハの国王が、崩御の知らせは聞いていると思う。君たちの兄妹が王に即位する時が来た」
ウィル卿はタルタハの今後について語り始めた。
今後一年、タルタハ王国は喪に服して、即位や戴冠式は来年の秋になるという。その間に女王となる義姉のアンジェリカは、出産を控えている。そんな身重の女王に代わって、王配である兄のノルマンが、大葬や国の行政を代行で行い、『王配に恵まれた女王』だと、タルタハでは早くも噂になっていると話してくれた。
「さて、我々も行動に移さねば。早速、国民も動き始めたようだ。君たちの結婚式を境にね」
そういうと、一咳して二人に訪ねる。
「ところで君たち、夫婦の勤めは毎夜、果たしているかね」
さっきの真面目な表情から一転して、冗談めいた口調で語り出す。
「子供の作り方を知らずに結婚したのではと、気になってな。さて、本題に入るとしょう」
そういうと、彼は、今の国王と自身の過去を打ち明けた。
「私が、慕っていた叔父の十七代国王エルベルトは、私にとっては叔父にあたる今の、十八代国王ヘンリーによって暗殺された」
ウィル卿が、先代国王の死において語り始めた。
今の国王は、十六代国王の弟(内親王)の子供である。彼の父親は体が弱く、彼の側で侍従として、世話をしていた女性との間にヘンリーは産まれた。
彼は両親の顔を知らない。父親は彼の誕生を待たずして、この世を去り、母も彼を産んで直ぐに、侍従を辞めて城を出た。
それでも『弟の忘れ形見』だと、十六代国王はヘンリーを養子に迎え、王子として育ててきた。
「叔父のエルベルトは、面倒見が良くて、誰とでも親しくなれた。一方で、ヘンリーは常に孤独を抱え、何事にも悲観的だったよ」
ウィル卿は子供の頃、母の故郷であるこのアスケニアに何度か訪れて、叔父の家族と過ごした。叔父が王様に即位した時は嬉しかったという。
「叔父が亡くなる十日前に、私の母親宛に手紙が届いた。その手紙には、『自分はヘンリーに殺されるかも知れない』と書いてあったそうだ。それから間もなくして、崩御との知らせが。その後、ヘンリーが即位。即位後は粛清と圧政の『暗黒期』の始まりだ」
「今の国王が、何故、簒奪し王に即位したのか、その理由を聞かせて貰えませんか?」
カノイがウィル卿に訪ねる。
「自分を棄てた母親が、王様になったら、名乗り出てくれると思っていたのかも知れない。だが、彼の母親は城を出て間もなく、病死していたのだ」
ウィル卿は更に続けた。
「私は、叔父の無念を晴らしたい。この王国の、民俗や身分格差を弛くして、女性の自立を実現させた。彼は勇気ある王様だった」
「あの、ひとつ質問をして良いですか」
ノアーサが訪ねる。
「『主君』の事を、今の王様は御存知なのでしょうか?」
「私は、仕事で何度も謁見しているが、偽名で、髪の色も変えている。因みに、本来の髪の色は赤毛ではないぞ。まあ、元の髪色に戻しても、彼は、甥の私を覚えてはいないだろう」
ウィル卿は、エルベルト国王が崩御後、死の真相を追及するために国籍を変え、内閣府の役人として勤めるようになる。
役人になって、粛清を言い渡された人たちの死亡届を偽装し、国内で辺境地や、騎士の領地で匿わせた。
王様の目が届かない場所で、国民を守るための努力はしたが、やはり、すべての国民を救うのは難しい。今の王様が即位してから十年の間に、三千万人もの国民が、命を落としているのである。
「僕達が、育った村も、粛清を逃れた人たちを集めた村だったんですね。でも、独特な民俗衣装と、文字や言葉にも、この大陸にはない特徴があった」
「あの村は、『東方の島国から渡来した人達』が開拓した場所と聞いている。君らは、あの国の文字や言語を理解できるのかね」
二人は、『はい』と答えた。黒い瞳と黒い髪の人達が多い村。独特な剣術や馬術も教わった。
村では稲作が行われ、田圃は水車で水を供給、その動力を活かしての精米。温泉という集団浴場はいつでも湯に浸かれた。
「あの村の住民は、落ち着いたら、また戻って来るだろう。タルタハとの国境区域。交易地点としても重要な交通路になる」
ウィル卿は、過去のすべてを語り終えると、一呼吸置いて呟いた。
「我が子らよ。簒奪するにあたり、君らに頼みたい事がある」
二人を見つめる眼差しが、普段は見ない表情で語りかける。
「もし、私がヘンリー国王のように暴君となってしまったら、迷わず私を斬り捨てて欲しい」
二人には、その言葉が深く心に突き刺さった。
「我が子らよ。君たちは私が作り上げた最高の『剣」と『盾』だ。だからこそ、君らにお願いする」
「それだけの覚悟を持って、即位なさるのですね」
カノイがそう言葉を返した。
「解りました。ノアーサいいね」
カノイは、ノアーサに声をかけると彼女は頷いた。そして、二人は、ウィル卿の前に右膝を付いて、カノイは剣をノアーサは短剣を抜いて胸に掲げた。
「私、カノイ・フォンミラージュと、妻、ノアーサ・フォンミラージュは貴方に絶対の忠義を尽くす事を、この剣にかけて誓います」
二人はウィル卿に騎士として仕える誓いの言葉を述べた。
「我が子らよ」
ウィル卿は、二人の前に腰を下ろして目線を合わせた。
「私はエルベルト国王の意思を引き継いで、王国を復活させてみせる」
彼は、これだけの強い意思で国王に即位する意思を固めている。彼なら、国民が豊かに暮らせる国家を作る事ができると二人は確信した。
この日、簒奪に向けて時計の針が動き始めたのである。
十八代国王の御世になって十二年。国民の許される催しや娯楽と言えば、結婚式ぐらいしかない。
今の王様は人を信用せず、とても嫉妬深い御方と噂に聞いていた。彼が即位してから多くの国民が粛清され、命を落としていた。
粛清の対象になったのは、今の王様に退位を求める官僚や貴族。
王様よりも才能や知識のある学者。宗教家。研究者。芸術家。ギルドの長たち。なかには無実の罪を着せられて処刑された者もいた。
かつての王都は、海外からの交易船で運ばれた異国からの舶来品。食材。香辛料などが市場に並び、町には大道芸人や路上演奏家で賑わっていた。今はその面影もなく、人々から笑顔と華やかさが消えて、もう何年になるだろう。
このままでは、今の王様に国の希望はないと、国民の誰もが噂していた。
※
先代の十七代国王が、首相だった頃、アスケニア国で『男女社会平等宣言』という、政策が打ち出された。今から十五年程前の事である。
世襲と、多民族国家であるこの国において、身分格差や人種、男女差別を廃止し、貴族も庶民も、ひとつの職業として互いを尊重し、女性も親の稼業や土地。仕事。財産を引き継ぐことができるという平等政策。
これにおいて、女性は結婚後もこれまでと同じように、職場で働けて、出産後は三年間の育休と、保育所も充実した。
これまでの女性は、結婚後、家事や子育てに専念し、家で仕事することが当たり前とされていた。しかし、夫に早く先立たれた場合、その後の妻の暮らしは、『再婚』か『修道院』しか居場所がなかった。
女性に財産の相続権は無く、息子のいない家計だと、親族に財産を没収され、嫁や娘は追い出されるのが貴族でも当たり前の社会とされた。
夫が死別しても、実家に戻る事が許されず、母子心中という事件も多発した。
『女性は、跡取りを産んでくれる大切な人財であり、自立、独立、自由、平等を得る権利がある。』と、国は職業訓練学舎を作り、寡婦や、職人、商人が男女関係なく自立して学べる専門校を各地方に幾つも作って、国の人材を向上させた。
あれから十年過ぎた今、この国では女性の労働者が八割を締めている。
出生率は二・八と、一世帯に二、三人の子供が普通で、男女の結婚年齢の平均は、二十三歳前後。当時の国民には頑張ればそれだけ報われるという希望があった。
しかし、今の王様の御時世、結婚、出生率が年々、減少傾向にある。
失業者の増加と、治安悪化。重税も国民の生活に影響している。
いづれにしても、この独裁政権に歯止めをかけなくてはならない所まで国は追い詰められていた。
※
結婚式から一夜が明けた。
初夜の甘い一時を引きずっていたい気分ではあるが、今日から二人の新たな人生が始まる。
目を覚ますと、自分の腕の中には妻となったノアーサがいた。彼女の肌の温もりが人肌を通して伝わってくる。
三年前に両親を失い、天涯孤独になってしまった自分を、側でいつも支え、励ましてくれたノアーサ。これからはもう一人ではない。彼女と夫婦になった。その事が何よりも嬉しい。
「おはようございます。お目覚めでしょうか。」
扉の向こう側から、侍従の声が聞こえてきた。普段はノックして返事をすれば扉が開くのだか、初夜から一夜明けた今朝は配慮してくれているようだ。
カノイは扉越しに返事をする。
扉を挟んで、侍従が風呂と朝食を用意している事を伝えた。その声にノアーサが目を覚ましたようである。
考えて見れば、山岳の村から王都に戻ってまだ、一月しか経っていないのに、亡き親の領地を引き継ぐと同時に、十年共に訓練を積んできた、ノアーサと結婚までしてしまうとは。
自分の両親が生きていたなら、この結婚は、もう少し後になっていただろう。
ノアーサの母親も、恐らく、離れていた娘との時間を埋めるように、常に側にいて、手放そうとはしなかったに違いない。
ノアーサが起きたのを確認すると、二人は風呂と朝食を共にする。夫婦になると、一緒というのが、当たり前のようだ。
暗殺者として、子供の頃から一緒に訓練を受け、暮らして来た。日常生活に於いてはあの頃と何も変わらない。
ノアーサは、朝食を済ませた後、結婚式で届いた祝いの品を侍従のメアリと整理している。
『主君』が二人に贈った祝いの品は「称号」と二人のために誂えた制服。今後は彼の元に「護衛騎士」として仕える事になりそうだ。
ノアーサは、昨夜読み出せなかったアンの手紙を思いだし、読み始めた。
王女アンジェリカとしてでなく、義姉のアンとして、ノアーサ個人に宛てられた手紙である。
私の愛する妹 ノアーサへ
ノアーサ。結婚おめでとう。私は看護師として、貴方たち二人のお母さんを見てきたから解る。二人はきっと貴方たちを祝福していると思うわ。私も嬉しい。
貴方たちと共に過ごした村での生活は、今でも良い思い出よ。
私は、身内同士で争う王族の環境に嫌気が指して、数年前に、従兄弟であるウィルフォンス卿を頼り、この国で、看護師の勉強を始めました。
騎士団の看護師に配属されて、ノルマンと出逢った。運命って不思議ね。ウィルが育てていた子が、まさか、ノルマンの妹だったなんて。
母国タルタハを捨てた私が再び、国に戻ったのは、曾祖父の危篤と、王位継承者として、私が選ばれたから。
私は辞退を願い出たけど、危篤の王様を介護するうちに、国の事情を知り、連れて来た「村人」たちやノルマンの協力もあって、私は、王位を継承する覚悟ができました。
ノアーサ。私のお腹に、新たな命が育っています。順調にゆけば、春には産まれる予定よ。貴女も早く、授かると良いわね。
貴方たちの『主君』であるウィルは、とても親しみやすい方よ。きっと良い国に導いてくれる。彼を王様へと導いてね。
貴方たちに、気楽に逢う事は叶わなくなってしまうけど、アスケニアとタルタハが、かつてのように往来し親睦を深めるように私も努力する。近いうちに良い知らせがあることを願っています。
貴方の姉 アンより
手紙を読んで、ノアーサは胸が熱くなった。義姉であったアンの国、タルタハは今、王様が危篤と聞いている。崩御も時間の問題だ。兄もそんな彼女を支え、即位させるため、彼女の体を気遣い、懸命に働いている事だろう。
「奥様。祝いのお手紙ですか?」
侍従のメアリの声に自分の事かと、気付く。改めて、自分が既婚者になったのだと思った。
「ええ、私の大切な親族から」
ノアーサはそう、伝えた。
「それより、書斎にお客様がお見えのようだけど、私も挨拶した方が良いかしら」
ノアーサは先程、村の教会で教鞭をとっているシリウスが屋敷に入ってゆくのを見かけた。
農地で訪ねたい事があって呼んだのかも知れない。
カノイは領主としての仕事に慣れようと必死なようだ。領地相続の手続きに負われ、ノアーサの父親が今日、休日を利用して、加勢に来ていた。
「大切なお話のようです。奥様は、お見送りだけでよろしいかと」
メアリはそう告げながら、手際よく祝いの品を片付けてゆく。
「その、奥様という言葉、まだ慣れないわ。カノイも夫というより、同胞だったから」
ノアーサはメアリにそう伝えた。
「大旦那様と大奥様も夫婦というより、同胞でしたよ。お勤め先は、ご一緒と聞いておりますが」
そう言いながら、二人に届いた制服を手入れしている。
「とても洒落た軍服。お仕えする主様から、お二方は大切にされているのですね」
黒の生地に赤い縁の入った制服を着た二人は、その後、ウィルフォンス卿の側近として、その十数年後に、歴史書に記される存在となった。
※
カノイは、書斎でノアーサの父親と、領地で教鞭を取るシリウスと話をしていた。
「父、亡き後も、領民を指導して下さり感謝します」
カノイはシリウスに礼を述べた。
「領主様から御礼を頂けるなんて。私は、先代の領主様から命を救って頂いた御恩があります」
かつて王宮が管理する農業試験所で作物の研究をしていた彼は、今の王様からの粛清を逃れ、この領地に匿われていた。
「あなたのお陰で、領民は飢えずに暮らしてゆける。僕は領主を引き継いだばかりなので、心強いです」
「義息子を頼みます。先代の領主、カエサルとは親友で、王国騎士団の同胞です」
ノアーサの父親がシリウスに挨拶する。両親亡き今、義理の親を立て、自身の後ろ楯があることを領民に知らせる必要があった。
「早速ですが、式の参列ありがとうございます」
シリウスはその言葉で、自分がこの屋敷に呼ばれた理由を悟った
「近いうちに国は変わりますよ。あの御方によって」
カノイはシリウスを信用できる人と見込んで話した。義理の父親である王国騎士団総長、ノルディックを挟んでの会話だけに、シリウスは緊張が走る。
「私が、王宮の農業試験所にいたのは過去のこと。式の日に『あの御方』から直接、話しかけられはしましたが」
彼は怯えた口調で話した。
「ご安心下さい。罪人として罰するのではなく、王宮での真実が知りたいだけです」
ノルディックがそう尋ねた。彼は王様の不正を掴もうとしている。
「王様は、私に芥子の栽培をするようにと。宮中の温室で密かに育てておりました」
国で厳しく取り締まっている薬物を、王様自らが 所持。薬物中毒との噂は本当らしい。
「芥子は痛み止め薬として栽培されますが、王様は煙草の製造を我々に頼みました」
かつては高級煙草として貴族たちの間で普及した『阿片』。吸引中毒に陥り、堕落していった人たちが多くいた。
国は阿片を禁止して、密輸の取り締まりを強化。見つかれば身分に関係なく厳罰に課せられる。
「あなたの協力に感謝します」
ノアーサの父親がそう答えた。
「貴方は村にとって、大切な人材です。これからも領民を指導していって欲しい。」
カノイはシリウスに語りかける。
「ありがとうございます」
シリウスは、挙式の日にウィルフォンスに出逢い、彼が王国を変えてくれる人物であると悟ったという。
「僕は前王の国家を知りません。しかし、前王に仕えた人たちの教育を、妻と受けました。身分相応に豊かで、自由な社会であったと」
「はい。先代の王様は気さくで、ウィルフォンス卿にどこか性格が似ております。『良き叔父だった』と彼が挙式で、私に直接、話してくださりました」
シリウスは昔を懐かしむように語った。彼は前国王と同い年。当時、王宮の植物園で研究員をしていたという。
ウィル卿の母親は、前王とは兄妹で第三王女。十六歳でタルタハに嫁いでいた。
前王は植物から、薬や精油を採取する工程が面白いと、研究室を訪れては熱心にその工程を見学していたという。
「前王は植物園での出来事を、ウィル卿に、話されていたようです。当時は、タルタハとアスケニアの交易が盛んでしたから」
「素晴らしいですね」
カノイがそう呟く。彼自身もそういう時代がまた、戻って来て欲しいと願った。
※
「お帰りになったようですね」
シリウスの帰りを見送り、ノアーサはカノイと父親のいる書斎へと顔を出した。
「お仕事は片付いた?」
「一応。仕事内容は、何とか理解できたよ」
カノイは、ノアーサの父親が指導してくれて助かったと話した。
「では、お父さんに個人的な話をしても良いかしら」
そういって二人が座る前のテーブルに兄夫婦の手紙を置いた。
「兄さんたちから、結婚を祝福する手紙が届いたわ。お父さんに報告しておこうと思って」
ノアーサは、この手紙から、アンと『主君』が従兄弟同士であることや、兄夫婦に子供が授かった事を父親に話した。
「王国騎士団にも二人の情報は入って来たが、まさか嫁のアンが隣国の王女で、息子が王配になるとはな」
ノルディックからは、少し複雑で寂しげな思いが伝わってくる。
「あいつはアンがいたことで、随分、救われたと思う」
「僕は、ノルマンに救われました。両親が亡くなって天涯孤独になってしまった僕に『これからは俺たちがお前の家族だ。』と言ってくれた。あの時は嬉しかった」
カノイはノルマン夫妻と、村の生活を送る中で、剣の手合わせも含め、多くの事を教わったと義父のノルディックに伝えた。
「お父さん、兄さんなら、きっと王配としての役目も果たせると思う」
「そう、信じて今は見守るしかないだろう」
ノアーサの父はそれ以外の言葉が見つからないようだ。
「どうやら、私の子供たちは、二人とも王族と御縁があるようだ。だが、お前たちは王族に仕える騎士であって、王族ではない。今後は騎士として、『主君』を御守りするんだ」
ノアーサの父親は二人に言い聞かせた。
昨日の二人の結婚式の裏側で、ウィル卿はこの国に今後、必要な人材に改革を呼びかけた事だろう。
十年近く、粛清や圧政により国民を苦しめていた王様の時代が終わりを告げようとしていた。
※
タルタハの国王、ジークベネディクト八世 崩御 享年九十二歳ーーー
隣国、タルタハの国王崩御の知らせが入ったのは、二人の結婚式から二週間後の事であった。
結婚式の後、二人は暫く領地に滞在し、領民との交流を深め、新婚生活を過ごした。
ウィル卿に呼び出されたのは、昨日の夕刻。翌朝には出勤するように言われ、昨夜のうちに王都の屋敷に戻って来ていた。
一夜明けて、二人はウィル卿から送られた制服に身を包み、王都の屋敷で朝食をとっている。
「ご主人様。奥様。昨夜は良くお休みになられましたか」
執事のロバートが、二人にお茶を注ぎながら、話しかける。
「お陰様で。領地が落ち着いたら、次は王都。父さんたちも、領地と王国騎士団を往復していたのかな」
カノイは、屋敷で両親のいた頃から、執事を勤めているロバートに訪ねた。
「はい。カノイ様もご一緒に、ご家族で移動されてましたよ。覚えておりますでしょうか」
朧気ながらだが、両親と過ごした日々の記憶がある。父が領地の葡萄畑に連れて行ってくれた。領民たちに倅だと、紹介され恥ずかしくて俯いた子供時代。父の肩車で、領地の葡萄を一房積んだ記憶がある。
「覚えているよ。僕は両親から、沢山の愛情を受けて育った。そして、両親を知る皆が、『いい人だった』といってくれる事が嬉しい。ノアーサ、僕もそんな父親になりたい」
カノイはノアーサを見る。
「それって、子供が欲しいって事かしら」
ノアーサが、困ったように言葉を返す。
「いづれにしても仲睦まじい。そろそろお時間ですよ。ご主人様。奥様」
執事のロバートに見送られながら、二人はウィル卿の勤める内閣府へと向かった。
※
国の政治。財政等を扱う内閣府は王宮の一角にあり、二人は政府の役人に、ウィル卿の執務室へと通された。
「我が子らよ。待っていたよ。制服も似合っている」
そう言うと、二人を側の椅子へと座らせる。
「タルタハの国王が、崩御の知らせは聞いていると思う。君たちの兄妹が王に即位する時が来た」
ウィル卿はタルタハの今後について語り始めた。
今後一年、タルタハ王国は喪に服して、即位や戴冠式は来年の秋になるという。その間に女王となる義姉のアンジェリカは、出産を控えている。そんな身重の女王に代わって、王配である兄のノルマンが、大葬や国の行政を代行で行い、『王配に恵まれた女王』だと、タルタハでは早くも噂になっていると話してくれた。
「さて、我々も行動に移さねば。早速、国民も動き始めたようだ。君たちの結婚式を境にね」
そういうと、一咳して二人に訪ねる。
「ところで君たち、夫婦の勤めは毎夜、果たしているかね」
さっきの真面目な表情から一転して、冗談めいた口調で語り出す。
「子供の作り方を知らずに結婚したのではと、気になってな。さて、本題に入るとしょう」
そういうと、彼は、今の国王と自身の過去を打ち明けた。
「私が、慕っていた叔父の十七代国王エルベルトは、私にとっては叔父にあたる今の、十八代国王ヘンリーによって暗殺された」
ウィル卿が、先代国王の死において語り始めた。
今の国王は、十六代国王の弟(内親王)の子供である。彼の父親は体が弱く、彼の側で侍従として、世話をしていた女性との間にヘンリーは産まれた。
彼は両親の顔を知らない。父親は彼の誕生を待たずして、この世を去り、母も彼を産んで直ぐに、侍従を辞めて城を出た。
それでも『弟の忘れ形見』だと、十六代国王はヘンリーを養子に迎え、王子として育ててきた。
「叔父のエルベルトは、面倒見が良くて、誰とでも親しくなれた。一方で、ヘンリーは常に孤独を抱え、何事にも悲観的だったよ」
ウィル卿は子供の頃、母の故郷であるこのアスケニアに何度か訪れて、叔父の家族と過ごした。叔父が王様に即位した時は嬉しかったという。
「叔父が亡くなる十日前に、私の母親宛に手紙が届いた。その手紙には、『自分はヘンリーに殺されるかも知れない』と書いてあったそうだ。それから間もなくして、崩御との知らせが。その後、ヘンリーが即位。即位後は粛清と圧政の『暗黒期』の始まりだ」
「今の国王が、何故、簒奪し王に即位したのか、その理由を聞かせて貰えませんか?」
カノイがウィル卿に訪ねる。
「自分を棄てた母親が、王様になったら、名乗り出てくれると思っていたのかも知れない。だが、彼の母親は城を出て間もなく、病死していたのだ」
ウィル卿は更に続けた。
「私は、叔父の無念を晴らしたい。この王国の、民俗や身分格差を弛くして、女性の自立を実現させた。彼は勇気ある王様だった」
「あの、ひとつ質問をして良いですか」
ノアーサが訪ねる。
「『主君』の事を、今の王様は御存知なのでしょうか?」
「私は、仕事で何度も謁見しているが、偽名で、髪の色も変えている。因みに、本来の髪の色は赤毛ではないぞ。まあ、元の髪色に戻しても、彼は、甥の私を覚えてはいないだろう」
ウィル卿は、エルベルト国王が崩御後、死の真相を追及するために国籍を変え、内閣府の役人として勤めるようになる。
役人になって、粛清を言い渡された人たちの死亡届を偽装し、国内で辺境地や、騎士の領地で匿わせた。
王様の目が届かない場所で、国民を守るための努力はしたが、やはり、すべての国民を救うのは難しい。今の王様が即位してから十年の間に、三千万人もの国民が、命を落としているのである。
「僕達が、育った村も、粛清を逃れた人たちを集めた村だったんですね。でも、独特な民俗衣装と、文字や言葉にも、この大陸にはない特徴があった」
「あの村は、『東方の島国から渡来した人達』が開拓した場所と聞いている。君らは、あの国の文字や言語を理解できるのかね」
二人は、『はい』と答えた。黒い瞳と黒い髪の人達が多い村。独特な剣術や馬術も教わった。
村では稲作が行われ、田圃は水車で水を供給、その動力を活かしての精米。温泉という集団浴場はいつでも湯に浸かれた。
「あの村の住民は、落ち着いたら、また戻って来るだろう。タルタハとの国境区域。交易地点としても重要な交通路になる」
ウィル卿は、過去のすべてを語り終えると、一呼吸置いて呟いた。
「我が子らよ。簒奪するにあたり、君らに頼みたい事がある」
二人を見つめる眼差しが、普段は見ない表情で語りかける。
「もし、私がヘンリー国王のように暴君となってしまったら、迷わず私を斬り捨てて欲しい」
二人には、その言葉が深く心に突き刺さった。
「我が子らよ。君たちは私が作り上げた最高の『剣」と『盾』だ。だからこそ、君らにお願いする」
「それだけの覚悟を持って、即位なさるのですね」
カノイがそう言葉を返した。
「解りました。ノアーサいいね」
カノイは、ノアーサに声をかけると彼女は頷いた。そして、二人は、ウィル卿の前に右膝を付いて、カノイは剣をノアーサは短剣を抜いて胸に掲げた。
「私、カノイ・フォンミラージュと、妻、ノアーサ・フォンミラージュは貴方に絶対の忠義を尽くす事を、この剣にかけて誓います」
二人はウィル卿に騎士として仕える誓いの言葉を述べた。
「我が子らよ」
ウィル卿は、二人の前に腰を下ろして目線を合わせた。
「私はエルベルト国王の意思を引き継いで、王国を復活させてみせる」
彼は、これだけの強い意思で国王に即位する意思を固めている。彼なら、国民が豊かに暮らせる国家を作る事ができると二人は確信した。
この日、簒奪に向けて時計の針が動き始めたのである。
0
あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~
Mio
ファンタジー
妻から手紙が来た。
妻が死んで18年目の今日。
息子の誕生日。
「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」
息子は…17年前に死んだ。
手紙はもう一通あった。
俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。
------------------------------

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

短編【シークレットベビー】契約結婚の初夜の後でいきなり離縁されたのでお腹の子はひとりで立派に育てます 〜銀の仮面の侯爵と秘密の愛し子〜
美咲アリス
恋愛
レティシアは義母と妹からのいじめから逃げるために契約結婚をする。結婚相手は醜い傷跡を銀の仮面で隠した侯爵のクラウスだ。「どんなに恐ろしいお方かしら⋯⋯」震えながら初夜をむかえるがクラウスは想像以上に甘い初体験を与えてくれた。「私たち、うまくやっていけるかもしれないわ」小さな希望を持つレティシア。だけどなぜかいきなり離縁をされてしまって⋯⋯?

冷遇妃マリアベルの監視報告書
Mag_Mel
ファンタジー
シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。
第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。
そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。
王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。
(小説家になろう様にも投稿しています)

わたしにしか懐かない龍神の子供(?)を拾いました~可愛いんで育てたいと思います
あきた
ファンタジー
明治大正風味のファンタジー恋愛もの。
化物みたいな能力を持ったせいでいじめられていたキイロは、強引に知らない家へ嫁入りすることに。
所が嫁入り先は火事だし、なんか子供を拾ってしまうしで、友人宅へ一旦避難。
親もいなさそうだし子供は私が育てようかな、どうせすぐに離縁されるだろうし。
そう呑気に考えていたキイロ、ところが嫁ぎ先の夫はキイロが行方不明で発狂寸前。
実は夫になる『薄氷の君』と呼ばれる銀髪の軍人、やんごとなき御家柄のしかも軍でも出世頭。
おまけに超美形。その彼はキイロに夢中。どうやら過去になにかあったようなのだが。
そしてその彼は、怒ったらとんでもない存在になってしまって。
※タイトルはそのうち変更するかもしれません※
※お気に入り登録お願いします!※

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる