3 / 4
夜は俺たちの時間。③
しおりを挟む
ドーンと大きな音がして目の前に花が咲く。
こんなに近くで花火を見るのは初めてだ。
「な?綺麗だろ?」
「五月蝿いけどな」
「それも花火の醍醐味じゃねぇの?」
ククッと笑うレビィは楽しそうだ。
そもそも今日が花火大会だという情報を仕入れてきたのもレビィの方だった。
「今日花火大会あるらしいぜ。最前列で見ようぜ」と俺の手を引っ張り宙を舞った。
あまり乗り気ではなかったが渋々空を飛ぶ。
悪魔のレビィと幽霊の俺は確かに最前列で花火を見ることが出来る。
幽霊になってから何度か花火を見たことがある。
ただ、レビィと出会うまで何に対しても興味がなかった俺は花火大会が行われていることを察すると離れるようにしていた。
だからこうしてまともに花火を見るのは久しぶりだった。
「元々花火って慰霊とか鎮魂とかそういう意味があるんだろ?リューセーにピッタリじゃねぇか」
「よく知ってんな」
「人間界の知識は割と持ってるぜ。もしかしたらリューセーより詳しいかもな」
レビィは目の前に飛んできた花火を避けるようにひらりと飛ぶ。
どうやら花火を使って遊んでいるらしい。
何でもかんでも楽しいモノとして変換出来るレビィが少し羨ましい。
離れた場所で眺めているとレビィがスーッと飛んできた。
「リューセーも遊べばいいのに」
「別に。見るだけで充分」
「そっかぁ?こんな機会、滅多にねぇぜ」
バシバシと背中を叩かれる。
出会った時から馴れ馴れしかったレビィは最近ますます馴れ馴れしくなってきた。
それを不快に思わなくなったのは俺も俺で馴れたからかもしれない。
「かもな。レビィ見てるとこっちまで気楽になれる」
「ははっ!褒め言葉として受け取るぜ。あー、花火終わっちまった。綺麗だったのによー」
「この時期なら別の場所でもやるって」
「おー、そっかそっか。じゃ、その時はまた一緒に見に行こうぜ」
俺の周りをぐるぐる飛ぶレビィは今日も満面の笑みを浮かべている。
そのポジティブさに助けられることも多い。
幽霊の俺ですら少しは前向きに考えられるようになったのだから悪魔界でのレビィの影響力は相当なものだろう。
「暇だったらな」
「幽霊に暇じゃねぇ時なんてあんのかよ」
「まぁ、ねぇな」
俺の返答にレビィは大爆笑し始めた。ツボに入ったらしい。
こうして一度笑い出すと止まらなくなる。レビィを放って空から地面に降りた。
花火大会が終わったからか人の波は一定方向に流れていた。
この先には駅がある。電車に乗って帰るのだろう。
自分が人間だった頃と今ではだいぶ世界が違っている。
流行りも移り変わり、何でもかんでも電子化していった。
今、人間として生き返ったとしても分からないことだらけだろう。
「おーい!置いていくなって」
文句を言いながらレビィが隣に降り立った。
今のレビィは人間に見えないようにしているらしく、大きな黒い翼を広げていても誰も見向きもしない。
好きに出来るのだから悪魔というものは便利だ。
「一人で笑ってた所為だろ」
「だってリューセーの言うことっていちいち面白ぇんだもん」
「レビィのツボが浅いだけだと思うけど」
「浅い方が何でも楽しめていいぜ。オススメ」
駅とは反対方向に歩き始めた俺にレビィはキョロキョロしながら着いてくる。
俺も俺でつい左右を見回しながら歩いてしまう。
普段は都会に居座っているが花火大会の為に少し離れた場所までつれてこられた。
けれどここは偶然にもよく知っている町だった。
懐かしいと思う。同時に変わったとも思う。
「リューセー?」
顔を覗き込まれてハッとする。
「ボーッとしてっけど大丈夫か?」
「あぁ、まぁ」
「んー……全然大丈夫じゃなさそうだな」
わしゃわしゃと短い髪をかいてからレビィは俺の手を掴んだ。
「何?」
「こういう時は海!そうだろ?」
「……別にそれ常識ってわけじゃねぇと思うけどな」
「いいんだよ。人間っつーのは悩んだ時でっけぇもん見りゃ晴れるもんだ」
グイッと引っ張るレビィの顔は真剣で──だから身を任せてしまった。
質量も何もない俺は宙を飛んだレビィに簡単に運ばれていく。
何故そんなにも人間に詳しいのだろうと思いながら──。
「よし、着いたぜ。好きに寝転がれよ」
海に着いてすぐレビィは砂の上に転がった。
羽を消して手を広げて空を仰ぐように。見習って同じように転がる。
眼前には夜空が広がっていた。
「ここは結構星も月も見えるんだな」
「普段それぐらいしか取り柄がないような町だからな」
「やっぱここ知ってんだろ?リューセーの故郷ってやつ?」
「察するの早過ぎる」
「いつもと雰囲気違ぇからすぐ分かったぜ。けど何でそんなに嬉しくなさそうなんだ?」
「まぁ……いい思い出ばかりじゃねぇからな」
視線を向けなくても分かる。レビィが俺を見ていることも、詳しい話を聞きたがっていることも。
だからわざとらしく「はあ」と溜息をついた。
「昔の話なんて聞きたいか?」
「俺はこの前散々語ったからな。今度はリューセーの番だ」
「お前みたいにドラマチックでもないし盛り上がりも何もない過去だけどな」
そう前置きをしてから自分の過去を語り始めた。
人間だった頃の自分は今よりも明るかった。
どちらかと言うとレビィに似ていたように思う。
ごく普通の家庭に生まれてごく普通の生活をしていた。
友達と騒ぐのが好きで恋愛もそれなりに経験して── 至って普通の人間だった、本当に。
好きなことは色々あったけれど一番好きなのはギターを弾くことだった。
中学時代に友達の影響で始めたギターは俺にかなり衝撃を与えた。
自分で音を奏でることがこんなにも気持ちいいことなのかと。
そしてすぐ親に頼んでギターを買ってもらった。
親に何かを買って欲しいと頼むのは初めてで、だからこそ親も喜んで買ってくれた。
最初のギターはアコースティックギターだった。
友達の家に持って行って一日中弾いている日もあった。
初めてバンドを組んだのは高校に入った時だ。
音楽で生きていくと決めた俺は地元であるこの場所を離れ、東京の高校に入学した。
田舎と都会では世界がまるで違った。
最初はその違いに戸惑った。上手くやっていける気がしなかった。
そんな不安はあったものの、社交性が高い俺はすぐに都会の学生と打ち解けることが出来た。
そしてバンド部に入部してすぐ気の合う仲間を見つけ、それからずっとそのメンバーとバンドを続けるようになった。
2年後にはそれなりに名のあるバンドになっていて、全てが順風満帆と言えた。
けれど「高校を卒業したらメジャーデビューする」とメンバー全員で決めた翌日──俺はこの世を去った。
バイク事故を起こした時のことは正直よく覚えていない。
ただ幽霊となって現世を漂っているうちにどういうことか理解した。
いつも家からバイト先までバイクで行っていた俺はその日もバイクで向かっていた。
慣れた道なのに街路樹に突っ込んで転倒した理由は「何か」に驚いたことだった。
突然出てきた猫なのか犬なのか動物でないものなのか──分からなかったけれど俺は咄嗟にそれを避けようとして運転を誤った。
そして運悪く致命傷を食らってしまった。
せめてもの救いは他人を巻き込まなかったことだ。
幽霊になって最初に浮かんだのは「誰かを巻き添えで殺してしまっていたらどうしよう」だったがそれだけは避けることが出来たらしい。
最期の自分はツイていたのだ、きっと。
けれど時間が経つにつれてそんな思いは消えていく。
何故自分はこんな所で終わってしまったのだろう。
何故自分は夢に向かって歩くことすら出来なくなってしまったのだろう。
考えれば考えるほど虚しくなる。
そして何十年も経った頃──考えるのを辞めた。
虚無になった方が楽になれると気付いたからだ。
理由は分からないけれど俺は幽霊のままこの世を漂い続けなければならなくなってしまった。
それなら心を失くした方がマシだとやっと気付くことが出来た。
未練など数え切れない程ある。
それが消える時などない。
だから俺は永遠とこうして存在し続けるのだと思っていた。
目に映る物に何の感情も抱かず、けれど自分の存在を消すことも出来ず──ただそこに在るモノとして存在していくのだと思っていた。
──レビィに会うまでは。
「そっか。つまりリューセーは夢を叶える為にここにいるんだな」
話し終えた俺にレビィは笑顔を向けてきた。
屈託のない笑みはいっそ清々しい。
「まだ弾きたいと思ってんだろ?ギター」
「そりゃな。叶うなら弾きたい。何も考えずに延々とギターかき鳴らしていたい」
「よし、まずそれ叶えてやるよ」
「はぁ?どうやってやるんだ?俺はモノなんて持てねぇのに」
呆れたように言う。
悪魔のレビィは自由にモノを触れるが幽霊の俺はそういうわけにもいかない。
レビィは俺が幽霊であることを忘れているのだ。
「俺を人間と同じだと思うなよ。出来ねぇことなんてねぇ」
立ち上がり腰に手をあてたレビィは誇らしげだ。
既に何かを成し遂げたかのように。
「って言っても具体的にどうするつもりだ?」
「行くぞ。楽器屋」
「はあ?」
ばっと背中に黒い翼を生やしたレビィは俺の手を掴んだ。再び空へと引っ張られる。
「田舎とはいえこの辺にもあるんだろ?そこ行こうぜ」
「俺がここに住んでた頃にはあったけどどうだかな」
何せ何十年も前だ。なくなっていてもおかしくはない。
むしろなくなっている可能性の方が高い。
けれどレビィはそこへ行くと決めたらしく俺に道案内を求めた。
空へ浮かぶと楽器屋のあった建物が目に入った。
「あ、あれだ」
俺が指を差すとレビィはニイッと笑って加速し、すぐに屋上へ降り立った。
そして難なく建物内に入っていく。
半透明の俺と違ってレビィには実体がある。
けれど悪魔は好きに透き通ることも出来るらしい。
「お、ここか。まだあったみたいだな」
建物の5階へ降りる。先を歩いていたレビィは楽器屋を見つけたらしい。
中学生の頃、何度も世話になった楽器屋はまだそこにあった。
少しだけ感傷に浸って──するりと店内へ侵入する。
「ギターってこれだよな。エレキとかアコギとかあるんだっけか」
「常々思ってたけどレビィって人間界のモノとか詳しいよな。好きなモノも多いし。何でそんなに人間界が好きなんだ?」
「あ、言ってなかったっけ?俺、昔人間と付き合ってたんだよな。その影響」
しれっと言われた言葉に衝撃を受ける。
レビィが人間と付き合っていた──それを聞いた瞬間、モヤモヤと心の中が曇った。
まるで嫉妬心が湧いたような。
「これがアコギでこれがエレキで……リューセー、どっち弾きたいんだっけ?って、どうした?顔面蒼白って感じじゃん」
レビィに頬をペチペチ叩かれて現実に戻される。
「……そこまで酷くはないだろ」
「ははっ!ツッコミサンキュー。確かにそこまで酷くねぇよ。すげぇ呆然としてたけどな。大丈夫か?」
「大丈夫だ。少し驚いただけ」
「つっても400年ぐらい前の話だけどな」
「すげぇ昔だな。影響受けてから変わってないのが不思議なぐらいだ」
想像よりずっと前の出来事で少しホッとしている自分がいた。
これはどう考えても嫉妬だ。
つまり俺はレビィに恋をしているということになる。
意外だとは思わない。ただ、幽霊でも新たな恋をするのだということには驚いた。
「まぁな。人間にとっては長ぇかもしれねぇけど俺には少し前だし。で、どっち弾くんだ?」
「調整しやすいしアコギにする。って、だから俺は幽霊だから持てねぇって」
「いいから持ってみな」
渡されたアコギを受け取る。
ぐっと物質の重さを感じ、思わず落としてしまいそうになった。
慌ててアコギを支える。
「は?え?……マジで持ててる」
「だから言っただろ。簡単に言えばギターを幽霊側に寄せただけだ。ま、こんなこと俺ぐらい優秀な悪魔じゃねぇと出来ねぇけどな」
カカカッと機嫌良く笑ったレビィに目を向けてからギターを構える。
久しぶりに──本当に久しぶりにギターを持ったというのにまるで昨日まで弾いていたかのようにしっくりくる。
それもそうだ。何年経とうが俺は18歳で時が止まっているのだから。
弦を弾いて音を奏でる。
それがものすごく幸せなことのように思えて──涙が零れてしまった。
「リューセー、本当にギターが好きだったんだな」
「……そうだったみたいだ」
「折角だから得意な曲聞かせてくれよ。多分知らねぇけど盛り上げっから」
にししと笑うレビィに軽く頷きを返す。
涙を拭ってギターを弾き始めた。
得意だった曲なんてすぐに思い出せる。
俺のギターにレビィは飛んだり跳ねたり拍手したりと全力で盛り上げてくれた。
自然と笑顔になって──同時にビリッと脳内に電流が走ったような気がした。
「!」
この光景を見たことがある気がする。
俺が奏でて、レビィが踊る。そして2人で笑い合う。
有り得ないはずなのに既視感がある。
けれど、それよりも今は弾くことに集中しなければ。
目の前には俺の演奏を笑顔で聞いてくれる悪魔がいるのだから。
暗い店内にたった一人の観客。
それが好きな人なのだから──この上なく幸せなことだと思うのだ。
こんなに近くで花火を見るのは初めてだ。
「な?綺麗だろ?」
「五月蝿いけどな」
「それも花火の醍醐味じゃねぇの?」
ククッと笑うレビィは楽しそうだ。
そもそも今日が花火大会だという情報を仕入れてきたのもレビィの方だった。
「今日花火大会あるらしいぜ。最前列で見ようぜ」と俺の手を引っ張り宙を舞った。
あまり乗り気ではなかったが渋々空を飛ぶ。
悪魔のレビィと幽霊の俺は確かに最前列で花火を見ることが出来る。
幽霊になってから何度か花火を見たことがある。
ただ、レビィと出会うまで何に対しても興味がなかった俺は花火大会が行われていることを察すると離れるようにしていた。
だからこうしてまともに花火を見るのは久しぶりだった。
「元々花火って慰霊とか鎮魂とかそういう意味があるんだろ?リューセーにピッタリじゃねぇか」
「よく知ってんな」
「人間界の知識は割と持ってるぜ。もしかしたらリューセーより詳しいかもな」
レビィは目の前に飛んできた花火を避けるようにひらりと飛ぶ。
どうやら花火を使って遊んでいるらしい。
何でもかんでも楽しいモノとして変換出来るレビィが少し羨ましい。
離れた場所で眺めているとレビィがスーッと飛んできた。
「リューセーも遊べばいいのに」
「別に。見るだけで充分」
「そっかぁ?こんな機会、滅多にねぇぜ」
バシバシと背中を叩かれる。
出会った時から馴れ馴れしかったレビィは最近ますます馴れ馴れしくなってきた。
それを不快に思わなくなったのは俺も俺で馴れたからかもしれない。
「かもな。レビィ見てるとこっちまで気楽になれる」
「ははっ!褒め言葉として受け取るぜ。あー、花火終わっちまった。綺麗だったのによー」
「この時期なら別の場所でもやるって」
「おー、そっかそっか。じゃ、その時はまた一緒に見に行こうぜ」
俺の周りをぐるぐる飛ぶレビィは今日も満面の笑みを浮かべている。
そのポジティブさに助けられることも多い。
幽霊の俺ですら少しは前向きに考えられるようになったのだから悪魔界でのレビィの影響力は相当なものだろう。
「暇だったらな」
「幽霊に暇じゃねぇ時なんてあんのかよ」
「まぁ、ねぇな」
俺の返答にレビィは大爆笑し始めた。ツボに入ったらしい。
こうして一度笑い出すと止まらなくなる。レビィを放って空から地面に降りた。
花火大会が終わったからか人の波は一定方向に流れていた。
この先には駅がある。電車に乗って帰るのだろう。
自分が人間だった頃と今ではだいぶ世界が違っている。
流行りも移り変わり、何でもかんでも電子化していった。
今、人間として生き返ったとしても分からないことだらけだろう。
「おーい!置いていくなって」
文句を言いながらレビィが隣に降り立った。
今のレビィは人間に見えないようにしているらしく、大きな黒い翼を広げていても誰も見向きもしない。
好きに出来るのだから悪魔というものは便利だ。
「一人で笑ってた所為だろ」
「だってリューセーの言うことっていちいち面白ぇんだもん」
「レビィのツボが浅いだけだと思うけど」
「浅い方が何でも楽しめていいぜ。オススメ」
駅とは反対方向に歩き始めた俺にレビィはキョロキョロしながら着いてくる。
俺も俺でつい左右を見回しながら歩いてしまう。
普段は都会に居座っているが花火大会の為に少し離れた場所までつれてこられた。
けれどここは偶然にもよく知っている町だった。
懐かしいと思う。同時に変わったとも思う。
「リューセー?」
顔を覗き込まれてハッとする。
「ボーッとしてっけど大丈夫か?」
「あぁ、まぁ」
「んー……全然大丈夫じゃなさそうだな」
わしゃわしゃと短い髪をかいてからレビィは俺の手を掴んだ。
「何?」
「こういう時は海!そうだろ?」
「……別にそれ常識ってわけじゃねぇと思うけどな」
「いいんだよ。人間っつーのは悩んだ時でっけぇもん見りゃ晴れるもんだ」
グイッと引っ張るレビィの顔は真剣で──だから身を任せてしまった。
質量も何もない俺は宙を飛んだレビィに簡単に運ばれていく。
何故そんなにも人間に詳しいのだろうと思いながら──。
「よし、着いたぜ。好きに寝転がれよ」
海に着いてすぐレビィは砂の上に転がった。
羽を消して手を広げて空を仰ぐように。見習って同じように転がる。
眼前には夜空が広がっていた。
「ここは結構星も月も見えるんだな」
「普段それぐらいしか取り柄がないような町だからな」
「やっぱここ知ってんだろ?リューセーの故郷ってやつ?」
「察するの早過ぎる」
「いつもと雰囲気違ぇからすぐ分かったぜ。けど何でそんなに嬉しくなさそうなんだ?」
「まぁ……いい思い出ばかりじゃねぇからな」
視線を向けなくても分かる。レビィが俺を見ていることも、詳しい話を聞きたがっていることも。
だからわざとらしく「はあ」と溜息をついた。
「昔の話なんて聞きたいか?」
「俺はこの前散々語ったからな。今度はリューセーの番だ」
「お前みたいにドラマチックでもないし盛り上がりも何もない過去だけどな」
そう前置きをしてから自分の過去を語り始めた。
人間だった頃の自分は今よりも明るかった。
どちらかと言うとレビィに似ていたように思う。
ごく普通の家庭に生まれてごく普通の生活をしていた。
友達と騒ぐのが好きで恋愛もそれなりに経験して── 至って普通の人間だった、本当に。
好きなことは色々あったけれど一番好きなのはギターを弾くことだった。
中学時代に友達の影響で始めたギターは俺にかなり衝撃を与えた。
自分で音を奏でることがこんなにも気持ちいいことなのかと。
そしてすぐ親に頼んでギターを買ってもらった。
親に何かを買って欲しいと頼むのは初めてで、だからこそ親も喜んで買ってくれた。
最初のギターはアコースティックギターだった。
友達の家に持って行って一日中弾いている日もあった。
初めてバンドを組んだのは高校に入った時だ。
音楽で生きていくと決めた俺は地元であるこの場所を離れ、東京の高校に入学した。
田舎と都会では世界がまるで違った。
最初はその違いに戸惑った。上手くやっていける気がしなかった。
そんな不安はあったものの、社交性が高い俺はすぐに都会の学生と打ち解けることが出来た。
そしてバンド部に入部してすぐ気の合う仲間を見つけ、それからずっとそのメンバーとバンドを続けるようになった。
2年後にはそれなりに名のあるバンドになっていて、全てが順風満帆と言えた。
けれど「高校を卒業したらメジャーデビューする」とメンバー全員で決めた翌日──俺はこの世を去った。
バイク事故を起こした時のことは正直よく覚えていない。
ただ幽霊となって現世を漂っているうちにどういうことか理解した。
いつも家からバイト先までバイクで行っていた俺はその日もバイクで向かっていた。
慣れた道なのに街路樹に突っ込んで転倒した理由は「何か」に驚いたことだった。
突然出てきた猫なのか犬なのか動物でないものなのか──分からなかったけれど俺は咄嗟にそれを避けようとして運転を誤った。
そして運悪く致命傷を食らってしまった。
せめてもの救いは他人を巻き込まなかったことだ。
幽霊になって最初に浮かんだのは「誰かを巻き添えで殺してしまっていたらどうしよう」だったがそれだけは避けることが出来たらしい。
最期の自分はツイていたのだ、きっと。
けれど時間が経つにつれてそんな思いは消えていく。
何故自分はこんな所で終わってしまったのだろう。
何故自分は夢に向かって歩くことすら出来なくなってしまったのだろう。
考えれば考えるほど虚しくなる。
そして何十年も経った頃──考えるのを辞めた。
虚無になった方が楽になれると気付いたからだ。
理由は分からないけれど俺は幽霊のままこの世を漂い続けなければならなくなってしまった。
それなら心を失くした方がマシだとやっと気付くことが出来た。
未練など数え切れない程ある。
それが消える時などない。
だから俺は永遠とこうして存在し続けるのだと思っていた。
目に映る物に何の感情も抱かず、けれど自分の存在を消すことも出来ず──ただそこに在るモノとして存在していくのだと思っていた。
──レビィに会うまでは。
「そっか。つまりリューセーは夢を叶える為にここにいるんだな」
話し終えた俺にレビィは笑顔を向けてきた。
屈託のない笑みはいっそ清々しい。
「まだ弾きたいと思ってんだろ?ギター」
「そりゃな。叶うなら弾きたい。何も考えずに延々とギターかき鳴らしていたい」
「よし、まずそれ叶えてやるよ」
「はぁ?どうやってやるんだ?俺はモノなんて持てねぇのに」
呆れたように言う。
悪魔のレビィは自由にモノを触れるが幽霊の俺はそういうわけにもいかない。
レビィは俺が幽霊であることを忘れているのだ。
「俺を人間と同じだと思うなよ。出来ねぇことなんてねぇ」
立ち上がり腰に手をあてたレビィは誇らしげだ。
既に何かを成し遂げたかのように。
「って言っても具体的にどうするつもりだ?」
「行くぞ。楽器屋」
「はあ?」
ばっと背中に黒い翼を生やしたレビィは俺の手を掴んだ。再び空へと引っ張られる。
「田舎とはいえこの辺にもあるんだろ?そこ行こうぜ」
「俺がここに住んでた頃にはあったけどどうだかな」
何せ何十年も前だ。なくなっていてもおかしくはない。
むしろなくなっている可能性の方が高い。
けれどレビィはそこへ行くと決めたらしく俺に道案内を求めた。
空へ浮かぶと楽器屋のあった建物が目に入った。
「あ、あれだ」
俺が指を差すとレビィはニイッと笑って加速し、すぐに屋上へ降り立った。
そして難なく建物内に入っていく。
半透明の俺と違ってレビィには実体がある。
けれど悪魔は好きに透き通ることも出来るらしい。
「お、ここか。まだあったみたいだな」
建物の5階へ降りる。先を歩いていたレビィは楽器屋を見つけたらしい。
中学生の頃、何度も世話になった楽器屋はまだそこにあった。
少しだけ感傷に浸って──するりと店内へ侵入する。
「ギターってこれだよな。エレキとかアコギとかあるんだっけか」
「常々思ってたけどレビィって人間界のモノとか詳しいよな。好きなモノも多いし。何でそんなに人間界が好きなんだ?」
「あ、言ってなかったっけ?俺、昔人間と付き合ってたんだよな。その影響」
しれっと言われた言葉に衝撃を受ける。
レビィが人間と付き合っていた──それを聞いた瞬間、モヤモヤと心の中が曇った。
まるで嫉妬心が湧いたような。
「これがアコギでこれがエレキで……リューセー、どっち弾きたいんだっけ?って、どうした?顔面蒼白って感じじゃん」
レビィに頬をペチペチ叩かれて現実に戻される。
「……そこまで酷くはないだろ」
「ははっ!ツッコミサンキュー。確かにそこまで酷くねぇよ。すげぇ呆然としてたけどな。大丈夫か?」
「大丈夫だ。少し驚いただけ」
「つっても400年ぐらい前の話だけどな」
「すげぇ昔だな。影響受けてから変わってないのが不思議なぐらいだ」
想像よりずっと前の出来事で少しホッとしている自分がいた。
これはどう考えても嫉妬だ。
つまり俺はレビィに恋をしているということになる。
意外だとは思わない。ただ、幽霊でも新たな恋をするのだということには驚いた。
「まぁな。人間にとっては長ぇかもしれねぇけど俺には少し前だし。で、どっち弾くんだ?」
「調整しやすいしアコギにする。って、だから俺は幽霊だから持てねぇって」
「いいから持ってみな」
渡されたアコギを受け取る。
ぐっと物質の重さを感じ、思わず落としてしまいそうになった。
慌ててアコギを支える。
「は?え?……マジで持ててる」
「だから言っただろ。簡単に言えばギターを幽霊側に寄せただけだ。ま、こんなこと俺ぐらい優秀な悪魔じゃねぇと出来ねぇけどな」
カカカッと機嫌良く笑ったレビィに目を向けてからギターを構える。
久しぶりに──本当に久しぶりにギターを持ったというのにまるで昨日まで弾いていたかのようにしっくりくる。
それもそうだ。何年経とうが俺は18歳で時が止まっているのだから。
弦を弾いて音を奏でる。
それがものすごく幸せなことのように思えて──涙が零れてしまった。
「リューセー、本当にギターが好きだったんだな」
「……そうだったみたいだ」
「折角だから得意な曲聞かせてくれよ。多分知らねぇけど盛り上げっから」
にししと笑うレビィに軽く頷きを返す。
涙を拭ってギターを弾き始めた。
得意だった曲なんてすぐに思い出せる。
俺のギターにレビィは飛んだり跳ねたり拍手したりと全力で盛り上げてくれた。
自然と笑顔になって──同時にビリッと脳内に電流が走ったような気がした。
「!」
この光景を見たことがある気がする。
俺が奏でて、レビィが踊る。そして2人で笑い合う。
有り得ないはずなのに既視感がある。
けれど、それよりも今は弾くことに集中しなければ。
目の前には俺の演奏を笑顔で聞いてくれる悪魔がいるのだから。
暗い店内にたった一人の観客。
それが好きな人なのだから──この上なく幸せなことだと思うのだ。
0
あなたにおすすめの小説

【完結】社畜の俺が一途な犬系イケメン大学生に告白された話
日向汐
BL
「好きです」
「…手離せよ」
「いやだ、」
じっと見つめてくる眼力に気圧される。
ただでさえ16時間勤務の後なんだ。勘弁してくれ──。
・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:
純真天然イケメン大学生(21)× 気怠げ社畜お兄さん(26)
閉店間際のスーパーでの出会いから始まる、
一途でほんわか甘いラブストーリー🥐☕️💕
・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:
📚 **全5話/9月20日(土)完結!** ✨
短期でサクッと読める完結作です♡
ぜひぜひ
ゆるりとお楽しみください☻*
・───────────・
🧸更新のお知らせや、2人の“舞台裏”の小話🫧
❥❥❥ https://x.com/ushio_hinata_2?s=21
・───────────・
応援していただけると励みになります💪( ¨̮ 💪)
なにとぞ、よしなに♡
・───────────・

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

サラリーマン二人、酔いどれ同伴
風
BL
久しぶりの飲み会!
楽しむ佐万里(さまり)は後輩の迅蛇(じんだ)と翌朝ベッドの上で出会う。
「……え、やった?」
「やりましたね」
「あれ、俺は受け?攻め?」
「受けでしたね」
絶望する佐万里!
しかし今週末も仕事終わりには飲み会だ!
こうして佐万里は同じ過ちを繰り返すのだった……。


僕たち、結婚することになりました
リリーブルー
BL
俺は、なぜか知らないが、会社の後輩(♂)と結婚することになった!
後輩はモテモテな25歳。
俺は37歳。
笑えるBL。ラブコメディ💛
fujossyの結婚テーマコンテスト応募作です。
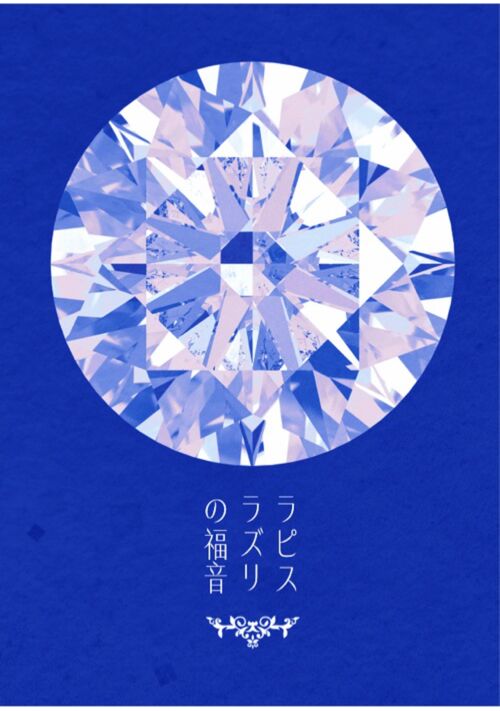
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

クズ彼氏にサヨナラして一途な攻めに告白される話
雨宮里玖
BL
密かに好きだった一条と成り行きで恋人同士になった真下。恋人になったはいいが、一条の態度は冷ややかで、真下は耐えきれずにこのことを塔矢に相談する。真下の事を一途に想っていた塔矢は一条に腹を立て、復讐を開始する——。
塔矢(21)攻。大学生&俳優業。一途に真下が好き。
真下(21)受。大学生。一条と恋人同士になるが早くも後悔。
一条廉(21)大学生。モテる。イケメン。真下のクズ彼氏。

雪色のラブレター
hamapito
BL
俺が遠くに行っても、圭は圭のまま、何も変わらないから。――それでよかった、のに。
そばにいられればいい。
想いは口にすることなく消えるはずだった。
高校卒業まであと三か月。
幼馴染である圭への気持ちを隠したまま、今日も変わらず隣を歩く翔。
そばにいられればいい。幼馴染のままでいい。
そう思っていたはずなのに、圭のひとことに抑えていた気持ちがこぼれてしまう。
翔は、圭の戸惑う声に、「忘れて」と逃げてしまい……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















