29 / 137
第二章 幽霊少女ミリィ
第二十九話 最後の誕生日プレゼント
しおりを挟む真っ暗な廊下を歩き、中央の大きな階段に出る。ミナヅキはそこをゆっくりと下りていった。
その左右をじっくりと確認しながら。
「階段に何かあるの? 特に何もなさそうだけど……」
ミナヅキにつられる形で、アヤメも階段の左右を見渡すが、特に何も変なところは見つからない。
「さぁな。もしかしたら何もないかもしれん」
「何よそれ……さっきの自信さはどこへ行ったっていうのよ?」
「自信はあるさ。気になるっていう部分にだけはな。そこで何が出てくるかは、流石に今の段階では分からんさ」
淡々と語るミナヅキに、アヤメは何も言えなくなってしまう。とりあえず彼の好きにさせてみよう――そう思うのだった。
やがて三人は、階段の一階まで折りきるところまでやってきた。
その時、ミナヅキがとある部分に注目する。
「ここって――」
アヤメもその場所を思い出した。ミナヅキがカンテラをかざしたそこには、血の跡がある手すりの柱があった。
「わたしが階段から落ちて、頭をぶつけた場所だね。多分だけど」
やはり自分が死んだ場所であるせいか、ミリィの表情が強張る。
「おにーさん、わざわざこれを見に来たの?」
「結果的にそうなるな。また凄い偶然ではあるんだが……よく見てみな」
ミナヅキが隣の手すりの柱もよく見えるように、カンテラを動かす。
「この血のついた柱だけ、他の柱と形が微妙に違うと思わないか?」
「え? うーん、そう言われてみれば……」
アヤメはじっくり見比べてみる。確かに少しだけ装飾が違う気がした。パッと見ただけでは分からない。本当に見比べなければ分からない程度の。
「多分この柱に何かが……あっ!」
ミナヅキが血の付いた柱を手で握り、グラグラと動かしてみると、その柱がポロっと取れてしまった。
「ちょ! アンタなに壊してるのよ!?」
「いやいや、そんなつもりは……ポロっと簡単に外れちまったんだって!」
流石に予想外だったためか、ミナヅキも慌てて弁解する。
その直後――
「な、なんだ!?」
ゴゴゴゴゴ――と、重々しい音が響き渡る。そして、階段前の絨毯がグラグラと動き出した。
床がベコッと一段階凹み、ゆっくりとスライドしていく。
そこに現れたのは――
「階段? 地下に通じているの?」
「す、凄い……家にこんなのがあったなんて……」
一階で終わりだった階段と、隠し階段が繋がり、地下へと延びる長い階段へと変貌を遂げた。その事実にアヤメもミリィも驚きを隠せない。
そんな彼女たちの前で、ミナヅキは得意げな笑みを浮かべていた。
「やっぱり調べて正解だったな。まだまだ探索してみる価値はありそうだ」
試しにカンテラをかざしてみるが、階段の奥は真っ暗で、何も見えなかった。
◇ ◇ ◇
「あの柱に注目したのは、おにーさんが初めてだよ」
地下への階段を下りていく中、ミリィがそう切り出した。
「それに、この家をあんな隅々まで調べたのも、もしかしたら初めてかも」
「そうなのか?」
「うん。他の人たちは、皆ビクビクしていて、かなり適当に歩き回るだけっていうのが殆どだったから」
ミリィの話に、ミナヅキはあり得そうだなと思い、笑みを浮かべる。
「ふーん。それじゃ俺たちは、相当なレアケースってワケだな」
「そういうこと。だからビックリしてる」
「なるほどね」
ミナヅキは頷きながら、今の話は限りなく本当なのだろうと思った。そもそもこうしてミリィと話すこと自体が珍しい――というより、ミリィからしてみれば初めてに等しいことなのだ。
そして自分さえも知らなかった、新たなる場所の発見。心なしかミリィの表情が豊かになっている気がしていた。
考えてみれば、自然なことかもしれない。
十年間も同じ場所を彷徨っていれば、飽き飽きするのが普通だ。ちゃんと意識があるのならば尚更である。
この先に何があるのかはともかく、ミリィにそれなりの刺激を与えることができたという点は、良かったのかもしれない。
そう思いながらミナヅキは、雑談がてら今回の調査について話すことにした。
「実を言うとさ。今回俺たちは調査で来たワケだけど、最初からそんな乗り気ってワケでもなかったんだよな」
「そうなの?」
少し驚きながら尋ねるミリィに、ミナヅキとアヤメは頷く。
「言っちゃあなんだけど、ソウイチさん……まぁ、俺らの知り合いの人から紹介されちまってたから、殆ど仕方なく引き受けたって感じだったんだよ」
「ヴィンフリートさんの感じも、なんかあんまり良さげじゃなかったもんね」
「全くだ」
参ったモノだと言わんばかりに、ミナヅキとアヤメは苦笑する。
そもそも二人がクルーラの町に来たのは、夫婦水入らずでバカンスを楽しむためであり、依頼を受けるつもりなんて全くなかったのだ。
無論、冒険者の中には、たとえ休暇中に訪れた先で依頼されれば、喜んで受ける者も少なくない。頼られるということは、冒険者にとってのステータスに直結していくからだ。
そこから繋がりが出来ていき、やがてギルドで大きな評価となって現れる。それを目論んで、休暇にもかかわらず自ら依頼に首を突っ込む者もおり、それもまた決して珍しくないのも確かであった。
しかしながら、そうではない冒険者もたくさんいる。
ミナヅキとアヤメもその該当者であり、休暇中に仕事を受けることは、自分たちが興味でも持たない限り、極力関わりたくないタイプであった。
たとえヴィンフリートが言っていたように、ギルド側から指名依頼されるという名誉な機会を得たとしても同じである。今回もソウイチが外堀を埋めるようなマネさえしなければ、断ろうとしていたくらいだ。
しかしながら二人は、心の底から苛立っている様子でもなかった。
それなりに思うところはあるが、こうなってしまった以上は仕方がない。彼らなりにそう割り切ったのだ。
「それで最初から、肝試しの気分全開だったんだね」
「そーゆーこと」
「ちょうど季節も夏だし、まさに絶好の環境って感じだと思ってたからね」
階段が終わり、更に真っ暗で長い通路が伸びていた。ミナヅキたちはゆっくりと進みつつ、話を続ける。
「まーでも、仕事は仕事だからな。調査の報告はちゃんとするつもりだよ」
「だからミリィのことも、しっかり話すことになるけど……」
アヤメがどこか言いにくそうにしていると、ミリィはアッサリと頷いた。
「いいよ。おにーさんたちが見たことをそのまま話してくれて。別に隠すようなことは何もないから」
「ありがとう。そう言ってくれて助かるよ」
前を歩くミナヅキが、振り向きながら笑顔を見せる。それにつられてか、ミリィも笑みを浮かべた。
三人はそのまま通路を進んでいくと、やがて一つの扉に辿り着く。
扉は重かったが、特にカギもかかっておらず、開けること自体は可能だった。ミナヅキが力を込めて扉を開けると、そこは小部屋となっていた。
「何もないな……いや、宝箱みたいなのが一個あるか」
ミナヅキの言うとおり、その小部屋にはポツンと一個だけ、宝箱がある。
まるで典型的なファンタジー世界の宝箱に、思わずミナヅキとアヤメはワクワクしてしまっていた。
「ねぇねぇミナヅキ、ちょっと開けてみようよ」
「あぁ」
はやる気持ちを抑えきれず、ミナヅキは宝箱を開けようとする。
しかし――
「……何だこれ、全然開かないぞ? マジでビクともしない」
取っ手も鍵穴もなく、上に開く可能性は勿論、スライドして開ける可能性も考慮してみたが、箱が開くことはなかった。
「ホントに開くのかな? ただの飾りってことはないよね?」
「だとしたら、相当な悪趣味と言わざるを得ないぞ」
首を傾げながら言うミリィに、ミナヅキはゲンナリとした様子を見せる。大がかりな仕掛けを作ってまで飾り物を置く――それが本当だとしたら、ワクワクした気持ちを返せと言いたくなる。
そう思いながら、ミナヅキは立ち上がった。
「アヤメも試してみるか?」
「あ、うん……」
ミナヅキに促されてアヤメが箱の前に立つ。そして試しに箱に手を伸ばした。
すると――
「え?」
「ひ、光った!?」
ミリィが叫んだとおり、急に箱が光り出した。そしてその直後、箱はパカッと開いてしまった。
あんなに開く気配すらなかったのに、手を触れただけでこの結果である。
三人は開いた箱を凝視しながら呆然としていた。
「……どーなってんだ、こりゃあ?」
三人の気持ちを引き受けるような形でミナヅキが呟くように言う。
「多分だけど……魔力だと思う。手をかざしたとき、体から何かが注ぎ込まれたような感触があったから」
「一定の魔力に反応して開く仕組みだった、とか?」
「分からないけど、多分そんな感じ?」
ミナヅキとアヤメが首を傾げ合う。流石に憶測に憶測を重ねるだけでは、何も分からなかった。
そこにミリィが二人の前に立ち、両手をパタパタと振る。
「ねぇねぇ、そんなことよりも早く中を見ようよ。折角開いたんだしさ」
「あ、あぁ……そうだな」
ミリィに促されたミナヅキは、不思議な宝箱もあるんだなぁという考えに留めることにしつつ、その箱の中を覗き込む。
入っていたのは一冊の本。それ以外は何もなかった。
試しに捲ってみると、なにやら日誌のような文章が書かれている。
「ふーん。クリストファーって人が書いたっぽいな、コレ……」
「えっ?」
ミナヅキの呟きに、ミリィが目を見開いた。それに気づいたアヤメは、視線を下ろしながら尋ねる。
「どうかしたの、ミリィ?」
「クリストファーって、わたしのおとーさんの名前だよ」
「え、マジか?」
ミナヅキも驚きの反応を見せる。そしてマジマジと発見した本を見つめた。
「まさかここに来て、ミリィの親父さんの手掛かりが見つかるとはな」
「それを読めば、何か分かるかもしれないわね」
「だな。もう他には何もなさそうだし、戻ってコイツを読んでみようぜ」
本を掲げながら提案するミナヅキに、アヤメとミリィも頷く。そして三人は地下の小部屋を後にし、ミリィの部屋へと戻っていくのだった。
◇ ◇ ◇
クリストファーが残した日誌を読んでいくと、色々なことが分かってきた。
元々冒険者だったクリストファーは、大きな功績を残したことから、当時のフレッド国王に認められ、貴族としての地位を授かった。それから故郷であるこの町に拠点を構え、丘の上に屋敷を構えたらしい。
愛する家族とともに、海と街を一望できる環境を望んだとのことだった。
父親の新たなる事実を知ったミリィは、驚きを隠せないでいた。
更に余談ながらアヤメは、クリストファーとその妻であるレオノーレの関係性について注目していた。
「ミリィのお父さんとお母さんは、幼なじみだったのね」
「俺たちと同じか」
「そうなの?」
驚くミリィに、ミナヅキとアヤメは揃って頷く。
「幼なじみっつっても、ずっと一緒にいたってワケじゃなかったけどな」
「私が無理やり結婚させられそうになって、駆け落ちしてきたのよ」
「ほぇー、おにーさんたちって、なかなかやるんだねー!」
素直に感心するミリィに苦笑いしつつ、ミナヅキは日誌を読み進める。するとあるページに、ミナヅキたちが望んでいた内容が記されていた。
「これは――!」
ミナヅキが目を見開いた。そこにはなんと、ミリィに送る予定だった誕生日プレゼントの詳細が書かれていたのだった。
アヤメとミリィも驚きを隠せず、気持ちを高ぶらせながら読んでいく。
「ミリィのお父さん、オーダーメイドのペンダントを送ろうとしていたのね」
「おとーさん……」
チラリと視線を向けると、ミリィがわずかに涙ぐんでいるのが見えた。ミナヅキは再び視線を戻し、更に目を通していく。
その材料も採取できる場所も、日誌の中に詳しく書かれていた。ミリィの誕生日当日に、クリストファーがその材料を集めようとしていたことも発覚する。
「ペンダントなら、生産工房で作ってもらえるな。素材を持ち込んで、鍛冶師か大工に頼めば、なんとかなるだろう」
この町にも工房があることは調べてある。ゴールが見えてきたことに、ミナヅキは嬉しさを覚えずにはいられなかった。
その時、アヤメが何かを思い出したような反応を見せる。
「……ねぇ、ミナヅキ? やっぱりこの本も、ヴィンフリートさんに提出したほうがいいわよね?」
ミナヅキもそれを聞いて、日誌を捲る手がピタッと止まる。自分たちがどうしてここに来たのかを、改めて思い出した。
「そうだな。今まで発見されてこなかったモノだし、提出はするべきだろう。悪いけど、それで良いか、ミリィ?」
「うん」
顔色を窺うように訪ねるミナヅキだったが、ミリィはアッサリと頷いた。その表情はサッパリとしており、日誌に未練を抱いている様子もない。
「おとーさんのことが少し分かったから。あとはその本に書かれていたペンダントさえもらえれば、きっと……」
「そうか、ありがとう」
ミナヅキはミリィのほうに体ごと顔を向ける。
「ミリィの最後の誕生日プレゼントは、俺たちが必ず用意して渡すから」
「もう少しだけ待っててね」
アヤメもミリィに顔を近づけ、優しく微笑みながら言った。
二人の力強く、そして暖かな表情にミリィは――
「うんっ、楽しみに待ってる!」
初めてといっても過言ではない、明るい笑顔でそう答えるのだった。
0
あなたにおすすめの小説
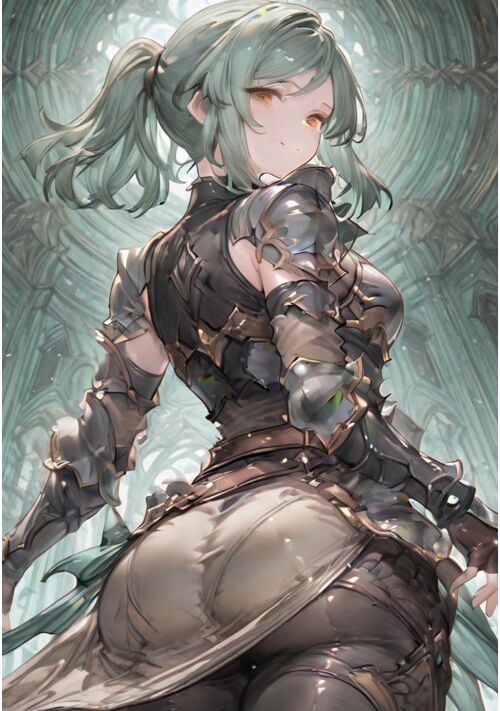
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。

【完結】スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

スキルはコピーして上書き最強でいいですか~改造初級魔法で便利に異世界ライフ~
深田くれと
ファンタジー
【文庫版2が4月8日に発売されます! ありがとうございます!】
異世界に飛ばされたものの、何の能力も得られなかった青年サナト。街で清掃係として働くかたわら、雑魚モンスターを狩る日々が続いていた。しかしある日、突然仕事を首になり、生きる糧を失ってしまう――。 そこで、サナトの人生を変える大事件が発生する!途方に暮れて挑んだダンジョンにて、ダンジョンを支配するドラゴンと遭遇し、自らを破壊するよう頼まれたのだ。その願いを聞きつつも、ダンジョンの後継者にはならず、能力だけを受け継いだサナト。新たな力――ダンジョンコアとともに、スキルを駆使して異世界で成り上がる!

【完結】まもの牧場へようこそ!~転移先は魔物牧場でした ~-ドラゴンの子育てから始める異世界田舎暮らし-
いっぺいちゃん
ファンタジー
平凡なサラリーマン、相原正人が目を覚ましたのは、
見知らぬ草原に佇むひとつの牧場だった。
そこは、人に捨てられ、行き場を失った魔物の孤児たちが集う場所。
泣き虫の赤子ドラゴン「リュー」。
やんちゃなフェンリルの仔「ギン」。
臆病なユニコーンの仔「フィーネ」。
ぷるぷる働き者のスライム「モチョ」。
彼らを「処分すべき危険種」と呼ぶ声が、王都や冒険者から届く。
けれど正人は誓う。
――この子たちは、ただの“危険”なんかじゃない。
――ここは、家族の居場所だ。
癒やしのスキル【癒やしの手】を頼りに、
命を守り、日々を紡ぎ、
“人と魔物が共に生きる未来”を探していく。
◇
🐉 癒やしと涙と、もふもふと。
――これは、小さな牧場から始まる大きな物語。
――世界に抗いながら、共に暮らすことを選んだ者たちの、優しい日常譚。
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

異世界召喚に条件を付けたのに、女神様に呼ばれた
りゅう
ファンタジー
異世界召喚。サラリーマンだって、そんな空想をする。
いや、さすがに大人なので空想する内容も大人だ。少年の心が残っていても、現実社会でもまれた人間はまた別の空想をするのだ。
その日の神岡龍二も、日々の生活から離れ異世界を想像して遊んでいるだけのハズだった。そこには何の問題もないハズだった。だが、そんなお気楽な日々は、この日が最後となってしまった。

ボンクラ王子の側近を任されました
里見知美
ファンタジー
「任されてくれるな?」
王宮にある宰相の執務室で、俺は頭を下げたまま脂汗を流していた。
人の良い弟である現国王を煽てあげ国の頂点へと導き出し、王国騎士団も魔術師団も視線一つで操ると噂の恐ろしい影の実力者。
そんな人に呼び出され開口一番、シンファエル殿下の側近になれと言われた。
義妹が婚約破棄を叩きつけた相手である。
王子16歳、俺26歳。側近てのは、年の近い家格のしっかりしたヤツがなるんじゃねえの?

クラス転移したけど、皆さん勘違いしてません?
青いウーパーと山椒魚
ファンタジー
加藤あいは高校2年生。
最近ネット小説にハマりまくっているごく普通の高校生である。
普通に過ごしていたら異世界転移に巻き込まれた?
しかも弱いからと森に捨てられた。
いやちょっとまてよ?
皆さん勘違いしてません?
これはあいの不思議な日常を書いた物語である。
本編完結しました!
相変わらず話ごちゃごちゃしていると思いますが、楽しんでいただけると嬉しいです!
1話は1000字くらいなのでササッと読めるはず…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















