96 / 137
第五章 ミナヅキと小さな弟
第九十六話 兄弟
しおりを挟むその夜、リュートはミナヅキと二人でベッドの中に入っていた。
――兄弟二人でゆっくりと話しなさい。
そう言ってアヤメに気を利かせられてしまい、ミナヅキは幼い弟を連れて部屋に戻ったのだった。いきなり過ぎやしないかと言ってはみたが、交流に早いも遅いもないという妻の言葉に対し、何も言い返すことができなかったのである。
当然ながらリュートは緊張状態だ。
最初はミナヅキから少し距離を取り、ベッドの端で身を縮めつつ、しっかりと背を向けていた。要は見事なまでに警戒されていたのだ。
無理もない話だとミナヅキは思っていた。
むしろこうして一緒に寝るところまで来たのは、かなり良いほうだろう。全力で拒否されてもおかしくなかったのだから。
このまま黙って寝てしまうのも一つの選択肢として思い浮かんだが、それもなんだか勿体ない気がした。故にミナヅキは、自分たち二人の共通している人物について切り出してみた。
そう――父親の話である。
「正直言うとな。俺は父親のことを殆ど覚えてない――いや、知らないと言ってもいいくらいだ」
ミナヅキが語り出すと同時に、リュートの体がピクッと動いた。
「そもそも、ちゃんと名前で呼ばれたこともあったかどうか……それすらも全然思い出せないくらいさ」
「ぼくも……」
自虐的な笑みを浮かべつつ話していると、か細い声が聞こえてきた。いつの間にかリュートが振り向いており、ミナヅキをじっと見つめている。
「ぼくも、よばれたこと……たぶんない」
「――そうか」
ミナヅキは一瞬驚いたような反応を見せ、そして優しい笑みに切り替える。無意識に手を伸ばしてリュートの頭をポンポンと撫でていた。しかしリュートは逃げようとせず、むしろ少しだけだが、ミナヅキに体を近づけてさえいた。
「ずっと家にいなくて、たまに帰ってきたときに話しかけてみたところで、ちっとも振り向いてくれやしなかった」
「……それ、ぼくもおなじ」
「そうなのか?」
「うん。おとーさんってよんでも、ぜんぜんへんじしてくれなかった」
「マジかよ……俺の時から全然変わってないってことか」
気がついたら二人は普通に話していた。あれだけ緊張していた気持ちはどこへ行ってしまったのかと、そう思いたくなるほどに。
ミナヅキ自身、これまで父親のことを考えることは全然してこなかった。
良い思い出なんか全くなく、最後に話した会話が会話なだけに、良い印象は全く抱いていない。だから思い出せば思い出すほど、憎しみが生まれてくるだけだろうと思っていたのだった。
しかし、こうしていざ話してみると、なんてことなく話せていることに驚く。
好きではないが恨んでもいない。あくまで血の繋がった赤の他人――それが自分にとっての父親なのだろうと、ミナヅキは思う。
「リュートは、お父さんたちに酷いことをされたとかはあるのか? こう、ゲンコツで頭をボカッと叩かれたとか……」
「ううん、ないよ」
「そうか」
ひとまず暴力による虐待はなさそうだということで、そこだけは安心した。もっとも盛大にネグレクトしている点は否定のしようもないため、ミナヅキは苦笑せずにはいられない。
「その様子だと、お父さんの笑顔を見たこともなさそうだな」
「あるよ」
「えっ、あるのか?」
ミナヅキは思わず驚いてしまった。しかし次のリュートの言葉で、ある意味最大級の納得をすることとなる。
「いそがしくはたらいて、こんなひろいいえをたてることができたおれは、なんてすばらしいにんげんなんだーとかいってた」
「……あぁ、そういう笑顔ね」
つまりはリュートに向けられたということではない。どこまでも自分に酔いしれ自分を中心に世界が回っていると思い込む――そんな姿が目に浮かぶ。
(ってことは、七年前のアレも……?)
病院の裏庭での一件。ミナヅキではなく、生まれたばかりのリュートを選んだのだと思っていた。
しかしそれは正しくもあり、間違っていたのだとしたら。
生まれたばかりの子を想い、泣く泣く前の妻との子に区切りをつける。そんな苦渋の選択をした自分は、まるでドラマを駆け巡る主人公のようだと、自分で自分をカッコいいと思い込んでいただけだったとしたら。
(……なんか普通にあり得そうだな)
全ては憶測。証拠は何もないし、見当違いかもしれない。しかしミナヅキは、どうにも当たっているような気がしてならなかった。
もっとも、今それを考えたところで、何も得られないのも確かであるのだが。
(あの父親がどんなことを考えていたにせよ、リュートを容赦なく置き去りにしちまったことは事実だ。もうその時点で許されることじゃあないわな)
そのまま車で逃げ出した父親とリュートの母親は、その後どうなったのか。それは知る由もないことだが、せめて罰の一つでも当たってほしいと、ミナヅキは無意識のうちにほくそ笑んでいた。
「リュートは、お父さんと離れ離れになって、寂しいか?」
「んー……よくわかんない」
「分からないか」
無理もない反応だとは思った。リュートも父親に笑顔を向けてもらった記憶すらないのだ。つまり良い意味でも悪い意味でも、本当に何もされることなく、こうして行き別れた状態となってしまったことになる。
驚きこそすれど、求めるような気持ちはない。こうして新しく暮らす場所が見つかったのならば尚更だろう。
あくまで父親と認識しているだけ――そこについては、リュートも自分と同じなのかもしれないと、ミナヅキは思った。
「ねぇ。おにーちゃんは、おとーさんがいなくてさびしい?」
「――さぁな。俺もよく分からん」
目を閉じながらミナヅキが答える。リュートから『おにーちゃん』と呼ばれたことに対して、思わずドキッとしたことをなんとか隠しながら。
「それよりも、リュートのほうが寂しいだろ? 幼稚園や小学校の友達と、お別れの挨拶もできなかっただろうし」
誤魔化すように話を振るミナヅキ。しかしリュートは、悩ましげにコテンと首を傾げた。
「ようちえんやしょうがっこうって……なに?」
「――えっ?」
ミナヅキは耳を疑った。まるでリュートは、本当にそれらの言葉を知らない様子であった。
(ウソだろ……いや、ウソを言ってるようには見えないし……まさか?)
ある一つの憶測を頭の中で立てつつ、ミナヅキは聞いてみることにした。
「じゃあ、今まではどこでどんなふうに過ごしていたんだ?」
「……おうちであそんでた」
「それだけか?」
「うん。おとーさんもおかーさんも、おうちからそとにはでるなって。おにわであそぶのはいいっていってた」
「つまり、家の外には、一度も出たことがなかったってことか?」
「うん。おとーさんたちとくるまにのってでたのがはじめて。そのあとに、ぼくをおいてどっかいっちゃったの」
「な、なるほど……」
つまり最後に置き去りにされるまでの間、リュートは幼稚園にも小学校にも行くこともなく、ずっと家の敷地内で過ごしていたことになる。
しかしそれならそれで、ミナヅキは疑問に思えてならないことがあった。
「周りの人たちは気づかなかったのか? 隣のお家とかもあったろ?」
「ううん、なかった」
「なかった?」
「うん。このおうちみたいになかった」
このおうち――すなわちラステカのミナヅキの家のことだ。
確かに田舎町の端っこにポツンと建つ家だけあって、隣近所との距離はかなり離れている。庭に野生のスライムが来ても、全く騒ぎにならないほどに。
しかし王都ないしそれに準ずる大きな町でもない限り、この世界ではそれほど珍しくもない。ラステカの町においては、むしろ住宅街の如く家がひしめき合っている光景のほうが珍しいくらいだ。
とはいえ、あくまでこれは異世界の事情である。
地球の現代日本で、そこまで広い土地が、果たしてどれだけあることか。
(ラステカみたいなだだっ広い土地は、俺の住んでた町にはないぞ? てゆーか、その周辺のどの町にも普通にあるとは思えんし……)
ミナヅキが悩ましげな表情で考えていると、リュートが何かを思い出したような反応を見せた。
「あとね、ねこさんがよくあそびにきてた」
「猫?」
「うん。なんかわかんないけど、ねこさんがぼくとあそんでくれたの」
リュートが笑顔で話す。それほど楽しかったのだろうということは分かるが、やはりどうしても気になることがあった。
「その猫さんは、どこから来たんだ?」
「わかんない。おうちのまわりはもりだったから」
「森?」
「うん。とちゅうでおおきなさくとかべがあって、そのさきにはいけなかったよ」
話を聞いているうちにミナヅキは思った。リュートが暮らしていた家は、どう考えても普通の住宅地にあるような家ではなさそうだと。
「大きな柵と壁、か……そこから外は見えなかったのか?」
「ぜんぜんみえなかったよ」
「そうか」
「でも、かべのおくから、ねこさんがでてくるのはみたことがあるかも」
「なるほどな。恐らく小さな隙間でもあったんだろう。猫ってのは、結構色んなところを潜り抜けちまうもんだからな」
「へぇー、そうなんだ」
興味深そうに笑顔を見せるリュートの頭を撫でつつ、ミナヅキは少し考える。
(広い庭に森、そして隣の家はなく、大きな壁に囲まれている。そしてリュートは外の世界を知らなかった……)
ミナヅキは頭の中で、これまでの会話で出てきたキーカードを並べていく。そしてリュートが暮らしていた家が、段々と思い浮かんできていた。
(住宅地から遠く外れた土地にある豪邸――恐らくそんなところか? 周りに家がないくらいに大きなその場所で、リュートは世間から隔離された状態で過ごしてきたんだろうな)
我ながら言い得て妙かもしれないとミナヅキは思う。しかしそれならそれで、大きな問題点が浮上してくる。
(オマケに幼稚園や小学校をマジで知らない。そしてそれが、外部から問題視されることすら恐らくなかった。薄々予感はしていたが、リュートは――)
出生届が出されていない――いわゆる無戸籍の子供の可能性が高い。
如何せんそう言った子供が少なくないことは、地球で暮らしていた時も耳にしたことはあった。まさか自分と血を分けた兄弟がその可能性に当たるとはと、ミナヅキは流石に驚きを隠せないでいたが。
(七歳の割には口調がおぼつかないと思っていたが……恐らく親と喋ることすら殆どなかったんだろうな。どこまでどうしようもない親たちだったんだ? 明らかにちゃんと育てる気ゼロじゃないか)
そもそもリュートの両親が、自分たちは親であると認識していたかどうかも非常に怪しい。父親のほうは考えるまでもないが、果たしてリュートの母親のほうはどうだったのか。
少なくともミナヅキの中では、とても良い方向に期待はできなかった。
(ユリスが気づいてくれなかったら、リュートは今頃死んでいたかもしれない。アイツにはマジで感謝しないといけないな)
気持ち良さそうに撫でられているリュートを見ながら、ミナヅキは強く思う。兄としてもそうだが、自分の父親がこんな小さな子をと考えただけで、腹の底から熱い何かがたぎってくる気持ちに駆られる。
やはり親たちには、大きな罰の一つや二つは当たってほしい――ミナヅキは心の底から、そう願って止まなかった。
「ねぇ、おにーちゃん」
リュートがミナヅキのパジャマを掴みながら尋ねてくる。
「おにーちゃんのおかーさんはどんなひとだったの?」
「……あぁ、それな」
その問いかけに、ミナヅキは困ったような表情を浮かべた。
「実を言うと……全く覚えてないんだな、これが」
誤魔化しなどではない。本当に思い出そうとしても思い出せなかったのだ。
思えば小さい頃、母親が愛人の男を自宅に連れ込み、寝室のベッドで大人の運動をしていた場面が見つかって以来、まともに姿を見ていない気さえする。
(リュートに聞かれるまで、マジで忘れてたな)
つまり自分にとっての母親は、その程度の存在だったということだ。自分を生んだ人以外の何者でもないと。
「おぼえてないの? ぼくでもおかーさんのことおぼえてるよ?」
リュートが信じられないと言わんばかりに驚き、詰め寄るようにして尋ねる。
確かにその疑問は、至極真っ当だと言える。どんな形であれ、母親という存在が当たり前のようにいる子供からすれば、尚更であろう。
「まぁ、何だ。ちょうどリュートぐらいの頃に会ったっきりだからな」
「ずっとあってないの?」
「あぁ。こうして大人になるまで、ずっとだ」
「そうなんだ……」
リュートはギュッとミナヅキのパジャマを掴む手を強める。それ以降、何も聞いてくることはなかった。
「――もう、寝ようか」
ミナヅキの声に、リュートは無言でコクリと頷く。ミナヅキは小さな笑みを浮かべながらリュートの頭を撫で、そのまま優しく抱き寄せる。
「おやすみ、リュート」
「うん……おやすみなさい」
戸惑いながらも答え、リュートはそのまま目を閉じる。二人は暖かい温もりを感じながら、意識を沈めていくのだった。
0
あなたにおすすめの小説
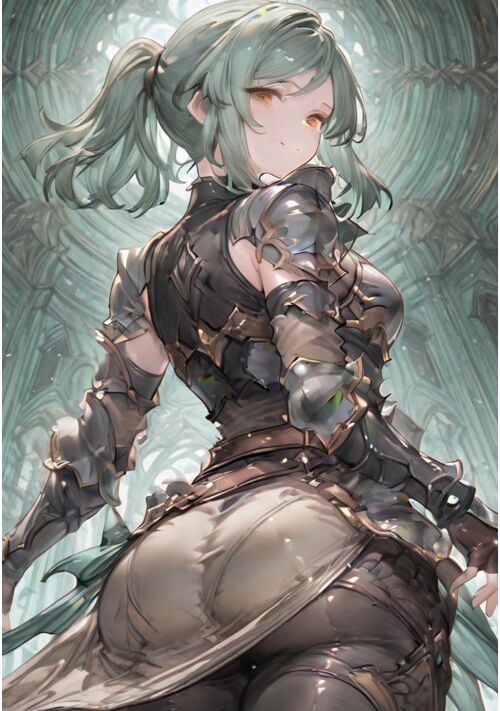
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

【完結】スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。

スキルはコピーして上書き最強でいいですか~改造初級魔法で便利に異世界ライフ~
深田くれと
ファンタジー
【文庫版2が4月8日に発売されます! ありがとうございます!】
異世界に飛ばされたものの、何の能力も得られなかった青年サナト。街で清掃係として働くかたわら、雑魚モンスターを狩る日々が続いていた。しかしある日、突然仕事を首になり、生きる糧を失ってしまう――。 そこで、サナトの人生を変える大事件が発生する!途方に暮れて挑んだダンジョンにて、ダンジョンを支配するドラゴンと遭遇し、自らを破壊するよう頼まれたのだ。その願いを聞きつつも、ダンジョンの後継者にはならず、能力だけを受け継いだサナト。新たな力――ダンジョンコアとともに、スキルを駆使して異世界で成り上がる!

ボンクラ王子の側近を任されました
里見知美
ファンタジー
「任されてくれるな?」
王宮にある宰相の執務室で、俺は頭を下げたまま脂汗を流していた。
人の良い弟である現国王を煽てあげ国の頂点へと導き出し、王国騎士団も魔術師団も視線一つで操ると噂の恐ろしい影の実力者。
そんな人に呼び出され開口一番、シンファエル殿下の側近になれと言われた。
義妹が婚約破棄を叩きつけた相手である。
王子16歳、俺26歳。側近てのは、年の近い家格のしっかりしたヤツがなるんじゃねえの?

【完結】まもの牧場へようこそ!~転移先は魔物牧場でした ~-ドラゴンの子育てから始める異世界田舎暮らし-
いっぺいちゃん
ファンタジー
平凡なサラリーマン、相原正人が目を覚ましたのは、
見知らぬ草原に佇むひとつの牧場だった。
そこは、人に捨てられ、行き場を失った魔物の孤児たちが集う場所。
泣き虫の赤子ドラゴン「リュー」。
やんちゃなフェンリルの仔「ギン」。
臆病なユニコーンの仔「フィーネ」。
ぷるぷる働き者のスライム「モチョ」。
彼らを「処分すべき危険種」と呼ぶ声が、王都や冒険者から届く。
けれど正人は誓う。
――この子たちは、ただの“危険”なんかじゃない。
――ここは、家族の居場所だ。
癒やしのスキル【癒やしの手】を頼りに、
命を守り、日々を紡ぎ、
“人と魔物が共に生きる未来”を探していく。
◇
🐉 癒やしと涙と、もふもふと。
――これは、小さな牧場から始まる大きな物語。
――世界に抗いながら、共に暮らすことを選んだ者たちの、優しい日常譚。
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

異世界召喚に条件を付けたのに、女神様に呼ばれた
りゅう
ファンタジー
異世界召喚。サラリーマンだって、そんな空想をする。
いや、さすがに大人なので空想する内容も大人だ。少年の心が残っていても、現実社会でもまれた人間はまた別の空想をするのだ。
その日の神岡龍二も、日々の生活から離れ異世界を想像して遊んでいるだけのハズだった。そこには何の問題もないハズだった。だが、そんなお気楽な日々は、この日が最後となってしまった。

クラス転移したけど、皆さん勘違いしてません?
青いウーパーと山椒魚
ファンタジー
加藤あいは高校2年生。
最近ネット小説にハマりまくっているごく普通の高校生である。
普通に過ごしていたら異世界転移に巻き込まれた?
しかも弱いからと森に捨てられた。
いやちょっとまてよ?
皆さん勘違いしてません?
これはあいの不思議な日常を書いた物語である。
本編完結しました!
相変わらず話ごちゃごちゃしていると思いますが、楽しんでいただけると嬉しいです!
1話は1000字くらいなのでササッと読めるはず…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















