108 / 137
第五章 ミナヅキと小さな弟
第百八話 ありふれた家族の形
しおりを挟む一足先に馬車で出発したミナヅキは、ラステカの町に戻ってきた。まずは自宅に戻って、アヤメに王都での出来事を報告する。
「そう。レノは無事に家族の元へ戻れたのね。良かったわ」
ソファーに座り、温かいジンジャーティーを飲みながらアヤメが微笑んだ。
「それで、そのエルヴァスティさんたちは、しばらくこの町で?」
「あぁ。まだどこに泊まるかは決まってないんだけどな」
「決まってないって……あ、そっか」
宿屋があるじゃないと言いかけたアヤメは、このラステカには現在、宿屋の類がないことを思い出した。
そして至極当たり前のように提案する。
「なら、ウチに泊めればいいんじゃない? お庭も広いから、ドラゴンの一匹くらい入るでしょうし、特に問題はないと思うけど?」
それを聞いたミナヅキは、思わず呆気に取られてしまう。まさかこんなあっけらかんと言われるとは思わなかったからだ。
「それなら話は早くて助かるが……良いのか? お前かなり不安定だろ、今?」
「人助けの一つや二つくらいどうってことないわよ」
「そうか? じゃあウチに招き入れるぞ?」
「えぇ。楽しみに待ってるわ」
ニッコリ微笑みながら、アヤメは再びジンジャーティーを口にする。どことなく不安はあったが、ここはお言葉に甘えようとミナヅキは思った。
「グルウオォォーーーッ!」
「あ、来たな」
ドラゴンの鳴き声にミナヅキは反応し、外へ向かう。アヤメもカップをおいて彼の後に続いた。
二人で外に出ると、ちょうど一体の大きなドラゴンが降り立っていた。
特に問題もなさそうであり、バージルたちが背から降り、リュートとスラポンがミナヅキたちの元に駆け寄ってくる。
「おにーちゃん、ただいま!」
「おう、おかえり」
飛び込んできたリュートを、ミナヅキが正面からポフっと抱き留める。そこにアヤメもニッコリ笑顔で近づいてきた。
「おかえり。随分と楽しんできたみたいね?」
「あ、おねーちゃん、ただいま。体の具合はだいじょーぶ?」
「うん。今日は調子が良いわ」
そう言いながら頭を撫でてくるアヤメに、リュートとスラポンはフニャッと柔らかい笑顔を見せる。
ここでミナヅキは、アヤメにバージルたちを紹介した。
「アヤメ。こちら、エルヴァスティ家の皆さん」
「初めまして。ミナヅキの妻でアヤメと申します」
「こちらこそ初めまして。エルヴァスティ家の主でバージルと申します」
そしてバージルはミルドレッドとベラ、そして乗ってきたドラゴンのジェロスのことも紹介する。
お互いに自己紹介し合ったところで、ミナヅキとバージルはジェロスとともに町長の元へ向かうことに。大きなドラゴンがいきなり降り立ったことに、人々は流石に驚いていたようであったが、事情を話すとすぐに理解を示した。
町長もエルヴァスティ一家を歓迎すると話し、一度ゆっくり話させてほしいと言われたバージルは、その誘いを受ける。
ミナヅキたちは町長の家から自宅へ戻ってくると、何とミルドレッドがエプロンを身に付け、料理をしていた。
「お帰りなさい。町長さんとの話は付けられましたか?」
「えぇ、まぁ……ところで、ミルドレッドさんは、一体何を?」
「夕飯を作らせてもらっていますわ♪」
ミルドレッドはウィンクをしながら答える。ミナヅキもバージルも、それは見れば分かると心の中で同時に呟いた。
そこにベラが、小さなため息をつきながら歩いてくる。
「気分の不安定な妊婦さんを働かせられないって、ママが張り切ってるの」
「そうなんだ。どうもすみません。気を使わせてしまって」
ミナヅキが申し訳なさそうに頭を下げると、ミルドレッドは手のひらを左右に振りながら軽い口調で言う。
「そんなお気になさらないでくださいな。子を産んだ母親として、血が騒いでしまっただけですもの。それにしても――」
ミルドレッドはキッチンに隣接してある石窯に視線を向けた。
「随分と立派な石窯を持ってらっしゃいますのね」
「ついこないだ、フレッド王都の工房から、譲り受けたんですよ。おかげで大きなリフォームになっちゃいましてね」
「これだけ大きければ、無理もありませんわ」
確かにと、同じく気になっていたバージルもベラも、心の中で同意した。もはや自宅で喫茶店かパン屋でも営むつもりなのではと思ったほどだった。
そんな中ミルドレッドは、真剣な表情でミナヅキとアヤメに向き直る。
「お二人の子供が生まれた際には、改めてお祝いに伺いますわ。その際に――」
そして目を輝かせながら、ミルドレッドは二人に迫った。
「是非ともこの立派な石窯で、私にお料理を作らせてほしいですのぉっ♪」
「――はぁ。それはまぁ、別に構いませんが」
呆気に取られながらミナヅキは答える。突然過ぎる迫力に、驚くチャンスすら見失ってしまっていた。
その一方で――
「またミルドレッドは人様の家で暴走して……」
「ママ、恥ずかしいってば……」
バージルとベラは、キャッキャと子供のようにはしゃぐミルドレッドの姿が、恥ずかしく思えて仕方がなかった。
苦笑を浮かべているミナヅキもアヤメも、言葉が浮かんでこない。
ちなみにリュートとスラポン、そしてレノは、今のやり取りを聞いてはいたが、特に興味もなかったらしく、すぐにまたじゃれ合うのに戻った。
「さてさて、こうしちゃいられないよー!」
我に返ったミルドレッドは、パンと手を叩きながら気合いを入れる。
「ミナヅキさんとアヤメさんは休んでいてくださいな。ベラ、アンタはリュート君たちの面倒を見ときなさい」
「はーい」
間延びした返事をするベラだったが、ミルドレッドは特に何も言わなかった。そしてその傍で突っ立っていたバージルに対して、視線をギラっと光らせる。
「アンタもボサッとしてないで、こっちで仕込みを手伝いな! モタモタしてると日が暮れちまうよ!」
「はいぃっ!」
その凄まじい気迫にバージルは背筋をピシッと伸ばし、殆ど反射的な勢いで威勢のいい返事をした。
そしてワタワタと動き出す父親を、母親が再びたしなめるその姿に、娘は心の底から呆れ果てた視線を向ける。
「……お客さんのハズなのに、完全にいつものパパとママになっちゃってるし」
ベラは深いため息をつきながら、改めて両親の様子を見る。
外では上品に振る舞っているミルドレッドは、もはや完全なる肝っ玉母さん状態となっている。普段は一家の主として、相棒のジェロスとともに竜の一族の務めを全力で果たすバージルは、もうすっかり尻に敷かれている情けないお父さん以外の何者でもない。
しかし言い換えれば、これこそがベラが毎日のように見ている家族の姿だった。
故に改めて外でそれを遺憾なく発揮されることが、どうにも恥ずかしく思えて仕方がないのだった。
きっと笑われるだろう――そう思いながらベラはチラリと振り向いた。
(――えっ?)
ベラは別の意味で驚いていた。ミナヅキもアヤメも、そしてリュートでさえ、揃って物珍しそうにキッチンで繰り広げられている光景を見ていたからだ。
気を使っているとかそんなモノではなく、純粋にきょとんとした表情でじっくりと観察する――こんな恥ずかしい光景にそれほどの価値があるのか。
「あの、どうかしたんですか?」
ベラは無性に気になって尋ねてみた。するとミナヅキたちは、特に誤魔化そうともせず自然な反応を見せる。
「あぁいや……正直あーゆーの、俺は見たことがなくってさ」
「ぼくも」
「私もなのよねぇ」
ミナヅキに続いて、リュートとアヤメも同じだと示す。三人の反応に、ベラはますます驚かずにはいられなかった。
「見たことがないって……むしろパパとママの姿としては普通だって……」
同年代の友達もため息交じりに言っていた。毎日のケンカもどこか楽しそうにしている感じがする、という言葉も聞いたことがある。
だからベラも思っていたのだ。両親のこの姿は普通なのだと。誰もが見たことのあるありふれた姿なのだと。
故にとてもじゃないが信じられなかった。今からでも遅くないから、冗談だよという言葉を笑いながら言ってほしいと、そう願うほどに。
しかし――
「驚かせちゃってゴメン。でもこればかりは、そうとしか言いようがないんだ」
「うん。育った環境はそれぞれ違うけど、私たちがありふれた家族の姿に恵まれてこなかったって言うのは事実だからね」
リュートも言葉こそ発していなかったが、スラポンを抱きしめる力を少しだけ強くしていた。ベラもそれを見て、ウソじゃないんだということを察する。
「ねぇ、教えて。そんなにひどい家族だったの?」
ベラはアヤメの座るソファーの隣に移動し、小声で尋ねる。妙な気遣いしてくるなぁと思いながら、アヤメは答えた。
「そうねぇ。私の生まれた家はお金持ちでね。両親は常に仕事ばかりだったわ」
仕事が忙しくて滅多に顔を合わせない。食事も同じ席でないのが当たり前。たまに顔を合わせれば、学校や習い事の成績は優秀でいるんだろうな、という確認しかしてこない。
ここで優秀な結果に対して褒められたのであれば、まだ良かっただろう。しかし両親は、そんな当たり前のことで喜ぶなと言うだけだった。頑張ったね――そんなありきたりな誉め言葉さえ、まともに言われたことがあったかどうか。
そして失敗したことがバレたら、決まって大説教の嵐。
音楽のコンクールで金賞を取ったにもかかわらず、その嵐を真正面から浴びせられた記憶は、忘れたくても忘れられない。
何故なら金賞の上に、最優秀賞という最高の賞が存在していたからだ。
トップ以外は大失敗も同然だ――そんな感じで何度怒鳴り散らされたことか。
そんな中、唯一褒めてくれたのがミナヅキだった。
――へぇーそうなんだ。凄いじゃん。
恐らくミナヅキからしてみれば、コンクールの意味なんて分かってないし、どれだけ大変だったかもまるで理解していなかったことだろう。
それでも嬉しかった。たったそれだけの言葉が、どれほど支えになったことか。
そしてアヤメは思ったのだ。きっといつか両親も褒めてくれる――そう信じて頑張ってみようと。
しかし、両親は最後の最後までブレることはなかった。
娘のことを、あくまで家を繁栄させるための道具としてしか見ていなかった。お偉いさんともなれば、そう言った考えも普通なのかもしれないが、アヤメはそれを受け入れることはできなかった。
「――そして私は家を飛び出してミナヅキと駆け落ちして、今に至る。こうして愛する人の子を身籠って、自由に暮らしている。こんなところかしら」
アヤメは懐かしむように語り切った。ところどころの口調に多少の苛立ちこそあったものの、恨み続けているようにも感じられなかった。
ここでようやくアヤメは気づいた。
流石に今のは子供にするような話ではない。聞かれたからつい正直にダラダラと喋ってしまったが、少しはオブラートに包むぐらいのことはしたほうが良かったのではないか。
しかしもう既に語ってしまった。ならば自分が言うべきことは――
「あー、なんかゴメンね? 暗いお話を聞かせてしまって」
素直に謝ることだけだとアヤメは思い、口に出す。横目でチラリとキッチンのほうを診てみると、ミルドレッドとバージルは夕飯づくりに集中しており、今の話は全く聞かれていないように見えた。
それでも後で、それとなく話したほうが良さそうだとも思ってはいたが。
「い、いえ……」
ベラは戸惑いながらも、改めてアヤメを見る。お腹を撫でながら笑みを浮かべているその姿は、やはり恨みも後悔もないと言わんばかりに思えた。
「リュートくん」
ベラはリュートを手招きする。そしてリュートを隣に座らせて尋ねた。
「ねぇ、もしかしてリュートくんやお兄さんも?」
「そうだなぁ……簡単に言えば、放ったらかしだったって感じかな」
「ぼくも」
ミナヅキに続いて、リュートも俯いたまま答える。
「ぼくも話したことない。捨てられるときにちゃんと話しかけてくれた」
「――っ!?」
捨てられた――その言葉に、ベラはショックを受け、絶句する。
「俺も、自分に弟がいることを知ったのは、その後だったんだ。正直、よくここまで元気を取り戻してくれたと思うよ」
ミナヅキがリュートの頭を撫でる。気持ち良さそうにしながら笑顔を浮かべ合う二人もまた、幸せであるようには見えていた。
しかしベラは、未だ驚きのほうが大いに勝っていた。
家族は一緒にいるのが当たり前じゃないのか。両親が毎日のように笑顔を向けてくれるのは、普通ではないのか。
少なくともベラは、今までずっとそれが当たり前だと思っていた。けれど、そうじゃない人たちもいるんだと、ここで思い知った気がした。
「まぁ、あくまで昔の話だし、どうってことはない。リュートは、もう少し時間が必要だろうけどな」
「短期間でここまで明るくなれたのは、ホント奇跡といっても良いくらいよね」
それも間違いなく、スラポンやレノがいたからだろう。ミナヅキもアヤメも、二匹の魔物には感謝してもしきれないと思っていた。
すると――
「だったら、あたしも……」
ベラは心の中で決意した。自分は今日から、本当の意味でリュートのお姉ちゃんになるんだ、と。
「ねぇ、リュートくん?」
ベラは満面の笑みを向けながら話しかけた。
「あたしのことは、今からベラ姉ちゃんって呼んでね?」
「え……?」
突然そう言われたリュートは、意味が分からず上手く反応が出来なかった。
(な、なに、いきなり?)
向けられている笑顔が怖いと思っていた。まるでそう呼ばなきゃ許さないと言われているような――そんな押しの強さを無意識に感じていた。
そんな中、ベラはリュートに向かって、更にズイッと笑顔を近づける。
「ほらほら早く、ベラ姉ちゃんって言ってみて?」
「ベ、ベラねーちゃん……?」
恐る恐る言葉を反復したリュート。本当にただそれだけのことだったが――
「はうぅっ!!」
ベラは見事なまでに、ノックアウトされてしまった。上目遣いで向けてくる怯えたような視線が、途轍もなく恐ろしい可愛さを出していたのだ。
「どうしたの、ベラねーちゃん?」
「なっ、何でもないっ。うん、全然なんでもないからっ!」
「……?」
怖い笑顔を向けたと思ったら、今度は急に顔を真っ赤にして慌てだした。コロコロと切り替わる表情に、リュートはコテンと首を傾げる。
すると――
「ぐっ……」
またしてもベラは、意識が揺らぎそうになった。
その首を傾げるのは反則じゃないの――そう言ってやりたかったが、それを言ったら言ったで、次にまた何をされるか分かったモノではない。
結局、そのまま悶々と頭を抱えることしかできないベラ。そしてそんなベラに対して首を傾げたり、顔を覗き込んだりするリュート。そしてそれに対して、プイッと真っ赤な顔を逸らし続けるベラ。
そんな感じの、なんとも言えない状況が出来上がるのだった。
(まぁ、とにかくさっきの微妙な空気はなんとか……ん?)
ミナヅキが心の中で安堵していたその時、ミルドレッドとバージルが、料理の手を休めて視線を向けながら、ニヤニヤと笑っていることに気づいた。
「あの子も押すわねぇ。流石は私の娘!」
「あぁ。しかし父親としては、少しばかり寂しい気も……」
「――何か言った?」
「いえ! 全く何も言っておりませんです、ハイ!」
「よろしい」
どこまでも妻に頭の上がらない夫――そんな光景にミナヅキは苦笑しつつ、ほんの少しだけ暖かい何かを感じたような気がしたのだった。
0
あなたにおすすめの小説

スキルはコピーして上書き最強でいいですか~改造初級魔法で便利に異世界ライフ~
深田くれと
ファンタジー
【文庫版2が4月8日に発売されます! ありがとうございます!】
異世界に飛ばされたものの、何の能力も得られなかった青年サナト。街で清掃係として働くかたわら、雑魚モンスターを狩る日々が続いていた。しかしある日、突然仕事を首になり、生きる糧を失ってしまう――。 そこで、サナトの人生を変える大事件が発生する!途方に暮れて挑んだダンジョンにて、ダンジョンを支配するドラゴンと遭遇し、自らを破壊するよう頼まれたのだ。その願いを聞きつつも、ダンジョンの後継者にはならず、能力だけを受け継いだサナト。新たな力――ダンジョンコアとともに、スキルを駆使して異世界で成り上がる!
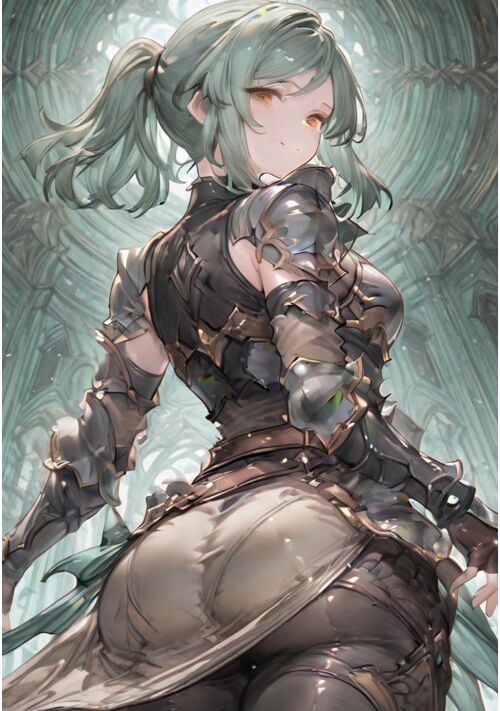
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

異世界召喚に条件を付けたのに、女神様に呼ばれた
りゅう
ファンタジー
異世界召喚。サラリーマンだって、そんな空想をする。
いや、さすがに大人なので空想する内容も大人だ。少年の心が残っていても、現実社会でもまれた人間はまた別の空想をするのだ。
その日の神岡龍二も、日々の生活から離れ異世界を想像して遊んでいるだけのハズだった。そこには何の問題もないハズだった。だが、そんなお気楽な日々は、この日が最後となってしまった。

ボンクラ王子の側近を任されました
里見知美
ファンタジー
「任されてくれるな?」
王宮にある宰相の執務室で、俺は頭を下げたまま脂汗を流していた。
人の良い弟である現国王を煽てあげ国の頂点へと導き出し、王国騎士団も魔術師団も視線一つで操ると噂の恐ろしい影の実力者。
そんな人に呼び出され開口一番、シンファエル殿下の側近になれと言われた。
義妹が婚約破棄を叩きつけた相手である。
王子16歳、俺26歳。側近てのは、年の近い家格のしっかりしたヤツがなるんじゃねえの?

封印されていたおじさん、500年後の世界で無双する
鶴井こう
ファンタジー
「魔王を押さえつけている今のうちに、俺ごとやれ!」と自ら犠牲になり、自分ごと魔王を封印した英雄ゼノン・ウェンライト。
突然目が覚めたと思ったら五百年後の世界だった。
しかもそこには弱体化して少女になっていた魔王もいた。
魔王を監視しつつ、とりあえず生活の金を稼ごうと、冒険者協会の門を叩くゼノン。
英雄ゼノンこと冒険者トントンは、おじさんだと馬鹿にされても気にせず、時代が変わってもその強さで無双し伝説を次々と作っていく。

【完結】まもの牧場へようこそ!~転移先は魔物牧場でした ~-ドラゴンの子育てから始める異世界田舎暮らし-
いっぺいちゃん
ファンタジー
平凡なサラリーマン、相原正人が目を覚ましたのは、
見知らぬ草原に佇むひとつの牧場だった。
そこは、人に捨てられ、行き場を失った魔物の孤児たちが集う場所。
泣き虫の赤子ドラゴン「リュー」。
やんちゃなフェンリルの仔「ギン」。
臆病なユニコーンの仔「フィーネ」。
ぷるぷる働き者のスライム「モチョ」。
彼らを「処分すべき危険種」と呼ぶ声が、王都や冒険者から届く。
けれど正人は誓う。
――この子たちは、ただの“危険”なんかじゃない。
――ここは、家族の居場所だ。
癒やしのスキル【癒やしの手】を頼りに、
命を守り、日々を紡ぎ、
“人と魔物が共に生きる未来”を探していく。
◇
🐉 癒やしと涙と、もふもふと。
――これは、小さな牧場から始まる大きな物語。
――世界に抗いながら、共に暮らすことを選んだ者たちの、優しい日常譚。
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

【完結】スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

クラス転移したけど、皆さん勘違いしてません?
青いウーパーと山椒魚
ファンタジー
加藤あいは高校2年生。
最近ネット小説にハマりまくっているごく普通の高校生である。
普通に過ごしていたら異世界転移に巻き込まれた?
しかも弱いからと森に捨てられた。
いやちょっとまてよ?
皆さん勘違いしてません?
これはあいの不思議な日常を書いた物語である。
本編完結しました!
相変わらず話ごちゃごちゃしていると思いますが、楽しんでいただけると嬉しいです!
1話は1000字くらいなのでササッと読めるはず…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















