2 / 5
2.混乱と配慮
しおりを挟む(最後まではしないと、侍女たちもみんな言っていたのに…。お兄様がそう言わせていたのかしら)
婚姻の際に女性側に求められるのは、処女であることだ。夫となる者以外の子を孕んでいる可能性がないため、理にかなっていると納得できていたのに、生まれてからずっと、仲の良かった兄によって失ってしまった。
デビュタントから三年、王女であるにも関わらず縁談が聞こえて来ず、諦めかけていたところに、止めを刺す一夜だった。
よりによって、あの一夜の翌日に、兄の友人であるランスロット・オーレンドルフ公爵に嫁ぐことに決まったと聞いた。
遠い昔の王弟が叙されて始まったオーレンドルフ家は、順調に発展し現存する数少ない公爵家だ。兄と公爵は同い年の幼馴染で、当然イザベルもよく遊んでもらった。兄の後ろをついて回ったイザベルにも優しく接してくれた公爵は、少し前まではもうひとりの兄のような存在だった。
イザベルが王家主催の夜会に出るとき、エスコートをするのは十六歳のデビュタントのときからずっとオーレンドルフ公爵、当時はまだ次期公爵の彼だった。身分も釣り合い、年下だからとイザベルを見下すこともなく、王女としてきちんと立ててくれる。ダンスもそつなくこなし、イザベルが不快に思うことは全くなかった。それがきっと、両親にも都合がよかったのだろう。
二年前に若くして公爵位を継いでからは忙しいらしく、夜会以外で顔を合わせることはなくなってしまった。それでも、年に数回の夜会で、エスコートのたびに微笑んでくれるその表情と気遣いのあふれる仕草に、惹かれてしまった。イザベルより六歳上で、同年代の男性とは異なる色気を纏う彼は、とりわけ輝いて見えた。
婚約者同士が仲を深める期間はなく、婚約発表と同時に結婚準備が始まった。見知った仲だからそれでも構わなかったが、イザベルが関わった打ち合わせは衣装合わせのみで、結婚する当人たちではなく、ライヘンバッハ王家とオーレンドルフ公爵家の意向が多大に反映された結婚式になることを覚悟した。
(お兄様とあんなことがあったあとで、まともに話せる気もしないけれど)
結婚式の間ずっと、久々対面した公爵がとても大人に見えて、動悸が止まらなかった。学院時代には同性から羨ましがられることや妬まれることも多かったが、素直に彼の妻になれることを喜びたかった。
(あの一夜がなければ…、いえ、王家に生まれたんだもの。お兄様の役に立ててよかったんだわ。唯一、私にできることだったもの……)
兄とは、あの一夜以来全く会っていなかった。国王として式に出席していたし、祝福の言葉もくれたが、目線はイザベルと完全には合わなかった。
イザベルはユスティンに別れの挨拶もせず、ランスロットの手を取りオーレンドルフ公爵邸へ向かった。
(今夜、何も知らない彼と……っ)
◇
(式で疲れただろうな。緊張もしているだろうし、ほぐしてやらないと)
無事に結婚式を終え、ランスロットがそう意気込んで寝室へ入ると、やけに落ち着いたイザベルが、薄い夜着を身につけて寝台の中央に座っていた。
「ランスロット様、お待ちしておりました」
「イザベル、敬称は止めてくれ。君のほうが身分は上だろう」
「もう王家の一員ではありません。夫を立てるのは妻の役目です」
「それはそうだが…。ふたりのときは、昔のように呼んでくれると嬉しい」
すっと隣へ腰を下ろし、肩に触れ目を合わせる。少し、イザベルの様子がおかしいようにも思える。緊張とは別の面持ちに、嫌な予感がした。初夜に、寝台の上。思い当たることが、ないわけではなかった。
「ねえ、もしかして…、誰か好きな人がいる?」
「っ……」
「イザベル、大丈夫。離婚とか、王家に迷惑をかけるような話はしないよ。君だって十九年生きてきたんだ、好きな人がいたっておかしくない」
はっと顔を上げたイザベルを見て、ランスロットはひとり納得した。
「僕との結婚は、身分の釣り合いを取った政略結婚だ。準備の関係で、君には急な話だったろうし、気持ちがついていかないのも当然だよ」
「ランスロット様…」
「今日絶対に、この行為を終えないといけないわけじゃない。君のことだ、この結婚もユスティンに通されたんだろう?」
「っ、私は…」
「いいよ、話さなくていい。イザベルが妻であることに変わりはないし、変える気もないんだ。知ってると思うけど、この地位を狙う女性は多いから…。その人を想っていても構わない。でも、僕が横にいるのを割り切ってくれると嬉しい。今日は久々会ったところで、僕にもこの部屋にも慣れていないだろう? だから、もう目を閉じて」
「ですが…」
「僕は隣の部屋にいるから、何かあれば入っておいで」
(そうだよな…、こんな想いになるなら、もっと会いに行っておくべきだった)
イザベルの言葉を聞きたくなかったランスロットは、彼女が口を開く間も与えず、夫婦の寝室の隣に配置された私室へ入った。
公爵位を継いだのは二年前、ランスロットは二十三歳、イザベルはまだ十七歳で、デビュタントに付き添って少し経ったころだった。父親が倒れそのまま帰らぬ人となり、長男であるランスロットは家を継がざるを得ず、恋愛の駆け引きをしている暇はなかった。
それでも、王家主催の夜会だけは欠かさなかった。ライヘンバッハ王家は、由緒あるオーレンドルフ公爵家が王女イザベルのエスコートを務めることが、貴族社会の安定に必要だと考えていた。ランスロットも同意見で、彼女への下心もあり、ユスティンから送られてくる招待だけは断らなかった。
16
あなたにおすすめの小説

田舎の幼馴染に囲い込まれた
兎角
恋愛
25.10/21 殴り書きの続き更新
都会に飛び出した田舎娘が渋々帰郷した田舎のムチムチ幼馴染に囲い込まれてズブズブになる予定 ※殴り書きなので改行などない状態です…そのうち直します。



放課後の保健室
一条凛子
恋愛
はじめまして。
数ある中から、この保健室を見つけてくださって、本当にありがとうございます。
わたくし、ここの主(あるじ)であり、夜間専門のカウンセラー、**一条 凛子(いちじょう りんこ)**と申します。
ここは、昼間の喧騒から逃れてきた、頑張り屋の大人たちのためだけの秘密の聖域(サンクチュアリ)。
あなたが、ようやく重たい鎧を脱いで、ありのままの姿で羽を休めることができる——夜だけ開く、特別な保健室です。



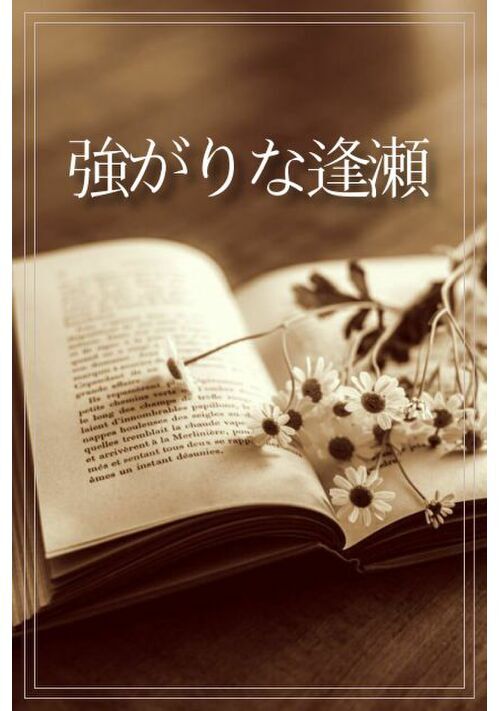
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















