8 / 27
第8話 自分を罵倒する
しおりを挟む
「僕も、そのコンテストに出品してみるよ」
「え、早川君が……官能小説を?」
「うん、僕も書いて綾瀬さんとお互いに評価し合う、で、お互いに出た意見をフィードバックさせて、完成度を上げていくんだ。
そうすれば、悩んで先に進めないなんてこと、減ると思うんだよ」
たしかに、誰かの意見があると問題は解決しやすい。
「でも、大丈夫なの? 早川君って、今度の丸川文庫の新人賞に応募するんじゃないの?」
「うん、でも向こうは締め切りが9月だから、まだ時間はある」
官能小説の締め切りは7月末日だ。それに比べて少しは余裕がある。だが、同時に二つの小説を書き進めることができるのだろうか?
それに、前期の試験だってある。
早川君が私を手伝ったとしても、デメリットしかない。
「大丈夫かな? 二つの作品を同時に書くって、難しくない?」
「確かに。だけど僕はバイトもしてないから時間はあるし、うまく頭を切り替えていけば書けないこともない」
さすがは早川君だ。私なんかより頭が良くて才能もあるから、二つ同時に書けてしまうのかもしれない。
でも……。
「あの……どうして?」
「ん?」
「どうして、早川君は私のために、そんなに協力してくれるの?」
「ええ?
え……と、僕も作品の幅を広げたいなと思ってたところで……、
そうしたら、綾瀬さんが官能小説を書いてるのを知っちゃったから、新しいジャンルとして良いかな……なんて。別に綾瀬さんのため、というわけじゃないんだ」
(そっか、そうだよね……わたしって、思いあがった事を言っちゃった)またもズレた発言をしてしまい、私は後悔する。
「そうなんだ、早川君って凄いね」
「そんなことないよ。そうだ、もうお昼だしランチにしようか?」
……ランチというと、あれだ。昼食の事だ。
私はビデオを観たら帰るものだと思っていたから、昼食の事まで考えていなかった。
(どうしよう……お財布には2,000円しか入っていない)
吉祥寺でランチを食べるとなると直ぐに2,000円なんて飛んでいく。いや、2,000円で済むのか?
適当な理由を作って、帰っちゃうか?
しかし、今後の事をまだ話し合っていない。そうだ、お店を限定すれば、例えばマックとか……、私は頭の中で電卓をピコピコと打つ。
「本当は、どこかお店で食べたいんだけど、この付近って観光客が多くて、この時間は凄い混雑してるんだよ」
「そ、そうだね……」動揺を抑えつつ相槌を打ち、心の中では(マッーク、マッーク」と合唱していた。
「せっかく来てくれて、こんなものしかご馳走できなくて悪いんだけど、宅配ピザでも大丈夫かな?」
(え、ピザ?)
ピザと言えば、高校生の時、学園祭の準備で遅くなった時に担任が奮発して注文してくれたことがある。
生徒一人につき一枚ずつしか食べられなかったけど、この世の中にこんなに美味しいものが存在したのかと感動したのを覚えている。
上京して、自分でもフライパンで見様見真似で作ったことがある。生地にケチャップを縫って、玉ねぎとピーマンのスライスを乗せ、チーズをばらまく。
あれでも十分美味しかったけど、まさか、本物を食べる日が来るとは!
私は興奮を抑えつつ、「うん、わたしピザ好きだし、よく食べてるから馴染みがあるものの方が助かるかな」と答えた。
(嘘です、食べてません)
「良かった~、ごめんね、手際が悪くて」
「ううん、でも、二人でランチ食べるって初めてだね」と言ってしまって、私はまた後悔する。
これって、初めて~しました的な、記念日作りたがり女子がやることだ。
またしても、(わたしの馬鹿、馬鹿、馬鹿! ああ~~~)」と心の中で頭を抱える。
「な、、なんだか記念日みたいだね」あはは、と笑う文剛。
今、彼は何を思ったのだろう? 付き合ってもいないのに、変な女と思われただろうか?
私の心配を他所に、事態は進む。
「綾瀬さんって、どれが好きなの」と言って、文剛はタブレットの画面を見せる。宅配ピザのメニューだ。
(うわ! こんなに種類があるのか!?)あまりの種類の多さに、私は戸惑った。
「(どうしよう? 何が何だかわからない)わたし何でも好きだから、早川君が適当に選んで」
「そう、じゃあ、クワトロにしようか」
「うん、わたし、クワトロ好きだよ。美味しいよね~」
「そうだね、4種類の味が楽しめるし」
(はて?)何の事だか私にはよく分からなかったが、とりあえずクワトロ味のピザを注文する事は分かった。
文剛は、タブレットに注文に必要な情報を入力すると、「30分くらいで着くって」と言った。
高校の時に注文した時は、90分くらいかかったと思うが、流石に東京のピザ屋は早い、と舌をまく。
「ピザが届くまでに、今後の事を話そうか?」
「うん、そうだね。どう進めていく?」
「まずは、綾瀬さんの環境なんだけど、いつも図書館のパソコンで書いているの?」
「うん、スマホで下書きして大方は書いているんだけど、どうしても誤字脱字ができてしまうから、最終的にパソコンで清書してチェックしてるの。
ライティングの仕事も同じやり方で済ませてるんだけど、自宅にパソコンがないから効率悪くて、なかなか捗らない」
「そうか、僕はノートに手書きして、それをパソコンで清書しているから、概ね同じやり方だね。
どうかな、平日はライティングの仕事に集中して、土曜日と日曜日に、ここで小説に集中するというのは。僕のパソコンを使えばよいよ」
「ここで? でも、お邪魔じゃないかしら。それに、早川君がパソコン使えなくて困らない?」
「お互いにアドバイスできて、その場で修正すれば効率良いし、僕はタブレットを使うから大丈夫。このタブレット、専用のキーボードついているから」
確かに魅力的な提案である。平日、ライティングの仕事に集中できれば収入も増えるし、週末に集中して小説を書ければ捗ることは確かだろう。
でも、そこまで彼に甘えて良いものだろうか?
それに、毎週男の子の部屋へ遊び――遊ぶわけではなく小説を書くことが目的ではあるが――に行くなんて、なんだか付き合っているみたいだ。
「付き合っているみたい……」
迂闊にも、心の中が口に出てしまい、私はハッとする。
(ああーー、盛大にやらかしてしまった! もう、頭上に隕石を落としてほしーーー! わたしの、ばか、バカ、馬鹿)
今日、何回目だろう? 自分を罵倒するのは。
「え、早川君が……官能小説を?」
「うん、僕も書いて綾瀬さんとお互いに評価し合う、で、お互いに出た意見をフィードバックさせて、完成度を上げていくんだ。
そうすれば、悩んで先に進めないなんてこと、減ると思うんだよ」
たしかに、誰かの意見があると問題は解決しやすい。
「でも、大丈夫なの? 早川君って、今度の丸川文庫の新人賞に応募するんじゃないの?」
「うん、でも向こうは締め切りが9月だから、まだ時間はある」
官能小説の締め切りは7月末日だ。それに比べて少しは余裕がある。だが、同時に二つの小説を書き進めることができるのだろうか?
それに、前期の試験だってある。
早川君が私を手伝ったとしても、デメリットしかない。
「大丈夫かな? 二つの作品を同時に書くって、難しくない?」
「確かに。だけど僕はバイトもしてないから時間はあるし、うまく頭を切り替えていけば書けないこともない」
さすがは早川君だ。私なんかより頭が良くて才能もあるから、二つ同時に書けてしまうのかもしれない。
でも……。
「あの……どうして?」
「ん?」
「どうして、早川君は私のために、そんなに協力してくれるの?」
「ええ?
え……と、僕も作品の幅を広げたいなと思ってたところで……、
そうしたら、綾瀬さんが官能小説を書いてるのを知っちゃったから、新しいジャンルとして良いかな……なんて。別に綾瀬さんのため、というわけじゃないんだ」
(そっか、そうだよね……わたしって、思いあがった事を言っちゃった)またもズレた発言をしてしまい、私は後悔する。
「そうなんだ、早川君って凄いね」
「そんなことないよ。そうだ、もうお昼だしランチにしようか?」
……ランチというと、あれだ。昼食の事だ。
私はビデオを観たら帰るものだと思っていたから、昼食の事まで考えていなかった。
(どうしよう……お財布には2,000円しか入っていない)
吉祥寺でランチを食べるとなると直ぐに2,000円なんて飛んでいく。いや、2,000円で済むのか?
適当な理由を作って、帰っちゃうか?
しかし、今後の事をまだ話し合っていない。そうだ、お店を限定すれば、例えばマックとか……、私は頭の中で電卓をピコピコと打つ。
「本当は、どこかお店で食べたいんだけど、この付近って観光客が多くて、この時間は凄い混雑してるんだよ」
「そ、そうだね……」動揺を抑えつつ相槌を打ち、心の中では(マッーク、マッーク」と合唱していた。
「せっかく来てくれて、こんなものしかご馳走できなくて悪いんだけど、宅配ピザでも大丈夫かな?」
(え、ピザ?)
ピザと言えば、高校生の時、学園祭の準備で遅くなった時に担任が奮発して注文してくれたことがある。
生徒一人につき一枚ずつしか食べられなかったけど、この世の中にこんなに美味しいものが存在したのかと感動したのを覚えている。
上京して、自分でもフライパンで見様見真似で作ったことがある。生地にケチャップを縫って、玉ねぎとピーマンのスライスを乗せ、チーズをばらまく。
あれでも十分美味しかったけど、まさか、本物を食べる日が来るとは!
私は興奮を抑えつつ、「うん、わたしピザ好きだし、よく食べてるから馴染みがあるものの方が助かるかな」と答えた。
(嘘です、食べてません)
「良かった~、ごめんね、手際が悪くて」
「ううん、でも、二人でランチ食べるって初めてだね」と言ってしまって、私はまた後悔する。
これって、初めて~しました的な、記念日作りたがり女子がやることだ。
またしても、(わたしの馬鹿、馬鹿、馬鹿! ああ~~~)」と心の中で頭を抱える。
「な、、なんだか記念日みたいだね」あはは、と笑う文剛。
今、彼は何を思ったのだろう? 付き合ってもいないのに、変な女と思われただろうか?
私の心配を他所に、事態は進む。
「綾瀬さんって、どれが好きなの」と言って、文剛はタブレットの画面を見せる。宅配ピザのメニューだ。
(うわ! こんなに種類があるのか!?)あまりの種類の多さに、私は戸惑った。
「(どうしよう? 何が何だかわからない)わたし何でも好きだから、早川君が適当に選んで」
「そう、じゃあ、クワトロにしようか」
「うん、わたし、クワトロ好きだよ。美味しいよね~」
「そうだね、4種類の味が楽しめるし」
(はて?)何の事だか私にはよく分からなかったが、とりあえずクワトロ味のピザを注文する事は分かった。
文剛は、タブレットに注文に必要な情報を入力すると、「30分くらいで着くって」と言った。
高校の時に注文した時は、90分くらいかかったと思うが、流石に東京のピザ屋は早い、と舌をまく。
「ピザが届くまでに、今後の事を話そうか?」
「うん、そうだね。どう進めていく?」
「まずは、綾瀬さんの環境なんだけど、いつも図書館のパソコンで書いているの?」
「うん、スマホで下書きして大方は書いているんだけど、どうしても誤字脱字ができてしまうから、最終的にパソコンで清書してチェックしてるの。
ライティングの仕事も同じやり方で済ませてるんだけど、自宅にパソコンがないから効率悪くて、なかなか捗らない」
「そうか、僕はノートに手書きして、それをパソコンで清書しているから、概ね同じやり方だね。
どうかな、平日はライティングの仕事に集中して、土曜日と日曜日に、ここで小説に集中するというのは。僕のパソコンを使えばよいよ」
「ここで? でも、お邪魔じゃないかしら。それに、早川君がパソコン使えなくて困らない?」
「お互いにアドバイスできて、その場で修正すれば効率良いし、僕はタブレットを使うから大丈夫。このタブレット、専用のキーボードついているから」
確かに魅力的な提案である。平日、ライティングの仕事に集中できれば収入も増えるし、週末に集中して小説を書ければ捗ることは確かだろう。
でも、そこまで彼に甘えて良いものだろうか?
それに、毎週男の子の部屋へ遊び――遊ぶわけではなく小説を書くことが目的ではあるが――に行くなんて、なんだか付き合っているみたいだ。
「付き合っているみたい……」
迂闊にも、心の中が口に出てしまい、私はハッとする。
(ああーー、盛大にやらかしてしまった! もう、頭上に隕石を落としてほしーーー! わたしの、ばか、バカ、馬鹿)
今日、何回目だろう? 自分を罵倒するのは。
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話
登夢
恋愛
春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。



友達の妹が、入浴してる。
つきのはい
恋愛
「交換してみない?」
冴えない高校生の藤堂夏弥は、親友のオシャレでモテまくり同級生、鈴川洋平にバカげた話を持ちかけられる。
それは、お互い現在同居中の妹達、藤堂秋乃と鈴川美咲を交換して生活しようというものだった。
鈴川美咲は、美男子の洋平に勝るとも劣らない美少女なのだけれど、男子に嫌悪感を示し、夏弥とも形式的な会話しかしなかった。
冴えない男子と冷めがちな女子の距離感が、二人暮らしのなかで徐々に変わっていく。
そんなラブコメディです。
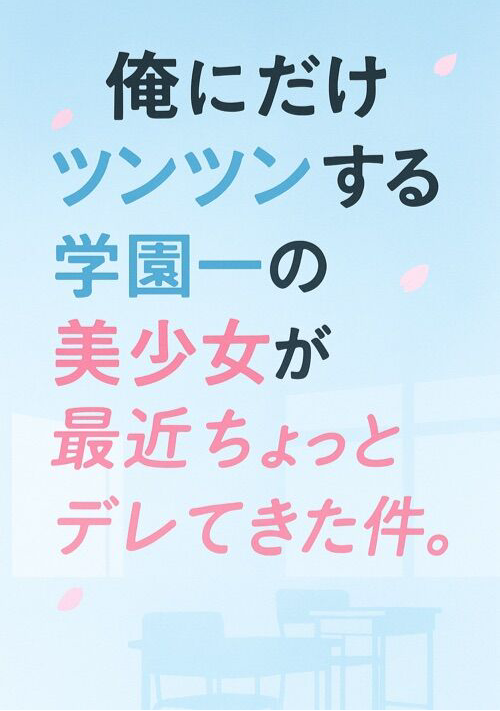
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















