あなたにおすすめの小説

勇者の様子がおかしい
しばたろう
ファンタジー
勇者は、少しおかしい。
そう思ったのは、王宮で出会ったその日からだった。
神に選ばれ、魔王討伐の旅に出た勇者マルク。
線の細い優男で、実力は確かだが、人と距離を取り、馴れ合いを嫌う奇妙な男。
だが、ある夜。
仲間のひとりは、決定的な違和感に気づいてしまう。
――勇者は、男ではなかった。
女であることを隠し、勇者として剣を振るうマルク。
そして、その秘密を知りながら「知らないふり」を選んだ仲間。
正体を隠す者と、真実を抱え込む者。
交わらぬはずの想いを抱えたまま、旅は続いていく。
これは、
「勇者であること」と
「自分であること」のあいだで揺れる物語。

追放された味噌カス第7王子の異種族たちと,のんびり辺境地開発
ハーフのクロエ
ファンタジー
アテナ王国の末っ子の第7王子に産まれたルーファスは魔力が0で無能者と言われ、大陸の妖精族や亜人やモンスターの多い大陸から離れた無人島に追放される。だが前世は万能スキル持ちで魔王を倒し英雄と呼ばれていたのを隠し生まれ変わってスローライフを送る為に無能者を装っていたのだ。そんなルーファスはスローライフを送るつもりが、無人島には人間族以外の種族の独自に進化した先住民がおり、周りの人たちが勝手に動いて気が付けば豊かで平和な強国を起こしていく物語です。
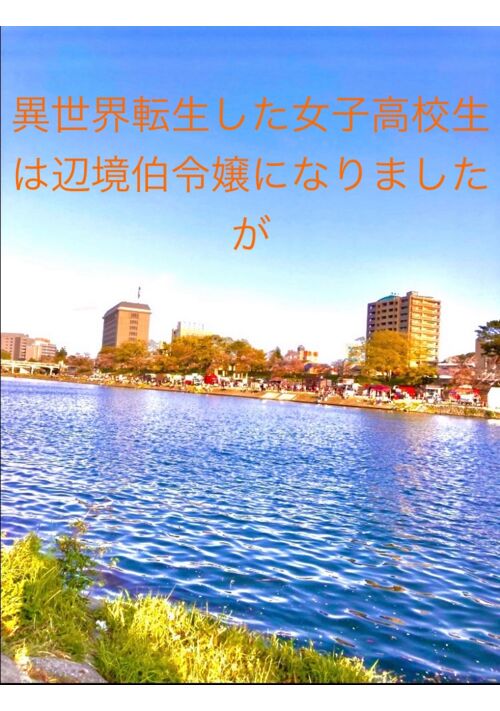
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

ゲーム未登場の性格最悪な悪役令嬢に転生したら推しの妻だったので、人生の恩人である推しには離婚して私以外と結婚してもらいます!
クナリ
ファンタジー
江藤樹里は、かつて画家になることを夢見ていた二十七歳の女性。
ある日気がつくと、彼女は大好きな乙女ゲームであるハイグランド・シンフォニーの世界へ転生していた。
しかし彼女が転生したのは、ヘビーユーザーであるはずの自分さえ知らない、ユーフィニアという女性。
ユーフィニアがどこの誰なのかが分からないまま戸惑う樹里の前に、ユーフィニアに仕えているメイドや、樹里がゲーム内で最も推しているキャラであり、どん底にいたときの自分の心を救ってくれたリルベオラスらが現れる。
そして樹里は、絶世の美貌を持ちながらもハイグラの世界では稀代の悪女とされているユーフィニアの実情を知っていく。
国政にまで影響をもたらすほどの悪名を持つユーフィニアを、最愛の恩人であるリルベオラスの妻でいさせるわけにはいかない。
樹里は、ゲーム未登場ながら圧倒的なアクの強さを持つユーフィニアをリルベオラスから引き離すべく、離婚を目指して動き始めた。

大ッ嫌いな英雄様達に告ぐ
鮭とば
ファンタジー
剣があって、魔法があって、けれども機械はない世界。妖魔族、俗に言う魔族と人間族の、原因は最早誰にもわからない、終わらない小競り合いに、いつからあらわれたのかは皆わからないが、一旦の終止符をねじ込んだ聖女様と、それを守る5人の英雄様。
それが約50年前。
聖女様はそれから2回代替わりをし、数年前に3回目の代替わりをしたばかりで、英雄様は数え切れないぐらい替わってる。
英雄の座は常に5つで、基本的にどこから英雄を選ぶかは決まってる。
俺は、なんとしても、聖女様のすぐ隣に居たい。
でも…英雄は5人もいらないな。


第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

偽夫婦お家騒動始末記
紫紺
歴史・時代
【第10回歴史時代大賞、奨励賞受賞しました!】
故郷を捨て、江戸で寺子屋の先生を生業として暮らす篠宮隼(しのみやはやて)は、ある夜、茶屋から足抜けしてきた陰間と出会う。
紫音(しおん)という若い男との奇妙な共同生活が始まるのだが。
隼には胸に秘めた決意があり、紫音との生活はそれを遂げるための策の一つだ。だが、紫音の方にも実は裏があって……。
江戸を舞台に様々な陰謀が駆け巡る。敢えて裏街道を走る隼に、念願を叶える日はくるのだろうか。
そして、拾った陰間、紫音の正体は。
活劇と謎解き、そして恋心の長編エンタメ時代小説です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















