6 / 13
6.フィランジェ王国のフォアグラ
しおりを挟む
「今後、セシリア嬢や側妃のことを口に出したのならば、即刻修道院に送ります」
王妃は侍女達に命じてビアンカを下がらせた。
「いやな思いをされたでしょう?ごめんなさいね」
王妃がアンジェリーナを労わる。
「国王として言うが、ウィンダムに側妃を娶る予定はないのだ。信じて欲しい」
眉間に皺を寄せて国王が言う。
「私も側妃など露ほども考えていません」
ウィンダムの言葉に、アンジェリーナは静かに目を伏せた。
「ビアンカは…」
少し迷ってからウィンダムが言い出した。
「あなたに張り合って意地悪をしてる面もあるのだが、実は婚約すら決まっていないのだ」
「はい」
アンジェリーナは静かに頷く。
「セシリア嬢の兄のカルロス・ベッキーノ伯爵令息に昔から熱を上げていて、そこ以外に嫁がないと言い張っている。今まで何度か内定した婚約も、手ひどく相手を侮辱して反故になった」
ウィンダムの話は続く。
ビアンカは七歳のお披露目でカルロス・ベッキーノ伯爵令息に一目惚れをして、以来彼を文字通り追いかけまわしている。
その年入学した学園ではそれが過ぎて「品位に欠ける」と学園側から厳重注意を何度も受けた。父母である国王夫妻が何度も諫めたがやめなかった。
どうにも収拾がつかなくなって、とうとうビアンカは学園から引き離されて、王宮での教育のみになった経緯がある。
他人と関わらずに使用人に傅かれて過ごしたビアンカは、王女であることを笠に着て、我儘で傲慢な娘に育ちあがってしまった。
王女の権威を振りかざして侍女やメイドを顎で使い、また買収して、カルロスに手紙を送り続けた。
ベッキーノ伯爵家では最初は迷惑に思っていたが、カルロスとセシリアの婚約者を探す年齢になると、ビアンカを利用することを考え始めたのだ。
セシリアとウィンダムが婚姻するならば、ビアンカとカルロスの婚姻を認めると上から出てきた。
王家にとって何の役得もないどころか損失でしかない縁談なので、撥ね付けたが。
それがまたベッキーノ伯爵家にはおもしろくない。散々ビアンカに悩まされた恨みもあるが、ベッキーノ伯爵家が成り上がるにはもってこいの機会だったからだ。ベッキーノ伯爵家は経済的にはやや苦しく、中央の重職についているわけでもない。王女の持参金と当然与えられるだろう重職を期待していたのだ。
ウィンダムとアンジェリーナの婚約は、アンジェリーナが産まれてすぐにフィランジェ王国がラバナン王国に打診したものだ。婚約内定は十二年前から調っており、たとえセシリア・ベッキーノ伯爵令嬢がいかなる好条件であっても飲めるものではない。
王太子の婚約が正式に発表された年からは、ビアンカはカルロスを通してベッキーノ伯爵に唆されて、側妃にセシリアをと迫るようになった。
王家で教育しているにもかかわらず、何も学ばず品位に欠けるビアンカを、国王夫妻は何度も
「いっそ修道院へ送ろう」
と考え話し合うのだが、王家の体面上なかなか踏み出せなかった。
とうとうビアンカやセシリアの適齢期が過ぎるころまで落ち着かなかったら、修道院行きと内定した。
「ビアンカは十六歳、ことによっては適齢期が過ぎなくとも修道院へ送ろうかとも考えています」
王妃がウィンダムの説明に、悲し気に締めくくった。
それも知らずに事あるごとにセシリアを焚きつけるビアンカを、ウィンダムは嫌っており、今では
「フォアグラ家鴨」
と陰で呼んでいた。
曰く
「自分の破滅を告げることも知らず鳴く病気の家鴨と同じだ」
いつしかフォアグラも忌み嫌うようになり、国王も王妃も見ると苦々しく思うので、宮廷ではフォアグラが食卓に上がらなくなった。
ウィンダムはアンジェリーナに手紙で
「フォアグラはお好きですか」
と尋ねたことがある。
アンジェリーナは返信にこう書いた。
「わざわざ病気にした家鴨の肝臓は好みません。我がラバナン王国ではフォアグラそのものを禁止しておりませんが、重税をかけることで流通と飼育を減らしております」
ウィンダムはこの言葉に好感を持った。
王妃は侍女達に命じてビアンカを下がらせた。
「いやな思いをされたでしょう?ごめんなさいね」
王妃がアンジェリーナを労わる。
「国王として言うが、ウィンダムに側妃を娶る予定はないのだ。信じて欲しい」
眉間に皺を寄せて国王が言う。
「私も側妃など露ほども考えていません」
ウィンダムの言葉に、アンジェリーナは静かに目を伏せた。
「ビアンカは…」
少し迷ってからウィンダムが言い出した。
「あなたに張り合って意地悪をしてる面もあるのだが、実は婚約すら決まっていないのだ」
「はい」
アンジェリーナは静かに頷く。
「セシリア嬢の兄のカルロス・ベッキーノ伯爵令息に昔から熱を上げていて、そこ以外に嫁がないと言い張っている。今まで何度か内定した婚約も、手ひどく相手を侮辱して反故になった」
ウィンダムの話は続く。
ビアンカは七歳のお披露目でカルロス・ベッキーノ伯爵令息に一目惚れをして、以来彼を文字通り追いかけまわしている。
その年入学した学園ではそれが過ぎて「品位に欠ける」と学園側から厳重注意を何度も受けた。父母である国王夫妻が何度も諫めたがやめなかった。
どうにも収拾がつかなくなって、とうとうビアンカは学園から引き離されて、王宮での教育のみになった経緯がある。
他人と関わらずに使用人に傅かれて過ごしたビアンカは、王女であることを笠に着て、我儘で傲慢な娘に育ちあがってしまった。
王女の権威を振りかざして侍女やメイドを顎で使い、また買収して、カルロスに手紙を送り続けた。
ベッキーノ伯爵家では最初は迷惑に思っていたが、カルロスとセシリアの婚約者を探す年齢になると、ビアンカを利用することを考え始めたのだ。
セシリアとウィンダムが婚姻するならば、ビアンカとカルロスの婚姻を認めると上から出てきた。
王家にとって何の役得もないどころか損失でしかない縁談なので、撥ね付けたが。
それがまたベッキーノ伯爵家にはおもしろくない。散々ビアンカに悩まされた恨みもあるが、ベッキーノ伯爵家が成り上がるにはもってこいの機会だったからだ。ベッキーノ伯爵家は経済的にはやや苦しく、中央の重職についているわけでもない。王女の持参金と当然与えられるだろう重職を期待していたのだ。
ウィンダムとアンジェリーナの婚約は、アンジェリーナが産まれてすぐにフィランジェ王国がラバナン王国に打診したものだ。婚約内定は十二年前から調っており、たとえセシリア・ベッキーノ伯爵令嬢がいかなる好条件であっても飲めるものではない。
王太子の婚約が正式に発表された年からは、ビアンカはカルロスを通してベッキーノ伯爵に唆されて、側妃にセシリアをと迫るようになった。
王家で教育しているにもかかわらず、何も学ばず品位に欠けるビアンカを、国王夫妻は何度も
「いっそ修道院へ送ろう」
と考え話し合うのだが、王家の体面上なかなか踏み出せなかった。
とうとうビアンカやセシリアの適齢期が過ぎるころまで落ち着かなかったら、修道院行きと内定した。
「ビアンカは十六歳、ことによっては適齢期が過ぎなくとも修道院へ送ろうかとも考えています」
王妃がウィンダムの説明に、悲し気に締めくくった。
それも知らずに事あるごとにセシリアを焚きつけるビアンカを、ウィンダムは嫌っており、今では
「フォアグラ家鴨」
と陰で呼んでいた。
曰く
「自分の破滅を告げることも知らず鳴く病気の家鴨と同じだ」
いつしかフォアグラも忌み嫌うようになり、国王も王妃も見ると苦々しく思うので、宮廷ではフォアグラが食卓に上がらなくなった。
ウィンダムはアンジェリーナに手紙で
「フォアグラはお好きですか」
と尋ねたことがある。
アンジェリーナは返信にこう書いた。
「わざわざ病気にした家鴨の肝臓は好みません。我がラバナン王国ではフォアグラそのものを禁止しておりませんが、重税をかけることで流通と飼育を減らしております」
ウィンダムはこの言葉に好感を持った。
12
あなたにおすすめの小説

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。

離婚するはずの旦那様を、なぜか看病しています
鍛高譚
恋愛
「結婚とは、貴族の義務。そこに愛など不要――」
そう割り切っていた公爵令嬢アルタイは、王命により辺境伯ベガと契約結婚することに。
お互い深入りしない仮面夫婦として過ごすはずが、ある日ベガが戦地へ赴くことになり、彼はアルタイにこう告げる。
「俺は生きて帰れる自信がない。……だから、お前を自由にしてやりたい」
あっさりと“離婚”を申し出る彼に、アルタイは皮肉めいた笑みを浮かべる。
「では、戦争が終わり、貴方が帰るまで離婚は待ちましょう。
戦地で女でも作ってきてください。そうすれば、心置きなく別れられます」
――しかし、戦争は長引き、何年も経ったのちにようやく帰還したベガは、深い傷を負っていた。
彼を看病しながら、アルタイは自分の心が変化していることに気づく。
「早く元気になってもらわないと、離婚できませんね?」
「……本当に、離婚したいのか?」
最初は“義務”だったはずの結婚。しかし、夫婦として過ごすうちに、仮面は次第に剥がれていく。
やがて、二人の離婚を巡る噂が王宮を騒がせる中、ベガは決意を固める――。

愛人を選んだ夫を捨てたら、元婚約者の公爵に捕まりました
由香
恋愛
伯爵夫人リュシエンヌは、夫が公然と愛人を囲う結婚生活を送っていた。
尽くしても感謝されず、妻としての役割だけを求められる日々。
けれど彼女は、泣きわめくことも縋ることもなく、静かに離婚を選ぶ。
そうして“捨てられた妻”になったはずの彼女の前に現れたのは、かつて婚約していた元婚約者――冷静沈着で有能な公爵セドリックだった。
再会とともに始まるのは、彼女の価値を正しく理解し、決して手放さない男による溺愛の日々。
一方、彼女を失った元夫は、妻が担っていたすべてを失い、社会的にも転落していく。
“尽くすだけの妻”から、“選ばれ、守られる女性”へ。
静かに離婚しただけなのに、
なぜか元婚約者の公爵に捕まりました。


勇者の様子がおかしい
しばたろう
ファンタジー
勇者は、少しおかしい。
そう思ったのは、王宮で出会ったその日からだった。
神に選ばれ、魔王討伐の旅に出た勇者マルク。
線の細い優男で、実力は確かだが、人と距離を取り、馴れ合いを嫌う奇妙な男。
だが、ある夜。
仲間のひとりは、決定的な違和感に気づいてしまう。
――勇者は、男ではなかった。
女であることを隠し、勇者として剣を振るうマルク。
そして、その秘密を知りながら「知らないふり」を選んだ仲間。
正体を隠す者と、真実を抱え込む者。
交わらぬはずの想いを抱えたまま、旅は続いていく。
これは、
「勇者であること」と
「自分であること」のあいだで揺れる物語。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
私は、夫にも子供にも選ばれなかった。
その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。
そこで待っていたのは、最悪の出来事――
けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。
夫は愛人と共に好きに生きればいい。
今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。
でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。
妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。
過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――
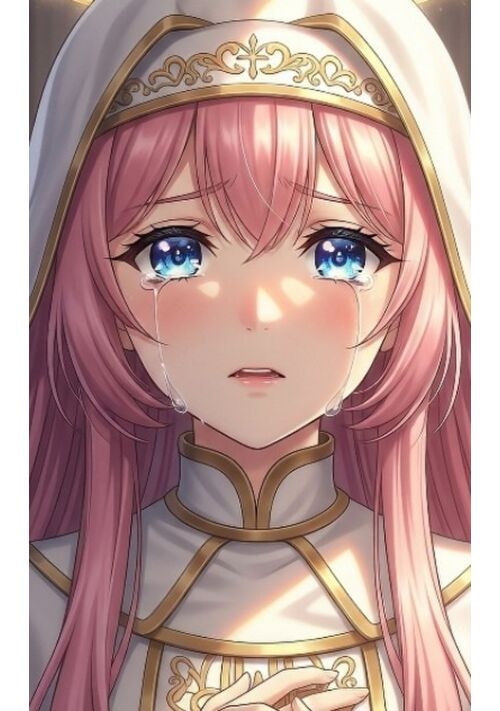
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!

婚約破棄して泥を投げつけた元婚約者が「無能」と笑う中、光り輝く幼なじみの王子に掠め取られました。
ムラサメ
恋愛
「お前のような無能、我が家には不要だ。今すぐ消えろ!」
婚約者・エドワードのために身を粉にして尽くしてきたフィオナは、卒業パーティーの夜、雨の中に放り出される。
泥にまみれ、絶望に沈む彼女の前に現れたのは、かつての幼なじみであり、今や国中から愛される「黄金の王子」シリルだった。
「やっと見つけた。……ねえ、フィオナ。あんなゴミに君を傷つけさせるなんて、僕の落ち度だね」
汚れを厭わずフィオナを抱き上げたシリルは、彼女を自分の屋敷へと連れ帰る。
「自分には価値がない」と思い込むフィオナを、シリルは異常なまでの執着と甘い言葉で、とろけるように溺愛し始めて――。
一方で、フィオナを捨てたエドワードは気づいていなかった。
自分の手柄だと思っていた仕事も、領地の繁栄も、すべてはフィオナの才能によるものだったということに。
ボロボロになっていく元婚約者。美しく着飾られ、シリルの腕の中で幸せに微笑むフィオナ。
「僕の星を捨てた報い、たっぷりと受けてもらうよ?」
圧倒的な光を放つ幼なじみによる、最高に華やかな逆転劇がいま始まる!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















