2 / 3
2
しおりを挟む
今日も酔いに任せて下卑た言葉を投げつけるお客が一杯でした。まだまだ私は新人でお客は酒の肴に私にちょっかいを出します。私は笑顔でくるくるとお店の中を立ち回るとこちらも上品とは言えない冗談でかわしていました。
化粧もせず清楚な身なりの私は夜の顔では珍しいようでたちまち人気者になりました。握手やハグを求められたり、チップを頂いたりと異様に店は盛り上がりました。お店のママはそれをひがむ事なく私を褒めてくれます。ママは夫の事を知っており、(ここらの飲み屋で私の夫はお代をよくつけにする危険客として知られています)私に同情して優しくしてくださいます。
私はお酒を注いでは片付けをし、話しかけられれば相槌だけでなくこちらからも話しかけ、歌を誘われればにこにこしながら声色を変え、酔い過ぎたお客がいれば介抱をし、一人二役といった具合で仕事をしていきました。忙しければ忙しいほど頭が明瞭になり煩わしいことから逃れられました。止まってしまうと駄目になるという気がしていたのです。
そして夜もさらに更けてお客がまばらになり始めた頃一組のお客がお店に入ってきました。髪を綺麗に飾った大柄な女と黒いハットを深く被った男です。その男は紛れもなく夫でした。夫は私には気付かず奥のボックス席に座りました。その場で私はひと時止まってしまいました。胸の鼓動は微かに何かを訴えるように早くなり始めました。ママの方を見ると、ママもまた夫に気付いているようで、顎をしゃくります。私は夫のいるテーブルへ行き平然を装い笑顔で言いました。
「いらっしゃいませ。お飲み物は何にしましょう。」
隣にいる大柄な女はかなり泥酔しているようで下を向いて自分の太腿をパタパタと叩いたりしています。そして、酔ったわ~、と甘い声をうわ言のように度々出しています。夫もかなりの量を飲んでいるらしく、いつもより顔が青白くなっていました。しかし夫はお酒に滅法強く、口調や態度に酔いは出ない人です。だから普通の人には今の夫がお酒を飲んでいるなんてわからないでしょう。私の顔を見て少し何かを考える間を置いて「君か。」と喋った顔もいつもとなんら変わらないようでした。
「はい、わたしです。」
「ウイスキーを下さい。」
夫はなんでもないように頼みました。
「かしこまりました。」
私は業務用の言葉でそう言いお酒を取りに行きました。お客用の事務的な言葉じゃないと、この人をただのお客と思って接しないと、私的な感情を出すともう自分が壊れてその場でわんわん泣いてしまう気がしたからです。
テーブルにお酒を持って戻ると夫は嗚咽を漏らして泣いていました。例の悲壮に満ちた顔でした。夫も壊れる寸前だったのでしょうか。
「ちょっと、お客さん、どうしたのですか。」
私は少し明るく微笑みは絶やさずに言いました。言ったあとに私はなんだか卑劣で嫌味で残酷な振る舞いをしているような気がしてきました。そして私は顔を顰める夫になんと声をかけて良いやらわからなくて居たたまれなくなり、その場から逃げ出しママの方へ行ったり洗い物の方へ行ったりしました。そうして遠くから夫のいるボックス席にちらちら視線を走らせていました。やはり平静は装えません。
「行かないでいいのかい。」
いつも格調の高い笑顔を浮かべていて、それで愛嬌も備えてあるママがいつになく真剣な顔をして言いました。その言葉で私はもう一度夫のテーブルに行く決意というか、勇気が出ました。
大柄な女はソファーに体を預けて目を閉じて唸っています。夫に入れ込んでいる女の一人でしょう。別に目の敵にしているわけではないのですが、馬鹿な女だと私は思いました。その大柄でマスクを被っているような厚い化粧をした煌びやかな女に水を飲ませトイレに案内し、一人になった夫に話しかけました。
「ここで働いている事話してなかったですね。」
「いいんです。僕が悪いんですから。」
夫は泣き止んでいて、それでも罪悪感を持っているような目で言いました。
「いえいえ。それよりここのママさん良い人でね、わたしでも気楽に働けるの。ここじゃわたし人気者なんですよ。」
喋ってはいるけれど私は自分で何を喋っているのかわかりませんでした。ただ夫の話す言葉だけに集中していました。
「今日は祭りだったんですね・・・・・。僕ちゃん泣いていましたね。」
夫は息子と私が今夜泣いていたのを聞いていたようです。私は黙ってしまいました。
「寂しかったのでしょう。僕も小さなとき、僕ちゃんみたいな寂しい思いをしたことがあります。僕には母親がいないって話はしたでしょう。父親しか僕にはいなくて、その父はいつも働き詰めでした。授業参観日というものが僕は大嫌いでした。周りの親は来ているのにいつも僕の親は来れなくて、学校が終わって下校途中によく泣いていました。そんな思いを僕は僕ちゃんにさせているのです。酷いですね僕は。僕の親は僕を育てる為に仕事をして参観日に来れなかったのに、僕ときたら何も理由がないのに僕ちゃんを寂しくさせている。君がここで働いているのも全て僕のせいだ。」
夫はグラスをくいっと空にし、ため息をつきながら顔を引き攣らせました。
「くそっ!こんな女、君の方が全く素敵で可愛げがあるのに。なんでこんな女と酒を飲み回らなければならないんだ!」
私は出会ってまだ月日の浅い、まだまともだった頃に夫が言った言葉を思い出していました。
冬の朝方、抜けるような青い空の下で夫はこう言ったのです。
「憎まれたほうが愛されるんです。」
その言葉が今私の中で充満して少し幸せな気分にしてくれました。もしかしたら夫は私に愛されたいがために憎まれようとしているのではないかという考えがポッと出たからです。私は自分をあきれ返るほどの楽天家だなと思い、そしてこんな堕落した夫でもまだ愛している自分に笑い声を吹き出してしまいました。こんな暗い雰囲気と良いことなんて何もない場面で私のその声はとても不釣り合いに響きました。ああいけないと思い、真剣な顔を作ろうと試みましたがもう笑い声は止まりません。抑えようにもくっくっ、と後から後からこみ上げてくるのです。夫もなぜだか笑いだしました。いつもの卑屈な冷笑ではなく、本当に久しぶりに夫の屈託のない笑い声を聞いたような気がします。その声でなんだか私の胸の奥にあった重く黒い塊は溶けていくようでした。ひとしきり二人で笑いあった後、二人とも違う理由で笑いあったのでしょうけど夫は改まって口を開きました。
「そろそろ帰ります。僕ちゃんの顔が見たくなりましたから。」
「あら、そうですか。」
私はこれから砕けた会話が少しでもできると思っていましたので、内心肩透かしを食らったような気分で、それでも虚勢を張りさらりと言いました。
夫はトイレから戻ってきていた女を起こし財布から五千円を抜き取るとそれをテーブルに置いて「また来ます。」と言って出て行きました。
今日は夫が帰っていると思い仕事が終わると足早に帰ってみましたが、居ませんでした。いつも寝相が悪く布団から抜け出てしまう息子が布団の中央で寝息を立てていたので、本当に家には一度帰ったようです。
化粧もせず清楚な身なりの私は夜の顔では珍しいようでたちまち人気者になりました。握手やハグを求められたり、チップを頂いたりと異様に店は盛り上がりました。お店のママはそれをひがむ事なく私を褒めてくれます。ママは夫の事を知っており、(ここらの飲み屋で私の夫はお代をよくつけにする危険客として知られています)私に同情して優しくしてくださいます。
私はお酒を注いでは片付けをし、話しかけられれば相槌だけでなくこちらからも話しかけ、歌を誘われればにこにこしながら声色を変え、酔い過ぎたお客がいれば介抱をし、一人二役といった具合で仕事をしていきました。忙しければ忙しいほど頭が明瞭になり煩わしいことから逃れられました。止まってしまうと駄目になるという気がしていたのです。
そして夜もさらに更けてお客がまばらになり始めた頃一組のお客がお店に入ってきました。髪を綺麗に飾った大柄な女と黒いハットを深く被った男です。その男は紛れもなく夫でした。夫は私には気付かず奥のボックス席に座りました。その場で私はひと時止まってしまいました。胸の鼓動は微かに何かを訴えるように早くなり始めました。ママの方を見ると、ママもまた夫に気付いているようで、顎をしゃくります。私は夫のいるテーブルへ行き平然を装い笑顔で言いました。
「いらっしゃいませ。お飲み物は何にしましょう。」
隣にいる大柄な女はかなり泥酔しているようで下を向いて自分の太腿をパタパタと叩いたりしています。そして、酔ったわ~、と甘い声をうわ言のように度々出しています。夫もかなりの量を飲んでいるらしく、いつもより顔が青白くなっていました。しかし夫はお酒に滅法強く、口調や態度に酔いは出ない人です。だから普通の人には今の夫がお酒を飲んでいるなんてわからないでしょう。私の顔を見て少し何かを考える間を置いて「君か。」と喋った顔もいつもとなんら変わらないようでした。
「はい、わたしです。」
「ウイスキーを下さい。」
夫はなんでもないように頼みました。
「かしこまりました。」
私は業務用の言葉でそう言いお酒を取りに行きました。お客用の事務的な言葉じゃないと、この人をただのお客と思って接しないと、私的な感情を出すともう自分が壊れてその場でわんわん泣いてしまう気がしたからです。
テーブルにお酒を持って戻ると夫は嗚咽を漏らして泣いていました。例の悲壮に満ちた顔でした。夫も壊れる寸前だったのでしょうか。
「ちょっと、お客さん、どうしたのですか。」
私は少し明るく微笑みは絶やさずに言いました。言ったあとに私はなんだか卑劣で嫌味で残酷な振る舞いをしているような気がしてきました。そして私は顔を顰める夫になんと声をかけて良いやらわからなくて居たたまれなくなり、その場から逃げ出しママの方へ行ったり洗い物の方へ行ったりしました。そうして遠くから夫のいるボックス席にちらちら視線を走らせていました。やはり平静は装えません。
「行かないでいいのかい。」
いつも格調の高い笑顔を浮かべていて、それで愛嬌も備えてあるママがいつになく真剣な顔をして言いました。その言葉で私はもう一度夫のテーブルに行く決意というか、勇気が出ました。
大柄な女はソファーに体を預けて目を閉じて唸っています。夫に入れ込んでいる女の一人でしょう。別に目の敵にしているわけではないのですが、馬鹿な女だと私は思いました。その大柄でマスクを被っているような厚い化粧をした煌びやかな女に水を飲ませトイレに案内し、一人になった夫に話しかけました。
「ここで働いている事話してなかったですね。」
「いいんです。僕が悪いんですから。」
夫は泣き止んでいて、それでも罪悪感を持っているような目で言いました。
「いえいえ。それよりここのママさん良い人でね、わたしでも気楽に働けるの。ここじゃわたし人気者なんですよ。」
喋ってはいるけれど私は自分で何を喋っているのかわかりませんでした。ただ夫の話す言葉だけに集中していました。
「今日は祭りだったんですね・・・・・。僕ちゃん泣いていましたね。」
夫は息子と私が今夜泣いていたのを聞いていたようです。私は黙ってしまいました。
「寂しかったのでしょう。僕も小さなとき、僕ちゃんみたいな寂しい思いをしたことがあります。僕には母親がいないって話はしたでしょう。父親しか僕にはいなくて、その父はいつも働き詰めでした。授業参観日というものが僕は大嫌いでした。周りの親は来ているのにいつも僕の親は来れなくて、学校が終わって下校途中によく泣いていました。そんな思いを僕は僕ちゃんにさせているのです。酷いですね僕は。僕の親は僕を育てる為に仕事をして参観日に来れなかったのに、僕ときたら何も理由がないのに僕ちゃんを寂しくさせている。君がここで働いているのも全て僕のせいだ。」
夫はグラスをくいっと空にし、ため息をつきながら顔を引き攣らせました。
「くそっ!こんな女、君の方が全く素敵で可愛げがあるのに。なんでこんな女と酒を飲み回らなければならないんだ!」
私は出会ってまだ月日の浅い、まだまともだった頃に夫が言った言葉を思い出していました。
冬の朝方、抜けるような青い空の下で夫はこう言ったのです。
「憎まれたほうが愛されるんです。」
その言葉が今私の中で充満して少し幸せな気分にしてくれました。もしかしたら夫は私に愛されたいがために憎まれようとしているのではないかという考えがポッと出たからです。私は自分をあきれ返るほどの楽天家だなと思い、そしてこんな堕落した夫でもまだ愛している自分に笑い声を吹き出してしまいました。こんな暗い雰囲気と良いことなんて何もない場面で私のその声はとても不釣り合いに響きました。ああいけないと思い、真剣な顔を作ろうと試みましたがもう笑い声は止まりません。抑えようにもくっくっ、と後から後からこみ上げてくるのです。夫もなぜだか笑いだしました。いつもの卑屈な冷笑ではなく、本当に久しぶりに夫の屈託のない笑い声を聞いたような気がします。その声でなんだか私の胸の奥にあった重く黒い塊は溶けていくようでした。ひとしきり二人で笑いあった後、二人とも違う理由で笑いあったのでしょうけど夫は改まって口を開きました。
「そろそろ帰ります。僕ちゃんの顔が見たくなりましたから。」
「あら、そうですか。」
私はこれから砕けた会話が少しでもできると思っていましたので、内心肩透かしを食らったような気分で、それでも虚勢を張りさらりと言いました。
夫はトイレから戻ってきていた女を起こし財布から五千円を抜き取るとそれをテーブルに置いて「また来ます。」と言って出て行きました。
今日は夫が帰っていると思い仕事が終わると足早に帰ってみましたが、居ませんでした。いつも寝相が悪く布団から抜け出てしまう息子が布団の中央で寝息を立てていたので、本当に家には一度帰ったようです。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。



JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
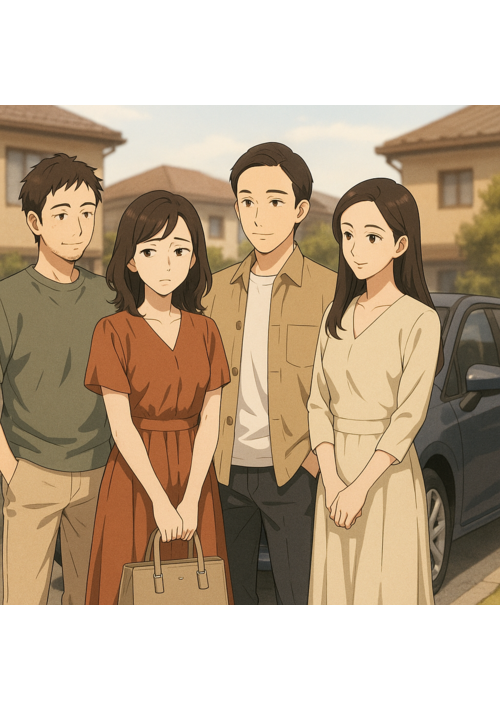
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















