15 / 52
魔法使いの同居人
15話
しおりを挟む
昨夜降った雨のせいで校庭はぬかるんでいた。歩くたびに靴の底に泥が貼りつく嫌な感触がする。倉庫前を待ち合わせ場所に選んだのは失敗だったかもしれない。呼び出した相手に申し訳ない気持ちになるが、今さら場所を変更するわけにもいかない。
しばらくすると校舎の方からこちらに向かってくる待ち人の姿が見えてきた。ゆっくりと余裕を感じさせる足取りでやって来る。
「一ノ瀬からサボりの誘いなんて、珍しいね。雪でも降るんじゃない?」
涼川さんはぶっきらぼうに言った。
「やめてよ。雪は嫌いなんだ」
「どうして?」
「特に理由はないけど」
「私は好きだよ。冬眠してしまう動物もいるけど、逆に冬にだけ姿を見せる動物がいて、他の季節とは違った楽しさがある」
涼川さんは目を閉じると薄く笑った。
瞼の裏に動物が見ているのかもしれない。
再び目を開いたとき、涼川さんの表情から笑みは消えていた。気だるそうないつもの彼女に戻っていた。
「それで、ここに呼び出した目的は何なの?」
「あれ? 紗月さんから聞かなかった?」
「紗月って? あの透明人間のこと?」
どうやら紗月さんは何も説明しなかったらしい。自分の名前すらも。自ら伝言役を買って出たくせに、ずさんな仕事ぶりだ。
僕は紗月さんについて簡単に説明する。催眠術を使えること。そして人形遣いを見つけるために学校へ忍び込んでいること。
彼女が泥棒であることと、僕の家に仕事で侵入していることはややこしいので伏せておいた。こればっかりは僕と紗月さんの問題であって、涼川さんには関係のないことだ。
説明を聞いた涼川さんは一言「なるほどね」と言った。
話を疑うこともなく、すんなりと飲み込んでくれる。きっと僕と同じように、彼女の能力を目の当たりしてしまった以上、信じるしかないといった心境なのだろう。
あるいは、自身も特別な力を持っていることで、免疫があるのかもしれない。
「それで」と涼川さんは切り出す。
「一ノ瀬はその友達を紹介するためにここへ来たの?」
「もちろん違うよ。でも、本題に入る前に紗月さんを紹介する必要があったんだ」
「それなら、そろそろ本題に入りましょう」
涼川さんの目はまっすぐに僕を見つめている。その目の奥に寂しさが混じっているように思えた。涼川さんはきっと呼び出された理由に勘付いているのだろう。
「人形遣いの正体は涼川さん、君なんだね」
僕は単刀直入に言った。
彼女から視線をそらさず正面から見つめ合う。
涼川さんに動じている様子はなかった。いつもの落ち着いた表情のままだ。
二人とも黙ったまま時間だけが過ぎる。気まずさはあったが、辛抱して彼女の言葉を待つ。
「一応、そう思った理由を聞いてもいい」
僕はズボンのポケットから、用意していた一枚の写真を取り出した。それは雨森さんの手帳に挟まれていた校庭の写真だった。今朝、雨森さんに頭を下げて拝借したのだ。
写真を涼川さんへ差し出す。
「先日二人でこれを見たのは覚えているよね」
「ええ。覚えてるわ」
「そこに何が写っているか教えてくれる?」
涼川さんは写真に目を落とすと「私たちが今いる校庭の写真でしょ。植えられた桜の木とフェンスの向こうには家がある」と見たものを一つ一つ説明してくれる。
「それから小学生が二人いるわね」
「ほかには?」
僕の問いに涼川さんは首を傾げる。
「ほかには何もいないけど」
「そうだよね。僕も涼川さんが言ってくれた以外のものは見えない。つまり僕と涼川さんには、その写真が同じように見えているんだ」
「当り前じゃない。一ノ瀬は何が言いたいわけ?」
「実は写真には、ほかにも写されているものがあるんだよ」
僕は涼川さんの手から写真を受け取る。そしてその中に写る、自分には見えていないあるものの姿を想像する。
「この写真にはね、猫がいるんだよ」
「猫?」
僕は頷く。写真の中には猫がいる。それは会長と雨森さんと紗月さん、三人から証言を得た情報だ。僕にはそれが見えない。
なぜ三人に見えて、僕には見えないのか。
言うまでもない、紗月さんの催眠術のせいだ。
「僕は募金活動のあった日に、募金箱をこの倉庫へ取りに行った。そのときに倉庫の中で紗月さんに催眠術を掛けてもらったんだ。その催眠術っていうのが、窓の外にいた猫を見えないようにするものだった」
あの日のやり取りを思い出す。
紗月さんの言葉と同時に、窓の外にいた猫が一瞬にして姿を消した。あの瞬間、催眠術によって、僕は三毛猫を認識することができなくなった。だから写真の中にいるはずの猫が僕には見えないのだ。
それでは涼川さんはどうだろう。
どうして僕と同じく、彼女にも猫が認識できないのか。
答えは一つしかない。
涼川さんも僕と同じタイミングで、紗月さんに催眠術に掛けられていたのだ。
「あのとき涼川さんも倉庫の中にいたんだ。僕らより先に倉庫に入っていた涼川さんは、おそらくドアの前で僕と用務員のおじさんが会話しているのを聞いて、物陰に隠れた。そして紗月さんが僕に掛けた催眠術に、君も掛かってしまったんだ」
倉庫で隠れているとき、涼川さんには紗月さんの声は聞こえていなかったはずだ。僕が独り言を言っているように聞こえただろう。
しかし紗月さんは言っていた。認識できなくなっただけで、紗月さんの声は催眠術を掛けられた人にも聞こえるのだと。
涼川さんは気づかないうちに、僕と同じく猫が見えなくなっていたのだ。
涼川さんは無言だった。無駄な口を挟まずに、まずは僕にすべてを話させようとしている。彼女の望み通り話を続ける。
「会長の事件が起きたとき、倉庫は密室になっていた。ドアノブの取り換え作業が行われていて、僕が部屋を出てから事件が終わるまで、誰も室内に入れない状態だった。それなのに僕が倉庫で見たライン引きが犯行に使われていた。密室となっていた倉庫から何者かに持ち出されていたんだ。でも犯人が密室になる前から室内にいたと考えれば、何も不思議なことはない。僕がいなくなった後に、室内から窓を使って外に出ればいいだけの話だ。倉庫の窓は室内からは開閉が可能で、外に出た後に窓を閉めればロックがかかる仕組みになっていた。手の込んだトリックも特殊能力も必要なかったんだ」
僕は間を置くと、もう一度確認の言葉を口にする。
「涼川さんが人形遣いだったんだね」
気づかなかったことにすることもできた。素知らぬ顔でこれまでと同じように付き合い続けることも可能だった。それでも僕は彼女と対峙することを選んだのだ。
涼川さんの顔に柔らかな色が差した。
「うん」どこか晴れやかな表情で涼川さんは首を縦に振った。
「私が人形遣いよ」
喉の奥にツンとした痛みが走る。胸に穴が開いたような気分だ。
間違いであってほしかった、というのが本心だった。
これだけカッコつけておいて「間違ってました」では、晩年まで忘れられない大恥をかくことになった。それでもこんな気持ちを味わうくらいなら、恥をかいた方がずっとよかった。
「なんだか一ノ瀬、名探偵みたいだったよ」
「買いかぶりすぎだよ。だって涼川さんがどうしてこんなことをしたのか、僕にはまるでわからないんだ」
急に強い風が吹いた。
涼川さんは乱れた前髪をかき上げながら、伏し目がちに語りだした。
「生徒会は文化祭の日程を延ばそうとしていたでしょ。それをどうしても食い止めたかったの」
予想外の回答に面食らってしまう。
確かに涼川さんは文化祭を楽しむタイプの人間ではないとは思うが、こんなことをしでかすほど嫌だったというのか。
「そんな理由で?」という言葉が出かけたが、思い直した。涼川さんが利己的な理由でこんなにことを仕出かすはずがない。僕には彼女の本心はわからないけれど、これだけは確信を持って言える。
「中庭の鳥小屋にいる子達ね、ケイスケとケイコっていうの」
急に話が変わった。意味するところがわからないので、黙って次の台詞を待つ。
「文化祭の期間中、中庭は模擬店とかで騒がしいから、あの子たちは用務員室に預けられることになってるの」
「知ってるよ。生徒会で手続きをしたからね」
「一ノ瀬は行ったことないかもしれないけど、用務員室って凄く埃っぽくて、湿度が高いの。人間にはわからないかもしれないけど、あの子たちに取ってはひどい環境なのよ。だから期間中、私が引き取ることを先生に提案してみた。でも学校で飼っている動物を生徒個人に預けることはできないって断られちゃった。だからせめて文化祭の開催日数だけでも短くしてあげたかったの。生徒会役員が不祥事で退任すれば、先生たちと交渉する人はいなくなるでしょ」
涼川さんが弱弱しく微笑んだ。見たことのない表情だった。
「それだけのためにあんな大事を起こしたなんて、一ノ瀬には理解できないでしょ?」
涼川さんが問いかけてくる。
正直に言えば理解できなかった。
彼女が動物を大事にしていることは知っているし、誰に頼まれたわけでもないのに献身的に世話を焼いているのを何度となく目撃したことがある。それでも僕には鶏のためにそこまでする彼女の気持ちがわからなかった。誤解を恐れずに言ってしまえば、たかが動物じゃないかと思ってしまう。
しかし涼川さんにとっては「たかが」ではないのだろう。人に迷惑をかけることを良しとしない彼女が僕らに牙を剥くほどに重要なことなのだ。
その気持ちを否定してはいけないことくらいわかる。理解はできなくても許容したいと思った。方法は間違っているかもしれない。だけどそれを許すことができるのは友達の特権だ。
一方で、僕が悔しくてしかたないのは、涼川さんに相談されなかったことだ。彼女は誰にも悩みを打ち明けることなく、不器用な計画を一人で実行した。誰よりも近い場所にいたはずなのに、大事なときに頼りにされなかった自分自身が情けない。
「気づいてあげられなくてごめん」
言えることはそれだけだった。
力になれなくてごめん。
「ううん」涼川さんははっきりと否定する。
「本当はもっといい方法があるはずなのに、もうこれしかないって盲目になってた。誰にも言えずに一人で殻にこもっていたの。一ノ瀬にまで手をだそうとするなんて、本当にどうかしてる。数少ない、私の友人なのに」
「いいんだ。それよりさ、僕にも鶏の件を手伝わせてほしい。今すぐに良い案は出ないけれど、会長にも相談してみるよ」
涼川さんは悲しんでいるとも、喜んでいるともつかない表情で笑った。目が潤んでいるように見えるのは、僕の勘違いだろうか。
「ありがとう。でも一ノ瀬にだけやらせるつもりはないよ。私も一緒に考えさせて。だからさ、仲直りさせてもらえないかな。虫がいいのはわかってるけど、これからも友達でいさせて欲しい」
「仲直りはできないよ」
涼川さんの顔が歪む。彼女のこんな表情は初めてだ。
僕は続けて言う。
「だって僕たち、始めから喧嘩なんてしてないんだからさ」
しばらくすると校舎の方からこちらに向かってくる待ち人の姿が見えてきた。ゆっくりと余裕を感じさせる足取りでやって来る。
「一ノ瀬からサボりの誘いなんて、珍しいね。雪でも降るんじゃない?」
涼川さんはぶっきらぼうに言った。
「やめてよ。雪は嫌いなんだ」
「どうして?」
「特に理由はないけど」
「私は好きだよ。冬眠してしまう動物もいるけど、逆に冬にだけ姿を見せる動物がいて、他の季節とは違った楽しさがある」
涼川さんは目を閉じると薄く笑った。
瞼の裏に動物が見ているのかもしれない。
再び目を開いたとき、涼川さんの表情から笑みは消えていた。気だるそうないつもの彼女に戻っていた。
「それで、ここに呼び出した目的は何なの?」
「あれ? 紗月さんから聞かなかった?」
「紗月って? あの透明人間のこと?」
どうやら紗月さんは何も説明しなかったらしい。自分の名前すらも。自ら伝言役を買って出たくせに、ずさんな仕事ぶりだ。
僕は紗月さんについて簡単に説明する。催眠術を使えること。そして人形遣いを見つけるために学校へ忍び込んでいること。
彼女が泥棒であることと、僕の家に仕事で侵入していることはややこしいので伏せておいた。こればっかりは僕と紗月さんの問題であって、涼川さんには関係のないことだ。
説明を聞いた涼川さんは一言「なるほどね」と言った。
話を疑うこともなく、すんなりと飲み込んでくれる。きっと僕と同じように、彼女の能力を目の当たりしてしまった以上、信じるしかないといった心境なのだろう。
あるいは、自身も特別な力を持っていることで、免疫があるのかもしれない。
「それで」と涼川さんは切り出す。
「一ノ瀬はその友達を紹介するためにここへ来たの?」
「もちろん違うよ。でも、本題に入る前に紗月さんを紹介する必要があったんだ」
「それなら、そろそろ本題に入りましょう」
涼川さんの目はまっすぐに僕を見つめている。その目の奥に寂しさが混じっているように思えた。涼川さんはきっと呼び出された理由に勘付いているのだろう。
「人形遣いの正体は涼川さん、君なんだね」
僕は単刀直入に言った。
彼女から視線をそらさず正面から見つめ合う。
涼川さんに動じている様子はなかった。いつもの落ち着いた表情のままだ。
二人とも黙ったまま時間だけが過ぎる。気まずさはあったが、辛抱して彼女の言葉を待つ。
「一応、そう思った理由を聞いてもいい」
僕はズボンのポケットから、用意していた一枚の写真を取り出した。それは雨森さんの手帳に挟まれていた校庭の写真だった。今朝、雨森さんに頭を下げて拝借したのだ。
写真を涼川さんへ差し出す。
「先日二人でこれを見たのは覚えているよね」
「ええ。覚えてるわ」
「そこに何が写っているか教えてくれる?」
涼川さんは写真に目を落とすと「私たちが今いる校庭の写真でしょ。植えられた桜の木とフェンスの向こうには家がある」と見たものを一つ一つ説明してくれる。
「それから小学生が二人いるわね」
「ほかには?」
僕の問いに涼川さんは首を傾げる。
「ほかには何もいないけど」
「そうだよね。僕も涼川さんが言ってくれた以外のものは見えない。つまり僕と涼川さんには、その写真が同じように見えているんだ」
「当り前じゃない。一ノ瀬は何が言いたいわけ?」
「実は写真には、ほかにも写されているものがあるんだよ」
僕は涼川さんの手から写真を受け取る。そしてその中に写る、自分には見えていないあるものの姿を想像する。
「この写真にはね、猫がいるんだよ」
「猫?」
僕は頷く。写真の中には猫がいる。それは会長と雨森さんと紗月さん、三人から証言を得た情報だ。僕にはそれが見えない。
なぜ三人に見えて、僕には見えないのか。
言うまでもない、紗月さんの催眠術のせいだ。
「僕は募金活動のあった日に、募金箱をこの倉庫へ取りに行った。そのときに倉庫の中で紗月さんに催眠術を掛けてもらったんだ。その催眠術っていうのが、窓の外にいた猫を見えないようにするものだった」
あの日のやり取りを思い出す。
紗月さんの言葉と同時に、窓の外にいた猫が一瞬にして姿を消した。あの瞬間、催眠術によって、僕は三毛猫を認識することができなくなった。だから写真の中にいるはずの猫が僕には見えないのだ。
それでは涼川さんはどうだろう。
どうして僕と同じく、彼女にも猫が認識できないのか。
答えは一つしかない。
涼川さんも僕と同じタイミングで、紗月さんに催眠術に掛けられていたのだ。
「あのとき涼川さんも倉庫の中にいたんだ。僕らより先に倉庫に入っていた涼川さんは、おそらくドアの前で僕と用務員のおじさんが会話しているのを聞いて、物陰に隠れた。そして紗月さんが僕に掛けた催眠術に、君も掛かってしまったんだ」
倉庫で隠れているとき、涼川さんには紗月さんの声は聞こえていなかったはずだ。僕が独り言を言っているように聞こえただろう。
しかし紗月さんは言っていた。認識できなくなっただけで、紗月さんの声は催眠術を掛けられた人にも聞こえるのだと。
涼川さんは気づかないうちに、僕と同じく猫が見えなくなっていたのだ。
涼川さんは無言だった。無駄な口を挟まずに、まずは僕にすべてを話させようとしている。彼女の望み通り話を続ける。
「会長の事件が起きたとき、倉庫は密室になっていた。ドアノブの取り換え作業が行われていて、僕が部屋を出てから事件が終わるまで、誰も室内に入れない状態だった。それなのに僕が倉庫で見たライン引きが犯行に使われていた。密室となっていた倉庫から何者かに持ち出されていたんだ。でも犯人が密室になる前から室内にいたと考えれば、何も不思議なことはない。僕がいなくなった後に、室内から窓を使って外に出ればいいだけの話だ。倉庫の窓は室内からは開閉が可能で、外に出た後に窓を閉めればロックがかかる仕組みになっていた。手の込んだトリックも特殊能力も必要なかったんだ」
僕は間を置くと、もう一度確認の言葉を口にする。
「涼川さんが人形遣いだったんだね」
気づかなかったことにすることもできた。素知らぬ顔でこれまでと同じように付き合い続けることも可能だった。それでも僕は彼女と対峙することを選んだのだ。
涼川さんの顔に柔らかな色が差した。
「うん」どこか晴れやかな表情で涼川さんは首を縦に振った。
「私が人形遣いよ」
喉の奥にツンとした痛みが走る。胸に穴が開いたような気分だ。
間違いであってほしかった、というのが本心だった。
これだけカッコつけておいて「間違ってました」では、晩年まで忘れられない大恥をかくことになった。それでもこんな気持ちを味わうくらいなら、恥をかいた方がずっとよかった。
「なんだか一ノ瀬、名探偵みたいだったよ」
「買いかぶりすぎだよ。だって涼川さんがどうしてこんなことをしたのか、僕にはまるでわからないんだ」
急に強い風が吹いた。
涼川さんは乱れた前髪をかき上げながら、伏し目がちに語りだした。
「生徒会は文化祭の日程を延ばそうとしていたでしょ。それをどうしても食い止めたかったの」
予想外の回答に面食らってしまう。
確かに涼川さんは文化祭を楽しむタイプの人間ではないとは思うが、こんなことをしでかすほど嫌だったというのか。
「そんな理由で?」という言葉が出かけたが、思い直した。涼川さんが利己的な理由でこんなにことを仕出かすはずがない。僕には彼女の本心はわからないけれど、これだけは確信を持って言える。
「中庭の鳥小屋にいる子達ね、ケイスケとケイコっていうの」
急に話が変わった。意味するところがわからないので、黙って次の台詞を待つ。
「文化祭の期間中、中庭は模擬店とかで騒がしいから、あの子たちは用務員室に預けられることになってるの」
「知ってるよ。生徒会で手続きをしたからね」
「一ノ瀬は行ったことないかもしれないけど、用務員室って凄く埃っぽくて、湿度が高いの。人間にはわからないかもしれないけど、あの子たちに取ってはひどい環境なのよ。だから期間中、私が引き取ることを先生に提案してみた。でも学校で飼っている動物を生徒個人に預けることはできないって断られちゃった。だからせめて文化祭の開催日数だけでも短くしてあげたかったの。生徒会役員が不祥事で退任すれば、先生たちと交渉する人はいなくなるでしょ」
涼川さんが弱弱しく微笑んだ。見たことのない表情だった。
「それだけのためにあんな大事を起こしたなんて、一ノ瀬には理解できないでしょ?」
涼川さんが問いかけてくる。
正直に言えば理解できなかった。
彼女が動物を大事にしていることは知っているし、誰に頼まれたわけでもないのに献身的に世話を焼いているのを何度となく目撃したことがある。それでも僕には鶏のためにそこまでする彼女の気持ちがわからなかった。誤解を恐れずに言ってしまえば、たかが動物じゃないかと思ってしまう。
しかし涼川さんにとっては「たかが」ではないのだろう。人に迷惑をかけることを良しとしない彼女が僕らに牙を剥くほどに重要なことなのだ。
その気持ちを否定してはいけないことくらいわかる。理解はできなくても許容したいと思った。方法は間違っているかもしれない。だけどそれを許すことができるのは友達の特権だ。
一方で、僕が悔しくてしかたないのは、涼川さんに相談されなかったことだ。彼女は誰にも悩みを打ち明けることなく、不器用な計画を一人で実行した。誰よりも近い場所にいたはずなのに、大事なときに頼りにされなかった自分自身が情けない。
「気づいてあげられなくてごめん」
言えることはそれだけだった。
力になれなくてごめん。
「ううん」涼川さんははっきりと否定する。
「本当はもっといい方法があるはずなのに、もうこれしかないって盲目になってた。誰にも言えずに一人で殻にこもっていたの。一ノ瀬にまで手をだそうとするなんて、本当にどうかしてる。数少ない、私の友人なのに」
「いいんだ。それよりさ、僕にも鶏の件を手伝わせてほしい。今すぐに良い案は出ないけれど、会長にも相談してみるよ」
涼川さんは悲しんでいるとも、喜んでいるともつかない表情で笑った。目が潤んでいるように見えるのは、僕の勘違いだろうか。
「ありがとう。でも一ノ瀬にだけやらせるつもりはないよ。私も一緒に考えさせて。だからさ、仲直りさせてもらえないかな。虫がいいのはわかってるけど、これからも友達でいさせて欲しい」
「仲直りはできないよ」
涼川さんの顔が歪む。彼女のこんな表情は初めてだ。
僕は続けて言う。
「だって僕たち、始めから喧嘩なんてしてないんだからさ」
0
あなたにおすすめの小説

クラスで1番の美少女のことが好きなのに、なぜかクラスで3番目に可愛い子に絡まれる
グミ食べたい
青春
高校一年生の高居宙は、クラスで一番の美少女・一ノ瀬雫に一目惚れし、片想い中。
彼女と仲良くなりたい一心で高校生活を送っていた……はずだった。
だが、なぜか隣の席の女子、三間坂雪が頻繁に絡んでくる。
容姿は良いが、距離感が近く、からかってくる厄介な存在――のはずだった。
「一ノ瀬さんのこと、好きなんでしょ? 手伝ってあげる」
そう言って始まったのは、恋の応援か、それとも別の何かか。
これは、一ノ瀬雫への恋をきっかけに始まる、
高居宙と三間坂雪の、少し騒がしくて少し甘い学園ラブコメディ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
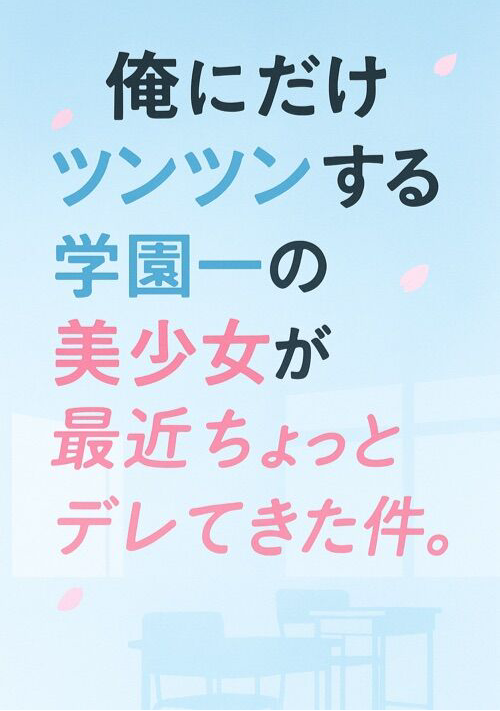
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

黒に染まった華を摘む
馬場 蓮実
青春
夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。
高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。
「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」
そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。
彼女の名は、立石麻美。
昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。
この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。
その日の放課後。
明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。
塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。
そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。
すべてに触れたとき、
明希は何を守り、何を選ぶのか。
光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。

彼女に振られた俺の転生先が高校生だった。それはいいけどなんで元カノ達まで居るんだろう。
遊。
青春
主人公、三澄悠太35才。
彼女にフラれ、現実にうんざりしていた彼は、事故にあって転生。
……した先はまるで俺がこうだったら良かったと思っていた世界を絵に書いたような学生時代。
でも何故か俺をフッた筈の元カノ達も居て!?
もう恋愛したくないリベンジ主人公❌そんな主人公がどこか気になる元カノ、他多数のドタバタラブコメディー!
ちょっとずつちょっとずつの更新になります!(主に土日。)
略称はフラれろう(色とりどりのラブコメに精一杯の呪いを添えて、、笑)

隣の家の幼馴染と転校生が可愛すぎるんだが
akua034
恋愛
隣に住む幼馴染・水瀬美羽。
毎朝、元気いっぱいに晴を起こしに来るのは、もう当たり前の光景だった。
そんな彼女と同じ高校に進学した――はずだったのに。
数ヶ月後、晴のクラスに転校してきたのは、まさかの“全国で人気の高校生アイドル”黒瀬紗耶。
平凡な高校生活を過ごしたいだけの晴の願いとは裏腹に、
幼馴染とアイドル、二人の存在が彼の日常をどんどんかき回していく。
笑って、悩んで、ちょっとドキドキ。
気づけば心を奪われる――
幼馴染 vs 転校生、青春ラブコメの火蓋がいま切られる!

怪我でサッカーを辞めた天才は、高校で熱狂的なファンから勧誘責めに遭う
もぐのすけ
青春
神童と言われた天才サッカー少年は中学時代、日本クラブユースサッカー選手権、高円宮杯においてクラブを二連覇させる大活躍を見せた。
将来はプロ確実と言われていた彼だったが中学3年のクラブユース選手権の予選において、選手生命が絶たれる程の大怪我を負ってしまう。
サッカーが出来なくなることで激しく落ち込む彼だったが、幼馴染の手助けを得て立ち上がり、高校生活という新しい未来に向かって歩き出す。
そんな中、高校で中学時代の高坂修斗を知る人達がここぞとばかりに部活や生徒会へ勧誘し始める。
サッカーを辞めても一部の人からは依然として評価の高い彼と、人気な彼の姿にヤキモキする幼馴染、それを取り巻く友人達との刺激的な高校生活が始まる。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















