35 / 38
『ひとつ、言葉を忘れていた』
しおりを挟む
最初に忘れたのは、ごくありふれた名詞だった。
朝のキッチンで、母親と会話をしているときだった。
トーストを焼きながら、俺はふと、言葉につまった。
「母さん、あれ……あれ、どこ?」
「……あれって?」
「……ほら、あの……お湯、沸かすやつ。金属の。取っ手がついてて」
母親が一瞬眉をひそめた後、笑った。
「ポット? それとも……やかん?」
「あ、それだ。やかん。ごめん」
そう言いながら笑ったが、胸の奥に小さなひっかかりが残った。
“やかん”という言葉を、思い出せなかったこと。
日常の中で、突然、穴に落ちたような感覚。
それは、一時的な記憶の抜けだと思っていた。
よくある、言葉が“喉元まで出かかっている”感覚。
誰だって一度は経験がある。
──でも、俺の場合、それが“戻ってこなかった”。
三日後、学校の廊下で友人と会ったとき。
「昨日のテレビ、見たか?」
「どれ?」
「ほら、あの番組。深夜の……なんていうか、芸人がいろいろやるやつ」
「……バラエティ?」
「あ、そう、それ」
自分で言いながら、冷や汗をかいていた。
“バラエティ”という言葉が、脳内からすっぽり抜け落ちていた。
しかも、“代わりに説明する語彙”すら、どこかぎこちなかった。
そして、また次の日──
こんどは、クラスメイトの名前が思い出せなかった。
その日の昼、教室で。
「なあ、あいつ今日休み?」
「誰?」
「ほら……えっと、前の席の。メガネかけてて……えーと……」
「佐久間?」
「あ、それそれ。佐久間」
──“それ”?
誰かの名前を、“それ”で済ませている自分に気づいた瞬間、背筋が冷たくなった。
言葉が、少しずつ、消えていく。
最初は、思い出しにくいだけだと思った。
でも違った。“覚えていない”のだ。
辞書を引いても、読み返しても、次の瞬間にはもう曖昧になっていた。
脳が、ことばの形をとどめていられない。
やがて、“言葉”が抜けたあとに、黒い染みのような“焦げ跡”が残るようになった。
(そこに“何か”があったはず……)
そう感じても、もはや「それが何だったか」がわからない。
そして、気づいた。
俺の言語中枢が、壊れていっている。
「なあ、お前、最近変じゃない?」
放課後、屋上で友人の宮田に言われた。
「変って、何が?」
「なんていうか……話し方が、曖昧っていうか。主語がないし、目的語も飛ぶし。最近、お前、“それ”ばっか言ってる」
「“それ”……?」
「そう。“それ”とか、“あれ”とか、“これ”。お前、名詞ぜんぶ忘れてないか?」
──そう言われたとき、俺は返せなかった。
自分がどんなふうに話しているのか、もはや正確に把握できていなかった。
“何かを言おう”と思っても、“言葉”がない。
“知っている”のに、“語れない”。
“分かっている”のに、“伝えられない”。
脳内では、たしかに概念が浮かんでいるのに──
それを表す“音”や“形”が、存在しない。
まるで、思考の骨組みが腐り落ちていくような感覚。
その夜、自分のノートを開いた。
驚いた。
日記の中の“単語”が、ほとんど“空欄”になっていたのだ。
《今日、□□□で□□をしていたら、△△が近づいてきて、×××と話した。……たぶん□□□の□□□が原因だと思う》
文字は残っているのに、意味がない。
名詞が、すべて“記号”や“代名詞”になっている。
しかも、それは「自分で書いた字」だった。
俺は──“知らない間に”、言葉を失っていたのだ。
翌朝、鏡の前でつぶやいてみた。
「おれは……□□□です」
自分の名前が、口から出てこなかった。
発声しようとした瞬間、舌が痺れたようになり、言葉にならなかった。
思い出せない。自分の名前を。
“名”を失った感覚は、ただならぬ恐怖だった。
言葉を失っていくのとは違う。
名前がなくなるということは、自分という存在のラベルを剥がされることだった。
俺は──“誰”なんだ?
学校の教科書も、黒板も、街の看板も。
少しずつ、“言葉”が読めなくなっていった。
文字はそこにあるのに、“意味”が届かない。
友人が話しかけても、“音”だけが聞こえて、内容がわからない。
教師が指名しても、自分の“名”を呼ばれている実感がない。
世界が、“無言”になっていく。
でも──自分の中の思考だけは、残っている。
言葉がなくても、考えはある。
感情もある。違和感もある。焦燥もある。
だけど──それを、“伝える術”が、ない。
そして、ある夜。
夢の中で、誰かが囁いた。
『ひとつ忘れた言葉は、“入口”だったんだよ』
──入口?
『最初に失った“やかん”。あれが、“最初の取っ手”だったの』
“取っ手”? 何の?
『ことばの世界の、扉の取っ手さ。君は、そこを開けたんじゃない。“閉じる”のを、忘れたの』
声は、空洞のような音だった。
『だから、君の“中の言葉”は、全部、外にこぼれてるんだよ』
──誰?
『ああ、それももう……忘れたか』
朝。目が覚めると、周囲のすべてが“無音”だった。
言葉が、見えなかった。
聞こえる音はあるのに、“意味”がついてこない。
世界から、言語が消えていた。
──いや、違う。
“俺から”言語が、消えていた。
家族の声が聞こえた。学校のざわめきも。
でも、内容がわからない。
“意味”が脳に届かない。
誰かが、俺を呼ぶ。
だけど、それが“誰か”なのか、もう、わからない。
俺が“誰”なのかも、もう、わからない。
いま、自分で何を書いているかも、わからない。
この文章は、“誰か”に届いているんだろうか。
もしかして、これは“読んでいる君”の話かもしれない。
君が今この文字を目で追っているとき──
すでに君の中の“あることば”が、消えはじめているかもしれない。
忘れていないか?
ほんの些細な、ひとつの言葉を──
──たとえば、君の“名前”を。
朝のキッチンで、母親と会話をしているときだった。
トーストを焼きながら、俺はふと、言葉につまった。
「母さん、あれ……あれ、どこ?」
「……あれって?」
「……ほら、あの……お湯、沸かすやつ。金属の。取っ手がついてて」
母親が一瞬眉をひそめた後、笑った。
「ポット? それとも……やかん?」
「あ、それだ。やかん。ごめん」
そう言いながら笑ったが、胸の奥に小さなひっかかりが残った。
“やかん”という言葉を、思い出せなかったこと。
日常の中で、突然、穴に落ちたような感覚。
それは、一時的な記憶の抜けだと思っていた。
よくある、言葉が“喉元まで出かかっている”感覚。
誰だって一度は経験がある。
──でも、俺の場合、それが“戻ってこなかった”。
三日後、学校の廊下で友人と会ったとき。
「昨日のテレビ、見たか?」
「どれ?」
「ほら、あの番組。深夜の……なんていうか、芸人がいろいろやるやつ」
「……バラエティ?」
「あ、そう、それ」
自分で言いながら、冷や汗をかいていた。
“バラエティ”という言葉が、脳内からすっぽり抜け落ちていた。
しかも、“代わりに説明する語彙”すら、どこかぎこちなかった。
そして、また次の日──
こんどは、クラスメイトの名前が思い出せなかった。
その日の昼、教室で。
「なあ、あいつ今日休み?」
「誰?」
「ほら……えっと、前の席の。メガネかけてて……えーと……」
「佐久間?」
「あ、それそれ。佐久間」
──“それ”?
誰かの名前を、“それ”で済ませている自分に気づいた瞬間、背筋が冷たくなった。
言葉が、少しずつ、消えていく。
最初は、思い出しにくいだけだと思った。
でも違った。“覚えていない”のだ。
辞書を引いても、読み返しても、次の瞬間にはもう曖昧になっていた。
脳が、ことばの形をとどめていられない。
やがて、“言葉”が抜けたあとに、黒い染みのような“焦げ跡”が残るようになった。
(そこに“何か”があったはず……)
そう感じても、もはや「それが何だったか」がわからない。
そして、気づいた。
俺の言語中枢が、壊れていっている。
「なあ、お前、最近変じゃない?」
放課後、屋上で友人の宮田に言われた。
「変って、何が?」
「なんていうか……話し方が、曖昧っていうか。主語がないし、目的語も飛ぶし。最近、お前、“それ”ばっか言ってる」
「“それ”……?」
「そう。“それ”とか、“あれ”とか、“これ”。お前、名詞ぜんぶ忘れてないか?」
──そう言われたとき、俺は返せなかった。
自分がどんなふうに話しているのか、もはや正確に把握できていなかった。
“何かを言おう”と思っても、“言葉”がない。
“知っている”のに、“語れない”。
“分かっている”のに、“伝えられない”。
脳内では、たしかに概念が浮かんでいるのに──
それを表す“音”や“形”が、存在しない。
まるで、思考の骨組みが腐り落ちていくような感覚。
その夜、自分のノートを開いた。
驚いた。
日記の中の“単語”が、ほとんど“空欄”になっていたのだ。
《今日、□□□で□□をしていたら、△△が近づいてきて、×××と話した。……たぶん□□□の□□□が原因だと思う》
文字は残っているのに、意味がない。
名詞が、すべて“記号”や“代名詞”になっている。
しかも、それは「自分で書いた字」だった。
俺は──“知らない間に”、言葉を失っていたのだ。
翌朝、鏡の前でつぶやいてみた。
「おれは……□□□です」
自分の名前が、口から出てこなかった。
発声しようとした瞬間、舌が痺れたようになり、言葉にならなかった。
思い出せない。自分の名前を。
“名”を失った感覚は、ただならぬ恐怖だった。
言葉を失っていくのとは違う。
名前がなくなるということは、自分という存在のラベルを剥がされることだった。
俺は──“誰”なんだ?
学校の教科書も、黒板も、街の看板も。
少しずつ、“言葉”が読めなくなっていった。
文字はそこにあるのに、“意味”が届かない。
友人が話しかけても、“音”だけが聞こえて、内容がわからない。
教師が指名しても、自分の“名”を呼ばれている実感がない。
世界が、“無言”になっていく。
でも──自分の中の思考だけは、残っている。
言葉がなくても、考えはある。
感情もある。違和感もある。焦燥もある。
だけど──それを、“伝える術”が、ない。
そして、ある夜。
夢の中で、誰かが囁いた。
『ひとつ忘れた言葉は、“入口”だったんだよ』
──入口?
『最初に失った“やかん”。あれが、“最初の取っ手”だったの』
“取っ手”? 何の?
『ことばの世界の、扉の取っ手さ。君は、そこを開けたんじゃない。“閉じる”のを、忘れたの』
声は、空洞のような音だった。
『だから、君の“中の言葉”は、全部、外にこぼれてるんだよ』
──誰?
『ああ、それももう……忘れたか』
朝。目が覚めると、周囲のすべてが“無音”だった。
言葉が、見えなかった。
聞こえる音はあるのに、“意味”がついてこない。
世界から、言語が消えていた。
──いや、違う。
“俺から”言語が、消えていた。
家族の声が聞こえた。学校のざわめきも。
でも、内容がわからない。
“意味”が脳に届かない。
誰かが、俺を呼ぶ。
だけど、それが“誰か”なのか、もう、わからない。
俺が“誰”なのかも、もう、わからない。
いま、自分で何を書いているかも、わからない。
この文章は、“誰か”に届いているんだろうか。
もしかして、これは“読んでいる君”の話かもしれない。
君が今この文字を目で追っているとき──
すでに君の中の“あることば”が、消えはじめているかもしれない。
忘れていないか?
ほんの些細な、ひとつの言葉を──
──たとえば、君の“名前”を。
0
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

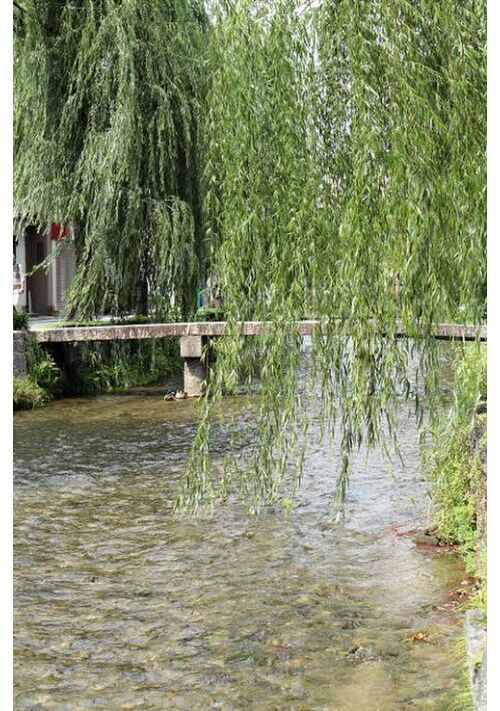

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】
絢郷水沙
ホラー
普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。
下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。
※全話オリジナル作品です。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【1分読書】意味が分かると怖いおとぎばなし
響ぴあの
ホラー
【1分読書】
意味が分かるとこわいおとぎ話。
意外な事実や知らなかった裏話。
浦島太郎は神になった。桃太郎の闇。本当に怖いかちかち山。かぐや姫は宇宙人。白雪姫の王子の誤算。舌切りすずめは三角関係の話。早く人間になりたい人魚姫。本当は怖い眠り姫、シンデレラ、さるかに合戦、はなさかじいさん、犬の呪いなどなど面白い雑学と創作短編をお楽しみください。
どこから読んでも大丈夫です。1話完結ショートショート。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















