9 / 109
第一章
第9話 ケチャップ
しおりを挟む
俺、いや私、ロボットメイドのアール。 今は魔法学院の入学試験を受けている。
俺のミスでとんでもないことになってしまった。事前に試験内容について調べるべきだったのだ。
そうすればこんな実技試験で勇者ばれのピンチになることなどなかった。
しかも、俺が余計なことを試験官に言ってしまったので、皆の注目を集めてしまった。 近くにいたツインドリルなんてとても興味津々である。
まずい、このプレッシャーは、額から汗がにじむ。 汗だと、ロボットである俺に汗など出るものかと思ったが。そうだった。そういう機能があった。
このメイドロボット三号機は高負荷の情報処理をする場合、発熱から守るために冷却水がでるしくみになっている。
二号機の爆発事故の教訓からそうしたのだが。プレッシャーでもそうなるのか、ふ、丁度いい、本当に汗をかいてるみたいじゃないか。これならロボットばれしなくて済みそうだ。
だから皆さん俺を見るな。どんどん汗がでるじゃないか。こんなに注目されるなんて。勇者時代でもなかった。
いやあったのだが。あれは勇者として堂々としていたからそんなにプレッシャーではなかった。それでも緊張していたが。
それに比べて今回の注目具合はなんだ、みんな興味津々というか奇妙な生き物をみるような目じゃないか。まずい、何とかしないと
俺は覚悟を決める。標的の魔導人形をにらみながら、おや5000年前から比べると随分と進歩してるな、割と人間味が出ているようだ。
前に見たときは、ただのカカシですな、と魔導人形の造形を馬鹿にしたものだった。まあデコイでしかないからな。
それにここは魔法学院だからか。使用する魔道具も軍用というよりはデザイン性も気を使われているといったところだろうか。
俺はこの魔導人形に向かって出来るだけ最弱に、そう最弱に、やってしまわないように。勇者ばれしませんようにと何度も集中する。
周りからみたら思いっきり集中しているため、さぞ巨大な魔法がでるのだろうと思っているかもしれない。残念だったなまったく逆だ。
だが、いい加減俺を見るのをやめてくれ。汗が止まらないじゃないか。そうして、できるだけ最弱に放った無詠唱魔法は小さな氷のダーツを射出する。
標的の真ん中に突き刺さった。
ふう、やりきった、俺はプレッシャーから解放されたのか地べたにひざまずいてしまった。
「アール嬢、大丈夫かね。
今のは確かに無詠唱魔法だった。……だがそうだね、それだけ消耗してしまうのは無理もないよ。
我が学院でも無詠唱魔法を使えるのは一握りの人間だけなのだから。
だが落ち込むことはない、君にはちゃんと才能がある。それを育てるのが我々の使命なのだから」
よし、なんとかなった。天才現るは回避できたようだ。
周りも関心が薄れたのか、それぞれ自分のやるべきことに戻っていった。
「ほら、あなた汗びっしょりよ、これを使いなさいな」
ツインドリルさんも俺にハンカチを差し出している。よし悪役令嬢に嫉妬されるフラグを回避できただろう。
まあ、彼女が悪役だとは言い切れない。ツインドリルだからといってそう思うのは偏見が過ぎるというものだ。
彼女とは友達になれるといいなと思ったのだった。
こうして無事、入学試験は終わった。まあ合格間違いないだろう。
俺は意気揚々と宿へと帰った。ツインドリルさんとはお互いに自己紹介をした。いつまでもツインドリルと呼ぶのは失礼だろう。
彼女はシルビアと名乗った。可愛い名前じゃないか。
俺が一人でこの町にいると言ったら。今度お買い物でもしましょうというながれになった。ぐいぐいこられても戸惑ってしまうが。
これも試練だ。いつまでも陰キャではいられない。それにシルビアさんは貴族の出身だと言っていたので俺の目的とも合致している。
まあ、最初からそういう目的で彼女と接したくはない。純粋に友達ができるのはいいことだと思うだけで今は充分なのだ。
宿に帰ると大宴会、は流石になかった。ここは高級宿である。どちらかと言えばホテルに近い。一階が酒場などという訳ではないのでそういう展開は回避できた。
ああいうのはコミュ障の俺では無理だ。そう俺はもう自覚した。自分はかなりのコミュ障だということに。
とりあえずカウンターに向かい。今朝のお弁当のお礼をして。試験は問題なく終わったと言うと。わがことのように喜んでくれたのでこちらも嬉しくなった。
いつのまにやらチェックインの時にいた支配人さんと、女将さんポジションの女性も顔を出してきた。俺の試験の話が伝わったのかみんな歓声をあげていた。
やはりここはアットホームな宿なのかとおもったが悪い気はしない。俺は自然と頬が緩んだ。
笑顔がとても素敵だと言われ、ドキッとしたが、男の俺にそんなことを言うもんじゃないと思いながら挨拶を済ませ部屋へと向かった。
「さてとロボさんや。とりあえず入学試験は問題なく終わった。問題なく終わったんだ、いいね?」
(はあ、マスターがそうおっしゃるならそうなのでしょう。ですが一つ問題があります)
「む、なんかやらかしたか? 心当たりがありすぎてどれのことやら」
(ご自覚があったのですか、少し安心しました。で、それは今回は置いときまして。とても重大なことです)
「な、なんだ。そんなやらかし俺はしたか? うまくいっただろう」
(いいえ、食事の仕方が汚すぎです。お弁当のサンドイッチの食べ方が汚すぎです。口からはみ出してボロボロとこぼしていましたよ)
「む? そのことか、それはしょうがない。君の口が小さすぎるのだ。生前の俺の口のサイズとの違いであって決してマナーがなってないわけではない」
(それでも、はぁ……口の周りにケチャップをつけているのは流石に引きます。なんども注意したではありませんか、入学前に直しておいてくださいね)
「む、むう、そうだな、今度シルビアさんと買い物をする約束をしたし、気を付けるとしよう」
(そうですよ、まあ逆に子供っぽいところを見せつけて敵意がないことをアピールするならありかもしれませんが)
「ぬ、さすがにそれは恥ずかしすぎる。そんなことにはならないよ、安心するがいい」
そうして、反省会はテーブルマナーの復習に始まり、やがてお弁当の味についての評価に変わり一日は過ぎた。ちなみにお弁当の評価は95点だった。食べにくいの理由でマイナス5点だ。
俺のミスでとんでもないことになってしまった。事前に試験内容について調べるべきだったのだ。
そうすればこんな実技試験で勇者ばれのピンチになることなどなかった。
しかも、俺が余計なことを試験官に言ってしまったので、皆の注目を集めてしまった。 近くにいたツインドリルなんてとても興味津々である。
まずい、このプレッシャーは、額から汗がにじむ。 汗だと、ロボットである俺に汗など出るものかと思ったが。そうだった。そういう機能があった。
このメイドロボット三号機は高負荷の情報処理をする場合、発熱から守るために冷却水がでるしくみになっている。
二号機の爆発事故の教訓からそうしたのだが。プレッシャーでもそうなるのか、ふ、丁度いい、本当に汗をかいてるみたいじゃないか。これならロボットばれしなくて済みそうだ。
だから皆さん俺を見るな。どんどん汗がでるじゃないか。こんなに注目されるなんて。勇者時代でもなかった。
いやあったのだが。あれは勇者として堂々としていたからそんなにプレッシャーではなかった。それでも緊張していたが。
それに比べて今回の注目具合はなんだ、みんな興味津々というか奇妙な生き物をみるような目じゃないか。まずい、何とかしないと
俺は覚悟を決める。標的の魔導人形をにらみながら、おや5000年前から比べると随分と進歩してるな、割と人間味が出ているようだ。
前に見たときは、ただのカカシですな、と魔導人形の造形を馬鹿にしたものだった。まあデコイでしかないからな。
それにここは魔法学院だからか。使用する魔道具も軍用というよりはデザイン性も気を使われているといったところだろうか。
俺はこの魔導人形に向かって出来るだけ最弱に、そう最弱に、やってしまわないように。勇者ばれしませんようにと何度も集中する。
周りからみたら思いっきり集中しているため、さぞ巨大な魔法がでるのだろうと思っているかもしれない。残念だったなまったく逆だ。
だが、いい加減俺を見るのをやめてくれ。汗が止まらないじゃないか。そうして、できるだけ最弱に放った無詠唱魔法は小さな氷のダーツを射出する。
標的の真ん中に突き刺さった。
ふう、やりきった、俺はプレッシャーから解放されたのか地べたにひざまずいてしまった。
「アール嬢、大丈夫かね。
今のは確かに無詠唱魔法だった。……だがそうだね、それだけ消耗してしまうのは無理もないよ。
我が学院でも無詠唱魔法を使えるのは一握りの人間だけなのだから。
だが落ち込むことはない、君にはちゃんと才能がある。それを育てるのが我々の使命なのだから」
よし、なんとかなった。天才現るは回避できたようだ。
周りも関心が薄れたのか、それぞれ自分のやるべきことに戻っていった。
「ほら、あなた汗びっしょりよ、これを使いなさいな」
ツインドリルさんも俺にハンカチを差し出している。よし悪役令嬢に嫉妬されるフラグを回避できただろう。
まあ、彼女が悪役だとは言い切れない。ツインドリルだからといってそう思うのは偏見が過ぎるというものだ。
彼女とは友達になれるといいなと思ったのだった。
こうして無事、入学試験は終わった。まあ合格間違いないだろう。
俺は意気揚々と宿へと帰った。ツインドリルさんとはお互いに自己紹介をした。いつまでもツインドリルと呼ぶのは失礼だろう。
彼女はシルビアと名乗った。可愛い名前じゃないか。
俺が一人でこの町にいると言ったら。今度お買い物でもしましょうというながれになった。ぐいぐいこられても戸惑ってしまうが。
これも試練だ。いつまでも陰キャではいられない。それにシルビアさんは貴族の出身だと言っていたので俺の目的とも合致している。
まあ、最初からそういう目的で彼女と接したくはない。純粋に友達ができるのはいいことだと思うだけで今は充分なのだ。
宿に帰ると大宴会、は流石になかった。ここは高級宿である。どちらかと言えばホテルに近い。一階が酒場などという訳ではないのでそういう展開は回避できた。
ああいうのはコミュ障の俺では無理だ。そう俺はもう自覚した。自分はかなりのコミュ障だということに。
とりあえずカウンターに向かい。今朝のお弁当のお礼をして。試験は問題なく終わったと言うと。わがことのように喜んでくれたのでこちらも嬉しくなった。
いつのまにやらチェックインの時にいた支配人さんと、女将さんポジションの女性も顔を出してきた。俺の試験の話が伝わったのかみんな歓声をあげていた。
やはりここはアットホームな宿なのかとおもったが悪い気はしない。俺は自然と頬が緩んだ。
笑顔がとても素敵だと言われ、ドキッとしたが、男の俺にそんなことを言うもんじゃないと思いながら挨拶を済ませ部屋へと向かった。
「さてとロボさんや。とりあえず入学試験は問題なく終わった。問題なく終わったんだ、いいね?」
(はあ、マスターがそうおっしゃるならそうなのでしょう。ですが一つ問題があります)
「む、なんかやらかしたか? 心当たりがありすぎてどれのことやら」
(ご自覚があったのですか、少し安心しました。で、それは今回は置いときまして。とても重大なことです)
「な、なんだ。そんなやらかし俺はしたか? うまくいっただろう」
(いいえ、食事の仕方が汚すぎです。お弁当のサンドイッチの食べ方が汚すぎです。口からはみ出してボロボロとこぼしていましたよ)
「む? そのことか、それはしょうがない。君の口が小さすぎるのだ。生前の俺の口のサイズとの違いであって決してマナーがなってないわけではない」
(それでも、はぁ……口の周りにケチャップをつけているのは流石に引きます。なんども注意したではありませんか、入学前に直しておいてくださいね)
「む、むう、そうだな、今度シルビアさんと買い物をする約束をしたし、気を付けるとしよう」
(そうですよ、まあ逆に子供っぽいところを見せつけて敵意がないことをアピールするならありかもしれませんが)
「ぬ、さすがにそれは恥ずかしすぎる。そんなことにはならないよ、安心するがいい」
そうして、反省会はテーブルマナーの復習に始まり、やがてお弁当の味についての評価に変わり一日は過ぎた。ちなみにお弁当の評価は95点だった。食べにくいの理由でマイナス5点だ。
1
あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。
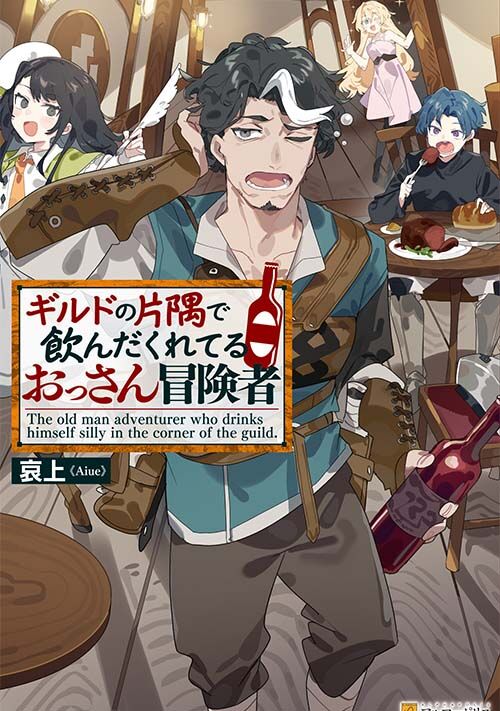
ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者
哀上
ファンタジー
チートを貰い転生した。
何も成し遂げることなく35年……
ついに前世の年齢を超えた。
※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。
※この小説は他サイトにも投稿しています。

悪役顔のモブに転生しました。特に影響が無いようなので好きに生きます
竹桜
ファンタジー
ある部屋の中で男が画面に向かいながら、ゲームをしていた。
そのゲームは主人公の勇者が魔王を倒し、ヒロインと結ばれるというものだ。
そして、ヒロインは4人いる。
ヒロイン達は聖女、剣士、武闘家、魔法使いだ。
エンドのルートしては六種類ある。
バットエンドを抜かすと、ハッピーエンドが五種類あり、ハッピーエンドの四種類、ヒロインの中の誰か1人と結ばれる。
残りのハッピーエンドはハーレムエンドである。
大好きなゲームの十回目のエンディングを迎えた主人公はお腹が空いたので、ご飯を食べようと思い、台所に行こうとして、足を滑らせ、頭を強く打ってしまった。
そして、主人公は不幸にも死んでしまった。
次に、主人公が目覚めると大好きなゲームの中に転生していた。
だが、主人公はゲームの中で名前しか出てこない悪役顔のモブに転生してしまった。
主人公は大好きなゲームの中に転生したことを心の底から喜んだ。
そして、折角転生したから、この世界を好きに生きようと考えた。

少し冷めた村人少年の冒険記
mizuno sei
ファンタジー
辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。
トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。
優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。


勇者パーティーにダンジョンで生贄にされました。これで上位神から押し付けられた、勇者の育成支援から解放される。
克全
ファンタジー
エドゥアルには大嫌いな役目、神与スキル『勇者の育成者』があった。力だけあって知能が低い下級神が、勇者にふさわしくない者に『勇者』スキルを与えてしまったせいで、上級神から与えられてしまったのだ。前世の知識と、それを利用して鍛えた絶大な魔力のあるエドゥアルだったが、神与スキル『勇者の育成者』には逆らえず、嫌々勇者を教育していた。だが、勇者ガブリエルは上級神の想像を絶する愚者だった。事もあろうに、エドゥアルを含む300人もの人間を生贄にして、ダンジョンの階層主を斃そうとした。流石にこのような下劣な行いをしては『勇者』スキルは消滅してしまう。対象となった勇者がいなくなれば『勇者の育成者』スキルも消滅する。自由を手に入れたエドゥアルは好き勝手に生きることにしたのだった。

ガチャと異世界転生 システムの欠陥を偶然発見し成り上がる!
よっしぃ
ファンタジー
偶然神のガチャシステムに欠陥がある事を発見したノーマルアイテムハンター(最底辺の冒険者)ランナル・エクヴァル・元日本人の転生者。
獲得したノーマルアイテムの売却時に、偶然発見したシステムの欠陥でとんでもない事になり、神に報告をするも再現できず否定され、しかも神が公認でそんな事が本当にあれば不正扱いしないからドンドンしていいと言われ、不正もとい欠陥を利用し最高ランクの装備を取得し成り上がり、無双するお話。
俺は西塔 徳仁(さいとう のりひと)、もうすぐ50過ぎのおっさんだ。
単身赴任で家族と離れ遠くで暮らしている。遠すぎて年に数回しか帰省できない。
ぶっちゃけ時間があるからと、ブラウザゲームをやっていたりする。
大抵ガチャがあるんだよな。
幾つかのゲームをしていたら、そのうちの一つのゲームで何やらハズレガチャを上位のアイテムにアップグレードしてくれるイベントがあって、それぞれ1から5までのランクがあり、それを15本投入すれば一度だけ例えばSRだったらSSRのアイテムに変えてくれるという有り難いイベントがあったっけ。
だが俺は運がなかった。
ゲームの話ではないぞ?
現実で、だ。
疲れて帰ってきた俺は体調が悪く、何とか自身が住んでいる社宅に到着したのだが・・・・俺は倒れたらしい。
そのまま救急搬送されたが、恐らく脳梗塞。
そのまま帰らぬ人となったようだ。
で、気が付けば俺は全く知らない場所にいた。
どうやら異世界だ。
魔物が闊歩する世界。魔法がある世界らしく、15歳になれば男は皆武器を手に魔物と祟罠くてはならないらしい。
しかも戦うにあたり、武器や防具は何故かガチャで手に入れるようだ。なんじゃそりゃ。
10歳の頃から生まれ育った村で魔物と戦う術や解体方法を身に着けたが、15になると村を出て、大きな街に向かった。
そこでダンジョンを知り、同じような境遇の面々とチームを組んでダンジョンで活動する。
5年、底辺から抜け出せないまま過ごしてしまった。
残念ながら日本の知識は持ち合わせていたが役に立たなかった。
そんなある日、変化がやってきた。
疲れていた俺は普段しない事をしてしまったのだ。
その結果、俺は信じられない出来事に遭遇、その後神との恐ろしい交渉を行い、最底辺の生活から脱出し、成り上がってく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















