あなたにおすすめの小説

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い
青の雀
恋愛
夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。
神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。
もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。
生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。
過去世と同じ轍を踏みたくない……


処刑台の皇妃、回帰して復讐を誓う ~冷酷公爵と偽りの婚約者~ おまえたちは許さない!
秦江湖
ファンタジー
皇妃エリアーナは、夫である皇帝アランと、たった一人の親友イザベラの策略により、無実の罪で処刑される。
民衆に罵られ、アランの冷酷な目とイザベラの嘲笑を「始まりの景色」として目に焼き付けながら絶命した彼女は、しかし、処刑の記憶を持ったまま三年前の過去に回帰する。
「おまえたちは許さない」
二度目の人生。
エリアーナの目的はただ一つ、自分を陥れた二人への完璧な復讐。
彼女はまず、アラン(皇太子)からの婚約内示を拒絶。そして、アラン最大の政敵である「北の冷血公爵」ルシアン・ヴァレリウスに接触する。
1周目で得た「未来の知識」を対価に、エリアーナはルシアンに持ちかける。
「貴方様には帝国の覇権を。わたくしには復讐の舞台を。そのための『契約婚約』を――」
憎悪を糧に生きる皇妃と、氷の瞳を持つ公爵。
二人の偽りの婚約の行く末は……

【大賞・完結】地味スキル《お片付け》は最強です!社畜OL、異世界でうっかり国を改革しちゃったら、騎士団長と皇帝陛下に溺愛されてるんですが!?
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
【第18回ファンタジー小説大賞で大賞をいただきました】→【規約変更で書籍化&コミカライズ「確約」は取り消しになりました。】
佐藤美佳子(サトウ・ミカコ)、享年28歳。死因は、過労。連日の徹夜と休日出勤の果てに、ブラック企業のオフィスで静かに息を引き取った彼女が次に目覚めたのは、剣と魔法のファンタジー世界だった。
新たな生を受けたのは、田舎のしがない貧乏貴族の娘、ミカ・アシュフィールド、16歳。神様がくれた転生特典は、なんと《完璧なる整理整頓》という、とんでもなく地味なスキルだった。
「せめて回復魔法とかが良かった……」
戦闘にも生産にも役立たないスキルに落胆し、今度こそは静かに、穏やかに生きたいと願うミカ。しかし、そんな彼女のささやかな望みは、王家からの突然の徴収命令によって打ち砕かれる。
「特殊技能持ちは、王宮へ出仕せよ」
家族を守るため、どうせ役立たずと追い返されるだろうと高をくくって王都へ向かったミカに与えられた任務は、あまりにも無謀なものだった。
「この『開かずの倉庫』を、整理せよ」
そこは、数百年分の備品や資材が山と積まれ、あまりの混沌ぶりに探検隊が遭難したとまで噂される、王家最大の禁足地。
絶望的な光景を前に、ミカが覚悟を決めてスキルを発動した瞬間――世界は、彼女の「お片付け」が持つ真の力に震撼することになる。
これは、地味スキルでうっかり国のすべてを最適化してしまった元社畜令嬢が、カタブツな騎士団長や有能すぎる皇帝陛下にその価値を見出され、なぜか過保護に甘やかされてしまう、お仕事改革ファンタジー。

つまらない妃と呼ばれた日
柴田はつみ
恋愛
公爵令嬢リーシャは政略結婚で王妃に迎えられる。だが国王レオニスの隣には、幼馴染のセレスが“当然”のように立っていた。祝宴の夜、リーシャは国王が「つまらない妃だ」と語る声を聞いてしまい、心を閉ざす。
舞踏会で差し出された手を取らず、王弟アドリアンの助けで踊ったことで、噂は一気に燃え上がる――「王妃は王弟と」「国王の本命は幼馴染」と。
さらに宰相は儀礼と世論を操り、王妃を孤立させる策略を進める。監視の影、届かない贈り物、すり替えられた言葉、そして“白薔薇の香”が事件現場に残る冤罪の罠。
リーシャは微笑を鎧に「今日から、王の隣に立たない」と決めるが、距離を取るほど誤解は確定し、王宮は二人を引き裂いていく。
――つまらない妃とは、いったい誰が作ったのか。真実が露わになった時、失われた“隣”は戻るのか。

初夜に暴言を吐いた夫は後悔し続ける──10年後の償い【完結】
星森 永羽(ほしもりとわ)
恋愛
王命により、辺境伯ロキアのもとへ嫁いだのは、金髪翠眼の美しき公爵令嬢スフィア。
だが、初夜に彼が告げたのは、愛も権限も与えないという冷酷な宣言だった。噂に踊らされ、彼女を「穢れた花嫁」と罵ったロキア。
しかし、わずか一日でスフィアは姿を消し、教会から届いたのは婚姻無効と慰謝料請求の書状──。
王と公爵の怒りを買ったロキアは、爵位も領地も名誉も奪われ、ただの補佐官として生きることに。
そして十年後、運命のいたずらか、彼は被災地で再びスフィアと出会う。
地位も捨て、娘を抱えて生きる彼女の姿に、ロキアの胸に去来するのは、悔恨と赦しを乞う想い──。
⚠️本作はAIの生成した文章を一部に使用しています。

追放された養女令嬢は、聖騎士団長の腕の中で真実の愛を知る。~元婚約者が自滅する横で、私は最高に幸せになります~
有賀冬馬
恋愛
「お前のような無能な女、私の格が下がるのだよ」
最愛の婚約者だったはずの王子に罵られ、雨の夜に放り出されたエルナ。
すべてを失った彼女が救われたのは、国の英雄である聖騎士団長・レオナードの手によってだった。
虚飾の社交界では見えなかった、本当の価値。
泥にまみれて子供たちを笑顔にするエルナの姿に、レオナードは心を奪われていく。
「君の隣に、私以外の居場所は作らせない」
そんな二人の裏側で、エルナを捨てた王子は破滅へのカウントダウンを始めていた。
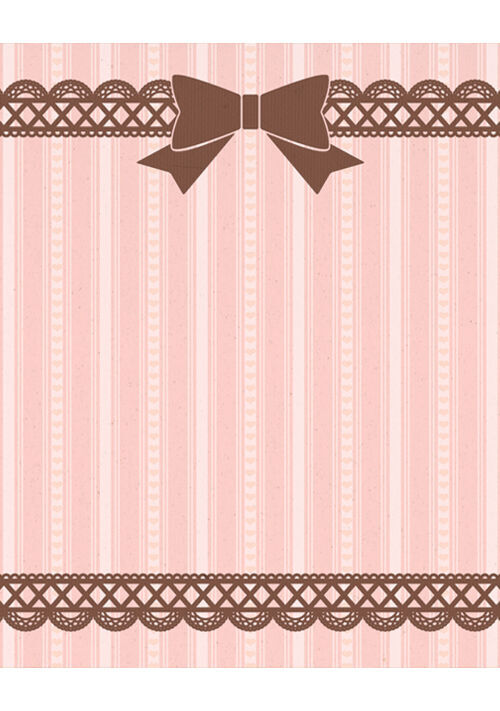
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















