26 / 29
閑話 リュークの選択
しおりを挟む
三人称視点
第五王子リュークは末っ子の王子として、皆の愛情を一身に受け、生きてきた。
ただ、愛を享受するのみで彼は生きてきたというより、生かされてきたと言えよう。
その最たる証拠がデ・ブライネ辺境伯家令嬢ヴィルヘルミナとの婚約だった。
この婚約はリュークにとってはなくてはならないものであり、ヴィルヘルミナにとっては禍であり、呪いに等しいものである。
それというのもヴィルヘルミナが有する稀有な聖女の力ゆえだった。
彼女の力は癒しである。
癒しの力自体はそれほど、珍しいものでもない。
治癒の魔法である程度の病や怪我は治療が可能だからだ。
だが、治癒の魔法にも限界はある。
失われた命を元に戻すことは出来ないし、欠損した部位を回復することも出来ない。
命に係わるほどの重症や重病も余程、腕利きのヒーラーでもない限りは治せないのだ。
ヴィルヘルミナは物心のつかない幼い頃より、この癒しを正式に学ぶことなく、直感のみで使うことが出来た。
それも無制限で使えたのだ。
父親に連れられて、王城に登城したヴィルヘルミナはそこで金髪の愛らしい男の子と出会った。
それが第五王子であるリュークだったのが、彼女の進む道を大きく変えることになる。
「何をしているの?」
「か、か、かあしゃまに……ふれせんとあげりゅの」
ヴィルヘルミナより年長であるにも関わらず、リュークの言語は明瞭ではなく、その視線もどこか、定まっていない不安定なものだった。
しかし、彼女はこう思った。
何て、きれいな目をして、無垢な子なのだろうと……。
だから、願ってしまったのだ。
『どうか、彼に幸あらんことを』と。
その時、眩いばかりの白銀の光が放たれ、奇跡が起きたのだと言う。
かくして、ヴィルヘルミナが王家に囚われる理由が出来てしまったのだが、彼女の聖女の力に代償が必要であることを知る者は少ない。
ヴィルヘルミナは確かに病や傷を癒すことが出来た。
出産時の事故で生まれながらにして、患っていたリュークの病をも治せた者はこれまで誰一人いなかった。
それを成し遂げたヴィルヘルミナはまさに不世出の才能を持った聖女と言うべきだが、その代償はあまりにも大きい。
彼女の癒しは交換の原理に近い。
傷や病をヴィルヘルミナが自らの体に取り込んでから、治癒させるものだ。
それゆえ、重症の患者を治療する際には彼女自身が激痛を体験しなければ、ならないのだ。
しかし、ヴィルヘルミナはそれを苦と思わない無垢な魂を持つ真の聖女だった。
だからこそ、命を失いかねない瀕死のブランカを助け、自らが三日間、生死の境を彷徨うことになろうとも後悔しなかったのだ。
だが、ここで気を付けなくてはならないのがそれが完治する病や傷だったという点である。
リュークの病は完治しない。
ヴィルヘルミナの傍にいて、彼女が無意識に力を使うことでどうにか、状態が改善していただけに過ぎないのだ。
リュークの不幸はそのことを知らないまま、生きてきたことだと言えよう。
全てを知ったのは全てを失った時だったというのが皮肉である。
これまで聞いていない、知らないで済まされていたことはもう許されない。
「ごめん……ミナ……ごめん……」
頬がこけ、落ち窪んだ眼窩。
その顔にかつて讃えられた美しき容貌は微塵も感じられない。
ただ、止めどもなく流れ落ちる涙を湛える青い瞳はどこまでも澄んでいて、純真な物だった。
婚約者だった王子がやつれ果てた姿になりながらもようやく、己を取り戻したのだと知って、ヴィルヘルミナも目頭を押さえる。
リュークは良くも悪くも純粋だったとヴィルヘルミナは逡巡していた。
「聞いていなかったよ」「知らなかったんだ」が口癖でとても王子とは思えない振る舞いをするリュークだったが、人を傷つけない優しさを持つ人であった、と。
そんな彼があんな下劣な行為に走ったのはなぜだったのか?
自分に至らぬ点があったからだろうか?
ヴィルヘルミナは考えに耽るあまり、複雑な表情をしていたことに気付かない。
「私は……君に……返す」
「え?」
リュークがようやく吐き出した言葉にヴィルヘルミナが気が付いた時には、リュークは既に意識を失っており、安らかな寝息を立てていた。
その顔からは険しさがなくなっており、何も知らない幼子のように無垢なものに見える。
「お疲れ様でした、リューク殿下。どうか、お体を大切に……」
かつての婚約者を一瞥したヴィルヘルミナの菫色の瞳に宿るのは憐憫といくらかの愛惜の色だった。
退室していく彼女の目にもう迷いはない。
後の世に書かれた史書にこれ以降、第五王子リュークの名が出てくることはなかった。
ただ、デ・ブライネ辺境伯領で余生を過ごした一人の貴人がいたと記されるのみである。
第五王子リュークは末っ子の王子として、皆の愛情を一身に受け、生きてきた。
ただ、愛を享受するのみで彼は生きてきたというより、生かされてきたと言えよう。
その最たる証拠がデ・ブライネ辺境伯家令嬢ヴィルヘルミナとの婚約だった。
この婚約はリュークにとってはなくてはならないものであり、ヴィルヘルミナにとっては禍であり、呪いに等しいものである。
それというのもヴィルヘルミナが有する稀有な聖女の力ゆえだった。
彼女の力は癒しである。
癒しの力自体はそれほど、珍しいものでもない。
治癒の魔法である程度の病や怪我は治療が可能だからだ。
だが、治癒の魔法にも限界はある。
失われた命を元に戻すことは出来ないし、欠損した部位を回復することも出来ない。
命に係わるほどの重症や重病も余程、腕利きのヒーラーでもない限りは治せないのだ。
ヴィルヘルミナは物心のつかない幼い頃より、この癒しを正式に学ぶことなく、直感のみで使うことが出来た。
それも無制限で使えたのだ。
父親に連れられて、王城に登城したヴィルヘルミナはそこで金髪の愛らしい男の子と出会った。
それが第五王子であるリュークだったのが、彼女の進む道を大きく変えることになる。
「何をしているの?」
「か、か、かあしゃまに……ふれせんとあげりゅの」
ヴィルヘルミナより年長であるにも関わらず、リュークの言語は明瞭ではなく、その視線もどこか、定まっていない不安定なものだった。
しかし、彼女はこう思った。
何て、きれいな目をして、無垢な子なのだろうと……。
だから、願ってしまったのだ。
『どうか、彼に幸あらんことを』と。
その時、眩いばかりの白銀の光が放たれ、奇跡が起きたのだと言う。
かくして、ヴィルヘルミナが王家に囚われる理由が出来てしまったのだが、彼女の聖女の力に代償が必要であることを知る者は少ない。
ヴィルヘルミナは確かに病や傷を癒すことが出来た。
出産時の事故で生まれながらにして、患っていたリュークの病をも治せた者はこれまで誰一人いなかった。
それを成し遂げたヴィルヘルミナはまさに不世出の才能を持った聖女と言うべきだが、その代償はあまりにも大きい。
彼女の癒しは交換の原理に近い。
傷や病をヴィルヘルミナが自らの体に取り込んでから、治癒させるものだ。
それゆえ、重症の患者を治療する際には彼女自身が激痛を体験しなければ、ならないのだ。
しかし、ヴィルヘルミナはそれを苦と思わない無垢な魂を持つ真の聖女だった。
だからこそ、命を失いかねない瀕死のブランカを助け、自らが三日間、生死の境を彷徨うことになろうとも後悔しなかったのだ。
だが、ここで気を付けなくてはならないのがそれが完治する病や傷だったという点である。
リュークの病は完治しない。
ヴィルヘルミナの傍にいて、彼女が無意識に力を使うことでどうにか、状態が改善していただけに過ぎないのだ。
リュークの不幸はそのことを知らないまま、生きてきたことだと言えよう。
全てを知ったのは全てを失った時だったというのが皮肉である。
これまで聞いていない、知らないで済まされていたことはもう許されない。
「ごめん……ミナ……ごめん……」
頬がこけ、落ち窪んだ眼窩。
その顔にかつて讃えられた美しき容貌は微塵も感じられない。
ただ、止めどもなく流れ落ちる涙を湛える青い瞳はどこまでも澄んでいて、純真な物だった。
婚約者だった王子がやつれ果てた姿になりながらもようやく、己を取り戻したのだと知って、ヴィルヘルミナも目頭を押さえる。
リュークは良くも悪くも純粋だったとヴィルヘルミナは逡巡していた。
「聞いていなかったよ」「知らなかったんだ」が口癖でとても王子とは思えない振る舞いをするリュークだったが、人を傷つけない優しさを持つ人であった、と。
そんな彼があんな下劣な行為に走ったのはなぜだったのか?
自分に至らぬ点があったからだろうか?
ヴィルヘルミナは考えに耽るあまり、複雑な表情をしていたことに気付かない。
「私は……君に……返す」
「え?」
リュークがようやく吐き出した言葉にヴィルヘルミナが気が付いた時には、リュークは既に意識を失っており、安らかな寝息を立てていた。
その顔からは険しさがなくなっており、何も知らない幼子のように無垢なものに見える。
「お疲れ様でした、リューク殿下。どうか、お体を大切に……」
かつての婚約者を一瞥したヴィルヘルミナの菫色の瞳に宿るのは憐憫といくらかの愛惜の色だった。
退室していく彼女の目にもう迷いはない。
後の世に書かれた史書にこれ以降、第五王子リュークの名が出てくることはなかった。
ただ、デ・ブライネ辺境伯領で余生を過ごした一人の貴人がいたと記されるのみである。
0
あなたにおすすめの小説

存在感のない聖女が姿を消した後 [完]
風龍佳乃
恋愛
聖女であるディアターナは
永く仕えた国を捨てた。
何故って?
それは新たに現れた聖女が
ヒロインだったから。
ディアターナは
いつの日からか新聖女と比べられ
人々の心が離れていった事を悟った。
もう私の役目は終わったわ…
神託を受けたディアターナは
手紙を残して消えた。
残された国は天災に見舞われ
てしまった。
しかし聖女は戻る事はなかった。
ディアターナは西帝国にて
初代聖女のコリーアンナに出会い
運命を切り開いて
自分自身の幸せをみつけるのだった。


白い結婚を捨てた王妃は、もう二度と振り向かない ――愛さぬと言った王子が全てを失うまで』
鍛高譚
恋愛
「私は王妃を愛さない。彼女とは白い結婚を誓う」
華やかな王宮の大聖堂で交わされたのは、愛の誓いではなく、冷たい拒絶の言葉だった。
王子アルフォンスの婚姻相手として選ばれたレイチェル・ウィンザー。しかし彼女は、王妃としての立場を与えられながらも、夫からも宮廷からも冷遇され、孤独な日々を強いられる。王の寵愛はすべて聖女ミレイユに注がれ、王宮の権力は彼女の手に落ちていった。侮蔑と屈辱に耐える中、レイチェルは誇りを失わず、密かに反撃の機会をうかがう。
そんな折、隣国の公爵アレクサンダーが彼女の前に現れる。「君の目はまだ死んでいないな」――その言葉に、彼女の中で何かが目覚める。彼はレイチェルに自由と新たな未来を提示し、密かに王宮からの脱出を計画する。
レイチェルが去ったことで、王宮は急速に崩壊していく。聖女ミレイユの策略が暴かれ、アルフォンスは自らの過ちに気づくも、時すでに遅し。彼が頼るべき王妃は、もはや遠く、隣国で新たな人生を歩んでいた。
「お願いだ……戻ってきてくれ……」
王国を失い、誇りを失い、全てを失った王子の懇願に、レイチェルはただ冷たく微笑む。
「もう遅いわ」
愛のない結婚を捨て、誇り高き未来へと進む王妃のざまぁ劇。
裏切りと策略が渦巻く宮廷で、彼女は己の運命を切り開く。
これは、偽りの婚姻から真の誓いへと至る、誇り高き王妃の物語。

無能聖女の失敗ポーション〜働き口を探していたはずなのに、何故みんなに甘やかされているのでしょう?〜
矢口愛留
恋愛
クリスティーナは、初級ポーションすら満足に作れない無能聖女。
成人を迎えたことをきっかけに、これまでずっと暮らしていた神殿を出なくてはいけなくなった。
ポーションをどうにかお金に変えようと、冒険者ギルドに向かったクリスティーナは、自作ポーションだけでは生活できないことに気付く。
その時タイミングよく、住み込み可の依頼(ただしとても怪しい)を発見した彼女は、駆け出し冒険者のアンディと共に依頼を受ける。
依頼書に記載の館を訪れた二人を迎えるのは、正体不明の主人に仕える使用人、ジェーンだった。
そこでクリスティーナは、自作の失敗ポーションを飲んで体力を回復しながら仕事に励むのだが、どういうわけかアンディとジェーンにやたら甘やかされるように。
そして、クリスティーナの前に、館の主人、ギルバートが姿を現す。
ギルバートは、クリスティーナの失敗ポーションを必要としていて――。
「毎日、私にポーションを作ってくれないか。私には君が必要だ」
これは無能聖女として搾取され続けていたクリスティーナが、居場所を見つけ、自由を見つけ、ゆったりとした時間の中で輝いていくお話。
*カクヨム、小説家になろうにも投稿しています。

王家を追放された落ちこぼれ聖女は、小さな村で鍛冶屋の妻候補になります
cotonoha garden
恋愛
「聖女失格です。王家にも国にも、あなたはもう必要ありません」——そう告げられた日、リーネは王女でいることさえ許されなくなりました。
聖女としても王女としても半人前。婚約者の王太子には冷たく切り捨てられ、居場所を失った彼女がたどり着いたのは、森と鉄の匂いが混ざる辺境の小さな村。
そこで出会ったのは、無骨で無口なくせに、さりげなく怪我の手当てをしてくれる鍛冶屋ユリウス。
村の事情から「書類上の仮妻」として迎えられたリーネは、鍛冶場の雑用や村人の看病をこなしながら、少しずつ「誰かに必要とされる感覚」を取り戻していきます。
かつては「落ちこぼれ聖女」とさげすまれた力が、今度は村の子どもたちの笑顔を守るために使われる。
そんな新しい日々の中で、ぶっきらぼうな鍛冶屋の優しさや、村人たちのさりげない気遣いが、冷え切っていたリーネの心をゆっくりと溶かしていきます。
やがて、国難を前に王都から使者が訪れ、「再び聖女として戻ってこい」と告げられたとき——
リーネが選ぶのは、きらびやかな王宮か、それとも鉄音の響く小さな家か。
理不尽な追放と婚約破棄から始まる物語は、
「大切にされなかった記憶」を持つ読者に寄り添いながら、
自分で選び取った居場所と、静かであたたかな愛へとたどり着く物語です。

【完結】濡れ衣聖女はもう戻らない 〜ホワイトな宮廷ギルドで努力の成果が実りました
冬月光輝
恋愛
代々魔術師の名家であるローエルシュタイン侯爵家は二人の聖女を輩出した。
一人は幼き頃より神童と呼ばれた天才で、史上最年少で聖女の称号を得たエキドナ。
もう一人はエキドナの姉で、妹に遅れをとること五年目にしてようやく聖女になれた努力家、ルシリア。
ルシリアは魔力の量も生まれつき、妹のエキドナの十分の一以下でローエルシュタインの落ちこぼれだと蔑まれていた。
しかし彼女は努力を惜しまず、魔力不足を補う方法をいくつも生み出し、教会から聖女だと認められるに至ったのである。
エキドナは目立ちたがりで、国に一人しかいなかった聖女に姉がなることを良しとしなかった。
そこで、自らの家宝の杖を壊し、その罪を姉になすりつけ、彼女を実家から追放させた。
「無駄な努力」だと勝ち誇った顔のエキドナに嘲り笑われたルシリアは失意のまま隣国へと足を運ぶ。
エキドナは知らなかった。魔物が増えた昨今、彼女の働きだけでは不足だと教会にみなされて、姉が聖女になったことを。
ルシリアは隣国で偶然再会した王太子、アークハルトにその力を認められ、宮廷ギルド入りを勧められ、宮仕えとしての第二の人生を送ることとなる。
※旧タイトル『妹が神童だと呼ばれていた聖女、「無駄な努力」だと言われ追放される〜「努力は才能を凌駕する」と隣国の宮廷ギルドで証明したので、もう戻りません』

聖女は王子たちを完全スルーして、呪われ大公に強引求婚します!
葵 すみれ
恋愛
今宵の舞踏会は、聖女シルヴィアが二人の王子のどちらに薔薇を捧げるのかで盛り上がっていた。
薔薇を捧げるのは求婚の証。彼女が選んだ王子が、王位争いの勝者となるだろうと人々は囁き交わす。
しかし、シルヴィアは薔薇を持ったまま、自信満々な第一王子も、気取った第二王子も素通りしてしまう。
彼女が薔薇を捧げたのは、呪われ大公と恐れられ、蔑まれるマテウスだった。
拒絶されるも、シルヴィアはめげない。
壁ドンで追い詰めると、強引に薔薇を握らせて宣言する。
「わたくし、絶対にあなたさまを幸せにしてみせますわ! 絶対に、絶対にです!」
ぐいぐい押していくシルヴィアと、たじたじなマテウス。
二人のラブコメディが始まる。
※他サイトにも投稿しています
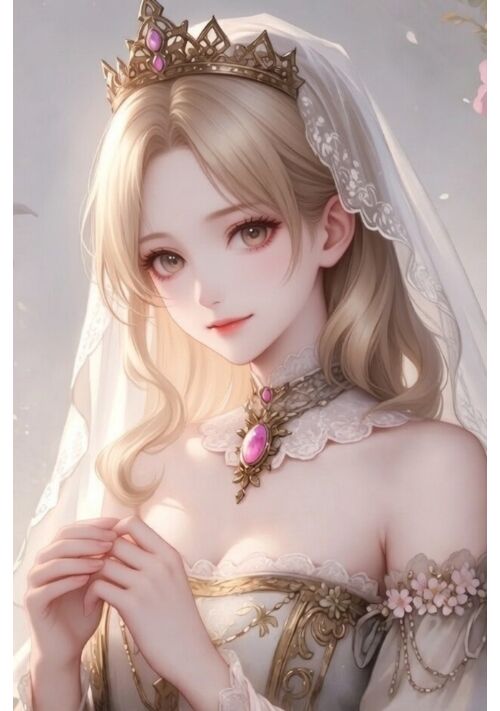
スキルなし王妃の逆転劇〜妹の策略で悪役令嬢にされ、婚約破棄された私が冷酷王の心を歌で揺らすまで〜
雪城 冴
恋愛
聖歌もファンファーレもない無音の結婚式。
「誓いの言葉は省略する」
冷酷王の宣言に、リリアナは言葉を失った。
スキル名を持たないという理由だけで“無能”と蔑まれてきたリリアナ。
妹の企みにより婚約破棄され、隣国の王・オスカーとの政略結婚が決まる。
義妹は悪魔のような笑みで言う。
「次は婚約破棄されないようにお気をつけて」
リリアナに残されたのは、自分を慰めるように歌うことだけ。
ところが、魔力が満ちるはずの王国には、舞踏会すら開かれない不気味な静寂が広がっていた。
――ここは〈音のない国〉
冷酷王が隠している“真実”とは?
そして、リリアナの本当のスキルとは――。
勇気と知性で運命を覆す、
痛快逆転ファンタジー。
※表紙絵はAI生成
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















