5 / 19
薬の効果が切れるまで後七日(2)
しおりを挟む
レオンの元に暗殺者が送り込まれていた頃、ソフィアとクリスティアーノは王都でも一番大きな劇場を訪れていた。
(オペラを見るのなんていつぶりかしら……)
少なくともここ数年で行った記憶はない。なんなら、レオンとは一度も行ったことがない。正直、この先も行くことはないと思っていた。
(それがまさかこんな形で行くことになるとは……なぜ殿下はここを選んだのかしら)
オペラ鑑賞なんて、それこそ『デート』ではないか。
わざわざ今ではなく、マルゲリータとの交流の際に行けばいいのに。と思ってしまう。
それとも、これにも理由があるのだろうか。
考えてみたが、わからない。
代わりに、昨日の出来事が脳裏に浮かび上がった。
執務室で目にしたのは、レオンとマルゲリータが身を寄せ合う姿。思わず見ているこちらが赤面してしまうくらい近かった。
(レオンがあの距離に甘んじていたってことは、あれが殿下たちの普通だったということなのかしら。それとも……マルゲリータ様が相手だったから?)
マルゲリータはソフィアと違い、妖艶な見た目をしている。黒い艶やかなウェーブの髪、バラのような赤い瞳、たった二歳しか変わらないとは思えない体つき。それでいて、貞淑な装いを好んでいる彼女のギャップがいいという男性は多い。
(レオンもああいう女性が好みだったってことかしら……)
そう考えると今までの自分に対する態度もしっくりする気がしてきた。
(そりゃあ好みじゃない女より、仕事の方が大切よね……)
考えれば考えるほど、悪い方向へと傾いていく。
「ソフィー。こっちへ」
「……え。ここ?」
「ああ。予約しておいたんだ」
暗い館内をクリスティアーノと繋いだ手を頼りに歩いて行った先にあったのは、二階のカップル席。大きめのソファーに二人で座りながら、オペラグラスを使って舞台を鑑賞する仕様らしい。しかも、カーテンを閉めると完全に二人きりになれる。
(ほ、本当にここで見るの?)
戸惑っていると背中を押された。
「大丈夫だから。座って」と小声で促され、座る。隣にクリスティアーノも腰を下ろした。
(近い……近すぎない?!)
「あ、あのっ」
「なに、飲む?」
差し出されたメニュー表。けれど、それに目を通す余裕などない。
「え、っと、あのオススメで」
「じゃあ、これとこれを」
注文を受けたスタッフが出ていく。その際、しっかりとカーテンも閉めて行った。緊張感が増す。
「あ、もう始まるね」
囁くように言われ、ソフィアは黙ってうなずくことしかできない。妙な緊張感の中、オペラ鑑賞を楽しむ余裕なんてない。と、思っていたのだが、途中運ばれてきたワインを口にしてからはすっかりその緊張感も溶けてしまった。
お酒の力か、はたまた偶然にもオペラの原作をソフィアが知っていたからか。
(これがあの……帰ったら教えてあげましょう。まあ、彼女のことだからもう知っているかもしれないけど)
原作を教えてくれた友人は大の恋愛小説好きだ。そんな彼女から聞いた話の内容は確かこうだった。
主人公はとある国の姫。幼い頃から姉妹の中でも不遇な扱いを受けてきた彼女は、ようやく自分だけを愛してくれる男性と出会う。彼女は父親である王に彼との婚約を願い出た。しかし、それを聞いた妹が横から割り込んでくる。王はなんと妹の願いを聞き入れた。妹の婚約者となってしまった彼。恋心は失われていないまま。彼もまた、彼女を愛していた。二人はもう一度王の説得を試みる。その過程で王家の不正を知ることとなる。最後は、彼女が女王となり、彼が王配となってハッピーエンドという物語。
「ソフィー……ソフィー」
名前を呼ばれ、瞼を開けた。顔を上げると、レオンと目が合う。
「ソフィー、もうすぐクライマックスだよ」
「クライ、マックス?」
「うん」
レオンの手がソフィアに伸び、わずかに乱れた髪を直す。
「あ、ありが……」
途中で我に返った。今、自分がどこにいるのか。そして、目の前のレオンの中身が誰なのか。先ほどまで誰の肩を借りていたのか。すべてを理解したソフィアはすぐさま謝罪しようとした。
しかし、頭を下げる前に止められた。
「そういうのは後で。今は見るのが先。はい、これ」
手渡されたオペラグラスを無意識に受け取る。すでに彼の視線は舞台へと向いている。彼に倣ってソフィアも舞台へ目を向けた。
最後まで見終わった後、改めてソフィアは頭を下げた。クリスティアーノは苦笑する。
「ソフィーは律儀だなあ。僕は気にしてないって言ってるのに」
「ですが、せっかく予約までしていただいたのに途中で寝るなんて……」
「うーん……あ、それなら、『クリス』って呼んでよ。昔みたいに」
「え……」
「入れ替わっている間だけでいいから。ね」
「それはさすがに……婚約者に悪いと言いますか……」
「そうかな? レオンなら気にしない気がするけど」
「……マルゲリータ様に悪いと思わないのですか?」
「別に。彼女は僕のことなんて……いや、これはいいか。とにかく決定ね。どうしても抵抗があるなら、二人きりの時だけでもいいから。名前を呼んでくれるならレオンには黙っててあげるよ。僕の肩でソフィーが寝たことはね」
「……わかり、ました」
一生の不覚を感じながらも、ソフィアは渋々頷き返したのだった。
◇
ソフィアとクリスティアーノが城へ戻ったのはそれからさらに二時間は経った後。
帰ってきたばかりの二人にその報せはもたらされた。
「え?!」
ルークという護衛騎士の報告にソフィアは息を呑む。
(執務室で殿下が暗殺者に襲われたですって?! 殿下は無事なの……って、そうだった。今、レオンが殿下になってるんだった。なら、大丈夫でしょうけど……いや、本当に大丈夫なのかしら。中身はレオンでも体は殿下のものだわ。思う通りに動かない可能性は十分にあるんじゃないかしら)
不安が募っていく中、クリスティアーノはすぐさま執務室へと足を向けた。一度振り向いて、ソフィアにも声をかける。
「ソフィーも一緒にきてくれ。おそらく大丈夫だとは思うが、念のため執務室にある書類をチェックしてもらいたい」
「え、ええ。もちろん」
ソフィアが一緒についていってもおかしくないような理由を提示してくれたのだろうと理解し、内心感謝しながらうなずき返す。
執務室は未だ荒れたままだった。床に紙がたくさん落ちている。けれど、思ったような惨状にはなっておらず、安堵する。レオンも無傷のようだ。
「レオン」
クリスティアーノの声に、レオンが反応した。
「一人かい?」
「ん……ああ。暗部がついてるから、外の護衛を二人に増やして、他のやつらは捕まえた連中の対応にあたらせた」
「そう……」
クリスティアーノが紙を拾い集め始めたので、ソフィアも倣って拾う。書類のチェックをしながら元の位置に戻していく二人を見て、レオンの眉間に皺が増える。
「それで、どうだったんだよ?」
「なにが?」と問い返そうとして、ソフィアは彼の不機嫌さに気づき、固まる。その反応がさらに彼を刺激したらしい。
「『デート』は楽しかったのか、って聞いてんだよ。俺がこんな目に遭っている間、おまえら『デート』してたんだろ。こんな時間まで……随分楽しんできたみてえだなあ? あ゛?」
(はあああああ?!)
ソフィアは思わず言い返そうとしたが、その言い返す言葉がないことに気づいて口を閉じる。
純粋に『デート』を楽しめたとは決して言えない。けれど、結果的に、というか傍目から見ればあれが『デート』であったのは間違いないだろう。加えて、最後のクリスティアーノとのやり取りは……。
「ごめんなさ……」
ソフィアが潔く謝ろうとした瞬間、クリスティアーノが「そうだね」と遮った。
「『デート』、とっても楽しかったよ。ねえ、ソフィー」
レオンの片眉がピクリと反応する。
「クリス。おまえ、よく俺の前でそんなこと言えるな」
「そんなことって、レオンが聞いてきたんじゃないか。あ、どんな『デート』だったかも聞きたいかい?」
「別にっ」
「今後の参考までに教えておいてあげるね。今日は、典型的な『デート』を楽しんできたよ。オシャレな店で食事をして、買い物をして、オペラ鑑賞に行ってきた。どれもレオン相手だと経験する機会ないだろうと思ってね」
感謝してねと言わんばかりのクリスティアーノに、レオンの怒りは頂点に達した。
「デートデートデートうるせえよ! なにが今後の参考だっ。俺だってなあ! それぐらいっ」
「できるなんて言わないよね。この一年間、デートどころか、茶会すらすっぽかしていたのに」
「だ、だからそれは、仕事が忙しくてっ」
「忙しいを言い訳にするのはどうかと思うな。私はいくら忙しくても時間は作っているよ。それが、婚約者としての務めだからね。……次期伯爵であるソフィーも同じだったと思うけど」
ソフィアは思わずコクコクうなずいてしまった。
「そ、それは……」と狼狽えるレオン。
「わ、わかった! 元に戻ったら俺もきちんと休み取ってソフィーとデートする!」
「いや無理でしょ」とつい、ソフィアの口から否定の言葉が漏れた。
冷静に考えて八日間も仕事を休んだ後に、さらに休みが取れるわけがない。第一、この一年間さんざん言ったにも拘わらず変わらなかったのがレオンなのだ。結局、何も変わらないというオチになるだろう。
レオンが今度はソフィアを見遣る。
「無理じゃねえよ! 俺だってな。こう見えて反省してるんだよ!」
「へえ……たとえばどんな?」
「どんな……たとえば、その……ソフィーの言う通り仕事中だけでもクリスに敬称付けるべきだった、とか」
「それが婚約者としての反省?」
「あ、いや。えっと、俺は今まで婚約者としての最低限のマナーってやつを守れてなかったんだと、自覚した。……今」
「「へえ(ほう)……」」
ソフィアとクリスティアーノの声が重なる。その反応に、レオンがむっと顔をしかめる。
「だからもうクリスと『デート』なんて行くんじゃねえぞ! 『デート』は俺の特権だからな! 戻ったら絶対にクリスよりも楽しい『デート』に俺が連れて行ってやるから、覚悟しておけよ!」
「覚悟が必要な『デート』って怖いんだけど。……まあ、気長に待ってるわ」
「おう!」
ソフィアは呆れた顔で「ところで」と会話を転換させた。
「ケガはしてないの?」
「ん?」
「……暗殺者が来たって聞いたけど?」
「……ああ。まあ、な」
「レオン?」
「いや……なんていうか、やっぱ俺は剣がないとダメだなと改めて思ったというか。もっと、剣に頼らない戦い方も学んでおかねえとな、というか……。クリスがつけておいてくれた暗部のおかげでなんとかなったけどよ。俺個人としては悔しい結果だったというか。……ああ、後、戻ったら部下の育成にももっと力を入れねえとな。剣を鞘から抜くタイミングも遅すぎたし……殺気を感じた瞬間に動けるよう、今日みたいな場面を想定した訓練も必要か……」
ぶつぶつと呟き始めたレオンは、すっかり護衛隊長としての顔つきになっている。
(へえ……そんな顔もできるんだ)
新たな一面を見てソフィアは瞬きを繰り返す。クリスティアーノの顔だからかわからないが、かっこよく見える。
ふと視界に入ったクリスティアーノにも目を向ける。彼もレオンをじっと見ていた。
その視線にソフィアはかすかな違和感を覚える。なにかを見極めようとしているかのようなその視線に。
(オペラを見るのなんていつぶりかしら……)
少なくともここ数年で行った記憶はない。なんなら、レオンとは一度も行ったことがない。正直、この先も行くことはないと思っていた。
(それがまさかこんな形で行くことになるとは……なぜ殿下はここを選んだのかしら)
オペラ鑑賞なんて、それこそ『デート』ではないか。
わざわざ今ではなく、マルゲリータとの交流の際に行けばいいのに。と思ってしまう。
それとも、これにも理由があるのだろうか。
考えてみたが、わからない。
代わりに、昨日の出来事が脳裏に浮かび上がった。
執務室で目にしたのは、レオンとマルゲリータが身を寄せ合う姿。思わず見ているこちらが赤面してしまうくらい近かった。
(レオンがあの距離に甘んじていたってことは、あれが殿下たちの普通だったということなのかしら。それとも……マルゲリータ様が相手だったから?)
マルゲリータはソフィアと違い、妖艶な見た目をしている。黒い艶やかなウェーブの髪、バラのような赤い瞳、たった二歳しか変わらないとは思えない体つき。それでいて、貞淑な装いを好んでいる彼女のギャップがいいという男性は多い。
(レオンもああいう女性が好みだったってことかしら……)
そう考えると今までの自分に対する態度もしっくりする気がしてきた。
(そりゃあ好みじゃない女より、仕事の方が大切よね……)
考えれば考えるほど、悪い方向へと傾いていく。
「ソフィー。こっちへ」
「……え。ここ?」
「ああ。予約しておいたんだ」
暗い館内をクリスティアーノと繋いだ手を頼りに歩いて行った先にあったのは、二階のカップル席。大きめのソファーに二人で座りながら、オペラグラスを使って舞台を鑑賞する仕様らしい。しかも、カーテンを閉めると完全に二人きりになれる。
(ほ、本当にここで見るの?)
戸惑っていると背中を押された。
「大丈夫だから。座って」と小声で促され、座る。隣にクリスティアーノも腰を下ろした。
(近い……近すぎない?!)
「あ、あのっ」
「なに、飲む?」
差し出されたメニュー表。けれど、それに目を通す余裕などない。
「え、っと、あのオススメで」
「じゃあ、これとこれを」
注文を受けたスタッフが出ていく。その際、しっかりとカーテンも閉めて行った。緊張感が増す。
「あ、もう始まるね」
囁くように言われ、ソフィアは黙ってうなずくことしかできない。妙な緊張感の中、オペラ鑑賞を楽しむ余裕なんてない。と、思っていたのだが、途中運ばれてきたワインを口にしてからはすっかりその緊張感も溶けてしまった。
お酒の力か、はたまた偶然にもオペラの原作をソフィアが知っていたからか。
(これがあの……帰ったら教えてあげましょう。まあ、彼女のことだからもう知っているかもしれないけど)
原作を教えてくれた友人は大の恋愛小説好きだ。そんな彼女から聞いた話の内容は確かこうだった。
主人公はとある国の姫。幼い頃から姉妹の中でも不遇な扱いを受けてきた彼女は、ようやく自分だけを愛してくれる男性と出会う。彼女は父親である王に彼との婚約を願い出た。しかし、それを聞いた妹が横から割り込んでくる。王はなんと妹の願いを聞き入れた。妹の婚約者となってしまった彼。恋心は失われていないまま。彼もまた、彼女を愛していた。二人はもう一度王の説得を試みる。その過程で王家の不正を知ることとなる。最後は、彼女が女王となり、彼が王配となってハッピーエンドという物語。
「ソフィー……ソフィー」
名前を呼ばれ、瞼を開けた。顔を上げると、レオンと目が合う。
「ソフィー、もうすぐクライマックスだよ」
「クライ、マックス?」
「うん」
レオンの手がソフィアに伸び、わずかに乱れた髪を直す。
「あ、ありが……」
途中で我に返った。今、自分がどこにいるのか。そして、目の前のレオンの中身が誰なのか。先ほどまで誰の肩を借りていたのか。すべてを理解したソフィアはすぐさま謝罪しようとした。
しかし、頭を下げる前に止められた。
「そういうのは後で。今は見るのが先。はい、これ」
手渡されたオペラグラスを無意識に受け取る。すでに彼の視線は舞台へと向いている。彼に倣ってソフィアも舞台へ目を向けた。
最後まで見終わった後、改めてソフィアは頭を下げた。クリスティアーノは苦笑する。
「ソフィーは律儀だなあ。僕は気にしてないって言ってるのに」
「ですが、せっかく予約までしていただいたのに途中で寝るなんて……」
「うーん……あ、それなら、『クリス』って呼んでよ。昔みたいに」
「え……」
「入れ替わっている間だけでいいから。ね」
「それはさすがに……婚約者に悪いと言いますか……」
「そうかな? レオンなら気にしない気がするけど」
「……マルゲリータ様に悪いと思わないのですか?」
「別に。彼女は僕のことなんて……いや、これはいいか。とにかく決定ね。どうしても抵抗があるなら、二人きりの時だけでもいいから。名前を呼んでくれるならレオンには黙っててあげるよ。僕の肩でソフィーが寝たことはね」
「……わかり、ました」
一生の不覚を感じながらも、ソフィアは渋々頷き返したのだった。
◇
ソフィアとクリスティアーノが城へ戻ったのはそれからさらに二時間は経った後。
帰ってきたばかりの二人にその報せはもたらされた。
「え?!」
ルークという護衛騎士の報告にソフィアは息を呑む。
(執務室で殿下が暗殺者に襲われたですって?! 殿下は無事なの……って、そうだった。今、レオンが殿下になってるんだった。なら、大丈夫でしょうけど……いや、本当に大丈夫なのかしら。中身はレオンでも体は殿下のものだわ。思う通りに動かない可能性は十分にあるんじゃないかしら)
不安が募っていく中、クリスティアーノはすぐさま執務室へと足を向けた。一度振り向いて、ソフィアにも声をかける。
「ソフィーも一緒にきてくれ。おそらく大丈夫だとは思うが、念のため執務室にある書類をチェックしてもらいたい」
「え、ええ。もちろん」
ソフィアが一緒についていってもおかしくないような理由を提示してくれたのだろうと理解し、内心感謝しながらうなずき返す。
執務室は未だ荒れたままだった。床に紙がたくさん落ちている。けれど、思ったような惨状にはなっておらず、安堵する。レオンも無傷のようだ。
「レオン」
クリスティアーノの声に、レオンが反応した。
「一人かい?」
「ん……ああ。暗部がついてるから、外の護衛を二人に増やして、他のやつらは捕まえた連中の対応にあたらせた」
「そう……」
クリスティアーノが紙を拾い集め始めたので、ソフィアも倣って拾う。書類のチェックをしながら元の位置に戻していく二人を見て、レオンの眉間に皺が増える。
「それで、どうだったんだよ?」
「なにが?」と問い返そうとして、ソフィアは彼の不機嫌さに気づき、固まる。その反応がさらに彼を刺激したらしい。
「『デート』は楽しかったのか、って聞いてんだよ。俺がこんな目に遭っている間、おまえら『デート』してたんだろ。こんな時間まで……随分楽しんできたみてえだなあ? あ゛?」
(はあああああ?!)
ソフィアは思わず言い返そうとしたが、その言い返す言葉がないことに気づいて口を閉じる。
純粋に『デート』を楽しめたとは決して言えない。けれど、結果的に、というか傍目から見ればあれが『デート』であったのは間違いないだろう。加えて、最後のクリスティアーノとのやり取りは……。
「ごめんなさ……」
ソフィアが潔く謝ろうとした瞬間、クリスティアーノが「そうだね」と遮った。
「『デート』、とっても楽しかったよ。ねえ、ソフィー」
レオンの片眉がピクリと反応する。
「クリス。おまえ、よく俺の前でそんなこと言えるな」
「そんなことって、レオンが聞いてきたんじゃないか。あ、どんな『デート』だったかも聞きたいかい?」
「別にっ」
「今後の参考までに教えておいてあげるね。今日は、典型的な『デート』を楽しんできたよ。オシャレな店で食事をして、買い物をして、オペラ鑑賞に行ってきた。どれもレオン相手だと経験する機会ないだろうと思ってね」
感謝してねと言わんばかりのクリスティアーノに、レオンの怒りは頂点に達した。
「デートデートデートうるせえよ! なにが今後の参考だっ。俺だってなあ! それぐらいっ」
「できるなんて言わないよね。この一年間、デートどころか、茶会すらすっぽかしていたのに」
「だ、だからそれは、仕事が忙しくてっ」
「忙しいを言い訳にするのはどうかと思うな。私はいくら忙しくても時間は作っているよ。それが、婚約者としての務めだからね。……次期伯爵であるソフィーも同じだったと思うけど」
ソフィアは思わずコクコクうなずいてしまった。
「そ、それは……」と狼狽えるレオン。
「わ、わかった! 元に戻ったら俺もきちんと休み取ってソフィーとデートする!」
「いや無理でしょ」とつい、ソフィアの口から否定の言葉が漏れた。
冷静に考えて八日間も仕事を休んだ後に、さらに休みが取れるわけがない。第一、この一年間さんざん言ったにも拘わらず変わらなかったのがレオンなのだ。結局、何も変わらないというオチになるだろう。
レオンが今度はソフィアを見遣る。
「無理じゃねえよ! 俺だってな。こう見えて反省してるんだよ!」
「へえ……たとえばどんな?」
「どんな……たとえば、その……ソフィーの言う通り仕事中だけでもクリスに敬称付けるべきだった、とか」
「それが婚約者としての反省?」
「あ、いや。えっと、俺は今まで婚約者としての最低限のマナーってやつを守れてなかったんだと、自覚した。……今」
「「へえ(ほう)……」」
ソフィアとクリスティアーノの声が重なる。その反応に、レオンがむっと顔をしかめる。
「だからもうクリスと『デート』なんて行くんじゃねえぞ! 『デート』は俺の特権だからな! 戻ったら絶対にクリスよりも楽しい『デート』に俺が連れて行ってやるから、覚悟しておけよ!」
「覚悟が必要な『デート』って怖いんだけど。……まあ、気長に待ってるわ」
「おう!」
ソフィアは呆れた顔で「ところで」と会話を転換させた。
「ケガはしてないの?」
「ん?」
「……暗殺者が来たって聞いたけど?」
「……ああ。まあ、な」
「レオン?」
「いや……なんていうか、やっぱ俺は剣がないとダメだなと改めて思ったというか。もっと、剣に頼らない戦い方も学んでおかねえとな、というか……。クリスがつけておいてくれた暗部のおかげでなんとかなったけどよ。俺個人としては悔しい結果だったというか。……ああ、後、戻ったら部下の育成にももっと力を入れねえとな。剣を鞘から抜くタイミングも遅すぎたし……殺気を感じた瞬間に動けるよう、今日みたいな場面を想定した訓練も必要か……」
ぶつぶつと呟き始めたレオンは、すっかり護衛隊長としての顔つきになっている。
(へえ……そんな顔もできるんだ)
新たな一面を見てソフィアは瞬きを繰り返す。クリスティアーノの顔だからかわからないが、かっこよく見える。
ふと視界に入ったクリスティアーノにも目を向ける。彼もレオンをじっと見ていた。
その視線にソフィアはかすかな違和感を覚える。なにかを見極めようとしているかのようなその視線に。
25
あなたにおすすめの小説

【旦那様は魔王様 外伝】魔界でいちばん大嫌い~絶対に好きになんて、ならないんだから!~
狭山ひびき
恋愛
「あんたなんか、大嫌いよ!」ミリアムは大きく息を吸い込んで、宣言した。はじめてアスヴィルと出会ったとき、彼は意地悪だった。二度と会いたくないと思うほど嫌っていたのに、ある日を境に、アスヴィルのミリアムに対する態度が激変する。突然アスヴィルは、ミリアムを愛していると言い出したのだ。しかしミリアムは昔のまま、彼のことが大嫌い。そんなミリアムを振り向かせようと、手紙やお菓子、果ては大声で愛を叫んで、気持ちを伝えようとするアスヴィル。果たして、アスヴィルの気持ちはミリアムに届くのか――
※本作品は、【旦那様は魔王様!】の外伝ですが、本編からは独立したお話です。

【完結】モブ令嬢としてひっそり生きたいのに、腹黒公爵に気に入られました
22時完結
恋愛
貴族の家に生まれたものの、特別な才能もなく、家の中でも空気のような存在だったセシリア。
華やかな社交界には興味もないし、政略結婚の道具にされるのも嫌。だからこそ、目立たず、慎ましく生きるのが一番——。
そう思っていたのに、なぜか冷酷無比と名高いディートハルト公爵に目をつけられてしまった!?
「……なぜ私なんですか?」
「君は実に興味深い。そんなふうにおとなしくしていると、余計に手を伸ばしたくなる」
ーーそんなこと言われても困ります!
目立たずモブとして生きたいのに、公爵様はなぜか私を執拗に追いかけてくる。
しかも、いつの間にか甘やかされ、独占欲丸出しで迫られる日々……!?
「君は俺のものだ。他の誰にも渡すつもりはない」
逃げても逃げても追いかけてくる腹黒公爵様から、私は無事にモブ人生を送れるのでしょうか……!?

むにゃむにゃしてたら私にだけ冷たい幼馴染と結婚してました~お飾り妻のはずですが溺愛しすぎじゃないですか⁉~
景華
恋愛
「シリウス・カルバン……むにゃむにゃ……私と結婚、してぇ……むにゃむにゃ」
「……は?」
そんな寝言のせいで、すれ違っていた二人が結婚することに!?
精霊が作りし国ローザニア王国。
セレンシア・ピエラ伯爵令嬢には、国家機密扱いとなるほどの秘密があった。
【寝言の強制実行】。
彼女の寝言で発せられた言葉は絶対だ。
精霊の加護を持つ王太子ですらパシリに使ってしまうほどの強制力。
そしてそんな【寝言の強制実行】のせいで結婚してしまった相手は、彼女の幼馴染で公爵令息にして副騎士団長のシリウス・カルバン。
セレンシアを元々愛してしまったがゆえに彼女の前でだけクールに装ってしまうようになっていたシリウスは、この結婚を機に自分の本当の思いを素直に出していくことを決意し自分の思うがままに溺愛しはじめるが、セレンシアはそれを寝言のせいでおかしくなっているのだと勘違いをしたまま。
それどころか、自分の寝言のせいで結婚してしまっては申し訳ないからと、3年間白い結婚をして離縁しようとまで言い出す始末。
自分の思いを信じてもらえないシリウスは、彼女の【寝言の強制実行】の力を消し去るため、どこかにいるであろう魔法使いを探し出す──!!
大人になるにつれて離れてしまった心と身体の距離が少しずつ縮まって、絡まった糸が解けていく。
すれ違っていた二人の両片思い勘違い恋愛ファンタジー!!

白い結婚のはずでしたが、冷血辺境伯の溺愛は想定外です
鍛高譚
恋愛
――私の結婚は、愛も干渉もない『白い結婚』のはずでした。
侯爵令嬢クレスタは王太子アレクシオンから一方的に婚約破棄を告げられ、冷徹と名高い辺境伯ジークフリートと政略結婚をすることに。 しかしその結婚には、『互いに干渉しない』『身体の関係を持たない』という特別な契約があった。
形だけの夫婦を続けながらも、ジークフリートの優しさや温もりに触れるうち、クレスタの傷ついた心は少しずつ癒されていく。 一方で、クレスタを捨てた王太子と平民の少女ミーナは『真実の愛』を声高に叫ぶが、次第にその実態が暴かれ、彼らの運命は思わぬ方向へと転落していく。
やがて訪れるざまぁな展開の先にあるのは、真実の愛によって結ばれる二人の未来――。

悪魔が泣いて逃げ出すほど不幸な私ですが、孤独な公爵様の花嫁になりました
ぜんだ 夕里
恋愛
「伴侶の記憶を食べる悪魔」に取り憑かれた公爵の元に嫁いできた男爵令嬢ビータ。婚約者は皆、記憶を奪われ逃げ出すという噂だが、彼女は平然としていた。なぜなら悪魔が彼女の記憶を食べようとした途端「まずい!ドブの味がする!」と逃げ出したから。
壮絶な過去を持つ令嬢と孤独な公爵の、少し変わった結婚生活が始まる。

結婚5年目の仮面夫婦ですが、そろそろ限界のようです!?
宮永レン
恋愛
没落したアルブレヒト伯爵家を援助すると声をかけてきたのは、成り上がり貴族と呼ばれるヴィルジール・シリングス子爵。援助の条件とは一人娘のミネットを妻にすること。
ミネットは形だけの結婚を申し出るが、ヴィルジールからは仕事に支障が出ると困るので外では仲の良い夫婦を演じてほしいと告げられる。
仮面夫婦としての生活を続けるうちに二人の心には変化が生まれるが……
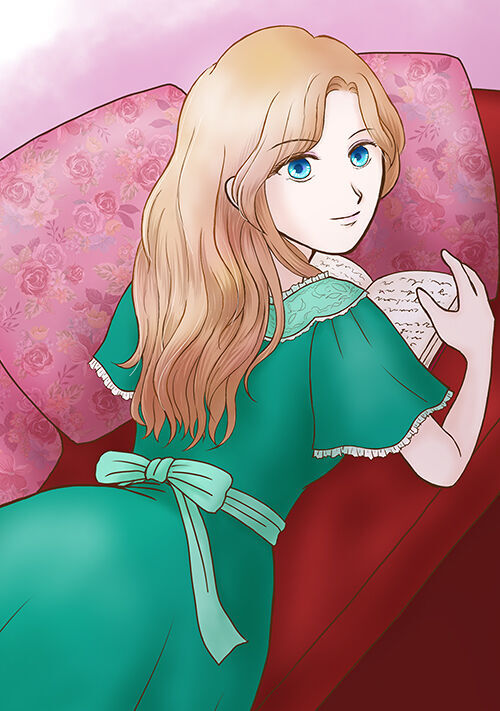
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

死にキャラに転生したけど、仲間たちに全力で守られて溺愛されています。
藤原遊
恋愛
「死ぬはずだった運命なんて、冒険者たちが全力で覆してくれる!」
街を守るために「死ぬ役目」を覚悟した私。
だけど、未来をやり直す彼らに溺愛されて、手放してくれません――!?
街を守り「死ぬ役目」に転生したスフィア。
彼女が覚悟を決めたその時――冒険者たちが全力で守り抜くと誓った!
未来を変えるため、スフィアを何度でも守る彼らの執着は止まらない!?
「君が笑っているだけでいい。それが、俺たちのすべてだ。」
運命に抗う冒険者たちが織り成す、異世界溺愛ファンタジー!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















