76 / 304
第1章 暗い闇と蒼い薔薇
副魔術師長の策略 4
しおりを挟む
サイラスは地下室の前にいる。
扉がわずかに開いていた。
その扉の前に、老人が立っている。
ローブ姿なのは、魔術師だからだ。
この城の使い道は、ほとんどこの老人に集約されていた。
彼の名はレスター。
サイラスより、ずっと年上だったが、実際に何歳なのかは知らない。
興味がなかったので調べなかっただけなのだけれども。
「あの2人は、儂の好きにしてよいのだな?」
老人は顎をしゃくり、扉の向こうを指し示す。
しわがれた声は、とても聞き苦しかった。
顔も皺だらけで、その皺に切り込みを入れたような目は、注視していなければ、目だと気づかないほど細い。
体をしゃんとさせれば、おそらくサイラスよりも背は高いはずだ。
が、背中が丸まっていて、してもいないのに会釈をしているように見える。
そのせいで、ちょうど顔の位置が同じくらいの高さになってしまうのが不快だった。
この老人はサイラスの「趣味」に合わない。
「基本的には、そうなんですがね。どちらか片方は生かしておいてもらわなければ困ります」
「生きておればよいのか?」
「まともに言葉が発せられる程度に、生かしておいてください」
老人が面白くないとでも言いたげに鼻を鳴らす。
サイラスにしても、面白くはないのだ。
が、この城を使う以上は、この老人もまた駒のひとつに換算すべきだと判断していた。
使えるものは、なんでも使う。
汚れた駒でも、駒は駒だ。
(あの残念な弟と同じくらい虫唾が走る老人ですが、備えにはなるでしょう)
レスターは、サイラスが魔力に顕現する前から、この城にいる。
何十年だか前に捕らえられ、幽閉されたのだ。
サイラスも含め、外の者は鍵さえあれば城への出入りが自由にできる。
が、レスターだけは出られない。
レスターの血には禁忌の印が刻まれているからだ。
その刻印により、この老人は城を出ることを封じられている。
理由は、有り余るほどあった。
レスターは魔力が顕現してからこっち、碌なことをしていない。
そのせいで、魔術師を危険視する声が高まったとも言える。
後人にとっては、いい迷惑だ。
「では、長持ちしたほうということにしておくか」
「どうぞ、お好きに」
レスターの嗜好は特異に過ぎる。
そして、美しさの欠片もない。
魔力の器が無駄に大きいのも厄介だった。
この城には、かつて隔離されていた者たちの魔力の残り滓が充満している。
魔力が外に出るのを疎外する構造になっているのだから当然だ。
それをレスターは吸い取ることで生きてきたのだろう。
でなければ、とっくに死んでいてもおかしくない。
魔力感知の必要もないくらい、レスターの持つ魔力を感じる。
上級魔術師と同程度の大きさの器に、溜め込めるだけ溜めているのだ。
「久しぶりに楽しめそうだ」
言葉に、不快感が体中に走った。
汚らわしいとしか言いようがない。
同じ殺戮者でも、ジョシュア・ローエルハイドとは質が異なる。
彼のような気高さも尊さも、目の前の老人にはなかった。
本音をさらせば、さわるのも見るのも嫌なのだ。
自分まで穢れる気がする。
だから、けしてふれたりはしない。
視覚は閉ざせないため、しかたなく細い目と視線を合わせていた。
が、見ているだけで視界から気持ちの悪いものが体に流れ込んでくる気がして、不快極まりないのだ。
「ところで、アンバス侯爵は、ここにはおいでになるんですか?」
老人の、特異な嗜好についてなど聞く気はなかった。
耳まで穢れそうなので、聞きたくもない。
「あの小僧か。時々は来るぞ」
ヒヒッと喉を引き攣らせ、レスターが笑う。
にやにやとしているのがわかるのは、唇のない口が動いたからだ。
口も深い皺に、ほぼ埋まっている。
見た目にも見苦しい老人だった。
手入れがされていようはずもない長い爪を、やたらに長い舌で、でろりと舐めている。
「何をしに来るんでしょう?」
だいたいの予測は立っていた。
レスターに問うたのは、予測を補完するためだ。
レスターの目が、いよいよ細められた。
皺と同化してしまい、どこにあるのか見定めるのが難しくなる。
さりとて、視線を合わせたくないサイラスは、気づかないフリをした。
「あの小僧の手に負えなくなった女を連れてくる。だいたいは平民の女だ」
この城に、そうした女性を放り込んで知らん顔。
そんなところだろう。
魔力を持たない者は、魔術師がいないと、ここから出られない。
扉の内鍵には「錠鎖」という刻印の術が、かけられていた。
刻印の術は魔術の前身にあたる。
まだ魔術の存在が認められてはいなかった頃にも、まともな魔術師もどきがいたのだろう。
魔力をこめた塗料で扉を塗り、中からは鍵が開かないようにした。
だが、刻印の術はすでに廃れている。
魔術が使えれば、必要のないものだからだ。
「そうですか」
捕らえられた女性たちが、どうなったのかは考えない。
レスターに説明されたくもなかった。
どうせ、彼女らは、2度と外の景色を見ることはなかっただろう。
考えても無駄だし、その価値もない。
「あなたにとっては、侯爵の色狂いも役に立ってるというわけですね」
「もっと頻繁に持ってくるのなら、礼のひとつも言うがな」
アンバス侯爵は、好色で名を馳せている。
ベッドをともにする相手は、男女問わずだった。
中には、無理に「つきあわせた」者もいたのかもしれない。
ここに連れてこられるのが平民の女だというだけで、うかがい知れる。
そもそも一時の遊びを好むので、アンバス侯爵は好色と言われているのだ。
愛妾にする気がないから、飽きれば面倒に感じるだけ。
レスターとは、存外、気が合っているのかもしれない。
直接に関わりたいと思ってはいないにしても。
(必要なことは聞けました。備えも、十分でしょう)
この城にレスターがいるのは知っていたので、あらかじめ「餌」を用意していた。
レスターから自分たちのことが露見するのは、望ましくなかったからだ。
こんな者の言うことを間に受ける愚か者も、王宮にはいる。
王太子が王位に就くのは決定された未来だった。
国王は第2王子に王位を継がせる気はないのだから。
それでも、ザカリーを持ち上げるものも少なからずいた。
王宮は、いつでも貴族同士の派閥争いで賑わっている。
王太子も、全面的に安泰ではないのだ。
早目の即位に向けて手を尽くしているのは、そういった裏事情もある。
そして、やはりサイラスは、このことを王太子には話していなかった。
レスターとの取引は、さすがに王太子も抵抗を覚えるに違いない。
(とはいえ、この老人は、そこそこの魔術の使い手。私1人では、手こずりそうですし。餌をやって黙らせておくほうが、面倒がないでしょうね)
執事とメイド長に、悪いとは思わなかった。
予定でなかったにもかかわらず、勝手に転移してきたのは彼らなのだ。
メイド長はレスター好みでもあったので、良いタイミングではあったけれど。
レスターが好むのは、いつも20代から30代の女性。
男性が犠牲になることあったようだが、それは餌が足りなかったに過ぎない。
レスターは殺戮者であり、拷問官きどりの狂人だ。
何人もの男女が犠牲となっている。
王宮にいれば、優秀な魔術師として重用されただろうに。
サイラスにとって、レスターは資源を無駄にしている愚か者に過ぎない。
「おや。彼ら、目を覚ましてますよ?」
扉の隙間から、彼らが見えた。
動いていることにより、生存確認はできている。
「くれぐれも気をつけてくださいね。2人とも殺してしまわないように」
「何度も言うな。儂は、時間をかけるのが好きなのでな」
老人の気持ちは、すでに中にいる2人に向いているようだ。
機嫌を損ねる気もなかったので、サイラスはレスターに背を向ける。
「では、行きますか」
レスターが彼らをどう料理するのかは知らないし、知りたくもない。
老人は、若い女性を甚振るのが好きなのだ。
魔力顕現した12歳の頃には、すでに貴族の娘を殺している。
最初の犠牲者は、レスターの姉だった。
サイラスは扉が閉まるのを待って、唇を歪める。
(魔術を拷問に使うなど、私には理解しがたいのですがね。まったく悍ましい限りですよ)
扉がわずかに開いていた。
その扉の前に、老人が立っている。
ローブ姿なのは、魔術師だからだ。
この城の使い道は、ほとんどこの老人に集約されていた。
彼の名はレスター。
サイラスより、ずっと年上だったが、実際に何歳なのかは知らない。
興味がなかったので調べなかっただけなのだけれども。
「あの2人は、儂の好きにしてよいのだな?」
老人は顎をしゃくり、扉の向こうを指し示す。
しわがれた声は、とても聞き苦しかった。
顔も皺だらけで、その皺に切り込みを入れたような目は、注視していなければ、目だと気づかないほど細い。
体をしゃんとさせれば、おそらくサイラスよりも背は高いはずだ。
が、背中が丸まっていて、してもいないのに会釈をしているように見える。
そのせいで、ちょうど顔の位置が同じくらいの高さになってしまうのが不快だった。
この老人はサイラスの「趣味」に合わない。
「基本的には、そうなんですがね。どちらか片方は生かしておいてもらわなければ困ります」
「生きておればよいのか?」
「まともに言葉が発せられる程度に、生かしておいてください」
老人が面白くないとでも言いたげに鼻を鳴らす。
サイラスにしても、面白くはないのだ。
が、この城を使う以上は、この老人もまた駒のひとつに換算すべきだと判断していた。
使えるものは、なんでも使う。
汚れた駒でも、駒は駒だ。
(あの残念な弟と同じくらい虫唾が走る老人ですが、備えにはなるでしょう)
レスターは、サイラスが魔力に顕現する前から、この城にいる。
何十年だか前に捕らえられ、幽閉されたのだ。
サイラスも含め、外の者は鍵さえあれば城への出入りが自由にできる。
が、レスターだけは出られない。
レスターの血には禁忌の印が刻まれているからだ。
その刻印により、この老人は城を出ることを封じられている。
理由は、有り余るほどあった。
レスターは魔力が顕現してからこっち、碌なことをしていない。
そのせいで、魔術師を危険視する声が高まったとも言える。
後人にとっては、いい迷惑だ。
「では、長持ちしたほうということにしておくか」
「どうぞ、お好きに」
レスターの嗜好は特異に過ぎる。
そして、美しさの欠片もない。
魔力の器が無駄に大きいのも厄介だった。
この城には、かつて隔離されていた者たちの魔力の残り滓が充満している。
魔力が外に出るのを疎外する構造になっているのだから当然だ。
それをレスターは吸い取ることで生きてきたのだろう。
でなければ、とっくに死んでいてもおかしくない。
魔力感知の必要もないくらい、レスターの持つ魔力を感じる。
上級魔術師と同程度の大きさの器に、溜め込めるだけ溜めているのだ。
「久しぶりに楽しめそうだ」
言葉に、不快感が体中に走った。
汚らわしいとしか言いようがない。
同じ殺戮者でも、ジョシュア・ローエルハイドとは質が異なる。
彼のような気高さも尊さも、目の前の老人にはなかった。
本音をさらせば、さわるのも見るのも嫌なのだ。
自分まで穢れる気がする。
だから、けしてふれたりはしない。
視覚は閉ざせないため、しかたなく細い目と視線を合わせていた。
が、見ているだけで視界から気持ちの悪いものが体に流れ込んでくる気がして、不快極まりないのだ。
「ところで、アンバス侯爵は、ここにはおいでになるんですか?」
老人の、特異な嗜好についてなど聞く気はなかった。
耳まで穢れそうなので、聞きたくもない。
「あの小僧か。時々は来るぞ」
ヒヒッと喉を引き攣らせ、レスターが笑う。
にやにやとしているのがわかるのは、唇のない口が動いたからだ。
口も深い皺に、ほぼ埋まっている。
見た目にも見苦しい老人だった。
手入れがされていようはずもない長い爪を、やたらに長い舌で、でろりと舐めている。
「何をしに来るんでしょう?」
だいたいの予測は立っていた。
レスターに問うたのは、予測を補完するためだ。
レスターの目が、いよいよ細められた。
皺と同化してしまい、どこにあるのか見定めるのが難しくなる。
さりとて、視線を合わせたくないサイラスは、気づかないフリをした。
「あの小僧の手に負えなくなった女を連れてくる。だいたいは平民の女だ」
この城に、そうした女性を放り込んで知らん顔。
そんなところだろう。
魔力を持たない者は、魔術師がいないと、ここから出られない。
扉の内鍵には「錠鎖」という刻印の術が、かけられていた。
刻印の術は魔術の前身にあたる。
まだ魔術の存在が認められてはいなかった頃にも、まともな魔術師もどきがいたのだろう。
魔力をこめた塗料で扉を塗り、中からは鍵が開かないようにした。
だが、刻印の術はすでに廃れている。
魔術が使えれば、必要のないものだからだ。
「そうですか」
捕らえられた女性たちが、どうなったのかは考えない。
レスターに説明されたくもなかった。
どうせ、彼女らは、2度と外の景色を見ることはなかっただろう。
考えても無駄だし、その価値もない。
「あなたにとっては、侯爵の色狂いも役に立ってるというわけですね」
「もっと頻繁に持ってくるのなら、礼のひとつも言うがな」
アンバス侯爵は、好色で名を馳せている。
ベッドをともにする相手は、男女問わずだった。
中には、無理に「つきあわせた」者もいたのかもしれない。
ここに連れてこられるのが平民の女だというだけで、うかがい知れる。
そもそも一時の遊びを好むので、アンバス侯爵は好色と言われているのだ。
愛妾にする気がないから、飽きれば面倒に感じるだけ。
レスターとは、存外、気が合っているのかもしれない。
直接に関わりたいと思ってはいないにしても。
(必要なことは聞けました。備えも、十分でしょう)
この城にレスターがいるのは知っていたので、あらかじめ「餌」を用意していた。
レスターから自分たちのことが露見するのは、望ましくなかったからだ。
こんな者の言うことを間に受ける愚か者も、王宮にはいる。
王太子が王位に就くのは決定された未来だった。
国王は第2王子に王位を継がせる気はないのだから。
それでも、ザカリーを持ち上げるものも少なからずいた。
王宮は、いつでも貴族同士の派閥争いで賑わっている。
王太子も、全面的に安泰ではないのだ。
早目の即位に向けて手を尽くしているのは、そういった裏事情もある。
そして、やはりサイラスは、このことを王太子には話していなかった。
レスターとの取引は、さすがに王太子も抵抗を覚えるに違いない。
(とはいえ、この老人は、そこそこの魔術の使い手。私1人では、手こずりそうですし。餌をやって黙らせておくほうが、面倒がないでしょうね)
執事とメイド長に、悪いとは思わなかった。
予定でなかったにもかかわらず、勝手に転移してきたのは彼らなのだ。
メイド長はレスター好みでもあったので、良いタイミングではあったけれど。
レスターが好むのは、いつも20代から30代の女性。
男性が犠牲になることあったようだが、それは餌が足りなかったに過ぎない。
レスターは殺戮者であり、拷問官きどりの狂人だ。
何人もの男女が犠牲となっている。
王宮にいれば、優秀な魔術師として重用されただろうに。
サイラスにとって、レスターは資源を無駄にしている愚か者に過ぎない。
「おや。彼ら、目を覚ましてますよ?」
扉の隙間から、彼らが見えた。
動いていることにより、生存確認はできている。
「くれぐれも気をつけてくださいね。2人とも殺してしまわないように」
「何度も言うな。儂は、時間をかけるのが好きなのでな」
老人の気持ちは、すでに中にいる2人に向いているようだ。
機嫌を損ねる気もなかったので、サイラスはレスターに背を向ける。
「では、行きますか」
レスターが彼らをどう料理するのかは知らないし、知りたくもない。
老人は、若い女性を甚振るのが好きなのだ。
魔力顕現した12歳の頃には、すでに貴族の娘を殺している。
最初の犠牲者は、レスターの姉だった。
サイラスは扉が閉まるのを待って、唇を歪める。
(魔術を拷問に使うなど、私には理解しがたいのですがね。まったく悍ましい限りですよ)
1
あなたにおすすめの小説

召喚先は、誰も居ない森でした
みん
恋愛
事故に巻き込まれて行方不明になった母を探す茉白。そんな茉白を側で支えてくれていた留学生のフィンもまた、居なくなってしまい、寂しいながらも毎日を過ごしていた。そんなある日、バイト帰りに名前を呼ばれたかと思った次の瞬間、眩しい程の光に包まれて──
次に目を開けた時、茉白は森の中に居た。そして、そこには誰も居らず──
その先で、茉白が見たモノは──
最初はシリアス展開が続きます。
❋他視点のお話もあります
❋独自設定有り
❋気を付けてはいますが、誤字脱字があると思います。気付いた時に訂正していきます。

赤貧令嬢の借金返済契約
夏菜しの
恋愛
大病を患った父の治療費がかさみ膨れ上がる借金。
いよいよ返す見込みが無くなった頃。父より爵位と領地を返還すれば借金は国が肩代わりしてくれると聞かされる。
クリスタは病床の父に代わり爵位を返還する為に一人で王都へ向かった。
王宮の中で会ったのは見た目は良いけど傍若無人な大貴族シリル。
彼は令嬢の過激なアプローチに困っていると言い、クリスタに婚約者のフリをしてくれるように依頼してきた。
それを条件に父の医療費に加えて、借金を肩代わりしてくれると言われてクリスタはその契約を承諾する。
赤貧令嬢クリスタと大貴族シリルのお話です。

【完】夫に売られて、売られた先の旦那様に溺愛されています。
112
恋愛
夫に売られた。他所に女を作り、売人から受け取った銀貨の入った小袋を懐に入れて、出ていった。呆気ない別れだった。
ローズ・クローは、元々公爵令嬢だった。夫、だった人物は男爵の三男。到底釣合うはずがなく、手に手を取って家を出た。いわゆる駆け落ち婚だった。
ローズは夫を信じ切っていた。金が尽き、宝石を差し出しても、夫は自分を愛していると信じて疑わなかった。
※完結しました。ありがとうございました。

虐げられていた次期公爵の四歳児の契約母になります!~幼子を幸せにしたいのに、未来の旦那様である王太子が私を溺愛してきます~
八重
恋愛
伯爵令嬢フローラは、公爵令息ディーターの婚約者。
しかし、そんな日々の裏で心を痛めていることが一つあった。
それはディーターの異母弟、四歳のルイトが兄に虐げられていること。
幼い彼を救いたいと思った彼女は、「ある計画」の準備を進めることにする。
それは、ルイトを救い出すための唯一の方法──。
そんな時、フローラはディーターから突然婚約破棄される。
婚約破棄宣言を受けた彼女は「今しかない」と計画を実行した。
彼女の計画、それは自らが代理母となること。
だが、この代理母には国との間で結ばれた「ある契約」が存在して……。
こうして始まったフローラの代理母としての生活。
しかし、ルイトの無邪気な笑顔と可愛さが、フローラの苦労を温かい喜びに変えていく。
さらに、見目麗しいながら策士として有名な第一王子ヴィルが、フローラに興味を持ち始めて……。
ほのぼの心温まる、子育て溺愛ストーリーです。
※ヒロインが序盤くじけがちな部分ありますが、それをバネに強くなります
※「小説家になろう」が先行公開です(第二章開始しました)
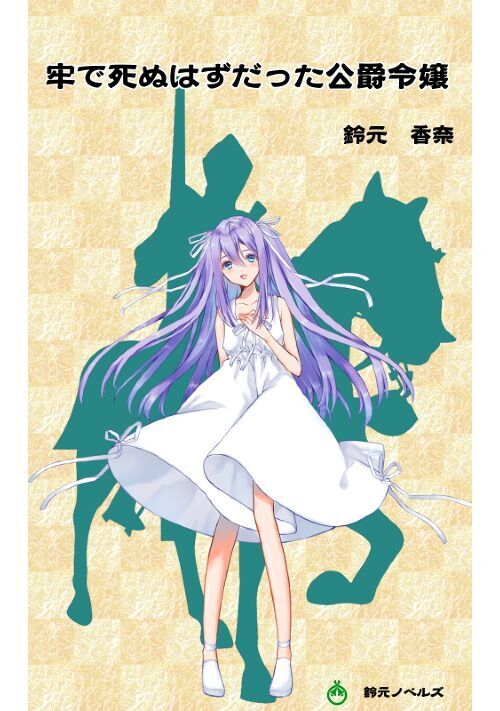
牢で死ぬはずだった公爵令嬢
鈴元 香奈
恋愛
婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。
表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。
小説家になろうさんにも投稿しています。

転生したら地味ダサ令嬢でしたが王子様に助けられて何故か執着されました
古里@3巻電子書籍化『王子に婚約破棄され
恋愛
皆様の応援のおかげでHOT女性向けランキング第7位獲得しました。
前世病弱だったニーナは転生したら周りから地味でダサいとバカにされる令嬢(もっとも平民)になっていた。「王女様とか公爵令嬢に転生したかった」と祖母に愚痴ったら叱られた。そんなニーナが祖母が死んで冒険者崩れに襲われた時に助けてくれたのが、ウィルと呼ばれる貴公子だった。
恋に落ちたニーナだが、平民の自分が二度と会うことはないだろうと思ったのも、束の間。魔法が使えることがバレて、晴れて貴族がいっぱいいる王立学園に入ることに!
しかし、そこにはウィルはいなかったけれど、何故か生徒会長ら高位貴族に絡まれて学園生活を送ることに……
見た目は地味ダサ、でも、行動力はピカ一の地味ダサ令嬢の巻き起こす波乱万丈学園恋愛物語の始まりです!?
小説家になろうでも公開しています。
第9回カクヨムWeb小説コンテスト中間選考通過作品

このたび、あこがれ騎士さまの妻になりました。
若松だんご
恋愛
「リリー。アナタ、結婚なさい」
それは、ある日突然、おつかえする王妃さまからくだされた命令。
まるで、「そこの髪飾りと取って」とか、「窓を開けてちょうだい」みたいなノリで発せられた。
お相手は、王妃さまのかつての乳兄弟で護衛騎士、エディル・ロードリックさま。
わたしのあこがれの騎士さま。
だけど、ちょっと待って!! 結婚だなんて、いくらなんでもそれはイキナリすぎるっ!!
「アナタたちならお似合いだと思うんだけど?」
そう思うのは、王妃さまだけですよ、絶対。
「試しに、二人で暮らしなさい。これは命令です」
なーんて、王妃さまの命令で、エディルさまの妻(仮)になったわたし。
あこがれの騎士さまと一つ屋根の下だなんてっ!!
わたし、どうなっちゃうのっ!? 妻(仮)ライフ、ドキドキしすぎで心臓がもたないっ!!

異世界から来た娘が、たまらなく可愛いのだが(同感)〜こっちにきてから何故かイケメンに囲まれています〜
京
恋愛
普通の女子高生、朱璃はいつのまにか異世界に迷い込んでいた。
右も左もわからない状態で偶然出会った青年にしがみついた結果、なんとかお世話になることになる。一宿一飯の恩義を返そうと懸命に生きているうちに、国の一大事に巻き込まれたり巻き込んだり。気付くと個性豊かなイケメンたちに大切に大切にされていた。
そんな乙女ゲームのようなお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















