4 / 1,289
第1話
(3)
しおりを挟む
昔から女性に言い寄られることが多いのは、この仕事に役立っているといえるだろう。しかし和彦が自分の容貌を評価している最大の理由は、一欠片でも同性に性的な興味を持っている男の目を惹きつけられるからだ。
よくわからないが、和彦からはそういう空気が立ち昇っているらしい。その空気に惹きつけられた一人が、千尋というわけだ。
「ぼくが目立つと、澤村先生の人気を奪いそうだから、ぼくの顔写真の使用は遠慮してもらおう」
「おう、よく先輩を立てる術を知ってるな。昼飯を奢ってやる」
勢いよく立ち上がった澤村が白衣を脱ぎ、笑みをこぼしながら和彦も倣う。ありがたく、今日の昼食は奢ってもらうことにした。
さっそく二人が医局を出ようとしたとき、背後から呼び止められた。
「佐伯先生、電話だよ」
澤村に待ってもらい、和彦は一番近くの電話に出る。
「お電話代わりました、佐伯です」
咄嗟に和彦の頭に浮かんだのは、午後から手術をすることになっている女性患者の存在だった。やはり、今日の手術は延期したいと言ってきたのだろう。そう思ったのだが――。
電話から返ってくる声はなかった。このとき和彦の中に、ヒヤリとした感覚が駆け抜ける。
またか、という言葉が頭に浮かんだ。
また、無言電話がかかってきた。この一週間ほど、和彦の元には無言電話が毎日かかってきている。不気味なのは、その無言電話が病院にだけかかってくるわけではないことだ。
最初にかかってきたのは、自宅の固定電話だった。次が、携帯電話。そして病院に。まるでローテーションでも組んでいるように、毎日一回、こうして違う電話にかかってくる。
「もしもし?」
念のため呼びかけて返答がないことを確かめると、すぐに受話器を置く。澤村を促して、足早に医局から離れた。
春の暖かな陽気を浴びながら、せっかくのテラスでの昼食だというのに、和彦は憂うつだった。昼食に出かける前にかかってきた無言電話のせいだ。
無意識のうちに周囲に鋭い視線を向け、他のテーブルの客や、カフェの外を行き交う人たちを観察する。無言電話の犯人が、どこかで自分を観察しているようで落ち着かない。
澤村の話に適当な相槌を打ちながら、頬杖をついた和彦は犯人の心当たりがないか、じっと考えていた。人から恨まれるほど深い人つき合いはしていないし、唯一何かありそうな仕事絡みにしても、クリニックでの人間関係に問題はない。手術の結果が気に入らない患者が恨んで、というパターンが一番ありえそうなのだが、生憎、和彦が手がけた手術に関して、それらしいクレームは入っていなかった。
ただ、逆恨みで、密かに和彦を憎んでいる〈誰か〉となると、見当をつけるのはお手上げだ。
順風満帆な日常において、ほんのわずかについたシミのようだった無言電話が、まさか一週間ほどで、ここまで危機を感じるものになるとは予想外だった。
和彦がそっとため息をついたとき、ふいに傍らに誰かが立つ。
「――今日は調子が悪そうですね、佐伯先生」
丁寧で柔らかな口調で話しかけられ、条件反射で和彦は姿勢を正す。視線を上げると、テーブルの横にこのカフェのウェイターが立っていた。日焼けした端正な顔に、人好きのする笑顔を浮かべている。この笑顔見たさに常連になる女性客もいるだろう。
三日前、ベッドの中で和彦を貪り尽くしながら、満足そうに浮かべていた笑顔とは大違いだ――。
「佐伯先生は、アレの日なんだ」
品のない受け答えをした澤村の足を、テーブルの下で軽く蹴りつける。大げさに痛がる澤村を見てウェイター――千尋が小さく笑い声を洩らす。白と黒を基調にした上品な制服を着ていると、笑い方まで品がよくなるらしい。
千尋を見上げながら、和彦はそんなことを考える。和彦も最初は、千尋のこんな表情にすっかり騙されたのだ。まさか、あんなに〈やんちゃ〉だったとは、想定外だ。もちろん、いい意味で。
和彦の視線に気づいたのか、サービスというには過剰すぎる色気たっぷりの流し目を千尋が向けてくる。
「コーヒーのお代わりはいかがですか?」
そう問いかけられ、頷いた和彦は空になったカップを千尋のほうに動かす。
「長嶺くんに妙に懐かれてるな、佐伯先生」
千尋が次のテーブルに移動すると、澤村が笑いながら言った。すらりとした千尋の後ろ姿を漫然と目で追っていた和彦は、露骨に顔をしかめて見せる。ちなみに長嶺というのが、千尋の姓だ。
「犬っころだな。彼を見ていると、くしゃくしゃと頭を撫で回したくなる」
「あはは、尻尾振って、大喜びしそうだな」
実際千尋は、似たようなものだ。甘えるのが好き、甘やかされるのが大好き。そのくせ、和彦にのしかかりながら、野性味たっぷりの獣に変わる。
「だけど、あの手のタイプはモテるだろうな。女の母性本能をくすぐるというか」
「かもな。このカフェで働き始めたときは危なっかしく見えたが、慣れてくると、客の扱いが上手い。それを勘違いする女性客がいても不思議じゃないだろうな」
千尋が、和彦が行きつけとしているこのカフェでアルバイトとして働き始めたのは、三か月ほど前だ。店が暇になるとさりげなく和彦に話しかけてきて、美容外科医だとわかると、親しげに『佐伯先生』と呼ぶようになった。そして携帯電話の番号を渡され、気まぐれに連絡を取り、外で頻繁に会うようになった。
体の関係を持ってから、そろそろ二か月になるが、二人の関係はきわめて良好だ。体の相性はそれ以上。
千尋は、いままで和彦が関係を持った誰よりも、刺激的で魅力的な遊び相手だ。面倒が起こればすぐに関係を断つつもりだったが、今のところそれもない。
まだ当分、千尋との関係は楽しめるだろう。
コーヒーにミルクを入れて掻き混ぜながら、和彦がそれとなく視線を向けると、先にこちらを見ていた千尋と目が合った。さりげなく、千尋は自分の左腕に手をかけた。ちょうど、タトゥーがある部分だ。
和彦は思わず、艶然とした笑みを浮かべていた。
仕事を終え、外で食事を済ませて戻ってきた和彦は車から降りると、肩に手をやる。今日は少々厄介な手術を立て続けにこなしたので、肩から腕にかけての筋肉がいまだに緊張して強張っている。
明日はクリニックは休みなので、久しぶりにスポーツジムで体を動かしてこようかと思いながら、ゆっくりと腕を回す。そうしながらマンションのエントランスに向かおうとした和彦は、扉の陰で闇に紛れるようにして立っている男の存在に気づいた。
何か確信があるわけではないが、ふいにゾクリと寒気を感じた。この瞬間頭に浮かんだのは、連日かかってくる無言電話のことだ。
和彦は男の存在に気づかないふりをして、エントランスに入ろうとしたが、突然、背後から駆け寄ってくる数人分の足音を聞いて素早く振り返る。
何もかもあっという間だった。
いつの間にか、エントランスの陰から男が飛び出してきて、和彦の側にやってくる。首筋に何かが押し当てられ、嫌な音がした。それがなんの音であるか考える前に、和彦の頭の中で閃光が弾けた。
痛みと、全身を駆け抜ける強い衝撃に、声も出せないままその場に卒倒しかけたが、寸前で誰かに体を受け止められ、一気に引きずられる。
全身が痺れて力が入らない。何かが自分の身に起きたと自覚できる程度には意識はあるのに、何もできない。
まるで荷物のように扱われ、スライドドアを開けて待っていた大型ワゴン車の後部座席に乗せられる。すぐにドアは閉められて、乱暴に車が発進した。
和彦の体はシートに押さえつけられ、車内の様子を認識する前に目隠しをされ、両手も後ろ手できつく拘束される。
このときになって和彦はようやく、自分が拉致されたのだとわかり、息も詰まるような恐怖を覚えた。
よくわからないが、和彦からはそういう空気が立ち昇っているらしい。その空気に惹きつけられた一人が、千尋というわけだ。
「ぼくが目立つと、澤村先生の人気を奪いそうだから、ぼくの顔写真の使用は遠慮してもらおう」
「おう、よく先輩を立てる術を知ってるな。昼飯を奢ってやる」
勢いよく立ち上がった澤村が白衣を脱ぎ、笑みをこぼしながら和彦も倣う。ありがたく、今日の昼食は奢ってもらうことにした。
さっそく二人が医局を出ようとしたとき、背後から呼び止められた。
「佐伯先生、電話だよ」
澤村に待ってもらい、和彦は一番近くの電話に出る。
「お電話代わりました、佐伯です」
咄嗟に和彦の頭に浮かんだのは、午後から手術をすることになっている女性患者の存在だった。やはり、今日の手術は延期したいと言ってきたのだろう。そう思ったのだが――。
電話から返ってくる声はなかった。このとき和彦の中に、ヒヤリとした感覚が駆け抜ける。
またか、という言葉が頭に浮かんだ。
また、無言電話がかかってきた。この一週間ほど、和彦の元には無言電話が毎日かかってきている。不気味なのは、その無言電話が病院にだけかかってくるわけではないことだ。
最初にかかってきたのは、自宅の固定電話だった。次が、携帯電話。そして病院に。まるでローテーションでも組んでいるように、毎日一回、こうして違う電話にかかってくる。
「もしもし?」
念のため呼びかけて返答がないことを確かめると、すぐに受話器を置く。澤村を促して、足早に医局から離れた。
春の暖かな陽気を浴びながら、せっかくのテラスでの昼食だというのに、和彦は憂うつだった。昼食に出かける前にかかってきた無言電話のせいだ。
無意識のうちに周囲に鋭い視線を向け、他のテーブルの客や、カフェの外を行き交う人たちを観察する。無言電話の犯人が、どこかで自分を観察しているようで落ち着かない。
澤村の話に適当な相槌を打ちながら、頬杖をついた和彦は犯人の心当たりがないか、じっと考えていた。人から恨まれるほど深い人つき合いはしていないし、唯一何かありそうな仕事絡みにしても、クリニックでの人間関係に問題はない。手術の結果が気に入らない患者が恨んで、というパターンが一番ありえそうなのだが、生憎、和彦が手がけた手術に関して、それらしいクレームは入っていなかった。
ただ、逆恨みで、密かに和彦を憎んでいる〈誰か〉となると、見当をつけるのはお手上げだ。
順風満帆な日常において、ほんのわずかについたシミのようだった無言電話が、まさか一週間ほどで、ここまで危機を感じるものになるとは予想外だった。
和彦がそっとため息をついたとき、ふいに傍らに誰かが立つ。
「――今日は調子が悪そうですね、佐伯先生」
丁寧で柔らかな口調で話しかけられ、条件反射で和彦は姿勢を正す。視線を上げると、テーブルの横にこのカフェのウェイターが立っていた。日焼けした端正な顔に、人好きのする笑顔を浮かべている。この笑顔見たさに常連になる女性客もいるだろう。
三日前、ベッドの中で和彦を貪り尽くしながら、満足そうに浮かべていた笑顔とは大違いだ――。
「佐伯先生は、アレの日なんだ」
品のない受け答えをした澤村の足を、テーブルの下で軽く蹴りつける。大げさに痛がる澤村を見てウェイター――千尋が小さく笑い声を洩らす。白と黒を基調にした上品な制服を着ていると、笑い方まで品がよくなるらしい。
千尋を見上げながら、和彦はそんなことを考える。和彦も最初は、千尋のこんな表情にすっかり騙されたのだ。まさか、あんなに〈やんちゃ〉だったとは、想定外だ。もちろん、いい意味で。
和彦の視線に気づいたのか、サービスというには過剰すぎる色気たっぷりの流し目を千尋が向けてくる。
「コーヒーのお代わりはいかがですか?」
そう問いかけられ、頷いた和彦は空になったカップを千尋のほうに動かす。
「長嶺くんに妙に懐かれてるな、佐伯先生」
千尋が次のテーブルに移動すると、澤村が笑いながら言った。すらりとした千尋の後ろ姿を漫然と目で追っていた和彦は、露骨に顔をしかめて見せる。ちなみに長嶺というのが、千尋の姓だ。
「犬っころだな。彼を見ていると、くしゃくしゃと頭を撫で回したくなる」
「あはは、尻尾振って、大喜びしそうだな」
実際千尋は、似たようなものだ。甘えるのが好き、甘やかされるのが大好き。そのくせ、和彦にのしかかりながら、野性味たっぷりの獣に変わる。
「だけど、あの手のタイプはモテるだろうな。女の母性本能をくすぐるというか」
「かもな。このカフェで働き始めたときは危なっかしく見えたが、慣れてくると、客の扱いが上手い。それを勘違いする女性客がいても不思議じゃないだろうな」
千尋が、和彦が行きつけとしているこのカフェでアルバイトとして働き始めたのは、三か月ほど前だ。店が暇になるとさりげなく和彦に話しかけてきて、美容外科医だとわかると、親しげに『佐伯先生』と呼ぶようになった。そして携帯電話の番号を渡され、気まぐれに連絡を取り、外で頻繁に会うようになった。
体の関係を持ってから、そろそろ二か月になるが、二人の関係はきわめて良好だ。体の相性はそれ以上。
千尋は、いままで和彦が関係を持った誰よりも、刺激的で魅力的な遊び相手だ。面倒が起こればすぐに関係を断つつもりだったが、今のところそれもない。
まだ当分、千尋との関係は楽しめるだろう。
コーヒーにミルクを入れて掻き混ぜながら、和彦がそれとなく視線を向けると、先にこちらを見ていた千尋と目が合った。さりげなく、千尋は自分の左腕に手をかけた。ちょうど、タトゥーがある部分だ。
和彦は思わず、艶然とした笑みを浮かべていた。
仕事を終え、外で食事を済ませて戻ってきた和彦は車から降りると、肩に手をやる。今日は少々厄介な手術を立て続けにこなしたので、肩から腕にかけての筋肉がいまだに緊張して強張っている。
明日はクリニックは休みなので、久しぶりにスポーツジムで体を動かしてこようかと思いながら、ゆっくりと腕を回す。そうしながらマンションのエントランスに向かおうとした和彦は、扉の陰で闇に紛れるようにして立っている男の存在に気づいた。
何か確信があるわけではないが、ふいにゾクリと寒気を感じた。この瞬間頭に浮かんだのは、連日かかってくる無言電話のことだ。
和彦は男の存在に気づかないふりをして、エントランスに入ろうとしたが、突然、背後から駆け寄ってくる数人分の足音を聞いて素早く振り返る。
何もかもあっという間だった。
いつの間にか、エントランスの陰から男が飛び出してきて、和彦の側にやってくる。首筋に何かが押し当てられ、嫌な音がした。それがなんの音であるか考える前に、和彦の頭の中で閃光が弾けた。
痛みと、全身を駆け抜ける強い衝撃に、声も出せないままその場に卒倒しかけたが、寸前で誰かに体を受け止められ、一気に引きずられる。
全身が痺れて力が入らない。何かが自分の身に起きたと自覚できる程度には意識はあるのに、何もできない。
まるで荷物のように扱われ、スライドドアを開けて待っていた大型ワゴン車の後部座席に乗せられる。すぐにドアは閉められて、乱暴に車が発進した。
和彦の体はシートに押さえつけられ、車内の様子を認識する前に目隠しをされ、両手も後ろ手できつく拘束される。
このときになって和彦はようやく、自分が拉致されたのだとわかり、息も詰まるような恐怖を覚えた。
125
あなたにおすすめの小説

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

結婚初夜に相手が舌打ちして寝室出て行こうとした
紫
BL
十数年間続いた王国と帝国の戦争の終結と和平の形として、元敵国の皇帝と結婚することになったカイル。
実家にはもう帰ってくるなと言われるし、結婚相手は心底嫌そうに舌打ちしてくるし、マジ最悪ってところから始まる話。
オメガバースでオメガの立場が低い世界
こんなあらすじとタイトルですが、主人公が可哀そうって感じは全然ないです
強くたくましくメンタルがオリハルコンな主人公です
主人公は耐える我慢する許す許容するということがあんまり出来ない人間です
倫理観もちょっと薄いです
というか、他人の事を自分と同じ人間だと思ってない部分があります
※この主人公は受けです

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

君に望むは僕の弔辞
爺誤
BL
僕は生まれつき身体が弱かった。父の期待に応えられなかった僕は屋敷のなかで打ち捨てられて、早く死んでしまいたいばかりだった。姉の成人で賑わう屋敷のなか、鍵のかけられた部屋で悲しみに押しつぶされかけた僕は、迷い込んだ客人に外に出してもらった。そこで自分の可能性を知り、希望を抱いた……。
全9話
匂わせBL(エ◻︎なし)。死ネタ注意
表紙はあいえだ様!!
小説家になろうにも投稿
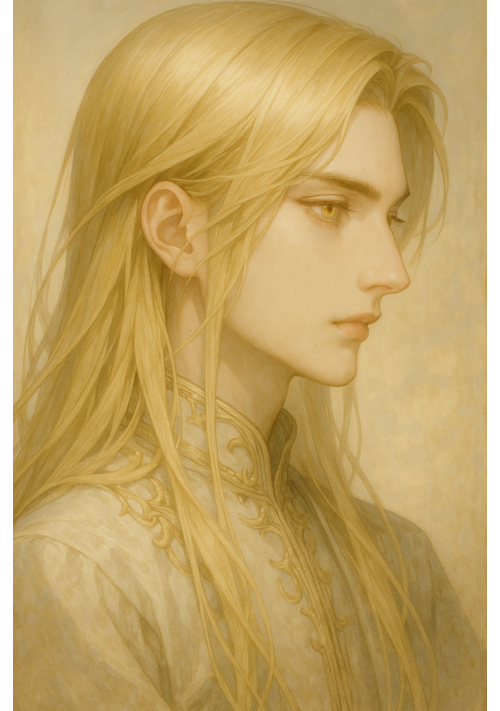
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















