510 / 1,289
第23話
(21)
しおりを挟む
和彦はタクシーで移動しながら、外にどれだけの数の警官や機動隊が動員されているか、自分の目で見ることができた。まるで威圧するように、塀の周囲を数メートル間隔で機動隊員が立っており、警官が往来で容赦なく所持品と身体検査を行い、花見会の出席者たちはおとなしく従っていた。
自分があんなに目に遭っていたらと考えるだけで、和彦は底知れない不安感に襲われる。今日は大丈夫だったとしても、いつかは、佐伯和彦という人間が何者なのか、警察に知られるかもしれないのだ。
靴を脱いで式台に上がった和彦は、改めて玄関前へと視線を向ける。玄関は開け放たれているのに、正面に据えられた門が頑なに閉ざされているというのは、不思議な感覚を与えてくるのだ。何より、門を内側から守っているのはダークスーツ姿の男たちで、門の外に立つのは警察という現実が、裏と表の世界の境界線を示していると感じる。
心の中に入り込もうとした何かを振り切るように踵を返し、和彦は男についていく。
案内されたのは、こじんまりとした和室だった。外からたっぷりの陽射しが差し込んでいるため室内は明るく、何より、窓から見える景色が贅沢なほど素晴らしい。生い茂った木々の間から池が見え、そこにかかる小さな橋の風情も相まって、まるで風景画のようだ。
「部屋の外にうちの者を立たせていますから、安心してお寛ぎください。会長が庭に出られるときに、声をおかけしますから」
わかりましたと和彦が答えると、男は一礼して障子を閉めた。
一人になって肩から力を抜いた和彦は、室内を見回す。ハンガーラックにはダークスーツ一式が掛けられていた。いつ必要になるかわからないものの賢吾に言われるまま仕立ててもらい、長嶺の本宅に置いてあったのだ。この先、身につける機会が増えるのかもしれない。
ゆっくりするのは後回しにして、とにかく着替えることにする。
ダークスーツを腕にかけたところで和彦は、この部屋にあるのは姿見ではなく、鏡台であることに気づいた。置かれた化粧箱や手鏡、部屋にさりげなく飾られた小物などから推測するに、どうやらこの部屋は、普段は女性の利用を主としているようだ。
自分の置かれた立場もあって、何か意味はあるのだろうかと深読みをしたくなるのは、自虐に近い感情ゆえだ。和彦は、鏡に映る難しい顔をした男を一瞥して、ジャケットのボタンに指をかけた。
柔らかな芝を踏みしめて歩いているという感覚が、まるでなかった。それどころか、手足がきちんと動いているのかすら、自分で認識できない。
緊張のあまり気分が悪くなりそうだと、荒く息を吐き出した和彦は無意識に喉元に手をやる。いつも通り締めたはずのネクタイを苦しく感じるが、当然、この状況で緩めることなどできるはずもない。
伏し目がちだった和彦は、思いきって視線を上げる。数歩先を歩いているのは、上背のある痩身の体を紋付羽織袴で包んだ総和会会長だ。黒羽二重の黒が豊かな白髪をより際立たせるが、だからといって老いを印象付けられることはない。そういう次元で、目の前の人物を捉えてはいけないのだ。
泰然と歩く後ろ姿は、まるで散歩でもしているようでもあるが、向けられた背に一体何が棲んでいるか知っていると、畏怖と畏敬の念を抱くだけだ。
それだけではない。和彦はさきほどから、獣のような野蛮で荒々しい気配を隣から感じていた。大柄な体をダークスーツで包んだ南郷だ。
庭に出る守光の同行者は、和彦と南郷の二人しかいない。せっかくの花見で、無粋に護衛を引き連れて歩くわけにはいかない、という守光自身の言葉があったためだが、なぜ自分がと、和彦は自問せずにはいられない。
「――肝が据わっていると評判の先生も、さすがに緊張しているようだな」
唐突に南郷が、揶揄するように話しかけてくる。和彦は冷ややかな一瞥を向けてから、頭上に咲く桜の花を見上げる。ちくちくと神経を刺激してくるような南郷の言葉に、わざわざ応える気にはなれなかった。南郷は機嫌を損ねたふうもなく、聞こえよがしに呟く。
「素っ気ない……」
率直に言って、和彦は南郷が苦手だ。鷹津も大概嫌な男だとは思うが、あの男の場合、言動が明け透けで遠慮がない分、和彦も同様に遠慮なく言い返せるため、割り切ってつき合う分にはストレスが少ない。何より刑事という肩書きが、狂犬のようなあの男の歯止めとなっている。だからこそ、和彦の番犬でもあるのだ。
一方の南郷は――とにかく得体が知れない。和彦の神経を逆撫でるような言動を取りながら、紳士的な姿勢だけは崩さない。しかし、獣のような本性が透けて見える。おそらく本人は計算したうえで、和彦の反応を楽しんでいるはずだ。
自分があんなに目に遭っていたらと考えるだけで、和彦は底知れない不安感に襲われる。今日は大丈夫だったとしても、いつかは、佐伯和彦という人間が何者なのか、警察に知られるかもしれないのだ。
靴を脱いで式台に上がった和彦は、改めて玄関前へと視線を向ける。玄関は開け放たれているのに、正面に据えられた門が頑なに閉ざされているというのは、不思議な感覚を与えてくるのだ。何より、門を内側から守っているのはダークスーツ姿の男たちで、門の外に立つのは警察という現実が、裏と表の世界の境界線を示していると感じる。
心の中に入り込もうとした何かを振り切るように踵を返し、和彦は男についていく。
案内されたのは、こじんまりとした和室だった。外からたっぷりの陽射しが差し込んでいるため室内は明るく、何より、窓から見える景色が贅沢なほど素晴らしい。生い茂った木々の間から池が見え、そこにかかる小さな橋の風情も相まって、まるで風景画のようだ。
「部屋の外にうちの者を立たせていますから、安心してお寛ぎください。会長が庭に出られるときに、声をおかけしますから」
わかりましたと和彦が答えると、男は一礼して障子を閉めた。
一人になって肩から力を抜いた和彦は、室内を見回す。ハンガーラックにはダークスーツ一式が掛けられていた。いつ必要になるかわからないものの賢吾に言われるまま仕立ててもらい、長嶺の本宅に置いてあったのだ。この先、身につける機会が増えるのかもしれない。
ゆっくりするのは後回しにして、とにかく着替えることにする。
ダークスーツを腕にかけたところで和彦は、この部屋にあるのは姿見ではなく、鏡台であることに気づいた。置かれた化粧箱や手鏡、部屋にさりげなく飾られた小物などから推測するに、どうやらこの部屋は、普段は女性の利用を主としているようだ。
自分の置かれた立場もあって、何か意味はあるのだろうかと深読みをしたくなるのは、自虐に近い感情ゆえだ。和彦は、鏡に映る難しい顔をした男を一瞥して、ジャケットのボタンに指をかけた。
柔らかな芝を踏みしめて歩いているという感覚が、まるでなかった。それどころか、手足がきちんと動いているのかすら、自分で認識できない。
緊張のあまり気分が悪くなりそうだと、荒く息を吐き出した和彦は無意識に喉元に手をやる。いつも通り締めたはずのネクタイを苦しく感じるが、当然、この状況で緩めることなどできるはずもない。
伏し目がちだった和彦は、思いきって視線を上げる。数歩先を歩いているのは、上背のある痩身の体を紋付羽織袴で包んだ総和会会長だ。黒羽二重の黒が豊かな白髪をより際立たせるが、だからといって老いを印象付けられることはない。そういう次元で、目の前の人物を捉えてはいけないのだ。
泰然と歩く後ろ姿は、まるで散歩でもしているようでもあるが、向けられた背に一体何が棲んでいるか知っていると、畏怖と畏敬の念を抱くだけだ。
それだけではない。和彦はさきほどから、獣のような野蛮で荒々しい気配を隣から感じていた。大柄な体をダークスーツで包んだ南郷だ。
庭に出る守光の同行者は、和彦と南郷の二人しかいない。せっかくの花見で、無粋に護衛を引き連れて歩くわけにはいかない、という守光自身の言葉があったためだが、なぜ自分がと、和彦は自問せずにはいられない。
「――肝が据わっていると評判の先生も、さすがに緊張しているようだな」
唐突に南郷が、揶揄するように話しかけてくる。和彦は冷ややかな一瞥を向けてから、頭上に咲く桜の花を見上げる。ちくちくと神経を刺激してくるような南郷の言葉に、わざわざ応える気にはなれなかった。南郷は機嫌を損ねたふうもなく、聞こえよがしに呟く。
「素っ気ない……」
率直に言って、和彦は南郷が苦手だ。鷹津も大概嫌な男だとは思うが、あの男の場合、言動が明け透けで遠慮がない分、和彦も同様に遠慮なく言い返せるため、割り切ってつき合う分にはストレスが少ない。何より刑事という肩書きが、狂犬のようなあの男の歯止めとなっている。だからこそ、和彦の番犬でもあるのだ。
一方の南郷は――とにかく得体が知れない。和彦の神経を逆撫でるような言動を取りながら、紳士的な姿勢だけは崩さない。しかし、獣のような本性が透けて見える。おそらく本人は計算したうえで、和彦の反応を楽しんでいるはずだ。
79
あなたにおすすめの小説

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

結婚初夜に相手が舌打ちして寝室出て行こうとした
紫
BL
十数年間続いた王国と帝国の戦争の終結と和平の形として、元敵国の皇帝と結婚することになったカイル。
実家にはもう帰ってくるなと言われるし、結婚相手は心底嫌そうに舌打ちしてくるし、マジ最悪ってところから始まる話。
オメガバースでオメガの立場が低い世界
こんなあらすじとタイトルですが、主人公が可哀そうって感じは全然ないです
強くたくましくメンタルがオリハルコンな主人公です
主人公は耐える我慢する許す許容するということがあんまり出来ない人間です
倫理観もちょっと薄いです
というか、他人の事を自分と同じ人間だと思ってない部分があります
※この主人公は受けです

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
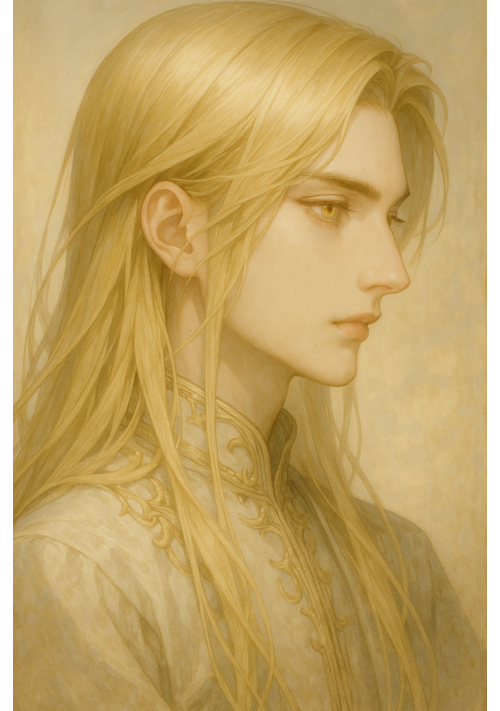
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















