717 / 1,289
第31話
(9)
しおりを挟む
「父さんが失いたくないのは、〈佐伯和彦〉だ。手に入れるために、あの父さんが奔走したぐらいだそうだし」
『どうして――』
英俊が何か言いかけたが、和彦のペースに巻き込まれていることに気づいたのだろう。一呼吸間に、いつもの落ち着きを取り戻していた。
『今、お前の面倒を見ているのが、どれだけ頼りになる人間かは知らないが、ずいぶん強気だな。だが――父さんは甘くはないぞ。わたしと違ってな』
さきほどの英俊の宣言めいた言葉も相まって、不穏な影に足首を掴まれたような感覚に襲われる。英俊は、苦し紛れのこけおどしなどしない。こうも俊哉の存在を仄めかすということは、何かが、あるのだ。
『お前の発言は、しっかりと父さんに伝えておく』
「……携帯の番号は、替えるから」
『別に、替えなくていいぞ。わたしはもう、かけるつもりはない』
唐突に電話が切られる。和彦は、耳元から引き剥がすように携帯電話を離すと、そのまま少しの間、ぼうっとしてしまう。我に返ったのは、運転手の男に呼ばれたからだ。
「――佐伯先生」
ハッとした和彦は、前方を見る。
「到着しました」
車は、総和会本部の前に停まっていた。
朝の時点で和彦は、漠然とした不安は感じていたのだ。総和会は、自分を自宅マンションに送り届けるつもりはないのではないか、と。その不安は的中したというわけだ。
和彦は手にしていた携帯電話の電源を切ると、アタッシェケースを持って車を降りる。ここで抗議をするほどの気力は、和彦には残っていなかった。
身の置き場がないとは、まさに今の自分の状況を指すのだろう。
ダイニングのイスに腰掛けた和彦は、手持ち無沙汰から鎮痛剤の箱を手の中で弄ぶ。夕食後に飲んだ鎮痛剤はとっくに効き目が表れ、今のところ頭痛は治まっている。英俊と話して興奮したせいか、一時は吐き気がするほどひどかったのだ。
風邪の症状が出ているわけでもないので、たっぷり睡眠を取れば、さほど気にするほどでもないはずだ。そう、考えていたのだが――。
本来であれば、自宅マンションで一人、ゆっくりと落ち着いた時間を過ごしている頃なのだろうが、和彦が現在いるのは、総和会本部内にある守光の住居だ。主である守光は、病院に検査入院しているというのに、なぜか和彦が、その守光の住居に今晩も泊まることになっていた。
ぜひお世話させてくださいと、柔らかながら、否とは言わせない口調で吾川に押し切られたのだ。守光の住居を使わせてもらえるということは、それだけ信用されているのだと思うべきかもしれないが、和彦には、ここまで厚遇されることが、かえって怖い。どんどん総和会に取り込まれていると感じ、おそらくそういう事態になっているのだろう。
何より怖いのは、総和会側の思惑が透けて見えていながらも、和彦は拒むことができないということだ。今晩は帰りたいと本気で訴えるなら、長嶺組組長に迎えに来てもらうしかない。当然、そんなことができるはずもないのだが。
「――佐伯先生」
背後から声をかけられ振り返ると、吾川が立っていた。普段、守光のためだけに仕えているであろう男は、和彦に対しても細やかな気遣いを見せてくれ、積極的に話しかけてくるでもなく、夕食や風呂の準備を整え、和彦が部屋を移動している間に片付けを済ませ、己の存在を意識させまいと努めている。おかげで和彦も、吾川と同じ空間にいることは苦痛ではない。
「床を延べましたから、いつでもお休みください。昨夜からあまり眠れなかったでしょう。わたしは同じ階におりますから、ご用があるときは、遠慮なく内線でお呼びください」
「あっ、はい、ありがとうございます」
慌てて立ち上がった和彦が頭を下げると、吾川も丁寧に一礼してから立ち去る。玄関のドアが閉まる音がした途端、一気に気が緩んだ。起きているのもつらいほど、体に疲労が溜まっていた。
和彦はダイニングの電気を消すと、ふらふらとした足取りで客間に入り、ほっと一息をつく。
何げなく床の間に目を向ければ、水辺で泳いでいる金魚を描いた掛け軸が掛かっていた。涼風がこちらにまで届きそうな爽やかな画に、少しの間和彦は見入ってしまう。もう夏なのだと、唐突に実感していた。
ようやく我に返ると、ハンガーにかけたジャケットのポケットから、携帯電話を取り出す。
千尋には夕方、もう一回連絡しており、守光は一通りの検査を終えて、病室で安静にしながら心電図を測っていると聞いた。千尋自身は長嶺の本宅に戻っており、新たな着信も残っていないことから、心配する事態にはなっていないようだ。
もう一台の携帯電話は、ポケットから出すことさえしなかった。帰路につく車中での英俊との会話を思い返すと、触る気にもなれないのだ。
『どうして――』
英俊が何か言いかけたが、和彦のペースに巻き込まれていることに気づいたのだろう。一呼吸間に、いつもの落ち着きを取り戻していた。
『今、お前の面倒を見ているのが、どれだけ頼りになる人間かは知らないが、ずいぶん強気だな。だが――父さんは甘くはないぞ。わたしと違ってな』
さきほどの英俊の宣言めいた言葉も相まって、不穏な影に足首を掴まれたような感覚に襲われる。英俊は、苦し紛れのこけおどしなどしない。こうも俊哉の存在を仄めかすということは、何かが、あるのだ。
『お前の発言は、しっかりと父さんに伝えておく』
「……携帯の番号は、替えるから」
『別に、替えなくていいぞ。わたしはもう、かけるつもりはない』
唐突に電話が切られる。和彦は、耳元から引き剥がすように携帯電話を離すと、そのまま少しの間、ぼうっとしてしまう。我に返ったのは、運転手の男に呼ばれたからだ。
「――佐伯先生」
ハッとした和彦は、前方を見る。
「到着しました」
車は、総和会本部の前に停まっていた。
朝の時点で和彦は、漠然とした不安は感じていたのだ。総和会は、自分を自宅マンションに送り届けるつもりはないのではないか、と。その不安は的中したというわけだ。
和彦は手にしていた携帯電話の電源を切ると、アタッシェケースを持って車を降りる。ここで抗議をするほどの気力は、和彦には残っていなかった。
身の置き場がないとは、まさに今の自分の状況を指すのだろう。
ダイニングのイスに腰掛けた和彦は、手持ち無沙汰から鎮痛剤の箱を手の中で弄ぶ。夕食後に飲んだ鎮痛剤はとっくに効き目が表れ、今のところ頭痛は治まっている。英俊と話して興奮したせいか、一時は吐き気がするほどひどかったのだ。
風邪の症状が出ているわけでもないので、たっぷり睡眠を取れば、さほど気にするほどでもないはずだ。そう、考えていたのだが――。
本来であれば、自宅マンションで一人、ゆっくりと落ち着いた時間を過ごしている頃なのだろうが、和彦が現在いるのは、総和会本部内にある守光の住居だ。主である守光は、病院に検査入院しているというのに、なぜか和彦が、その守光の住居に今晩も泊まることになっていた。
ぜひお世話させてくださいと、柔らかながら、否とは言わせない口調で吾川に押し切られたのだ。守光の住居を使わせてもらえるということは、それだけ信用されているのだと思うべきかもしれないが、和彦には、ここまで厚遇されることが、かえって怖い。どんどん総和会に取り込まれていると感じ、おそらくそういう事態になっているのだろう。
何より怖いのは、総和会側の思惑が透けて見えていながらも、和彦は拒むことができないということだ。今晩は帰りたいと本気で訴えるなら、長嶺組組長に迎えに来てもらうしかない。当然、そんなことができるはずもないのだが。
「――佐伯先生」
背後から声をかけられ振り返ると、吾川が立っていた。普段、守光のためだけに仕えているであろう男は、和彦に対しても細やかな気遣いを見せてくれ、積極的に話しかけてくるでもなく、夕食や風呂の準備を整え、和彦が部屋を移動している間に片付けを済ませ、己の存在を意識させまいと努めている。おかげで和彦も、吾川と同じ空間にいることは苦痛ではない。
「床を延べましたから、いつでもお休みください。昨夜からあまり眠れなかったでしょう。わたしは同じ階におりますから、ご用があるときは、遠慮なく内線でお呼びください」
「あっ、はい、ありがとうございます」
慌てて立ち上がった和彦が頭を下げると、吾川も丁寧に一礼してから立ち去る。玄関のドアが閉まる音がした途端、一気に気が緩んだ。起きているのもつらいほど、体に疲労が溜まっていた。
和彦はダイニングの電気を消すと、ふらふらとした足取りで客間に入り、ほっと一息をつく。
何げなく床の間に目を向ければ、水辺で泳いでいる金魚を描いた掛け軸が掛かっていた。涼風がこちらにまで届きそうな爽やかな画に、少しの間和彦は見入ってしまう。もう夏なのだと、唐突に実感していた。
ようやく我に返ると、ハンガーにかけたジャケットのポケットから、携帯電話を取り出す。
千尋には夕方、もう一回連絡しており、守光は一通りの検査を終えて、病室で安静にしながら心電図を測っていると聞いた。千尋自身は長嶺の本宅に戻っており、新たな着信も残っていないことから、心配する事態にはなっていないようだ。
もう一台の携帯電話は、ポケットから出すことさえしなかった。帰路につく車中での英俊との会話を思い返すと、触る気にもなれないのだ。
60
あなたにおすすめの小説

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。


奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

オム・ファタールと無いものねだり
狗空堂
BL
この世の全てが手に入る者たちが、永遠に手に入れられないたった一つのものの話。
前野の血を引く人間は、人を良くも悪くもぐちゃぐちゃにする。その血の呪いのせいで、後田宗介の主人兼親友である前野篤志はトラブルに巻き込まれてばかり。
この度編入した金持ち全寮制の男子校では、学園を牽引する眉目秀麗で優秀な生徒ばかり惹きつけて学内風紀を乱す日々。どうやら篤志の一挙手一投足は『大衆に求められすぎる』天才たちの心に刺さって抜けないらしい。
天才たちは蟻の如く篤志に群がるし、それを快く思わない天才たちのファンからはやっかみを買うし、でも主人は毎日能天気だし。
そんな主人を全てのものから護る為、今日も宗介は全方向に噛み付きながら学生生活を奔走する。
これは、天才の影に隠れたとるに足らない凡人が、凡人なりに走り続けて少しずつ認められ愛されていく話。
2025.10.30 第13回BL大賞に参加しています。応援していただけると嬉しいです。
※王道学園の脇役受け。
※主人公は従者の方です。
※序盤は主人の方が大勢に好かれています。
※嫌われ(?)→愛されですが、全員が従者を愛すわけではありません。
※呪いとかが平然と存在しているので若干ファンタジーです。
※pixivでも掲載しています。
色々と初めてなので、至らぬ点がありましたらご指摘いただけますと幸いです。
いいねやコメントは頂けましたら嬉しくて踊ります。
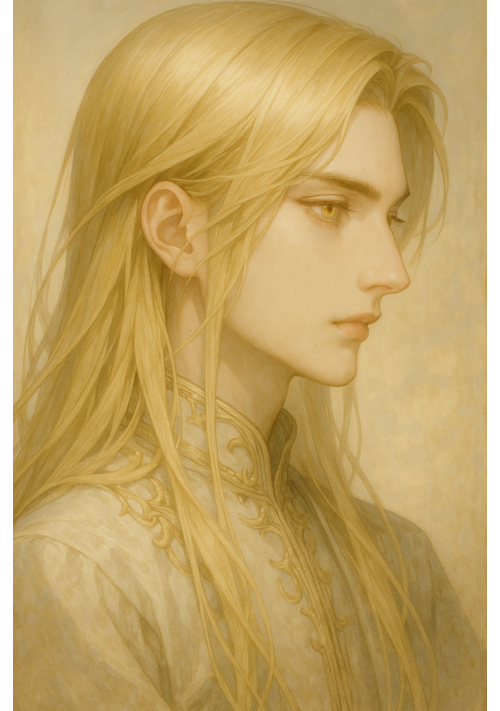
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















