900 / 1,289
第37話
(12)
しおりを挟む
自分は被害者どころか、鷹津の共犯者だ。
苦々しさを噛み締めながら和彦は、自身に言い聞かせる。物騒な男たちに守られる日常生活を取り戻しながらも、まるで棘が刺さっているかのようにときおり痛みを発するのは、俊哉の存在だ。
接触したことを口外しないのは誰のためなのか、すでにもう和彦にもわからなくなっていた。今の生活を失いたくないと思う一方で、沈黙を続けることは、長嶺の男たちを危険に晒す。だが話してしまえば、鷹津に対する追跡は厳しさを増すかもしれない。
思索の迷路に入り込みそうになったところで、中嶋が立ち上がった気配にハッとする。
「ツマミがなくなってきたんで、持ってきますね」
空いた皿を手に中嶋の姿がキッチンに消えると、一度はグラスに視線を落とした和彦だが、すぐにうかがうように秦を見る。物言いたげな和彦の様子にとっくに気づいていたらしく、首を傾げて笑いかけられた。
「中嶋がいると聞きにくいことがあるんでしょう、先生」
「……察しがいいな」
「あいつはあいつで、聞いた以上、総和会に報告せざるをえなくなりますから、わざと席を外したんだと思いますよ」
そういうことかと、ちらりとキッチンのほうを見遣る。
ためらったのはわずかな間で、和彦は声を抑えて秦に尋ねた。
「――鷹津から、何か聞いてないのか?」
「何か、とは……」
「なんでも。どうして、あんな行動を取ったのか。警察を辞めてどうするのか。……どこに行くのか」
秦は小さく首を横に振る。
「皆さんから聞かれましたが、わたしは何も。そもそも、大事なことを打ち明けてもらえるほど、わたしは鷹津さんに信用されてはいませんでしたから」
「でも、仲はよさそうに見えた……」
和彦の率直な感想に、秦はなんとも複雑そうな笑みを見せた。
「鷹津さんには、よくタダ酒を集られました。いつも不機嫌で、他人を一切信用してなくて、そのくせ、他人を利用する気満々で。世間一般では、〈嫌な人間〉と呼ばれるでしょうね。だけどわたしは、そういう鷹津さんをけっこう気に入ってましたよ」
「……故人を偲んでいるような言い方だな」
冗談を言ったつもりはないのだが、秦は声を上げて笑う。
「鷹津さんは大丈夫ですよ。あの人は、殺しても死なない。――何を使ってでも、自分の身を守る。そして、目的を果たす」
目的、と和彦は声に出さずに呟く。秦がじっと自分を見つめていることに気づき、ドキリとした。
「やっぱり……、何か知っているんじゃないか?」
「何も。それに、もし仮にわたしが何か知っていたとしても、先生は聞かないほうがいいでしょう。優しい先生は、隠し事が下手だ」
すでに隠し事をしているとは、口が裂けても言えない。ここで中嶋が、ハムとチーズを皿にのせて戻ってくる。
「二人でどんな話をしていたんですか? ずいぶん楽しそうでしたけど」
中嶋の言葉に、思わず和彦は秦と顔を見合わせる。
「……鷹津の思い出話を……」
「クセの強い人でしたね。俺はあまり、直接話す機会はありませんでしたが。でも、秦さんとはよく飲んでいたみたいですよ。たまに鷹津さんに頼み事もしていたみたいですし」
「飲み代として、ちょっとした仕事を頼んでいたんです」
「なんだ。タダ酒の代金はしっかり受け取っていたんじゃないか」
そんな会話を交わしていると、中嶋の携帯電話が鳴る。座ったばかりだというのに中嶋は、携帯電話の表示を確認してすぐにまた立ち上がる。仕事の電話だと言って一旦部屋を出て行ったが、三十秒もしないうちに戻ってきた。
「すみません、うちの若い奴が近くまで来ているみたいなんで、少し出てきます。すぐに戻りますから、食器とか、そのままにしておいてください」
片手を上げて応じたのは秦だった。玄関のドアが閉まる音がして、和彦はため息交じりにこぼす。
「忙しいみたいだ。……無理させたのかもな。ぼくの夜遊びのためにつき合わせたのだとしたら」
「――喜んでますよ。わたしも、中嶋も。塞ぎ込んでいた先生が、やっと立ち直ってくれたんですから。そして、夜遊びを始めた先生の様子に、総和会や長嶺組の皆さんも安心する。いいことづくめですよ」
とんでもない詭弁だなと苦笑を洩らした和彦だが、秦のほうはまじめな表情を崩さない。それがなんだかおかしくて、とうとう声を上げて笑っていた。自覚もないまま酔ってしまったのかもしれない。
顔が熱くなってきて、おしぼりを頬に当てていると、秦が立ち上がり、窓を開けた。入り込んでくる風は、涼しいというより冷たいほどだが、それが心地いい。
「先生」
ふいに秦に呼ばれる。視線を向けた先で秦は、窓の外を見ていた。手招きされ、何事かと思いながら和彦も窓に近づく。
苦々しさを噛み締めながら和彦は、自身に言い聞かせる。物騒な男たちに守られる日常生活を取り戻しながらも、まるで棘が刺さっているかのようにときおり痛みを発するのは、俊哉の存在だ。
接触したことを口外しないのは誰のためなのか、すでにもう和彦にもわからなくなっていた。今の生活を失いたくないと思う一方で、沈黙を続けることは、長嶺の男たちを危険に晒す。だが話してしまえば、鷹津に対する追跡は厳しさを増すかもしれない。
思索の迷路に入り込みそうになったところで、中嶋が立ち上がった気配にハッとする。
「ツマミがなくなってきたんで、持ってきますね」
空いた皿を手に中嶋の姿がキッチンに消えると、一度はグラスに視線を落とした和彦だが、すぐにうかがうように秦を見る。物言いたげな和彦の様子にとっくに気づいていたらしく、首を傾げて笑いかけられた。
「中嶋がいると聞きにくいことがあるんでしょう、先生」
「……察しがいいな」
「あいつはあいつで、聞いた以上、総和会に報告せざるをえなくなりますから、わざと席を外したんだと思いますよ」
そういうことかと、ちらりとキッチンのほうを見遣る。
ためらったのはわずかな間で、和彦は声を抑えて秦に尋ねた。
「――鷹津から、何か聞いてないのか?」
「何か、とは……」
「なんでも。どうして、あんな行動を取ったのか。警察を辞めてどうするのか。……どこに行くのか」
秦は小さく首を横に振る。
「皆さんから聞かれましたが、わたしは何も。そもそも、大事なことを打ち明けてもらえるほど、わたしは鷹津さんに信用されてはいませんでしたから」
「でも、仲はよさそうに見えた……」
和彦の率直な感想に、秦はなんとも複雑そうな笑みを見せた。
「鷹津さんには、よくタダ酒を集られました。いつも不機嫌で、他人を一切信用してなくて、そのくせ、他人を利用する気満々で。世間一般では、〈嫌な人間〉と呼ばれるでしょうね。だけどわたしは、そういう鷹津さんをけっこう気に入ってましたよ」
「……故人を偲んでいるような言い方だな」
冗談を言ったつもりはないのだが、秦は声を上げて笑う。
「鷹津さんは大丈夫ですよ。あの人は、殺しても死なない。――何を使ってでも、自分の身を守る。そして、目的を果たす」
目的、と和彦は声に出さずに呟く。秦がじっと自分を見つめていることに気づき、ドキリとした。
「やっぱり……、何か知っているんじゃないか?」
「何も。それに、もし仮にわたしが何か知っていたとしても、先生は聞かないほうがいいでしょう。優しい先生は、隠し事が下手だ」
すでに隠し事をしているとは、口が裂けても言えない。ここで中嶋が、ハムとチーズを皿にのせて戻ってくる。
「二人でどんな話をしていたんですか? ずいぶん楽しそうでしたけど」
中嶋の言葉に、思わず和彦は秦と顔を見合わせる。
「……鷹津の思い出話を……」
「クセの強い人でしたね。俺はあまり、直接話す機会はありませんでしたが。でも、秦さんとはよく飲んでいたみたいですよ。たまに鷹津さんに頼み事もしていたみたいですし」
「飲み代として、ちょっとした仕事を頼んでいたんです」
「なんだ。タダ酒の代金はしっかり受け取っていたんじゃないか」
そんな会話を交わしていると、中嶋の携帯電話が鳴る。座ったばかりだというのに中嶋は、携帯電話の表示を確認してすぐにまた立ち上がる。仕事の電話だと言って一旦部屋を出て行ったが、三十秒もしないうちに戻ってきた。
「すみません、うちの若い奴が近くまで来ているみたいなんで、少し出てきます。すぐに戻りますから、食器とか、そのままにしておいてください」
片手を上げて応じたのは秦だった。玄関のドアが閉まる音がして、和彦はため息交じりにこぼす。
「忙しいみたいだ。……無理させたのかもな。ぼくの夜遊びのためにつき合わせたのだとしたら」
「――喜んでますよ。わたしも、中嶋も。塞ぎ込んでいた先生が、やっと立ち直ってくれたんですから。そして、夜遊びを始めた先生の様子に、総和会や長嶺組の皆さんも安心する。いいことづくめですよ」
とんでもない詭弁だなと苦笑を洩らした和彦だが、秦のほうはまじめな表情を崩さない。それがなんだかおかしくて、とうとう声を上げて笑っていた。自覚もないまま酔ってしまったのかもしれない。
顔が熱くなってきて、おしぼりを頬に当てていると、秦が立ち上がり、窓を開けた。入り込んでくる風は、涼しいというより冷たいほどだが、それが心地いい。
「先生」
ふいに秦に呼ばれる。視線を向けた先で秦は、窓の外を見ていた。手招きされ、何事かと思いながら和彦も窓に近づく。
63
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
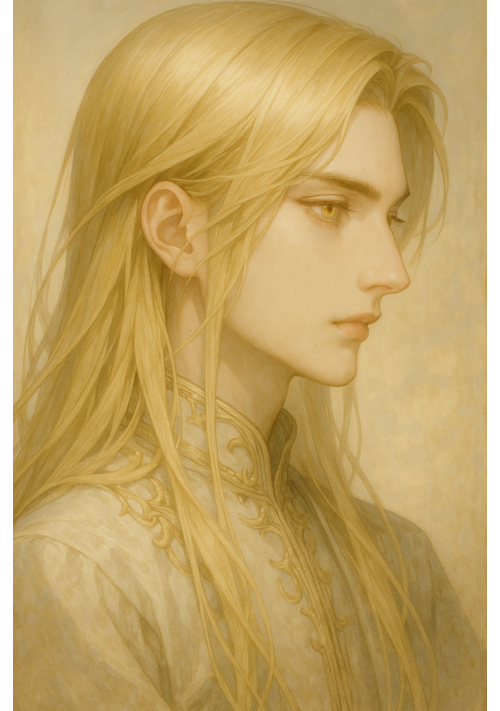
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















