914 / 1,289
第37話
(26)
しおりを挟む
床の上に積み重ねた本たちを、本棚のわずかなスペースに押し込んでいると、廊下からパタパタと足音が近づいてくる。
「先生っ」
勢いよく千尋が書斎に駆け込んでくる。せっかく着替えを用意してやったというのに、下着を穿いただけの姿だ。一体何事だと和彦は目を丸くする。
「……着替えなら出しておいただろ。というか、お前がカラスの行水なのは知ってるけど、さすがに早すぎだろ。きちんと体を洗ったのか?」
「ピッカピカに磨いてきたけど」
どうだか、と呟いた和彦の側に千尋が歩み寄ってきたかと思うと、いきなり抱き締められた。まだ湿り気を帯びた肌からは、確かに石けんの香りが立ちのぼっている。
「――ここ最近の先生は、ふっとどこかに行っちゃいそうで、怖い……というより、不安」
「何言ってるんだ」
和彦は、宥めるように千尋の背をさすろうとして、ドキリとした。自分の記憶にある、滑らかで瑞々しい肌の感触ではなかったからだ。ここで、今の千尋の背に何があるのか思い出した。
「ああ、そうか。お披露目してくれるんだったな」
和彦の言葉を受け、体を離した千尋が背をこちらに向ける。久しぶりに目にした千尋の裸の背には、一面に刺青が彫られていた。和彦がこれまで見てきた男たちの刺青とは違い、鮮やかな色が使われているわけではなく、黒一色で描かれている。しかし、墨の濃淡が使い分けられ、肌本来の色も覗いており、こういう刺青もあるのかと、息を呑む。
「墨を入れたばかりだから、まだ黒々としてるけど、時間が経ってくると、少しずつ色が落ち着いてくるんだ。オヤジみたいな青みがかった色合いが出るのは、何年かかるだろ……」
刺青の細かい部分に見入っていた和彦だが、ハッと我に返って一歩だけ後ずさる。こうすることで、千尋の背に一体何が彫られているのか、よく見ることができた。
不思議な獣だ。千尋の肌の色を活かした白い毛と、墨で塗りたくるように彫られた部分が黒い毛として表現され、それが獣の毛並みと柄を巧みに表している。獣は丸い目を見開き、牙を剥き出しにして、何かを威嚇しているようだった。その理由はおそらく、獣の体にたおやかそうな腕を回し、艶めかしい表情で寄り添っている人間を守るためだろう。人一人を背に乗せられそうな大きな体躯は、それが可能だと思わせる力強さを漲らせている。
和彦の顔が知らず知らずのうちに熱くなってくる。獣に寄り添っているのは女かと思ったが、そうではないと気づいたのだ。はだけた着物の胸元に膨らみはなく、裾が大きく捲れ上がって露わになったふくらはぎから腿のラインは、明らかに女のものではない。
これは、男だ。そして、男が寄り添っている獣は――。
「……犬、か」
「先生、里見八犬伝って知ってる?」
「中学生のときに読んだ」
「さすが。俺なんて、刺青のモチーフを相談したときに、彫り師の人に言われて初めて読んでみたんだ。で、これだって思ったんだ」
「執念深い犬だよな。初めて読んだときは、怖かった」
会話を交わしながら和彦は、てのひらでそっと背を撫でる。そこに彫られた犬を可愛がるように。
「でも、一途だ。惚れたお姫様をどうしても自分のものにしたくて、犬の身ですごいことをやった。結果として、手に入れたんだ」
「だからって、お前、この刺青は……」
千尋がピクリと肩を震わせ、振り返った顔は不安そうな表情を浮かべている。
「――……この刺青、嫌い?」
その表情から、千尋が何を思ってこの刺青を入れたのか、推測するのは容易い。
「きれいだ。だけどお前、こんなに大きなのを入れたら、体に負担が――」
言いかけて、やめる。こんなに立派な刺青を入れた今、忠告はすでに無駄であり、ささやかな道徳心を示したい和彦の偽善でしかない。何もかも覚悟したうえで、この刺青を背負うことにした千尋の気持ちを尊重するべきなのだろう。
「本当にきれいだ。ぼくがいままで見てきた刺青とは、色合いも雰囲気も違う。……お前だけの刺青だな」
「見たらわかると思うけど、俺と先生の姿だよ」
和彦と向き直った千尋が、強い光を放つ目でまっすぐ見つめてくる。怖いほどに純粋で一途な目は、ある意味、凶器だ。和彦の心に深々と突き刺さってくる。言葉ではなく眼差しで、こう訴えてくるのだ。
自分から逃げたら許さない、と。
「先生のことだからきっと、この先、もし自分に飽きたらどうするんだと言いたいだろうけど、そんなこと心配しなくていいよ。俺はずっと決めている。今は、じいちゃんとオヤジのものでもある先生を、将来絶対、俺だけのものに……オンナにするって」
「心配って……、お前、自惚れるな」
「先生っ」
勢いよく千尋が書斎に駆け込んでくる。せっかく着替えを用意してやったというのに、下着を穿いただけの姿だ。一体何事だと和彦は目を丸くする。
「……着替えなら出しておいただろ。というか、お前がカラスの行水なのは知ってるけど、さすがに早すぎだろ。きちんと体を洗ったのか?」
「ピッカピカに磨いてきたけど」
どうだか、と呟いた和彦の側に千尋が歩み寄ってきたかと思うと、いきなり抱き締められた。まだ湿り気を帯びた肌からは、確かに石けんの香りが立ちのぼっている。
「――ここ最近の先生は、ふっとどこかに行っちゃいそうで、怖い……というより、不安」
「何言ってるんだ」
和彦は、宥めるように千尋の背をさすろうとして、ドキリとした。自分の記憶にある、滑らかで瑞々しい肌の感触ではなかったからだ。ここで、今の千尋の背に何があるのか思い出した。
「ああ、そうか。お披露目してくれるんだったな」
和彦の言葉を受け、体を離した千尋が背をこちらに向ける。久しぶりに目にした千尋の裸の背には、一面に刺青が彫られていた。和彦がこれまで見てきた男たちの刺青とは違い、鮮やかな色が使われているわけではなく、黒一色で描かれている。しかし、墨の濃淡が使い分けられ、肌本来の色も覗いており、こういう刺青もあるのかと、息を呑む。
「墨を入れたばかりだから、まだ黒々としてるけど、時間が経ってくると、少しずつ色が落ち着いてくるんだ。オヤジみたいな青みがかった色合いが出るのは、何年かかるだろ……」
刺青の細かい部分に見入っていた和彦だが、ハッと我に返って一歩だけ後ずさる。こうすることで、千尋の背に一体何が彫られているのか、よく見ることができた。
不思議な獣だ。千尋の肌の色を活かした白い毛と、墨で塗りたくるように彫られた部分が黒い毛として表現され、それが獣の毛並みと柄を巧みに表している。獣は丸い目を見開き、牙を剥き出しにして、何かを威嚇しているようだった。その理由はおそらく、獣の体にたおやかそうな腕を回し、艶めかしい表情で寄り添っている人間を守るためだろう。人一人を背に乗せられそうな大きな体躯は、それが可能だと思わせる力強さを漲らせている。
和彦の顔が知らず知らずのうちに熱くなってくる。獣に寄り添っているのは女かと思ったが、そうではないと気づいたのだ。はだけた着物の胸元に膨らみはなく、裾が大きく捲れ上がって露わになったふくらはぎから腿のラインは、明らかに女のものではない。
これは、男だ。そして、男が寄り添っている獣は――。
「……犬、か」
「先生、里見八犬伝って知ってる?」
「中学生のときに読んだ」
「さすが。俺なんて、刺青のモチーフを相談したときに、彫り師の人に言われて初めて読んでみたんだ。で、これだって思ったんだ」
「執念深い犬だよな。初めて読んだときは、怖かった」
会話を交わしながら和彦は、てのひらでそっと背を撫でる。そこに彫られた犬を可愛がるように。
「でも、一途だ。惚れたお姫様をどうしても自分のものにしたくて、犬の身ですごいことをやった。結果として、手に入れたんだ」
「だからって、お前、この刺青は……」
千尋がピクリと肩を震わせ、振り返った顔は不安そうな表情を浮かべている。
「――……この刺青、嫌い?」
その表情から、千尋が何を思ってこの刺青を入れたのか、推測するのは容易い。
「きれいだ。だけどお前、こんなに大きなのを入れたら、体に負担が――」
言いかけて、やめる。こんなに立派な刺青を入れた今、忠告はすでに無駄であり、ささやかな道徳心を示したい和彦の偽善でしかない。何もかも覚悟したうえで、この刺青を背負うことにした千尋の気持ちを尊重するべきなのだろう。
「本当にきれいだ。ぼくがいままで見てきた刺青とは、色合いも雰囲気も違う。……お前だけの刺青だな」
「見たらわかると思うけど、俺と先生の姿だよ」
和彦と向き直った千尋が、強い光を放つ目でまっすぐ見つめてくる。怖いほどに純粋で一途な目は、ある意味、凶器だ。和彦の心に深々と突き刺さってくる。言葉ではなく眼差しで、こう訴えてくるのだ。
自分から逃げたら許さない、と。
「先生のことだからきっと、この先、もし自分に飽きたらどうするんだと言いたいだろうけど、そんなこと心配しなくていいよ。俺はずっと決めている。今は、じいちゃんとオヤジのものでもある先生を、将来絶対、俺だけのものに……オンナにするって」
「心配って……、お前、自惚れるな」
78
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
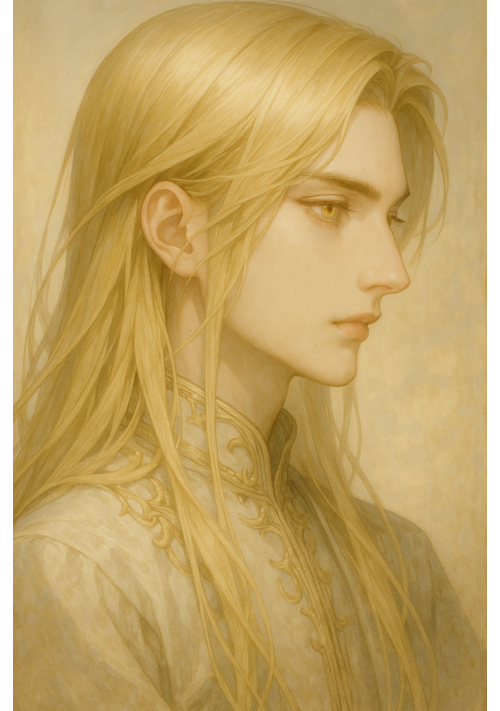
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















