1,053 / 1,289
第41話
(27)
しおりを挟む
千尋とともに賢吾の部屋に向かうと、ちょうど賢吾は電話をかけている最中だった。二人の姿を見るなり、少し待てというように賢吾が軽く片手を上げる。
千尋はいそいそと自分の分の座布団を用意して、和彦には座椅子を勧める。自分はかまわないと首を横に振ったが、肩を掴まれ、半ば強引に座卓につかされた。
並んで座った和彦と千尋を見て、電話を切った賢吾が微苦笑を浮かべる。話を聞くのなら、この席順はおかしくないかと思った和彦だが、賢吾も同様らしい。だが、些細なことだと言わんばかりに、いきなり本題を切り出した。
「メシの前に、胸が悪くなる話は済ませておこうと思ってな。――年末年始の間、お前を佐伯家に戻すよう、佐伯俊哉が要求してきたというのは、本当か?」
隣で、千尋がわずかに身じろぐ。しかし声は発しなかった。
和彦は視線を伏せたまま頷き、俊哉の言葉を伝える。ただし、説明してかまわないと言われたところまで。
無条件に俊哉の言葉に従ってしまう自分に口惜しさを覚えつつ、一方で、俊哉の目的がわからない以上、長嶺の男たちの疑心をさらに煽るのは危険だと、理性的な部分で判断もしている。
「オヤジは、お前に判断を任せると言っていた。もっともらしい渋面を浮かべていたが、腹の中はわかったもんじゃない。すでにもう、お前の父親との間で話がついているのかもしれないしな。お前はけっこうな値段がつきそうだ」
芝居がかった辛辣な言葉を放ったあと、そんな自分にうんざりしたように賢吾は荒く息を吐き出す。
「下世話な話をするなら、長嶺組は佐伯和彦に対してけっこうな金を投資している。じっくりと先を見越しての投資だ。総和会が無理を通そうとしても、長嶺組としては承服しかねると突っぱねる理由にはなる」
長嶺組として、俊哉からの要求を断ることができると仄めかされ、和彦の胸に広がったのは安堵の感情だった。ただしその感情は、繊細な砂糖菓子のようにあっという間に溶けてしまう。
賢吾や千尋を、こちらの事情で危険に晒すわけにはいかないのだ。
「……父さんは今回の要求で、総和会や長嶺組と揉めるつもりはないと思う。放蕩者の次男が行方不明のままで通すわけにはいかないから、年末年始の間だけ実家に滞在して、周囲の人間に対して言い訳が立つようにしたいんだ。それで済む話だ」
「その口ぶりだと、戻る決心はついているということか」
その指摘に和彦はハッとして、ああ、と吐息を洩らす。
「子供の頃からだ。父さんの言うことには、なんでも従うのが当たり前になってるんだ」
「だったら、逆らってみるか?」
賢吾に問われて、口ごもる。長嶺の男二人から向けられる視線が痛かった。
「……行くよ。不義理をしていたのは確かだから、せめて、父さんや兄さんの顔を立てるぐらいはしておきたい」
「俺は反対だ」
ここまで黙って話を聞いていた千尋がようやく口を開く。激情を堪えているのか、まるで呻き声のような一言だった。
「俺はずっと見てきたんだ。和彦が自分の家族に会うたびに、ものすごく不安定になって、落ち込んで、人を寄せつけなくなるところを。それが、何日も一緒にいて平気なのかよっ……。年末年始の間だけって言うけど、信用できねーよ。もしかして和彦を閉じ込めて、俺たちのところに帰さないつもりかもしれないし」
「ぼくはここに戻ってくる。――……戻ってきたいと思っている」
これは偽らざる本心だった。ただひたすらに静かな賢吾の目と、不安に揺れる千尋の目を交互に見つめ、和彦はもう一度、戻ってくる、と告げる。
昨夜から混乱し続けていた思考が、こうして声に出すことでまとまっていく。俊哉によって逃げ道を塞がれてしまうのなら、数少ない選択肢の中からとにかく選択するしかないのだ。
「お前の意思はともかく、佐伯家がそれを許すか?」
「いざとなれば、ぼくの出生について、佐伯家を脅す」
ずいっと座卓に身を乗り出してきた賢吾が、鋭い笑みを浮かべる。
「お前が自分の生まれについて告白してくれたとき、こうも言ってたな。自分の父親が、組や俺たち父子に何かしようとするなら、取引の材料にしてくれと。お前が示してくれた誠意だから、当然、オヤジには話していない。知っているのは、俺と千尋だけだ」
「それは、信用している」
「俺は躊躇しないぞ。お前を逃がさないためなら。こう見えて、汚い仕事は得意なんだぜ」
本気とも冗談とも取れる言葉に、ふっと唇を緩めてから、和彦は首を横に振る。
「――違う。ぼくが、ぼくの実家を脅すんだ。……自分の生活を守るために」
昼間眠ったせいか、夜になって布団に入っても目が冴えたままだった。和彦は客間の天井を見上げ、何度も自問を繰り返していた。
今の自分は冷静なのだろうか。自分の選択は間違っていないのだろうかと。
一か月後に自分が置かれているであろう状況を想像すると、心臓を締め上げられるような不安が押し寄せてくるが、数瞬後にはふっと気が緩む。それはここが、怖い男たちに守られた場所だからだろう。
これではいけない――。
和彦はようやく覚悟を決めると、起き上がる。羽織に袖を通してから客間を出ると、足音を抑えて廊下を歩く。もっとも夜更けとはいえ、誰かしら起きているのがこの本宅だ。ちらりと見えたダイニングには電気がついており、人影が動いている。
詰め所の前を素知らぬ顔をして通り過ぎると、組員たちも心得たもので、和彦に気づかないふりをして声すらかけてこない。夜、和彦が賢吾の部屋を訪ねる意味を、よく理解しているのだ。
すでに電気が消えている賢吾の部屋の前で軽く呼吸を整えてから、静かに障子を開ける。さらに奥の寝室へと入ると、暗い中、ゾクリとするほど官能的なバリトンが響いた。
「夜這いに来てくれたのか」
数秒の間を置いて枕元のライトが灯り、室内をぼんやりと照らす。賢吾がのそりと起き上がり、布団の上に座った。手招きされ、和彦も布団の傍らに座る。
「眠れないのか?」
賢吾の柔らかな声音に胸が詰まった。同時に、確信もしていた。
賢吾は、和彦があることを切り出すのを待っていたのだ。試されていたとは思わない。自分は信頼されているのだと思うことにする。
「――……夕方、千尋の前では言えなかったことがあるんだ」
「なんだ、夜這いじゃねーのか」
和彦は小さく笑みをこぼしたが、すぐに表情を引き締める。
そして、俊哉の手引きによって、里見と会ったことを話し始めた。
千尋はいそいそと自分の分の座布団を用意して、和彦には座椅子を勧める。自分はかまわないと首を横に振ったが、肩を掴まれ、半ば強引に座卓につかされた。
並んで座った和彦と千尋を見て、電話を切った賢吾が微苦笑を浮かべる。話を聞くのなら、この席順はおかしくないかと思った和彦だが、賢吾も同様らしい。だが、些細なことだと言わんばかりに、いきなり本題を切り出した。
「メシの前に、胸が悪くなる話は済ませておこうと思ってな。――年末年始の間、お前を佐伯家に戻すよう、佐伯俊哉が要求してきたというのは、本当か?」
隣で、千尋がわずかに身じろぐ。しかし声は発しなかった。
和彦は視線を伏せたまま頷き、俊哉の言葉を伝える。ただし、説明してかまわないと言われたところまで。
無条件に俊哉の言葉に従ってしまう自分に口惜しさを覚えつつ、一方で、俊哉の目的がわからない以上、長嶺の男たちの疑心をさらに煽るのは危険だと、理性的な部分で判断もしている。
「オヤジは、お前に判断を任せると言っていた。もっともらしい渋面を浮かべていたが、腹の中はわかったもんじゃない。すでにもう、お前の父親との間で話がついているのかもしれないしな。お前はけっこうな値段がつきそうだ」
芝居がかった辛辣な言葉を放ったあと、そんな自分にうんざりしたように賢吾は荒く息を吐き出す。
「下世話な話をするなら、長嶺組は佐伯和彦に対してけっこうな金を投資している。じっくりと先を見越しての投資だ。総和会が無理を通そうとしても、長嶺組としては承服しかねると突っぱねる理由にはなる」
長嶺組として、俊哉からの要求を断ることができると仄めかされ、和彦の胸に広がったのは安堵の感情だった。ただしその感情は、繊細な砂糖菓子のようにあっという間に溶けてしまう。
賢吾や千尋を、こちらの事情で危険に晒すわけにはいかないのだ。
「……父さんは今回の要求で、総和会や長嶺組と揉めるつもりはないと思う。放蕩者の次男が行方不明のままで通すわけにはいかないから、年末年始の間だけ実家に滞在して、周囲の人間に対して言い訳が立つようにしたいんだ。それで済む話だ」
「その口ぶりだと、戻る決心はついているということか」
その指摘に和彦はハッとして、ああ、と吐息を洩らす。
「子供の頃からだ。父さんの言うことには、なんでも従うのが当たり前になってるんだ」
「だったら、逆らってみるか?」
賢吾に問われて、口ごもる。長嶺の男二人から向けられる視線が痛かった。
「……行くよ。不義理をしていたのは確かだから、せめて、父さんや兄さんの顔を立てるぐらいはしておきたい」
「俺は反対だ」
ここまで黙って話を聞いていた千尋がようやく口を開く。激情を堪えているのか、まるで呻き声のような一言だった。
「俺はずっと見てきたんだ。和彦が自分の家族に会うたびに、ものすごく不安定になって、落ち込んで、人を寄せつけなくなるところを。それが、何日も一緒にいて平気なのかよっ……。年末年始の間だけって言うけど、信用できねーよ。もしかして和彦を閉じ込めて、俺たちのところに帰さないつもりかもしれないし」
「ぼくはここに戻ってくる。――……戻ってきたいと思っている」
これは偽らざる本心だった。ただひたすらに静かな賢吾の目と、不安に揺れる千尋の目を交互に見つめ、和彦はもう一度、戻ってくる、と告げる。
昨夜から混乱し続けていた思考が、こうして声に出すことでまとまっていく。俊哉によって逃げ道を塞がれてしまうのなら、数少ない選択肢の中からとにかく選択するしかないのだ。
「お前の意思はともかく、佐伯家がそれを許すか?」
「いざとなれば、ぼくの出生について、佐伯家を脅す」
ずいっと座卓に身を乗り出してきた賢吾が、鋭い笑みを浮かべる。
「お前が自分の生まれについて告白してくれたとき、こうも言ってたな。自分の父親が、組や俺たち父子に何かしようとするなら、取引の材料にしてくれと。お前が示してくれた誠意だから、当然、オヤジには話していない。知っているのは、俺と千尋だけだ」
「それは、信用している」
「俺は躊躇しないぞ。お前を逃がさないためなら。こう見えて、汚い仕事は得意なんだぜ」
本気とも冗談とも取れる言葉に、ふっと唇を緩めてから、和彦は首を横に振る。
「――違う。ぼくが、ぼくの実家を脅すんだ。……自分の生活を守るために」
昼間眠ったせいか、夜になって布団に入っても目が冴えたままだった。和彦は客間の天井を見上げ、何度も自問を繰り返していた。
今の自分は冷静なのだろうか。自分の選択は間違っていないのだろうかと。
一か月後に自分が置かれているであろう状況を想像すると、心臓を締め上げられるような不安が押し寄せてくるが、数瞬後にはふっと気が緩む。それはここが、怖い男たちに守られた場所だからだろう。
これではいけない――。
和彦はようやく覚悟を決めると、起き上がる。羽織に袖を通してから客間を出ると、足音を抑えて廊下を歩く。もっとも夜更けとはいえ、誰かしら起きているのがこの本宅だ。ちらりと見えたダイニングには電気がついており、人影が動いている。
詰め所の前を素知らぬ顔をして通り過ぎると、組員たちも心得たもので、和彦に気づかないふりをして声すらかけてこない。夜、和彦が賢吾の部屋を訪ねる意味を、よく理解しているのだ。
すでに電気が消えている賢吾の部屋の前で軽く呼吸を整えてから、静かに障子を開ける。さらに奥の寝室へと入ると、暗い中、ゾクリとするほど官能的なバリトンが響いた。
「夜這いに来てくれたのか」
数秒の間を置いて枕元のライトが灯り、室内をぼんやりと照らす。賢吾がのそりと起き上がり、布団の上に座った。手招きされ、和彦も布団の傍らに座る。
「眠れないのか?」
賢吾の柔らかな声音に胸が詰まった。同時に、確信もしていた。
賢吾は、和彦があることを切り出すのを待っていたのだ。試されていたとは思わない。自分は信頼されているのだと思うことにする。
「――……夕方、千尋の前では言えなかったことがあるんだ」
「なんだ、夜這いじゃねーのか」
和彦は小さく笑みをこぼしたが、すぐに表情を引き締める。
そして、俊哉の手引きによって、里見と会ったことを話し始めた。
76
あなたにおすすめの小説

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。


奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

オム・ファタールと無いものねだり
狗空堂
BL
この世の全てが手に入る者たちが、永遠に手に入れられないたった一つのものの話。
前野の血を引く人間は、人を良くも悪くもぐちゃぐちゃにする。その血の呪いのせいで、後田宗介の主人兼親友である前野篤志はトラブルに巻き込まれてばかり。
この度編入した金持ち全寮制の男子校では、学園を牽引する眉目秀麗で優秀な生徒ばかり惹きつけて学内風紀を乱す日々。どうやら篤志の一挙手一投足は『大衆に求められすぎる』天才たちの心に刺さって抜けないらしい。
天才たちは蟻の如く篤志に群がるし、それを快く思わない天才たちのファンからはやっかみを買うし、でも主人は毎日能天気だし。
そんな主人を全てのものから護る為、今日も宗介は全方向に噛み付きながら学生生活を奔走する。
これは、天才の影に隠れたとるに足らない凡人が、凡人なりに走り続けて少しずつ認められ愛されていく話。
2025.10.30 第13回BL大賞に参加しています。応援していただけると嬉しいです。
※王道学園の脇役受け。
※主人公は従者の方です。
※序盤は主人の方が大勢に好かれています。
※嫌われ(?)→愛されですが、全員が従者を愛すわけではありません。
※呪いとかが平然と存在しているので若干ファンタジーです。
※pixivでも掲載しています。
色々と初めてなので、至らぬ点がありましたらご指摘いただけますと幸いです。
いいねやコメントは頂けましたら嬉しくて踊ります。
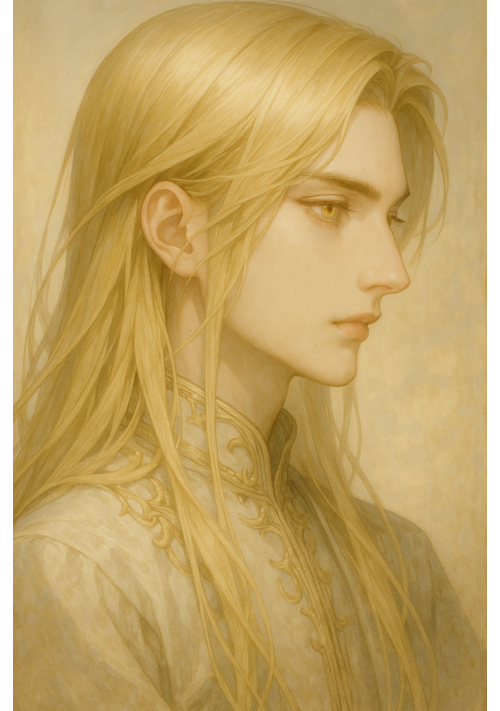
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















