1,062 / 1,289
第41話
(36)
しおりを挟む
「――……ぼくはもう、里見さんと会いたくないんだ。あなたは、昔のあなたじゃない。ぼくを特別扱いして、優しく守ってくれた、あの頃の里見さんじゃ……」
和彦の物言いから察するものがあったのか、里見がため息交じりに呟いた。
「君に関することだけは、おれは昔から変わってないよ。君だけが特別で、大事だ」
「だから、ぼくと似ている兄さんと、寝ている?」
「君は嫌がる言い方かもしれないが、割り切った関係だ。……お互い、利用し合っている。おれは、物分かりのいい大人を続けるために、君の面影にすがりつきたかった。英俊くんは、リスクの少ない相手と息抜きをしたかったというのもあるだろうが、多分、君に対する優越感を得たかったんだろう」
「優越感……?」
「自惚れを承知で言うなら、弟の大事なものを奪った、と英俊くんは思っているはずだ」
足元がふらついた和彦は、壁にもたれかかる。里見はさりげなく腕を差し出してきたが、すがりつくようなことはしなかった。
思い返すのは、実家で暮らしていた頃、たびたび訪れていた里見に対する英俊の態度だ。いつも一定の距離を取り、特に関心を示すわけでもなく、素っ気ないとすら言える態度だった。あの頃すでに、英俊の中では特別な感情――里見と体を重ねてもいいと思えるものが芽生えていたのかもしれない。それとも、衝動的な感情の結果なのか。
あれこれと思案するには、和彦はあまりに英俊という人間を知らない。一緒に暮らしながら和彦と英俊は、互いを理解しようとする以前に、知ろうとはしなかった。
「……ぼくには、わからない。里見さんの気持ちも、兄さんの気持ちも……」
「だったらおれは、君の気持ちがわからない。救いの手が差し伸べられているのに、どうして危険な環境から逃げ出そうとしないのか。君は頭がいい。いくら大事に扱われたところで、それは君を利用するためだと冷静に判断できているはずだ。こんなクリニック惜しさに、今の生活が手放せないなんて思ってもいないだろう」
里見の言葉に、ここで積み上げてきた生活や苦労を否定されたようで、不快さがじわりと胸に広がる。この感覚がさらに強くなった先にあるのは、おそらく敵意だ。
里見にそんな感情を抱きたくなくて、和彦はなんとか表情を取り繕う。
「もうここを閉めるから、とにかく外に出よう。……食事はできない。迎えの車を待たせてあるんだ」
「それらしい車は停まってなかったけど。おれが警察を引き連れてくるとでも思って、警戒されたかな」
里見は、自分が堅気であるという強みをよく理解している。もちろん、こちら側の弱みも。
「……今日は、タクシーで帰る。遅くなると、心配させるから……」
「食事が無理なら、せめてお茶でも飲もう。もう少し君と話したい。英俊くんとのことも説明したい」
「説明されたところで、困る。ぼくには関係ないし」
「本当にそう思っている?」
その言い方は卑怯だと、激した和彦は里見に食ってかかろうとしたが、言葉が出てこない。里見の発言によって、いいように感情を掻き乱され、そんな自分に何より腹が立つ。
里見の胸に抱き込まれそうになったが、寸前のところで拒み、軽く揉み合っていた。その拍子にアタッシェケースが足元に落ちる。
「里見さんっ」
和彦が鋭い声を発しても、里見の腕の力は緩むどころか、ますます強くなる。本能的な怯えから、身が竦みそうだった。
里見を拒んだ瞬間、過去の思い出すらも壊れてなくなってしまいそうで、それが和彦に本気の抵抗をためらわせる。しかし、昔のように抱き締められたくないという気持ちもある。
この腕は、もう自分のものではないのだ。
「里見さん、離してっ――」
前触れもなく、待合室に黒い影が飛び込んできた。
何事かと思ったときには、絡み付いていた里見の腕が引き剥がされ、黒い影が壁となって目の前に立ちはだかる。
地味な色のスーツに包まれた広い背は、見覚えがあるどころではなく、和彦にとって馴染み深いものだった。
「三田村……」
どうしてここにいるのかと、まず和彦は困惑する。しかし疑問を口にする間もなく、三田村と里見は対峙する格好となっていた。
「――君は?」
短い問いかけが里見から発せられたものだと、すぐには和彦はわからなかった。それほど冷淡な声だったからだ。応じたのは、ハスキーな声だった。
「誰でもいい。……先生を迎えに来た」
「ということは、長嶺組の組員かな」
「そうだと言ったら」
三田村の口調は落ち着いてはいるが、突き刺すような殺気に満ちている。里見は怯むどころか、口元に皮肉げな笑みを浮かべた。
和彦の物言いから察するものがあったのか、里見がため息交じりに呟いた。
「君に関することだけは、おれは昔から変わってないよ。君だけが特別で、大事だ」
「だから、ぼくと似ている兄さんと、寝ている?」
「君は嫌がる言い方かもしれないが、割り切った関係だ。……お互い、利用し合っている。おれは、物分かりのいい大人を続けるために、君の面影にすがりつきたかった。英俊くんは、リスクの少ない相手と息抜きをしたかったというのもあるだろうが、多分、君に対する優越感を得たかったんだろう」
「優越感……?」
「自惚れを承知で言うなら、弟の大事なものを奪った、と英俊くんは思っているはずだ」
足元がふらついた和彦は、壁にもたれかかる。里見はさりげなく腕を差し出してきたが、すがりつくようなことはしなかった。
思い返すのは、実家で暮らしていた頃、たびたび訪れていた里見に対する英俊の態度だ。いつも一定の距離を取り、特に関心を示すわけでもなく、素っ気ないとすら言える態度だった。あの頃すでに、英俊の中では特別な感情――里見と体を重ねてもいいと思えるものが芽生えていたのかもしれない。それとも、衝動的な感情の結果なのか。
あれこれと思案するには、和彦はあまりに英俊という人間を知らない。一緒に暮らしながら和彦と英俊は、互いを理解しようとする以前に、知ろうとはしなかった。
「……ぼくには、わからない。里見さんの気持ちも、兄さんの気持ちも……」
「だったらおれは、君の気持ちがわからない。救いの手が差し伸べられているのに、どうして危険な環境から逃げ出そうとしないのか。君は頭がいい。いくら大事に扱われたところで、それは君を利用するためだと冷静に判断できているはずだ。こんなクリニック惜しさに、今の生活が手放せないなんて思ってもいないだろう」
里見の言葉に、ここで積み上げてきた生活や苦労を否定されたようで、不快さがじわりと胸に広がる。この感覚がさらに強くなった先にあるのは、おそらく敵意だ。
里見にそんな感情を抱きたくなくて、和彦はなんとか表情を取り繕う。
「もうここを閉めるから、とにかく外に出よう。……食事はできない。迎えの車を待たせてあるんだ」
「それらしい車は停まってなかったけど。おれが警察を引き連れてくるとでも思って、警戒されたかな」
里見は、自分が堅気であるという強みをよく理解している。もちろん、こちら側の弱みも。
「……今日は、タクシーで帰る。遅くなると、心配させるから……」
「食事が無理なら、せめてお茶でも飲もう。もう少し君と話したい。英俊くんとのことも説明したい」
「説明されたところで、困る。ぼくには関係ないし」
「本当にそう思っている?」
その言い方は卑怯だと、激した和彦は里見に食ってかかろうとしたが、言葉が出てこない。里見の発言によって、いいように感情を掻き乱され、そんな自分に何より腹が立つ。
里見の胸に抱き込まれそうになったが、寸前のところで拒み、軽く揉み合っていた。その拍子にアタッシェケースが足元に落ちる。
「里見さんっ」
和彦が鋭い声を発しても、里見の腕の力は緩むどころか、ますます強くなる。本能的な怯えから、身が竦みそうだった。
里見を拒んだ瞬間、過去の思い出すらも壊れてなくなってしまいそうで、それが和彦に本気の抵抗をためらわせる。しかし、昔のように抱き締められたくないという気持ちもある。
この腕は、もう自分のものではないのだ。
「里見さん、離してっ――」
前触れもなく、待合室に黒い影が飛び込んできた。
何事かと思ったときには、絡み付いていた里見の腕が引き剥がされ、黒い影が壁となって目の前に立ちはだかる。
地味な色のスーツに包まれた広い背は、見覚えがあるどころではなく、和彦にとって馴染み深いものだった。
「三田村……」
どうしてここにいるのかと、まず和彦は困惑する。しかし疑問を口にする間もなく、三田村と里見は対峙する格好となっていた。
「――君は?」
短い問いかけが里見から発せられたものだと、すぐには和彦はわからなかった。それほど冷淡な声だったからだ。応じたのは、ハスキーな声だった。
「誰でもいい。……先生を迎えに来た」
「ということは、長嶺組の組員かな」
「そうだと言ったら」
三田村の口調は落ち着いてはいるが、突き刺すような殺気に満ちている。里見は怯むどころか、口元に皮肉げな笑みを浮かべた。
76
あなたにおすすめの小説

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

結婚初夜に相手が舌打ちして寝室出て行こうとした
紫
BL
十数年間続いた王国と帝国の戦争の終結と和平の形として、元敵国の皇帝と結婚することになったカイル。
実家にはもう帰ってくるなと言われるし、結婚相手は心底嫌そうに舌打ちしてくるし、マジ最悪ってところから始まる話。
オメガバースでオメガの立場が低い世界
こんなあらすじとタイトルですが、主人公が可哀そうって感じは全然ないです
強くたくましくメンタルがオリハルコンな主人公です
主人公は耐える我慢する許す許容するということがあんまり出来ない人間です
倫理観もちょっと薄いです
というか、他人の事を自分と同じ人間だと思ってない部分があります
※この主人公は受けです

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
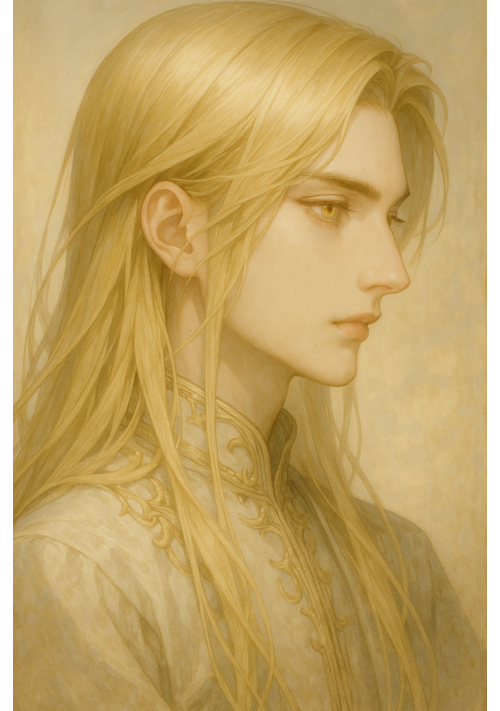
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















