1,198 / 1,289
第45話
(18)
しおりを挟む結局、俊哉との電話のあと、和彦は部屋に閉じこもったまま、誰とも顔を合わせることができなかった。総子が様子をうかがいに来てくれたが、板戸越しに最低限の会話を交わすのが精一杯で、それで総子は察してくれたようだ。
夕食はわざわざ部屋まで運んでもらったが、ほとんど口をつけることができなかった。
届けられた抗不安薬を服用したあと、和彦はただ横になって天井を見上げていた。ゆらゆらと視界が揺れていたのは、薬のせいなのか、浮かべた涙のせいなのかも、気に留めなかったぐらいだ。ただひたすら、考え続けていた。
いつ自分が眠ったのかもわからず、ひどい喉の渇きを覚えて目を覚ましたとき、今が何時なのかわからず混乱する。
部屋の電気はつけたままではあるが、ヒーターは消して休んでいたことに安堵する。しばらく和彦の傍らにいてくれた黒猫も、そろそろ仲間の元に戻るようにと、抱えて廊下に出したのだ。
頭上に手を伸ばし、リモコンをたぐり寄せる。テレビをつけると、見覚えのあるニュースキャスターがニュースを読んでいる。画面の隅に表示された時刻を見て、小さく声を洩らす。
「朝、だ……」
テレビに目を向けたまま和彦はぼんやりしていたが、いつまでもこうしているわけにはいかず、気力を振り絞って起き上がる。両瞼が腫れぼったく、きっとひどい顔になっているだろうなとため息をつく。
顔を洗いに行こうと半纏を着込んで外に出ると、何か抱えた総子がこちらにやってくる。
昨夜、礼を失した態度を取ったことを謝罪しようとしたが、そんな和彦を柔らかく制し、総子は微笑んだ。
「お風呂が沸いているから、入ってきてください。温まってから、朝食にしましょう」
差し出されたのは、きれいにアイロンがかけられたワイシャツだった。
受け取ったワイシャツを眺めて、今日の予定を思い出す。
「……今の状態だと、弁護士さんの話をまともに聞けそうにありません」
ぽろりとこぼした弱音に、表情を変えないまま総子が応じる。
「何も心配はいりません。面倒なことは、この家と弁護士の先生で引き受けますから。あなたは必要な手続きを済ませればいいだけです」
「ぼくに、そこまでしてもらえる価値はあるんでしょうか」
総子の顔からスッと微笑みが消える。憔悴しきった和彦の様子から、斟酌は簡単だったようだ。
「昨日は……、あまりいい話は聞けなかったようですね。俊哉さんから」
「楽しい話ではありませんでした」
和彦は自嘲気味に言うと、ふうっと息を吐き出して、視線を窓の外に向ける。今朝は、山茶花の側に猫の姿はない。
「ずっと、何を考えているのかわからない人でしたが、昨日電話で話して、ますますわからなくなりました……」
俊哉は、自分の生き方に対して、他人からの理解も共感も得られるとは思っていないだろう。そもそも、必要としていないのだ。傲慢で身勝手で冷徹。それが、俊哉という人間だ。その俊哉が生み出した〈呪い〉を押し付けられようとしている理不尽さに、和彦は何度も息が詰まりそうになる。
しかし、総子に打ち明けるつもりはなかった。信用しているか否かの問題ではなく、綾香と紗香の母親である総子を、間違いなく傷つけると確信しているからだ。
「――俊哉さんの抱えた闇は深い、ということでしょうね」
「闇……なんでしょうか。父さん自身は、光を見出しているのかもしれないと、なんとなく思って……」
「あなたは、引きずられてはいけませんよ。闇だろうが、光だろうが、それは俊哉さんのものでしかないんです。――わたしの娘たちは、それがわからなかったのかもしれません」
そう言った総子が、突然何かを思い出したように、小さく声を洩らした。一瞬、逡巡する素振りを見せたものの、毅然とした眼差しで和彦を見上げてきた。
「お風呂に向かう前に、あなたに見てもらいたいものがあります。……いろいろ思い出したあとですから、もしかするとつらいかもしれませんが」
かまわないと答えた和彦は、総子について歩く。向かったのは、屋敷の奥にある部屋だった。奥とはいっても、晴れた日であれば日当たりのいい一角なのだろう。残念ながら今は薄曇りのうえに霧も出ているが、窓から見える景色は計算されたかのように素晴らしい。けぶる山々と、近景の生垣と花壇の花と。
「入ってください」
総子に言われるまま部屋に足を踏み入れて、和彦は目を見開く。なんのための部屋であるか、すぐにわかった。
「ここは……」
紗香のための仏間だった。仏壇には、墓に供えてあったのと同じ種類の花が飾られており、室内の雰囲気を明るいものにしていた。
仏壇の前に正座すると、総子は小さいテーブルの上に並んだ写真立ての一つを差し出してきた。収められている写真には、まだ少女らしい面影を残した綾香と、もう一人、わずかに年若でよく似た顔立ちの女性が写っている。片方だけが、穏やかに微笑んでいた。
この人が、と和彦は心の中で呟く。写真を見ても、不思議なほど気持ちは凪いでいた。記憶にあるのは成長した姿の紗香で、写真の少女とは面影が似ているだけとも思えるせいだ。
「女の子なのに、二人ともあまり写真が好きではなかったから、あまり撮ってあげられなくて……。あとになって後悔しました」
他の写真も見せてもらったが、高校の入学式らしい制服姿の紗香に、胸が詰まった。生まじめな硬い表情を浮かべており、それが、自分自身の姿と重なった。
「似て、ますね……。ぼくに。顔もだけど、佇まいというか。晴れやかな場面で、上手く笑えないところとか――」
「恥ずかしがり屋なのでしょうね。あなたも、紗香も」
ぎこちなく笑みを浮かべたものの、和彦はこぼれそうになる涙を堪えるのに必死だった。
仏壇に手を合わせてから、テーブルの上に、写真立てと一緒に置かれた陶器製の鉢に目を留める。艶やかなピンク色の花が咲いており、なんとなく気になって、総子に花の名を尋ねる。ベゴニアといい、紗香が好きだった花だと教えてくれた。
仏間を出て廊下を歩いていると、総子を探していたのか、君代が慌てた様子でやってきた。二人組のお客様が見えられた、と報告を受けて、総子は顔を綻ばせる。心当たりがあるのか、君代に短く指示を出してから、和彦を見た。
「……あの?」
「じっとしているのが落ち着かない性分だと、よく話している人たちですよ。行動力があって、優秀。若いのに、それなりに修羅場も経験しているそうです。だから――あなたのことをお任せしようと決めました」
客人を出迎えるつもりなのか、総子が向かったのは玄関だ。必然的に和彦もついていく。
靴を脱いでいる二人組の姿を見て、思わず声を洩らす。そこにいたのは、昨日墓参りに向かう途中で見かけた男たちだった。
64
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
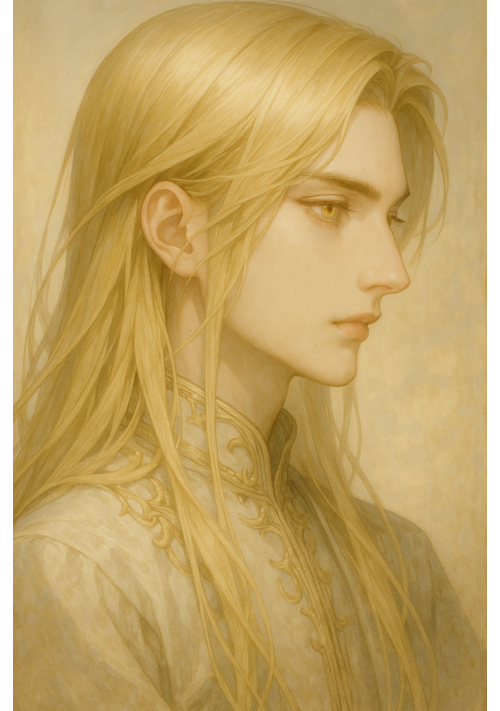
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















