1,207 / 1,289
第46話
(8)
しおりを挟む道に積もった雪には、轍はおろか、人の足跡すら残されていない。溶け始めて水分を含んで重くなりつつ雪を踏みしめて、和彦は背後を振り返る。そこには、二人の足跡がログハウスから続いている。
陽射しを受ける雪の眩さに思わず目を細める。数日ぶりに外に出たせいで、外の明るさにまだ順応できないのだ。何より、寒さに。
外出時の標準装備であるセーターを含めた重ね着の上から、ダウンコートを羽織り、ネックウォーマーに毛糸の帽子や手袋を身につけて、さらに鷹津から、あらゆるポケットにカイロも突っ込まれたが、それでも突き刺すような冷気を感じる。ただ、新鮮な空気に触れるのは心地いい。
数歩あるいては立ち止まる和彦に、鷹津は急かすことなくついてくる。今回の散歩コースは、前回和彦が歩いた道とは逆方向になっている。こちらは比較的坂が緩やかなうえに、足を滑らせたところで山から転がり落ちる心配もないという。とはいっても、ふくらはぎの辺りまで積もった雪は想像以上に歩きにくく、容赦なく乏しい体力を削っていく。転がり落ちるまでもなく、その場に倒れ込みそうだ。
ネックウォーマーで口元まで覆っていたが、息苦しさに耐え切れず下ろす。吐き出した白い息がキラキラと輝きながら大気に溶ける。思い切り息を吸ってから咳き込むと、鷹津に背をさすられた。
「……病み上がりが無茶するなよ」
「多少無茶しないと、体力が戻らないんだ」
「その結果、また熱を出す事態にならなきゃいいがな」
「たぶん、今回は大丈夫だ」
目に見えるものではないが、自分の体のことなので実感できるものがある。ようやく、気力が体内を巡り始めたのだ。体力が落ちようが、手足を動かす原動力にはなる。
「――お前は、わかりやすいな」
「何が?」
「駅でお前を捕まえてここに連れてきてからずっと、拾われてきた猫みたいに不安げな様子だったのが、今はやっと性根が据わった顔つきになった」
「今朝鏡を見たら、やつれたままだったけどな」
苦笑いしながら和彦は自分の顔に触れる。
「そういう意味じゃねーよ。……わかっててとぼけるんなら、もう何も言わんぞ」
道の傍らに広がるブナ林から、甲高い鳥の鳴き声が聞こえてくる。なんの鳥かと尋ねたが、鷹津から返ってきたのは、知らん、という素っ気ない一言だった。少しの間立ち止まり、鳥の姿が見えないかと目を凝らしても、気配はもうない。枝から雪が落ちたのをきっかけに、再び歩き出す。
「……拾われてきた猫かどうかはともかく、不安だったのは確かだ。体は思うとおりに動かないし、何かやろうにも気力が湧かない。あんたはひたすら甘やかしてくるだけだし。ゆるゆると、このまま時間が流れていけば楽になっていくのかなと思った」
突き詰めれば、自分は何者でなければいけないのかを見失っていたのかもしれない。両親についての真実を教えられ、自ら封印していた記憶を取り戻した結果、〈佐伯和彦〉を構成していたものを削り取られたようなものなのだ。そう、和彦は感じた。ログハウスで生活しながら、どこか他人事のように空虚となった自身を眺めていたが、案外早く変化は訪れた。
「ぼくはけっこう図太くて、逞しいみたいだ。自覚はあったけど、改めて実感してる……」
「俺はとっくに知ってた。いや、お前以外の奴はみんな知ってるかもな」
和彦は素早く雪を掬い上げると、鷹津にぶつけてやる。動じるでもなく、鷹津はニヤニヤする。もう一回雪をぶつけようとしたが足を滑らせ、大きくバランスを崩そうとして、すかさず強い力で引っ張り上げられた。和彦は鷹津に掴まりながら体勢を直す。
「足がふらふらじゃねーか。もう少しがんばれよ。休める場所がある」
鷹津に掴まったまま呼吸を整える。雪を掻き分けるようにして歩いていたせいで、疲れた足が重くなっており、爪先から寒さが這い上がってくる。鷹津のほうは息も乱しておらず、和彦を支えながら足取りはしっかりしている。
この男の安定感はどこから来ているのだろうかと、ふと思った。肉体的な強靭さのことではなく、精神的なものについてだ。出世は望めないにしても公務員の職を捨て、暴力団組織にケンカを売るようなまねをした挙げ句、厄介事の権化のようなものである和彦を懐に抱え込んでいる。なのに微塵も不安さを覗かせないのだ。ふてぶてしい、の一言では済ませられない。
鷹津が歩き出し、掴んだ腕から手が離せないまま和彦も続く。
「――どうした。急にまじまじと俺の顔を見て」
「あんた、怖いとか不安だとか感じるネジが抜け落ちてるんじゃないかと思ったんだ。いまさらながら」
「俺は、食えないクソどもとのつき合いが長いからな。覚悟と準備があれば、ビクビクする必要はない。いざとなれば、外国に高跳びするって手もある。お前も連れて」
「……つき合いがいいな」
「秦の奴が何回も言ってたんだ。二人分のパスポートぐらい用意してやるってな。俺については、お前の用心棒にでもなってくれればいいと思ってたんだろ。あいつは妙に、お前を気に入っているし」
いつだったか、鷹津と秦が一緒に飲んでいる光景を思い出し、和彦はふっと笑う。
「なんだかんだで、仲がいいよな。あんたと秦」
「やめろ。気色悪い」
心底嫌そうに吐き出す鷹津がおもしろい。しかしすぐに真剣な横顔を見せ、ぽつりと鷹津は洩らした。
「お前が何もかも投げ出したいと言うなら、俺はすぐに海外に逃がすつもりだ。お互い余計なしがらみを抱えちまってるが、目に見える鎖で手足を縛り付けられてるわけじゃない。行こうと思えば、どこにだって行ける――と、お前の世話を焼きながら、ずっと考えてた」
分厚いダウンコートを通しても感じられる鷹津の腕は、和彦をどこまでも引っ張っていく逞しさと力強さがある。大言壮語ではなく、鷹津は実行する男だ。対して自分はと、今のひ弱さに和彦はため息をついた。
「ぼくは……、考えることを放棄してた。気力が湧かないまま、周りのお膳立てに甘えて、ただ悲劇の主人公になりきってた」
「そうは言うが、けっこうな生い立ちだろ。お前。正直、もっと塞ぎ込まれて、八つ当たりされるのは覚悟していた」
「あんたは何も悪くないのに?」
珍しく鷹津が一瞬、きまり悪そうな顔をする。俊哉と繋がっていたことを責められると思っていたのかもしれない。ただ和彦としては、鷹津の心情を推察するのは難しいことではなかった。
鷹津が指さした先に、数軒の小さな建物が並んで建っており、軒下にはベンチも置いてある。観光客相手の土産物屋だそうだが、冬の間は閉めており、誰もいないのだという。ベンチに積もった雪を払って、二人並んで腰掛ける。腰から冷たさが伝わってくるが、それ以上に足が冷え切っているので、さほど気にならない。
「――総和会相手にぶつけるなら、お前の父親……佐伯俊哉しかいないと思っていた」
和彦は手袋を外してカイロで指先を暖めながら、鷹津の告白を聞く。
「お前はどんどん総和会に引き込まれて、取り返しのつかないところまで行くのは目に見えてる。そうなる前に、状況を掻き回したかった。が、二人が既知の間柄だったというのは、予想外だったがな。もっとも、悪くはない手だったようだ。相手の出方の予想がつくというのは、やりにくいからな。そのせいなのか、性分なのか、佐伯俊哉は慎重だった。それに、人使いが荒い。いかにも官僚様ってやつだな」
「本人に会ったら、そう伝えておくよ」
鷹津に笑いかけた和彦だが、すぐにうろたえることになる。カイロごと、きつく手を握り締められた。
「俺は、最善の策を取れたということだな。だからこうして、お前は今、俺の隣にいる」
「……下手したら、コンクリ詰めにされたり、海に沈められたりしたかもしれないのに、よくやるよ」
ログハウスに連れて来られてから、ようやく初めて、取り繕うことなく会話を交わせていた。鷹津はずっと、和彦が自ら行動を起こすのを待っていたのだろう。ただ静かに――。
88
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
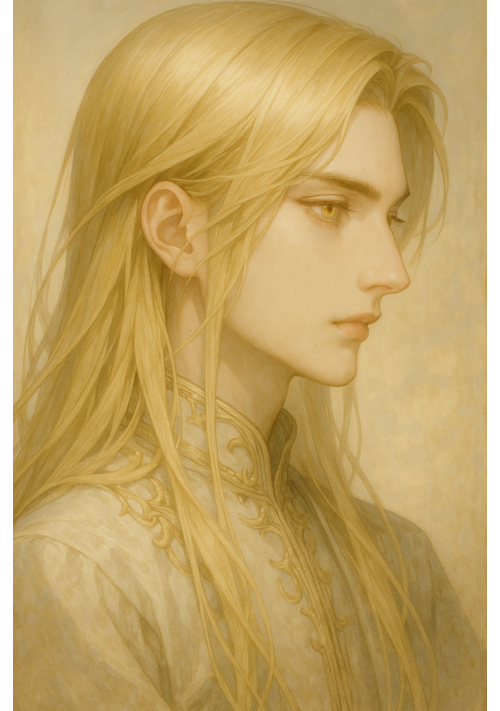
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















