558 / 871
一人飯
557
しおりを挟む
野菜を袋に入れて、二人に持たせる。白菜と大根だけでもかなり重いので里芋は郵送するようにするのだ。沙夜の所へは一馬の所に送り、あとでわけてもらうようにする。翔の家にも送るようにしてくれた。
その間、沙夜は物産館へ来てちりめんじゃこと塩を選ぶ。一馬は先に帰ってしまった。二人で帰れば来るときと同じように不自然なので、沙夜は一本あとの電車で帰るのだ。
物産館で塩を手にしたとき、入り口から辰雄がやってきた。そして沙夜に伝票を渡す。
「ほら。送っておいたから。」
「ありがとう。これから昭人君を迎えに行くの?」
「せっかくこっちまで来たしな。ちょっと早いけどそうする。」
伝票をバッグに入れて、また沙夜は物産館の品を見ていた。するとドレッシングが目に付く。これは辰雄の懇意にしている漁師が作っているモノだと言っていた。訳ありの人が多く居るような土地には、全くこの土地と縁もゆかりもない人が集まることもあるが、この漁師は昔からここに住んでいる人だ。全く違う土地にいた女性と一緒になり、子供が居るらしい。
買いたいものを買って物産館の外に出る。まだ電車が来るまでは時間があるようだ。その間、沙夜は海の方を見ていた。海はどこでも繋がっていて、あの外国の土地にも繋がっている。そして沙夜の中で少し迷いが出て来ていた。
「あいつさ。」
辰雄はポケットから煙草を取り出して、沙夜に言う。
「一馬のこと?」
「人が良すぎるな。真面目すぎてお前らみたいな世界には合っていない気がするけど。K街で暮らしていたわりに、全然擦れてないというか。」
「やっぱり辰雄さんもそう思う?」
「お前もそう思っていたのに担当なんかしてるのか。」
苦笑いをして辰雄は煙草の灰を灰皿に落とす。
「あいつの奥さんも真面目なんだろうな。だからメディアの言うことなんかにも黙っていたんだろう。」
「でもそれが嘘だってわかったわ。」
「そうだな。俺もその記事を昔読んだことがあるけど、そういうヤツってのは家庭に問題があったりして性の知識が歪んでいるヤツなら考えられなくも無い。だけど普通の女ならそんなことをするとは思えない。読んでてもあぁ、これはメディアが作ったことだなってのはすぐにわかったよ。」
「でもあの時は周りがみんなそういう風に思っていたって言っていたわね。」
「それだけ影響力があるんだ。それを支えていた男がずっと奥さんを支えているってのは、その奥さんにとってもかけがえのない人なんだろうな。」
「辰雄さんはそういう人は居ないの?」
煙を吐き出して、辰雄は頷いた。
「居たよ。」
「居たって事は昔はって事かしら。」
「何でも話せて守ってもらったし、守ったこともある。けど……俺は、あいつの何もわかってなかった。今は年賀状をやりとりするくらいだ。それで生きてればそれで良い。その奥さんもその幼なじみとそういう距離の取り方をしていれば良いんだ。旦那がいてもその相手とそういう繋がりを持っていたら、旦那だって存在意義を疑う。どっかで線引きをするべきだったんだ。」
おそらく辰雄が何でも話せるという相手は、異性なのだ。連絡を頻繁に取らないのは忍に遠慮しているから。辰雄はそうやって忍ともその相手とも上手く距離を保っていたのだ。
「……何て言って良いのかわからないけれど……その人は一馬がいないときには家に泊まったりすることもあるし、子供さんも懐いていて……どっちが父親なんだって思っていたみたいなのよね。」
「そりゃ、そう思うだろうな。でもさ。沙夜。」
煙草を消して、辰雄は沙夜に言う。
「だからってお前が逃げ口になることは無いんだ。お前もどこかで線引きをするべきなんだよ。芹のことを思うならな。」
すると沙夜は首を横に振った。そして辰雄に言う。
「……ずっと思っていたことがあるの。一馬にも言っていないんだけど。」
「俺には言って良いのか。」
「きっと辰雄さんはわかっていると思うから。芹には……。」
それに気がついていたのだ。辰雄は深いため息を付いて、沙夜の頭を撫でる。
「苦しかったな。それを一馬にも言うのか?」
「……一馬には隠したくない。だから……今度二人で会うときがあったら言うつもりにしているの。」
「あいつは別れろって言うだろうな。でもお前らが別れてもあいつとは一緒になれないと思うけど。」
「一緒にはなれないから。」
海をまた見た。この向こうの国へ行くのは、まだ現実から逃げている気がする。きっちりけじめは付けないといけない。二人のことを大事に思うならそうするべきなのだ。
N県から帰ってきた芹は、そのまま出版社へ行き打ち合わせをする。石森愛が別室を取ってくれて、そこで取材してきた内容を見ているのだ。
「ふーん……ギターねぇ。」
芹がわざわざまたN県へ行ったのは、ギタリストがギターを始めたときに手に入れた練習用のギターが倉庫で眠っていたというのを聞いたからだ。そのギターは本当に安いモノだったし、それも中古で売られていたくず鉄のようなモノだった。だがそれでも弦を張り替えたり、型番が違う機材を使って何とか弾けるように努力をしたようなのだ。
「世間で言われるほど乱暴なヤツじゃ無かったみたいだな。」
「そうだって聞いてる。ステージでは大暴れをするけれど、終わったらスタッフと一緒に片付けをするような人なんだってあなたの調べでも言っていたし。外見だけなのよねぇ。」
愛はそう言ってギターの写真を見ていた。塗装のはげたようなギターは、表に出せるようなモノでは無いし、ネックの所も塗装がはげている。乱暴な扱いでは無かったようだ。
「そういえば「二藍」の純も同じようなことを言っていたか。」
「純君ね?もらったギターでいつも練習をしていたって言ってたから。」
「そういうヤツが報われないと意味が無いよな。」
「でも実際は努力が実るとは限らないのよね。良い曲を作っても日に当たらないことがほとんどだし、「二藍」は本当に運が良かったわ。なんせリー・ブラウンから声がかかるくらいだもの。相当気に入ったみたいね。」
「へぇ。海外進出とかって声がかかったのかな。」
そうだとしたら、沙夜は担当だけであれば海外へ行くことは無い。沙夜が言うのには、沙夜は担当として一般の仕事をしているだけだから。だが「夜」であれば少し話が違ってくる。沙夜をひっくるめて海外へ呼ぼうと思うだろう。
「そうみたい。」
「無理だろ。「二藍」ってのはこの国だから受け入れられてるところがあるんだ。ハードロックに少し和テイストが入ったような感じだ。あっちへ行ったら普通のハードロックになる。そうなれば個性もあったもんじゃ無い。」
「そうならないと思うわ。もし、リー・ブラウンもそうだけど、ハリー・モーガンがいるのだったら。」
「ハリー?」
「ヨーロッパの方のレコード会社の人間。かなりやり手だから。その人と泉さんが組めば、「二藍」の良さは更に高くなるでしょうね。」
「……。」
つまり向こうの支所の人間やプロデューサーからも沙夜は気に入られているのだ。だから海外へ来ないかという言葉が出ているのだろう。だが行かせたくない。行くんだったら芹も一緒に行きたいと思う。芹の仕事は海外でも出来ることだからだ。
だが芹には心残りがあった。それは沙菜のこと。沙菜を置いて行くのだろうか。これだけ体を重ねているのだ。回数だけなら沙夜とセックスをするよりも多いかもしれない。
だからといって沙夜と別れて沙菜と一緒になることは無い。好きでは無いのだから。芹はそう思いながら手を握る。その様子に石森愛は面白そうに笑った。
「今すぐどうって話じゃ無いのよね。「二藍」はこれからアルバムを出して、ツアーに出るでしょ?その話があるとしたら、春頃からの話にならないかしらね。」
「それまでに結婚出来てれば良いな。」
「泉さんと?」
「それ以外誰がいるんだよ。」
「朝倉さんかと思った。」
「何で朝倉さん?」
そう言われて愛は少し呆れたように芹にを見る。芹はすずのことは本当に何も思っていないのだ。
「それはともかくとして、あなたは結婚しない方が良いと思うんだけど。」
「結婚なんて個人の自由だろ?」
「そうだけどね。あなたの良さが消える気がするわ。」
すると芹はため息交じりに言う。
「捨てられて未練がましい女の曲が人気かも知れない。だけど、それだけじゃ駄目だから。」
やっと気が付いたか。愛はそう思いながら、また芹が調べてきた資料に目を落とす。このギタリストのように、芹はイメージにとらわれて損をするような真似をされたくないと思っていたのだ。せっかく良い文章や歌詞を書くのだから。
その間、沙夜は物産館へ来てちりめんじゃこと塩を選ぶ。一馬は先に帰ってしまった。二人で帰れば来るときと同じように不自然なので、沙夜は一本あとの電車で帰るのだ。
物産館で塩を手にしたとき、入り口から辰雄がやってきた。そして沙夜に伝票を渡す。
「ほら。送っておいたから。」
「ありがとう。これから昭人君を迎えに行くの?」
「せっかくこっちまで来たしな。ちょっと早いけどそうする。」
伝票をバッグに入れて、また沙夜は物産館の品を見ていた。するとドレッシングが目に付く。これは辰雄の懇意にしている漁師が作っているモノだと言っていた。訳ありの人が多く居るような土地には、全くこの土地と縁もゆかりもない人が集まることもあるが、この漁師は昔からここに住んでいる人だ。全く違う土地にいた女性と一緒になり、子供が居るらしい。
買いたいものを買って物産館の外に出る。まだ電車が来るまでは時間があるようだ。その間、沙夜は海の方を見ていた。海はどこでも繋がっていて、あの外国の土地にも繋がっている。そして沙夜の中で少し迷いが出て来ていた。
「あいつさ。」
辰雄はポケットから煙草を取り出して、沙夜に言う。
「一馬のこと?」
「人が良すぎるな。真面目すぎてお前らみたいな世界には合っていない気がするけど。K街で暮らしていたわりに、全然擦れてないというか。」
「やっぱり辰雄さんもそう思う?」
「お前もそう思っていたのに担当なんかしてるのか。」
苦笑いをして辰雄は煙草の灰を灰皿に落とす。
「あいつの奥さんも真面目なんだろうな。だからメディアの言うことなんかにも黙っていたんだろう。」
「でもそれが嘘だってわかったわ。」
「そうだな。俺もその記事を昔読んだことがあるけど、そういうヤツってのは家庭に問題があったりして性の知識が歪んでいるヤツなら考えられなくも無い。だけど普通の女ならそんなことをするとは思えない。読んでてもあぁ、これはメディアが作ったことだなってのはすぐにわかったよ。」
「でもあの時は周りがみんなそういう風に思っていたって言っていたわね。」
「それだけ影響力があるんだ。それを支えていた男がずっと奥さんを支えているってのは、その奥さんにとってもかけがえのない人なんだろうな。」
「辰雄さんはそういう人は居ないの?」
煙を吐き出して、辰雄は頷いた。
「居たよ。」
「居たって事は昔はって事かしら。」
「何でも話せて守ってもらったし、守ったこともある。けど……俺は、あいつの何もわかってなかった。今は年賀状をやりとりするくらいだ。それで生きてればそれで良い。その奥さんもその幼なじみとそういう距離の取り方をしていれば良いんだ。旦那がいてもその相手とそういう繋がりを持っていたら、旦那だって存在意義を疑う。どっかで線引きをするべきだったんだ。」
おそらく辰雄が何でも話せるという相手は、異性なのだ。連絡を頻繁に取らないのは忍に遠慮しているから。辰雄はそうやって忍ともその相手とも上手く距離を保っていたのだ。
「……何て言って良いのかわからないけれど……その人は一馬がいないときには家に泊まったりすることもあるし、子供さんも懐いていて……どっちが父親なんだって思っていたみたいなのよね。」
「そりゃ、そう思うだろうな。でもさ。沙夜。」
煙草を消して、辰雄は沙夜に言う。
「だからってお前が逃げ口になることは無いんだ。お前もどこかで線引きをするべきなんだよ。芹のことを思うならな。」
すると沙夜は首を横に振った。そして辰雄に言う。
「……ずっと思っていたことがあるの。一馬にも言っていないんだけど。」
「俺には言って良いのか。」
「きっと辰雄さんはわかっていると思うから。芹には……。」
それに気がついていたのだ。辰雄は深いため息を付いて、沙夜の頭を撫でる。
「苦しかったな。それを一馬にも言うのか?」
「……一馬には隠したくない。だから……今度二人で会うときがあったら言うつもりにしているの。」
「あいつは別れろって言うだろうな。でもお前らが別れてもあいつとは一緒になれないと思うけど。」
「一緒にはなれないから。」
海をまた見た。この向こうの国へ行くのは、まだ現実から逃げている気がする。きっちりけじめは付けないといけない。二人のことを大事に思うならそうするべきなのだ。
N県から帰ってきた芹は、そのまま出版社へ行き打ち合わせをする。石森愛が別室を取ってくれて、そこで取材してきた内容を見ているのだ。
「ふーん……ギターねぇ。」
芹がわざわざまたN県へ行ったのは、ギタリストがギターを始めたときに手に入れた練習用のギターが倉庫で眠っていたというのを聞いたからだ。そのギターは本当に安いモノだったし、それも中古で売られていたくず鉄のようなモノだった。だがそれでも弦を張り替えたり、型番が違う機材を使って何とか弾けるように努力をしたようなのだ。
「世間で言われるほど乱暴なヤツじゃ無かったみたいだな。」
「そうだって聞いてる。ステージでは大暴れをするけれど、終わったらスタッフと一緒に片付けをするような人なんだってあなたの調べでも言っていたし。外見だけなのよねぇ。」
愛はそう言ってギターの写真を見ていた。塗装のはげたようなギターは、表に出せるようなモノでは無いし、ネックの所も塗装がはげている。乱暴な扱いでは無かったようだ。
「そういえば「二藍」の純も同じようなことを言っていたか。」
「純君ね?もらったギターでいつも練習をしていたって言ってたから。」
「そういうヤツが報われないと意味が無いよな。」
「でも実際は努力が実るとは限らないのよね。良い曲を作っても日に当たらないことがほとんどだし、「二藍」は本当に運が良かったわ。なんせリー・ブラウンから声がかかるくらいだもの。相当気に入ったみたいね。」
「へぇ。海外進出とかって声がかかったのかな。」
そうだとしたら、沙夜は担当だけであれば海外へ行くことは無い。沙夜が言うのには、沙夜は担当として一般の仕事をしているだけだから。だが「夜」であれば少し話が違ってくる。沙夜をひっくるめて海外へ呼ぼうと思うだろう。
「そうみたい。」
「無理だろ。「二藍」ってのはこの国だから受け入れられてるところがあるんだ。ハードロックに少し和テイストが入ったような感じだ。あっちへ行ったら普通のハードロックになる。そうなれば個性もあったもんじゃ無い。」
「そうならないと思うわ。もし、リー・ブラウンもそうだけど、ハリー・モーガンがいるのだったら。」
「ハリー?」
「ヨーロッパの方のレコード会社の人間。かなりやり手だから。その人と泉さんが組めば、「二藍」の良さは更に高くなるでしょうね。」
「……。」
つまり向こうの支所の人間やプロデューサーからも沙夜は気に入られているのだ。だから海外へ来ないかという言葉が出ているのだろう。だが行かせたくない。行くんだったら芹も一緒に行きたいと思う。芹の仕事は海外でも出来ることだからだ。
だが芹には心残りがあった。それは沙菜のこと。沙菜を置いて行くのだろうか。これだけ体を重ねているのだ。回数だけなら沙夜とセックスをするよりも多いかもしれない。
だからといって沙夜と別れて沙菜と一緒になることは無い。好きでは無いのだから。芹はそう思いながら手を握る。その様子に石森愛は面白そうに笑った。
「今すぐどうって話じゃ無いのよね。「二藍」はこれからアルバムを出して、ツアーに出るでしょ?その話があるとしたら、春頃からの話にならないかしらね。」
「それまでに結婚出来てれば良いな。」
「泉さんと?」
「それ以外誰がいるんだよ。」
「朝倉さんかと思った。」
「何で朝倉さん?」
そう言われて愛は少し呆れたように芹にを見る。芹はすずのことは本当に何も思っていないのだ。
「それはともかくとして、あなたは結婚しない方が良いと思うんだけど。」
「結婚なんて個人の自由だろ?」
「そうだけどね。あなたの良さが消える気がするわ。」
すると芹はため息交じりに言う。
「捨てられて未練がましい女の曲が人気かも知れない。だけど、それだけじゃ駄目だから。」
やっと気が付いたか。愛はそう思いながら、また芹が調べてきた資料に目を落とす。このギタリストのように、芹はイメージにとらわれて損をするような真似をされたくないと思っていたのだ。せっかく良い文章や歌詞を書くのだから。
0
あなたにおすすめの小説

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。


“熟年恋愛”物語
山田森湖
恋愛
妻を亡くし、独りで過ごす日々に慣れつつあった 圭介(56)。
子育てを終え、長く封じ込めていた“自分の時間”をようやく取り戻した 佳奈美(54)。
どちらも、恋を求めていたわけではない。
ただ——「誰かと話したい」「同じ時間を共有したい」、
そんな小さな願いが胸に生まれた夜。
ふたりは、50代以上限定の交流イベント“シングルナイト”で出会う。
最初の一言は、たった「こんばんは」。
それだけなのに、どこか懐かしいような安心感が、お互いの心に灯った。
週末の夜に交わした小さな会話は、
やがて食事の誘いへ、
そして“誰にも言えない本音”を語り合える関係へと変わっていく。
過去の傷、家族の距離、仕事を終えた後の空虚——
人生の後半戦だからこそ抱える孤独や不安を共有しながら、
ふたりはゆっくりと心の距離を縮めていく。
恋に臆病になった大人たちが、
無理をせず、飾らず、素のままの自分で惹かれ合う——
そんな“優しい恋”の物語。
もう恋なんてしないと思っていた。
でも、あの夜、確かに何かが始まった。

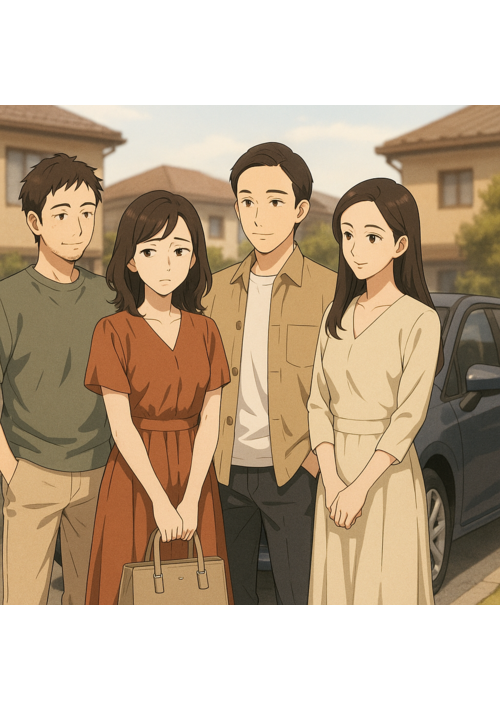


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















