23 / 44
23:動き出す王国
しおりを挟む
セリム対キーラの決着が着いた頃、ある一つの情報が伝えられていた。
クロント王国。神敵スキル保持者を排除する事を掲げる国の一つである。クロント王国にある王城の一室で一人の男がクロント王国現国王、ライドリヒ・クロントに向かい報告をしていた。
「その情報は本当の事か? 虚言の報告ではあるまいな?」
「そのようなことは。私、アガレスティ・バブルフが直接視たゆえら虚言などではありません」
今現在この部屋には二人の人物以外いない。一人はこの国の王、ライドリヒ・クロント。
ライドリヒは見た目三十代と言っても過言ではない若々しい見た目の持ち主だ。白髪の髪をオールバックにし、赤い瞳からは狂気とでも呼べるような、何か悍ましいものが宿った眼をしている。国王と言う身分ゆえ、身体を鍛えたいる時間も暇もない筈だが、ある程度筋肉が付きがっしりした身体つきである。そんじょそこらの冒険者と比べた場合はライドリヒの方引き締まった身体をしているかもしれない。だが実際の年齢はもう六十近い。なぜこんなに若いのか世間では疑問の声が上がったり王家に伝わる秘術ではと言う噂が飛び交っている。しかし誰一人として知る者はいない。知りえるのは王に近しい存在だけだ。
その王に近しい存在の一人はアガレスティ・バブルフ。彼はセリムが村にいた頃に勇者探索という命のもとやってきた者である。研究者として重要な案件に関わる事も多く、研究所所長の座を預かっている。
そんな二人が今話しているのは十数日前にアガレスティが目撃したセリムの事であった。
「そうか…疑ってすまんな。だが、そうとなれば忌々しき事態だ。早急に手を打たねばなるまい」
言葉では大変な事態だといいつつもその表情や仕草を見れば焦っている感じは全くといいほど受けない。現にあれだけのことを言いながらも書類の整理などの仕事をしながらアガレスティからもたらされた話をきいているのだから。
「そうですね。ですが、何分情報が少ないですからまずは情報の公開をするべきかと。ギルドに指名手配者として情報を提供させます。それから情報を得次第、次に移すと言う事でいかがでしょうか?」
アガレスティは内心この王が苦手だった。圧迫するような眼、天敵にでも睨まれているかような、そんな嫌な感じを覚えるのだ。狂喜にも似た光を孕む眼を持つライドリヒの前では、例外なく誰もが本能的恐怖とでも呼べるものを覚える、そう言えるだけの力を感じさせる。とても齢六十の眼力ではない。帝国の皇帝にもあったことがあるアガレスティだが、こう言っては失礼だが、帝国の皇帝よりも味方であるライドリヒの方が怖いと感じる。
「無難な方法だがそれが一番だろう。して、次の手の準備はできているのか?」
「えぇ、もちろんでございます」
「それは計画に使えそうか?」
「それは分かりませんが、成功すれば必ず成果は出せるかと」
「そうか、楽しみにしている」
「誠心誠意望ませていただく所存です」
それだけ言いアガレスティは一礼し、部屋から退室した。うっすらと口元に笑みを浮かべながら。
同時刻、都市アルスギルド地下闘技場内。その場は静寂が支配していた。皆セリムの事を眼で追うことすらが出来なかった為である。気付いたらキーラの背後に現れて、手刀を寸止めしていたのだから。
「一体何が起こったんだ?」
「さ、さぁ? 気が付いたらセリムがキーラの後ろに現れててそれで…」
「そんなことはわかてんだよ、何で後ろにいたのかだよ!さっきまで反対側にいただろ」
「もしかして転移魔法とかか?」
周りにいた冒険者は一様に何があったか分からず、お互いに質問をしてはそれを潰していくと言う作業としていた。その中で見えたものはと言うと…
(はえーな、まさかあんなに強いとは。それにさっきの魔法かなりの魔力を込めてやがったな。失敗してなけりゃ確実にここにいる奴数十人はお釈迦だったかもしんねぇぞ…つーか帯剣してたのに使わってねーしまだ底は見せてねぇかもな)
アーサーが自ら見たものの見解を頭の中で整理する。離れた所ではレイニーもセリムの事を考えていた。
(あの速度に魔力。前に戦った時は本気じゃなかったのね。それに魔法を使えるなんて書いてなっかた筈だし。色々考えなきゃかもしれないわね…)
頭が痛いのをこらえるかのようにレイニーはこめかみを抑えため息を吐く。だが今一番直近の問題はキーラの事だった。キーラの事情の知ってる身としてはそこを心配しえない。
「何で…何が起こったの…気付いたら試合が終わってて」
酷く混乱するのも無理がないだろう。いくらエルフが魔法が得意だとは言っても所詮は生物レベル。セリムはもうすでに生物の枠からは片足はみ出している。魂に関しては完全にモンスターに近いと言ってもいいだろう。それを相手どったのだ。せめても救いはセリムが魔法技術が未熟だったところか。
(ありゃ完全に打ちのめされたな…ったくこんなに強いなんて聞いてないぞ)
文句を垂れながらキーラの所まで行き連れ帰る。その日はそのままお開きになった。
その頃のセリムはと言えば、森でモンスター相手に魔法の練習をしていた。
「はぁ~、クッソ時間がかかりすぎて使えねぇか」
魔力操作がまだ拙いために時間がかかってしまい本物の戦闘では撃てずにいた。とりあえずは魔力操作の訓練をするために魔法を主体にし戦闘を繰り広げていた。
魔力操作により魔法を手にとどめたまま直接当てたり、範囲や形を出来るだけ細かく指定してひたすらに練習をする。モンスターが現れればそれを実験台に。
数時間後――
やっとのことで魔力操作のコツをつかんできたらしくらお陰で魔法を発動しそれ自体の形を変えて武器にして振り回せるようになった。いきなり武器にしたりはできないし動きもぎこちなかったが。
そうして今日はある程度の成果を得たことで宿屋に戻るのだった。
部屋に戻るとぐで~とベットに寝転がる。
「さすがに大人げなかったかもな。つってな俺の方が年下なわけだし」
案外複雑だと思いながら今朝キーラが見せた魔法の同時発動について考える。
あれは今後戦う上で大いに役立つと思い習得したいと考えいた。カルラも使っていたので教えてもらえればよかったと今更ながら後悔の念が押し寄せてくる。
魔法を同時に発動するの職業専用スキルなのか、普通のスキルなのか見当もつかない為にどうするかと頭を抱えるのだった。
その頃のキーラはと言えば、宿に戻り一人泣いていた。
「私は…強くならなくちゃいけないのに…戦いに負けて、魔法でも…」
正確に言えばセリムのは魔力にものを言わせ無理矢理に押し固めたものなので技術的なものではキーラの方が圧倒的に上なのだか、勝敗がそれを曇らせていた。
「ごめんなさい。お父さん、お母さん」
急に両親に謝りだす。それは何のためか…その日は疲れて寝てしまうまでずっと試合の事を考え続けるのだった。
都市アルスギルドにて一組の男女がギルドマスターの部屋で話し合っていた。
テーブルには紅茶が出され黙々と暖かな湯気を立てている。
「さて何の件かしら…とは言っても今朝の事なのは大体分かるけど」
と少し憂鬱な感じでティーカップを傾けながらレイニーが向かいの男に向けて言う。向かいの男ーーアーサー・ソリッドはそれにそうだと言い頷きを返す。
「担当直入に聞く。ありゃ何だ?」
「何だとはどうゆう意味かしら?」
ある程度は意味は察することが出来たレイニーだったが、正直な話どう対処すればいいのかレイニー自身も困っていた為答えたくなかったのである。
「分かってんだろ、セリムの事だ。ありゃ、異常だろ。あの年であの強さに魔力。どっかの回し者とかじゃねーのか?」
「訓練を受けたスパイだって言いたいのね。しかも無理矢理に強化された」
アーサーはセリムが強いと言う事を人伝に聞いただけだったので、まさかここまで強いとは思ってもみなかった為に間者じゃないのかと疑ったのである。
「そうだ、だが強化であそこまで強くするなんて可能な国があるのかどうか…」
「確かにそうよね。でも間者ではないと思うわよ」
この回答に対しアーサーは少し感心に近い感覚を覚える。まだ情報が少ない中で多分とは言え答えを出したのだ。それを出すに足り得る情報をレイニーは持っていると考えていた。
「それは?」
紅茶に口を付け喉を潤していたレイニーだったが、アーサーから向けられる視線にやれやれねと肩を竦めると音を立てずにカップをソーサーに置いた。そして息を吐き出すと話し出した。
「セリムはここ都市アルスに来た時に身分証明できる物を持ってなかったそうよ」
「…本当か?」
「えぇ、それに冒険者の事についても知らなかったわね、ジョブについてとか。フィーネが聞かれたと言っていたのを覚えているわ」
そこまで聞きアーサー自身もセリムに指名手配の事を教えたのも思い出していた。演技だとしたらここまで知らないのはいくら何でも無知すぎる。そう考え間者の可能性を狭める。自分の考えのどこかに穴がないかを考える為に紅茶を飲み間を埋める。そして次の言葉を口にした。
「だとしたら、本当にただ強い奴ってことになるな、とびきりの」
「そうね、そしたらあの子は次世代を担う子になるでしょうね」
「あぁ、あれは間違いなくな。そこで考えなきゃならないのが他国や王都の連中の事だ。余計ちょっかいをだしてくる可能性もあるぞ」
アーサーは都市アルスにとってセリムは今後重要な戦力になると考えているのである。冒険者とは言ってしまえば防衛に使うための駒だ。
王都や帝都などの国の主要な場所には王などが要るため、戦力も十分といって良いほど整っている。だが、地方はそうはいかない。多少騎士なりがいても主要な場所に比べれば、戦力の差は明らか。そこで冒険者の存在である。彼らには何の誓約もないので街などを護ることをする義務も理由もないのだが、もし戦わず逃げれば家や家族を失う者が出てくるだろう。だからこそ彼らは護るために戦うことになる。もしそれを他の甘い言葉によって引き抜かかれれば、戦争などが起こった際には最悪敵として戦わなければならなくなると言っているのである。
「分かっているわよ、それをどうにかしなくちゃいけないのわね」
レイニーはそれをどうするかを悩んで頭を抱えていたのである。正直な話あの若さでのあの力は今後の成長を見込めるだけに手放すと厄介になると考えていたのはレイニーも同じだ。だが、どうすればいいのかが分からず詰んでいたのだ。
「なら、お前が色仕掛けでもしたらどうだ?おっぱい大きいんだし、あの年頃の男なら食いつくぞ。んでもって妊娠したとかいってここに止めとくんだ」
どうだ!いいアイディアだろとサムズアップしながら言ってくるアーサー。普段あまり怒らないレイニーでも少しイラっときた。それに女である自分を売れと言われているようで内心ショックを覚えるのだ。こいつデリカシーないのかしらと。
「無理ね。私はそんなに安くないわよ」
「あ、そっか。齢200越えの女なんて誰も欲しがらないか」
納得と言う感じで拳を手のひらに叩きつけるアーサー。ポンっといい音が響き、同時にビキッと変な音が鳴る。
「言い度胸ね、アーサー」
一件いつもの変わらぬ口調で言ってるはずなのにそれだけなのに得も言われぬ迫力が身体中からあふれてきているレイニー。顔を見ればわかるが、目は笑っておらず額には青筋が浮かんでいる。それを見てアーサーはやべっ怒らせたと思いながらものすごい迫力に圧される。
「冗談、そう冗談だよ。俺は抱きたいよ!レイニー。あんたみたいな良い女はそうそういないからね。あぁ~抱きたいなな~」
恥ずかしげもなく大声で言い張るアーサー。この際プライドも尊厳もあったもんじゃない。あまり気持ちが籠っている感じの声ではなかったが、この対応に逆にレイニーの方が恥ずかしくなりこの話を打ち止めにする。紅茶を一口飲んで息を整え話を戻す。
「それで実際にはどうするのがベストだと思うかしら?」
「それは俺に聞くことじゃないだろ。ギルドマスターならマスターらしく決めろよ」
先程までふざけた提案をしていたくせに真面目な話になるといきなりすべてをマスターに任せると言い出すアーサー。少し冷たいともいえるかもしれない態度だ。
「そう、ならギルドマスターは下の意見を聞く事もマスターの仕事じゃないかしら。私はA級冒険者 聖王アーサーとしての貴方の意見を聞きたいのよ」
「へいへい分かったよ。その前にセリムに関する情報を見してくれ」
それから数分後、はぁとため息をつきアーサーは答えを語る。
「まずはギルドでのランクをDまででもいいからモンスター討伐できるまでに上げる事だな。街中でしかクエスト受けられないんじゃ退屈だろう。実力に見合った事をさせるのが一番だが、さすがにそれは優遇が過ぎる。だからあとは監視の意味も込めて俺がセリムの面倒を見るさ」
何かしらの答えは出してくるとは思っていたがまさか自ら面倒事を引き受けるとは思ってもみなかったレイニーは少し意外感を露わにする。
「…そう、なら任せるわ。でもくれぐれもキーラの事もしっかりして頂戴ね。故郷を失ってまだそれほど時間が経ってないんだから」
「分かってるさ、それにキーラにとってみればいい刺激になるだろう」
こうして長時間に及んだセリムの待遇は決まったのだった。アーサーに付きまとわれる事になるセリムの誕生だとも言えるが…
クロント王国。神敵スキル保持者を排除する事を掲げる国の一つである。クロント王国にある王城の一室で一人の男がクロント王国現国王、ライドリヒ・クロントに向かい報告をしていた。
「その情報は本当の事か? 虚言の報告ではあるまいな?」
「そのようなことは。私、アガレスティ・バブルフが直接視たゆえら虚言などではありません」
今現在この部屋には二人の人物以外いない。一人はこの国の王、ライドリヒ・クロント。
ライドリヒは見た目三十代と言っても過言ではない若々しい見た目の持ち主だ。白髪の髪をオールバックにし、赤い瞳からは狂気とでも呼べるような、何か悍ましいものが宿った眼をしている。国王と言う身分ゆえ、身体を鍛えたいる時間も暇もない筈だが、ある程度筋肉が付きがっしりした身体つきである。そんじょそこらの冒険者と比べた場合はライドリヒの方引き締まった身体をしているかもしれない。だが実際の年齢はもう六十近い。なぜこんなに若いのか世間では疑問の声が上がったり王家に伝わる秘術ではと言う噂が飛び交っている。しかし誰一人として知る者はいない。知りえるのは王に近しい存在だけだ。
その王に近しい存在の一人はアガレスティ・バブルフ。彼はセリムが村にいた頃に勇者探索という命のもとやってきた者である。研究者として重要な案件に関わる事も多く、研究所所長の座を預かっている。
そんな二人が今話しているのは十数日前にアガレスティが目撃したセリムの事であった。
「そうか…疑ってすまんな。だが、そうとなれば忌々しき事態だ。早急に手を打たねばなるまい」
言葉では大変な事態だといいつつもその表情や仕草を見れば焦っている感じは全くといいほど受けない。現にあれだけのことを言いながらも書類の整理などの仕事をしながらアガレスティからもたらされた話をきいているのだから。
「そうですね。ですが、何分情報が少ないですからまずは情報の公開をするべきかと。ギルドに指名手配者として情報を提供させます。それから情報を得次第、次に移すと言う事でいかがでしょうか?」
アガレスティは内心この王が苦手だった。圧迫するような眼、天敵にでも睨まれているかような、そんな嫌な感じを覚えるのだ。狂喜にも似た光を孕む眼を持つライドリヒの前では、例外なく誰もが本能的恐怖とでも呼べるものを覚える、そう言えるだけの力を感じさせる。とても齢六十の眼力ではない。帝国の皇帝にもあったことがあるアガレスティだが、こう言っては失礼だが、帝国の皇帝よりも味方であるライドリヒの方が怖いと感じる。
「無難な方法だがそれが一番だろう。して、次の手の準備はできているのか?」
「えぇ、もちろんでございます」
「それは計画に使えそうか?」
「それは分かりませんが、成功すれば必ず成果は出せるかと」
「そうか、楽しみにしている」
「誠心誠意望ませていただく所存です」
それだけ言いアガレスティは一礼し、部屋から退室した。うっすらと口元に笑みを浮かべながら。
同時刻、都市アルスギルド地下闘技場内。その場は静寂が支配していた。皆セリムの事を眼で追うことすらが出来なかった為である。気付いたらキーラの背後に現れて、手刀を寸止めしていたのだから。
「一体何が起こったんだ?」
「さ、さぁ? 気が付いたらセリムがキーラの後ろに現れててそれで…」
「そんなことはわかてんだよ、何で後ろにいたのかだよ!さっきまで反対側にいただろ」
「もしかして転移魔法とかか?」
周りにいた冒険者は一様に何があったか分からず、お互いに質問をしてはそれを潰していくと言う作業としていた。その中で見えたものはと言うと…
(はえーな、まさかあんなに強いとは。それにさっきの魔法かなりの魔力を込めてやがったな。失敗してなけりゃ確実にここにいる奴数十人はお釈迦だったかもしんねぇぞ…つーか帯剣してたのに使わってねーしまだ底は見せてねぇかもな)
アーサーが自ら見たものの見解を頭の中で整理する。離れた所ではレイニーもセリムの事を考えていた。
(あの速度に魔力。前に戦った時は本気じゃなかったのね。それに魔法を使えるなんて書いてなっかた筈だし。色々考えなきゃかもしれないわね…)
頭が痛いのをこらえるかのようにレイニーはこめかみを抑えため息を吐く。だが今一番直近の問題はキーラの事だった。キーラの事情の知ってる身としてはそこを心配しえない。
「何で…何が起こったの…気付いたら試合が終わってて」
酷く混乱するのも無理がないだろう。いくらエルフが魔法が得意だとは言っても所詮は生物レベル。セリムはもうすでに生物の枠からは片足はみ出している。魂に関しては完全にモンスターに近いと言ってもいいだろう。それを相手どったのだ。せめても救いはセリムが魔法技術が未熟だったところか。
(ありゃ完全に打ちのめされたな…ったくこんなに強いなんて聞いてないぞ)
文句を垂れながらキーラの所まで行き連れ帰る。その日はそのままお開きになった。
その頃のセリムはと言えば、森でモンスター相手に魔法の練習をしていた。
「はぁ~、クッソ時間がかかりすぎて使えねぇか」
魔力操作がまだ拙いために時間がかかってしまい本物の戦闘では撃てずにいた。とりあえずは魔力操作の訓練をするために魔法を主体にし戦闘を繰り広げていた。
魔力操作により魔法を手にとどめたまま直接当てたり、範囲や形を出来るだけ細かく指定してひたすらに練習をする。モンスターが現れればそれを実験台に。
数時間後――
やっとのことで魔力操作のコツをつかんできたらしくらお陰で魔法を発動しそれ自体の形を変えて武器にして振り回せるようになった。いきなり武器にしたりはできないし動きもぎこちなかったが。
そうして今日はある程度の成果を得たことで宿屋に戻るのだった。
部屋に戻るとぐで~とベットに寝転がる。
「さすがに大人げなかったかもな。つってな俺の方が年下なわけだし」
案外複雑だと思いながら今朝キーラが見せた魔法の同時発動について考える。
あれは今後戦う上で大いに役立つと思い習得したいと考えいた。カルラも使っていたので教えてもらえればよかったと今更ながら後悔の念が押し寄せてくる。
魔法を同時に発動するの職業専用スキルなのか、普通のスキルなのか見当もつかない為にどうするかと頭を抱えるのだった。
その頃のキーラはと言えば、宿に戻り一人泣いていた。
「私は…強くならなくちゃいけないのに…戦いに負けて、魔法でも…」
正確に言えばセリムのは魔力にものを言わせ無理矢理に押し固めたものなので技術的なものではキーラの方が圧倒的に上なのだか、勝敗がそれを曇らせていた。
「ごめんなさい。お父さん、お母さん」
急に両親に謝りだす。それは何のためか…その日は疲れて寝てしまうまでずっと試合の事を考え続けるのだった。
都市アルスギルドにて一組の男女がギルドマスターの部屋で話し合っていた。
テーブルには紅茶が出され黙々と暖かな湯気を立てている。
「さて何の件かしら…とは言っても今朝の事なのは大体分かるけど」
と少し憂鬱な感じでティーカップを傾けながらレイニーが向かいの男に向けて言う。向かいの男ーーアーサー・ソリッドはそれにそうだと言い頷きを返す。
「担当直入に聞く。ありゃ何だ?」
「何だとはどうゆう意味かしら?」
ある程度は意味は察することが出来たレイニーだったが、正直な話どう対処すればいいのかレイニー自身も困っていた為答えたくなかったのである。
「分かってんだろ、セリムの事だ。ありゃ、異常だろ。あの年であの強さに魔力。どっかの回し者とかじゃねーのか?」
「訓練を受けたスパイだって言いたいのね。しかも無理矢理に強化された」
アーサーはセリムが強いと言う事を人伝に聞いただけだったので、まさかここまで強いとは思ってもみなかった為に間者じゃないのかと疑ったのである。
「そうだ、だが強化であそこまで強くするなんて可能な国があるのかどうか…」
「確かにそうよね。でも間者ではないと思うわよ」
この回答に対しアーサーは少し感心に近い感覚を覚える。まだ情報が少ない中で多分とは言え答えを出したのだ。それを出すに足り得る情報をレイニーは持っていると考えていた。
「それは?」
紅茶に口を付け喉を潤していたレイニーだったが、アーサーから向けられる視線にやれやれねと肩を竦めると音を立てずにカップをソーサーに置いた。そして息を吐き出すと話し出した。
「セリムはここ都市アルスに来た時に身分証明できる物を持ってなかったそうよ」
「…本当か?」
「えぇ、それに冒険者の事についても知らなかったわね、ジョブについてとか。フィーネが聞かれたと言っていたのを覚えているわ」
そこまで聞きアーサー自身もセリムに指名手配の事を教えたのも思い出していた。演技だとしたらここまで知らないのはいくら何でも無知すぎる。そう考え間者の可能性を狭める。自分の考えのどこかに穴がないかを考える為に紅茶を飲み間を埋める。そして次の言葉を口にした。
「だとしたら、本当にただ強い奴ってことになるな、とびきりの」
「そうね、そしたらあの子は次世代を担う子になるでしょうね」
「あぁ、あれは間違いなくな。そこで考えなきゃならないのが他国や王都の連中の事だ。余計ちょっかいをだしてくる可能性もあるぞ」
アーサーは都市アルスにとってセリムは今後重要な戦力になると考えているのである。冒険者とは言ってしまえば防衛に使うための駒だ。
王都や帝都などの国の主要な場所には王などが要るため、戦力も十分といって良いほど整っている。だが、地方はそうはいかない。多少騎士なりがいても主要な場所に比べれば、戦力の差は明らか。そこで冒険者の存在である。彼らには何の誓約もないので街などを護ることをする義務も理由もないのだが、もし戦わず逃げれば家や家族を失う者が出てくるだろう。だからこそ彼らは護るために戦うことになる。もしそれを他の甘い言葉によって引き抜かかれれば、戦争などが起こった際には最悪敵として戦わなければならなくなると言っているのである。
「分かっているわよ、それをどうにかしなくちゃいけないのわね」
レイニーはそれをどうするかを悩んで頭を抱えていたのである。正直な話あの若さでのあの力は今後の成長を見込めるだけに手放すと厄介になると考えていたのはレイニーも同じだ。だが、どうすればいいのかが分からず詰んでいたのだ。
「なら、お前が色仕掛けでもしたらどうだ?おっぱい大きいんだし、あの年頃の男なら食いつくぞ。んでもって妊娠したとかいってここに止めとくんだ」
どうだ!いいアイディアだろとサムズアップしながら言ってくるアーサー。普段あまり怒らないレイニーでも少しイラっときた。それに女である自分を売れと言われているようで内心ショックを覚えるのだ。こいつデリカシーないのかしらと。
「無理ね。私はそんなに安くないわよ」
「あ、そっか。齢200越えの女なんて誰も欲しがらないか」
納得と言う感じで拳を手のひらに叩きつけるアーサー。ポンっといい音が響き、同時にビキッと変な音が鳴る。
「言い度胸ね、アーサー」
一件いつもの変わらぬ口調で言ってるはずなのにそれだけなのに得も言われぬ迫力が身体中からあふれてきているレイニー。顔を見ればわかるが、目は笑っておらず額には青筋が浮かんでいる。それを見てアーサーはやべっ怒らせたと思いながらものすごい迫力に圧される。
「冗談、そう冗談だよ。俺は抱きたいよ!レイニー。あんたみたいな良い女はそうそういないからね。あぁ~抱きたいなな~」
恥ずかしげもなく大声で言い張るアーサー。この際プライドも尊厳もあったもんじゃない。あまり気持ちが籠っている感じの声ではなかったが、この対応に逆にレイニーの方が恥ずかしくなりこの話を打ち止めにする。紅茶を一口飲んで息を整え話を戻す。
「それで実際にはどうするのがベストだと思うかしら?」
「それは俺に聞くことじゃないだろ。ギルドマスターならマスターらしく決めろよ」
先程までふざけた提案をしていたくせに真面目な話になるといきなりすべてをマスターに任せると言い出すアーサー。少し冷たいともいえるかもしれない態度だ。
「そう、ならギルドマスターは下の意見を聞く事もマスターの仕事じゃないかしら。私はA級冒険者 聖王アーサーとしての貴方の意見を聞きたいのよ」
「へいへい分かったよ。その前にセリムに関する情報を見してくれ」
それから数分後、はぁとため息をつきアーサーは答えを語る。
「まずはギルドでのランクをDまででもいいからモンスター討伐できるまでに上げる事だな。街中でしかクエスト受けられないんじゃ退屈だろう。実力に見合った事をさせるのが一番だが、さすがにそれは優遇が過ぎる。だからあとは監視の意味も込めて俺がセリムの面倒を見るさ」
何かしらの答えは出してくるとは思っていたがまさか自ら面倒事を引き受けるとは思ってもみなかったレイニーは少し意外感を露わにする。
「…そう、なら任せるわ。でもくれぐれもキーラの事もしっかりして頂戴ね。故郷を失ってまだそれほど時間が経ってないんだから」
「分かってるさ、それにキーラにとってみればいい刺激になるだろう」
こうして長時間に及んだセリムの待遇は決まったのだった。アーサーに付きまとわれる事になるセリムの誕生だとも言えるが…
0
あなたにおすすめの小説

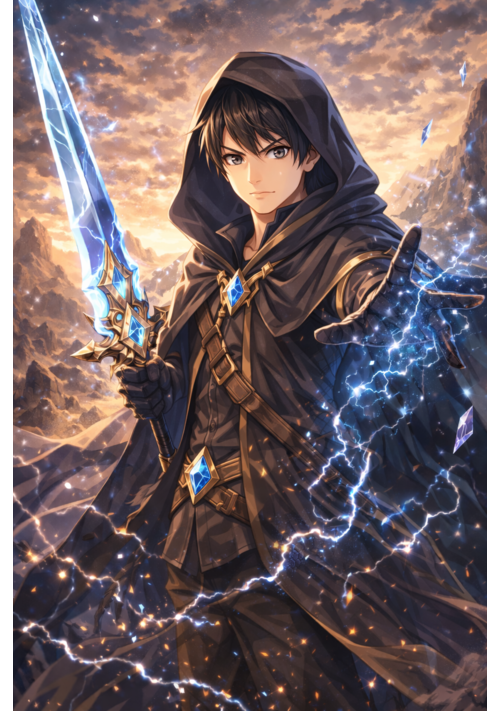
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
そのまま半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。
凛人はその命令を、拒否する。
不死であっても無敵ではない。
戦いでは英雄王に殴り倒される始末。しかし一つ選択を誤れば国が滅びる危うい存在。
それでも彼は、星を守るために戦う道を選んだ。
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

処刑された勇者は二度目の人生で復讐を選ぶ
シロタカズキ
ファンタジー
──勇者は、すべてを裏切られ、処刑された。
だが、彼の魂は復讐の炎と共に蘇る──。
かつて魔王を討ち、人類を救った勇者 レオン・アルヴァレス。
だが、彼を待っていたのは称賛ではなく、 王族・貴族・元仲間たちによる裏切りと処刑だった。
「力が強すぎる」という理由で異端者として断罪され、広場で公開処刑されるレオン。
国民は歓喜し、王は満足げに笑い、かつての仲間たちは目を背ける。
そして、勇者は 死んだ。
──はずだった。
十年後。
王国は繁栄の影で腐敗し、裏切り者たちは安穏とした日々を送っていた。
しかし、そんな彼らの前に死んだはずの勇者が現れる。
「よくもまあ、のうのうと生きていられたものだな」
これは、英雄ではなくなった男の復讐譚。
彼を裏切った王族、貴族、そしてかつての仲間たちを絶望の淵に叩き落とすための第二の人生が、いま始まる──。

最強賢者の最強メイド~主人もメイドもこの世界に敵がいないようです~
津ヶ谷
ファンタジー
綾瀬樹、都内の私立高校に通う高校二年生だった。
ある日、樹は交通事故で命を落としてしまう。
目覚めた樹の前に現れたのは神を名乗る人物だった。
その神により、チートな力を与えられた樹は異世界へと転生することになる。
その世界での樹の功績は認められ、ほんの数ヶ月で最強賢者として名前が広がりつつあった。
そこで、褒美として、王都に拠点となる屋敷をもらい、執事とメイドを派遣してもらうことになるのだが、このメイドも実は元世界最強だったのだ。
これは、世界最強賢者の樹と世界最強メイドのアリアの異世界英雄譚。

巻き込まれ異世界召喚、なぜか俺だけ竜皇女の推しになった
ノラクラ
ファンタジー
俺、霧島悠斗は筋金入りの陰キャ高校生。
学校が終わったら即帰宅して、ゲームライフを満喫するのが至福の時間――のはずだった。
だがある日の帰り道、玄関前で学園トップスターたちの修羅場に遭遇してしまう。
暴君・赤城獅童、王子様系イケメン・天条院義孝、清楚系美少女・柊奏、その親友・羽里友莉。
よりによって学園の顔ぶれが勢ぞろいして大口論!?
……陰キャ代表の俺に混ざる理由なんて一ミリもない。見なかったことにしてゲームしに帰りたい!
そう願った矢先――空気が変わり、街に巨大な魔法陣が出現。
赤城たちは光に呑まれ、異世界へと召喚されてしまった。
「お~、異世界召喚ね。ラノベあるあるだな」
そう、他人事のように見送った俺だったが……。
直後、俺の足元にも魔法陣が浮かび上がる。
「ちょ、待て待て待て! 俺は陰キャだぞ!? 勇者じゃないんだぞ!?」
――かくして、ゲームライフを愛する陰キャ高校生の異世界行きが始まる。

九尾と契約した日。霊力ゼロの陰陽師見習いが大成するまで。
三科異邦
ファンタジー
「霊力も使えない。術式も出せない。
……西園寺玄弥、お前は本当に陰陽師か?」
その言葉は、もう何度聞いたか分からない。
霊術学院の訓練場で、俺はただ立ち尽くしていた。
周囲では炎が舞い、水がうねり、風が刃のように走る。
同年代の陰陽師たちが、当たり前のように霊を操っている。
――俺だけが、何もできない。
反論したい気持ちはある。
でも、できない事実は変わらない。
そんな俺が、
世界最強クラスの妖怪と契約することになるなんて――
この時は、まだ知る由もなかった。
これは――
妖怪の王を倒すべく、九尾の葛葉や他の仲間達と力を合わせて成長していく陰陽師見習いの物語。

悪徳貴族の、イメージ改善、慈善事業
ウィリアム・ブロック
ファンタジー
現代日本から死亡したラスティは貴族に転生する。しかしその世界では貴族はあんまり良く思われていなかった。なのでノブリス・オブリージュを徹底させて、貴族のイメージ改善を目指すのだった。

SSSレア・スライムに転生した魚屋さん ~戦うつもりはないけど、どんどん強くなる~
草笛あたる(乱暴)
ファンタジー
転生したらスライムの突然変異だった。
レアらしくて、成長が異常に早いよ。
せっかくだから、自分の特技を活かして、日本の魚屋技術を異世界に広めたいな。
出刃包丁がない世界だったので、スライムの体内で作ったら、名刀に仕上がっちゃった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















